コラム検索
検索条件
 夏の鍋ものはいい。疲れていたり、忙しいときには特にいい。一口食べると意外にも、自分の胃袋が温かみを欲していることに気づくはずだ。ただし、暑い時期なので煮ながら食べると熱すぎる。テーブルに鍋を移して食べるといい。この時季の並のゴマサバは決して脂がのっているわけではないし、味があるわけでもない。それを甘辛いすき焼きの地でカバーする。一切れがあまり大きくなく、煮つけのように強く煮ていないので比較的柔らかい。煮えた夏野菜のおいしさとゴマサバから出ただしが一体となると、やけにうまい。そしてまた、やけにご飯がうまい。くどいようだが、エアコンの冷気を24時間浴びて、体が疲弊している、そんなときこそ夏の鍋だ。ちなみにスーパーの切り身なので包丁を使うのは最小限である。今回はすき焼きの地を自分で作ったが、市販のもので充分だ。夏野菜をたっぷり食べるためにも、作ってほしい夏の鍋だ。ついでにいうと、作り方といっても、材料を鍋に並べて、熱いすき焼き地をそそぐだけで、煮る時間もそんなにかからない。家族揃って食べることの少なくなった今、鍋に材料を並べておいて随時食べてもいいと思っている。
夏の鍋ものはいい。疲れていたり、忙しいときには特にいい。一口食べると意外にも、自分の胃袋が温かみを欲していることに気づくはずだ。ただし、暑い時期なので煮ながら食べると熱すぎる。テーブルに鍋を移して食べるといい。この時季の並のゴマサバは決して脂がのっているわけではないし、味があるわけでもない。それを甘辛いすき焼きの地でカバーする。一切れがあまり大きくなく、煮つけのように強く煮ていないので比較的柔らかい。煮えた夏野菜のおいしさとゴマサバから出ただしが一体となると、やけにうまい。そしてまた、やけにご飯がうまい。くどいようだが、エアコンの冷気を24時間浴びて、体が疲弊している、そんなときこそ夏の鍋だ。ちなみにスーパーの切り身なので包丁を使うのは最小限である。今回はすき焼きの地を自分で作ったが、市販のもので充分だ。夏野菜をたっぷり食べるためにも、作ってほしい夏の鍋だ。ついでにいうと、作り方といっても、材料を鍋に並べて、熱いすき焼き地をそそぐだけで、煮る時間もそんなにかからない。家族揃って食べることの少なくなった今、鍋に材料を並べておいて随時食べてもいいと思っている。 皿を冷やした上に、底にも保冷剤を敷いている。そうしないと室温で表面がうるうるする。刺身を口に入れた途端に溶けるといったもので、これ刺身なんだろうか? と疑問に思えるほどだ。ただし脂がさらりとして軽く、きよらかな舌触りで、しっかり背の青い魚の味もある。濃厚で強い味なのに箸が伸びる。高値なのに飛ぶように売れていた、そのわけは食べるとわかる。群馬県中之条町の「貴娘」というイケル酒を用意したが、飲む間が見つけられなかった。酒の肴はおいしすぎてはいけないのだ。
皿を冷やした上に、底にも保冷剤を敷いている。そうしないと室温で表面がうるうるする。刺身を口に入れた途端に溶けるといったもので、これ刺身なんだろうか? と疑問に思えるほどだ。ただし脂がさらりとして軽く、きよらかな舌触りで、しっかり背の青い魚の味もある。濃厚で強い味なのに箸が伸びる。高値なのに飛ぶように売れていた、そのわけは食べるとわかる。群馬県中之条町の「貴娘」というイケル酒を用意したが、飲む間が見つけられなかった。酒の肴はおいしすぎてはいけないのだ。 スズキ目タイ科の魚の塩焼きは上品でいながら、味わい深い。当然、クロダイの塩焼きは抜群にうまい。クロダイの問題点は生きている水域で味が違うことだ。神奈川県相模湾のもので臭みのあるものはないが、東京都墨田区の横か北かはわからないが十間川、また江戸川区新川の個体は釣り上げたときから臭ったという。クロダイはほぼ淡水でも生きていけるし、汚染にも強い。育ちで味の違う魚だが、海で揚がったものはほぼ大丈夫である。今回の大分県佐伯産、クロダイの塩焼きは絶品だった。脂がのっていたので、焼いた香りがよく、表面に脂から産まれる香ばしさがある。あまりにも皮がうまいので、身を食べ忘れてしまいそうだった。しょうが、柚子果汁、大根おろしを用意したけど、無用だった。
スズキ目タイ科の魚の塩焼きは上品でいながら、味わい深い。当然、クロダイの塩焼きは抜群にうまい。クロダイの問題点は生きている水域で味が違うことだ。神奈川県相模湾のもので臭みのあるものはないが、東京都墨田区の横か北かはわからないが十間川、また江戸川区新川の個体は釣り上げたときから臭ったという。クロダイはほぼ淡水でも生きていけるし、汚染にも強い。育ちで味の違う魚だが、海で揚がったものはほぼ大丈夫である。今回の大分県佐伯産、クロダイの塩焼きは絶品だった。脂がのっていたので、焼いた香りがよく、表面に脂から産まれる香ばしさがある。あまりにも皮がうまいので、身を食べ忘れてしまいそうだった。しょうが、柚子果汁、大根おろしを用意したけど、無用だった。 マグロの心臓を干したのは初めて。おいしいではないか。あまり魚の内臓は好きではないが、もともと血抜きをしていたのもあるが、再度血抜きをしたのがよかったかも。いただきもののシークヮーサーをじゃぶじゃぶかけながら食べる。非常に食べやすい。少し硬めだけど、マグロの血液の風味があり、うま味がある。後味に甘さが来るのもいい。100%酒のつまみだけど、このようなものが一品あるといい。
マグロの心臓を干したのは初めて。おいしいではないか。あまり魚の内臓は好きではないが、もともと血抜きをしていたのもあるが、再度血抜きをしたのがよかったかも。いただきもののシークヮーサーをじゃぶじゃぶかけながら食べる。非常に食べやすい。少し硬めだけど、マグロの血液の風味があり、うま味がある。後味に甘さが来るのもいい。100%酒のつまみだけど、このようなものが一品あるといい。 八王子卸売協同組合、舵丸水産に根室・厚岸から13(13尾で2㎏)と11(11尾で2㎏)が来ていた。迷うことなく根室市杉山水産の11を買う。昨年は18から始めているので、今年は滑り出しから上々である。値段は500円なのでワンコインである。ここ数年でいちばんいいものだし、安いと思う。さすがに室温で表面が潤むというほどではないが、身が脂のせいで非常に柔らかい。当然、脂から来る甘味がある。サンマには特有の渋甘い味わいがあるが、久々に魅了される。非常に酒をやりたくなったが、お昼なのでご飯で我慢する。ご飯だってすすみすぎて、困った。今年の初サンマは上々吉。これ以上はいらぬ。
八王子卸売協同組合、舵丸水産に根室・厚岸から13(13尾で2㎏)と11(11尾で2㎏)が来ていた。迷うことなく根室市杉山水産の11を買う。昨年は18から始めているので、今年は滑り出しから上々である。値段は500円なのでワンコインである。ここ数年でいちばんいいものだし、安いと思う。さすがに室温で表面が潤むというほどではないが、身が脂のせいで非常に柔らかい。当然、脂から来る甘味がある。サンマには特有の渋甘い味わいがあるが、久々に魅了される。非常に酒をやりたくなったが、お昼なのでご飯で我慢する。ご飯だってすすみすぎて、困った。今年の初サンマは上々吉。これ以上はいらぬ。 市場に来てみませんか? という話をしたい。関東を見回しても、一般客を受け入れない市場はなくなったと言っていいだろう。むしろ、一般客大歓迎といった市場ばかりである。市場では高級料理店でしか食べられない魚が、手に入る。もちろんお買い得なものもたっぷりある。野菜なども同じである。
市場に来てみませんか? という話をしたい。関東を見回しても、一般客を受け入れない市場はなくなったと言っていいだろう。むしろ、一般客大歓迎といった市場ばかりである。市場では高級料理店でしか食べられない魚が、手に入る。もちろんお買い得なものもたっぷりある。野菜なども同じである。 サザエでもっとも簡単な料理法は、塩ゆでである。今回は、三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にサザエがたっぷり入っていた。撮影していろんな料理にしたが、たっぷり入っていたので、何個かをそのまま水洗いして水を張り、塩を加えた鍋に入れて火をつけた。たぶん約8分くらいゆでてそのまま鍋止め(鍋のまま冷ます)する。ゆで汁は吸物程度の塩分濃度である。このやり方は昔々、防波堤釣りで川奈港(静岡県伊東市)に通っていたことがあり、そこでお昼ご飯を一緒に食べていた(引退した)漁師さんに習ったもの。島根県隠岐では少量の水分で蒸すという話を聞いたが、要はゆでるだけなので、さほど深く考える必要はない。最近までやや濃い目の塩水で煮ていたが、最近薄味でもいいと思うようになっている。ふたの隙間に貝剥き(貝棒)を入れて軟体部分を取りだし、砂を噛んでいたらゆで汁で洗う。あとは酢みそでもいいし、意外にそのまま食べてもおいしい。ルール無用なので好きなように食べるといい。ちなみに知り合いの居酒屋オヤジのおすすめはタバスコ&マヨ(ネーズ)だ。醤油で食べてもいい。ちょっと変だけど、ウスターソースで食べてみた。これが変だけどうまい。ときどきサザエは苦みだなんて通っぽいことを言う人がいるが、そんな人にはワタだけ食べてもらってもいい。ボクは通などになりたくもなし(一応一茶風に)、なのでワタの苦みはちょっぴりでいい。このどうにでもしてね、というのがサザエのよさだ。
サザエでもっとも簡単な料理法は、塩ゆでである。今回は、三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にサザエがたっぷり入っていた。撮影していろんな料理にしたが、たっぷり入っていたので、何個かをそのまま水洗いして水を張り、塩を加えた鍋に入れて火をつけた。たぶん約8分くらいゆでてそのまま鍋止め(鍋のまま冷ます)する。ゆで汁は吸物程度の塩分濃度である。このやり方は昔々、防波堤釣りで川奈港(静岡県伊東市)に通っていたことがあり、そこでお昼ご飯を一緒に食べていた(引退した)漁師さんに習ったもの。島根県隠岐では少量の水分で蒸すという話を聞いたが、要はゆでるだけなので、さほど深く考える必要はない。最近までやや濃い目の塩水で煮ていたが、最近薄味でもいいと思うようになっている。ふたの隙間に貝剥き(貝棒)を入れて軟体部分を取りだし、砂を噛んでいたらゆで汁で洗う。あとは酢みそでもいいし、意外にそのまま食べてもおいしい。ルール無用なので好きなように食べるといい。ちなみに知り合いの居酒屋オヤジのおすすめはタバスコ&マヨ(ネーズ)だ。醤油で食べてもいい。ちょっと変だけど、ウスターソースで食べてみた。これが変だけどうまい。ときどきサザエは苦みだなんて通っぽいことを言う人がいるが、そんな人にはワタだけ食べてもらってもいい。ボクは通などになりたくもなし(一応一茶風に)、なのでワタの苦みはちょっぴりでいい。このどうにでもしてね、というのがサザエのよさだ。 さかな上手とは、水産物(食用水産生物)を上手に、日々活用できる人間のことである。人間は生きていること自体が自然破壊、自然に対する悪影響を極力抑えなければならないが、生き物を無駄なく使うことも重要である。そのためには、さかな料理を習得しなければならないが、そのとき守るべきことをいくつか挙げる。さかな料理の入門八箇条(第一考)一、料理などで知ったかぶりはしない。知らないを武器にする。二、最初、向上心はいらない。もっとおいしくとか、正しい料理法とかは考えなくてもいい。向上心はおいおい勝手に自分の中に生まれてくる。三、道具は買わない。包丁くらいは家にあると思う。あればいい。さかな用に買うなんてやってはけない。だいたい包丁にこだわっている人に限って包丁を知らない。包丁を買うべき時は、自然にやってくると思うし、買うべきときが来なければ、切れない包丁を一生使い続けてもまったく問題はない。四、できるだけ下ごしらえは他人任せにする。スーパーとか魚屋でやってもらう。あとは焼くだけ、とか煮るだけ、とかがいい。五、惣菜を買って来ても勉強にはなる。外食も大いにするといい。コンビニにもさかな料理はある。刺身でも塩焼きでも煮物でも、まずは買って食べてみるべし。六、好奇心こそ料理上手を作る。さかな料理を楽しむべし。花から花へ飛んでいくモンシロチョウになれ。七、自分が作ったものは、おいしくない、と思いがちである。自分が作った料理はうまい、と思え。八、通の話は無視すべし。世に本物の通はいない。世間で通と言われる人はやけに説得力はあるが、正しいことを言っていない。自分本位である。他人のことは考えないし、排他的な考え方をする。できるだけ、通ではない素直な自分を探し出せ。入門編で終わっても、それでいいのだ。もっと詳しくなりたいと思ってから、もっと勉強すべし。さかな上手になるために、入門編は非常に大切である。この段階を経ないと「さかな上手」になるのがとても難しくなる。■写真は東京都八王子市、『舵丸水産』。
さかな上手とは、水産物(食用水産生物)を上手に、日々活用できる人間のことである。人間は生きていること自体が自然破壊、自然に対する悪影響を極力抑えなければならないが、生き物を無駄なく使うことも重要である。そのためには、さかな料理を習得しなければならないが、そのとき守るべきことをいくつか挙げる。さかな料理の入門八箇条(第一考)一、料理などで知ったかぶりはしない。知らないを武器にする。二、最初、向上心はいらない。もっとおいしくとか、正しい料理法とかは考えなくてもいい。向上心はおいおい勝手に自分の中に生まれてくる。三、道具は買わない。包丁くらいは家にあると思う。あればいい。さかな用に買うなんてやってはけない。だいたい包丁にこだわっている人に限って包丁を知らない。包丁を買うべき時は、自然にやってくると思うし、買うべきときが来なければ、切れない包丁を一生使い続けてもまったく問題はない。四、できるだけ下ごしらえは他人任せにする。スーパーとか魚屋でやってもらう。あとは焼くだけ、とか煮るだけ、とかがいい。五、惣菜を買って来ても勉強にはなる。外食も大いにするといい。コンビニにもさかな料理はある。刺身でも塩焼きでも煮物でも、まずは買って食べてみるべし。六、好奇心こそ料理上手を作る。さかな料理を楽しむべし。花から花へ飛んでいくモンシロチョウになれ。七、自分が作ったものは、おいしくない、と思いがちである。自分が作った料理はうまい、と思え。八、通の話は無視すべし。世に本物の通はいない。世間で通と言われる人はやけに説得力はあるが、正しいことを言っていない。自分本位である。他人のことは考えないし、排他的な考え方をする。できるだけ、通ではない素直な自分を探し出せ。入門編で終わっても、それでいいのだ。もっと詳しくなりたいと思ってから、もっと勉強すべし。さかな上手になるために、入門編は非常に大切である。この段階を経ないと「さかな上手」になるのがとても難しくなる。■写真は東京都八王子市、『舵丸水産』。 〈目黒不動尊の参拝をかねて、鷹狩りに出かけた松平出羽守(出雲松江藩藩主)。「下総の下人どもが食(しょく)いたします俗に下魚(げうお)と唱えまするものゆえ、高位の君があがるものではございません」という進言を無視して、近所の百姓家でさんまを食べたのだが、さあその美味さが忘れられない。翌日、殿中の溜の間で諸侯を前にこのはなし。これをきいた黒田筑前守(筑前国福岡藩主)が早速に家来に申しつけ、房州の網元からさんまを取り寄せたのだが、御膳奉行が「塩の強い、油のはなはだしきものをあがりつけないお上ゆえ」と、塩と油気をすっかり抜いてさし出したから美味いわけがない。あくる日、出羽守をつかまえると、「まるで木をゆで、かんでいるようなもの」「まずいとおっしゃるが、ご貴殿さまはいずれから……」「家来に申しつけ、房州の網元から」「黒田候、それは房州だからまずい。さんまは目黒にかぎる」〉『目黒のさんま』矢野誠一の『落語長屋の四季の味』(文春文庫)に出てくる。先月なくなった矢野誠一のエッセイや評論はすべて我が家にある。落語はそんなに好きではないというか、時間がないのでじっくり聞いていられないのだけど、矢野誠一の文章は好きでならない。矢野誠一の死で「東京やなぎ句会」は全員が冥土に旅立ったことになる。ひとつの時代が終わったのだ。■銚子産の丸干し。少し黄ばんでいるが、江戸時代、明治時代にはもっとくすんだものだったはず
〈目黒不動尊の参拝をかねて、鷹狩りに出かけた松平出羽守(出雲松江藩藩主)。「下総の下人どもが食(しょく)いたします俗に下魚(げうお)と唱えまするものゆえ、高位の君があがるものではございません」という進言を無視して、近所の百姓家でさんまを食べたのだが、さあその美味さが忘れられない。翌日、殿中の溜の間で諸侯を前にこのはなし。これをきいた黒田筑前守(筑前国福岡藩主)が早速に家来に申しつけ、房州の網元からさんまを取り寄せたのだが、御膳奉行が「塩の強い、油のはなはだしきものをあがりつけないお上ゆえ」と、塩と油気をすっかり抜いてさし出したから美味いわけがない。あくる日、出羽守をつかまえると、「まるで木をゆで、かんでいるようなもの」「まずいとおっしゃるが、ご貴殿さまはいずれから……」「家来に申しつけ、房州の網元から」「黒田候、それは房州だからまずい。さんまは目黒にかぎる」〉『目黒のさんま』矢野誠一の『落語長屋の四季の味』(文春文庫)に出てくる。先月なくなった矢野誠一のエッセイや評論はすべて我が家にある。落語はそんなに好きではないというか、時間がないのでじっくり聞いていられないのだけど、矢野誠一の文章は好きでならない。矢野誠一の死で「東京やなぎ句会」は全員が冥土に旅立ったことになる。ひとつの時代が終わったのだ。■銚子産の丸干し。少し黄ばんでいるが、江戸時代、明治時代にはもっとくすんだものだったはず 〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。
〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。 ナウなことには興味がないし、テレビもザッピングでしか見ないので、世の評判などとはまったく無縁である。あらゆる情報から離れたところにいる、といってもいいだろう。国内各地に行くと、店の位置まではネットを見るが、できる限り、その土地に根づいているものを探す。お昼ご飯を食べるときは、できれば個人経営の店を目指す。余談になるが、ボクは明らかに知名度ゼロの人間である。どこからどう見ても目立たない薄汚いデブオヤジだ。たまたまだろうが、浜松市で3組の方達から声をかけられた。希に、ごく希に「ですよね」と話しかけられることがあるが、複数の方に声をかけられたのは初めてだ。昼を過ぎていたので、その中のご夫婦の方に、「このあたりに昔ながらのものが食べられるところありますか?」と聞いたら、ついてきなさいと言ったので、ついて行った。ムムム、そこは思いもしなかったところ、ボクが絶対に足を踏み入れないところ、チェーン店だったのだ。仕方なく店内に入って席に着くやいなや、目撃したその光景にビックリ仰天した。出て来た料理と店員さんとで写真をとっている家族がいたのだ。とすると、これはこれで「昔ながらのもの」なのか?あとあとウィキで調べると、なんだかんだあって今の形の創業は1989年のようだ。どう考えても老舗とは言えないと思うが、悪意で教えてくれたわけでもないだろう。
ナウなことには興味がないし、テレビもザッピングでしか見ないので、世の評判などとはまったく無縁である。あらゆる情報から離れたところにいる、といってもいいだろう。国内各地に行くと、店の位置まではネットを見るが、できる限り、その土地に根づいているものを探す。お昼ご飯を食べるときは、できれば個人経営の店を目指す。余談になるが、ボクは明らかに知名度ゼロの人間である。どこからどう見ても目立たない薄汚いデブオヤジだ。たまたまだろうが、浜松市で3組の方達から声をかけられた。希に、ごく希に「ですよね」と話しかけられることがあるが、複数の方に声をかけられたのは初めてだ。昼を過ぎていたので、その中のご夫婦の方に、「このあたりに昔ながらのものが食べられるところありますか?」と聞いたら、ついてきなさいと言ったので、ついて行った。ムムム、そこは思いもしなかったところ、ボクが絶対に足を踏み入れないところ、チェーン店だったのだ。仕方なく店内に入って席に着くやいなや、目撃したその光景にビックリ仰天した。出て来た料理と店員さんとで写真をとっている家族がいたのだ。とすると、これはこれで「昔ながらのもの」なのか?あとあとウィキで調べると、なんだかんだあって今の形の創業は1989年のようだ。どう考えても老舗とは言えないと思うが、悪意で教えてくれたわけでもないだろう。 8月になって、神奈川県小田原市、小田原魚市場で揚がっていたクロダイは触った限りだけど、身に張りがあり、脂を感じるものだった。落とせなかったのもあって、魚屋さんをつかまえて、聞いてみると、みな「最高だよ」という。比較的保守的な、と思われる人までいいと言うことは、旬だと断定してもいいようだ。さて、それでは大分県佐伯産のクロダイはどうなのか?脂ののりこそ驚くほどではなかったが、うま味が充実して、多様なアミノ酸が生み出す、甘味が感じられる。醤油をつけないで口に入れているのに生臭みを感じない。結構な味としかいいようがない。違う産地でみてもクロダイは6、7月は不安定で、8月になると回復する。ほぼ一年を通して安定している。これだけうまいクロダイの刺身を前に、やることが立て込んでいるので、深夜一人で凍頂ウーロン茶とは情けない。
8月になって、神奈川県小田原市、小田原魚市場で揚がっていたクロダイは触った限りだけど、身に張りがあり、脂を感じるものだった。落とせなかったのもあって、魚屋さんをつかまえて、聞いてみると、みな「最高だよ」という。比較的保守的な、と思われる人までいいと言うことは、旬だと断定してもいいようだ。さて、それでは大分県佐伯産のクロダイはどうなのか?脂ののりこそ驚くほどではなかったが、うま味が充実して、多様なアミノ酸が生み出す、甘味が感じられる。醤油をつけないで口に入れているのに生臭みを感じない。結構な味としかいいようがない。違う産地でみてもクロダイは6、7月は不安定で、8月になると回復する。ほぼ一年を通して安定している。これだけうまいクロダイの刺身を前に、やることが立て込んでいるので、深夜一人で凍頂ウーロン茶とは情けない。 ボクが調べているのは水産生物でもあるし、地域性でもあるし、季節でもある。47都道府県のいろんな地域に行っているが、特色のあるものを、もちろん食品に限るが買って帰ってきている。静岡県に行くと必ず買ってくるのが、「金山寺みそ」である。意外に「金山寺みそ」とか、「醤油のみ(ひしお)」が好きなのだけど、静岡県に行くとどこのスーパーに寄っても「金山寺みそ」である。これほど「金山寺みそ」の多い県も少ない気がする。
ボクが調べているのは水産生物でもあるし、地域性でもあるし、季節でもある。47都道府県のいろんな地域に行っているが、特色のあるものを、もちろん食品に限るが買って帰ってきている。静岡県に行くと必ず買ってくるのが、「金山寺みそ」である。意外に「金山寺みそ」とか、「醤油のみ(ひしお)」が好きなのだけど、静岡県に行くとどこのスーパーに寄っても「金山寺みそ」である。これほど「金山寺みそ」の多い県も少ない気がする。 神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置にまた「ごっそり」がまとまって入り出した。「ごっそり」は平均して1尾90g以下のイサキのことである。今回のものは小は60g、大は110gで大きさにばらつきがある。大きさが微妙に違っているし、量的に多すぎるので出荷できない。最近ではこれを買い受ける人(買える店)があるにはあるが、ほぼダンベ(大型容器)行きである。「ごっそり」は非常においしい、しかも安いので飛ぶように売れてもいいはず。なのに売れないのは消費者が無知だからだ。米の価格を騒ぐよりも、安くてうまいものを買うべし、なのだ。さて、「ごっそり」といえばまずは刺身である。イサキの特長は小さくても脂があること。「ごっそり」の刺身には脂の口溶け感からくる甘味があり、しかもうま味が豊か。これでご飯を食べると一升飯といったものだ。ちなみに刺身はごっそり作り、そのまま食べるだけ食べて、あとは醤油・みりんに漬け込んで置く。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置にまた「ごっそり」がまとまって入り出した。「ごっそり」は平均して1尾90g以下のイサキのことである。今回のものは小は60g、大は110gで大きさにばらつきがある。大きさが微妙に違っているし、量的に多すぎるので出荷できない。最近ではこれを買い受ける人(買える店)があるにはあるが、ほぼダンベ(大型容器)行きである。「ごっそり」は非常においしい、しかも安いので飛ぶように売れてもいいはず。なのに売れないのは消費者が無知だからだ。米の価格を騒ぐよりも、安くてうまいものを買うべし、なのだ。さて、「ごっそり」といえばまずは刺身である。イサキの特長は小さくても脂があること。「ごっそり」の刺身には脂の口溶け感からくる甘味があり、しかもうま味が豊か。これでご飯を食べると一升飯といったものだ。ちなみに刺身はごっそり作り、そのまま食べるだけ食べて、あとは醤油・みりんに漬け込んで置く。 八王子卸売協同組合、舵丸水産に江戸前、船橋(千葉県船橋市)から新子なのか、「こはだ」なのか微妙なのがやって来ていた。7月とは違い、10cm・15g前後なので開きやすいのもありがたい。開いてみたら1枚漬け(1尾で1かんの握り)には小さすぎるので、ぎりぎり新子ということにする。最近、豊洲でもそうだが、多少大きくても新子で通っていることが多い。個人的には1枚漬けになるサイズは「こはだ」である。ボクの最大のテーマは季節と地域性なのであるが、コノシロには未だに季節が感じられる。コノシロはこのサイズから味わい深くなる。新子は季節を味わうものだが、成長するに従いコノシロの味を楽しむものに代わる。このサイズはうま味が豊かで、柔らかいのであっけなく喉に消えていく。いくらでも食べられるし、箸が伸びて困る。非常に軽い味なので、夜の酒に合う。最近、夜酒が多く、PCを終了させてからの時間を楽しむことが多い。そんなときにもこのサイズは好ましい。群馬県前橋市、「桂川」を正一合。
八王子卸売協同組合、舵丸水産に江戸前、船橋(千葉県船橋市)から新子なのか、「こはだ」なのか微妙なのがやって来ていた。7月とは違い、10cm・15g前後なので開きやすいのもありがたい。開いてみたら1枚漬け(1尾で1かんの握り)には小さすぎるので、ぎりぎり新子ということにする。最近、豊洲でもそうだが、多少大きくても新子で通っていることが多い。個人的には1枚漬けになるサイズは「こはだ」である。ボクの最大のテーマは季節と地域性なのであるが、コノシロには未だに季節が感じられる。コノシロはこのサイズから味わい深くなる。新子は季節を味わうものだが、成長するに従いコノシロの味を楽しむものに代わる。このサイズはうま味が豊かで、柔らかいのであっけなく喉に消えていく。いくらでも食べられるし、箸が伸びて困る。非常に軽い味なので、夜の酒に合う。最近、夜酒が多く、PCを終了させてからの時間を楽しむことが多い。そんなときにもこのサイズは好ましい。群馬県前橋市、「桂川」を正一合。 初めて食べたのは愛知県師崎(愛知県知多郡南知多町師)の旅館である。非常においしくなかった。以後長いこと避けていた。おいしさを知ったのは20年くらい前、ドラム缶たき火で焼いて食べたときだ。大アサリ(ウチムラサキ)焼きたてをあつつ、といいながら食べないとダメなのだ。もしくは、せめて温かい内、冷める前に口に放り込む。これほど焼きたてと、焼いて冷めたものとの味の落差のある食材はない気がしている。焼きすぎると硬くなるが、温かい内ならば、これがいいのである。無闇に噛むしかないのだけど、じわじわとおいしいがにじみ出てくる。個人的には酒と醤油少々と、貝からでてきたおいしさを、軟体にまぶしつけて食べる。終いに貝殻の内側をしゃぶるのが好きだ。
初めて食べたのは愛知県師崎(愛知県知多郡南知多町師)の旅館である。非常においしくなかった。以後長いこと避けていた。おいしさを知ったのは20年くらい前、ドラム缶たき火で焼いて食べたときだ。大アサリ(ウチムラサキ)焼きたてをあつつ、といいながら食べないとダメなのだ。もしくは、せめて温かい内、冷める前に口に放り込む。これほど焼きたてと、焼いて冷めたものとの味の落差のある食材はない気がしている。焼きすぎると硬くなるが、温かい内ならば、これがいいのである。無闇に噛むしかないのだけど、じわじわとおいしいがにじみ出てくる。個人的には酒と醤油少々と、貝からでてきたおいしさを、軟体にまぶしつけて食べる。終いに貝殻の内側をしゃぶるのが好きだ。 〈鰯こしらいとくれ、鰯を。南風が吹いてるんだよ、ぽかときているんだよ、腐っちまうよ、い、わ、しッ〉五代目、柳家小さんが得意としていた、『猫久』という話の一説である。ここに出てくるのが、「鰯のぬた」だ。矢野誠一の『落語長屋の四季の味』に出てくる。先月なくなった矢野誠一のエッセイや評論はすべて我が家にある。落語はそんなに好きではないというか、時間がないのでじっくり聞いていられないのだけど、矢野誠一の文章は好きでならない。矢野誠一の死で「東京やなぎ句会」は全員が冥土に旅立ったことになる。ひとつの時代が終わったのだ。さて、時代は不明だが、「猫久」には髪結床が出てくるくらいなので、江戸時代を設定としているのだろう。昼飯のおかずに、亭主の熊さんが鰯をおろして、女房がみそをすり鉢ですり、酢みそを作るのが「鰯のぬた」だ。髪結床から帰って来たばかりの熊さんに女房が早く鰯をおろせとせっつく。言われた熊さんが、髪結床で聞いた話を話している隙に、猫がやって来て鰯をくわえていく。落ちはわかりにくいが長屋の風景が浮かんでくるようである。せっかくなので鰯(マイワシ)を買って来て、手開きにする。振り塩をして少し寝かせ、酢で一度洗ってそのまま少し置く。水分をきり、酢みそをかけてご飯ではなく、酒を一合。鰯のぬたで酒を飲みながら矢野誠一のエッセイを読む。
〈鰯こしらいとくれ、鰯を。南風が吹いてるんだよ、ぽかときているんだよ、腐っちまうよ、い、わ、しッ〉五代目、柳家小さんが得意としていた、『猫久』という話の一説である。ここに出てくるのが、「鰯のぬた」だ。矢野誠一の『落語長屋の四季の味』に出てくる。先月なくなった矢野誠一のエッセイや評論はすべて我が家にある。落語はそんなに好きではないというか、時間がないのでじっくり聞いていられないのだけど、矢野誠一の文章は好きでならない。矢野誠一の死で「東京やなぎ句会」は全員が冥土に旅立ったことになる。ひとつの時代が終わったのだ。さて、時代は不明だが、「猫久」には髪結床が出てくるくらいなので、江戸時代を設定としているのだろう。昼飯のおかずに、亭主の熊さんが鰯をおろして、女房がみそをすり鉢ですり、酢みそを作るのが「鰯のぬた」だ。髪結床から帰って来たばかりの熊さんに女房が早く鰯をおろせとせっつく。言われた熊さんが、髪結床で聞いた話を話している隙に、猫がやって来て鰯をくわえていく。落ちはわかりにくいが長屋の風景が浮かんでくるようである。せっかくなので鰯(マイワシ)を買って来て、手開きにする。振り塩をして少し寝かせ、酢で一度洗ってそのまま少し置く。水分をきり、酢みそをかけてご飯ではなく、酒を一合。鰯のぬたで酒を飲みながら矢野誠一のエッセイを読む。 ピンクペッパーは懐かしい味がした。子供の頃は草木の実を見ると、「食えるか? 食えないか?」とよく話したものだ。1960年前後まではそんな時代だったとも言える。食べられる実を教わると、食べてみるのが当たり前だった。その無数に食べた実のどれかに似ている。同じような赤い実だったけどなんだったのだろう?辛みはあまり強くなく、ちょっとだけ酸味があり、口の中に爽やかさ、いい香りが広がる。酸味もある。ピンクペッパーは薄く切りつけて塩・オリーブオイル・にんにくで味つけしたクロダイにぴったりはまる。今回のクロダイは明らかに旬を迎えていた。とても脂がのっていて、おいしかったのもあるが、このぴったり感はまるで寸法を計ったようだ。ボクが作るカルパッチョのテーマは「野に咲く花の名前は知らない」だけど、ピンクペッパーは野に咲く花のようでもある。合わせたのは安いジンの水割りだけど、滅法合う。
ピンクペッパーは懐かしい味がした。子供の頃は草木の実を見ると、「食えるか? 食えないか?」とよく話したものだ。1960年前後まではそんな時代だったとも言える。食べられる実を教わると、食べてみるのが当たり前だった。その無数に食べた実のどれかに似ている。同じような赤い実だったけどなんだったのだろう?辛みはあまり強くなく、ちょっとだけ酸味があり、口の中に爽やかさ、いい香りが広がる。酸味もある。ピンクペッパーは薄く切りつけて塩・オリーブオイル・にんにくで味つけしたクロダイにぴったりはまる。今回のクロダイは明らかに旬を迎えていた。とても脂がのっていて、おいしかったのもあるが、このぴったり感はまるで寸法を計ったようだ。ボクが作るカルパッチョのテーマは「野に咲く花の名前は知らない」だけど、ピンクペッパーは野に咲く花のようでもある。合わせたのは安いジンの水割りだけど、滅法合う。 2025年8月8日の港のおっかさんのところでの朝ご飯は、カマス(ヤマトカマス)のフライであった。カマスのフライはある意味、小田原夏の風物詩と言ってもいいだろう。アカカマスと比べておいしくないなんて言う人のいるヤマトカマスであるが、そんなことはありませぬ、と声を大にしていいたい。小田原魚市場にあがったばかりの「青かます」は、皮目に独特の風味があって、身に強いうま味がある。揚げたてなのでふわっふわっである。市場を歩くのは重労働なので、大盛りご飯にしたいのはやまやまである。それをぐっと堪えて小盛りご飯なのは残念でならないが、これも人生なんだと諦める。
2025年8月8日の港のおっかさんのところでの朝ご飯は、カマス(ヤマトカマス)のフライであった。カマスのフライはある意味、小田原夏の風物詩と言ってもいいだろう。アカカマスと比べておいしくないなんて言う人のいるヤマトカマスであるが、そんなことはありませぬ、と声を大にしていいたい。小田原魚市場にあがったばかりの「青かます」は、皮目に独特の風味があって、身に強いうま味がある。揚げたてなのでふわっふわっである。市場を歩くのは重労働なので、大盛りご飯にしたいのはやまやまである。それをぐっと堪えて小盛りご飯なのは残念でならないが、これも人生なんだと諦める。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中に「がんこーじ(オニサザエ)」が入っていたというのは前回も書いた。「がんこーじ」の刺身は嫌みがなく、しかもシコシコッっとした食感が心地よいので、非常に魅力的である。噛んでいると身(足)から甘味が出てくるので、最後までうまい。今回は高知県土佐山の柚子果汁と塩で食べたけど、柑橘類との相性が抜群にいい。ちなみにボクだけの個人的な考えだけど、貝の刺身と柑橘類のときにはジンとかウオッカが合う。ころころと切りつけた刺身を口に放り込んで、ウオッカで流す。ヴァランダーの深みにはまっているので飲んでいる、アブソルートととても合うのがうれしい。
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中に「がんこーじ(オニサザエ)」が入っていたというのは前回も書いた。「がんこーじ」の刺身は嫌みがなく、しかもシコシコッっとした食感が心地よいので、非常に魅力的である。噛んでいると身(足)から甘味が出てくるので、最後までうまい。今回は高知県土佐山の柚子果汁と塩で食べたけど、柑橘類との相性が抜群にいい。ちなみにボクだけの個人的な考えだけど、貝の刺身と柑橘類のときにはジンとかウオッカが合う。ころころと切りつけた刺身を口に放り込んで、ウオッカで流す。ヴァランダーの深みにはまっているので飲んでいる、アブソルートととても合うのがうれしい。 神奈川県小田原から持ち帰った魚で処理済みのもの(塩をしたり、ゆでて干したり)がまだかなり残っている。そんな魚の在庫を見てから八王子総合卸売センター・八王子卸売協同組合に行ったが、それほど欲しいものはない。八王子総合卸売センター、福泉でなんとなくクロダイを買う。小田原で話題に上ったからでもあるし、この日いちばん上等だったからだ。帰宅してクロダイを下ろしながら、一般家庭にもっとも取り入れてほしい魚料理、みそ汁を作る。中骨をとんとんと食べやすい大きさに切る。ボクは魚の臭みに敏感なので湯通しして霜降りに、冷水に落とし鰭際のぬるを流し、水分をよくきる。ちなみに沖縄本島泡瀬であったトビイカ漁師は、毎日飲むみそ汁、「いまいゆの魚汁(いうしる)」を作るときにはこんな面倒なことはやらない。適当に切って、水で煮るだけだという。考えてみると魚のみそ汁はいい加減に作るべきなのかも。家庭料理に向上心はいらないと思っているが、魚が苦手だった過去は捨てられない。差し昆布をした水に放り込み。昆布はあくまでもボク流であるのでやらなくてもいい。なににでも差し昆布をするのはボクのくせだ。煮立てて、あくをすくって多めのみそ(長崎みそ)を溶く。あとは、しょうがの搾り汁を数滴垂らし、ねぎを散らすだけ。みそは多すぎるくらいのみそ汁だけど、やけに体に効くのである。8月の大分県のクロダイは脂がのっていて、みそ汁の表面がギラついているし、強いうま味がある。市場から帰り着いて、なかなか去らなかった熱気がとれる。ちなみに先に述べたトビイカ漁師は、毎日飲むみそ汁、「いまいゆの魚汁(いうしる)」には、味の素的なものを入れるというし、チューブのにんにくも入れるという。チューブのにんにくは恐くてまだ試していないが、家庭料理にはルール無用(ルールというのは害があるけど益はない)なのでやってみたい。
神奈川県小田原から持ち帰った魚で処理済みのもの(塩をしたり、ゆでて干したり)がまだかなり残っている。そんな魚の在庫を見てから八王子総合卸売センター・八王子卸売協同組合に行ったが、それほど欲しいものはない。八王子総合卸売センター、福泉でなんとなくクロダイを買う。小田原で話題に上ったからでもあるし、この日いちばん上等だったからだ。帰宅してクロダイを下ろしながら、一般家庭にもっとも取り入れてほしい魚料理、みそ汁を作る。中骨をとんとんと食べやすい大きさに切る。ボクは魚の臭みに敏感なので湯通しして霜降りに、冷水に落とし鰭際のぬるを流し、水分をよくきる。ちなみに沖縄本島泡瀬であったトビイカ漁師は、毎日飲むみそ汁、「いまいゆの魚汁(いうしる)」を作るときにはこんな面倒なことはやらない。適当に切って、水で煮るだけだという。考えてみると魚のみそ汁はいい加減に作るべきなのかも。家庭料理に向上心はいらないと思っているが、魚が苦手だった過去は捨てられない。差し昆布をした水に放り込み。昆布はあくまでもボク流であるのでやらなくてもいい。なににでも差し昆布をするのはボクのくせだ。煮立てて、あくをすくって多めのみそ(長崎みそ)を溶く。あとは、しょうがの搾り汁を数滴垂らし、ねぎを散らすだけ。みそは多すぎるくらいのみそ汁だけど、やけに体に効くのである。8月の大分県のクロダイは脂がのっていて、みそ汁の表面がギラついているし、強いうま味がある。市場から帰り着いて、なかなか去らなかった熱気がとれる。ちなみに先に述べたトビイカ漁師は、毎日飲むみそ汁、「いまいゆの魚汁(いうしる)」には、味の素的なものを入れるというし、チューブのにんにくも入れるという。チューブのにんにくは恐くてまだ試していないが、家庭料理にはルール無用(ルールというのは害があるけど益はない)なのでやってみたい。 ツバイは小型の巻き貝なので主に煮つけや塩ゆでで食べられている。身(軟体)は取りだし安く、煮ても軟らかく、甘味が強い。ワタに苦みがなく味わい深いので子供にも人気がある。安い上に、甘味があるので日本海側ではおやつとして食べたという人も少なくない。
ツバイは小型の巻き貝なので主に煮つけや塩ゆでで食べられている。身(軟体)は取りだし安く、煮ても軟らかく、甘味が強い。ワタに苦みがなく味わい深いので子供にも人気がある。安い上に、甘味があるので日本海側ではおやつとして食べたという人も少なくない。 ヒラソウダは産卵期の7、8、9月は不安定な時季だと思っている。9月下旬から安定する。海水温が下がるとともに脂がのってくる。それでは真夏(気象庁が定義する)はおいしくないか、というとおいしいのである。ヒラソウダは脂がのったものもうまいが、脂があまりない時季もうまい。8月8日、小田原魚市場に見事なヒラソウダが並んでいたので、買受人の『さんの水産』さんにお願いして1尾確保してもらう。今回のヒラソウダは体長44cm・1.492kgで大きい。丸々と太っていて触ると非常に硬い。三枚に下ろすと、身が赤く、脂はほどんとない。これが実にうまいのである。すいすいと箸が伸びてすいすいと胃袋に消えて行く。明らかに酸味があるが、うま味100とすると5くらいの比率である。とにかく舌がよろこんでねじれるくらいにうまい。今回は三重県尾鷲市の青唐辛子、「虎の尾」と酢と醤油で食べたら相性がよく、結局半身全部食べてしまう。プーアール茶で我慢しようとしたが無理だった。群馬県吉岡町、「船尾瀧 本醸造」をば冷やして小一合。
ヒラソウダは産卵期の7、8、9月は不安定な時季だと思っている。9月下旬から安定する。海水温が下がるとともに脂がのってくる。それでは真夏(気象庁が定義する)はおいしくないか、というとおいしいのである。ヒラソウダは脂がのったものもうまいが、脂があまりない時季もうまい。8月8日、小田原魚市場に見事なヒラソウダが並んでいたので、買受人の『さんの水産』さんにお願いして1尾確保してもらう。今回のヒラソウダは体長44cm・1.492kgで大きい。丸々と太っていて触ると非常に硬い。三枚に下ろすと、身が赤く、脂はほどんとない。これが実にうまいのである。すいすいと箸が伸びてすいすいと胃袋に消えて行く。明らかに酸味があるが、うま味100とすると5くらいの比率である。とにかく舌がよろこんでねじれるくらいにうまい。今回は三重県尾鷲市の青唐辛子、「虎の尾」と酢と醤油で食べたら相性がよく、結局半身全部食べてしまう。プーアール茶で我慢しようとしたが無理だった。群馬県吉岡町、「船尾瀧 本醸造」をば冷やして小一合。 長野地方卸売市場(長野県長野市)、『万雷食堂』で朝の日替わり定食を食べた。サワラムニエルオイル焼き、納豆、食べ放題のサラダ、きゅうりの醤油味の漬物、みそ汁。どれもこれもおいしいし、満足度も高い。店員さんがほがらかで親切なのもいい。
長野地方卸売市場(長野県長野市)、『万雷食堂』で朝の日替わり定食を食べた。サワラムニエルオイル焼き、納豆、食べ放題のサラダ、きゅうりの醤油味の漬物、みそ汁。どれもこれもおいしいし、満足度も高い。店員さんがほがらかで親切なのもいい。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中に「さんで(サザエ)」がたっぷり入っていた。荷物のふたを開けた途端に海の匂いがした。磯の貝にだけある匂いで、これがこのまま磯の貝の持ち味になる。海の匂いそのままの料理というと「さんで飯(サザエ飯)」だろう、といそいそと素直にサザエの炊き込みご飯を作る。炊き込みご飯は炊き上がりがご馳走だが、ふたを取った途端、予想通りに海の匂いがした。予想通りにうれしくてふわふわした。サザエは硬くない。たまには大人味にしたくて、生殖巣と少しだけの肝膵臓を投入してみたが、微かに苦みがある程度で子供味が好きなボクにもイケル。けだしサザエとは海のうま味と香りそのもので、醤油との相性が抜群にいい。朝昼晩と1日で2合を食べきった、ほどにおいしい。さざえめし 青空真下の 海女のたなごころ
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中に「さんで(サザエ)」がたっぷり入っていた。荷物のふたを開けた途端に海の匂いがした。磯の貝にだけある匂いで、これがこのまま磯の貝の持ち味になる。海の匂いそのままの料理というと「さんで飯(サザエ飯)」だろう、といそいそと素直にサザエの炊き込みご飯を作る。炊き込みご飯は炊き上がりがご馳走だが、ふたを取った途端、予想通りに海の匂いがした。予想通りにうれしくてふわふわした。サザエは硬くない。たまには大人味にしたくて、生殖巣と少しだけの肝膵臓を投入してみたが、微かに苦みがある程度で子供味が好きなボクにもイケル。けだしサザエとは海のうま味と香りそのもので、醤油との相性が抜群にいい。朝昼晩と1日で2合を食べきった、ほどにおいしい。さざえめし 青空真下の 海女のたなごころ 1944年、『松尾食堂』での話である。鎌倉に河岸(魚河岸?)があったらしいということも、非常に興味深い。〈……たまに麺米や平貝が俵で配給された時は、「平貝丼」——貝殻を割って取り出した生のままを5ミリ位の厚さに切り、煮立ったお醤油の中に、さっとくぐらせ、麺米の丼飯の上にならべる——を昼食に出しました。……平貝は現在出廻っているくにゃくにゃとやわらかい物と違い、逗子や鎌倉でとれた物でしたから身がこりこりと硬くしまっていて、大きな真黒な貝を割るのは大変でしたが、それはとてもおいしいものでした。〉「麺米」は資料ではみたことがあるが、実際には知らない。乾麺を細かく切って米粒のようにしたものとある。ゆでてご飯代わりにしたのだろう。それにしても逗子、鎌倉で平貝(タイラギ)が俵に入れて配給するくらいとれたというのは、信じられない話でもある。この湘南の海が今では開発が進み、いかに生き物の棲めない窮屈な海となっているかがわかる。タイラギの貝柱を取り出して、5ミリ前後に切る。これを煮立った生醤油につけて、炊きたてのご飯にのせる。さすがに麺米は探す気にもなれなかった。現代版「平貝丼」である。日本列島すべての人が不幸であった戦時中のことを思うと、申し訳ない気持ちになるが、ご飯に乗せて作る「平貝丼」は素晴らしい味である。みりんや酒を使わずにタイラギだけなのに、強い甘味が醤油にも感じられるのは、貝柱からにじみ出てきた甘味である。酢飯ではなく、ご飯というのがいい。
1944年、『松尾食堂』での話である。鎌倉に河岸(魚河岸?)があったらしいということも、非常に興味深い。〈……たまに麺米や平貝が俵で配給された時は、「平貝丼」——貝殻を割って取り出した生のままを5ミリ位の厚さに切り、煮立ったお醤油の中に、さっとくぐらせ、麺米の丼飯の上にならべる——を昼食に出しました。……平貝は現在出廻っているくにゃくにゃとやわらかい物と違い、逗子や鎌倉でとれた物でしたから身がこりこりと硬くしまっていて、大きな真黒な貝を割るのは大変でしたが、それはとてもおいしいものでした。〉「麺米」は資料ではみたことがあるが、実際には知らない。乾麺を細かく切って米粒のようにしたものとある。ゆでてご飯代わりにしたのだろう。それにしても逗子、鎌倉で平貝(タイラギ)が俵に入れて配給するくらいとれたというのは、信じられない話でもある。この湘南の海が今では開発が進み、いかに生き物の棲めない窮屈な海となっているかがわかる。タイラギの貝柱を取り出して、5ミリ前後に切る。これを煮立った生醤油につけて、炊きたてのご飯にのせる。さすがに麺米は探す気にもなれなかった。現代版「平貝丼」である。日本列島すべての人が不幸であった戦時中のことを思うと、申し訳ない気持ちになるが、ご飯に乗せて作る「平貝丼」は素晴らしい味である。みりんや酒を使わずにタイラギだけなのに、強い甘味が醤油にも感じられるのは、貝柱からにじみ出てきた甘味である。酢飯ではなく、ご飯というのがいい。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道増毛産の甘エビ(ホッコクアカエビ)をたっぷり買った。魚を料理するには暑すぎるし、郷土料理を作りたかったのもあるし、いただいた食材と試したかったのもある。ちなみに北海道の甘エビ漁はほぼ日本海で行われているが、増毛では甘エビ(ホッコクアカエビ)、縞エビ(モロトゲアカエビ)、牡丹エビ(トヤマエビ)の3種前部が安定的に水揚げされている。もっとも行ってみたい町のひとつでもある。本種を生まれて初めて食べたのは学生時代で、アンノン族そのものだった家族とわざわざ銀座まで食べに行ったのだ。1980年前後、とてもトレンディな食べ物だったことがわかる。今や近縁種のホンホッコクアカエビとともに冷凍輸入されてもいるので、非常に身近な、どちらかというと地味なものとなっている。ただし、一度も凍らせていない国産の刺身はスーパーなどに並ぶ格安もののとは別物である。ときどき刺身を飽食したくなるのは、ただ単純にうまいからだ。頭は別の料理に使ったので、もう翌日になった頃に、安物のジンと合わせる。わさびと醤油だけで食べ始めると、非常に甘いけど、この甘いと感じる味はとても複雑である。ねっとりした身と甘いと感じる味とは一体で、口の中でなんの変容も起こさない。ここにスダチ果汁を落としただけのジンが合う。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道増毛産の甘エビ(ホッコクアカエビ)をたっぷり買った。魚を料理するには暑すぎるし、郷土料理を作りたかったのもあるし、いただいた食材と試したかったのもある。ちなみに北海道の甘エビ漁はほぼ日本海で行われているが、増毛では甘エビ(ホッコクアカエビ)、縞エビ(モロトゲアカエビ)、牡丹エビ(トヤマエビ)の3種前部が安定的に水揚げされている。もっとも行ってみたい町のひとつでもある。本種を生まれて初めて食べたのは学生時代で、アンノン族そのものだった家族とわざわざ銀座まで食べに行ったのだ。1980年前後、とてもトレンディな食べ物だったことがわかる。今や近縁種のホンホッコクアカエビとともに冷凍輸入されてもいるので、非常に身近な、どちらかというと地味なものとなっている。ただし、一度も凍らせていない国産の刺身はスーパーなどに並ぶ格安もののとは別物である。ときどき刺身を飽食したくなるのは、ただ単純にうまいからだ。頭は別の料理に使ったので、もう翌日になった頃に、安物のジンと合わせる。わさびと醤油だけで食べ始めると、非常に甘いけど、この甘いと感じる味はとても複雑である。ねっとりした身と甘いと感じる味とは一体で、口の中でなんの変容も起こさない。ここにスダチ果汁を落としただけのジンが合う。 山口県産巨大なシマセトダイを買ったら初めて見る釣り針を飲んでいた。夏であるし、マダイが同じ箱に入っていたので、そんなに水深はない。想像ではマダイ・アマダイなどをねらう延縄のものだろう。飾り気がなく、チモトからケンサキにかけてねむっていなくて真四角な感じ。明らかに漁師専用の針である。今どきの釣り人のキンキラキンとか赤いとかではなく、銀色で質実剛健である。最近の非常に高価な、船釣り用の針よりも釣れそうな気がする。■舵丸水産は、一般客に優しいので、ぜひ近くにお住まいの方は一度お寄り頂きたい。
山口県産巨大なシマセトダイを買ったら初めて見る釣り針を飲んでいた。夏であるし、マダイが同じ箱に入っていたので、そんなに水深はない。想像ではマダイ・アマダイなどをねらう延縄のものだろう。飾り気がなく、チモトからケンサキにかけてねむっていなくて真四角な感じ。明らかに漁師専用の針である。今どきの釣り人のキンキラキンとか赤いとかではなく、銀色で質実剛健である。最近の非常に高価な、船釣り用の針よりも釣れそうな気がする。■舵丸水産は、一般客に優しいので、ぜひ近くにお住まいの方は一度お寄り頂きたい。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に山口県下関市、『下関勇次水産』から真っ黒な魚が来ていた。パーチを剥がすとなんとシマセトダイだった。重さ2㎏はこの魚の最大級だと思う。刺身などいろいろ作っているときに三重県尾鷲市、岩田昭人さんから地元の青唐辛子、「虎の尾」が来た。毎年毎年とてもありがたい。助かります。シマセトダイの刺身を「虎の尾」、酢、醤油で食べ、翌日、安いジンの友にまた刺身を作った。2キロ級はめったに手に入らないと思うが、シマセトダイは小型はあまり味がなく、大きければ大きいほどおいしいと考えていたが、今回の個体など、まさにこれを立証していた。小型ばかり食べていたので、この格差に驚かざるおえない。なんと味のあることだろう。そこに「虎の尾」というのがとてもいい。今回のシマセトダイは、さほど脂がなかったものの、身に張りがありうま味が豊かである。舌に感じる味が長々と続きダレがない。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に山口県下関市、『下関勇次水産』から真っ黒な魚が来ていた。パーチを剥がすとなんとシマセトダイだった。重さ2㎏はこの魚の最大級だと思う。刺身などいろいろ作っているときに三重県尾鷲市、岩田昭人さんから地元の青唐辛子、「虎の尾」が来た。毎年毎年とてもありがたい。助かります。シマセトダイの刺身を「虎の尾」、酢、醤油で食べ、翌日、安いジンの友にまた刺身を作った。2キロ級はめったに手に入らないと思うが、シマセトダイは小型はあまり味がなく、大きければ大きいほどおいしいと考えていたが、今回の個体など、まさにこれを立証していた。小型ばかり食べていたので、この格差に驚かざるおえない。なんと味のあることだろう。そこに「虎の尾」というのがとてもいい。今回のシマセトダイは、さほど脂がなかったものの、身に張りがありうま味が豊かである。舌に感じる味が長々と続きダレがない。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にイワガキが入っていて、でかいのが1つ混ざっていた。最近、天然ものは小型化しているので、18cm・837gはすごい。これを今、いちばん食べたい蒸しイワガキにする。今年は我が故郷徳島県産も、いきなり知らない人がくれた産地不明のイワガキも蒸して食べている。最近流行りの言葉で言えば、マイブームというやつである。我がサイトのうまいもん順もイワガキの1位は蒸す、に変えている。今年に入って連続して作っているものの、今だに蒸し時間がよくわからない。5分蒸し、あとは2分ごとにみて、約10分くらい蒸した。これを食べやすい大きさに切って、すだち果汁を落としては食べる。鳥羽市安楽島のイワガキは産卵期はまだ先のようで、7月末日の個体は非常に食感がよかった。甘味や渋味は蒸すと少し弱くなるが、口の中でおいしさのとどまっている時間が長くなる。ずーっとうまい。実は、すだちはうまさのブレーキ役で、でおいしいの暴走をほどよく抑えている。酒はお礼にもらった缶アルコールいろいろの中から角ハイボールにしたけど、なんでもよかったかもな。
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にイワガキが入っていて、でかいのが1つ混ざっていた。最近、天然ものは小型化しているので、18cm・837gはすごい。これを今、いちばん食べたい蒸しイワガキにする。今年は我が故郷徳島県産も、いきなり知らない人がくれた産地不明のイワガキも蒸して食べている。最近流行りの言葉で言えば、マイブームというやつである。我がサイトのうまいもん順もイワガキの1位は蒸す、に変えている。今年に入って連続して作っているものの、今だに蒸し時間がよくわからない。5分蒸し、あとは2分ごとにみて、約10分くらい蒸した。これを食べやすい大きさに切って、すだち果汁を落としては食べる。鳥羽市安楽島のイワガキは産卵期はまだ先のようで、7月末日の個体は非常に食感がよかった。甘味や渋味は蒸すと少し弱くなるが、口の中でおいしさのとどまっている時間が長くなる。ずーっとうまい。実は、すだちはうまさのブレーキ役で、でおいしいの暴走をほどよく抑えている。酒はお礼にもらった缶アルコールいろいろの中から角ハイボールにしたけど、なんでもよかったかもな。 7月25日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室市『坂井商店』からのマイワシを買った。棒受け網、花咲港揚がりである。1尾70gほどなので小羽サイズである。小さいのにものすごく高い。触ってそのわけがわかる。非常に脂が乗っているのである。しかも鮮度抜群。マイワシは最近、荷(一箱の大きさ)が小さくなり、仕立て(出荷法)で勝負する時代なのがわかる。触るそばから脂がにじみ出るので、刺身は決してきれいじゃない。脂が皮下に層を作るとともに身に刺し込んでいるからだ。1尾分、普通の濃口醤油と辛味控えめのボタンゴショウ(長野県中野市の唐辛子)で食べたら、脂だけではなく背の青い魚のおいしさにもあふれていた。あとはいただきものの鳥取県で醸された刺身醤油をかけ、にんにくをからめ、ご飯にのせて一気食い。関東の濃口醤油にはない、まったりした味の醤油と合わせると、やたらにご飯が進む。小羽なのに味が大きいね〜。
7月25日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室市『坂井商店』からのマイワシを買った。棒受け網、花咲港揚がりである。1尾70gほどなので小羽サイズである。小さいのにものすごく高い。触ってそのわけがわかる。非常に脂が乗っているのである。しかも鮮度抜群。マイワシは最近、荷(一箱の大きさ)が小さくなり、仕立て(出荷法)で勝負する時代なのがわかる。触るそばから脂がにじみ出るので、刺身は決してきれいじゃない。脂が皮下に層を作るとともに身に刺し込んでいるからだ。1尾分、普通の濃口醤油と辛味控えめのボタンゴショウ(長野県中野市の唐辛子)で食べたら、脂だけではなく背の青い魚のおいしさにもあふれていた。あとはいただきものの鳥取県で醸された刺身醤油をかけ、にんにくをからめ、ご飯にのせて一気食い。関東の濃口醤油にはない、まったりした味の醤油と合わせると、やたらにご飯が進む。小羽なのに味が大きいね〜。 八王子総合卸売センター、福泉に、ダツ(ダツ科テンジクダツ属)が来ていた。背鰭の軟条を数えているとみんなが見に来る。見ないでとも言えないので、とにかく数える。すべて25なのでテンジクダツである。1尾買うか、2尾買うかで迷った末に大きなものばかりだったので1尾だけ。ものすごく忙しい日だったので産地を見忘れた。これがボクの今季初テンジクダツ属である。8月から晩秋まで途切れることなく入荷してくる。味のよさを知る人が少ないので安いのもありがたい。押っ取り刀で家に帰り、大急ぎで下ろす。1m近いので半分にして三枚に下ろす。前の方は腹骨や血合い骨が複雑なので、腹鰭の少し前から後ろを刺身にする。この部分は血合い骨こそあるものの、マサバなどとなんら変わりがない。すすーっと刺身にして味見すると、びっくり仰天、脂たっぷりうま味も強い。なにより程よい食感があるのがいい。朝なので、凍頂烏龍茶の茶の子にしたらおいしすぎて、困るほどだった。お昼ご飯もテンジクダツの刺身定食。夜、群馬県前橋市、「桂川 本醸造」ロックで口中を洗いながらくらう。かなりたっぷり食べたのに飽きが来ない。これから背鰭の軟条を数える日々が続くけど、楽しい日々でもある。
八王子総合卸売センター、福泉に、ダツ(ダツ科テンジクダツ属)が来ていた。背鰭の軟条を数えているとみんなが見に来る。見ないでとも言えないので、とにかく数える。すべて25なのでテンジクダツである。1尾買うか、2尾買うかで迷った末に大きなものばかりだったので1尾だけ。ものすごく忙しい日だったので産地を見忘れた。これがボクの今季初テンジクダツ属である。8月から晩秋まで途切れることなく入荷してくる。味のよさを知る人が少ないので安いのもありがたい。押っ取り刀で家に帰り、大急ぎで下ろす。1m近いので半分にして三枚に下ろす。前の方は腹骨や血合い骨が複雑なので、腹鰭の少し前から後ろを刺身にする。この部分は血合い骨こそあるものの、マサバなどとなんら変わりがない。すすーっと刺身にして味見すると、びっくり仰天、脂たっぷりうま味も強い。なにより程よい食感があるのがいい。朝なので、凍頂烏龍茶の茶の子にしたらおいしすぎて、困るほどだった。お昼ご飯もテンジクダツの刺身定食。夜、群馬県前橋市、「桂川 本醸造」ロックで口中を洗いながらくらう。かなりたっぷり食べたのに飽きが来ない。これから背鰭の軟条を数える日々が続くけど、楽しい日々でもある。 今、創造の世界にいて頭を叩いたり、脳みそをかき混ぜたりと、外出できないので仕方がなく保存食でご飯を食べる。最近のご飯は簡単ご飯で、一汁一菜なので、冷凍庫でめぼしいものを掘り起こす。出て来たのはツムブリの腹身で、すでに振り塩をしてある。下ろした日に左右の腹身に振り塩をし、1時間以上置き、水分を拭き取る。片方を焼き、片方を冷凍保存した、その片割れである。室温28℃もあるので、解凍はあっと言う間、水分を拭き取って焼くだけである。取り分け脂が豊かな部分なので、すぐにグリルの中で小さな炎があがる。焼き上がりが早いのでまめに位置を変えて、ひっくり返す。
今、創造の世界にいて頭を叩いたり、脳みそをかき混ぜたりと、外出できないので仕方がなく保存食でご飯を食べる。最近のご飯は簡単ご飯で、一汁一菜なので、冷凍庫でめぼしいものを掘り起こす。出て来たのはツムブリの腹身で、すでに振り塩をしてある。下ろした日に左右の腹身に振り塩をし、1時間以上置き、水分を拭き取る。片方を焼き、片方を冷凍保存した、その片割れである。室温28℃もあるので、解凍はあっと言う間、水分を拭き取って焼くだけである。取り分け脂が豊かな部分なので、すぐにグリルの中で小さな炎があがる。焼き上がりが早いのでまめに位置を変えて、ひっくり返す。 7月25日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でタイラギを買った。いちばん悪いときなのにビックリするくらい高い。八王子というところは豊洲などと比べると安いにも関わらず、この値段か? と、知りあいのすし屋と顔を見合わせた。それでもすし屋は買って行くし、ボクも1つだけ買う。夏枯れに、大型のタイラギはありがたいくらいなのだろう。貝殻の長さが31cm・重さは614gで、軟体の重さは2割前後と痩せていた。生殖巣は見られなかったので、産卵後だと思われる。ただ、下ろしたら貝柱はそれほど痩せていない。すし屋のすごいところは重さや脇から見た感じで、良し悪しを見極めているところだ。ボクが買おうと思ったのも、すし屋の見極めを信じたからだ。貝柱はふくよかさに欠けていたが実にいい味であった。食感が心地よく、うま味が非常に豊かでしかも独特のおいしい渋味がある。甘味は後から追いかけてくるのだけれども、こちらも強い。ついでに言うと、びら(外套膜)がやたらにおいしかった。小さい方の貝柱も同様にうまい。7月末日の産地不明のタイラギはアタリだったが、自分で選ぶ自信はない。
7月25日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でタイラギを買った。いちばん悪いときなのにビックリするくらい高い。八王子というところは豊洲などと比べると安いにも関わらず、この値段か? と、知りあいのすし屋と顔を見合わせた。それでもすし屋は買って行くし、ボクも1つだけ買う。夏枯れに、大型のタイラギはありがたいくらいなのだろう。貝殻の長さが31cm・重さは614gで、軟体の重さは2割前後と痩せていた。生殖巣は見られなかったので、産卵後だと思われる。ただ、下ろしたら貝柱はそれほど痩せていない。すし屋のすごいところは重さや脇から見た感じで、良し悪しを見極めているところだ。ボクが買おうと思ったのも、すし屋の見極めを信じたからだ。貝柱はふくよかさに欠けていたが実にいい味であった。食感が心地よく、うま味が非常に豊かでしかも独特のおいしい渋味がある。甘味は後から追いかけてくるのだけれども、こちらも強い。ついでに言うと、びら(外套膜)がやたらにおいしかった。小さい方の貝柱も同様にうまい。7月末日の産地不明のタイラギはアタリだったが、自分で選ぶ自信はない。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にサザエがたっぷり入っていた。今、創造の世界にいて、引きこもり状態となっているので、ありがたや♪ ありがたや♪ by守屋浩である。(ちょい旅先で耳に飛び込んできて、頭から離れない。これはまさしく名曲だと思う)大きめのサザエを剥き身にして苦味のある内臓は少しだけ残し、足を刺身にする。ワタは湯通しして氷水に落とし、水分を切る。ちなみにサザエは剥き身にしやすく、刺身にしてもぬめりが少ない。巻き貝の中でももっとも難易度が低い。しかも料理に困ったらそのまま壺焼きにすればいい。たっぷり造って、たっぷり食べたいのがサザエの刺身だ。これにいただきものの『夢産地とさやま開発公社』(高知市土佐山桑尾)の柚子果汁をじゃぶじゃぶかけて、塩味で食べる。ちょうどヴァランダーを再読したいと思っているので、酒はスエーデンのアブソルートのソーダ割り。刺身を楊子でちまちま口に運んではアブソルートで舌を洗い、またサザエでアブソルートというのがいいのである。サザエの刺身は磯というか海の香がする。海風を思わせる味でもある。大量に造っても足りないくらいにボク好みの味で、合いの手で食べるワタも少しだけならいい感じである。刺身を食べ終わった途端、意識が遠のいて行く、ありがたや♪ ありがたや♪
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にサザエがたっぷり入っていた。今、創造の世界にいて、引きこもり状態となっているので、ありがたや♪ ありがたや♪ by守屋浩である。(ちょい旅先で耳に飛び込んできて、頭から離れない。これはまさしく名曲だと思う)大きめのサザエを剥き身にして苦味のある内臓は少しだけ残し、足を刺身にする。ワタは湯通しして氷水に落とし、水分を切る。ちなみにサザエは剥き身にしやすく、刺身にしてもぬめりが少ない。巻き貝の中でももっとも難易度が低い。しかも料理に困ったらそのまま壺焼きにすればいい。たっぷり造って、たっぷり食べたいのがサザエの刺身だ。これにいただきものの『夢産地とさやま開発公社』(高知市土佐山桑尾)の柚子果汁をじゃぶじゃぶかけて、塩味で食べる。ちょうどヴァランダーを再読したいと思っているので、酒はスエーデンのアブソルートのソーダ割り。刺身を楊子でちまちま口に運んではアブソルートで舌を洗い、またサザエでアブソルートというのがいいのである。サザエの刺身は磯というか海の香がする。海風を思わせる味でもある。大量に造っても足りないくらいにボク好みの味で、合いの手で食べるワタも少しだけならいい感じである。刺身を食べ終わった途端、意識が遠のいて行く、ありがたや♪ ありがたや♪ ボクが生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)には、「うどん屋」はあったけど、「そば屋」はなかった。あくまで麺の話ではあるが、県の真ん中あたりにある剣山に、近ければ近いほど「そば食文化」で、街中にくると「うどん食文化」だった。商店だったので、小学生くらいになると店が忙しいときは、歩いてすぐのところにある、『みどり屋』か、『飯田食堂』で、うどんか中華そばを食べた。配達で奥(一宇村もしくは端山村)に行くと、土釜のうどんを食べることが決まりだった。これがボクがときどき再現している理想のうどんである。理想の素うどんのうどんはゆでうどんであり、温めるとき、芯まで温めるが熱くしてはいけない。噛んで熱いと感じたら失格だ。つゆは煮干しでとったつゆで角があって、きれがよいもので、最初に塩気が来て、醤油のこくがあり、後からうま味の大波がくる。終いはサラリとした感じるのが理想だ。丼の中全体があまり熱くないのでするすると、短時間で麺をすすり込み、もういっぱい食べたくならないとダメだ。それにしても東京に真っ赤な「板つけ」がないのが悲しい。致し方なく、油揚げを刻んだが、「板つけ」やーい、とぞ思う。ついでに丼は1950年代以前のものだけど、今現在のうどん1前を入れるには小さすぎる。うどんは昔は間食のようなものであって、食事ではなかったのだ。これに合うゆでうどんがあるともっともっと理想的だ。
ボクが生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)には、「うどん屋」はあったけど、「そば屋」はなかった。あくまで麺の話ではあるが、県の真ん中あたりにある剣山に、近ければ近いほど「そば食文化」で、街中にくると「うどん食文化」だった。商店だったので、小学生くらいになると店が忙しいときは、歩いてすぐのところにある、『みどり屋』か、『飯田食堂』で、うどんか中華そばを食べた。配達で奥(一宇村もしくは端山村)に行くと、土釜のうどんを食べることが決まりだった。これがボクがときどき再現している理想のうどんである。理想の素うどんのうどんはゆでうどんであり、温めるとき、芯まで温めるが熱くしてはいけない。噛んで熱いと感じたら失格だ。つゆは煮干しでとったつゆで角があって、きれがよいもので、最初に塩気が来て、醤油のこくがあり、後からうま味の大波がくる。終いはサラリとした感じるのが理想だ。丼の中全体があまり熱くないのでするすると、短時間で麺をすすり込み、もういっぱい食べたくならないとダメだ。それにしても東京に真っ赤な「板つけ」がないのが悲しい。致し方なく、油揚げを刻んだが、「板つけ」やーい、とぞ思う。ついでに丼は1950年代以前のものだけど、今現在のうどん1前を入れるには小さすぎる。うどんは昔は間食のようなものであって、食事ではなかったのだ。これに合うゆでうどんがあるともっともっと理想的だ。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にオニサザエが入っていた。せっかくなので「食用貝類基本のキ」を書く。オニサザエは食用貝だが、認知度はきわめて低い。知っていたら学者級である。オニサザエはアッキガイ科テングガイ属の巻き貝だ。この属の巻き貝は国内に約16種いるが、大型は総て食用貝である可能性が高く、おしなべて味がいい。本種は房総半島・能登半島以南の浅い磯(岩礁域)に生息している。褐色で岩そのものの色合いで黒褐色で、非常に刺々しい。棘はざらついて長い。ちなみに同じアッキガイ科テングガイ属のオニサザエ、センジュモドキ、ガンゼキボラの3種は同じように浅い岩礁域にいて、同じ食文化を作っている。手に入れていないがセンジュガイもそこに入ると思われる。4種は非常に似ていて、貝の同定に熟達していないと区別がつかないので、よくとり違えられていることも知って置くべきだ。ただし実見した限りでは、いちばん小売店などで見かける機会が多いのがオニサザエで、また地方名も多い。『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社)とボク自身が集めた呼び名を整理するとその特徴が浮かんでくる。「棘」や「針」、「鬼」がつく名前が多いのは棘だらけだから。鳥羽市安楽島の「がんこーじ」は直感的だが「岩」に関係しているでは、と考えている。同様な例では「岩ぼら」がある。「さざえ」と呼ぶ地域があるがこれも「細石」の転訛だとしたら石のことだ。「鬼の手拳」、「鬼の手ご」なども貝殻が非常に硬いことと、その刺々しいところから来たのだろう。
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに送って頂いた貝類の中にオニサザエが入っていた。せっかくなので「食用貝類基本のキ」を書く。オニサザエは食用貝だが、認知度はきわめて低い。知っていたら学者級である。オニサザエはアッキガイ科テングガイ属の巻き貝だ。この属の巻き貝は国内に約16種いるが、大型は総て食用貝である可能性が高く、おしなべて味がいい。本種は房総半島・能登半島以南の浅い磯(岩礁域)に生息している。褐色で岩そのものの色合いで黒褐色で、非常に刺々しい。棘はざらついて長い。ちなみに同じアッキガイ科テングガイ属のオニサザエ、センジュモドキ、ガンゼキボラの3種は同じように浅い岩礁域にいて、同じ食文化を作っている。手に入れていないがセンジュガイもそこに入ると思われる。4種は非常に似ていて、貝の同定に熟達していないと区別がつかないので、よくとり違えられていることも知って置くべきだ。ただし実見した限りでは、いちばん小売店などで見かける機会が多いのがオニサザエで、また地方名も多い。『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社)とボク自身が集めた呼び名を整理するとその特徴が浮かんでくる。「棘」や「針」、「鬼」がつく名前が多いのは棘だらけだから。鳥羽市安楽島の「がんこーじ」は直感的だが「岩」に関係しているでは、と考えている。同様な例では「岩ぼら」がある。「さざえ」と呼ぶ地域があるがこれも「細石」の転訛だとしたら石のことだ。「鬼の手拳」、「鬼の手ご」なども貝殻が非常に硬いことと、その刺々しいところから来たのだろう。 石川県・福井県に「塩いり」・「浜いり」、沖縄県に「まーす煮」というのがある。やや強めの塩水で短時間水分を飛ばしながら煮るというもの。郷土料理ではあるが古代には日本列島全域で作られていたものだろう。また我がサイトでデータとして聞取し、画像を持っているのがこの3県だけだという話で、全国を見渡すといずれかの地域に同様の料理が残っているはずである。スズキの頭部やあらを塩煮にしようとして、豆腐がないことに気がついた。塩煮の豆腐は魚以上にうまい。非常に残念だが、なければそれでいいのが家庭料理のよさなのである。ていねいに鱗をとり、水分をきったあらを用意する。大きめの鉄鍋に水と多めの塩を煮立たせたなかに放り込む。あとは一気呵成、終始強火で煮るだけである。物理的には塩分濃度の高い煮汁の中にうま味が出てしまいそうだが、出ない。水分量が少ないためだと思う。それでも煮汁は非常に味が濃い。塩が濃いというよりもうま味豊かだと言えばわかってもらえるだろう。請戸のスズキが非常にていねいに処理され、乗っているためだろうか、煮上がりが美しいし、非常に柔らかい。全部が全部おいしさの塊のようである。最近、長野県長野市「若緑」本醸造をロックで飲む、そんなひ弱なボクだけど、いい酒の時間が過ごせた。
石川県・福井県に「塩いり」・「浜いり」、沖縄県に「まーす煮」というのがある。やや強めの塩水で短時間水分を飛ばしながら煮るというもの。郷土料理ではあるが古代には日本列島全域で作られていたものだろう。また我がサイトでデータとして聞取し、画像を持っているのがこの3県だけだという話で、全国を見渡すといずれかの地域に同様の料理が残っているはずである。スズキの頭部やあらを塩煮にしようとして、豆腐がないことに気がついた。塩煮の豆腐は魚以上にうまい。非常に残念だが、なければそれでいいのが家庭料理のよさなのである。ていねいに鱗をとり、水分をきったあらを用意する。大きめの鉄鍋に水と多めの塩を煮立たせたなかに放り込む。あとは一気呵成、終始強火で煮るだけである。物理的には塩分濃度の高い煮汁の中にうま味が出てしまいそうだが、出ない。水分量が少ないためだと思う。それでも煮汁は非常に味が濃い。塩が濃いというよりもうま味豊かだと言えばわかってもらえるだろう。請戸のスズキが非常にていねいに処理され、乗っているためだろうか、煮上がりが美しいし、非常に柔らかい。全部が全部おいしさの塊のようである。最近、長野県長野市「若緑」本醸造をロックで飲む、そんなひ弱なボクだけど、いい酒の時間が過ごせた。 イタリアナスはイタリア語でVioletta di Firenze と言うらしいと、近所のオバチャンが調べてくれた。最近、やっちゃ場(青果市場)では在り来たりな野菜らしい。初めて来たときは飛びついたが、今は安いときだけ買う。近所のスーパーにもあって、かなりお高かった。八王子総合卸売センター、八百角ではなく普通の店で買うと高いのだろうな。これをツムブリとソテーしたら、丸ナスとか普通のナスよりも上、とまでは言えないけど、切身のふんわり感にナスのふんわり感がとても調和してよかった。要するにツムブリを多めの油でソテーすると、うま味と、焦げた風味がじわりと出る。それを少しだけふんわりしたイタリアナスが吸う。なんだか食べでがあるし、一気に食べてしまうだけの魅力がある。昼に、これと凍頂烏龍茶だけで、夜まで間食なしで過ごせた。腹持ちのいいナスである。本当の主役はツムブリなのに、脇役のはずの西村晃が目立っていたといった感じ。
イタリアナスはイタリア語でVioletta di Firenze と言うらしいと、近所のオバチャンが調べてくれた。最近、やっちゃ場(青果市場)では在り来たりな野菜らしい。初めて来たときは飛びついたが、今は安いときだけ買う。近所のスーパーにもあって、かなりお高かった。八王子総合卸売センター、八百角ではなく普通の店で買うと高いのだろうな。これをツムブリとソテーしたら、丸ナスとか普通のナスよりも上、とまでは言えないけど、切身のふんわり感にナスのふんわり感がとても調和してよかった。要するにツムブリを多めの油でソテーすると、うま味と、焦げた風味がじわりと出る。それを少しだけふんわりしたイタリアナスが吸う。なんだか食べでがあるし、一気に食べてしまうだけの魅力がある。昼に、これと凍頂烏龍茶だけで、夜まで間食なしで過ごせた。腹持ちのいいナスである。本当の主役はツムブリなのに、脇役のはずの西村晃が目立っていたといった感じ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げて来たもので、3㎏を超える雄の白子持ちの個体でこれでもか、と料理した。中でももっとも大量に作ったのが「なめろう(みそたたき)」だ。「なめろう」は、「みそたたき」の千葉県外房での呼び名だが、特徴は酢で食べることだ。「なめろう」はできるだけ切れる包丁で、ツムブリの身、夏の青じそ、みょうが、長野県中野市の青唐辛子「ぼたんごしょう」、静岡県浜松市『加藤醤油』の「大地」というみそでかなり徹底的にたたく。魚のうま味に香辛野菜の味、夏の青唐辛子の辛味、そしてみその味わいを全部足し算したのが「なめろう」である。「うまいに決まってるだろう」と千葉県千倉のオッカサンに言われてことがあるが、「なめろう」は作る魚で味が違っている。アジ科の魚はすべて「なめろう」に向いている。あまり脂が乗っていなかったツムブリだけど、豊かなうま味がある。酸味はほとんどないが、酢をつけながら食べることで夏の熱気が失せる。小型のツムブリで作ったことはあるが、うま味は今回の個体ほどにはなかった。鱠皿いっぱいのツムブリの「なめろう」が見る間に消えて行く。それにしても浜松市のみそはうまい。「ぼたんごしょう」の辛味もいい。半分翌日の「さんが焼き」に残したいと思ったが、残せなかった。「なめろう」に合わせたのは、サッポロの銀座ライオンビヤホールスペシャルという、長い名前のビールを350mlだけ。なめろう(みそたたき)はビールにも合う。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げて来たもので、3㎏を超える雄の白子持ちの個体でこれでもか、と料理した。中でももっとも大量に作ったのが「なめろう(みそたたき)」だ。「なめろう」は、「みそたたき」の千葉県外房での呼び名だが、特徴は酢で食べることだ。「なめろう」はできるだけ切れる包丁で、ツムブリの身、夏の青じそ、みょうが、長野県中野市の青唐辛子「ぼたんごしょう」、静岡県浜松市『加藤醤油』の「大地」というみそでかなり徹底的にたたく。魚のうま味に香辛野菜の味、夏の青唐辛子の辛味、そしてみその味わいを全部足し算したのが「なめろう」である。「うまいに決まってるだろう」と千葉県千倉のオッカサンに言われてことがあるが、「なめろう」は作る魚で味が違っている。アジ科の魚はすべて「なめろう」に向いている。あまり脂が乗っていなかったツムブリだけど、豊かなうま味がある。酸味はほとんどないが、酢をつけながら食べることで夏の熱気が失せる。小型のツムブリで作ったことはあるが、うま味は今回の個体ほどにはなかった。鱠皿いっぱいのツムブリの「なめろう」が見る間に消えて行く。それにしても浜松市のみそはうまい。「ぼたんごしょう」の辛味もいい。半分翌日の「さんが焼き」に残したいと思ったが、残せなかった。「なめろう」に合わせたのは、サッポロの銀座ライオンビヤホールスペシャルという、長い名前のビールを350mlだけ。なめろう(みそたたき)はビールにも合う。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に福島県浪江町請戸から「ふっこ(スズキの若い個体)」が来ていた。いわき市の『海宝水産』からで、体高があり、背が左右に膨らんでいる。触らなくても上物だ、と思えたので、いきなり確保する。体長34cm・0.6㎏なのでまさに「ふっこサイズ」だ。以上は前回書いた。今回は刺身、塩焼き、煮つけと平凡な料理ばかり作った。取り分けおいしかったのは塩焼きである。塩焼きの作り方は切り身にして振り塩をするだけ。コツはすぐに焼かないことだ。できれば1時間以上は寝かして欲しいものである。今回は買ったその日に振り塩をして、翌日夜に酒の肴に焼いた。ときどき小さな炎が上がるので、焼け具合を見ながら焼く。皿に盛り、いの一番に香りをいただく。汽水域に多いスズキは皮目の香りが御馳走である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に福島県浪江町請戸から「ふっこ(スズキの若い個体)」が来ていた。いわき市の『海宝水産』からで、体高があり、背が左右に膨らんでいる。触らなくても上物だ、と思えたので、いきなり確保する。体長34cm・0.6㎏なのでまさに「ふっこサイズ」だ。以上は前回書いた。今回は刺身、塩焼き、煮つけと平凡な料理ばかり作った。取り分けおいしかったのは塩焼きである。塩焼きの作り方は切り身にして振り塩をするだけ。コツはすぐに焼かないことだ。できれば1時間以上は寝かして欲しいものである。今回は買ったその日に振り塩をして、翌日夜に酒の肴に焼いた。ときどき小さな炎が上がるので、焼け具合を見ながら焼く。皿に盛り、いの一番に香りをいただく。汽水域に多いスズキは皮目の香りが御馳走である。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でキハダマグロの若い個体18kg前後のロインをサクにしていた。忙しい日だったので1サク買って帰ってきた。キハダマグロのサク買いは安くて、おいしくて、市場から帰った日のお昼ご飯にすぐ食べることができて、といいこと尽くめである。ちなみに築地に大物競りを見に通っていた2005年から2010年くらいまで、大物競り場でたくさんの人の話を聞いた。本マ(クロマグロ)だけの築地だとばっかり思っていたら、意外にキハダマグロを好む仲買が決して少なくないことに気づいた。大物の目利きで、キハダマグロをついでに競って帰る人がいる。気になったので、キハダマグロを競り落とした方の店までサクを買いに行ったこともある。このサクのおいしかったこと、は今も忘れない。以来のキハダ好きである。ちなみに雑喉場研究家だった故酒井亮介さんは、大阪の「はつ好き」(はつは大阪でのキハダマグロの呼び名)は産地である紀州(和歌山)が近いからだと言っていた。東京では周辺であまりとれないので、あまり食べなかったようだ。それが今や東京近海はクロマグロよりも、キハダマグロが多い気がする。関東でもキハダマグロをふんだんに食べるべきなのである。銚子産のキハダの刺身がやたらにうまかった。18kgくらいだろうと言っていたが、もっと大型かも知れぬ。もちろんクロマグロの脂の甘さや濃厚なうま味はないものの、さらりとおいしくてちゃんとマグロらしいうまさが楽しめる。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でキハダマグロの若い個体18kg前後のロインをサクにしていた。忙しい日だったので1サク買って帰ってきた。キハダマグロのサク買いは安くて、おいしくて、市場から帰った日のお昼ご飯にすぐ食べることができて、といいこと尽くめである。ちなみに築地に大物競りを見に通っていた2005年から2010年くらいまで、大物競り場でたくさんの人の話を聞いた。本マ(クロマグロ)だけの築地だとばっかり思っていたら、意外にキハダマグロを好む仲買が決して少なくないことに気づいた。大物の目利きで、キハダマグロをついでに競って帰る人がいる。気になったので、キハダマグロを競り落とした方の店までサクを買いに行ったこともある。このサクのおいしかったこと、は今も忘れない。以来のキハダ好きである。ちなみに雑喉場研究家だった故酒井亮介さんは、大阪の「はつ好き」(はつは大阪でのキハダマグロの呼び名)は産地である紀州(和歌山)が近いからだと言っていた。東京では周辺であまりとれないので、あまり食べなかったようだ。それが今や東京近海はクロマグロよりも、キハダマグロが多い気がする。関東でもキハダマグロをふんだんに食べるべきなのである。銚子産のキハダの刺身がやたらにうまかった。18kgくらいだろうと言っていたが、もっと大型かも知れぬ。もちろんクロマグロの脂の甘さや濃厚なうま味はないものの、さらりとおいしくてちゃんとマグロらしいうまさが楽しめる。 節約生活になり、やってくる荷物を待ったり、テレビ電話に応じたりで、外出不能となったときは、炊き込みご飯とあいなる。炊き込みご飯は簡単だし、しかも素材を無駄なく使える。7月半ば、八王子卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが利島か銭州で釣り上げた、クサヤモロを塩焼きにした。大失敗して炭っぽくなったのを、捨てないで表面の粉状の炭をこそげ取り冷凍保存して置いた。解凍してあらくほぐして、小骨だけをよけて。中骨などはそのまま、醤油・酒で炊き込む。炊き上がりにミョウガ、粗挽き黒コショウを混ぜ込み、長野県北信の青唐辛子「ぼたんごしょう」を刻み盛る。焼きすぎた塩焼きを炊き込むと、焼きすぎがむしろ味となる。クサヤモロは脂こそそんなに豊かではないが強い味がある。このところし醤油味で炊き込んでいるが、醤油の風味との相性もいい。黒コショウのピリもいい感じである。鉄釜での2合炊きで、4食分になるのだから助かる。大量買いした安い緑晩茶ではなく、静岡県掛川の上煎茶を淹れる。
節約生活になり、やってくる荷物を待ったり、テレビ電話に応じたりで、外出不能となったときは、炊き込みご飯とあいなる。炊き込みご飯は簡単だし、しかも素材を無駄なく使える。7月半ば、八王子卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが利島か銭州で釣り上げた、クサヤモロを塩焼きにした。大失敗して炭っぽくなったのを、捨てないで表面の粉状の炭をこそげ取り冷凍保存して置いた。解凍してあらくほぐして、小骨だけをよけて。中骨などはそのまま、醤油・酒で炊き込む。炊き上がりにミョウガ、粗挽き黒コショウを混ぜ込み、長野県北信の青唐辛子「ぼたんごしょう」を刻み盛る。焼きすぎた塩焼きを炊き込むと、焼きすぎがむしろ味となる。クサヤモロは脂こそそんなに豊かではないが強い味がある。このところし醤油味で炊き込んでいるが、醤油の風味との相性もいい。黒コショウのピリもいい感じである。鉄釜での2合炊きで、4食分になるのだから助かる。大量買いした安い緑晩茶ではなく、静岡県掛川の上煎茶を淹れる。 中野市、長野市、飯綱町、信濃町の北信地方のナスといったら丸ナスである。実際、この地域のスーパーにも直売所にも、普通のナスもあるけど、地元で栽培されだろう丸ナスが幅をきかせている。新潟でもナスの分布域を調べたいけど、まだ実行していない。今現在新潟県の情報は妙高市新井の女性も丸ナスをよく食べていたということだけだ。長野県飯綱町の滝澤さんにも、信濃町の老人にも、中野市のそば屋さん、妙高市の女性にしても、基本的な料理法は油で炒める、である。実際、多めの油でソテーして、醤油をかけ回して食べると、やたらにおいしい。もちろんみそ汁に入れてもいいけど、油を使った料理に向いている気がする。■写真は丸ナスを青唐辛子の「ぼたんごしょう」と多めの油で炒めて醤油を回しかけたもの。
中野市、長野市、飯綱町、信濃町の北信地方のナスといったら丸ナスである。実際、この地域のスーパーにも直売所にも、普通のナスもあるけど、地元で栽培されだろう丸ナスが幅をきかせている。新潟でもナスの分布域を調べたいけど、まだ実行していない。今現在新潟県の情報は妙高市新井の女性も丸ナスをよく食べていたということだけだ。長野県飯綱町の滝澤さんにも、信濃町の老人にも、中野市のそば屋さん、妙高市の女性にしても、基本的な料理法は油で炒める、である。実際、多めの油でソテーして、醤油をかけ回して食べると、やたらにおいしい。もちろんみそ汁に入れてもいいけど、油を使った料理に向いている気がする。■写真は丸ナスを青唐辛子の「ぼたんごしょう」と多めの油で炒めて醤油を回しかけたもの。 生まれて初めてのミンチカツは、徳島市内、市場で買ってもらったものだと記憶してる。ボクの生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)商店街の、家の通りを挟んだ正面の肉屋にはなかった気がする。上京したら「ミンチカツ」じゃなくて「メンチカツ」と書かれていた。それほど気にしないでミンチカツと言ったりメンチカツと言ったりした。東京都世田谷区弦巻の洋食店で、1週間に1度だけ外食していた時期があって、メンチカツばかり食べていた。ロースカツよりも安かったからだ。どうやら関西圏ではミンチカツで、関東ではメンチカツみたいだと明確に脳みそに刻みつけたのはその頃だ。ということでカツオの血合いを叩いてカツ(フライ)にしたものも、徳島生まれのボクにはミンチカツかな。ナツメッグがきいているのもいい。いつもは牛乳を使うのだけど、切らしていてバターと卵黄、小麦粉を加えてソフトにした。ミンチにしてもカツオ特有のうまい、がぐんぐんと舌を押してくる。しっとりしているのはバターのせいだが、硬く締まりがちなカツオの身が柔らかいのもいい。じゃぼじゃぼとウスターソースをかけて、お昼ご飯にする。
生まれて初めてのミンチカツは、徳島市内、市場で買ってもらったものだと記憶してる。ボクの生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)商店街の、家の通りを挟んだ正面の肉屋にはなかった気がする。上京したら「ミンチカツ」じゃなくて「メンチカツ」と書かれていた。それほど気にしないでミンチカツと言ったりメンチカツと言ったりした。東京都世田谷区弦巻の洋食店で、1週間に1度だけ外食していた時期があって、メンチカツばかり食べていた。ロースカツよりも安かったからだ。どうやら関西圏ではミンチカツで、関東ではメンチカツみたいだと明確に脳みそに刻みつけたのはその頃だ。ということでカツオの血合いを叩いてカツ(フライ)にしたものも、徳島生まれのボクにはミンチカツかな。ナツメッグがきいているのもいい。いつもは牛乳を使うのだけど、切らしていてバターと卵黄、小麦粉を加えてソフトにした。ミンチにしてもカツオ特有のうまい、がぐんぐんと舌を押してくる。しっとりしているのはバターのせいだが、硬く締まりがちなカツオの身が柔らかいのもいい。じゃぼじゃぼとウスターソースをかけて、お昼ご飯にする。 そろそろイカだな、と思って八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店先に行き。バライカ(スルメイカの若い個体)にするか、ダルマ(小型のケンサキイカ)にするか迷って、ケンサキイカを2はいを手に取る。長崎県平戸産である。メヒカリイカ型(小型のまま繁殖する個体群)で小さいが抱卵していた。素直に刺身にして酒の肴にする。小さくてもちゃんとねっとりして甘い。非常に味が濃い。意外なおいしさにちょっとだけ驚き、味のメモをとろうとして文字が浮かばない。平戸産小型のケンサキはうまいとしか書きようがない。
そろそろイカだな、と思って八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の店先に行き。バライカ(スルメイカの若い個体)にするか、ダルマ(小型のケンサキイカ)にするか迷って、ケンサキイカを2はいを手に取る。長崎県平戸産である。メヒカリイカ型(小型のまま繁殖する個体群)で小さいが抱卵していた。素直に刺身にして酒の肴にする。小さくてもちゃんとねっとりして甘い。非常に味が濃い。意外なおいしさにちょっとだけ驚き、味のメモをとろうとして文字が浮かばない。平戸産小型のケンサキはうまいとしか書きようがない。 ミョウガの足のみそ汁をすすりながら暫し思ったこと。「ミョウガの足」は東京都八王子市やっちゃ場(青果市場)での呼び名で、高知県では「みょうがの茎」というらしい。八王子総合卸売センター、八百角で見つけると必ず買うもので、根本は少し硬いが赤茶色の花(?)の部分は柔らかい。ミョウガのみそ汁は毎日でもいいので、これをざくざく粗く刻んでだし(このときのだしは、アジ節/ムロアジ、さば節/ゴマサバに日高昆布)にぶっ込み、みそを溶く。ミョウガは物忘れもしそうだが、暑さ忘れも出来る。
ミョウガの足のみそ汁をすすりながら暫し思ったこと。「ミョウガの足」は東京都八王子市やっちゃ場(青果市場)での呼び名で、高知県では「みょうがの茎」というらしい。八王子総合卸売センター、八百角で見つけると必ず買うもので、根本は少し硬いが赤茶色の花(?)の部分は柔らかい。ミョウガのみそ汁は毎日でもいいので、これをざくざく粗く刻んでだし(このときのだしは、アジ節/ムロアジ、さば節/ゴマサバに日高昆布)にぶっ込み、みそを溶く。ミョウガは物忘れもしそうだが、暑さ忘れも出来る。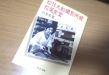 『松竹大船撮影所前 松尾食堂』(山本若菜 中公文庫)は単行本としては1986年のもの。神奈川県鎌倉市大船、撮影所前にあった『松尾食堂』の歴史でもあるが、ここには松竹大船撮影所の歴史というか映画の歴史がある。食堂という場所でなければ見られない映画監督、俳優の、地の部分が垣間見えるのも面白い。文章の中に少ないながら料理の変遷や料理名の変化が見て取れる。
『松竹大船撮影所前 松尾食堂』(山本若菜 中公文庫)は単行本としては1986年のもの。神奈川県鎌倉市大船、撮影所前にあった『松尾食堂』の歴史でもあるが、ここには松竹大船撮影所の歴史というか映画の歴史がある。食堂という場所でなければ見られない映画監督、俳優の、地の部分が垣間見えるのも面白い。文章の中に少ないながら料理の変遷や料理名の変化が見て取れる。 年間を通して、いろんな大きさのツムブリを食べているが、やはり2㎏以上がおいしい。旬は8月以降で秋が深まると脂が乗ってくる。7月の3㎏ものは小さな白子を抱えていた。産卵はまだまだ先である。毎年、8月後半から脂が乗ってくるので、7月はまだ脂の乗りはわるい。ただ獲物を飽食しているのだろう。刺身は食感がほどよく強いうま味がある。この味が舌の上で延々と残る。
年間を通して、いろんな大きさのツムブリを食べているが、やはり2㎏以上がおいしい。旬は8月以降で秋が深まると脂が乗ってくる。7月の3㎏ものは小さな白子を抱えていた。産卵はまだまだ先である。毎年、8月後半から脂が乗ってくるので、7月はまだ脂の乗りはわるい。ただ獲物を飽食しているのだろう。刺身は食感がほどよく強いうま味がある。この味が舌の上で延々と残る。 エゴマの醤油漬けでご飯、というのがやたらに好きだ。醤油と胡麻油で1枚1枚漬け込んでいるだけの醤油漬けは、ご飯をどんどん消費していく。やめられなくなる。しかも夏を感じる味でもある。エゴマの独特の風味はエゴマの風味としか表現できない。青じそとの違いは葉に甘みがあることかも。そこがご飯に合う。
エゴマの醤油漬けでご飯、というのがやたらに好きだ。醤油と胡麻油で1枚1枚漬け込んでいるだけの醤油漬けは、ご飯をどんどん消費していく。やめられなくなる。しかも夏を感じる味でもある。エゴマの独特の風味はエゴマの風味としか表現できない。青じそとの違いは葉に甘みがあることかも。そこがご飯に合う。 水産生物と人間との関わりを調べている限り、普通の小売店、魚屋、スーパー巡りは欠かせない。市場や漁場で水産生物を探しているだけでは、なんにもわかりはしない。さて、長野県飯綱町、第一スーパーで見つけたのが「山田のさばカツ」だ。大分県佐伯市『山田水産』が作っているもので、九州から北信に送られて来たんだな、というのも感慨深い。大きな会社らしいが、このようなオヤジの琴線に触れる商品を作っているところがすごい。サバのカツ(フライ)に甘辛いたれを染み込ませたもので、実にイケている味である。ちょっと温めるとやたらにおいしくて、もうひとつの「さんまの蒲焼き」も買えばよかったと後悔した。ちなみに最近、やたら無機質なラベルの、無機質で上品な加工品が多くなってきている。ちっとも魅力的ではないけど、売れるんだろう。「山田のさばカツ」のような人間味のある商品が増えるといいな。たぶん今どきの若い衆も好きだと思う。
水産生物と人間との関わりを調べている限り、普通の小売店、魚屋、スーパー巡りは欠かせない。市場や漁場で水産生物を探しているだけでは、なんにもわかりはしない。さて、長野県飯綱町、第一スーパーで見つけたのが「山田のさばカツ」だ。大分県佐伯市『山田水産』が作っているもので、九州から北信に送られて来たんだな、というのも感慨深い。大きな会社らしいが、このようなオヤジの琴線に触れる商品を作っているところがすごい。サバのカツ(フライ)に甘辛いたれを染み込ませたもので、実にイケている味である。ちょっと温めるとやたらにおいしくて、もうひとつの「さんまの蒲焼き」も買えばよかったと後悔した。ちなみに最近、やたら無機質なラベルの、無機質で上品な加工品が多くなってきている。ちっとも魅力的ではないけど、売れるんだろう。「山田のさばカツ」のような人間味のある商品が増えるといいな。たぶん今どきの若い衆も好きだと思う。 秋田県男鹿半島沖、痩せた個体が多い場所の赤テリ(ウスメバル)を刺身、焼霜造り、煮つけ、バター焼きにしてみた。3尾いて一番左右幅のあるものの刺身は、非常においしかった。ウスメバルは漁期ははっきりしているが、卵胎生の魚の特徴として旬がわかりにくい。今回、この個体だけ身に張りがあり、刺身に引くと味と甘味があった。舌の上で味のだれがない。このおいしさは予想外。
秋田県男鹿半島沖、痩せた個体が多い場所の赤テリ(ウスメバル)を刺身、焼霜造り、煮つけ、バター焼きにしてみた。3尾いて一番左右幅のあるものの刺身は、非常においしかった。ウスメバルは漁期ははっきりしているが、卵胎生の魚の特徴として旬がわかりにくい。今回、この個体だけ身に張りがあり、刺身に引くと味と甘味があった。舌の上で味のだれがない。このおいしさは予想外。 コノシロは北海道南部から九州までの汽水域や内湾に生息している。内湾にたまった泥を飲み込み、中にいる珪藻や甲殻類などを食べている。「子代」という漢字を当てることがある。下野に住んでいた娘と有間皇子(ありまのみこ。孝徳天皇の悲劇の皇子。640年-658年)が登場するわざとらしい話があるなど、話題豊富な魚である。大都市圏のある内湾域に多い魚なので知名度は高い。古くからの共通固有名詞があるので、なんらかの形で古代に流通していたはずである。この魚の問題点は食べる地域が狭すぎるということだ。関東では全長20cmくらいまではすし種に使うが、それ以上になると流通量がぐっと減り、最底辺の価格帯になる。当然、産地で水揚げされても廃棄(フィッシュミール)などになることが多い。■写真は全長25cm以上の「このしろサイズ」のコノシロ。
コノシロは北海道南部から九州までの汽水域や内湾に生息している。内湾にたまった泥を飲み込み、中にいる珪藻や甲殻類などを食べている。「子代」という漢字を当てることがある。下野に住んでいた娘と有間皇子(ありまのみこ。孝徳天皇の悲劇の皇子。640年-658年)が登場するわざとらしい話があるなど、話題豊富な魚である。大都市圏のある内湾域に多い魚なので知名度は高い。古くからの共通固有名詞があるので、なんらかの形で古代に流通していたはずである。この魚の問題点は食べる地域が狭すぎるということだ。関東では全長20cmくらいまではすし種に使うが、それ以上になると流通量がぐっと減り、最底辺の価格帯になる。当然、産地で水揚げされても廃棄(フィッシュミール)などになることが多い。■写真は全長25cm以上の「このしろサイズ」のコノシロ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に福島県浪江町請戸から「ふっこ」が来ていた。いわき市の『海宝水産』からで、体高があり、背が左右に膨らんでいる。触らなくても上物だ、と思えたので、いきなり確保する。体長34cm・0.6㎏なのでスズキとしては小振りである。帰宅後、下ろしながら浮き浮きしているボクがいる。「野バラ咲いてる♪」を唄っているボクがいる。下ろすのが楽しい。活け締めしたばかりのような身色だし、味見すると心地よい食感だし、とりあえず、昼ご飯のおかずにして楽しむ。うま味豊か、小振りなのに、脂の乗りがほどよい。醤油なしで食べても、おいしいのにびっくり。おいしい刺身はご飯がいい。酒の味が邪魔ですらある。それにしても20年以上前の請戸のことが思い出される。福島の水産は新しい時代を迎えているのかも。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に福島県浪江町請戸から「ふっこ」が来ていた。いわき市の『海宝水産』からで、体高があり、背が左右に膨らんでいる。触らなくても上物だ、と思えたので、いきなり確保する。体長34cm・0.6㎏なのでスズキとしては小振りである。帰宅後、下ろしながら浮き浮きしているボクがいる。「野バラ咲いてる♪」を唄っているボクがいる。下ろすのが楽しい。活け締めしたばかりのような身色だし、味見すると心地よい食感だし、とりあえず、昼ご飯のおかずにして楽しむ。うま味豊か、小振りなのに、脂の乗りがほどよい。醤油なしで食べても、おいしいのにびっくり。おいしい刺身はご飯がいい。酒の味が邪魔ですらある。それにしても20年以上前の請戸のことが思い出される。福島の水産は新しい時代を迎えているのかも。 都心に出たり、テレビ電話(なんていうんだろう?)とか、あまりに生活が苦しいので、なんでもかんでも引き受けている。たまには本音を言わせてもらうと、水産生物と人との関わりを調べるのってとっても大変なのだ。自己否定の繰り返しなので、精神的にも辛いし、めまいの症状が出てしまう。さて、メバルは2008年まで1種とされていて、それが3種に分かれる。それ以前に撮影したネガもポジもデジタル画像も3種に分けていないわけで無意味なものとなる。比較的無意味ではない画像を整理していたら、ここ1週間でたぶん5時間くらい時間を消費している。ボクは、日々大量の水産生物を撮影して料理しているし、テレビ電話とか、いろんな仕事上の相談とかがあるので、このメバル3種に費やした5時間だってバカにならない。ただ3種に分けた魚類学者は何年もかけて、遺伝子まで調べているわけで、その研究に費やした時間は信じられないくらい膨大だろう。3種に分けるということは19世紀、キュビエの時代にまで遡る必要があるのだ。例えばタイプがフランスにあるとしたら、とか考えると息苦しくなる。その話をテレビ電話で Dに話したら、「(2008年なのに)昔にもさかなクンがいたんですね」と言われてびっくりした。さかなクンには会ったことがないので実力はわからない。でもテレビを見ないボクにとっては、著書がない。論文もない可能性が高いし、あっても第一著者論文はないんじゃないかな。動物学はある意味論文が総てなので、ボクにとってさかなクンは無でしかない。それをこのメバル3種に分けたある意味、偉大な魚類学者たちになぞるのはあまりにもハレンチじゃないかな?思わず、Dにバカと言ったことは後悔しているが、本音だぞ、と言いたい。念のために、過去に、さかなクンの番組のホンカキに対して不愉快だなと思ったことはあるが、本人に対しては白紙である。会ってみないとわからないけど、さかなクンというのは魚類学者ではないと思っている。
都心に出たり、テレビ電話(なんていうんだろう?)とか、あまりに生活が苦しいので、なんでもかんでも引き受けている。たまには本音を言わせてもらうと、水産生物と人との関わりを調べるのってとっても大変なのだ。自己否定の繰り返しなので、精神的にも辛いし、めまいの症状が出てしまう。さて、メバルは2008年まで1種とされていて、それが3種に分かれる。それ以前に撮影したネガもポジもデジタル画像も3種に分けていないわけで無意味なものとなる。比較的無意味ではない画像を整理していたら、ここ1週間でたぶん5時間くらい時間を消費している。ボクは、日々大量の水産生物を撮影して料理しているし、テレビ電話とか、いろんな仕事上の相談とかがあるので、このメバル3種に費やした5時間だってバカにならない。ただ3種に分けた魚類学者は何年もかけて、遺伝子まで調べているわけで、その研究に費やした時間は信じられないくらい膨大だろう。3種に分けるということは19世紀、キュビエの時代にまで遡る必要があるのだ。例えばタイプがフランスにあるとしたら、とか考えると息苦しくなる。その話をテレビ電話で Dに話したら、「(2008年なのに)昔にもさかなクンがいたんですね」と言われてびっくりした。さかなクンには会ったことがないので実力はわからない。でもテレビを見ないボクにとっては、著書がない。論文もない可能性が高いし、あっても第一著者論文はないんじゃないかな。動物学はある意味論文が総てなので、ボクにとってさかなクンは無でしかない。それをこのメバル3種に分けたある意味、偉大な魚類学者たちになぞるのはあまりにもハレンチじゃないかな?思わず、Dにバカと言ったことは後悔しているが、本音だぞ、と言いたい。念のために、過去に、さかなクンの番組のホンカキに対して不愉快だなと思ったことはあるが、本人に対しては白紙である。会ってみないとわからないけど、さかなクンというのは魚類学者ではないと思っている。 近所のスーパーの魚売り場は定期的に見て回っている。ボクは水産生物の一般性を調べているので、これをやらないわけにはいかない。今や水産物の「一般を感じられるもの」はスーパーにしかない。売り場で唄を唄っている人がいた。「マグロはマグロ〜♪」もちろん聞き耳を立てているので聞けたというくらいの小声で。ふたりの会話はあっちのマグロはこっちの半分の大きさでほぼ1000円、こっちは半額で大きさは2倍、「同じマグロなら、これでいいわ」ということらしい。ボクのお目当てもビンナガで、国内で豊漁と聞いたから来た。残念ながら宮城県産も和歌山県産もなかった。3軒のスーパーをまわり、2軒にビンナガがあった。こちらのスーパーの産地はバヌアツで、もう一軒は太平洋産だった。せっかく鼻歌を盗み聞きしたので一冊買った。なにしろあっちの本マグロ解凍の2分の1の値段は大きい。ビンナガマグロは脂こそのっていないものの、酸味がほどよく、味がある。ボクはマグロなどなんでもいい派かも知れない。
近所のスーパーの魚売り場は定期的に見て回っている。ボクは水産生物の一般性を調べているので、これをやらないわけにはいかない。今や水産物の「一般を感じられるもの」はスーパーにしかない。売り場で唄を唄っている人がいた。「マグロはマグロ〜♪」もちろん聞き耳を立てているので聞けたというくらいの小声で。ふたりの会話はあっちのマグロはこっちの半分の大きさでほぼ1000円、こっちは半額で大きさは2倍、「同じマグロなら、これでいいわ」ということらしい。ボクのお目当てもビンナガで、国内で豊漁と聞いたから来た。残念ながら宮城県産も和歌山県産もなかった。3軒のスーパーをまわり、2軒にビンナガがあった。こちらのスーパーの産地はバヌアツで、もう一軒は太平洋産だった。せっかく鼻歌を盗み聞きしたので一冊買った。なにしろあっちの本マグロ解凍の2分の1の値段は大きい。ビンナガマグロは脂こそのっていないものの、酸味がほどよく、味がある。ボクはマグロなどなんでもいい派かも知れない。 近藤亮さん(第八松宝丸 秋田県男鹿市)に秋田県男鹿半島沖の魚を送っていただいた。中にムツが混ざっていた。これが我がサイト、最北のムツである。圧倒的に伊豆諸島以南の太平洋側に多く、日本海のものは少ないので非常に貴重である。近藤さんには感謝しかない。さて、今回の体長25cm・重さ299gの個体は、相模湾では深場に落ちていく途中のサイズである。近藤さんが釣り上げた水深も120mなので、だいたい相模湾と同じではないかと思っている。さて、男鹿沖のムツであるが、脂が乗っている。この点でも相模湾のものと変わらない。水洗いして三枚に下ろすと、包丁が微かに重い。頭に近い方は皮を引き刺身にする。ムツの脂は非常に上質でさらさらしており、下に接触するととろっと甘く感じる。身は柔らかく舌にねっとりしている。一昨年の兵庫県香住産同様、非常にいい。上物といっていいだろう。
近藤亮さん(第八松宝丸 秋田県男鹿市)に秋田県男鹿半島沖の魚を送っていただいた。中にムツが混ざっていた。これが我がサイト、最北のムツである。圧倒的に伊豆諸島以南の太平洋側に多く、日本海のものは少ないので非常に貴重である。近藤さんには感謝しかない。さて、今回の体長25cm・重さ299gの個体は、相模湾では深場に落ちていく途中のサイズである。近藤さんが釣り上げた水深も120mなので、だいたい相模湾と同じではないかと思っている。さて、男鹿沖のムツであるが、脂が乗っている。この点でも相模湾のものと変わらない。水洗いして三枚に下ろすと、包丁が微かに重い。頭に近い方は皮を引き刺身にする。ムツの脂は非常に上質でさらさらしており、下に接触するととろっと甘く感じる。身は柔らかく舌にねっとりしている。一昨年の兵庫県香住産同様、非常にいい。上物といっていいだろう。 このところバライカ(スルメイカの若い個体)ばっかり買っている。魚がないからで、市場でも買い、東京都杉並区下高井戸、いつもの肉屋そばの魚屋でも念のためにバライカを買った。小さなスルメイカほど重宝するものはない。それなりに、たまった冷凍げそを解凍し、布巾に包んですりこぎでしばく、たたく、しばく、そして細かく切る。郷土料理のために買った水耕栽培の三つ葉を適当に刻む。ボウルにバライカのばらばらと、刻んだ三つ葉を合わせて小麦粉をまぶす。徳島県美馬郡つるぎ町、杉本手延製麺の半田素麺は、だいたい4分から5分で茹で上がる。ゆでている間にバライカ・三つ葉のボウルに衣を投入してしゃもじですくっては揚げる。思い切って強めに揚げてかりっとさせる。素麺が茹で上がったら冷水に取り、水を何度か取り替え、少し揉み洗いして、水切りをする。つゆは長崎県平戸市の「あご煮干し」でとっただしに、塩・みりん・薄口醤油だ。
このところバライカ(スルメイカの若い個体)ばっかり買っている。魚がないからで、市場でも買い、東京都杉並区下高井戸、いつもの肉屋そばの魚屋でも念のためにバライカを買った。小さなスルメイカほど重宝するものはない。それなりに、たまった冷凍げそを解凍し、布巾に包んですりこぎでしばく、たたく、しばく、そして細かく切る。郷土料理のために買った水耕栽培の三つ葉を適当に刻む。ボウルにバライカのばらばらと、刻んだ三つ葉を合わせて小麦粉をまぶす。徳島県美馬郡つるぎ町、杉本手延製麺の半田素麺は、だいたい4分から5分で茹で上がる。ゆでている間にバライカ・三つ葉のボウルに衣を投入してしゃもじですくっては揚げる。思い切って強めに揚げてかりっとさせる。素麺が茹で上がったら冷水に取り、水を何度か取り替え、少し揉み洗いして、水切りをする。つゆは長崎県平戸市の「あご煮干し」でとっただしに、塩・みりん・薄口醤油だ。 日本列島のエイの食文化には北のガンギエイ科の「かすべ」と、南のアカエイ科がある。今回はアカエイの話である。アカエイは北海道、本州、四国、九州の内湾や川の河口域などの浅場に生息している。夏、干潟や漁港などで観察していると簡単に見つけることのできる、ありふれた魚だ。非常に原始的な軟骨魚類の仲間で、体に硬い骨はなく、全体に柔らかい。体は上下に平たく円盤形で細長い尾を持ち、尾の中ほどに太くてざらざらした棒状の毒を持つ棘がある。ちなみにアカエイはとても大人しい魚であり、攻撃してくるようなことはない。また誤って刺された経験のある漁師さんに聞いた限りでは、非常に痛かったが、数日で痛みは引いたらしい。棘を踏んでしまったときなどは確かに危険であるが猛毒で人を死に至らしめる、というのは極端な例である。市場に出回るものは棘のある尾を切り落としているので安全である。目は背中についていているが一見、目のように見えるのは噴水口で目は近くにあるが目立たない。鰓と口は体の下に開いている。1980年代に築地(東京都東京中央市場。現豊洲市場)に行き始めたとき、箱単位で売る仲卸に高く積まれていたのを見ている。場内でアカエイをぶつ切りにしている光景を見て、メモをとっていたら、「買わねーのか?」と言われたので、買っている。それ以前、江戸川区小岩の食堂で煮つけを食べているし、魚屋やスーパーで切り身が普通に売られていた。東京都内では「えいの煮つけ」は至って普通の食べ物だったのである。東京では食堂など庶民的な店だけではなく、料亭などでも使うもので、夏の魚として欠かすことの出来ない魚であったという。江戸時代には適当に切って行商していたようで、これを「赤えいのたちうり(断ち売り)」といった。どんな切り身だったはわからないが、裏長屋での売り買いの情景が浮かんでくるようだ。夏でも体に保持する尿酸のために腐敗しにくいために、江戸の町だけではなく、山間部にとっても貴重なたんぱく源であったはずだ。明らかに高度成長期には「アカエイの煮つけ」は「カレイの煮つけ」と同じように日常的な魚だった。一般に馴染みのない魚となったのは2000年前後くらいからではないか、と思う。アカエイの未利用魚化を食文化衰退型としてもいいだろう。関東のスーパーなどではほとんど並ばなくなっている。比較的見る機会が多い地域と少ない地域が斑模様となっているが、全体の消費量は急激に減っている。アカエイを食べる食文化が消費地から消え、いつの間にか普通の食用魚ではなくなりつつあるのだ。この食文化衰退の原因をアカエイが不気味だからだという人がいる。そう行ったリアクションをするタレントなども見かけるが、牛や豚と比べてもそれほど不気味だとは思えない。昔はアカエイ専門の空バリ漁が国内各地で行われていた。それほど需要が高かったのだと思われる。今では底曳き網や刺し網、定置網などで混獲されているだけだ。それでも漁獲量は決して少なくない。漁港などで見ている限り、その多くが廃棄されている。
日本列島のエイの食文化には北のガンギエイ科の「かすべ」と、南のアカエイ科がある。今回はアカエイの話である。アカエイは北海道、本州、四国、九州の内湾や川の河口域などの浅場に生息している。夏、干潟や漁港などで観察していると簡単に見つけることのできる、ありふれた魚だ。非常に原始的な軟骨魚類の仲間で、体に硬い骨はなく、全体に柔らかい。体は上下に平たく円盤形で細長い尾を持ち、尾の中ほどに太くてざらざらした棒状の毒を持つ棘がある。ちなみにアカエイはとても大人しい魚であり、攻撃してくるようなことはない。また誤って刺された経験のある漁師さんに聞いた限りでは、非常に痛かったが、数日で痛みは引いたらしい。棘を踏んでしまったときなどは確かに危険であるが猛毒で人を死に至らしめる、というのは極端な例である。市場に出回るものは棘のある尾を切り落としているので安全である。目は背中についていているが一見、目のように見えるのは噴水口で目は近くにあるが目立たない。鰓と口は体の下に開いている。1980年代に築地(東京都東京中央市場。現豊洲市場)に行き始めたとき、箱単位で売る仲卸に高く積まれていたのを見ている。場内でアカエイをぶつ切りにしている光景を見て、メモをとっていたら、「買わねーのか?」と言われたので、買っている。それ以前、江戸川区小岩の食堂で煮つけを食べているし、魚屋やスーパーで切り身が普通に売られていた。東京都内では「えいの煮つけ」は至って普通の食べ物だったのである。東京では食堂など庶民的な店だけではなく、料亭などでも使うもので、夏の魚として欠かすことの出来ない魚であったという。江戸時代には適当に切って行商していたようで、これを「赤えいのたちうり(断ち売り)」といった。どんな切り身だったはわからないが、裏長屋での売り買いの情景が浮かんでくるようだ。夏でも体に保持する尿酸のために腐敗しにくいために、江戸の町だけではなく、山間部にとっても貴重なたんぱく源であったはずだ。明らかに高度成長期には「アカエイの煮つけ」は「カレイの煮つけ」と同じように日常的な魚だった。一般に馴染みのない魚となったのは2000年前後くらいからではないか、と思う。アカエイの未利用魚化を食文化衰退型としてもいいだろう。関東のスーパーなどではほとんど並ばなくなっている。比較的見る機会が多い地域と少ない地域が斑模様となっているが、全体の消費量は急激に減っている。アカエイを食べる食文化が消費地から消え、いつの間にか普通の食用魚ではなくなりつつあるのだ。この食文化衰退の原因をアカエイが不気味だからだという人がいる。そう行ったリアクションをするタレントなども見かけるが、牛や豚と比べてもそれほど不気味だとは思えない。昔はアカエイ専門の空バリ漁が国内各地で行われていた。それほど需要が高かったのだと思われる。今では底曳き網や刺し網、定置網などで混獲されているだけだ。それでも漁獲量は決して少なくない。漁港などで見ている限り、その多くが廃棄されている。 三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。
三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。 甲殻類などアレルギーを持つ人がいるので、どうしようもないことだけど、最近の「ちりめん」、「しらす干し」は混じりけなしでつまらない。ボクはアレルギーがまったくないので、地方に行き昔のような混ざり物の多いものを見つけると、思わず手が出てしまう。小型のフグが入っているとうれしかった。ところが最近では小フグ混じりで大騒ぎになる。MU値(マウスユニット)0だと思うのに回収したり、ニュースになるのは、保健所が暇だからだろう。幼児でもフグは認識できるのだから、どければいいと思うし、ボクなど子供の頃には探して口に入れていた、それなのに今でも死んでいない。食べ物を大切にする心がないのだろう。甲殻類の幼生類に、同じく甲殻類等脚目のヘラムシ、エソ類・タチウオやホウボウの稚魚、レプトケファルス(ウナギやアナゴなどカライワシ下区の稚魚)、イカタコの小さいのなどなど、子供の頃は夢中になって皿の上に並べて遊んだものである。浜松市雄踏にあった直売所、『よらっせYUTO』で買った「しらすぼし」は少しだけ混ざりものがあった。忙しいときなので同定はしなかったものの、ほぼイカだった。ツツイカ類(スルメイカやケンサキイカ、アオリイカ)ではなく、コウイカ類(コウイカやカミナリイカ)の子じゃないかと考えた。よく見ると、十脚目クルマエビ科らしきもののゾエアのようなものもある。直売所では、地元舞阪産か静岡県御前崎産ではないかという。干し加減が強くて、非常にうまかった。
甲殻類などアレルギーを持つ人がいるので、どうしようもないことだけど、最近の「ちりめん」、「しらす干し」は混じりけなしでつまらない。ボクはアレルギーがまったくないので、地方に行き昔のような混ざり物の多いものを見つけると、思わず手が出てしまう。小型のフグが入っているとうれしかった。ところが最近では小フグ混じりで大騒ぎになる。MU値(マウスユニット)0だと思うのに回収したり、ニュースになるのは、保健所が暇だからだろう。幼児でもフグは認識できるのだから、どければいいと思うし、ボクなど子供の頃には探して口に入れていた、それなのに今でも死んでいない。食べ物を大切にする心がないのだろう。甲殻類の幼生類に、同じく甲殻類等脚目のヘラムシ、エソ類・タチウオやホウボウの稚魚、レプトケファルス(ウナギやアナゴなどカライワシ下区の稚魚)、イカタコの小さいのなどなど、子供の頃は夢中になって皿の上に並べて遊んだものである。浜松市雄踏にあった直売所、『よらっせYUTO』で買った「しらすぼし」は少しだけ混ざりものがあった。忙しいときなので同定はしなかったものの、ほぼイカだった。ツツイカ類(スルメイカやケンサキイカ、アオリイカ)ではなく、コウイカ類(コウイカやカミナリイカ)の子じゃないかと考えた。よく見ると、十脚目クルマエビ科らしきもののゾエアのようなものもある。直売所では、地元舞阪産か静岡県御前崎産ではないかという。干し加減が強くて、非常にうまかった。 オニカジカは体長30cm前後になる。北にいる魚で日本海や東北太平洋側以北に生息しているが、取り分け北海道に多い。本種の問題点はその姿形である。非常に棘が長く強く、漁のときに非常にやっかいなのである。漁師にもっとも嫌われている魚でもある。いきなり横道にそれるが、国内では、西日本においては、そんなに問題のない魚なのに、未利用魚だとしてあれこれ騒いだりする。逆に北海道に深刻な未利用魚が多々あるのにあまり騒がない。これがお国柄なのか? というと違うのではないかと考えている。北海道は大量にとれる魚が何種類もいて、漁業的にも安定していた地域だったので、細かいことまで気が回らなかっただけだ。サケ、スケトウダラ、カレイ類、今では少なくなったとはいえニシンなど、数え切れないくらい多獲性魚類やそれに準じる魚が存在する。その多獲性魚類のために見逃されてきた深刻な未利用魚、問題のある魚は少なくない。実際、国内的にみても、北海道は未利用魚銀座そのものなのだ。
オニカジカは体長30cm前後になる。北にいる魚で日本海や東北太平洋側以北に生息しているが、取り分け北海道に多い。本種の問題点はその姿形である。非常に棘が長く強く、漁のときに非常にやっかいなのである。漁師にもっとも嫌われている魚でもある。いきなり横道にそれるが、国内では、西日本においては、そんなに問題のない魚なのに、未利用魚だとしてあれこれ騒いだりする。逆に北海道に深刻な未利用魚が多々あるのにあまり騒がない。これがお国柄なのか? というと違うのではないかと考えている。北海道は大量にとれる魚が何種類もいて、漁業的にも安定していた地域だったので、細かいことまで気が回らなかっただけだ。サケ、スケトウダラ、カレイ類、今では少なくなったとはいえニシンなど、数え切れないくらい多獲性魚類やそれに準じる魚が存在する。その多獲性魚類のために見逃されてきた深刻な未利用魚、問題のある魚は少なくない。実際、国内的にみても、北海道は未利用魚銀座そのものなのだ。 ボクの故郷、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)は県内、吉野川真ん中あたりで、都会に出るというと徳島市だった。香川県に出ることはほとんどなく、意外に遠い場所だった気がする。「香川」というと記憶が曖昧だけど丸亀(?)であって、家族がウチワを仕入れに行くとき何度かついて行った。ウチワの注文をして、名を入れる、とかいろんなことをやっている間、まだ子供のボクは、瓦煎餅とかまんじゅうでお茶を飲むのが楽しみだった。ウチワ屋のお茶は苦いけど軽くて口の中がすっきりした。これが、碁石茶だった気がする。碁石茶は高知県大豊町などで作っている国内では珍しい発酵茶で、高知県ではなく香川県海辺や離島で飲まれていた。海水浴で何度か行った、香川県海岸寺の海の家で飲んでいたお茶も同じ味だった気がする。ちなみに父は職人だったので、他にも何軒か回った。そのときのお茶は我が家と同じ緑茶で、ボクにはジュースが出た。ジュースとお茶をかわりばんこに飲むの見た、得意先のオバサンに笑われたりした。曖昧模糊で、はっきりしないけど、「めも」なのでお許しを。塩飽諸島など離島、漁師さんが飲むものという話があるが、このような家内工業の場や海の家などでも飲んでいたのだと思う。ちなみに碁石茶らしきものを意識したのは、サンテレビ(?)の伊丹十三の番組でだと記憶する。四国の山間部を歩くという番組だった。新聞のテレビ欄まで見て、合わせて帰宅していたくらい面白い番組だった。もしも録画が残っているなら、もう一度見てみたい。
ボクの故郷、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)は県内、吉野川真ん中あたりで、都会に出るというと徳島市だった。香川県に出ることはほとんどなく、意外に遠い場所だった気がする。「香川」というと記憶が曖昧だけど丸亀(?)であって、家族がウチワを仕入れに行くとき何度かついて行った。ウチワの注文をして、名を入れる、とかいろんなことをやっている間、まだ子供のボクは、瓦煎餅とかまんじゅうでお茶を飲むのが楽しみだった。ウチワ屋のお茶は苦いけど軽くて口の中がすっきりした。これが、碁石茶だった気がする。碁石茶は高知県大豊町などで作っている国内では珍しい発酵茶で、高知県ではなく香川県海辺や離島で飲まれていた。海水浴で何度か行った、香川県海岸寺の海の家で飲んでいたお茶も同じ味だった気がする。ちなみに父は職人だったので、他にも何軒か回った。そのときのお茶は我が家と同じ緑茶で、ボクにはジュースが出た。ジュースとお茶をかわりばんこに飲むの見た、得意先のオバサンに笑われたりした。曖昧模糊で、はっきりしないけど、「めも」なのでお許しを。塩飽諸島など離島、漁師さんが飲むものという話があるが、このような家内工業の場や海の家などでも飲んでいたのだと思う。ちなみに碁石茶らしきものを意識したのは、サンテレビ(?)の伊丹十三の番組でだと記憶する。四国の山間部を歩くという番組だった。新聞のテレビ欄まで見て、合わせて帰宅していたくらい面白い番組だった。もしも録画が残っているなら、もう一度見てみたい。 八王子総合卸売センター、八百角でナスを買って帰ってきたら、近所に住む名前さえ知らない、立ち話だけする家族がいて、「田舎のものですがもらってくれませんか?」と手渡されたのがナスだ。百日咳(合っているかな)の子供に、子供の本をあげたお返しなのかもしれない。買ったばかりなので、と断るのも剣呑なのでいただいたら、レジ袋にぱんぱんに詰め込まれている。以後、ナス尽くし、だ。このところ連日入荷しているバライカ(スルメイカの若い個体)と一緒に、お昼ご飯にみそ炒めかな? と思ったが、みそ汁の具がこれまたナスだったので、単純に炒めて醤油味でジュって感じの「イカナス炒め」を作った。バライカは冷凍保存を保存袋のまま流水で解凍する。適当に切る。調味料は鷹の爪3分の1本だけ。ただただ多めの油でナスとバライカを炒めて、生醤油で味付けしただけ。あまりの暑さに、真面目に料理など作っていられっかい、てなもんで出来上がりに白ごまを振る。鷹の爪ちょぼっとなのにピリっと来るのは、辛いのがダメにボクがなったから。ぴりっとするのが、唯一の味の変化で、酒もみりんもなしの醤油オンリーの炒め物がそれなりにおいしい。見た目こそ悪いもののナスがやけにうまい。チンしたご飯にも合う。夏は、絶対にマジで料理しない、いつもより二倍手抜きする、が今のボクの、信条だ。
八王子総合卸売センター、八百角でナスを買って帰ってきたら、近所に住む名前さえ知らない、立ち話だけする家族がいて、「田舎のものですがもらってくれませんか?」と手渡されたのがナスだ。百日咳(合っているかな)の子供に、子供の本をあげたお返しなのかもしれない。買ったばかりなので、と断るのも剣呑なのでいただいたら、レジ袋にぱんぱんに詰め込まれている。以後、ナス尽くし、だ。このところ連日入荷しているバライカ(スルメイカの若い個体)と一緒に、お昼ご飯にみそ炒めかな? と思ったが、みそ汁の具がこれまたナスだったので、単純に炒めて醤油味でジュって感じの「イカナス炒め」を作った。バライカは冷凍保存を保存袋のまま流水で解凍する。適当に切る。調味料は鷹の爪3分の1本だけ。ただただ多めの油でナスとバライカを炒めて、生醤油で味付けしただけ。あまりの暑さに、真面目に料理など作っていられっかい、てなもんで出来上がりに白ごまを振る。鷹の爪ちょぼっとなのにピリっと来るのは、辛いのがダメにボクがなったから。ぴりっとするのが、唯一の味の変化で、酒もみりんもなしの醤油オンリーの炒め物がそれなりにおいしい。見た目こそ悪いもののナスがやけにうまい。チンしたご飯にも合う。夏は、絶対にマジで料理しない、いつもより二倍手抜きする、が今のボクの、信条だ。 我が徳島県ではアイゴの胃と腸管をその形から「ぜんまい」という。昔は好んで食べる人がいた。実際に食べてみると非常にうまいが、かなり臭い。このうまいと、臭いのせめぎ合いが、いいのだそうだ。今でも少ないながら、「最近のばり(アイゴ)」は臭味が弱いのでおいしくない、という漁師さんすらいる。「ぜんまい」は強いうま味の塊のようなもので、その上、あの臭味が好きだったら、それはそれはこれ以上ない御馳走だろう。さて、念のために静岡県湖西市鷲津漁港で手に入れた小振りの「しゃくしゃ(アイゴ)」の「ぜんまい」を煮つけにしてみた。若い個体なので「ぜんまい」も当然小さい、にもかかわらず、非常に強いうま味があり、思わず「お、お、お」っとのけぞるほどうまい。しかも臭味が少ない。それほど臭味に強くないボクにとっても珠玉の味である。もちろん臭味はないにこしたことはないが、活け締めにした若い個体の「ぜんまい」がこんなにおいしいとは思わなかった。鷲津漁協の方で少し活かして、体の中にあるエサを吐き出させてから刺身で食べると言った方がいた。ひょっとすると活け越し(数日活かしておく)すると、小型の身だけではなく、「ぜんまい」の臭味も消えるのではないか? 次回の浜名湖が楽しみだ。
我が徳島県ではアイゴの胃と腸管をその形から「ぜんまい」という。昔は好んで食べる人がいた。実際に食べてみると非常にうまいが、かなり臭い。このうまいと、臭いのせめぎ合いが、いいのだそうだ。今でも少ないながら、「最近のばり(アイゴ)」は臭味が弱いのでおいしくない、という漁師さんすらいる。「ぜんまい」は強いうま味の塊のようなもので、その上、あの臭味が好きだったら、それはそれはこれ以上ない御馳走だろう。さて、念のために静岡県湖西市鷲津漁港で手に入れた小振りの「しゃくしゃ(アイゴ)」の「ぜんまい」を煮つけにしてみた。若い個体なので「ぜんまい」も当然小さい、にもかかわらず、非常に強いうま味があり、思わず「お、お、お」っとのけぞるほどうまい。しかも臭味が少ない。それほど臭味に強くないボクにとっても珠玉の味である。もちろん臭味はないにこしたことはないが、活け締めにした若い個体の「ぜんまい」がこんなにおいしいとは思わなかった。鷲津漁協の方で少し活かして、体の中にあるエサを吐き出させてから刺身で食べると言った方がいた。ひょっとすると活け越し(数日活かしておく)すると、小型の身だけではなく、「ぜんまい」の臭味も消えるのではないか? 次回の浜名湖が楽しみだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州でウメイロをたっぷり釣り上げて来た。銭州の本命はシマアジのようだが、ボクなどシマアジは脇役、ウメイロが主役だ、と勝手に思っている。昔は腐っても鯛(マダイ)などと言われたものだが、今やマダイは時季と産地と扱い次第で値が違っている。高級魚といえるのはごくわずかだ。対するにウメイロはいつでも、どこでとれても高い。昔は関東の高級魚だったが、今や全国区になりつつある。ボクがウメイロを手に入れたいと思うときは、間違いなくうまいものを食べたいときで、ウメイロの刺身は2人前だろうが、3人前だろうが一気に喉を通り過ぎてしまう。当たるとわかって引くクジのようなものだ。時季なのもあるが脂がのって口溶け感があるし、この脂が甘い。強いうま味が感じられるのも、後味がいいだけに不思議である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州でウメイロをたっぷり釣り上げて来た。銭州の本命はシマアジのようだが、ボクなどシマアジは脇役、ウメイロが主役だ、と勝手に思っている。昔は腐っても鯛(マダイ)などと言われたものだが、今やマダイは時季と産地と扱い次第で値が違っている。高級魚といえるのはごくわずかだ。対するにウメイロはいつでも、どこでとれても高い。昔は関東の高級魚だったが、今や全国区になりつつある。ボクがウメイロを手に入れたいと思うときは、間違いなくうまいものを食べたいときで、ウメイロの刺身は2人前だろうが、3人前だろうが一気に喉を通り過ぎてしまう。当たるとわかって引くクジのようなものだ。時季なのもあるが脂がのって口溶け感があるし、この脂が甘い。強いうま味が感じられるのも、後味がいいだけに不思議である。 ボクの故郷、貞光町(現徳島県美馬郡つるぎ町貞光)には、お好み焼き屋がいっぱいあった。小さな時、近所の『吉田屋』の、タイル張りのどっしりした台の鉄板で食べていたのは、卵なし、小麦粉を溶いて、キャベツと天かすが入っただけのもので、ソースは甘い徳島特有(イチミツボシ加賀屋のものだったかも)のものだ。少年サンデーをとってもらっていたので、他の漫画のあるお好み焼き屋に行くことが多かった。「墓場の鬼太郎」を読むためにときどき寄っていた店で、裏のアンニャが食べさせてくれたのが牛肉入り(?)の焼きうどんだ。ボクはこのとき、小学校高学年になるまで、店で焼きうどんを食べたことがなかったと思う。中学・高校と、よく焼きうどんを食べた。焼きそばよりも焼きうどん好きだった。「イカ入り」よりも「肉入り(牛肉)」が多かった。数年前、市場人集まったの無駄話中に、前後は思い出せないが、すし職人のたかさんに「焼きうどんは醤油だろう」なんて言われた、相模原の居酒屋のオヤジに「だし醤油な」とも。マグロ屋までもが「醤油味が普通だな」なんて宣う。焼きうどんにソース(お好み焼きソースもしくはトンカツソース)というのはボクだけだった。まったく関係のない話だけど、ボクにとっての焼きうどんは牛肉とキャベツだったが、大人になるとイカ(スルメイカもしくはイカを下ろしたときの鰭やげそ)ばかりになった。ちなみに大人になると外でお好み焼きを食べなくなった。そしてこのところ、バライカ(小型のスルメイカで、並べないで流通するのでバラのイカ)ばかりで焼きうどんを作っている。徳島の甘いソースがないので、生醤油だけの味付けだ。本当は、スルメイカは大型の方が焼きうどんには向いているが、バライカもうまいじゃないかと、独りごちている。たなみに写真は一人前の蒸しうどんだけど、最近では半分でよくなった。なぜか? まんじゅう、食いすぎだから、だ。
ボクの故郷、貞光町(現徳島県美馬郡つるぎ町貞光)には、お好み焼き屋がいっぱいあった。小さな時、近所の『吉田屋』の、タイル張りのどっしりした台の鉄板で食べていたのは、卵なし、小麦粉を溶いて、キャベツと天かすが入っただけのもので、ソースは甘い徳島特有(イチミツボシ加賀屋のものだったかも)のものだ。少年サンデーをとってもらっていたので、他の漫画のあるお好み焼き屋に行くことが多かった。「墓場の鬼太郎」を読むためにときどき寄っていた店で、裏のアンニャが食べさせてくれたのが牛肉入り(?)の焼きうどんだ。ボクはこのとき、小学校高学年になるまで、店で焼きうどんを食べたことがなかったと思う。中学・高校と、よく焼きうどんを食べた。焼きそばよりも焼きうどん好きだった。「イカ入り」よりも「肉入り(牛肉)」が多かった。数年前、市場人集まったの無駄話中に、前後は思い出せないが、すし職人のたかさんに「焼きうどんは醤油だろう」なんて言われた、相模原の居酒屋のオヤジに「だし醤油な」とも。マグロ屋までもが「醤油味が普通だな」なんて宣う。焼きうどんにソース(お好み焼きソースもしくはトンカツソース)というのはボクだけだった。まったく関係のない話だけど、ボクにとっての焼きうどんは牛肉とキャベツだったが、大人になるとイカ(スルメイカもしくはイカを下ろしたときの鰭やげそ)ばかりになった。ちなみに大人になると外でお好み焼きを食べなくなった。そしてこのところ、バライカ(小型のスルメイカで、並べないで流通するのでバラのイカ)ばかりで焼きうどんを作っている。徳島の甘いソースがないので、生醤油だけの味付けだ。本当は、スルメイカは大型の方が焼きうどんには向いているが、バライカもうまいじゃないかと、独りごちている。たなみに写真は一人前の蒸しうどんだけど、最近では半分でよくなった。なぜか? まんじゅう、食いすぎだから、だ。 八王子総合卸売センター、福泉に、東京都神津島からクサカリツボダイが来ていた、総て体長30cm以上で鮮度もいい。「つぼだい」として有名で、干ものの魚と思われているが、希に鮮魚でも流通する。鮮魚はめったに手に入らないのが難点であるが、安くておいしい魚である。久しぶりなので、刺身にしてみた。神津島産は過去にない鮮度で、しかも皮を引くと身が真っ白である。身質は深海魚特有の脂があるなどキチジ(きんき)、オオサガ(荒神目抜け)とそっくり。脂が薄くて弱い筋繊維の中にコロイド状になってたまっているようだ。刺身は食感こそ上等とは言えないが、味は他に類をみないおいしさである。スーパーなどでもお馴染みの魚であるが、干もの・塩蔵品だけじゃない、鮮魚のよさも知って頂きたい。
八王子総合卸売センター、福泉に、東京都神津島からクサカリツボダイが来ていた、総て体長30cm以上で鮮度もいい。「つぼだい」として有名で、干ものの魚と思われているが、希に鮮魚でも流通する。鮮魚はめったに手に入らないのが難点であるが、安くておいしい魚である。久しぶりなので、刺身にしてみた。神津島産は過去にない鮮度で、しかも皮を引くと身が真っ白である。身質は深海魚特有の脂があるなどキチジ(きんき)、オオサガ(荒神目抜け)とそっくり。脂が薄くて弱い筋繊維の中にコロイド状になってたまっているようだ。刺身は食感こそ上等とは言えないが、味は他に類をみないおいしさである。スーパーなどでもお馴染みの魚であるが、干もの・塩蔵品だけじゃない、鮮魚のよさも知って頂きたい。 冷凍保存しておいたクサヤモロ(魚はなんでもいい)の塩焼きと、四葉きゅうり(すうようきゅうり)、トマトがありました。5分以内に食べられるものを、と作ったのが市販のドレッシングで和えただけのサラダだ。余談になるが、ボクはある系統の人間とは数秒で仲良くなれる。あまり幸せな出会い(そんなに深刻ではない)ではなかったが、近所の家族と会うたびに長話をする仲になっている。その5人家族がモーレツ忙しい。夫婦が同じ職業でもあるので、今現在のように子供の病気が大流行(何が流行っているのかはわからない)しているときなど、端から見ても地獄のようだ。一家は魚をまったく食べない。「どうしたら子供が魚を食べるかな?」と聞かれたので近所のスーパーで塩蔵サバの特売をしていること、それを使ったサラダの作り方を教えた、それが今回の料理だ。手順は、焼く(この状態で保存する)、切る、混ぜ合わせる、ドレッシングを加える、の4つでしかなく、コツなどない。忙しいときなど10分で作る料理を5分で作る、ことを目指すべきだが、これなどもっと時短できる。アレンジもきく。回遊性の魚はうま味が豊かだし、ほどよく繊維質である。ほぐした身と四葉きゅうりの歯触りがいい感じである。そしてトマトの全体をまとめる感。近所の居酒屋が使っているという、優れもののドレッシングは魔法の調味料である。
冷凍保存しておいたクサヤモロ(魚はなんでもいい)の塩焼きと、四葉きゅうり(すうようきゅうり)、トマトがありました。5分以内に食べられるものを、と作ったのが市販のドレッシングで和えただけのサラダだ。余談になるが、ボクはある系統の人間とは数秒で仲良くなれる。あまり幸せな出会い(そんなに深刻ではない)ではなかったが、近所の家族と会うたびに長話をする仲になっている。その5人家族がモーレツ忙しい。夫婦が同じ職業でもあるので、今現在のように子供の病気が大流行(何が流行っているのかはわからない)しているときなど、端から見ても地獄のようだ。一家は魚をまったく食べない。「どうしたら子供が魚を食べるかな?」と聞かれたので近所のスーパーで塩蔵サバの特売をしていること、それを使ったサラダの作り方を教えた、それが今回の料理だ。手順は、焼く(この状態で保存する)、切る、混ぜ合わせる、ドレッシングを加える、の4つでしかなく、コツなどない。忙しいときなど10分で作る料理を5分で作る、ことを目指すべきだが、これなどもっと時短できる。アレンジもきく。回遊性の魚はうま味が豊かだし、ほどよく繊維質である。ほぐした身と四葉きゅうりの歯触りがいい感じである。そしてトマトの全体をまとめる感。近所の居酒屋が使っているという、優れもののドレッシングは魔法の調味料である。 せっかく浜名湖に行ったのだからと、お世話になっている『海老仙』さんで白焼きを買わせていただく。へそ曲がりと言われそうだが、7月も土用丑の日にはウナギ(ニホンウナギ)を食べない。お盆過ぎくらいまでは食べないので、これをウナギの断(だん)と勝手に呼んでいる。なぜなら店で食べるとして行列嫌いだし、取り寄せはしないし、安すぎて自然破壊になりかねない大量生産、冷凍ウナギ、輸入ウナギは買わないからだ。『海老仙』さんの白焼きをみると、背開きである。食べたら地焼き(蒸しの工程がない)である。厚みがあって膨らみを感じる。早朝のウナギ水揚げや、裂いているのを見ているので、水揚げし、泥抜きを終えた個体を揚げてすぐに裂いて、焼いたものであることがわかる。帰宅当日深夜は、白焼きの尾に近い部分をそのままあぶって酒の肴にする。浜名湖はそんなに遠くはないものの、往復の運転で体の底の方に疲れがたまっている。仮眠してもこの疲れの塊はとれない。これをウナギで追い払う。冷めた白焼きは少しあぶると表面に脂が滲み出してきて、泡立つ。ふっくらした感じが戻る。おいしい白焼きはわさび醤油が合う。この日は静岡県藤枝市、『志太泉 生酒』の冷え冷えを2合も飲む。あとは深い眠りにつくのみである。
せっかく浜名湖に行ったのだからと、お世話になっている『海老仙』さんで白焼きを買わせていただく。へそ曲がりと言われそうだが、7月も土用丑の日にはウナギ(ニホンウナギ)を食べない。お盆過ぎくらいまでは食べないので、これをウナギの断(だん)と勝手に呼んでいる。なぜなら店で食べるとして行列嫌いだし、取り寄せはしないし、安すぎて自然破壊になりかねない大量生産、冷凍ウナギ、輸入ウナギは買わないからだ。『海老仙』さんの白焼きをみると、背開きである。食べたら地焼き(蒸しの工程がない)である。厚みがあって膨らみを感じる。早朝のウナギ水揚げや、裂いているのを見ているので、水揚げし、泥抜きを終えた個体を揚げてすぐに裂いて、焼いたものであることがわかる。帰宅当日深夜は、白焼きの尾に近い部分をそのままあぶって酒の肴にする。浜名湖はそんなに遠くはないものの、往復の運転で体の底の方に疲れがたまっている。仮眠してもこの疲れの塊はとれない。これをウナギで追い払う。冷めた白焼きは少しあぶると表面に脂が滲み出してきて、泡立つ。ふっくらした感じが戻る。おいしい白焼きはわさび醤油が合う。この日は静岡県藤枝市、『志太泉 生酒』の冷え冷えを2合も飲む。あとは深い眠りにつくのみである。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州でクサヤモロをいっぱい釣ってきた。1尾くらいいなくなってもいいだろう、と思って失敬してきた。ごめんね。クサヤモロって、勝手に連れてきたくなるほどうまいのである。問題は鮮度落ちと、血合いの変色が早いことだけなので、早めに食べれば最上級の魚といってもいい。銭州でクサヤモロというと、エサ取りとか、大物のエサといった存在に思われていそうだけど、「もろこ(マハタなどの老成魚)」とか、シマアジなどと比べて決して味が劣るわけではない。持ち帰って、すぐに三枚に下ろし、12時間後に刺身で食べたが、食感がいい上にうま味豊かである。血合いの酸味もとてもいい。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州でクサヤモロをいっぱい釣ってきた。1尾くらいいなくなってもいいだろう、と思って失敬してきた。ごめんね。クサヤモロって、勝手に連れてきたくなるほどうまいのである。問題は鮮度落ちと、血合いの変色が早いことだけなので、早めに食べれば最上級の魚といってもいい。銭州でクサヤモロというと、エサ取りとか、大物のエサといった存在に思われていそうだけど、「もろこ(マハタなどの老成魚)」とか、シマアジなどと比べて決して味が劣るわけではない。持ち帰って、すぐに三枚に下ろし、12時間後に刺身で食べたが、食感がいい上にうま味豊かである。血合いの酸味もとてもいい。 にんにくをぎょうさん入れたので、口に入れる前から、にんにく甘く感じる。時差をつけてマイワシの濃厚なうま味が襲い来る。このうま味はオリーブオイルと一緒くたになったおいしさで、スパゲッティとくんつほぐれつ口の中で混合して、セモリナ粉の風味と食感、マイワシのおいしさなどでブラックホールの中のようになる。刻んだバジルは異次元の風味というか、そこだけおいしさの離れ小島のようである。刻んだマイワシの丸干しが素揚げになり、じゃり、かりっとして非常にうまい。そんじょそこいらのイタリアンに負けてたまるかよ、って味である。
にんにくをぎょうさん入れたので、口に入れる前から、にんにく甘く感じる。時差をつけてマイワシの濃厚なうま味が襲い来る。このうま味はオリーブオイルと一緒くたになったおいしさで、スパゲッティとくんつほぐれつ口の中で混合して、セモリナ粉の風味と食感、マイワシのおいしさなどでブラックホールの中のようになる。刻んだバジルは異次元の風味というか、そこだけおいしさの離れ小島のようである。刻んだマイワシの丸干しが素揚げになり、じゃり、かりっとして非常にうまい。そんじょそこいらのイタリアンに負けてたまるかよ、って味である。 近所のスーパーで千葉県木更津産アサリを連続買い。東京湾上総のアサリが完全復活したようだ。3パック買ったのに、なぜか木更津ブルーが見つからない。これを名付け親不幸という。木更津ブルーを見つけると、幸せになるとか、ならないとか?
近所のスーパーで千葉県木更津産アサリを連続買い。東京湾上総のアサリが完全復活したようだ。3パック買ったのに、なぜか木更津ブルーが見つからない。これを名付け親不幸という。木更津ブルーを見つけると、幸せになるとか、ならないとか? 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウがシノビテングハギを新島沖で釣ってきた。ボクのために釣ってきたに違いないので、断りもなく連れ帰ってきた。記載されたのが2011年で、標準和名がついたのが2013年という真新しい魚だが、我がデータベースには2002年の画像が不明種として残っている。あまりにも特徴がないというか、地味すぎるので、忍び(隠蔽種)であったのかも知れない。ニザダイ科テングハギ属の魚が相模湾全域で増えているが、シノビテングハギは伊豆諸島では平凡な魚と思っていいのかも。いまだに珍魚ではあると思っているが、非常に味のいい魚でもある。ニザダイ科の魚ではあるが臭味がなく、身質がよく、血合いが美しい。7月7日の個体など脂が乗っていて、同日のシマアジよりも箸が伸びがちだった。本種に関しては、とても博物館に差し上げたくはない、そんな魚である。酒はなしの凍頂烏龍茶であるが、お茶で食べてもうまい。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウがシノビテングハギを新島沖で釣ってきた。ボクのために釣ってきたに違いないので、断りもなく連れ帰ってきた。記載されたのが2011年で、標準和名がついたのが2013年という真新しい魚だが、我がデータベースには2002年の画像が不明種として残っている。あまりにも特徴がないというか、地味すぎるので、忍び(隠蔽種)であったのかも知れない。ニザダイ科テングハギ属の魚が相模湾全域で増えているが、シノビテングハギは伊豆諸島では平凡な魚と思っていいのかも。いまだに珍魚ではあると思っているが、非常に味のいい魚でもある。ニザダイ科の魚ではあるが臭味がなく、身質がよく、血合いが美しい。7月7日の個体など脂が乗っていて、同日のシマアジよりも箸が伸びがちだった。本種に関しては、とても博物館に差し上げたくはない、そんな魚である。酒はなしの凍頂烏龍茶であるが、お茶で食べてもうまい。 「茶がゆ」を初めて食べたのは、学生の時で、夏真っ盛りの晴れた日、多武峰談山神社(奈良県桜井市)から桜井駅まで歩いた、その途中で、だ。今、地図を見ると崇峻天皇陵のあたりだと推測する。当時は文献地図帖を持っての旅で、一本道を下りながら、ゆるやかに遭難したのだ。あのとき、農家らしい家の方が、大量の水と茶がゆを恵んでくれなかったら、死んでいたのかも知れない。当時は熱中症という言葉はなく、熱射病だった。あのときの水のおいしかったことと、梅干しと茶がゆが喉を通ったときの感覚は今でもおぼえている。以来、「茶がゆ」は夏の味である。さて、遅摘みの茶をしんなりさせて、釜で煎るタイプのお茶は、西日本各地にあるが、不思議なことに、ボクが勝手に「茶がゆ圏」としている奈良県、三重県西部、和歌山県のものは独特である。焙じる前の製法はわからないが、例えば同じ番茶と言われるものでも島根県伯太町(現米子市)のものとは似ても似つかないものだ。茶がゆ圏の番茶は苦味が強くどっしりと重い感じがする。伯太町の伯太番茶など限りなく軽く優しい味である。この、「茶がゆ圏」の古いタイプの番茶を探す旅がしてみたい。今回はその崇峻天皇陵近くで教わった通りのやり方で茶がゆをたいてみた。濃く煮だした奈良県十津川村の番茶に洗わない米を投入してたく、という奈良県ではもっとも一般的なやり方である。洗った米を投入すると、さらさらと軽い味になるし、茶色に染まる米粒の色も淡い。洗わないで入れると濃い茶色に米粒が染まり、かゆ自体が重い味になる。非常に濃く入れた茶の苦味が口にも喉にも残るが、この苦味が夏バテの薬なのではなかろうか。三重県伊賀市で会った赤目(三重県名張市)出身の大正生まれの女性は、「茶がゆ」は、「さいら(サンマ)」の丸干しと食べることが多かったという。当時の丸干しは木槌でよく叩かないと硬くて食べられなかったといが、この日合わせた三重県尾鷲市、『丸清北村商店』の丸干しは硬干しではあるけど、そのまま焼けば食べられる。
「茶がゆ」を初めて食べたのは、学生の時で、夏真っ盛りの晴れた日、多武峰談山神社(奈良県桜井市)から桜井駅まで歩いた、その途中で、だ。今、地図を見ると崇峻天皇陵のあたりだと推測する。当時は文献地図帖を持っての旅で、一本道を下りながら、ゆるやかに遭難したのだ。あのとき、農家らしい家の方が、大量の水と茶がゆを恵んでくれなかったら、死んでいたのかも知れない。当時は熱中症という言葉はなく、熱射病だった。あのときの水のおいしかったことと、梅干しと茶がゆが喉を通ったときの感覚は今でもおぼえている。以来、「茶がゆ」は夏の味である。さて、遅摘みの茶をしんなりさせて、釜で煎るタイプのお茶は、西日本各地にあるが、不思議なことに、ボクが勝手に「茶がゆ圏」としている奈良県、三重県西部、和歌山県のものは独特である。焙じる前の製法はわからないが、例えば同じ番茶と言われるものでも島根県伯太町(現米子市)のものとは似ても似つかないものだ。茶がゆ圏の番茶は苦味が強くどっしりと重い感じがする。伯太町の伯太番茶など限りなく軽く優しい味である。この、「茶がゆ圏」の古いタイプの番茶を探す旅がしてみたい。今回はその崇峻天皇陵近くで教わった通りのやり方で茶がゆをたいてみた。濃く煮だした奈良県十津川村の番茶に洗わない米を投入してたく、という奈良県ではもっとも一般的なやり方である。洗った米を投入すると、さらさらと軽い味になるし、茶色に染まる米粒の色も淡い。洗わないで入れると濃い茶色に米粒が染まり、かゆ自体が重い味になる。非常に濃く入れた茶の苦味が口にも喉にも残るが、この苦味が夏バテの薬なのではなかろうか。三重県伊賀市で会った赤目(三重県名張市)出身の大正生まれの女性は、「茶がゆ」は、「さいら(サンマ)」の丸干しと食べることが多かったという。当時の丸干しは木槌でよく叩かないと硬くて食べられなかったといが、この日合わせた三重県尾鷲市、『丸清北村商店』の丸干しは硬干しではあるけど、そのまま焼けば食べられる。 八王子総合卸売センター、福泉に新潟県佐渡から入合(何種類かの魚を1つの箱に入れて流通させたもの)が来ていて、中にクロダイが含まれていた。体長26.5cm・461g で関東では「かいず」と呼ばれているサイズで、佐渡では大小に関わらず「ちんだい」だ。どう見ても野締め(漁の最中に死んでしまったもの)である。これが今年の10個体目になる。毎年20個体くらいは状態をチェックしているので、クロダイの個体数から今年も半分終わったことがわかる。佐渡の「ちんだい」は明らかに産卵後だけど、身に張りがあるし、そんなに痩せてもいない。ちなみに新潟県ではクロダイは決してやっかいな存在ではない。夏だとマダイよりも高値がつくこともある。考えてみるとクロダイを未利用魚だとか、やっかいな存在だとか言っているのは非常に狭い地域だけのことでしかない。クロダイを未利用魚と喧伝しすぎてはいけない。理由は、むしろ普通の食用魚として利用している地域でのクロダイの評価を下げることになるからだ。さて、昼ご飯に刺身、焼霜造りにする。刺身は脂こそそんなにのっていなかったものの、うま味が実に豊かだった。夏の「ちんだい」うまいじゃないか!なんて思ったほどだ。
八王子総合卸売センター、福泉に新潟県佐渡から入合(何種類かの魚を1つの箱に入れて流通させたもの)が来ていて、中にクロダイが含まれていた。体長26.5cm・461g で関東では「かいず」と呼ばれているサイズで、佐渡では大小に関わらず「ちんだい」だ。どう見ても野締め(漁の最中に死んでしまったもの)である。これが今年の10個体目になる。毎年20個体くらいは状態をチェックしているので、クロダイの個体数から今年も半分終わったことがわかる。佐渡の「ちんだい」は明らかに産卵後だけど、身に張りがあるし、そんなに痩せてもいない。ちなみに新潟県ではクロダイは決してやっかいな存在ではない。夏だとマダイよりも高値がつくこともある。考えてみるとクロダイを未利用魚だとか、やっかいな存在だとか言っているのは非常に狭い地域だけのことでしかない。クロダイを未利用魚と喧伝しすぎてはいけない。理由は、むしろ普通の食用魚として利用している地域でのクロダイの評価を下げることになるからだ。さて、昼ご飯に刺身、焼霜造りにする。刺身は脂こそそんなにのっていなかったものの、うま味が実に豊かだった。夏の「ちんだい」うまいじゃないか!なんて思ったほどだ。 「わかし」からにじみ出たうま味だけで夏野菜を煮たもので、2日間かけて食べる。本来は捨ててしまう尾鰭と尾柄部(尾鰭のつけ根)、かま(胸鰭まわり)から非常に味わい深いだしが出てくる。尾にもかまにもたっぷり身があってほどよく締まり、調味料と調和して甘い。「わかし」のうま味を吸い取った夏野菜がうまいのは当たり前である。ぎょうさん作ってこつこつ食べるのが煮つけというものの本来の形である。ボクはこのような平凡な料理が好きで、昔々から平凡を研究している。あたらめて、紹介させてもらうと、ボクは「け」の研究家なのである。
「わかし」からにじみ出たうま味だけで夏野菜を煮たもので、2日間かけて食べる。本来は捨ててしまう尾鰭と尾柄部(尾鰭のつけ根)、かま(胸鰭まわり)から非常に味わい深いだしが出てくる。尾にもかまにもたっぷり身があってほどよく締まり、調味料と調和して甘い。「わかし」のうま味を吸い取った夏野菜がうまいのは当たり前である。ぎょうさん作ってこつこつ食べるのが煮つけというものの本来の形である。ボクはこのような平凡な料理が好きで、昔々から平凡を研究している。あたらめて、紹介させてもらうと、ボクは「け」の研究家なのである。 野に咲く花の名前は知らないけど、とても美しい。人間が努力して栽培した花の数十億倍きれいである。優れた料理も同じだと思う。名前は知らないけど、「あの素晴らしい味をもう一度」食べたいと、泣きたいほど思う、そんなものである。なんにも考えないで、それがなんとなく目の前にあるという事実がすごい。きゅうりとゆでたマグロ(Tuna)とマヨネーズが材料なのであっと言う間に出来上がる。しかも久しぶりに、非常に久しぶりに作ったのに、思った通りの味なのである。塩気はゆでたマグロだけのものだけど、実に濃厚なうまさを感じるのは、マグロが持っているうま味成分のためだ。真逆にあるのがきゅうりだけど、たぶんきゅうりのない夏は考えられないほど爽やかな味である。そしてマヨネーズ、起源はどうでもいいけど、ボクが子供の頃から食卓にあった、すごいヤツなのだ。
野に咲く花の名前は知らないけど、とても美しい。人間が努力して栽培した花の数十億倍きれいである。優れた料理も同じだと思う。名前は知らないけど、「あの素晴らしい味をもう一度」食べたいと、泣きたいほど思う、そんなものである。なんにも考えないで、それがなんとなく目の前にあるという事実がすごい。きゅうりとゆでたマグロ(Tuna)とマヨネーズが材料なのであっと言う間に出来上がる。しかも久しぶりに、非常に久しぶりに作ったのに、思った通りの味なのである。塩気はゆでたマグロだけのものだけど、実に濃厚なうまさを感じるのは、マグロが持っているうま味成分のためだ。真逆にあるのがきゅうりだけど、たぶんきゅうりのない夏は考えられないほど爽やかな味である。そしてマヨネーズ、起源はどうでもいいけど、ボクが子供の頃から食卓にあった、すごいヤツなのだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道根室市『北海屋商店』からマイワシが来ていた。たぶん2㎏判で、上イワシとされるものである。マイワシは年間を通して産地ごとに買って比べているので、数尾買う。帰宅後、すべて手開きにする。驚くことに中骨近くが赤い。脳みそに「?」がいっぱい浮かんだが、根室から航空便(空の便を使って送られたもの)で来るには、経費から考えても上物でなければならない。脂がないのか? あるのか?皮を剥いたら皮の下にある脂の層が、牡丹雪が積もったようである。口の中に入れた途端に溶ける。醤油を落として、そのまま茶の友とする。非常に濃い目に煮だした奈良県十津川村の番茶が合う。刺身だって茶菓子代わりになる、のである。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道根室市『北海屋商店』からマイワシが来ていた。たぶん2㎏判で、上イワシとされるものである。マイワシは年間を通して産地ごとに買って比べているので、数尾買う。帰宅後、すべて手開きにする。驚くことに中骨近くが赤い。脳みそに「?」がいっぱい浮かんだが、根室から航空便(空の便を使って送られたもの)で来るには、経費から考えても上物でなければならない。脂がないのか? あるのか?皮を剥いたら皮の下にある脂の層が、牡丹雪が積もったようである。口の中に入れた途端に溶ける。醤油を落として、そのまま茶の友とする。非常に濃い目に煮だした奈良県十津川村の番茶が合う。刺身だって茶菓子代わりになる、のである。 夏だ、夏だ、夏バテで、穴子だ、なんて思う。蒸し暑いし、やることが多すぎるし、で、7月になったばかりなのに滅法バテている。こんなときには長いものがいい。ドジョウでもいいのだけど、手に入らない。浜名湖で買った鰻を食べて、今度は穴子を食べる。煮立て穴子を軽くあぶって、ツメを塗って逢魔が時に本物ビールをやる。煮穴子は舌の上で脆弱に崩れていきながら、強いうま味と、調味料の甘みが一体化する。これをビールで流す。
夏だ、夏だ、夏バテで、穴子だ、なんて思う。蒸し暑いし、やることが多すぎるし、で、7月になったばかりなのに滅法バテている。こんなときには長いものがいい。ドジョウでもいいのだけど、手に入らない。浜名湖で買った鰻を食べて、今度は穴子を食べる。煮立て穴子を軽くあぶって、ツメを塗って逢魔が時に本物ビールをやる。煮穴子は舌の上で脆弱に崩れていきながら、強いうま味と、調味料の甘みが一体化する。これをビールで流す。 外気温は34度もあり、ベランダの温度計は38度などという日の、常備菜は十六ささげ(ジュウロクササゲ)と薩摩揚げをたいたものだ。十六ささげは八百屋の特売品だし、薩摩揚げはそろそろダメになりそうだったもので、日常生活というのは、実はこのような合理性によって営まれているのである。このとりたててうまいとも思えないものが、ないと寂しいのは米好きだからかも。米(ご飯)というのは多様な脇役を要するものなのだ。
外気温は34度もあり、ベランダの温度計は38度などという日の、常備菜は十六ささげ(ジュウロクササゲ)と薩摩揚げをたいたものだ。十六ささげは八百屋の特売品だし、薩摩揚げはそろそろダメになりそうだったもので、日常生活というのは、実はこのような合理性によって営まれているのである。このとりたててうまいとも思えないものが、ないと寂しいのは米好きだからかも。米(ご飯)というのは多様な脇役を要するものなのだ。 新子(コノシロの稚魚・幼魚)は手が届く値段になると、買うことにしている。別に生粋の江戸っ子ではないので、そんなに急いでは買わない。だいたい最初は100g、20000円くらいするので、とても手が出ない。ちなみに今回買った体長7㎝・7g前後くらいになると、開きやすくなるし、味が出てくる。袋入りで産地不明だが、実に鮮度がよく開きやすかった。開いて腹骨と背鰭を取り、やや強めの振り塩をする。8分ほどおいて、安い酢で洗う。軽く酢を切って保存する。1時間ほどで酢が回る。念のために新子、こはだだけは味や香りのある酢は避けたい。できればミツカンの「白菊」クラスだけど、手に入りやすいミツカンの「銘撰」を使った。さて、このサイズになるとしっかりニシン目ならではの味がする。小さい割りになだらかな中にピークのある味といったらいいだろう。非常に脆弱なのでたいして噛むこともなく半分溶ける。
新子(コノシロの稚魚・幼魚)は手が届く値段になると、買うことにしている。別に生粋の江戸っ子ではないので、そんなに急いでは買わない。だいたい最初は100g、20000円くらいするので、とても手が出ない。ちなみに今回買った体長7㎝・7g前後くらいになると、開きやすくなるし、味が出てくる。袋入りで産地不明だが、実に鮮度がよく開きやすかった。開いて腹骨と背鰭を取り、やや強めの振り塩をする。8分ほどおいて、安い酢で洗う。軽く酢を切って保存する。1時間ほどで酢が回る。念のために新子、こはだだけは味や香りのある酢は避けたい。できればミツカンの「白菊」クラスだけど、手に入りやすいミツカンの「銘撰」を使った。さて、このサイズになるとしっかりニシン目ならではの味がする。小さい割りになだらかな中にピークのある味といったらいいだろう。非常に脆弱なのでたいして噛むこともなく半分溶ける。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にキツネダイが来ていた。伊豆半島の以東にあまりいない魚で、西、駿河湾以南に多い。今回のものは静岡県御前崎産であるが、過去にも何度か御前崎の荷を見ている。体長30cm・624g なので本種としては大型である。ベラ科タキベラ属は味のいい魚が多いが、本種は取り分けうまい。ただ旬がよくわからない。さて、三枚に下ろすと身に張りがあり、少ししっとりしている。透明感がなく少し白濁しているのは、少ないながら脂ありとみた。皮に味があるので水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮付きのまま刺身状にきる。これを沸かした塩水の中で2、3秒湯引きする。梅肉とわさび醤油で食べたが、やはりおいしい魚だと改めて思った。水揚げ量がそれほど多くないので知名度が低い。そのせいで高級魚ではあるが、それ以上ではない。湯引きは飽きることがなく、半身分作って食べ尽くすことができた。今回は上品過ぎると思った身にほどよい甘味があり、食感の心地よさを楽しめた。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にキツネダイが来ていた。伊豆半島の以東にあまりいない魚で、西、駿河湾以南に多い。今回のものは静岡県御前崎産であるが、過去にも何度か御前崎の荷を見ている。体長30cm・624g なので本種としては大型である。ベラ科タキベラ属は味のいい魚が多いが、本種は取り分けうまい。ただ旬がよくわからない。さて、三枚に下ろすと身に張りがあり、少ししっとりしている。透明感がなく少し白濁しているのは、少ないながら脂ありとみた。皮に味があるので水洗いして三枚に下ろす。腹骨・血合い骨を取り、皮付きのまま刺身状にきる。これを沸かした塩水の中で2、3秒湯引きする。梅肉とわさび醤油で食べたが、やはりおいしい魚だと改めて思った。水揚げ量がそれほど多くないので知名度が低い。そのせいで高級魚ではあるが、それ以上ではない。湯引きは飽きることがなく、半身分作って食べ尽くすことができた。今回は上品過ぎると思った身にほどよい甘味があり、食感の心地よさを楽しめた。 日記風に。朝一番の冷たい茶漬けほどうまいものはない。最低限のおかずと、焙じたての番茶と、それだけがいい。十津川村など奈良県や三重県などの番茶でなけらば出ない、さらりとした味と苦味が夏バテぎみのボクを現に戻してくれる。
日記風に。朝一番の冷たい茶漬けほどうまいものはない。最低限のおかずと、焙じたての番茶と、それだけがいい。十津川村など奈良県や三重県などの番茶でなけらば出ない、さらりとした味と苦味が夏バテぎみのボクを現に戻してくれる。 岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。
岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。 神奈川県小田原市、小田原魚市場、江ノ浦沖、江の安漁場日渉丸、ワタルさんに体長25cm・250g前後の「わかし」を分けていただく。もちろんしっかり締めて血抜き済みである。6月7日には体長17cm・90g前後だったものが、1ヶ月経った7月4日には重さで2倍以上に成長している。相模湾では「わかし釣り」の時季となっている。さて、ワタルさんが締めた魚は、それだけで別格である。持ち帰ったばかり昼ご飯のおかずと、夜、酒の肴にしたが、「わかし」の刺身は非常に味わい深い。普通、「わかし」は数時間で食感が落ちてしまうが、ワタルさんの締めたものはその食感が水揚げしたてと変わらない。軽い味だけど、豊かなうま味が感じられるし、終いの方に酸味がくる。夜には2尾分の刺身を造って、食べきったほどなので飽きの来ない味といってもいいだろう。事ほど左様に、名人が締めて、ていねいに持ち帰った「わかし」はうまいのである。このとこと静岡県藤枝市「志太泉」を飲み過ぎていて、また2合がなくなる。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、江ノ浦沖、江の安漁場日渉丸、ワタルさんに体長25cm・250g前後の「わかし」を分けていただく。もちろんしっかり締めて血抜き済みである。6月7日には体長17cm・90g前後だったものが、1ヶ月経った7月4日には重さで2倍以上に成長している。相模湾では「わかし釣り」の時季となっている。さて、ワタルさんが締めた魚は、それだけで別格である。持ち帰ったばかり昼ご飯のおかずと、夜、酒の肴にしたが、「わかし」の刺身は非常に味わい深い。普通、「わかし」は数時間で食感が落ちてしまうが、ワタルさんの締めたものはその食感が水揚げしたてと変わらない。軽い味だけど、豊かなうま味が感じられるし、終いの方に酸味がくる。夜には2尾分の刺身を造って、食べきったほどなので飽きの来ない味といってもいいだろう。事ほど左様に、名人が締めて、ていねいに持ち帰った「わかし」はうまいのである。このとこと静岡県藤枝市「志太泉」を飲み過ぎていて、また2合がなくなる。 6月8日、神奈川県小田原市、二宮定置の水揚げを見ているときエソ科マエソ属の何かを渡してくれた。マエソ属に関しては奮闘努力中なので、とてもありがたい。ところが、またまた今回も、魚類検索が悪いのか、ボクが悪いのか?検索できない。困ったときの和田英敏さんに送ったら、答えが返ってきた。なーんだマエソかよとは思ったが、ものすごく勉強になった気がする。このような、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード、紆余曲折の果てに、マエソ属が恐くなくなる。マエソにはまさか隠蔽種はいないと思うけど、全部要注意! 細心の検索を要す。
6月8日、神奈川県小田原市、二宮定置の水揚げを見ているときエソ科マエソ属の何かを渡してくれた。マエソ属に関しては奮闘努力中なので、とてもありがたい。ところが、またまた今回も、魚類検索が悪いのか、ボクが悪いのか?検索できない。困ったときの和田英敏さんに送ったら、答えが返ってきた。なーんだマエソかよとは思ったが、ものすごく勉強になった気がする。このような、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード、紆余曲折の果てに、マエソ属が恐くなくなる。マエソにはまさか隠蔽種はいないと思うけど、全部要注意! 細心の検索を要す。 神奈川県小田原市、小田原魚市場の定置網は夏枯れ状態が続いている。水揚げ量が全体に減っており、場内ではむしろ深場の魚が目立つ。そんな中、小田原江ノ浦沖、江の安漁場日渉丸、ワタルさんに体長12cm〜15cmのマイワシを分けてもらう。コバルトブルーに輝く素晴らしいマイワシである。当然、刺身だろう。とは思ったが、丸干しを作りたかったので分けてもらったものなので、迷わす、丸干しを作る。立て塩を作る。鍋に水を張り塩を入れてかき混ぜ、溶けにくいと感じるくらいの量の塩を加える。一煮立ちさせて、渋いくらいの塩辛さになったら冷やす。マイワシは大ザルに入れて真水で洗う。水分をよく切る。冷えた立て塩に8分間漬け、水分を切る。徹底的に水分を取り、サーキュレーターと扇風機で丸一日かけて干し上げる。ザルに入れて冷蔵庫で半日冷やす。あとは保存するだけだ。これで14食分の丸干しが出来上がった。
神奈川県小田原市、小田原魚市場の定置網は夏枯れ状態が続いている。水揚げ量が全体に減っており、場内ではむしろ深場の魚が目立つ。そんな中、小田原江ノ浦沖、江の安漁場日渉丸、ワタルさんに体長12cm〜15cmのマイワシを分けてもらう。コバルトブルーに輝く素晴らしいマイワシである。当然、刺身だろう。とは思ったが、丸干しを作りたかったので分けてもらったものなので、迷わす、丸干しを作る。立て塩を作る。鍋に水を張り塩を入れてかき混ぜ、溶けにくいと感じるくらいの量の塩を加える。一煮立ちさせて、渋いくらいの塩辛さになったら冷やす。マイワシは大ザルに入れて真水で洗う。水分をよく切る。冷えた立て塩に8分間漬け、水分を切る。徹底的に水分を取り、サーキュレーターと扇風機で丸一日かけて干し上げる。ザルに入れて冷蔵庫で半日冷やす。あとは保存するだけだ。これで14食分の丸干しが出来上がった。 数量的にはわからないけど、浅いところの泥を網ですくっても貝が入ってこない。護岸を見ても貝類があまり見当たらないのはなぜだろう?大量についているはずのムラサキイガイがあまりいないし、昔、アサリ漁をやっていたことがあるという人に聞くと、タマガイ科の貝がいないという。「あけみがい(イソシジミ)」はもっと見ていないらしい。マガキの付着も少ない気がする。鷲津方面で落ちていないかと探したタマガイ科の巻き貝はやはり見つけられなかった。今回、落ちている貝殻の中でヒラフネガイも探したけど見つからず。今回は慌ただしくて、じっくり見て回れなかったが、次回は車中泊しながら水辺をじっくり観察したいと考えている。それにしても浜名湖にたくさんいたタマガイ科などなどは、どこに行ったんだろう。今の浜名湖は、どことなく不気味である。今回の参院選でひとりも自然保護や温暖化を叫ぶ立候補者がいない。生き物を見ていても明らかに危険な状況にある、と思うんだけど、自然保護は金にならないからやらないんだろうな。
数量的にはわからないけど、浅いところの泥を網ですくっても貝が入ってこない。護岸を見ても貝類があまり見当たらないのはなぜだろう?大量についているはずのムラサキイガイがあまりいないし、昔、アサリ漁をやっていたことがあるという人に聞くと、タマガイ科の貝がいないという。「あけみがい(イソシジミ)」はもっと見ていないらしい。マガキの付着も少ない気がする。鷲津方面で落ちていないかと探したタマガイ科の巻き貝はやはり見つけられなかった。今回、落ちている貝殻の中でヒラフネガイも探したけど見つからず。今回は慌ただしくて、じっくり見て回れなかったが、次回は車中泊しながら水辺をじっくり観察したいと考えている。それにしても浜名湖にたくさんいたタマガイ科などなどは、どこに行ったんだろう。今の浜名湖は、どことなく不気味である。今回の参院選でひとりも自然保護や温暖化を叫ぶ立候補者がいない。生き物を見ていても明らかに危険な状況にある、と思うんだけど、自然保護は金にならないからやらないんだろうな。 神奈川県小田原市、小田原魚市場の定置網は夏枯れ状態が続いている。水揚げ量が全体に減っており、場内ではむしろ深場の魚が目立つ。この夏場の状況は毎年変わらない。それでは定置網においしい魚はいないのだろうか? というとさにあらず、小田原の定置は扱いがていねいなので魅力的なものがいっぱいあるのである。今回はいろいろあって水揚げに集中できなかったので、定置網の方達が引き上げた後に、瓜坊(イサキの幼魚)体長15cm・70g前後をひとつふたつみっつ、とダンベから救出してきた。定置網の魚でダンベに行くというのは、魚粉になるということで、人の口に直接入らない、魚たちである。とった魚は直接人の口に入る方が自然に優しいし、温暖化防止になる。ところがイサキの100g以下は流通しない。流通しないというのは、今どきの曖昧言語を使うと未利用魚である。この100g以下のイサキがまずいかというと、真逆で漁師さんも知る非常においしい魚なのである。これが高値で飛ぶように売れるようになると、温暖化もほんのわずかストップできるのだけどな、と思いながら内臓をずぼ抜き。振り塩をして保存する。2日後に取り出して、水分を拭き取り、焼きたてをあつつと言いながら食べる。縦縞の消えた大人のイサキと比べると脂は少ないとはいえ、比べなければ脂は十二分にあるし、本体全部が非常にうまい。ちなみにイサキのおいしい点は少しだけ磯の香りがして、上品過ぎないところにある。イサキの塩焼きご飯一升というけれど、瓜坊の塩焼きでも5合はいけるだろう。最近のボクは、酒に溺れているので、静岡県藤枝市、志太泉を、なんと2合、も。どんなに瓜坊が栄養豊かでも、これでは夏が越せない。
神奈川県小田原市、小田原魚市場の定置網は夏枯れ状態が続いている。水揚げ量が全体に減っており、場内ではむしろ深場の魚が目立つ。この夏場の状況は毎年変わらない。それでは定置網においしい魚はいないのだろうか? というとさにあらず、小田原の定置は扱いがていねいなので魅力的なものがいっぱいあるのである。今回はいろいろあって水揚げに集中できなかったので、定置網の方達が引き上げた後に、瓜坊(イサキの幼魚)体長15cm・70g前後をひとつふたつみっつ、とダンベから救出してきた。定置網の魚でダンベに行くというのは、魚粉になるということで、人の口に直接入らない、魚たちである。とった魚は直接人の口に入る方が自然に優しいし、温暖化防止になる。ところがイサキの100g以下は流通しない。流通しないというのは、今どきの曖昧言語を使うと未利用魚である。この100g以下のイサキがまずいかというと、真逆で漁師さんも知る非常においしい魚なのである。これが高値で飛ぶように売れるようになると、温暖化もほんのわずかストップできるのだけどな、と思いながら内臓をずぼ抜き。振り塩をして保存する。2日後に取り出して、水分を拭き取り、焼きたてをあつつと言いながら食べる。縦縞の消えた大人のイサキと比べると脂は少ないとはいえ、比べなければ脂は十二分にあるし、本体全部が非常にうまい。ちなみにイサキのおいしい点は少しだけ磯の香りがして、上品過ぎないところにある。イサキの塩焼きご飯一升というけれど、瓜坊の塩焼きでも5合はいけるだろう。最近のボクは、酒に溺れているので、静岡県藤枝市、志太泉を、なんと2合、も。どんなに瓜坊が栄養豊かでも、これでは夏が越せない。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが新島沖でアヤメカサゴを釣り上げて来た。魚屋ならではの確かな締めで、鮮度抜群である。カサゴ類の旬はわかりにくいので、他のカサゴ類とともに本種も定期的に食べてみている。さて、今回のものは下ろした感じではさほど身に脂を感じない。カサゴ類は元来脂ののりの少ない魚だが、9月になると身がしっとりとしてくる。まずは湯引きにしてみた。三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮付きのまま刺身状に切り、塩を入れた湯の中で1、2秒揺らす。氷水に落として、粗熱を取り、水分をきった。やはり本種のうまい部分は皮と皮の直下である。皮を引くとおいしい部分が消えてしまう。この切りつけて湯引きするというのは、カサゴ類にもっとも適した料理だと思った。熱を通した分、皮が少しだけ柔らかくなって、身のうま味が増した。梅肉酢で食べたらとまらなくなる。ここ数日、あまりの暑さに冷や酒を飲み過ぎているが、静岡県藤枝市の「初亀」の冷え冷えが合う。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが新島沖でアヤメカサゴを釣り上げて来た。魚屋ならではの確かな締めで、鮮度抜群である。カサゴ類の旬はわかりにくいので、他のカサゴ類とともに本種も定期的に食べてみている。さて、今回のものは下ろした感じではさほど身に脂を感じない。カサゴ類は元来脂ののりの少ない魚だが、9月になると身がしっとりとしてくる。まずは湯引きにしてみた。三枚に下ろして腹骨・血合い骨を取る。皮付きのまま刺身状に切り、塩を入れた湯の中で1、2秒揺らす。氷水に落として、粗熱を取り、水分をきった。やはり本種のうまい部分は皮と皮の直下である。皮を引くとおいしい部分が消えてしまう。この切りつけて湯引きするというのは、カサゴ類にもっとも適した料理だと思った。熱を通した分、皮が少しだけ柔らかくなって、身のうま味が増した。梅肉酢で食べたらとまらなくなる。ここ数日、あまりの暑さに冷や酒を飲み過ぎているが、静岡県藤枝市の「初亀」の冷え冷えが合う。 岡山県ではとくに秋の小型を珍重する。大型魚よりも値が張る。昔、静岡県御前崎港で釣り上げた超小型もおいしくて、本命のメジナにはお帰り願い、アイゴ釣りに専念したこともある。そしてこのたび、静岡県湖西市鷲津漁港で体長15cm前後の「しゃくしゃ(アイゴ)」をいただいてきた。活魚だったので、締めて持ち帰った。鷲津で会った方は、一定期間生かして消化管の中のエサを出してから食べる、と言っていた。ただ今回のものは水揚げしたてを締め、血抜きしなかったが臭いはまったくなかった。しかも脂がのっていた。口に含むと脂があるのだろう、少しだけとろっととろける感じがする。アイゴならではの豊かなうま味もあり、舌を飽きさせない。4個体持ち帰って総て味見したが同じであった。防波堤釣り師(波止釣り師)としては、今度は自分で釣り上げて食べてみたいと思う。
岡山県ではとくに秋の小型を珍重する。大型魚よりも値が張る。昔、静岡県御前崎港で釣り上げた超小型もおいしくて、本命のメジナにはお帰り願い、アイゴ釣りに専念したこともある。そしてこのたび、静岡県湖西市鷲津漁港で体長15cm前後の「しゃくしゃ(アイゴ)」をいただいてきた。活魚だったので、締めて持ち帰った。鷲津で会った方は、一定期間生かして消化管の中のエサを出してから食べる、と言っていた。ただ今回のものは水揚げしたてを締め、血抜きしなかったが臭いはまったくなかった。しかも脂がのっていた。口に含むと脂があるのだろう、少しだけとろっととろける感じがする。アイゴならではの豊かなうま味もあり、舌を飽きさせない。4個体持ち帰って総て味見したが同じであった。防波堤釣り師(波止釣り師)としては、今度は自分で釣り上げて食べてみたいと思う。 浜名湖の雄踏の漁師さんに細かい魚たちを分けていただく。中に外套長50mmほどのジンドウイカと、10mm以下のミミイカが混ざっていた。連れて帰ってきたら食べる、と決めているので、「ねこた(ヒイラギ)」を煮た煮汁で、そのまま煮た。ものすごく小さな個体だけれど、温暖化対策のためというか、自然保護は「食べられるものを有効に利用する」ことが基本だ、と思っているので、無駄にはしない。無駄にはしないどころか、ジンドウイカは柔らかく、しっかりイカらしい風味がある。ミミイカなど極小なのに、「イカなのにタコ」的な食感があって、ワタに味があった。口寂しい、昼下がりにちょうどよいおやつとなる。浜名湖さん、ありがとさん。
浜名湖の雄踏の漁師さんに細かい魚たちを分けていただく。中に外套長50mmほどのジンドウイカと、10mm以下のミミイカが混ざっていた。連れて帰ってきたら食べる、と決めているので、「ねこた(ヒイラギ)」を煮た煮汁で、そのまま煮た。ものすごく小さな個体だけれど、温暖化対策のためというか、自然保護は「食べられるものを有効に利用する」ことが基本だ、と思っているので、無駄にはしない。無駄にはしないどころか、ジンドウイカは柔らかく、しっかりイカらしい風味がある。ミミイカなど極小なのに、「イカなのにタコ」的な食感があって、ワタに味があった。口寂しい、昼下がりにちょうどよいおやつとなる。浜名湖さん、ありがとさん。 ボクはあまり集中力がある方ではない。調べ物をしているときは、別のことができないし、外出も不可能だ。そんなときよく作るのが炊き込みご飯である。今回は塩サクラマスがあったので、まず解凍させて、時間をかけて香ばしく焼き上げる。粗熱がとれたら水飯の用意ができたところに入れ、刻み生姜、少量の酒・醤油を加える。塩サクラマスに塩気があるので醤油は風味づけ程度だ。炊飯は、米を洗うが数分、水加減して浸水30分、炊くのはたぶん10分、蒸らし10〜15分である。浸水の30分で塩サクラマスを焼き上げる。つきっきりでやらなくてもいい上に1時間以内で食べられる。炊き上がりを食べたら、鼻に抜ける香りにうっとりする。うま味を放出しているはずのサクラマスの身に強いうま味は感じられるし、甘味がある。混ぜ込んだ刻んだミョウガが、いい味を出している。当たり前だけど、サクラマスのうま味に満ちた飯のうまきことよ。みそ汁を作る間もなかったので、炊き込みご飯のみ2膳で、こんな日もある、ありすぎるボクだった。
ボクはあまり集中力がある方ではない。調べ物をしているときは、別のことができないし、外出も不可能だ。そんなときよく作るのが炊き込みご飯である。今回は塩サクラマスがあったので、まず解凍させて、時間をかけて香ばしく焼き上げる。粗熱がとれたら水飯の用意ができたところに入れ、刻み生姜、少量の酒・醤油を加える。塩サクラマスに塩気があるので醤油は風味づけ程度だ。炊飯は、米を洗うが数分、水加減して浸水30分、炊くのはたぶん10分、蒸らし10〜15分である。浸水の30分で塩サクラマスを焼き上げる。つきっきりでやらなくてもいい上に1時間以内で食べられる。炊き上がりを食べたら、鼻に抜ける香りにうっとりする。うま味を放出しているはずのサクラマスの身に強いうま味は感じられるし、甘味がある。混ぜ込んだ刻んだミョウガが、いい味を出している。当たり前だけど、サクラマスのうま味に満ちた飯のうまきことよ。みそ汁を作る間もなかったので、炊き込みご飯のみ2膳で、こんな日もある、ありすぎるボクだった。 浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、廃棄もしくは放流することになるらしい。以上は前回もかいた。片身を刺身にして、あらをあら汁にした。骨つきの半身はムニエルにする。横道にそれるが、サイトの運営上しかたがなく、特定のサイトなどを見ることがあるが、非常にいかがわしい、というか薄汚い。当たり前の魚を「超レア」だとか、もっとも嫌いな言葉「究極の」とか、「これ以上の魚はない」、「これが究極の料理法だ」などと書いてある。世の中に特別なものは存在しない、と思っているのでこのような言語を使うこと自体、愚かしいと思っている。魚は日常的に当たり前に食べてこそ、日本の自給率を上げることが出来るのに、これじゃ逆効果だし、自然に優しくない。ということで、今回の「ちんた」など買ったとしても安いものだし、珍しいものでもない。ボクのケ(日常)の日のお昼に、至って平凡にムニエルにして食べた。これに、いただきものの食パン1枚(高そうなパンで少し甘みがある)と日東紅茶とトマト1個のお昼だけれど、トマトが大きいので腹持ちがいい。クロダイの骨つきの半身は、塩コショウして小麦粉をつけてじっくりソテーしただけ。ムニエルは意外なくらい難易度が高い料理だけど、失敗しても失敗したと言うほどまずくないのがいい。タイ科のムニエルの特徴は、ソテーの仕方次第だが、皮がかりっと香ばしく上がり、身にしっとりと潤いが残ることだ。自画自賛はいかんが、今回は非常に上手にソテーできた。「ちんた」のムニエル、滅法うまいではないか。皮を食べただけでも御馳走だし、身に甘味がある。今回はパンに合わせたが、ご飯に合わせるときは醤油をたらすとよりご飯向きになる。今回の問題点は高そうな食パンに甘みがありすぎたことだけだ。魚料理に合わせるときのパンには、あまり上等なのはいらぬ。
浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、廃棄もしくは放流することになるらしい。以上は前回もかいた。片身を刺身にして、あらをあら汁にした。骨つきの半身はムニエルにする。横道にそれるが、サイトの運営上しかたがなく、特定のサイトなどを見ることがあるが、非常にいかがわしい、というか薄汚い。当たり前の魚を「超レア」だとか、もっとも嫌いな言葉「究極の」とか、「これ以上の魚はない」、「これが究極の料理法だ」などと書いてある。世の中に特別なものは存在しない、と思っているのでこのような言語を使うこと自体、愚かしいと思っている。魚は日常的に当たり前に食べてこそ、日本の自給率を上げることが出来るのに、これじゃ逆効果だし、自然に優しくない。ということで、今回の「ちんた」など買ったとしても安いものだし、珍しいものでもない。ボクのケ(日常)の日のお昼に、至って平凡にムニエルにして食べた。これに、いただきものの食パン1枚(高そうなパンで少し甘みがある)と日東紅茶とトマト1個のお昼だけれど、トマトが大きいので腹持ちがいい。クロダイの骨つきの半身は、塩コショウして小麦粉をつけてじっくりソテーしただけ。ムニエルは意外なくらい難易度が高い料理だけど、失敗しても失敗したと言うほどまずくないのがいい。タイ科のムニエルの特徴は、ソテーの仕方次第だが、皮がかりっと香ばしく上がり、身にしっとりと潤いが残ることだ。自画自賛はいかんが、今回は非常に上手にソテーできた。「ちんた」のムニエル、滅法うまいではないか。皮を食べただけでも御馳走だし、身に甘味がある。今回はパンに合わせたが、ご飯に合わせるときは醤油をたらすとよりご飯向きになる。今回の問題点は高そうな食パンに甘みがありすぎたことだけだ。魚料理に合わせるときのパンには、あまり上等なのはいらぬ。 浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。浜名湖では300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、放流することになるらしい。ちなみに1㎏前後は競り場に生きた状態で並んでいたし、直売所では刺身が売られていた。これを活かして持ち帰っている途中、高速道路上で後ろからバシャバシャと音がする。PAに入って見ると、「ちんた」が大暴れをしているではないか。仕方なく締めて、血抜きしないで持ち帰った。暴れたせいで尾鰭がぼろぼろ、決していい状態とは言えない。帰り着いた日に下ろして翌日刺身にする。大きさも、漁の後のボクの締め方にも、期待できるところはなにもない。ところが、これがうまかったのである。脂はないが、味がある。口に入れてすぐに甘味とうま味があり、中だるみがない。「ちんた」は「ちんた」なりのおいしさがあるのだな、なんて思ったものだ。ついでに言えば水域での汚れや汚染に影響を受けやすい魚だが、浜名湖はこの点からしても大丈夫らしい。
浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。浜名湖では300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、放流することになるらしい。ちなみに1㎏前後は競り場に生きた状態で並んでいたし、直売所では刺身が売られていた。これを活かして持ち帰っている途中、高速道路上で後ろからバシャバシャと音がする。PAに入って見ると、「ちんた」が大暴れをしているではないか。仕方なく締めて、血抜きしないで持ち帰った。暴れたせいで尾鰭がぼろぼろ、決していい状態とは言えない。帰り着いた日に下ろして翌日刺身にする。大きさも、漁の後のボクの締め方にも、期待できるところはなにもない。ところが、これがうまかったのである。脂はないが、味がある。口に入れてすぐに甘味とうま味があり、中だるみがない。「ちんた」は「ちんた」なりのおいしさがあるのだな、なんて思ったものだ。ついでに言えば水域での汚れや汚染に影響を受けやすい魚だが、浜名湖はこの点からしても大丈夫らしい。 浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。実際に行って、いろいろ話を聞くと、食文化はまったく別で、魚の評価も違っていた。例えばヒイラギは、浜名湖の西の湖西市鷲津・入出では「ぜんめ」、「ぜんな」、東の浜松市雄踏では「ねこた(猫またぎ)」という。西では食べ物で、東出は捨てる物だ。東、雄踏漁協の漁師さんにお願いしなくても、いただくことが出来たのが「ねこた」である。それでは浜名湖のヒイラギは、東西で味が違うのだろうか? というと、そんなことはない。「ヒイラギはとてもうまい魚だ」ということを東の漁師さんにいただいたヒイラギで、改めて思う。棘をハサミで切り取り、粗塩でぬめりを取って、水洗い。あとはざっと煮るだけ。高知市の漁師さんで、ぬめりも味だという人がいるので、ぬめり取りは不要かも。身離れがよく、身に甘味があり、とってもおいしゅう、ござんした。
浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。実際に行って、いろいろ話を聞くと、食文化はまったく別で、魚の評価も違っていた。例えばヒイラギは、浜名湖の西の湖西市鷲津・入出では「ぜんめ」、「ぜんな」、東の浜松市雄踏では「ねこた(猫またぎ)」という。西では食べ物で、東出は捨てる物だ。東、雄踏漁協の漁師さんにお願いしなくても、いただくことが出来たのが「ねこた」である。それでは浜名湖のヒイラギは、東西で味が違うのだろうか? というと、そんなことはない。「ヒイラギはとてもうまい魚だ」ということを東の漁師さんにいただいたヒイラギで、改めて思う。棘をハサミで切り取り、粗塩でぬめりを取って、水洗い。あとはざっと煮るだけ。高知市の漁師さんで、ぬめりも味だという人がいるので、ぬめり取りは不要かも。身離れがよく、身に甘味があり、とってもおいしゅう、ござんした。 カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。高知県の旅では中土佐町、いの町で実演しているのを見ている。実に手慣れたもので、あぶる、切る、塩をつけた手でたたく、と次々に出来上がる。あまりにもうまそうなので、思わず買ってしまいそうになる。この本来、カツオで造る、「塩たたき」を「だるま(メバチマグロの幼魚)」で造る。出来上がりを盛り付けて、すだちを1個全部搾り、みょうがに青じそに、にんにくを天盛りにした。仕上げに追いスダチをする。塩気は充分なので、スダチと香辛野菜だけの単純な組み合わせで食べる。脂ののった「だるま」は、うま味も非常に豊かで恐るべきうまさである。スダチ2個を搾ったが、もっと多くてもよかったかも。香酸柑橘類の旬はまだまだ遠い。
カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。高知県の旅では中土佐町、いの町で実演しているのを見ている。実に手慣れたもので、あぶる、切る、塩をつけた手でたたく、と次々に出来上がる。あまりにもうまそうなので、思わず買ってしまいそうになる。この本来、カツオで造る、「塩たたき」を「だるま(メバチマグロの幼魚)」で造る。出来上がりを盛り付けて、すだちを1個全部搾り、みょうがに青じそに、にんにくを天盛りにした。仕上げに追いスダチをする。塩気は充分なので、スダチと香辛野菜だけの単純な組み合わせで食べる。脂ののった「だるま」は、うま味も非常に豊かで恐るべきうまさである。スダチ2個を搾ったが、もっと多くてもよかったかも。香酸柑橘類の旬はまだまだ遠い。 浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。大型魚はスズキ、クロダイ、ボラなどだが、むしろ小型魚であるコノシロ、はんだ(サッパ)、ねこた(ヒイラギ)、夏はぜ(ウロハゼ)などが多いようだ。浜松市雄踏では「はんだ(サッパ)」は当日見た限りでは、競りに出すことがなく、廃棄されているようだった。これは浜名湖西部の鷲津でも同じである。ちなみにサッパは大きな括りではニシンやマイワシに近い魚で、腹部の底の部分に非常に硬い鱗があるのが特徴である。水揚げを見ていたとき、雄踏漁協の漁師さんたちに分けていただいたので、持ち帰って計測して食べてみた。それほど面倒な料理ではなく、岡山県で普通に作られている焼き漬けである。じっくり時間をかけて素焼きにし、二杯酢に1日漬け込んだだけ。酢と相性がいいのもあるが、非常にこくのある味で、濃厚なうま味が舌に残る。サッパという魚は、小骨が硬くて多いという二重苦を背負っているが、うま味の豊かさという点ではニシン類の中でもトップクラスである。岡山県人をして、「ままかり料理」の第一にあげる人が多いわけがわかる。旅の後なので、静岡県藤枝市の志太泉 原酒を冷やして舌を洗う。
浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。大型魚はスズキ、クロダイ、ボラなどだが、むしろ小型魚であるコノシロ、はんだ(サッパ)、ねこた(ヒイラギ)、夏はぜ(ウロハゼ)などが多いようだ。浜松市雄踏では「はんだ(サッパ)」は当日見た限りでは、競りに出すことがなく、廃棄されているようだった。これは浜名湖西部の鷲津でも同じである。ちなみにサッパは大きな括りではニシンやマイワシに近い魚で、腹部の底の部分に非常に硬い鱗があるのが特徴である。水揚げを見ていたとき、雄踏漁協の漁師さんたちに分けていただいたので、持ち帰って計測して食べてみた。それほど面倒な料理ではなく、岡山県で普通に作られている焼き漬けである。じっくり時間をかけて素焼きにし、二杯酢に1日漬け込んだだけ。酢と相性がいいのもあるが、非常にこくのある味で、濃厚なうま味が舌に残る。サッパという魚は、小骨が硬くて多いという二重苦を背負っているが、うま味の豊かさという点ではニシン類の中でもトップクラスである。岡山県人をして、「ままかり料理」の第一にあげる人が多いわけがわかる。旅の後なので、静岡県藤枝市の志太泉 原酒を冷やして舌を洗う。 山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。「山かけ」で重要なのは大和芋をおろし器でおろし、そのあとすり鉢に移して徹底的にすることだ。コツと言ってなにもないが、すり鉢の中で容赦もなくする、する。手が疲れるくらいすったら、すり鉢の中にぶつを入れ、こんどは和えて、和えて、和える。これも徹底的に和える。大和芋はこれくらいしないとブツと混ざらない。ボクの場合はあれこれやらず、生醤油とわさびで食べる。「だるま(メバチマグロの幼魚)」なのに、中心に近い部分にも味がある。一日寝かしてブツにしたせいか、下ろしたてよりも酸味がある。大和芋の強いねばりと微かな渋味とうま味が、酸味のあるブツとよく合う。
山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。「山かけ」で重要なのは大和芋をおろし器でおろし、そのあとすり鉢に移して徹底的にすることだ。コツと言ってなにもないが、すり鉢の中で容赦もなくする、する。手が疲れるくらいすったら、すり鉢の中にぶつを入れ、こんどは和えて、和えて、和える。これも徹底的に和える。大和芋はこれくらいしないとブツと混ざらない。ボクの場合はあれこれやらず、生醤油とわさびで食べる。「だるま(メバチマグロの幼魚)」なのに、中心に近い部分にも味がある。一日寝かしてブツにしたせいか、下ろしたてよりも酸味がある。大和芋の強いねばりと微かな渋味とうま味が、酸味のあるブツとよく合う。



