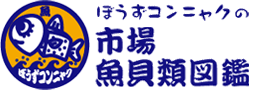コラム検索
検索条件
全59件中 全レコードを表示しています
 高知県幡多郡大月町にある道の駅大月、「ふれあい市場」はとても面白い。前回行ったときにも発見がありすぎて困ったものだが、今回は面白すぎて困っちゃう、といったものを発見した。磯の貝の塩ゆでである。真四角のケースに入っていて、標準和名、地域名がごちゃ混ぜになっている。ニシキウズ貝(ニシキウズガイ)、ニガニシ(キナレイシ)、カタベ貝(カタベガイ)、チャンバラ貝(マガキガイ)だ。製造者は同町の矢野雄二さんであるが、これ、冷凍してもあまり味が変わらないので、お土産にもなる。しかも磯の貝の入門にも役に立つ。個々の貝について解説していきたい。
高知県幡多郡大月町にある道の駅大月、「ふれあい市場」はとても面白い。前回行ったときにも発見がありすぎて困ったものだが、今回は面白すぎて困っちゃう、といったものを発見した。磯の貝の塩ゆでである。真四角のケースに入っていて、標準和名、地域名がごちゃ混ぜになっている。ニシキウズ貝(ニシキウズガイ)、ニガニシ(キナレイシ)、カタベ貝(カタベガイ)、チャンバラ貝(マガキガイ)だ。製造者は同町の矢野雄二さんであるが、これ、冷凍してもあまり味が変わらないので、お土産にもなる。しかも磯の貝の入門にも役に立つ。個々の貝について解説していきたい。 〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。
〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。 三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。
三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。 岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。
岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。 『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)は机周りにおいて、ときどき拾い読みをしている。中でも「懐かしのカドザメ」にある「酢の物」の作り方は、非常に合理的で、しかもおいしい。ちなみに木村守克は1936年生まれなので戦中・戦後を生きている。この書籍はとても貴重である。家庭料理の出来上がるまでの時間は短ければ短いほどよく、できるだけ単純でなければならない。できるだけ手間を省いて、しかもおいしくなければならない。この点からしても、弘前の「酢の物」は、料理屋の料理人の料理よりも優れていると思っている。この「酢の物」が非常にうまいのである。見た目は大根おろしの白に、ゆでたネズミザメ(カドザメ。モウカザメとも)も白なので料理自体が白一色、地味なことこの上ないものだが、最近、家庭料理は格好つけすぎなのだ。見た目の割りにまずいレシピが雑誌などを見ていても多すぎる。この見た目の地味さに反してのおいしさには感動できる。食卓の一隅にあると、アン・ドゥ・トロワの次くらいに箸が伸びる。ネズミザメの身はまったくくせがない。しかも柔らかく、後から甘味を伴ったうま味がくる。そして大根おろしが甘酸っぱい。料理の考え方としておぼえておくと、他の素材にも生かせそうである。
『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)は机周りにおいて、ときどき拾い読みをしている。中でも「懐かしのカドザメ」にある「酢の物」の作り方は、非常に合理的で、しかもおいしい。ちなみに木村守克は1936年生まれなので戦中・戦後を生きている。この書籍はとても貴重である。家庭料理の出来上がるまでの時間は短ければ短いほどよく、できるだけ単純でなければならない。できるだけ手間を省いて、しかもおいしくなければならない。この点からしても、弘前の「酢の物」は、料理屋の料理人の料理よりも優れていると思っている。この「酢の物」が非常にうまいのである。見た目は大根おろしの白に、ゆでたネズミザメ(カドザメ。モウカザメとも)も白なので料理自体が白一色、地味なことこの上ないものだが、最近、家庭料理は格好つけすぎなのだ。見た目の割りにまずいレシピが雑誌などを見ていても多すぎる。この見た目の地味さに反してのおいしさには感動できる。食卓の一隅にあると、アン・ドゥ・トロワの次くらいに箸が伸びる。ネズミザメの身はまったくくせがない。しかも柔らかく、後から甘味を伴ったうま味がくる。そして大根おろしが甘酸っぱい。料理の考え方としておぼえておくと、他の素材にも生かせそうである。 先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。くどいようだが、1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域本来の食文化が破壊される前である。郷土料理は急速に失われつつある。実際、小田原魚市場で「魚玉茶漬」を知っているか、聞いてもだれも知りはしない。さて、ご飯をチンするところから。
先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。くどいようだが、1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域本来の食文化が破壊される前である。郷土料理は急速に失われつつある。実際、小田原魚市場で「魚玉茶漬」を知っているか、聞いてもだれも知りはしない。さて、ご飯をチンするところから。 どんちっちあじは脂がのっていた。ただ、それにしても刺身ばかりでは飽きる。そこで作ったのが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という魚玉茶漬だ。1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域の本来の食文化が破壊される前である。卵と醤油で作る漬けは、愛媛県南部の「鯛飯」の食べ方に似ているが、あちらは生醤油ではなく、加減醤油を使うし、あちらは漬けではなく、即席で作る。要するに玉子(卵)と醤油の地に漬け込んだものをご飯にのせて、熱い番茶にのせて食べるものなので、小田原のものは家庭料理の延長線にあるのだろう。正確には醤油卵で、醤油の比率の方が高い。この地で漬けにしただけのもので、それだけで食べておいしいとは予想できなかった。脂が乗ったマアジだからかも知れないが、単なる漬けよりも味の奥行きを感じる。意外性のある、味である。これを熱々のご飯の上に乗せて、番茶をそそぐ。あとは茶漬けなのでしゃばしゃばと。もの足りなかったら、ちょっと醤油卵を足して、味を調えて食べる。今回は辛味は使わなかったけど、わさびが合うと思う。小田原に行ったら、みなに食べたことがあるか、聞かなくては。それにしても、小田原にこんな名物があったなんて。
どんちっちあじは脂がのっていた。ただ、それにしても刺身ばかりでは飽きる。そこで作ったのが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という魚玉茶漬だ。1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域の本来の食文化が破壊される前である。卵と醤油で作る漬けは、愛媛県南部の「鯛飯」の食べ方に似ているが、あちらは生醤油ではなく、加減醤油を使うし、あちらは漬けではなく、即席で作る。要するに玉子(卵)と醤油の地に漬け込んだものをご飯にのせて、熱い番茶にのせて食べるものなので、小田原のものは家庭料理の延長線にあるのだろう。正確には醤油卵で、醤油の比率の方が高い。この地で漬けにしただけのもので、それだけで食べておいしいとは予想できなかった。脂が乗ったマアジだからかも知れないが、単なる漬けよりも味の奥行きを感じる。意外性のある、味である。これを熱々のご飯の上に乗せて、番茶をそそぐ。あとは茶漬けなのでしゃばしゃばと。もの足りなかったら、ちょっと醤油卵を足して、味を調えて食べる。今回は辛味は使わなかったけど、わさびが合うと思う。小田原に行ったら、みなに食べたことがあるか、聞かなくては。それにしても、小田原にこんな名物があったなんて。 個人的に料理はできるだけ簡単に、時間は短く、こだわりを捨てて作りたい。料理の距離は1ミクロンでも短く、だ。意外にそのような、どうでもいい感じの料理の方がうまい。遙か昔の昔、親戚のおばちゃんが作った、竹の子のたいたんが、いまだに心に残っているが、作っているところなんざー、見ていられませんといったいい加減なものなのである。だけど、竹の子1本食い切るくらいにうまい。これが家庭料理の神髄なのだ。さて、酢のもん(酢のもの)の話だ。ボクの故郷は徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)だが、親戚の多くは、吉野川の対岸にある美馬町(現美馬市美馬町)に住んでいた。だから再三再四、美馬町に、赤い美馬橋を渡って行ったいたものである。さて、そんな美馬町も我が貞光町でも、日常的にも冠婚葬祭のときにも作っていたのが、じゃこ(ちりめんじゃこ/カタクチイワシの稚魚をゆでて干したもの)と鳴門ワカメと、きゅうりの酢のもんである。作り置きすると10日間くらい食べ続けられる。食卓にあるとありがたいもので、要するに保存食だ。
個人的に料理はできるだけ簡単に、時間は短く、こだわりを捨てて作りたい。料理の距離は1ミクロンでも短く、だ。意外にそのような、どうでもいい感じの料理の方がうまい。遙か昔の昔、親戚のおばちゃんが作った、竹の子のたいたんが、いまだに心に残っているが、作っているところなんざー、見ていられませんといったいい加減なものなのである。だけど、竹の子1本食い切るくらいにうまい。これが家庭料理の神髄なのだ。さて、酢のもん(酢のもの)の話だ。ボクの故郷は徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)だが、親戚の多くは、吉野川の対岸にある美馬町(現美馬市美馬町)に住んでいた。だから再三再四、美馬町に、赤い美馬橋を渡って行ったいたものである。さて、そんな美馬町も我が貞光町でも、日常的にも冠婚葬祭のときにも作っていたのが、じゃこ(ちりめんじゃこ/カタクチイワシの稚魚をゆでて干したもの)と鳴門ワカメと、きゅうりの酢のもんである。作り置きすると10日間くらい食べ続けられる。食卓にあるとありがたいもので、要するに保存食だ。 秋田県男鹿市船川の漁師、近藤亮さんにワカメをいただいた。男鹿のワカメは、鮮度がいいことはもちろん、葉先・茎は柔らかく、めかぶはよくねばり、でとてもいいワカメだ。荷物の中に出来上がった「とろとろわかめ(とろとろワカメ)」が入っていた。秋田県男鹿半島だけのもので、男鹿名物といってもいいだろう。「めかぶ」のようなねばりけではなく、名前のように「とろとろ」としている。ボクにはまったく新しい味覚である。朝ご飯にあると実にありがたい。
秋田県男鹿市船川の漁師、近藤亮さんにワカメをいただいた。男鹿のワカメは、鮮度がいいことはもちろん、葉先・茎は柔らかく、めかぶはよくねばり、でとてもいいワカメだ。荷物の中に出来上がった「とろとろわかめ(とろとろワカメ)」が入っていた。秋田県男鹿半島だけのもので、男鹿名物といってもいいだろう。「めかぶ」のようなねばりけではなく、名前のように「とろとろ」としている。ボクにはまったく新しい味覚である。朝ご飯にあると実にありがたい。 ここ数日、使っている福島県只見町、目黒麹店のみそが非常によい。みそ仕立ての「どんこ汁」は汁からすするのだけど、このみそ、甘味がほとんどなく、あっさりしていながら味がある。生でも汁にしてもいい。「どんこ(チゴダラ)」のだしが、「どんこ」の味として楽しめる。じゃまをしない。「どんこ汁」は肝と一緒にひとすすりすると、やけに重圧な味で、おいしさが大きいのに、後味がきわめていい。寒い朝に胃袋のあたりにカイロを当てたような感じになる。くせのない上品な白身が、みそと一緒になって、味わいのあるものに変身する。根切りの九条ねぎがやけにおいしいのも不思議だ。汁なのにごちそうである。しかもたぶん酒にも合うだろう。そしてご飯には合いすぎる。汁だけで大盛りご飯が食べられる。デブなので5勺の飯で我慢する、のは滅法つらい。
ここ数日、使っている福島県只見町、目黒麹店のみそが非常によい。みそ仕立ての「どんこ汁」は汁からすするのだけど、このみそ、甘味がほとんどなく、あっさりしていながら味がある。生でも汁にしてもいい。「どんこ(チゴダラ)」のだしが、「どんこ」の味として楽しめる。じゃまをしない。「どんこ汁」は肝と一緒にひとすすりすると、やけに重圧な味で、おいしさが大きいのに、後味がきわめていい。寒い朝に胃袋のあたりにカイロを当てたような感じになる。くせのない上品な白身が、みそと一緒になって、味わいのあるものに変身する。根切りの九条ねぎがやけにおいしいのも不思議だ。汁なのにごちそうである。しかもたぶん酒にも合うだろう。そしてご飯には合いすぎる。汁だけで大盛りご飯が食べられる。デブなので5勺の飯で我慢する、のは滅法つらい。 磯周りにいるメジナ、クロメジナ、イシダイ、イシガキダイ、イサキ、タカノハダイ、ニザダイなどを皮付きのまま、皮の方を焼いて切りつけたものを、高知県などでは「焼き切り(焼き切れ)」という。熱が通っているのは皮周辺だけで、明らかに魚の生食だ。高知県室戸などでは主に漁師の料理だという。一部の地域でサバ科の魚も使うが、ここでは切り放して考えていきたい。食物民族学者の近藤弘はこれを「ヤキギリ文化」としている。「焼き切り」、「焼き切れ」、「焼きたたき」、「たたき」など様々な呼び名があるが、この「ヤキギリ文化」とすると確かに整理しやすい。また、近藤弘は〈薩摩(鹿児島県)から土佐(高知県)の一切、柏島(ともに幡多郡大月町)を経て足摺岬まで分布していた。〉に「ヤキギリ文化」が存在すると考えていたようだ。実際は高知県室戸市三津・東洋町、徳島県海部郡海陽町宍喰にも存在している。また島根県隠岐諸島中ノ島では「皮焼き」というらしい。近藤弘は鮮度がよすぎる魚を食べるための料理法だとしている。とれたてはアデノシン三リン酸がイノシンに分解していない、これを熱を通すことでうま味を引き出すためだとしている。現在のところ、確認できているのは、徳島県(たたき)、高知県(焼き切れ)、愛媛県(焼き切り)、宮崎県(焼き切り)、鹿児島県(焼き切り)である。徳島県と室戸市のは焼いて、並べて塩・柚子を手に付けて叩くというのが入る。この手順が加わることを近藤弘はまた〈数歩進歩した生食の仕方。〉といっている。産地の漁師さんなどに、この磯にいる白身魚の「ヤキギリ」を聞き取りしているが、整理のための土台がない。以後、本コラムを土台として整理していくつもりである。■写真は大分県日田市で出会った佐伯市の方に教わったものだが、土着的なものであるのかは不明である。
磯周りにいるメジナ、クロメジナ、イシダイ、イシガキダイ、イサキ、タカノハダイ、ニザダイなどを皮付きのまま、皮の方を焼いて切りつけたものを、高知県などでは「焼き切り(焼き切れ)」という。熱が通っているのは皮周辺だけで、明らかに魚の生食だ。高知県室戸などでは主に漁師の料理だという。一部の地域でサバ科の魚も使うが、ここでは切り放して考えていきたい。食物民族学者の近藤弘はこれを「ヤキギリ文化」としている。「焼き切り」、「焼き切れ」、「焼きたたき」、「たたき」など様々な呼び名があるが、この「ヤキギリ文化」とすると確かに整理しやすい。また、近藤弘は〈薩摩(鹿児島県)から土佐(高知県)の一切、柏島(ともに幡多郡大月町)を経て足摺岬まで分布していた。〉に「ヤキギリ文化」が存在すると考えていたようだ。実際は高知県室戸市三津・東洋町、徳島県海部郡海陽町宍喰にも存在している。また島根県隠岐諸島中ノ島では「皮焼き」というらしい。近藤弘は鮮度がよすぎる魚を食べるための料理法だとしている。とれたてはアデノシン三リン酸がイノシンに分解していない、これを熱を通すことでうま味を引き出すためだとしている。現在のところ、確認できているのは、徳島県(たたき)、高知県(焼き切れ)、愛媛県(焼き切り)、宮崎県(焼き切り)、鹿児島県(焼き切り)である。徳島県と室戸市のは焼いて、並べて塩・柚子を手に付けて叩くというのが入る。この手順が加わることを近藤弘はまた〈数歩進歩した生食の仕方。〉といっている。産地の漁師さんなどに、この磯にいる白身魚の「ヤキギリ」を聞き取りしているが、整理のための土台がない。以後、本コラムを土台として整理していくつもりである。■写真は大分県日田市で出会った佐伯市の方に教わったものだが、土着的なものであるのかは不明である。 栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の利根川水系周辺で初午の日に作るのが「しもつかれ」である。塩ザケの頭と大豆、にんじん、大根、油揚げ、酒粕、ときに酢を入れる人もいる。これを大鍋で煮るという料理で、この地域のものはほとんど変わらぬ作り方と、味だ。ところが福島県南会津町(旧舘岩村・伊南村・南郷村)では「つむづかり」と訛り、作り方も具材も違っている。基本的に南会津町岩下で分けていただいたものなので、南会津町全域が同じとは思えないものの、栃木県の「しもつかれ」とは似て非なるものである。南会津は栃木県の湯西川や日光、大田原市などと郷里が近く、当然、関わりも深い。「出稼ぎの地」でもある。「つむづかり」は栃木県から伝わったとされているが、取り分けこの「出稼ぎの地」から伝わった可能性が高い。聞取した限りでも栃木県から伝わったのは明治時代にまではたどれそうである。本来、栃木県の「しもつかれ」は旧暦の初午の日に作られていた。南会津では最初から新暦で作られているところにも明治時代以降の伝播だからではないかと思っている。■写真は2月の南会津町岩下。
栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の利根川水系周辺で初午の日に作るのが「しもつかれ」である。塩ザケの頭と大豆、にんじん、大根、油揚げ、酒粕、ときに酢を入れる人もいる。これを大鍋で煮るという料理で、この地域のものはほとんど変わらぬ作り方と、味だ。ところが福島県南会津町(旧舘岩村・伊南村・南郷村)では「つむづかり」と訛り、作り方も具材も違っている。基本的に南会津町岩下で分けていただいたものなので、南会津町全域が同じとは思えないものの、栃木県の「しもつかれ」とは似て非なるものである。南会津は栃木県の湯西川や日光、大田原市などと郷里が近く、当然、関わりも深い。「出稼ぎの地」でもある。「つむづかり」は栃木県から伝わったとされているが、取り分けこの「出稼ぎの地」から伝わった可能性が高い。聞取した限りでも栃木県から伝わったのは明治時代にまではたどれそうである。本来、栃木県の「しもつかれ」は旧暦の初午の日に作られていた。南会津では最初から新暦で作られているところにも明治時代以降の伝播だからではないかと思っている。■写真は2月の南会津町岩下。 ワタ煮は数日に亘って食べる。もちろん酒の肴である。消化管はこりこりして、ちょっとだけにょごっ、とする。噛みしめるとうま味が染み出してくる。肝はほくっとして甘く、舌にざらざらとうま味を残す。この内臓巡りの旅、こそが「わた煮」のよさだ。ブリのサイズも産地もわからない。ちゃんと魚屋に言えば、真子・白子入りもあるけど、次回持ち越し。酒は新潟県上越市、雪中梅の普通酒だ。
ワタ煮は数日に亘って食べる。もちろん酒の肴である。消化管はこりこりして、ちょっとだけにょごっ、とする。噛みしめるとうま味が染み出してくる。肝はほくっとして甘く、舌にざらざらとうま味を残す。この内臓巡りの旅、こそが「わた煮」のよさだ。ブリのサイズも産地もわからない。ちゃんと魚屋に言えば、真子・白子入りもあるけど、次回持ち越し。酒は新潟県上越市、雪中梅の普通酒だ。 飯綱町で滝澤農園を営んでいる滝澤卓さんが、なぜ、滝澤賢さんになったのだろうか、はともかく……。飯綱町では、「ふきのとうみそ」でお握りを作ってリンゴ作りの合間に、畑で食べているという。もちろん農作業の合間に畑で食べた方がおいしかろう。
飯綱町で滝澤農園を営んでいる滝澤卓さんが、なぜ、滝澤賢さんになったのだろうか、はともかく……。飯綱町では、「ふきのとうみそ」でお握りを作ってリンゴ作りの合間に、畑で食べているという。もちろん農作業の合間に畑で食べた方がおいしかろう。 「たら汁」は日本各北陸以北、東北で作られているものだが。青森県の「じゃっぱ汁」、秋田県の「たら汁」、山形県の「どんがら汁」などはマダラで作る。新潟県以西は主に「たら(「すけそ」とも。スケトウダラ)」で作る。塩味の汁、醤油味、みそ味などいろいろあるが、新潟県はなんだろう? と思っていたら、上越市では「粕汁」だという。「粕汁」と初めて出合ったのは秋田県横手市だが、あまりにも塩辛いのでビックリして味がよくわからなかった。以来粕汁とは長々と縁がなかった。だいたいみそ汁に酒粕を入れる文化は、ボクの生まれた四国の町にはなかった。実際、上越市内のスーパーに行くと、酒粕がたらの切り身の横に置いてある。「ばら粕」というばらけた酒粕で、ちょうど手に取っていたバアチャンに作り方を聞いたら、最初に湯の中で酒粕を溶かしておくのがコツで、あとは「たらのみそ汁を作ればいい」のだという。大根やニンジンを入れるといいと聞いたけど、やめた。とにかく大量に作って正月を越そうと思ったのだ。作りたてはみそと酒粕のせいで、ちょっと濃厚な味わいではあるが、さほど感心できる味ではなかった。酒粕のアルコールが残っている気がして、少し煮込んでみたが、やはり味は平凡だった。想像したよりは、うまい、といったところだ。
「たら汁」は日本各北陸以北、東北で作られているものだが。青森県の「じゃっぱ汁」、秋田県の「たら汁」、山形県の「どんがら汁」などはマダラで作る。新潟県以西は主に「たら(「すけそ」とも。スケトウダラ)」で作る。塩味の汁、醤油味、みそ味などいろいろあるが、新潟県はなんだろう? と思っていたら、上越市では「粕汁」だという。「粕汁」と初めて出合ったのは秋田県横手市だが、あまりにも塩辛いのでビックリして味がよくわからなかった。以来粕汁とは長々と縁がなかった。だいたいみそ汁に酒粕を入れる文化は、ボクの生まれた四国の町にはなかった。実際、上越市内のスーパーに行くと、酒粕がたらの切り身の横に置いてある。「ばら粕」というばらけた酒粕で、ちょうど手に取っていたバアチャンに作り方を聞いたら、最初に湯の中で酒粕を溶かしておくのがコツで、あとは「たらのみそ汁を作ればいい」のだという。大根やニンジンを入れるといいと聞いたけど、やめた。とにかく大量に作って正月を越そうと思ったのだ。作りたてはみそと酒粕のせいで、ちょっと濃厚な味わいではあるが、さほど感心できる味ではなかった。酒粕のアルコールが残っている気がして、少し煮込んでみたが、やはり味は平凡だった。想像したよりは、うまい、といったところだ。 「しか煮」はソウダガツオ属と玉ねぎを使って作る、「すき焼き」風の煮物で、神奈川県小田原・真鶴の郷土料理だ。高い牛肉・豚肉ではなく、海に近いところなので安い魚で代用したものだ。このソウダガツオを使った「すき焼き風惣菜」に対して「しか煮」という言語がなぜ生まれたのかはわからない。漢字は「鹿煮」だという人がいる。鹿肉のような味がするためらしい。また四角く切って作るので「四角煮」が「しか煮」になったとも。基本的には「うずわ(マルソウダ)」で作るらしく、「『うずわ』でなければおいしくない」、「『うずわ』で作るから『しか煮』だ」という人もいる。もちろん、「そうだ(ヒラソウダ)」でもいいという人もいる。確かに「うずわ(マルソウダ)」で作ると煮て硬く締まり、この硬さが肉(鹿肉)を思わせる。うま味も豊かである。対するに「そうだ(ヒラソウダ)」は煮ると軟らかく、うま味は「うずわ」と比べると少ない。「うずわ(マルソウダ)」よりも魚の煮つけ的な味だ。比較しなければどちらもおいしいが、水揚げされているのを見て、どちらを選ぶかと言われると、「うずわ(マルソウダ)」を手に取ることになる。今のところ、神奈川県小田原市・真鶴町だけの料理のようだが、調べていく内に作っている地域が広がったり、逆に狭まったりする可能性がある。本料理は小田原市鴨宮にある鮮魚店『魚竹』さんと、小田原市江之浦、江の安 ワタルさん夫婦に教わったもの。また、『魚竹』さんはジャガイモを入れて、「肉じゃが風」にするというので、こちらも作ってみた。協力に感謝します。
「しか煮」はソウダガツオ属と玉ねぎを使って作る、「すき焼き」風の煮物で、神奈川県小田原・真鶴の郷土料理だ。高い牛肉・豚肉ではなく、海に近いところなので安い魚で代用したものだ。このソウダガツオを使った「すき焼き風惣菜」に対して「しか煮」という言語がなぜ生まれたのかはわからない。漢字は「鹿煮」だという人がいる。鹿肉のような味がするためらしい。また四角く切って作るので「四角煮」が「しか煮」になったとも。基本的には「うずわ(マルソウダ)」で作るらしく、「『うずわ』でなければおいしくない」、「『うずわ』で作るから『しか煮』だ」という人もいる。もちろん、「そうだ(ヒラソウダ)」でもいいという人もいる。確かに「うずわ(マルソウダ)」で作ると煮て硬く締まり、この硬さが肉(鹿肉)を思わせる。うま味も豊かである。対するに「そうだ(ヒラソウダ)」は煮ると軟らかく、うま味は「うずわ」と比べると少ない。「うずわ(マルソウダ)」よりも魚の煮つけ的な味だ。比較しなければどちらもおいしいが、水揚げされているのを見て、どちらを選ぶかと言われると、「うずわ(マルソウダ)」を手に取ることになる。今のところ、神奈川県小田原市・真鶴町だけの料理のようだが、調べていく内に作っている地域が広がったり、逆に狭まったりする可能性がある。本料理は小田原市鴨宮にある鮮魚店『魚竹』さんと、小田原市江之浦、江の安 ワタルさん夫婦に教わったもの。また、『魚竹』さんはジャガイモを入れて、「肉じゃが風」にするというので、こちらも作ってみた。協力に感謝します。 「ざっこの貝焼き」は「ざっこ」のみそ汁である。「貝焼き(かやき)」は東北や新潟県の言葉で、もともとはホタテガイの貝殻を鍋にして作る、醤油・みそ仕立ての料理のことだ。ヤツメウナギやホタテガイ、みそ仕立ての卵料理などがある。ここ秋田県旧館合村(現横手市雄物川町)でも、また古くは貝殻を鍋にして作っていたことから「貝焼き」なのだ、と思われる。
「ざっこの貝焼き」は「ざっこ」のみそ汁である。「貝焼き(かやき)」は東北や新潟県の言葉で、もともとはホタテガイの貝殻を鍋にして作る、醤油・みそ仕立ての料理のことだ。ヤツメウナギやホタテガイ、みそ仕立ての卵料理などがある。ここ秋田県旧館合村(現横手市雄物川町)でも、また古くは貝殻を鍋にして作っていたことから「貝焼き」なのだ、と思われる。 秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんが作ってくれた「ざっこ蒸」は「ためっこ漁」でとれた「ざっこ」の大方を使って作る。「ざっこ蒸」は「塩蒸しざっこ」ともいう。柔らかくほどよい塩味で、内臓に苦味がある。けっして食べやすいものではないが、残して置きたい雄物川の冬の味覚である。
秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんが作ってくれた「ざっこ蒸」は「ためっこ漁」でとれた「ざっこ」の大方を使って作る。「ざっこ蒸」は「塩蒸しざっこ」ともいう。柔らかくほどよい塩味で、内臓に苦味がある。けっして食べやすいものではないが、残して置きたい雄物川の冬の味覚である。 「いもじく」の炒め煮は、炒め煮界のトップというか、他に類を見ないうまさなのである。しゃきしゃきっとしていて、ほどよく青臭くて、蕗とは違う味がある。ちなみに南方で過酷な戦争体験をした、加東大介は来る日も来る日も、サツマイモとその茎ばかりで飢えをしのいだと書いている。サツマイモの茎はおいしいじゃない、と一瞬思ったが、醤油も油揚げもない南方でどのように料理していたのだろう。やたらにうまいのに、もっとたくさん買って来ればよかった、と思わないのは、手間がかかるからだ。この「いもじく」の皮を剥いてくれる優しい女性、いるわけないよな。
「いもじく」の炒め煮は、炒め煮界のトップというか、他に類を見ないうまさなのである。しゃきしゃきっとしていて、ほどよく青臭くて、蕗とは違う味がある。ちなみに南方で過酷な戦争体験をした、加東大介は来る日も来る日も、サツマイモとその茎ばかりで飢えをしのいだと書いている。サツマイモの茎はおいしいじゃない、と一瞬思ったが、醤油も油揚げもない南方でどのように料理していたのだろう。やたらにうまいのに、もっとたくさん買って来ればよかった、と思わないのは、手間がかかるからだ。この「いもじく」の皮を剥いてくれる優しい女性、いるわけないよな。 北海道根室市は国内で唯一、オオノガイ漁が行われているところ。2024年6月24日の北海道根室市温根沼や春国岱でのオオノガイ漁解禁日(解禁日は年2回)に漁を見に行った。オオノガイは干潟の泥の中にもぐり込んでいるので、動力船などでの漁はできない。すべて手掘りである。この手掘り漁を、干潟を駆けずり回って見せて頂いた。オオノガイの料理に関しても聞いて回ったが、水管を刺身で食べるという人は少なく、常備菜とか保存食にする人ばかりだった。塩辛を作る、もしくは作っていたという人は取り分け多かったが、今でも毎年作るという人は少なかった。仕方がないので作り方を教わって、わたを譲り受けて作ってみた。
北海道根室市は国内で唯一、オオノガイ漁が行われているところ。2024年6月24日の北海道根室市温根沼や春国岱でのオオノガイ漁解禁日(解禁日は年2回)に漁を見に行った。オオノガイは干潟の泥の中にもぐり込んでいるので、動力船などでの漁はできない。すべて手掘りである。この手掘り漁を、干潟を駆けずり回って見せて頂いた。オオノガイの料理に関しても聞いて回ったが、水管を刺身で食べるという人は少なく、常備菜とか保存食にする人ばかりだった。塩辛を作る、もしくは作っていたという人は取り分け多かったが、今でも毎年作るという人は少なかった。仕方がないので作り方を教わって、わたを譲り受けて作ってみた。 久しぶりの「氷頭なます」にどうにも箸が止まらない。日本酒にも合うので、ついつい杯を重ねることになり、終いにはコップ酒になる。心地よくなって、この「氷頭(上顎の先端と目の間の皮と軟骨)を食べようと思った始まりの地はどこだろう?」なんて考えてしまう。きっと村上市の人は、うちだ、といい。岩手の人も、うちだ、といいそうだ。こりっこりっとして噛みしめると髄液のような、不思議な液体が出てくる。軟骨なのにうま味がとても強いのはこの正体不明の液体のせいだろう。分厚い皮に微かに脂と甘味があるのもいい。ちなみに市販の「氷頭なます」で、うまいものに出合ったことがない。また作るしかないけど、来季かも知れぬ。
久しぶりの「氷頭なます」にどうにも箸が止まらない。日本酒にも合うので、ついつい杯を重ねることになり、終いにはコップ酒になる。心地よくなって、この「氷頭(上顎の先端と目の間の皮と軟骨)を食べようと思った始まりの地はどこだろう?」なんて考えてしまう。きっと村上市の人は、うちだ、といい。岩手の人も、うちだ、といいそうだ。こりっこりっとして噛みしめると髄液のような、不思議な液体が出てくる。軟骨なのにうま味がとても強いのはこの正体不明の液体のせいだろう。分厚い皮に微かに脂と甘味があるのもいい。ちなみに市販の「氷頭なます」で、うまいものに出合ったことがない。また作るしかないけど、来季かも知れぬ。 アルマイトの弁当箱に入ったご飯はやけにうまいという話をしたい。我が家にあるアルミの弁当箱は2つ。ひとつはただのアルミで、アルマイトではない銀色のもの。片方は大分県日田市の雑貨店で、昔、中学生(旧制で現在の高等学校)の学生が使ったというサイズのアルマイトだ。165㎜・105㎜で深さが54㎜あるが、これ以上のも、もっと大型も昔はあったらしい。買ってきて、ご飯をつめてビックリ仰天した。言われた通りにぎゅうぎゅうにつめると1合半くらい入る。ふんわりつめても1合で、おかず入れを脇に入れてふんわり詰めても、食堂の大盛りご飯以上だ。ここで大問題が発生する。ただのご飯なのにアルマイトの弁当箱につめるとず、ずーんとうまくなるのだ。しかもふんわりつめるよりも、ぎゅうぎゅう詰めの方がおいしい。昔、日の丸弁当(梅干しだけの弁当)なんて最低だ、と思っていたのは大間違いだったことに気づく。ちなみにボクはあまり弁当経験がない。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の小学生は、お昼は家に食べに帰っていた。中学生の時は給食だった。高校生になると弁当を持っていくようになったが、ブックタイプというやつで箸箱が脇につき、おかず入れはパッチンとやるやつだった。初めて松本周辺に行ったのが、1990年代。この時代、旧制高校に通っていた世代がまだずいぶん生きていた。彼らは昭和2年から5年生まれで、アルマイトの弁当箱が高級品だった世代だ。話をもとにもどすと、このアルマイトの弁当箱に、飛騨高山や松本市では正月明けに塩鰤を入れて持っていくのがステータスだった。塩鰤が年取魚でもっとも高価だったためだ。久しぶりに旧制中学弁当を再現してみた。塩鰤だけでは寂しいので、梅干しにたくわんを加えたが、今どきこんな貧相な弁当を持っていく子供はいないだろう。ただ、不思議なほどうまいアルマイトの弁当箱のご飯に、熟成して濃厚かつ強い塩味の塩鰤が入っていたら、きっとこの上のサイズの弁当箱でも食い尽くせるはずだし、実は途方もなくぜいたくな弁当だといえないだろうか。これを食い切り、まだ胃の腑に余地があるのもアルマイト弁当箱マジックかも。
アルマイトの弁当箱に入ったご飯はやけにうまいという話をしたい。我が家にあるアルミの弁当箱は2つ。ひとつはただのアルミで、アルマイトではない銀色のもの。片方は大分県日田市の雑貨店で、昔、中学生(旧制で現在の高等学校)の学生が使ったというサイズのアルマイトだ。165㎜・105㎜で深さが54㎜あるが、これ以上のも、もっと大型も昔はあったらしい。買ってきて、ご飯をつめてビックリ仰天した。言われた通りにぎゅうぎゅうにつめると1合半くらい入る。ふんわりつめても1合で、おかず入れを脇に入れてふんわり詰めても、食堂の大盛りご飯以上だ。ここで大問題が発生する。ただのご飯なのにアルマイトの弁当箱につめるとず、ずーんとうまくなるのだ。しかもふんわりつめるよりも、ぎゅうぎゅう詰めの方がおいしい。昔、日の丸弁当(梅干しだけの弁当)なんて最低だ、と思っていたのは大間違いだったことに気づく。ちなみにボクはあまり弁当経験がない。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の小学生は、お昼は家に食べに帰っていた。中学生の時は給食だった。高校生になると弁当を持っていくようになったが、ブックタイプというやつで箸箱が脇につき、おかず入れはパッチンとやるやつだった。初めて松本周辺に行ったのが、1990年代。この時代、旧制高校に通っていた世代がまだずいぶん生きていた。彼らは昭和2年から5年生まれで、アルマイトの弁当箱が高級品だった世代だ。話をもとにもどすと、このアルマイトの弁当箱に、飛騨高山や松本市では正月明けに塩鰤を入れて持っていくのがステータスだった。塩鰤が年取魚でもっとも高価だったためだ。久しぶりに旧制中学弁当を再現してみた。塩鰤だけでは寂しいので、梅干しにたくわんを加えたが、今どきこんな貧相な弁当を持っていく子供はいないだろう。ただ、不思議なほどうまいアルマイトの弁当箱のご飯に、熟成して濃厚かつ強い塩味の塩鰤が入っていたら、きっとこの上のサイズの弁当箱でも食い尽くせるはずだし、実は途方もなくぜいたくな弁当だといえないだろうか。これを食い切り、まだ胃の腑に余地があるのもアルマイト弁当箱マジックかも。 年取魚(大晦日から新年にかけて食べる魚)のブリはすべて塩鰤であった。新潟から富山、石川、山陰、玄海灘にかけて揚がったら、すべて塩蔵して保存していた。これを旧暦の正月前に売っていた。旧暦の正月は太陽暦の1月下旬から2月前半くらいまでなので、ブリは新暦の11月から1月にかけてとって塩蔵した。ブリ漁の最盛期は新暦の1月以降なので、新暦の年取・正月には間に合わない。そのため、2010年代初めまでは、岐阜県飛騨高山の安い塩鰤は養殖もの、高いものは富山湾などの天然ものであった。天然ものが、すごく高いのは氷見産であったり、時季外れに塩鰤を作るからだ。そして今、飛騨高山の塩鰤は養殖ものが下級品、北海道産が高級品となっている。
年取魚(大晦日から新年にかけて食べる魚)のブリはすべて塩鰤であった。新潟から富山、石川、山陰、玄海灘にかけて揚がったら、すべて塩蔵して保存していた。これを旧暦の正月前に売っていた。旧暦の正月は太陽暦の1月下旬から2月前半くらいまでなので、ブリは新暦の11月から1月にかけてとって塩蔵した。ブリ漁の最盛期は新暦の1月以降なので、新暦の年取・正月には間に合わない。そのため、2010年代初めまでは、岐阜県飛騨高山の安い塩鰤は養殖もの、高いものは富山湾などの天然ものであった。天然ものが、すごく高いのは氷見産であったり、時季外れに塩鰤を作るからだ。そして今、飛騨高山の塩鰤は養殖ものが下級品、北海道産が高級品となっている。 仕事が行き詰まっているので、暫し寄り道的なことを。秋になり気温が下がると「かつおぶし削り節(以後単にカツオ節もしくは削り節)」を買う。「削り節買う」はボクの秋の季語だ。今回は、東京都足立市場内の『伊勢重』という店で削りたてを買うことができた。ちなみに削り節は、基本冷蔵保存である。冷蔵庫が小さいので、保冷するものが多い夏の間は保管できない。だから夏は煮干し類一辺倒でだしをとる。ちなみに疲れているときはだしの素も使っているわけで、だしの素も嫌いではない、ということも忘れないで言っておく。
仕事が行き詰まっているので、暫し寄り道的なことを。秋になり気温が下がると「かつおぶし削り節(以後単にカツオ節もしくは削り節)」を買う。「削り節買う」はボクの秋の季語だ。今回は、東京都足立市場内の『伊勢重』という店で削りたてを買うことができた。ちなみに削り節は、基本冷蔵保存である。冷蔵庫が小さいので、保冷するものが多い夏の間は保管できない。だから夏は煮干し類一辺倒でだしをとる。ちなみに疲れているときはだしの素も使っているわけで、だしの素も嫌いではない、ということも忘れないで言っておく。 アカエイの郷土料理は数知れずあると思っている。とりあえず農文協の聞き書シリーズの料理をじょじょに作り始めている。三重県伊勢地方の「えいのどろぼう焼き」もそのひとつだ。伊勢地方(伊勢市)は巨大な伊勢湾の、南の端にあって、宮川、五十鈴川が流れ込み、豊かな干潟が広がっている。このような水域に多いのがアカエイである。この干潟のある水域は日本中にあり、多くが都市の前海なのである。だからアカエイは大量漁獲され、大量に食べられていたのだ。伊勢地方と古墳時代からの都である奈良県、大阪府との関わりが深い。そして有名な伊勢神宮がある。この地が大和王権と深く結びついたのは飛鳥地方と北緯が同じ位置にあり、古くから街道があったためである。奈良県の郷土料理にアカエイが登場するのも伊勢湾との繋がりを感じる。初夏に産卵のために浅瀬に来るアカエイで作る。ぶつ切りにして串焼きにし味噌をつけたもの。こんがり串焼きにして軟骨が香ばしい。〈泥をつけた棒ということで、料理の姿から名づけられたもの。〉『聞書き 三重の食事』(農山漁村文化協会)
アカエイの郷土料理は数知れずあると思っている。とりあえず農文協の聞き書シリーズの料理をじょじょに作り始めている。三重県伊勢地方の「えいのどろぼう焼き」もそのひとつだ。伊勢地方(伊勢市)は巨大な伊勢湾の、南の端にあって、宮川、五十鈴川が流れ込み、豊かな干潟が広がっている。このような水域に多いのがアカエイである。この干潟のある水域は日本中にあり、多くが都市の前海なのである。だからアカエイは大量漁獲され、大量に食べられていたのだ。伊勢地方と古墳時代からの都である奈良県、大阪府との関わりが深い。そして有名な伊勢神宮がある。この地が大和王権と深く結びついたのは飛鳥地方と北緯が同じ位置にあり、古くから街道があったためである。奈良県の郷土料理にアカエイが登場するのも伊勢湾との繋がりを感じる。初夏に産卵のために浅瀬に来るアカエイで作る。ぶつ切りにして串焼きにし味噌をつけたもの。こんがり串焼きにして軟骨が香ばしい。〈泥をつけた棒ということで、料理の姿から名づけられたもの。〉『聞書き 三重の食事』(農山漁村文化協会) これが三度目の「やっぎ」だ。漢字にすると「焼切」で、日本各地で作られている「焼き切り(焼き切れ)」と同じだ。前々回は市場流通してきたものを、買って2日目に作ったが、弾力がなく皮目の香ばしさが感じられなかった。これを小田原の活け締めで作ったら想像だにできなかった、まるで別物の料理となる。鹿児島県南さつま市笠沙周辺の郷土料理なので、当地でも、当然とれたばかりを料理しているはずなのだだ。だから人気があるのだろう。あえて言うと、とれたて、もしくはとれて翌日くらいのものを使ってを作らないと、作れないということがわかったことになる。今回のものは神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置で活け締めしていただいたもので、当日、夜に作ったのが「やっぎ」だ。口に含んだ途端、焼いた香りが口中に広がる。これが「やっぎ」の真骨頂だのだとわかる。アイゴの皮周辺の濃厚なうま味と、噛むとじわりと染み出てくる脂など他に類をみない。考えてみると「やっぎ」は噛む料理なのだなとわかってくる。漁師さんが輪になって食べるとき、口中にある時間が長い、それもいいところだろう。ちなみに普通の濃口醤油とわさびで食べたが、鹿児島の甘い醤油の方がよかったやも知れない。合わせたのは、ジンハイボールだ。
これが三度目の「やっぎ」だ。漢字にすると「焼切」で、日本各地で作られている「焼き切り(焼き切れ)」と同じだ。前々回は市場流通してきたものを、買って2日目に作ったが、弾力がなく皮目の香ばしさが感じられなかった。これを小田原の活け締めで作ったら想像だにできなかった、まるで別物の料理となる。鹿児島県南さつま市笠沙周辺の郷土料理なので、当地でも、当然とれたばかりを料理しているはずなのだだ。だから人気があるのだろう。あえて言うと、とれたて、もしくはとれて翌日くらいのものを使ってを作らないと、作れないということがわかったことになる。今回のものは神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置で活け締めしていただいたもので、当日、夜に作ったのが「やっぎ」だ。口に含んだ途端、焼いた香りが口中に広がる。これが「やっぎ」の真骨頂だのだとわかる。アイゴの皮周辺の濃厚なうま味と、噛むとじわりと染み出てくる脂など他に類をみない。考えてみると「やっぎ」は噛む料理なのだなとわかってくる。漁師さんが輪になって食べるとき、口中にある時間が長い、それもいいところだろう。ちなみに普通の濃口醤油とわさびで食べたが、鹿児島の甘い醤油の方がよかったやも知れない。合わせたのは、ジンハイボールだ。 三重県鳥羽市周辺、愛知県三河湾篠島に「にし汁(螺汁)」という郷土料理がある。この周辺だけではなく、国内各地に普通に見られる磯の小型の巻き貝である「にし」を使った、汁とも、なんとも、いえそうにない料理だ。今回は、三重県鳥羽市周辺で作られている「にし汁」を地元の方に聞いて作ってみた。思った以上に時間を要した末に出来上がったものはどろっとしたもので、決して見た目がいいとは言えそうにない。まずは汁を飲んでみる。中に混ざった「にし」の足(筋肉)の部分の部分に甘味があるものの、肝膵臓や生殖巣などが含まれる液状の部分が少々生臭い。しかも舌だけではなく、口の天井から脇、舌の裏側までぴりぴりする。今回使ったレイシガイは別名、「辛螺(からにし)」、「煙草螺(たばこにし)」というが、そんな呼び名通りの辛味というか、いがらっぽさがある。ちなみに汁と足に味があることはある。むしろ非常に豊かにあると言ってもいいだろう。ただし、おいしさ以前に刺激が口中から喉に移り、胃の腑に入ると、なんだか胃袋が熱っぽく感じられる。この口の中から胃袋にかけての刺激的な味がなかなか去ってくれない。汁だけで飲むよりも、と思ってご飯と一緒に食べたが、同じだった。食べた後、喉のあたりにいがらっぽさが強く残った。鳥羽に住んでいる人からも聞いたとおり、好きな人は好き、だめな人はなめるのもだめ、といったものだ。個人的には決して好きだとは言えそうにないが、地元の人と、もう一度試してみたい気もする。協力/出間リカさん(三重県鳥羽市)、岩尾豊紀さん(鳥羽市水産研究所)
三重県鳥羽市周辺、愛知県三河湾篠島に「にし汁(螺汁)」という郷土料理がある。この周辺だけではなく、国内各地に普通に見られる磯の小型の巻き貝である「にし」を使った、汁とも、なんとも、いえそうにない料理だ。今回は、三重県鳥羽市周辺で作られている「にし汁」を地元の方に聞いて作ってみた。思った以上に時間を要した末に出来上がったものはどろっとしたもので、決して見た目がいいとは言えそうにない。まずは汁を飲んでみる。中に混ざった「にし」の足(筋肉)の部分の部分に甘味があるものの、肝膵臓や生殖巣などが含まれる液状の部分が少々生臭い。しかも舌だけではなく、口の天井から脇、舌の裏側までぴりぴりする。今回使ったレイシガイは別名、「辛螺(からにし)」、「煙草螺(たばこにし)」というが、そんな呼び名通りの辛味というか、いがらっぽさがある。ちなみに汁と足に味があることはある。むしろ非常に豊かにあると言ってもいいだろう。ただし、おいしさ以前に刺激が口中から喉に移り、胃の腑に入ると、なんだか胃袋が熱っぽく感じられる。この口の中から胃袋にかけての刺激的な味がなかなか去ってくれない。汁だけで飲むよりも、と思ってご飯と一緒に食べたが、同じだった。食べた後、喉のあたりにいがらっぽさが強く残った。鳥羽に住んでいる人からも聞いたとおり、好きな人は好き、だめな人はなめるのもだめ、といったものだ。個人的には決して好きだとは言えそうにないが、地元の人と、もう一度試してみたい気もする。協力/出間リカさん(三重県鳥羽市)、岩尾豊紀さん(鳥羽市水産研究所) 北海道根室市、温根沼、春国岱などの干潟を行ったり来たり、底なし沼にはまって出られなくなったり、クマが近くで目撃されたり。波瀾万丈の時間を干潟で過ごした。少しは痩せられたかも、という以前に寒いのと疲れとで人事不省となる。さて、ここでいろんな方達に話を聞いた。なかでもビックリしたのが、アサリの刺身である。刺身以上のアサリの食べ方はない、という。この温根沼周辺はアマモが大量に生えていて水がとてもキレイなのである。東京湾や愛知県三河でもアサリはとれると思うけど、そのまま生で食べるなんて思いも寄らない。アサリの刺身は北海道東部にある汽水域の、郷土料理と考えるといいのかも。ここのアサリなら刺身にしてうまそうだ、と思うのは、周りに護岸がなく、人家がほとんどないためだ。
北海道根室市、温根沼、春国岱などの干潟を行ったり来たり、底なし沼にはまって出られなくなったり、クマが近くで目撃されたり。波瀾万丈の時間を干潟で過ごした。少しは痩せられたかも、という以前に寒いのと疲れとで人事不省となる。さて、ここでいろんな方達に話を聞いた。なかでもビックリしたのが、アサリの刺身である。刺身以上のアサリの食べ方はない、という。この温根沼周辺はアマモが大量に生えていて水がとてもキレイなのである。東京湾や愛知県三河でもアサリはとれると思うけど、そのまま生で食べるなんて思いも寄らない。アサリの刺身は北海道東部にある汽水域の、郷土料理と考えるといいのかも。ここのアサリなら刺身にしてうまそうだ、と思うのは、周りに護岸がなく、人家がほとんどないためだ。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。以上は以前書いた。さて、もらった目的は塩ゆでにしたいためだ。高知県で「ゆで節」、「煮節」などという。ボクの作り方は高知県中土佐町久礼の魚屋さんで教わったやり方である。作り方は非常に単純。今回は片身の血合い・腹骨周り・中骨、と片身を煮立った塩水の中で約8分くらいゆでる。完全に火を通すのがコツだ。久礼の人は一生懸命団扇で扇いで粗熱を取っていたという。ボクは扇風機で楽にやる。これを袋などに入れて冷蔵庫で完全に冷やし込む。煮節(塩ゆで)の完成である。カツオ節の工場などで作るなまり節とは別物で、もっと遙かに惣菜的なものだ。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。以上は以前書いた。さて、もらった目的は塩ゆでにしたいためだ。高知県で「ゆで節」、「煮節」などという。ボクの作り方は高知県中土佐町久礼の魚屋さんで教わったやり方である。作り方は非常に単純。今回は片身の血合い・腹骨周り・中骨、と片身を煮立った塩水の中で約8分くらいゆでる。完全に火を通すのがコツだ。久礼の人は一生懸命団扇で扇いで粗熱を取っていたという。ボクは扇風機で楽にやる。これを袋などに入れて冷蔵庫で完全に冷やし込む。煮節(塩ゆで)の完成である。カツオ節の工場などで作るなまり節とは別物で、もっと遙かに惣菜的なものだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。 高知県大月町はなんとしても再訪したい地ナンバーワンである。水産生物を人との関わりから調べている人間としては、ここほど興味深いところがあるとは思えない。2015年に行ったものの、ほとんど時間がなかったのが残念でならない。いくつかの貴重な話が聞取できたが、取り分け興味深かったのがニザダイの利用法である。大月町ではクロハゲという。道の駅大月というボクが道の駅ランキングをつけるとしたら第1位といった、最高の道の駅の魚売り場にたくさん並んでいた。気になったのが皮付きの「たたき」だ。ニザダイの皮はサンドペーパーのようで硬く、鱗は引くに引けない。皮がうまいという話は、同じニザダイ科のクロハギ属の話として、南半球の熱帯域で聞取している。これと同様のことが、この国の高知県でもありえるのか、知りたくて知りたくて身もだえるほどだ。とりあえずは、同じ物を作ってみるしかない。ちなみに今回のニザダイは活魚をしめて、帰宅後すぐに内臓を抜いたもので作っている。大月町でもニザダイは内臓を抜いた状態で売っている。道の駅で、この売り方が気にくわないという老人がいて、「クロハゲは臭い方がうまい」らしい。この世代的な嗜好の変化も面白いのである。余談になるが、本日で4日目になるが、刺身にして非常においしく、もちろん臭味はまったくない。
高知県大月町はなんとしても再訪したい地ナンバーワンである。水産生物を人との関わりから調べている人間としては、ここほど興味深いところがあるとは思えない。2015年に行ったものの、ほとんど時間がなかったのが残念でならない。いくつかの貴重な話が聞取できたが、取り分け興味深かったのがニザダイの利用法である。大月町ではクロハゲという。道の駅大月というボクが道の駅ランキングをつけるとしたら第1位といった、最高の道の駅の魚売り場にたくさん並んでいた。気になったのが皮付きの「たたき」だ。ニザダイの皮はサンドペーパーのようで硬く、鱗は引くに引けない。皮がうまいという話は、同じニザダイ科のクロハギ属の話として、南半球の熱帯域で聞取している。これと同様のことが、この国の高知県でもありえるのか、知りたくて知りたくて身もだえるほどだ。とりあえずは、同じ物を作ってみるしかない。ちなみに今回のニザダイは活魚をしめて、帰宅後すぐに内臓を抜いたもので作っている。大月町でもニザダイは内臓を抜いた状態で売っている。道の駅で、この売り方が気にくわないという老人がいて、「クロハゲは臭い方がうまい」らしい。この世代的な嗜好の変化も面白いのである。余談になるが、本日で4日目になるが、刺身にして非常においしく、もちろん臭味はまったくない。 琉球列島以南はいざしらず、日本列島でコイ食わぬところは少ない。食べない地区はあるが、例えば県とか、流域を考えるとコイは全国的な食い物と考えていい。一度食えばわかることだが、コイに恋するほどコイはうまい。この場合のコイはヤマトゴイとされる中国や台湾などから養殖用に輸入されて、大大的に養殖され、また野生化が進んだもののことだ。ヤマトゴイの由来は一説には奈良県大和郡山市で養殖用に作り出されたので、大和郡山の大和を冠したのだとされている。大和郡山は今では、観賞用の金魚で有名だが、古くは食用のコイやフナを養殖していたのだろう。この養殖されたヤマトゴイは冷蔵庫のない時代、貴重な保存しておける生きたたんぱく源だった。飛鳥時代・奈良時代を通して官人に対して動物たんぱくの供給はないに等しい。それに銭(平安前期までの銭は使える地域が非常に狭かったので、平安後期の銭とは別物)だが、銭でサケの干ものなど少ないながらたんぱく源を買い、また奈良盆地ではウナギ、コイ(在来種かも)などを含めて採取して食べていたのだろう。そうしないと、ヒトは生きていけない。コイはヒトが生きていくためにも需要だったはずである。このコイを食べる習慣のある地域を少しずつ探している。コイを食べる地域には供給地が存在する。群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の四県が接する水郷地帯を中心に放射線状にコイを食べる地域が広がる。だから関東平野のウナギ屋の多くがコイの洗いを出す。これをコイに最適な生息環境に広がるコイを食べる地域という。この四県が接する水郷地帯以上に関東での巨大な供給地が霞ヶ浦・利根川である。この平野型に対して山間部型がある。生産の場となっているのが山間地にある田であり、溜池であった。これを産業に進化させた地域が長野県佐久である。佐久のコイ養殖業者は生きたままのコイを長野県内だけではなく、軽井沢を越えて群馬県にまで売って歩いていたようである。だから群馬県松井田町の老人達は「佐久鯉」という言語を今でも使う。佐久は歴史的に見ても非常に重要な地といってもいい。ちなみに京料理が現在のように洗練されたのも、コイ・フナをはじめ琵琶湖の淡水生物があったからだ。さて、群馬県に行ったらコイを買わずには帰って来れない、と考えている。今回も筒切り1尾分ほかを買って来た。もう真子がついている。いつも館林市か板倉町で買っているが、この地では鱗を引くのが特徴だと思う。個人的には鱗付きのほうが好きだが、コイであるだけでありがたい。
琉球列島以南はいざしらず、日本列島でコイ食わぬところは少ない。食べない地区はあるが、例えば県とか、流域を考えるとコイは全国的な食い物と考えていい。一度食えばわかることだが、コイに恋するほどコイはうまい。この場合のコイはヤマトゴイとされる中国や台湾などから養殖用に輸入されて、大大的に養殖され、また野生化が進んだもののことだ。ヤマトゴイの由来は一説には奈良県大和郡山市で養殖用に作り出されたので、大和郡山の大和を冠したのだとされている。大和郡山は今では、観賞用の金魚で有名だが、古くは食用のコイやフナを養殖していたのだろう。この養殖されたヤマトゴイは冷蔵庫のない時代、貴重な保存しておける生きたたんぱく源だった。飛鳥時代・奈良時代を通して官人に対して動物たんぱくの供給はないに等しい。それに銭(平安前期までの銭は使える地域が非常に狭かったので、平安後期の銭とは別物)だが、銭でサケの干ものなど少ないながらたんぱく源を買い、また奈良盆地ではウナギ、コイ(在来種かも)などを含めて採取して食べていたのだろう。そうしないと、ヒトは生きていけない。コイはヒトが生きていくためにも需要だったはずである。このコイを食べる習慣のある地域を少しずつ探している。コイを食べる地域には供給地が存在する。群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の四県が接する水郷地帯を中心に放射線状にコイを食べる地域が広がる。だから関東平野のウナギ屋の多くがコイの洗いを出す。これをコイに最適な生息環境に広がるコイを食べる地域という。この四県が接する水郷地帯以上に関東での巨大な供給地が霞ヶ浦・利根川である。この平野型に対して山間部型がある。生産の場となっているのが山間地にある田であり、溜池であった。これを産業に進化させた地域が長野県佐久である。佐久のコイ養殖業者は生きたままのコイを長野県内だけではなく、軽井沢を越えて群馬県にまで売って歩いていたようである。だから群馬県松井田町の老人達は「佐久鯉」という言語を今でも使う。佐久は歴史的に見ても非常に重要な地といってもいい。ちなみに京料理が現在のように洗練されたのも、コイ・フナをはじめ琵琶湖の淡水生物があったからだ。さて、群馬県に行ったらコイを買わずには帰って来れない、と考えている。今回も筒切り1尾分ほかを買って来た。もう真子がついている。いつも館林市か板倉町で買っているが、この地では鱗を引くのが特徴だと思う。個人的には鱗付きのほうが好きだが、コイであるだけでありがたい。 魚のみそ汁はたぶん国内全域で作られていると思っている。特に漁師さんにとっては日常食に近いものだろう。そのせいか、漁師さんに「みそ汁を作りますか?」、「どんな魚で作りますか?」と聞いてもなかなか返事が返ってこない。魚のみそ汁はなかなか表舞台に出てこない地味な存在なのかも知れぬ。だが、みそ汁こそは、魚料理でもっとも優れているもののひとつなのだ。基本的に汁であるが、実は菜(さい)でもある。みそ汁を作ると、あとはご飯だけで一食になるし、満足感も得られる。しかも魚の可食部を無駄なく食べ尽くすことができる。重要な郷土料理なのだけど、先にも述べたようにあまりにも日常的なために、郷土料理として浮かび上がってこないのが残念でならない。沖縄のように食堂などで、汁以上に主菜ならクローズアップされるところだが、毎朝食べるとか、酒の友にするとかだと、作って食べていること自体に気がづかないのだと思う。長崎県平戸市度島の福畑敏光さんのお宅では、ホウボウのみそ汁をよく作るようだ。とすると平戸周辺でホウボウが昔からよく揚がっていた証拠にもなる。前海は岩と砂地が入り交じっているのかも知れない、などと想像するのも楽しい。作り方は聞くまでもないが、豆腐を加えるというので、豆腐入りホウボウのみそ汁を作ってみた。平戸は麦みそ圏なので近所で長崎県の麦みそを購う。わけぎが欲しかったのだが、東京では手に入れにくいので小ネギで代用する。
魚のみそ汁はたぶん国内全域で作られていると思っている。特に漁師さんにとっては日常食に近いものだろう。そのせいか、漁師さんに「みそ汁を作りますか?」、「どんな魚で作りますか?」と聞いてもなかなか返事が返ってこない。魚のみそ汁はなかなか表舞台に出てこない地味な存在なのかも知れぬ。だが、みそ汁こそは、魚料理でもっとも優れているもののひとつなのだ。基本的に汁であるが、実は菜(さい)でもある。みそ汁を作ると、あとはご飯だけで一食になるし、満足感も得られる。しかも魚の可食部を無駄なく食べ尽くすことができる。重要な郷土料理なのだけど、先にも述べたようにあまりにも日常的なために、郷土料理として浮かび上がってこないのが残念でならない。沖縄のように食堂などで、汁以上に主菜ならクローズアップされるところだが、毎朝食べるとか、酒の友にするとかだと、作って食べていること自体に気がづかないのだと思う。長崎県平戸市度島の福畑敏光さんのお宅では、ホウボウのみそ汁をよく作るようだ。とすると平戸周辺でホウボウが昔からよく揚がっていた証拠にもなる。前海は岩と砂地が入り交じっているのかも知れない、などと想像するのも楽しい。作り方は聞くまでもないが、豆腐を加えるというので、豆腐入りホウボウのみそ汁を作ってみた。平戸は麦みそ圏なので近所で長崎県の麦みそを購う。わけぎが欲しかったのだが、東京では手に入れにくいので小ネギで代用する。 15年前、午前3時の那覇市農連市場でおばあの朝ご飯を見せてもらった。沖縄らしい味つけした魚の天ぷらがタッパーに入っていて、何人かで分けて食べていた。うるま市の農連市場でも同じものを食べていたが、こちらは自家製ではなく市内の天ぷら店の天ぷらだった。魚の天ぷらならグルクン(タカサゴ)やグルクマー、キハダあたりかなと思ったら、意外すぎるものだったのでビックリした。サンマの天ぷらだったのだ。沖縄本島中のスーパーを片っ端に見て歩くと、確かに解凍サンマが普通に置いてある。総菜売り場にもサンマの天ぷらがあった。いかにも旅のもんですが、といった感じでサンマのことを聞いたら、島の魚よりも人気があり、天ぷらも作るという。サンマの不漁に「サンマが食べられなくなる」とこの国の人間は突然降って湧いたかのように宣い、テレビでも報道する。これには強い違和感を感じないではいられない。本来サンマを食べない地域にも売り込み、本来サンマ漁をやっていなかった臺灣にサンマ漁を導入させたのも、この国の仕業ではないのかな?漁業と自由主義経済は切り放して、厳格化しないとダメだと思うな。自由経済は明らかに破綻していて、ある意味、弁証法のように大きな視点で考えるときが来ていると思う。ちなみに我がサイトは多様な生物を多様な料理法で食べることが、自然には優しいということからはじまっている。そろそろ生きること、食べることは自然と直結することだと、思って欲しいものである。いろんな自然保護のイベントや活動をやって目立っている人達は無数にいるけど、この日常的なことをから自然を考えようと思っている人が少なすぎる。イベント的な自然保護活動は否定しないけど、日常的に自然保護を考える方が地球を救う効果は数十倍ある。
15年前、午前3時の那覇市農連市場でおばあの朝ご飯を見せてもらった。沖縄らしい味つけした魚の天ぷらがタッパーに入っていて、何人かで分けて食べていた。うるま市の農連市場でも同じものを食べていたが、こちらは自家製ではなく市内の天ぷら店の天ぷらだった。魚の天ぷらならグルクン(タカサゴ)やグルクマー、キハダあたりかなと思ったら、意外すぎるものだったのでビックリした。サンマの天ぷらだったのだ。沖縄本島中のスーパーを片っ端に見て歩くと、確かに解凍サンマが普通に置いてある。総菜売り場にもサンマの天ぷらがあった。いかにも旅のもんですが、といった感じでサンマのことを聞いたら、島の魚よりも人気があり、天ぷらも作るという。サンマの不漁に「サンマが食べられなくなる」とこの国の人間は突然降って湧いたかのように宣い、テレビでも報道する。これには強い違和感を感じないではいられない。本来サンマを食べない地域にも売り込み、本来サンマ漁をやっていなかった臺灣にサンマ漁を導入させたのも、この国の仕業ではないのかな?漁業と自由主義経済は切り放して、厳格化しないとダメだと思うな。自由経済は明らかに破綻していて、ある意味、弁証法のように大きな視点で考えるときが来ていると思う。ちなみに我がサイトは多様な生物を多様な料理法で食べることが、自然には優しいということからはじまっている。そろそろ生きること、食べることは自然と直結することだと、思って欲しいものである。いろんな自然保護のイベントや活動をやって目立っている人達は無数にいるけど、この日常的なことをから自然を考えようと思っている人が少なすぎる。イベント的な自然保護活動は否定しないけど、日常的に自然保護を考える方が地球を救う効果は数十倍ある。 「三平汁」は近世江戸時代に「にしん漁場」で作り始められたもの。ニシンの「塩漬け(魚自体も使うとは思うが現在の魚醬のようなものか)」と野菜を煮た汁のこと。「さんべ汁」、「さんぺ」、「まくり汁」、「かぼし汁」ともいうが、語源は不明であるようだ。三平という人物が存在して、おいしい汁を考え出したので、「三平汁」という説を聞いたことがあるが、なんら根拠はない。これが「塩漬けニシン」から「すしにしん(ニシンのぬか漬け)」に代わる。野菜はあり合わせのものでよく、ニシンの塩気があるので材料も少なくてすむ。非常に合理的なものである。古くは保存食である「塩漬けにしん」や「すしにしん」を使ったものが、鮮魚を使うようになる。今現在、「塩漬けにしん」は手に入らないので「すしにしん」で三平汁を作る。また魚は鮮魚も使うようになり、サケ、タラ類、メバル類など手に入るものはことごとく使っていたようである。参考/『聞書き 北海道の食事』(農文協)
「三平汁」は近世江戸時代に「にしん漁場」で作り始められたもの。ニシンの「塩漬け(魚自体も使うとは思うが現在の魚醬のようなものか)」と野菜を煮た汁のこと。「さんべ汁」、「さんぺ」、「まくり汁」、「かぼし汁」ともいうが、語源は不明であるようだ。三平という人物が存在して、おいしい汁を考え出したので、「三平汁」という説を聞いたことがあるが、なんら根拠はない。これが「塩漬けニシン」から「すしにしん(ニシンのぬか漬け)」に代わる。野菜はあり合わせのものでよく、ニシンの塩気があるので材料も少なくてすむ。非常に合理的なものである。古くは保存食である「塩漬けにしん」や「すしにしん」を使ったものが、鮮魚を使うようになる。今現在、「塩漬けにしん」は手に入らないので「すしにしん」で三平汁を作る。また魚は鮮魚も使うようになり、サケ、タラ類、メバル類など手に入るものはことごとく使っていたようである。参考/『聞書き 北海道の食事』(農文協) 関東で「ざっこ」、「ざこ」、「小魚」などと呼ばれているものをまとめる。同様のもので「もろこ」、「はや」があるが別項とする。関東で「ざっこ(雑魚)」はコイ目コイ科、十脚目テナガエビ科の淡水生物である。主流はモツゴとタモロコなどの小魚で、ここにスジエビ、テナガエビが混ざる。ともに淡水の比較的ながれのない水路や池(沼)、湖などに多い。例えば流れのあるところにいるウグイやオイカワなどは、関東では「ざっこ」には入らない。関東は平安時代から水田耕作も畑作も発達し、耕作地や住宅地域での土地開発が国内でももっとも進んだ地域である。鎌倉時代、室町時代、江戸時代と関東は政治的な中心地でもあった。ちなみに室町時代、政治の中心は京都にあったかのように見えるが、関東は明らかに独立国家であって、独立した政治が行われていた。時代が進むとともに土地改良が進み、水路や運河が発達する。この膨大に広がった水域である、用水路、水路、運河を住み家とするのがコイ科の小魚とテナガエビ科の小エビである。これをとる漁は今でも関東平野でほそぼそと続けられている。江戸時代の江戸御府内をはじめ関東平野全域に、たくさんの川と沼がある。今でも江戸時代葛飾であった東京都隅田川東岸、群馬県南部の埼玉県・栃木県茨城県にまたがる地域と、霞ヶ浦、北浦、手賀沼、印旛沼などは特に広い水域をもち、ときに水郷とさえ呼ばれている。関東平野は、もともと広大な水域を持っていた上に、より魚を取りやすい場所である水路が発達したために様々な水産加工品、料理が生まれる。江戸時代初期から大川河口域にある佃島で、江戸の猟師町で揚がった小魚類を煮上げて、浅草や日本橋の魚河岸などで商っていた。これで小魚類を醤油で煮たものを「佃煮」と呼ぶようになったとされる。今や「佃煮」は今や水産物を醤油で強く煮つめたものの総称になってさえもいる。ただ、佃島が関東で小魚を煮て食べた発祥の地とは思えない。この小魚を煮た「佃煮」を集めるとわかることだけど、関東平野は現在、「佃煮」と呼ばれる食品のもうひとつの発祥の地である可能性がある。「佃煮」を語るとき枕詞のように佃島が登場するのはいかがなものかと思うがどうだろう。ちなみに茨城県や利根川周辺に「煮干し」と呼ばれるものがある、汽水域、淡水域の生物を塩水で煮て、放冷したものである。こちらの方が歴史は古いと思っている。現在の「佃煮」は江戸初期は江戸府内だけのものだった可能性が高い。関東で醤油が手に入りやすくなった江戸時代中期以降に醤油味の煮物である「佃煮」が本当の意味で誕生したのだと思っている。さて、江戸(汽水域)を中心にした醤油味で小魚を煮たものと、関東平野のもの(汽水域と純淡水域)は歴史的にも原材料的にも入り混ざっていることも述べておかねばならない。
関東で「ざっこ」、「ざこ」、「小魚」などと呼ばれているものをまとめる。同様のもので「もろこ」、「はや」があるが別項とする。関東で「ざっこ(雑魚)」はコイ目コイ科、十脚目テナガエビ科の淡水生物である。主流はモツゴとタモロコなどの小魚で、ここにスジエビ、テナガエビが混ざる。ともに淡水の比較的ながれのない水路や池(沼)、湖などに多い。例えば流れのあるところにいるウグイやオイカワなどは、関東では「ざっこ」には入らない。関東は平安時代から水田耕作も畑作も発達し、耕作地や住宅地域での土地開発が国内でももっとも進んだ地域である。鎌倉時代、室町時代、江戸時代と関東は政治的な中心地でもあった。ちなみに室町時代、政治の中心は京都にあったかのように見えるが、関東は明らかに独立国家であって、独立した政治が行われていた。時代が進むとともに土地改良が進み、水路や運河が発達する。この膨大に広がった水域である、用水路、水路、運河を住み家とするのがコイ科の小魚とテナガエビ科の小エビである。これをとる漁は今でも関東平野でほそぼそと続けられている。江戸時代の江戸御府内をはじめ関東平野全域に、たくさんの川と沼がある。今でも江戸時代葛飾であった東京都隅田川東岸、群馬県南部の埼玉県・栃木県茨城県にまたがる地域と、霞ヶ浦、北浦、手賀沼、印旛沼などは特に広い水域をもち、ときに水郷とさえ呼ばれている。関東平野は、もともと広大な水域を持っていた上に、より魚を取りやすい場所である水路が発達したために様々な水産加工品、料理が生まれる。江戸時代初期から大川河口域にある佃島で、江戸の猟師町で揚がった小魚類を煮上げて、浅草や日本橋の魚河岸などで商っていた。これで小魚類を醤油で煮たものを「佃煮」と呼ぶようになったとされる。今や「佃煮」は今や水産物を醤油で強く煮つめたものの総称になってさえもいる。ただ、佃島が関東で小魚を煮て食べた発祥の地とは思えない。この小魚を煮た「佃煮」を集めるとわかることだけど、関東平野は現在、「佃煮」と呼ばれる食品のもうひとつの発祥の地である可能性がある。「佃煮」を語るとき枕詞のように佃島が登場するのはいかがなものかと思うがどうだろう。ちなみに茨城県や利根川周辺に「煮干し」と呼ばれるものがある、汽水域、淡水域の生物を塩水で煮て、放冷したものである。こちらの方が歴史は古いと思っている。現在の「佃煮」は江戸初期は江戸府内だけのものだった可能性が高い。関東で醤油が手に入りやすくなった江戸時代中期以降に醤油味の煮物である「佃煮」が本当の意味で誕生したのだと思っている。さて、江戸(汽水域)を中心にした醤油味で小魚を煮たものと、関東平野のもの(汽水域と純淡水域)は歴史的にも原材料的にも入り混ざっていることも述べておかねばならない。 鹿児島県川辺町(南九州市)で会った老人と宮崎県飫肥(日南市)の直売所で聞いた料理に「湯なます」がある。聞取ではイワシ(ウルメイワシかも)でもアジ(マアジ)、キビナゴでもいいので、大根と一緒に油で炒めて醤油・砂糖・酢で味つけする、という料理だった。料理法も油を使ってもいいし、ただ煮てもいいというので、帰宅して書籍で整理し直そうと思ったら意外にも情報がない。鹿児島の「湯なます」は知覧のものが『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている。大根やにんじんと塩いわしの筒切と油で炒めて、酢やみかん汁を加えるものや、完全に汁ものもある。宮崎県の「湯なます」は大根をせん切りにする。いりこを砕いたものと大根のせん切り、唐辛子を油で炒めて醤油と砂糖で味つけするというのがある。ここでは酢を加えていないが、編集時に書き落としたのではないかと考えている。『聞書き 宮崎の食事』(農文協)。また「湯なます」は「煮なます」と同じものであるとしている。両県ともに「湯なます」はアジ(マアジ)もしくはニシン目の魚であるキビナゴ、ウルメイワシやマイワシなどを使うこと。醤油・砂糖に必ず酢を加えることが基本のようである。写真は『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている汁ものの「煮なます」である。ここではマアジを使ったがイワシ(ウルメイワシなど)などでもいい。適当に切り、湯をかけてくさみを取る。冷水に落として汚れやぬめりを流す。適当に切り、だし・薄口醤油・みりんの中で大根とにんじんのせん切り、魚を煮る。仕上げに酢を加える。
鹿児島県川辺町(南九州市)で会った老人と宮崎県飫肥(日南市)の直売所で聞いた料理に「湯なます」がある。聞取ではイワシ(ウルメイワシかも)でもアジ(マアジ)、キビナゴでもいいので、大根と一緒に油で炒めて醤油・砂糖・酢で味つけする、という料理だった。料理法も油を使ってもいいし、ただ煮てもいいというので、帰宅して書籍で整理し直そうと思ったら意外にも情報がない。鹿児島の「湯なます」は知覧のものが『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている。大根やにんじんと塩いわしの筒切と油で炒めて、酢やみかん汁を加えるものや、完全に汁ものもある。宮崎県の「湯なます」は大根をせん切りにする。いりこを砕いたものと大根のせん切り、唐辛子を油で炒めて醤油と砂糖で味つけするというのがある。ここでは酢を加えていないが、編集時に書き落としたのではないかと考えている。『聞書き 宮崎の食事』(農文協)。また「湯なます」は「煮なます」と同じものであるとしている。両県ともに「湯なます」はアジ(マアジ)もしくはニシン目の魚であるキビナゴ、ウルメイワシやマイワシなどを使うこと。醤油・砂糖に必ず酢を加えることが基本のようである。写真は『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている汁ものの「煮なます」である。ここではマアジを使ったがイワシ(ウルメイワシなど)などでもいい。適当に切り、湯をかけてくさみを取る。冷水に落として汚れやぬめりを流す。適当に切り、だし・薄口醤油・みりんの中で大根とにんじんのせん切り、魚を煮る。仕上げに酢を加える。 「なます」は本膳料理(室町時代に生まれた武家の形式立てた料理の提供法)での小鉢などにもって提供するもので、火を通した素材を酢などで和えたもの。野菜だけのものを「膾」、魚を使ったものを「鱠」という漢字を当てる。島根県出雲地方の「煮なます」は「鱠」のひとつである。「煮なます」は島根県出雲地方の郷土料理だ。魚の内臓、魚を酢・酒・砂糖・醤油の味つけで大根とともに煮た料理である。宍道湖・中海の汽水域ではスズキ、ワカサギで作り、島根半島ではブリを使う。個人的にはこれほどうまい料理はないと思っている。スズキ・ブリの「煮なます」は身を使うのではなく内臓を使って作る。島根県出雲地方西部にはバショウカジキの内臓を使った料理もある。これと島根半島のブリのわたで作る、「煮なます」、宍道湖・中海のスズキの内臓で作る「煮なます」との関係も考えておくべきだろう。もともとは漁師料理なのかも知れない。ただそれだけでは地域的に広がる可能性は低い。宍道湖東部にある松江市は、城下町でもあり、商業や家内工業、水産業の町でもある。この汽水域に囲まれた町屋でもっともよく食べられたのがスズキであり、夏などは刺身に塩焼きにとよく食べられていた。ただし古くから白身魚は高級なもので、なかなか庶民の食卓に上るというものではなかった。そんな中、松江の町では日常的に内臓が安く売られていたのだと思っている。だからこそ生まれた料理なのではないだろうか。(写真はスズキで身は塩焼き、刺身などに内臓は別にして売られていた)宍道湖・中海で揚がるアマサギ(ワカサギ)を焼いたもので作った「煮なます」は、根菜類といい保存食で作れる便利な一品だったはずだ。宮崎県、鹿児島県には「湯なます」というものがある。基本的な料理法は魚と大根、にんじんなどの根菜類。油で魚以外の材料を炒り、魚を加えて醤油・砂糖・酒(本来は使わないのかも)で味つけするもの。水を加えて汁気を多めにした煮もの、水がたっぷりでなますというよりも汁といった方がいいようなものもある。宮崎県などでは「煮なます」という場合もあるようで、もともとは島根県の「煮なます」と同様の起源なのかもしれない。「なます」という言葉が指す料理は多様である。ほとんど刺身に近いもの、酢を使った和えもの、そして酢を使った煮ものも「なます」のひとつなのである。参考文献/『味のふるさと 17 島根の味』(角川書店 1978)、『聞書き 島根の食事』(農文協)、松江市、安来市では聞取もした。
「なます」は本膳料理(室町時代に生まれた武家の形式立てた料理の提供法)での小鉢などにもって提供するもので、火を通した素材を酢などで和えたもの。野菜だけのものを「膾」、魚を使ったものを「鱠」という漢字を当てる。島根県出雲地方の「煮なます」は「鱠」のひとつである。「煮なます」は島根県出雲地方の郷土料理だ。魚の内臓、魚を酢・酒・砂糖・醤油の味つけで大根とともに煮た料理である。宍道湖・中海の汽水域ではスズキ、ワカサギで作り、島根半島ではブリを使う。個人的にはこれほどうまい料理はないと思っている。スズキ・ブリの「煮なます」は身を使うのではなく内臓を使って作る。島根県出雲地方西部にはバショウカジキの内臓を使った料理もある。これと島根半島のブリのわたで作る、「煮なます」、宍道湖・中海のスズキの内臓で作る「煮なます」との関係も考えておくべきだろう。もともとは漁師料理なのかも知れない。ただそれだけでは地域的に広がる可能性は低い。宍道湖東部にある松江市は、城下町でもあり、商業や家内工業、水産業の町でもある。この汽水域に囲まれた町屋でもっともよく食べられたのがスズキであり、夏などは刺身に塩焼きにとよく食べられていた。ただし古くから白身魚は高級なもので、なかなか庶民の食卓に上るというものではなかった。そんな中、松江の町では日常的に内臓が安く売られていたのだと思っている。だからこそ生まれた料理なのではないだろうか。(写真はスズキで身は塩焼き、刺身などに内臓は別にして売られていた)宍道湖・中海で揚がるアマサギ(ワカサギ)を焼いたもので作った「煮なます」は、根菜類といい保存食で作れる便利な一品だったはずだ。宮崎県、鹿児島県には「湯なます」というものがある。基本的な料理法は魚と大根、にんじんなどの根菜類。油で魚以外の材料を炒り、魚を加えて醤油・砂糖・酒(本来は使わないのかも)で味つけするもの。水を加えて汁気を多めにした煮もの、水がたっぷりでなますというよりも汁といった方がいいようなものもある。宮崎県などでは「煮なます」という場合もあるようで、もともとは島根県の「煮なます」と同様の起源なのかもしれない。「なます」という言葉が指す料理は多様である。ほとんど刺身に近いもの、酢を使った和えもの、そして酢を使った煮ものも「なます」のひとつなのである。参考文献/『味のふるさと 17 島根の味』(角川書店 1978)、『聞書き 島根の食事』(農文協)、松江市、安来市では聞取もした。 石川県、福井県で作られている「塩いり」、「浜いり」は呼び名は違うが同じ調理法だ。「塩いり」は石川・福井両県でみられるもので、資料としても残っている。浜(漁港)でとれたばかりの魚の保存性を高めるために作られていたものと、家庭などで作られていたものに二分する。明らかに浜で生まれた料理が一般家庭にも広がったのだと考えている。料理店、一般家庭で作られているものは塩分濃度がとても低く、保存性も低い。「浜いり」という言語は今のところ、石川県加賀市塩屋でしか採取していない。強い塩水で水分を飛ばしながら火を通し、完全に水気をなくしたものだ。一般家庭で作っているという人には出会えていない。基本的に漁港周辺で作られる四十物で保存性を高めるために作られる。この四十物としての「塩いり」、「浜いり」は海から遠い地域へ送られたり、行商していたはずだが、このあたりの資料は見つかっていない。また新潟県から島根県にかけて浜焼きがある。こちらも山間部へ運ぶための四十物である。塩辛、塩漬け、ぬか漬けなどとともに、日本海で生まれた四十物のひとつが「塩いり」、「浜いり」なのだと思っている。同じような料理が鹿児島県奄美諸島、沖縄県にもある。「塩煮(まーす煮)」である。冷蔵庫のない時代にはいかに魚を長持ちさせるかが、もっとも重要なことであった。それが家庭料理にも浸透していくなど同じような広がり方をしている。
石川県、福井県で作られている「塩いり」、「浜いり」は呼び名は違うが同じ調理法だ。「塩いり」は石川・福井両県でみられるもので、資料としても残っている。浜(漁港)でとれたばかりの魚の保存性を高めるために作られていたものと、家庭などで作られていたものに二分する。明らかに浜で生まれた料理が一般家庭にも広がったのだと考えている。料理店、一般家庭で作られているものは塩分濃度がとても低く、保存性も低い。「浜いり」という言語は今のところ、石川県加賀市塩屋でしか採取していない。強い塩水で水分を飛ばしながら火を通し、完全に水気をなくしたものだ。一般家庭で作っているという人には出会えていない。基本的に漁港周辺で作られる四十物で保存性を高めるために作られる。この四十物としての「塩いり」、「浜いり」は海から遠い地域へ送られたり、行商していたはずだが、このあたりの資料は見つかっていない。また新潟県から島根県にかけて浜焼きがある。こちらも山間部へ運ぶための四十物である。塩辛、塩漬け、ぬか漬けなどとともに、日本海で生まれた四十物のひとつが「塩いり」、「浜いり」なのだと思っている。同じような料理が鹿児島県奄美諸島、沖縄県にもある。「塩煮(まーす煮)」である。冷蔵庫のない時代にはいかに魚を長持ちさせるかが、もっとも重要なことであった。それが家庭料理にも浸透していくなど同じような広がり方をしている。 兵庫県但馬地方の「じゃう」は魚を水洗いして適当に切り、野菜と一緒に煮て作る醤油味の煮もの、汁、もしくは鍋だ。1960年代以前の食生活を聞書いた、『聞き書 兵庫の食事』(農文協)にも1行ほど「さばのじゃう」が載っていて、写真を見る限りは煮ものそのものだ。合わせる野菜は聞取した限りではゴボウ、ネギが基本形であるようだ。これ一品を作るだけでおかずにもなり、汁にもなり、酒の肴にもなる。手間いらずな料理でもあるようだ。よく「じゃう」を「すき焼き」のことだとしている書があるが、たぶん間違いだと思う。獣肉などを少量の液体で調理するのが「すき焼き」で、「じゃう」は鍋にするにしても液体の量が多いのである。要するに知名度が上がり一人歩きしはじめた「すき焼き」という言葉を多くの地域でそれらしい料理に当てはめた。それをまた見識のない人が広めたのだと思う。実際、西日本の家庭で作られる「すき焼き」の多くが液体の多い醤油味の鍋である。料理名「じゃう」 同様の料理は日本各地にありそうである。大阪府のもっとも古い形の「うおすき」、滋賀県の「じゅんじゅん」、三重県尾鷲市の「じふ」、島根県石見地方の「煮食い(にぐい)」などだ。作り方などもそっくりなので魚がとれるところで自然発生的に生まれた可能性もある。醤油以前は「みそたまり(みそから染み出る液体)」で作った可能性が高いと考えられる。料理の理念 どの地方でも言えることだが、漁で揚がった売れないいろんな魚を使い作ること、また様々な作り方があることなども同じである。言うなれば魚を煮て食べるという単純な料理だから今に続いているのだ。このような売れない魚を使った料理は、例えばフランスのブイヤベース、イタリアのカッチュッコ、ロシアのウハーなどとも共通する。写真は鍋の「さばのじゃう」だ。昔、兵庫県の日本海側、但馬地方は国内屈指のマサバの産地であった。産地でもっともたくさんとれる魚を使うのが「じゃう」なのである。また鍋でもあるというのは寒い時季の料理だからだ。汁や煮ものよりも煮ながら食べる鍋の方が効率的だし、また家族が食べたいだけ食べられるなどの利点がある聞取した限りでは、日本海に面した但馬地方では、今現在も「山がれい(ヒレグロ)」、「はた(ハタハタ)」で作られているという。この2種は寒い時季にあるていどまとまってとれ、また「山がれい」の小型は売り物にならない魚の漁師さんの家庭での自家消費といえる。また国内で長年問題となっていたリジン欠乏症には特効薬的なものだったのではないか。当然優れた料理なので漁業のある海辺から、山間部への広がりもあったはずだ。
兵庫県但馬地方の「じゃう」は魚を水洗いして適当に切り、野菜と一緒に煮て作る醤油味の煮もの、汁、もしくは鍋だ。1960年代以前の食生活を聞書いた、『聞き書 兵庫の食事』(農文協)にも1行ほど「さばのじゃう」が載っていて、写真を見る限りは煮ものそのものだ。合わせる野菜は聞取した限りではゴボウ、ネギが基本形であるようだ。これ一品を作るだけでおかずにもなり、汁にもなり、酒の肴にもなる。手間いらずな料理でもあるようだ。よく「じゃう」を「すき焼き」のことだとしている書があるが、たぶん間違いだと思う。獣肉などを少量の液体で調理するのが「すき焼き」で、「じゃう」は鍋にするにしても液体の量が多いのである。要するに知名度が上がり一人歩きしはじめた「すき焼き」という言葉を多くの地域でそれらしい料理に当てはめた。それをまた見識のない人が広めたのだと思う。実際、西日本の家庭で作られる「すき焼き」の多くが液体の多い醤油味の鍋である。料理名「じゃう」 同様の料理は日本各地にありそうである。大阪府のもっとも古い形の「うおすき」、滋賀県の「じゅんじゅん」、三重県尾鷲市の「じふ」、島根県石見地方の「煮食い(にぐい)」などだ。作り方などもそっくりなので魚がとれるところで自然発生的に生まれた可能性もある。醤油以前は「みそたまり(みそから染み出る液体)」で作った可能性が高いと考えられる。料理の理念 どの地方でも言えることだが、漁で揚がった売れないいろんな魚を使い作ること、また様々な作り方があることなども同じである。言うなれば魚を煮て食べるという単純な料理だから今に続いているのだ。このような売れない魚を使った料理は、例えばフランスのブイヤベース、イタリアのカッチュッコ、ロシアのウハーなどとも共通する。写真は鍋の「さばのじゃう」だ。昔、兵庫県の日本海側、但馬地方は国内屈指のマサバの産地であった。産地でもっともたくさんとれる魚を使うのが「じゃう」なのである。また鍋でもあるというのは寒い時季の料理だからだ。汁や煮ものよりも煮ながら食べる鍋の方が効率的だし、また家族が食べたいだけ食べられるなどの利点がある聞取した限りでは、日本海に面した但馬地方では、今現在も「山がれい(ヒレグロ)」、「はた(ハタハタ)」で作られているという。この2種は寒い時季にあるていどまとまってとれ、また「山がれい」の小型は売り物にならない魚の漁師さんの家庭での自家消費といえる。また国内で長年問題となっていたリジン欠乏症には特効薬的なものだったのではないか。当然優れた料理なので漁業のある海辺から、山間部への広がりもあったはずだ。 船場とは大阪市中区の北は土佐堀川、南は長堀通、西は御堂筋、東は東横堀川までの広い地域のことだ。典型的な大阪といった場所で丼池の繊維街、薬を扱う道修町、証券会社の集まる北浜などがある。今でも上品な大阪言葉が残っていたりする場所で、今どきの大阪弁であるごっつい泥臭さとは無縁の地なのだ。この船場と言われるところを歩いてみたが往時の商人町の面影はほとんど残っていない。あえていえば北浜の適塾(幕末にあった緒方洪庵の医術塾)や古い薬問屋、丼池の繊維街の喧噪くらいかも知れない。大阪中心部のこのあたりは大商人の町なので、丁稚どんに番頭どん、などたくさんの働き手が暮らしていた。多くは共同生活、集団での食事である。大正時代、船場平野町の薬問屋、安田市兵衛商店で丁稚だった日本演劇界の巨人、菊田一夫は、食事も完全なる階級制であり、大番頭は畳敷きの場所で座って食事を摂り、中番頭以下は土間に沿った板の間で食べたという。菊田一夫は身長が低く、食べるのが遅かった。ゆっくり食べていると十分に食べられない。そこで編み出したのが汁と飯を熱々の状態でかき込むということだ。汁がおかずでもあった証拠といえるだろう。大阪の商人町の食事は極端に動物性たんぱくが少なかったようだ。そんな中でも登場回数の多かったのが塩サバだった。関西のマサバの供給地は日本海の北陸・山陰で、太平洋側では紀伊水道、熊野灘だった。これが大阪の地に送られて来ていたのだ。当時のマサバの流通は鮮魚もあっただろうが、ほとんどが塩蔵品、もしくは干ものだったと思われる。しかも今では考えられない程の塩分濃度の濃いもの。この体幹部分は焼き、あらの部分を大根とたいて作ったのが「船場汁」、「船場煮」だ。汁といっても大根を煮て、塩蔵サバのあらを入れるだけ。塩味は塩蔵サバから出るし、あら自体も塩辛い。厳しい商家の生活にはなくてはならなかったものだろう。寒い時季に食べるもので、ときには生(鮮魚)を使って作られることもあるという。また重要なのは「船場汁」というのは大阪市の言葉だということ。他の地域でも同じような料理が作られている可能性が高い。地元の料理は地元の言葉で作り、食べて欲しい。参考/『聞き書 大阪の食事』(農文協)、『船場道修町』(三島佑一 人文書院 1990)、『評伝 菊田一夫』(小幡欣治 岩波書店 2008)
船場とは大阪市中区の北は土佐堀川、南は長堀通、西は御堂筋、東は東横堀川までの広い地域のことだ。典型的な大阪といった場所で丼池の繊維街、薬を扱う道修町、証券会社の集まる北浜などがある。今でも上品な大阪言葉が残っていたりする場所で、今どきの大阪弁であるごっつい泥臭さとは無縁の地なのだ。この船場と言われるところを歩いてみたが往時の商人町の面影はほとんど残っていない。あえていえば北浜の適塾(幕末にあった緒方洪庵の医術塾)や古い薬問屋、丼池の繊維街の喧噪くらいかも知れない。大阪中心部のこのあたりは大商人の町なので、丁稚どんに番頭どん、などたくさんの働き手が暮らしていた。多くは共同生活、集団での食事である。大正時代、船場平野町の薬問屋、安田市兵衛商店で丁稚だった日本演劇界の巨人、菊田一夫は、食事も完全なる階級制であり、大番頭は畳敷きの場所で座って食事を摂り、中番頭以下は土間に沿った板の間で食べたという。菊田一夫は身長が低く、食べるのが遅かった。ゆっくり食べていると十分に食べられない。そこで編み出したのが汁と飯を熱々の状態でかき込むということだ。汁がおかずでもあった証拠といえるだろう。大阪の商人町の食事は極端に動物性たんぱくが少なかったようだ。そんな中でも登場回数の多かったのが塩サバだった。関西のマサバの供給地は日本海の北陸・山陰で、太平洋側では紀伊水道、熊野灘だった。これが大阪の地に送られて来ていたのだ。当時のマサバの流通は鮮魚もあっただろうが、ほとんどが塩蔵品、もしくは干ものだったと思われる。しかも今では考えられない程の塩分濃度の濃いもの。この体幹部分は焼き、あらの部分を大根とたいて作ったのが「船場汁」、「船場煮」だ。汁といっても大根を煮て、塩蔵サバのあらを入れるだけ。塩味は塩蔵サバから出るし、あら自体も塩辛い。厳しい商家の生活にはなくてはならなかったものだろう。寒い時季に食べるもので、ときには生(鮮魚)を使って作られることもあるという。また重要なのは「船場汁」というのは大阪市の言葉だということ。他の地域でも同じような料理が作られている可能性が高い。地元の料理は地元の言葉で作り、食べて欲しい。参考/『聞き書 大阪の食事』(農文協)、『船場道修町』(三島佑一 人文書院 1990)、『評伝 菊田一夫』(小幡欣治 岩波書店 2008) 岡山中央市場や書籍、また旧児島湾周辺で教わったものだ。要するに白身魚を使った、汁かけ飯である。いろいろ取材した限りでは岡山市、玉野市などでの家庭料理であるようだ。またげた(ウシノシタ類)やフナはミンチ状にしたものが市販されている。マゴチ、シロゴチ(ヨシノゴチ)、ボラ、げた(クロウシノシタ、イヌノシタ、アカシタビラメ)、フナなどを使う。ゆでてほぐした身か、ミンチ状にした生の身を、野菜と一緒に煮汁(ミンチの場合にはそのまま煮た汁)と一緒に汁にして醤油味をつけたもの。野菜はゴボウ、ニンジン、シイタケ、大根、青み(セリや三つ葉)などあるものでいい。あっさりとした味わいで、ご飯との相性が非常によい。
岡山中央市場や書籍、また旧児島湾周辺で教わったものだ。要するに白身魚を使った、汁かけ飯である。いろいろ取材した限りでは岡山市、玉野市などでの家庭料理であるようだ。またげた(ウシノシタ類)やフナはミンチ状にしたものが市販されている。マゴチ、シロゴチ(ヨシノゴチ)、ボラ、げた(クロウシノシタ、イヌノシタ、アカシタビラメ)、フナなどを使う。ゆでてほぐした身か、ミンチ状にした生の身を、野菜と一緒に煮汁(ミンチの場合にはそのまま煮た汁)と一緒に汁にして醤油味をつけたもの。野菜はゴボウ、ニンジン、シイタケ、大根、青み(セリや三つ葉)などあるものでいい。あっさりとした味わいで、ご飯との相性が非常によい。 山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる。東北や新潟県では大黒様が嫁を取りの日ともされており、「大黒様の嫁取り」、「大黒様の祝言」ともいう。大黒は豊穣の神として民間信仰の対象である。豆や豆腐、大根などには五穀豊穣・子孫繁栄を祈るという意味があるのだろう。ちなみに庄内地方の「まっか大根」は二股になった大根のことで、お供えにする。膳には主に豆料理と大根を使ったなます、そしてハタハタの田楽が並ぶ。スーパーなどには数日前から「ハタハタの田楽」と豆料理、また「大黒様のお年夜」用のセットが売られる。古くは家庭で作ったものかも知れないが、今では鮮魚店・スーパーなどで買うものとなっている。■左上から「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」、「黒豆煮」、中央中「黒豆のなます」、「豆腐の田楽」、下左「黒豆ごはん」、「納豆汁」。膳の右側にあるのが「こめいり(おこしともいう。これをを固めたもの、ばらのものもある)」。明らかに子孫繁栄をいのる祭事である。
山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる。東北や新潟県では大黒様が嫁を取りの日ともされており、「大黒様の嫁取り」、「大黒様の祝言」ともいう。大黒は豊穣の神として民間信仰の対象である。豆や豆腐、大根などには五穀豊穣・子孫繁栄を祈るという意味があるのだろう。ちなみに庄内地方の「まっか大根」は二股になった大根のことで、お供えにする。膳には主に豆料理と大根を使ったなます、そしてハタハタの田楽が並ぶ。スーパーなどには数日前から「ハタハタの田楽」と豆料理、また「大黒様のお年夜」用のセットが売られる。古くは家庭で作ったものかも知れないが、今では鮮魚店・スーパーなどで買うものとなっている。■左上から「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」、「黒豆煮」、中央中「黒豆のなます」、「豆腐の田楽」、下左「黒豆ごはん」、「納豆汁」。膳の右側にあるのが「こめいり(おこしともいう。これをを固めたもの、ばらのものもある)」。明らかに子孫繁栄をいのる祭事である。 長崎県平戸市度島で作られている。ムツやクサビ(アカササノハベラもしくはササノハベラ属)を水洗いして素焼きにする。ほぐして硬い骨(中骨)を取りみそと混ぜる。これでご飯を食べたり、お握りの具にも入れたりする。酒の肴にもなる。また高知県の「やえこ」のように焼いてもおいしい。ムツは幼魚で十分。大きさにばらつきがあり、また数尾しかいないときでもいい。また小サバ類などと一緒になっているときは数種類の魚と一緒にして作ってもいい。ここでは長崎県雲仙市ヤマト醤油の麦みそを使ったが、どのようなものでもいい。麦みそは独特の香ばしさがあり、塩分が少ない。関東などのみそを使うときは砂糖を加えてもいいだろう。[福畑光敏さん 長崎県平戸市度島]
長崎県平戸市度島で作られている。ムツやクサビ(アカササノハベラもしくはササノハベラ属)を水洗いして素焼きにする。ほぐして硬い骨(中骨)を取りみそと混ぜる。これでご飯を食べたり、お握りの具にも入れたりする。酒の肴にもなる。また高知県の「やえこ」のように焼いてもおいしい。ムツは幼魚で十分。大きさにばらつきがあり、また数尾しかいないときでもいい。また小サバ類などと一緒になっているときは数種類の魚と一緒にして作ってもいい。ここでは長崎県雲仙市ヤマト醤油の麦みそを使ったが、どのようなものでもいい。麦みそは独特の香ばしさがあり、塩分が少ない。関東などのみそを使うときは砂糖を加えてもいいだろう。[福畑光敏さん 長崎県平戸市度島] 「ゆで捨て」は長崎県雲仙市富津、佐藤厚さんに教わった魚の調理法である。マサバやマダイなどを適当に切り、強めの塩をして寝かせておく。塩が馴染んだところで多めの真水で均等に火が通るまでゆでて、ゆで汁は捨てる。素材は下ごしらえで水洗いして塩さえしておけば保存性が高くなり、食べる直前にゆでるだけで出来上がる。鮮魚ではなく塩サバで作ってもおいしい。この強い塩をしておき、食べるときにゆでるものを雲仙市の隣諫早市などでは「ゆでもの(さばのゆでもの)」ともいう。定番素材のマサバでやってみたら非常においしい。柑橘類をかけて食べるとまた一層うまい。オリーブオイルやスパイスを利かせても、マヨネーズ、酢コチュジャンなどもいいと思う。今の暮らしにマッチした料理である。液体(水)と塩を使って魚に火を通す料理法は日本各地に様々な調理法があり、各地に様々な名称がある。例を挙げないとわかりにくいのでいくつか挙げると。例えば北海道などの「湯あげ」、山形県などの「湯煮」は塩水でゆっくり、魚自体のエキスが煮汁に出てしまわないように煮る。石川県・福井県などの「浜いり」、「塩いり」、沖縄県の「まーす煮」は少量の強い塩水で短時間で煮上げるもので、もともとは保存性を高めるための調理法だ。これらは少、あまりにも在り来たりな料理法なので料理名のない地域も多そうである。すべて日本料理の基本的なものだが、日本各地で様々な魚が使われ、その魚にあった火の通し方、塩分添加の仕方がある。我がサイトではこれらを「水と塩だけの料理」として紹介していく。
「ゆで捨て」は長崎県雲仙市富津、佐藤厚さんに教わった魚の調理法である。マサバやマダイなどを適当に切り、強めの塩をして寝かせておく。塩が馴染んだところで多めの真水で均等に火が通るまでゆでて、ゆで汁は捨てる。素材は下ごしらえで水洗いして塩さえしておけば保存性が高くなり、食べる直前にゆでるだけで出来上がる。鮮魚ではなく塩サバで作ってもおいしい。この強い塩をしておき、食べるときにゆでるものを雲仙市の隣諫早市などでは「ゆでもの(さばのゆでもの)」ともいう。定番素材のマサバでやってみたら非常においしい。柑橘類をかけて食べるとまた一層うまい。オリーブオイルやスパイスを利かせても、マヨネーズ、酢コチュジャンなどもいいと思う。今の暮らしにマッチした料理である。液体(水)と塩を使って魚に火を通す料理法は日本各地に様々な調理法があり、各地に様々な名称がある。例を挙げないとわかりにくいのでいくつか挙げると。例えば北海道などの「湯あげ」、山形県などの「湯煮」は塩水でゆっくり、魚自体のエキスが煮汁に出てしまわないように煮る。石川県・福井県などの「浜いり」、「塩いり」、沖縄県の「まーす煮」は少量の強い塩水で短時間で煮上げるもので、もともとは保存性を高めるための調理法だ。これらは少、あまりにも在り来たりな料理法なので料理名のない地域も多そうである。すべて日本料理の基本的なものだが、日本各地で様々な魚が使われ、その魚にあった火の通し方、塩分添加の仕方がある。我がサイトではこれらを「水と塩だけの料理」として紹介していく。 「しもつかれ」は初午前日に作る稲荷神への供えるもののひとつ。本来、旧暦の2月(新暦の3月)の最初の午の日のために作るものだ。赤飯と一緒にして稲荷神社に、稲荷様に供えるのが基本である。ただし現在ではほとんどの地域で新暦の2月に作られている。古くは春の行事であったものが、新暦になって厳冬期の行事になったことがわかる。ちなみに今でも初午の行事を旧暦で行う地域もある。基本的な作り方は塩サケの頭(地域によっては塩マスの頭)を煮るか焼くかする。これをほぐして、酒粕・鬼下ろしで下ろした大根、大豆、にんじん、油揚げと煮て作る。これを初午の日に稲荷神社、稲荷の祠に供える。例を挙げると、那須塩原市西那須野町には〈二月の午の日(初午)には鳥ヶ森のお稲荷さんにおまいりして、五色の神と、わらつとに赤飯としもつかれを入れたものを供え、農産物の豊作祈願をする〉。もっとも広域で作っている栃木県で「しもつかれ」という。福島県南会津地方、群馬県、茨城県、埼玉県の広い地域で作られている料理で、「しみつかれ」、「すみつかり」、「すみつかれ」、「すみずかり」、「つむづかり」ともいう。ちなみに栃木県などで「霜疲れ」という漢字を当てているが、春のものだとすると疑問だ。稲荷と初午というと、稲荷の総本宮である京都伏見稲荷の創建時(711)の伝説に稲荷山の三ヶ峰に稲荷神が降りてきたのが、初午の日に当たり、同社では大祭が行われる。この「稲荷と初午」の話が、稲荷神社と稲荷の祠と一緒に日本各地に伝わったのだと考えている。稲荷神社は日本各地に膨大にあり、祠(小さな社)を含めると数え切れないほどだ。百済の帰化氏族である秦氏の創建した社であることから、「稲荷と初午」に関しては朝鮮半島との結びつきも考えるべきだ。「しもつかれ」群という料理の起源や呼び名の意味は鎌倉時代、平安時代にまでたどれるようだ。〈『宇治拾物語』(源隆国/正二位まで上りつめた公卿。鎌倉時代前期、1221-1221)の「慈恵僧正戒壇築たる事」に「すむつかり」があって〈大豆を煎って酢をかけたもの。酢をかけると大豆に皺が寄って箸で挟みやすくなる。これを子どもがむずがって顔をくしゃくしゃにしているようだというので、「酢憤(すむつか)り」という〉という話が出ている。慈恵僧正は良源といい天台座主だ。とすると、似たような料理は平安時代の京にまで遡れる可能性が高い。『たべもの史話』(鈴木晋一 平凡社)料理法の期限は古く、平安時代の京に起源があるとしても、関東での分布域を見ると利根川水系とその周辺域に多いことがわかる。水系に当たらない栃木県大田原市、那須塩原市、湯西川などは利根川水系から伝播したものだろう。福島県南会津町旧舘岩村・伊南村・南郷村は栃木県へ出稼ぎに行った人がもたらしたものだという。福島県南会津地方、関東の栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県で初午、もしくは二の午の前日に作る。多くの地域で、初午の日(今は新暦の2月の最初の午の日だが、本来は旧暦なので新暦だと3月初旬)にわらづとなどにくるみ稲荷神に奉る。■写真は福島県南会津町の稲荷の祠に供えられた、「つむずかり」。
「しもつかれ」は初午前日に作る稲荷神への供えるもののひとつ。本来、旧暦の2月(新暦の3月)の最初の午の日のために作るものだ。赤飯と一緒にして稲荷神社に、稲荷様に供えるのが基本である。ただし現在ではほとんどの地域で新暦の2月に作られている。古くは春の行事であったものが、新暦になって厳冬期の行事になったことがわかる。ちなみに今でも初午の行事を旧暦で行う地域もある。基本的な作り方は塩サケの頭(地域によっては塩マスの頭)を煮るか焼くかする。これをほぐして、酒粕・鬼下ろしで下ろした大根、大豆、にんじん、油揚げと煮て作る。これを初午の日に稲荷神社、稲荷の祠に供える。例を挙げると、那須塩原市西那須野町には〈二月の午の日(初午)には鳥ヶ森のお稲荷さんにおまいりして、五色の神と、わらつとに赤飯としもつかれを入れたものを供え、農産物の豊作祈願をする〉。もっとも広域で作っている栃木県で「しもつかれ」という。福島県南会津地方、群馬県、茨城県、埼玉県の広い地域で作られている料理で、「しみつかれ」、「すみつかり」、「すみつかれ」、「すみずかり」、「つむづかり」ともいう。ちなみに栃木県などで「霜疲れ」という漢字を当てているが、春のものだとすると疑問だ。稲荷と初午というと、稲荷の総本宮である京都伏見稲荷の創建時(711)の伝説に稲荷山の三ヶ峰に稲荷神が降りてきたのが、初午の日に当たり、同社では大祭が行われる。この「稲荷と初午」の話が、稲荷神社と稲荷の祠と一緒に日本各地に伝わったのだと考えている。稲荷神社は日本各地に膨大にあり、祠(小さな社)を含めると数え切れないほどだ。百済の帰化氏族である秦氏の創建した社であることから、「稲荷と初午」に関しては朝鮮半島との結びつきも考えるべきだ。「しもつかれ」群という料理の起源や呼び名の意味は鎌倉時代、平安時代にまでたどれるようだ。〈『宇治拾物語』(源隆国/正二位まで上りつめた公卿。鎌倉時代前期、1221-1221)の「慈恵僧正戒壇築たる事」に「すむつかり」があって〈大豆を煎って酢をかけたもの。酢をかけると大豆に皺が寄って箸で挟みやすくなる。これを子どもがむずがって顔をくしゃくしゃにしているようだというので、「酢憤(すむつか)り」という〉という話が出ている。慈恵僧正は良源といい天台座主だ。とすると、似たような料理は平安時代の京にまで遡れる可能性が高い。『たべもの史話』(鈴木晋一 平凡社)料理法の期限は古く、平安時代の京に起源があるとしても、関東での分布域を見ると利根川水系とその周辺域に多いことがわかる。水系に当たらない栃木県大田原市、那須塩原市、湯西川などは利根川水系から伝播したものだろう。福島県南会津町旧舘岩村・伊南村・南郷村は栃木県へ出稼ぎに行った人がもたらしたものだという。福島県南会津地方、関東の栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県で初午、もしくは二の午の前日に作る。多くの地域で、初午の日(今は新暦の2月の最初の午の日だが、本来は旧暦なので新暦だと3月初旬)にわらづとなどにくるみ稲荷神に奉る。■写真は福島県南会津町の稲荷の祠に供えられた、「つむずかり」。 熱帯域で揚がる魚のもっとも一般的な料理法は素揚げである。国内でのように片栗粉や小麦粉を使って揚げることはなく、塩コショウするだけで揚げて、柑橘類などをふって食べている。主食はタロイモやキャッサバなどだ。沖縄県の浅海で揚がる魚は基本的にたんぱくな白身魚であることが多い。沖縄の競り場などに来ていた方達に聞く限り、この淡泊さを補うために沖縄県でも揚げることが多かったようだ。今でもウミンチュ(潜水漁師)などは魚を素揚げにしてよく食べるようだ。
熱帯域で揚がる魚のもっとも一般的な料理法は素揚げである。国内でのように片栗粉や小麦粉を使って揚げることはなく、塩コショウするだけで揚げて、柑橘類などをふって食べている。主食はタロイモやキャッサバなどだ。沖縄県の浅海で揚がる魚は基本的にたんぱくな白身魚であることが多い。沖縄の競り場などに来ていた方達に聞く限り、この淡泊さを補うために沖縄県でも揚げることが多かったようだ。今でもウミンチュ(潜水漁師)などは魚を素揚げにしてよく食べるようだ。 深川というのは東京都江東区の深川八幡宮あたり。隅田川の東、深川には遊廓や有名な神社お寺があり、「深川八景」といわれる名所であった。その深川を冠した名物が「深川飯」である。深川には猟師町も魚河岸もあり、江戸前の魚と密接な関係にあった。内房からの貝類やイカタコ、魚などの集積地であったのかも知れない。江戸時代から1945年の戦前くらいまで江戸の町(東京)ではバカガイ(青柳)、ハマグリ、アサリなどの剥き身が売られていた。二枚貝で殻付きのまま売られていたのは、汽水域でとれたシジミ(ヤマトシジミ)だけだった可能性もある。深川周辺でもアサリなどがとれていたものの、主体は千葉県浦安・船橋などから小名木川、仙台堀川などを船でやってきていたものの方が多かったはずだ。バカガイは殻付きで運ぶのがアサリと比べると難しい。それで剥き身にしたのはわかる。でアサリ、ハマグリまで剥き身にするのはなぜだろう。流通の主体が堀という今の高速道路のようなものを使った時代、物理的な理由かも知れない。貝の剥き身をつかった、みそ仕立ての「ぶっかけ飯」を安いのもあって日常的に食べていた。これを「深川飯」と呼んだのは後のことだと思っている。初期にはバカガイの剥き身を使ったとも言う。これがアサリやハマグリも使われるようになり、明治後期には安食堂のメニューとしても定着していたようだ。本来は剥き身の、みそ汁かけご飯であったものが、大根やごぼう、油揚げをくわえた炊き込みご飯の「深川飯」となる。また、炊き込みご飯も「深川飯」と呼ぶことががある。『たべもの語源辞典』(清水桂一 東京堂出版)/『聞き書き 東京の食事』(農文協)他を参考としました
深川というのは東京都江東区の深川八幡宮あたり。隅田川の東、深川には遊廓や有名な神社お寺があり、「深川八景」といわれる名所であった。その深川を冠した名物が「深川飯」である。深川には猟師町も魚河岸もあり、江戸前の魚と密接な関係にあった。内房からの貝類やイカタコ、魚などの集積地であったのかも知れない。江戸時代から1945年の戦前くらいまで江戸の町(東京)ではバカガイ(青柳)、ハマグリ、アサリなどの剥き身が売られていた。二枚貝で殻付きのまま売られていたのは、汽水域でとれたシジミ(ヤマトシジミ)だけだった可能性もある。深川周辺でもアサリなどがとれていたものの、主体は千葉県浦安・船橋などから小名木川、仙台堀川などを船でやってきていたものの方が多かったはずだ。バカガイは殻付きで運ぶのがアサリと比べると難しい。それで剥き身にしたのはわかる。でアサリ、ハマグリまで剥き身にするのはなぜだろう。流通の主体が堀という今の高速道路のようなものを使った時代、物理的な理由かも知れない。貝の剥き身をつかった、みそ仕立ての「ぶっかけ飯」を安いのもあって日常的に食べていた。これを「深川飯」と呼んだのは後のことだと思っている。初期にはバカガイの剥き身を使ったとも言う。これがアサリやハマグリも使われるようになり、明治後期には安食堂のメニューとしても定着していたようだ。本来は剥き身の、みそ汁かけご飯であったものが、大根やごぼう、油揚げをくわえた炊き込みご飯の「深川飯」となる。また、炊き込みご飯も「深川飯」と呼ぶことががある。『たべもの語源辞典』(清水桂一 東京堂出版)/『聞き書き 東京の食事』(農文協)他を参考としました 鹿児島県屋久島で「もみこみ」、種子島で「つかまぜ」、「つかんまぜ」という料理がある。屋久島内でも他に呼び名があるかもしれないし、種子島で同じ雑貨店のご夫婦でも音が微妙に違っていた。鹿児島県川辺町でも同様の料理を作っている人に会っている。鹿児島県内だけではなくもっと広い地域で同じような料理が作られているとも思うので、同様の料理の呼び名も採取しないとだめだ。これが漁師さんが作り始めたものだとすると、言語的にも作っている地域もかなり広い可能性がある。「つき」という大根おろしを粗いケンにする道具と、料理法の広がりも重要だと思う。このような日常的な料理に名前がない、もしくはあっても消えてしまっていることが多いので、できるだけ早く言語を記録すべきだと思う。今回は「もみこみ」、「つかんまぜ」という言語を使ったが、土地土地で呼び名が違う可能性が高い。無闇に1つの呼び名を使っては絶対にいけない。特に民俗学や郷土料理を研究している人間は慎重に採取すべきだと思う。1つの言語が一人歩きすることを言語の癌化と我がサイトでは定義している。同様の料理法がお住まいの周辺にあるなら教えて頂きたい。
鹿児島県屋久島で「もみこみ」、種子島で「つかまぜ」、「つかんまぜ」という料理がある。屋久島内でも他に呼び名があるかもしれないし、種子島で同じ雑貨店のご夫婦でも音が微妙に違っていた。鹿児島県川辺町でも同様の料理を作っている人に会っている。鹿児島県内だけではなくもっと広い地域で同じような料理が作られているとも思うので、同様の料理の呼び名も採取しないとだめだ。これが漁師さんが作り始めたものだとすると、言語的にも作っている地域もかなり広い可能性がある。「つき」という大根おろしを粗いケンにする道具と、料理法の広がりも重要だと思う。このような日常的な料理に名前がない、もしくはあっても消えてしまっていることが多いので、できるだけ早く言語を記録すべきだと思う。今回は「もみこみ」、「つかんまぜ」という言語を使ったが、土地土地で呼び名が違う可能性が高い。無闇に1つの呼び名を使っては絶対にいけない。特に民俗学や郷土料理を研究している人間は慎重に採取すべきだと思う。1つの言語が一人歩きすることを言語の癌化と我がサイトでは定義している。同様の料理法がお住まいの周辺にあるなら教えて頂きたい。 沖縄県でカツオを「カチュウ」、「カッチウ」、「カチュー」と呼ぶ。これに「汁」をつけるとカツオ節に熱湯を注いだだけで作る簡便な汁ということになる。日常的にも作ったし、病、特に風邪のときなどにも作ったという。調味料はみそ、もしくはしょうゆだ。どうやらどちらでもいい。沖縄県では古くからカツオ節、なまり節を作っている。その起源はいずこにあるのかは不明だ。モルジブなどでもハガツオを使ったカツオ節がある。この年間を通してカツオ節に最適な脂のないカツオがとれる地域(熱帯・亜熱帯)がカツオ節(なまり節)誕生の地なのかも知れない。カツオ節、なまり節は沖縄県の家庭では必需品だった。常にあるものを使って即席で食べることができる。当然、どこの家庭でも作られているという沖縄の伝統料理である。
沖縄県でカツオを「カチュウ」、「カッチウ」、「カチュー」と呼ぶ。これに「汁」をつけるとカツオ節に熱湯を注いだだけで作る簡便な汁ということになる。日常的にも作ったし、病、特に風邪のときなどにも作ったという。調味料はみそ、もしくはしょうゆだ。どうやらどちらでもいい。沖縄県では古くからカツオ節、なまり節を作っている。その起源はいずこにあるのかは不明だ。モルジブなどでもハガツオを使ったカツオ節がある。この年間を通してカツオ節に最適な脂のないカツオがとれる地域(熱帯・亜熱帯)がカツオ節(なまり節)誕生の地なのかも知れない。カツオ節、なまり節は沖縄県の家庭では必需品だった。常にあるものを使って即席で食べることができる。当然、どこの家庭でも作られているという沖縄の伝統料理である。 宮本常一が昭和17年12月(1942)に能登一宮の気多神社(石川県羽咋市寺)で行われる鵜祭の、ウをとる村(現七尾市鵜浦)まで行く。そこで作られていたのが「タラ飯」である。富山湾はすり鉢状の地形で、浜から鱈場(深場)までの距離が短い。またタラ科のスケトウダラ、マダラは産卵期が近づき、浅場に上がってきている。動力船のない江戸時代以前にもタラをとるのが容易であったので、タラを食べる文化が発達したとされ、今でもタラの加工をする会社が少なくないとされている。「魚食の民」などという言葉が一人歩きしているが、この国は決して「魚食」でも「米食」でもなく、20世紀になるまで手に入れやすい食料を、ひたすら食べていたに過ぎない。例えば「おかず」という概念すら、都市部ではあったかも知れないが地方にはなかった可能性がある。タラ飯はタラ科の魚の「炊き込みご飯」でもなく、「まぜご飯」でもない。タラの身をひたすらご飯のごとく食べるというものだ。魚の身だけで腹を満たしても、糖質はほとんどなく、タンパク質だけの食事。塩味がついていることだけが救いだけど、おかず(副菜)もなく、とても現代に生きる身には食べにくいものだろうと考えていた。ところが実際に作ってみると、とてもおいしい。椀に1ぱいくらいならときどき作ってもいい、と思えるほどだった。ただこれが寒い時季の主食で、ごちそうであるとしたら寂しい限りだ。
宮本常一が昭和17年12月(1942)に能登一宮の気多神社(石川県羽咋市寺)で行われる鵜祭の、ウをとる村(現七尾市鵜浦)まで行く。そこで作られていたのが「タラ飯」である。富山湾はすり鉢状の地形で、浜から鱈場(深場)までの距離が短い。またタラ科のスケトウダラ、マダラは産卵期が近づき、浅場に上がってきている。動力船のない江戸時代以前にもタラをとるのが容易であったので、タラを食べる文化が発達したとされ、今でもタラの加工をする会社が少なくないとされている。「魚食の民」などという言葉が一人歩きしているが、この国は決して「魚食」でも「米食」でもなく、20世紀になるまで手に入れやすい食料を、ひたすら食べていたに過ぎない。例えば「おかず」という概念すら、都市部ではあったかも知れないが地方にはなかった可能性がある。タラ飯はタラ科の魚の「炊き込みご飯」でもなく、「まぜご飯」でもない。タラの身をひたすらご飯のごとく食べるというものだ。魚の身だけで腹を満たしても、糖質はほとんどなく、タンパク質だけの食事。塩味がついていることだけが救いだけど、おかず(副菜)もなく、とても現代に生きる身には食べにくいものだろうと考えていた。ところが実際に作ってみると、とてもおいしい。椀に1ぱいくらいならときどき作ってもいい、と思えるほどだった。ただこれが寒い時季の主食で、ごちそうであるとしたら寂しい限りだ。 昔、東京市場築地場内の老人が、「エイの煮凝りで飯食うのがいちばんだね」と言った。実は医者に酒を止められた人が、「代わりに飯だ」ということで、たらこ、アジの塩焼き、ちりめんなどご飯に合う水産物の話をしていたのである。確かに、煮つけ自体よりも翌日の煮凝りという人は多い。アカエイの場合、ゼラチン質が多いのでさほど気温が低くなくても、煮こごる。老人達のひとりが井戸に吊して置いたと言ったが、この景色がいいと思ったものだ。井戸に吊した煮凝りで、朝、飯を丼で、なんて最高かも知れない。実際今でも煮凝りでご飯は、糖質制限をしている身には毒である。
昔、東京市場築地場内の老人が、「エイの煮凝りで飯食うのがいちばんだね」と言った。実は医者に酒を止められた人が、「代わりに飯だ」ということで、たらこ、アジの塩焼き、ちりめんなどご飯に合う水産物の話をしていたのである。確かに、煮つけ自体よりも翌日の煮凝りという人は多い。アカエイの場合、ゼラチン質が多いのでさほど気温が低くなくても、煮こごる。老人達のひとりが井戸に吊して置いたと言ったが、この景色がいいと思ったものだ。井戸に吊した煮凝りで、朝、飯を丼で、なんて最高かも知れない。実際今でも煮凝りでご飯は、糖質制限をしている身には毒である。 2017年12月08日、宮城県栗原市若柳にある『くりでん』という産直市場で見つけたもの。輸入ものの小エビではなくスジエビもしくはテナガエビをしょうゆ味で煮て餅にからめている。隣の登米市でも同じ物が売られていた。この周辺には伊豆沼、長沼と白鳥が飛来する湖沼、また河川の多いところ。淡水漁業が盛んだったはず。ドジョウを焼いて餅にからめた「ふすべ餅」も同様に淡水漁業の産物である。この地域で行われていた淡水漁業を探りたい。
2017年12月08日、宮城県栗原市若柳にある『くりでん』という産直市場で見つけたもの。輸入ものの小エビではなくスジエビもしくはテナガエビをしょうゆ味で煮て餅にからめている。隣の登米市でも同じ物が売られていた。この周辺には伊豆沼、長沼と白鳥が飛来する湖沼、また河川の多いところ。淡水漁業が盛んだったはず。ドジョウを焼いて餅にからめた「ふすべ餅」も同様に淡水漁業の産物である。この地域で行われていた淡水漁業を探りたい。 宮城県で作られている「焼きガレイ」の原料は、本来は県内でとれていたものを使っていた。ただし、現在は大方が冷凍輸入されたもので作られている。宮城県のカレイ科ではマガレイ、マコガレイ、ババガレイなどが浮かぶが、なかでもサメガレイのものがいちばん人気があったという。実際に現在でもサメガレイの「焼きガレイ」はとても貴重でなかなか手に入らないという。「焼きガレイ」は産地で水揚げされたカレイ類の保存性を高めるために作られた。昔、魚貝類は鮮魚ではなく四十物(あいもの)、すなわち加工品として流通するのが基本だった。これが会津若松で手に入るのは、宮城県塩竃市などで作られて、山間部に送られた歴史があるからだ。たぶん会津地方では大ご馳走だったのだろう。このまま食べるのが現在では普通らしい。少し焼き直すか、レンジで温めて食べると、鮮魚を焼いたものとは別種の味わいがある。他の地方の方達にもぜひ一度味わって欲しい名品だと思う。協力/会津若松市公設地方卸売市場
宮城県で作られている「焼きガレイ」の原料は、本来は県内でとれていたものを使っていた。ただし、現在は大方が冷凍輸入されたもので作られている。宮城県のカレイ科ではマガレイ、マコガレイ、ババガレイなどが浮かぶが、なかでもサメガレイのものがいちばん人気があったという。実際に現在でもサメガレイの「焼きガレイ」はとても貴重でなかなか手に入らないという。「焼きガレイ」は産地で水揚げされたカレイ類の保存性を高めるために作られた。昔、魚貝類は鮮魚ではなく四十物(あいもの)、すなわち加工品として流通するのが基本だった。これが会津若松で手に入るのは、宮城県塩竃市などで作られて、山間部に送られた歴史があるからだ。たぶん会津地方では大ご馳走だったのだろう。このまま食べるのが現在では普通らしい。少し焼き直すか、レンジで温めて食べると、鮮魚を焼いたものとは別種の味わいがある。他の地方の方達にもぜひ一度味わって欲しい名品だと思う。協力/会津若松市公設地方卸売市場 東京都八王子市諏訪町の魚屋、ダイシンさんに聞き取る。昔、海から遠い八王子では、丸干しのマイワシを手開きにして、酢につけて食べたという。これを「いわしの刺身」と言った。八王子市は人工的にも面積でも大きな都市だ。歴史的にも古く、鎌倉時代、北条執権時代、室町期、戦国期、江戸時代でも要所であった。特に戦国時代には後北条氏、武田氏の領地の中間にある合戦場でもあったはず。この八王子は西の八王子城から開けて、徐々に東に市街地を広げる。当然、諏訪町は八王寺の中でももっとも早く開けた場所と言える。干ものを酢で締めると、身がぼろっとして見た目は悪いものの、意外にもとても味がいい。干ものを煮ると苦みが出てしまうが、生だとそれがない。ひょっとしたら、今にも通用する料理かも。
東京都八王子市諏訪町の魚屋、ダイシンさんに聞き取る。昔、海から遠い八王子では、丸干しのマイワシを手開きにして、酢につけて食べたという。これを「いわしの刺身」と言った。八王子市は人工的にも面積でも大きな都市だ。歴史的にも古く、鎌倉時代、北条執権時代、室町期、戦国期、江戸時代でも要所であった。特に戦国時代には後北条氏、武田氏の領地の中間にある合戦場でもあったはず。この八王子は西の八王子城から開けて、徐々に東に市街地を広げる。当然、諏訪町は八王寺の中でももっとも早く開けた場所と言える。干ものを酢で締めると、身がぼろっとして見た目は悪いものの、意外にもとても味がいい。干ものを煮ると苦みが出てしまうが、生だとそれがない。ひょっとしたら、今にも通用する料理かも。全59件中 全レコードを表示しています