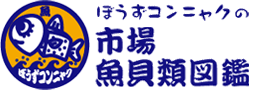コラム検索
検索条件
全18件中 全レコードを表示しています
 著者の木村守克は昭和11年(1936)弘前市生まれだ。「カドザメ(ネズミザメ)」は〈1853年(幕末)になると次第においしさが知られるようになり、多くの人々が賞味するようになりました〉とある。また、〈カレーライスにも肉の代わりに入れて、よく食べられていました〉ともある。よくよく考えてみると、津軽地方に限らず、カレーの材料としてネズミザメは普通に使われていた可能性が高い。さて、木村守克の子供時代というと第二次世界大戦の戦前戦後と考えるべきだろう。カレーは明治維新と同時に国内に来た。これが北海道でじゃがいも、西洋ニンジン、玉ねぎが作られ始めるに従い普及する。東京など大都市では、外食として、農村地帯では主婦の労働軽減のために国が政策として広めたとされている。大都市部と農村地帯の時差がない料理だったといえる。肉の代わりにネズミザメの身を使っただけの、昔ながらのカレー粉を使ったカレーにしてみた。じゃがいもや玉ねぎ、にんじんなどの野菜と適当に切ったネズミザメの身を炒めて、カレーと小麦粉を油で炒めて合わせたものを加える。ネズミザメの身は炒めて煮ても硬くならず、確かに食感は肉に近い。だまって出すと、鶏のささみのようである。ただカレー粉を使ったカレーはどことなくもの足りない。昔のカレーはこんな味だったのかもわからないが、現在の肉などで作ったカレーと比較できない。
著者の木村守克は昭和11年(1936)弘前市生まれだ。「カドザメ(ネズミザメ)」は〈1853年(幕末)になると次第においしさが知られるようになり、多くの人々が賞味するようになりました〉とある。また、〈カレーライスにも肉の代わりに入れて、よく食べられていました〉ともある。よくよく考えてみると、津軽地方に限らず、カレーの材料としてネズミザメは普通に使われていた可能性が高い。さて、木村守克の子供時代というと第二次世界大戦の戦前戦後と考えるべきだろう。カレーは明治維新と同時に国内に来た。これが北海道でじゃがいも、西洋ニンジン、玉ねぎが作られ始めるに従い普及する。東京など大都市では、外食として、農村地帯では主婦の労働軽減のために国が政策として広めたとされている。大都市部と農村地帯の時差がない料理だったといえる。肉の代わりにネズミザメの身を使っただけの、昔ながらのカレー粉を使ったカレーにしてみた。じゃがいもや玉ねぎ、にんじんなどの野菜と適当に切ったネズミザメの身を炒めて、カレーと小麦粉を油で炒めて合わせたものを加える。ネズミザメの身は炒めて煮ても硬くならず、確かに食感は肉に近い。だまって出すと、鶏のささみのようである。ただカレー粉を使ったカレーはどことなくもの足りない。昔のカレーはこんな味だったのかもわからないが、現在の肉などで作ったカレーと比較できない。 『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)は、青森県の食に関して外すことができない本である。この書籍は、発売と同時期に東京都神保町で見つけ買い求めている。何気なく買ったものだが、平易な文章なのにも関わらず資料性が高い。青森関係ではもっとも頻繁にリファレンスする一冊となっている。木村守克の故郷は海から遠い弘前市で、1936年に生まれている。東北栄養専門学校を卒業しており、食や歴史に関する在野の研究家だろう。「懐かしのカドザメ」の章には、津軽地方である弘前市、鰺ヶ沢町などで「カドザメ(書籍内がカタカナなので)」と呼ばれていたこと。その由来、料理法などが書かれている。この「カドザメ」の由来についてから始めたい。まずは予め現標準和名、ネズミザメについて。青森県八戸市の呼び名で『魚名集覧』(渋沢敬三 アチック・ミューゼアム・財団常民の刊行物 1934-1981)にあるため、1945年以前に採取された可能性が高い。同じく、東京でもネズミザメがある。このあたり東京への供給地としての青森県八戸市が見えてくる。同じ『魚名集覧』に北海道釧路、青森、北陸の「カトウザメ」がある。そして『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)には「カドザメ」がある。これらから青森県では主に日本海側で主に日本海で「カドザメ」、「カトウザメ」、「カトーザメ」と呼ばれ、太平洋側ではネズミザメと呼ばれていたのかもしれない。ただ、今現在で、この呼び名たちは青森県内で混ざり合って使われている気がする。八戸市のネズミザメの由来は明らかに頭部がネズミのようにとんがっているためだ。「カドザメ」には2説あるが、どちらが正しいかは結局不明だ。1 「カドザメ」とは、加藤という人に由来する。〈『弘藩明治一統誌月例雑報摘要抄』(内藤官八郎が明治時代に著したもの)に、この「加藤鮫」のいわれについて興味深い記事がありますので……「加藤鮫の事。この大鮫は、昔は漁をすることがありませんでした。天保十四年(1843)秋のこと、下前村(現小泊町下前?)の漁師で加藤音吉という者が、龍飛汐の口で、九月に一種の大鮫の漁をしたことに始まりました。〉これでは「カドザメ」が説明できない。同じく青森県の「カトウザメ」・「カトーザメ」は加藤がぴたりと当てはまる。ちなみに木村守克は、〈カドザメは、かつて鰺ヶ沢などでよくとれたものですが、今では需要も少ないので、すっかり漁が廃れてしまいました。今、魚屋で売られているものは、北海道でとれたものが解体され、ブロックになって青森に入荷したものです。〉とあり、サメの流通での北海道と青森との関係を述べている。ちなみに北陸の「カトウザメ」はアオザメである可能性がある。2 ニシン(カド)をエサとしているため。〈民俗学者の研究家である森山泰太郞氏(1915-2003)は、「カドザメ」と津軽で呼んでいるのはフカ(一般に大型のサメのこと)という魚のことで、カドつまりニシンを食うサメということだ。従って俗説のように加藤という漁師の姓とは関係がない〉。この場合、生息域の北限にあたるアオザメが含まれるということだろう。こちらは「カドザメ」には当てはまるが、「カトウザメ」・「カトーザメ」には当てはまらない。それにしても青森県はサメに縁がある。同書には、津軽半島のつけ根、ネズミザメか、アブラツノザメかは不明だが、津軽地方鰺ヶ沢で、元禄期十六年(1703)以前からカドザメ漁をする「サメ取船」が五十六隻もあったともある。
『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)は、青森県の食に関して外すことができない本である。この書籍は、発売と同時期に東京都神保町で見つけ買い求めている。何気なく買ったものだが、平易な文章なのにも関わらず資料性が高い。青森関係ではもっとも頻繁にリファレンスする一冊となっている。木村守克の故郷は海から遠い弘前市で、1936年に生まれている。東北栄養専門学校を卒業しており、食や歴史に関する在野の研究家だろう。「懐かしのカドザメ」の章には、津軽地方である弘前市、鰺ヶ沢町などで「カドザメ(書籍内がカタカナなので)」と呼ばれていたこと。その由来、料理法などが書かれている。この「カドザメ」の由来についてから始めたい。まずは予め現標準和名、ネズミザメについて。青森県八戸市の呼び名で『魚名集覧』(渋沢敬三 アチック・ミューゼアム・財団常民の刊行物 1934-1981)にあるため、1945年以前に採取された可能性が高い。同じく、東京でもネズミザメがある。このあたり東京への供給地としての青森県八戸市が見えてくる。同じ『魚名集覧』に北海道釧路、青森、北陸の「カトウザメ」がある。そして『みちのく食物誌』(木村守克 路上社 1986)には「カドザメ」がある。これらから青森県では主に日本海側で主に日本海で「カドザメ」、「カトウザメ」、「カトーザメ」と呼ばれ、太平洋側ではネズミザメと呼ばれていたのかもしれない。ただ、今現在で、この呼び名たちは青森県内で混ざり合って使われている気がする。八戸市のネズミザメの由来は明らかに頭部がネズミのようにとんがっているためだ。「カドザメ」には2説あるが、どちらが正しいかは結局不明だ。1 「カドザメ」とは、加藤という人に由来する。〈『弘藩明治一統誌月例雑報摘要抄』(内藤官八郎が明治時代に著したもの)に、この「加藤鮫」のいわれについて興味深い記事がありますので……「加藤鮫の事。この大鮫は、昔は漁をすることがありませんでした。天保十四年(1843)秋のこと、下前村(現小泊町下前?)の漁師で加藤音吉という者が、龍飛汐の口で、九月に一種の大鮫の漁をしたことに始まりました。〉これでは「カドザメ」が説明できない。同じく青森県の「カトウザメ」・「カトーザメ」は加藤がぴたりと当てはまる。ちなみに木村守克は、〈カドザメは、かつて鰺ヶ沢などでよくとれたものですが、今では需要も少ないので、すっかり漁が廃れてしまいました。今、魚屋で売られているものは、北海道でとれたものが解体され、ブロックになって青森に入荷したものです。〉とあり、サメの流通での北海道と青森との関係を述べている。ちなみに北陸の「カトウザメ」はアオザメである可能性がある。2 ニシン(カド)をエサとしているため。〈民俗学者の研究家である森山泰太郞氏(1915-2003)は、「カドザメ」と津軽で呼んでいるのはフカ(一般に大型のサメのこと)という魚のことで、カドつまりニシンを食うサメということだ。従って俗説のように加藤という漁師の姓とは関係がない〉。この場合、生息域の北限にあたるアオザメが含まれるということだろう。こちらは「カドザメ」には当てはまるが、「カトウザメ」・「カトーザメ」には当てはまらない。それにしても青森県はサメに縁がある。同書には、津軽半島のつけ根、ネズミザメか、アブラツノザメかは不明だが、津軽地方鰺ヶ沢で、元禄期十六年(1703)以前からカドザメ漁をする「サメ取船」が五十六隻もあったともある。 ネズミザメの食の歴史は有史以前からだと思うが詳しくはわからないが、明治時代以前から重要な食用魚であったことは間違いない。実際、1945年の敗戦後も国内中部千布の一部、北陸地方の一部、東日本ではもっとも一般的な食用魚だった。このネズミザメの食文化は衰退気味であるが、それでも根強く日本各地に残っている。中でも岐阜県飛騨地方(現高山市・飛驒市・下呂市がそれに当たると考えている)でのネズミザメの食文化は独特の進化を遂げている。例えば夏場の塩分補給の意味で「塩もーか(ネズミザメの塩蔵品)」や、生で送られて来たものを刺身にしたり、鍋ものにしたりもする。今回は飛騨地方の郷土料理「ぼた鍋」を作ってみた。生の「ぼた」、ネズミザメの塊が入荷したときに作るものである。単純に切り身と野菜などを鍋にしたもので、一般的には「水炊き」といったところだろう。生のネズミザメを買ってきて、適当に切る。これを最初水だけで煮て、あくをすくい、野菜などと煮てみた。これでも充分おいしいけど、つけたポン酢の味に負けている気がした。鍋を替えて昆布だし・酒・塩であくをすくいながら煮る。ここに野菜とか豆腐を加えて煮ながら食べたら、実に味わい深い。鶏のささみを思わせる食感だが、もっと味は軽い。柔らかいのでだしと一緒くたになって食べられるのがうれしい。この鍋なら日を明かさず食べられるし、寒い時季など毎日食べても飽きない味でもある。飛騨地方で愛されてきたわけもわかる。今現在、多くの人に受け入れられる味でもあり、郷土料理として絶やして欲しくはない。
ネズミザメの食の歴史は有史以前からだと思うが詳しくはわからないが、明治時代以前から重要な食用魚であったことは間違いない。実際、1945年の敗戦後も国内中部千布の一部、北陸地方の一部、東日本ではもっとも一般的な食用魚だった。このネズミザメの食文化は衰退気味であるが、それでも根強く日本各地に残っている。中でも岐阜県飛騨地方(現高山市・飛驒市・下呂市がそれに当たると考えている)でのネズミザメの食文化は独特の進化を遂げている。例えば夏場の塩分補給の意味で「塩もーか(ネズミザメの塩蔵品)」や、生で送られて来たものを刺身にしたり、鍋ものにしたりもする。今回は飛騨地方の郷土料理「ぼた鍋」を作ってみた。生の「ぼた」、ネズミザメの塊が入荷したときに作るものである。単純に切り身と野菜などを鍋にしたもので、一般的には「水炊き」といったところだろう。生のネズミザメを買ってきて、適当に切る。これを最初水だけで煮て、あくをすくい、野菜などと煮てみた。これでも充分おいしいけど、つけたポン酢の味に負けている気がした。鍋を替えて昆布だし・酒・塩であくをすくいながら煮る。ここに野菜とか豆腐を加えて煮ながら食べたら、実に味わい深い。鶏のささみを思わせる食感だが、もっと味は軽い。柔らかいのでだしと一緒くたになって食べられるのがうれしい。この鍋なら日を明かさず食べられるし、寒い時季など毎日食べても飽きない味でもある。飛騨地方で愛されてきたわけもわかる。今現在、多くの人に受け入れられる味でもあり、郷土料理として絶やして欲しくはない。 新潟県上越市直江津と、上越市高田と妙高市全域はともによくサメを食べるものの、違うサメ食文化である。海辺の直江津で食べるのは主に「むきざめ(アブラツノザメ)」であり、上越高田・妙高では「むきざめ」も食べるが「ふかざめ(ネズミザメ)」の比率が高い。ネズミザメ科のネズミザメ・アオザメと、ツノザメ科のアブラツノザメなどとの食べ方の違いはなにか?生食するか否かである。ツノザメ科のサメは希に生で食べることもあるが、一般的に生で食べる地域はない。ネズミザメ科のサメは少ないながら、好んで生で食べる地域がある。そしてそれが現在にまで続いている地域は、新潟県上越市と広島県備北地方だけだと思う。上越市の年越しにもっとも広範囲に作られているのが「ふかざめ」料理であるが、ここに「ぬた」がある。「ぬた」なのでゆでて酢みそで和えるのだな、と思っていたら、もっと多彩であった。妙高市・上越市高田で聞取をしたら、まったくの生を酢みそで、表面を霜降り状にして酢みそで、かなりしっかりゆでて酢みそでの3通りであった。酢みそで食べるものの、まったく生ということは刺身である。刺身になるほど鮮度のいい「ふかざめ」を手に入れるために年末、宮城県気仙沼から丸のまま「ふかざめ」を送ってもらい、競売が行われているといっても過言ではない。これは明治時代も同様であるようだ。ネズミザメは日本海でも揚がる。上越市から糸魚川市で揚がったサメは海辺では積極的食べられることなく、山間部に送られて、様々な料理になり、刺身にもなっていたことになる。
新潟県上越市直江津と、上越市高田と妙高市全域はともによくサメを食べるものの、違うサメ食文化である。海辺の直江津で食べるのは主に「むきざめ(アブラツノザメ)」であり、上越高田・妙高では「むきざめ」も食べるが「ふかざめ(ネズミザメ)」の比率が高い。ネズミザメ科のネズミザメ・アオザメと、ツノザメ科のアブラツノザメなどとの食べ方の違いはなにか?生食するか否かである。ツノザメ科のサメは希に生で食べることもあるが、一般的に生で食べる地域はない。ネズミザメ科のサメは少ないながら、好んで生で食べる地域がある。そしてそれが現在にまで続いている地域は、新潟県上越市と広島県備北地方だけだと思う。上越市の年越しにもっとも広範囲に作られているのが「ふかざめ」料理であるが、ここに「ぬた」がある。「ぬた」なのでゆでて酢みそで和えるのだな、と思っていたら、もっと多彩であった。妙高市・上越市高田で聞取をしたら、まったくの生を酢みそで、表面を霜降り状にして酢みそで、かなりしっかりゆでて酢みそでの3通りであった。酢みそで食べるものの、まったく生ということは刺身である。刺身になるほど鮮度のいい「ふかざめ」を手に入れるために年末、宮城県気仙沼から丸のまま「ふかざめ」を送ってもらい、競売が行われているといっても過言ではない。これは明治時代も同様であるようだ。ネズミザメは日本海でも揚がる。上越市から糸魚川市で揚がったサメは海辺では積極的食べられることなく、山間部に送られて、様々な料理になり、刺身にもなっていたことになる。 上越市高田から南、妙高市全域は明らかに海から遠く、山間部といってもいいだろう。ただ、明治時代も半ばになると、日本海からは遠いが、信越本線の開業で東京がぐんと近くなる。日本海で揚がる「むきざめ(アブラツノザメ)」よりも、東京経由でくる「ふかざめ(ネズミザメ)」の方がある意味近く、しかも安定的に供給されていた可能性もある。上越市でも海辺の直江津が「むきざめ」で、山側の高田が「ふかざめ」なのはこんなところにある。東北太平洋側で揚がり、東京経由でやってきた、「ふかざめ」で正月前後に作られているのが「煮凝り」である。正月に煮凝りを食べる習慣があるのは東京都内(関東)と同じである。見た目的にも作り方まで同じ。この煮凝りからこの上越・妙高と東京との繋がりを感じる。ちなみに正月前になると「ふかざめ」が宮城県気仙沼から送られてくる。このときはコロ(輪切にしたもの)で売り買いする。なぜコロなのか、も「煮凝り」について上越市高田、妙高市で聞取してわかってきた。
上越市高田から南、妙高市全域は明らかに海から遠く、山間部といってもいいだろう。ただ、明治時代も半ばになると、日本海からは遠いが、信越本線の開業で東京がぐんと近くなる。日本海で揚がる「むきざめ(アブラツノザメ)」よりも、東京経由でくる「ふかざめ(ネズミザメ)」の方がある意味近く、しかも安定的に供給されていた可能性もある。上越市でも海辺の直江津が「むきざめ」で、山側の高田が「ふかざめ」なのはこんなところにある。東北太平洋側で揚がり、東京経由でやってきた、「ふかざめ」で正月前後に作られているのが「煮凝り」である。正月に煮凝りを食べる習慣があるのは東京都内(関東)と同じである。見た目的にも作り方まで同じ。この煮凝りからこの上越・妙高と東京との繋がりを感じる。ちなみに正月前になると「ふかざめ」が宮城県気仙沼から送られてくる。このときはコロ(輪切にしたもの)で売り買いする。なぜコロなのか、も「煮凝り」について上越市高田、妙高市で聞取してわかってきた。 国内で日常的にサメを食べる地域が年々減少している。あまりにも極端なサメのイメージが横行しているせいだし、あのジョーズのせいでもある。サメは古代より至って平凡な食用魚である。昔はアンモリアなどが身に混在して臭いものもあったが、現在流通するもので臭味のあるものは存在しない。なんの根拠もなく忌避されているサメは長年、日本列島の重要なたんぱく源であったし、人々を飢餓から救っていたのだ。1945年の敗戦後食糧難の時代、東京都多摩地区などでは需要が多すぎて、供給が追いつかなかったくらいだ。このサメの恐怖感を煽る人間は下劣である。さて、サメ食といってもサメの種類は地域によって違っている。サメ食というと広島県備北の庄原市、三次市がまず挙がるくらい、この地域は有名である。盆と正月に欠かせない魚でもある。この備北の山間部に送っていたのは、サメ漁を行っている島根県五十猛だとする説もある。この五十猛(現島根県大田市)から石見銀山の銀山街道をたどると三次に至る。江戸時代はこの流通経路が使われていたのだろう。現在、島根県の山間の地、奥出雲などでもサメが売られている。この流通経路でサメの食文化が広がったに違いない。当然、備北というよりも日本海から遠い地域と考えた方がいいのかも知れない。この地域のサメ食文化をになっていた鮮魚店が急激に閉店しているのも気になる。ここでは主に刺身で食べられている。煮凝りが作られているし、当然煮つけにもなる。ただ、この地域で食べられているサメの種が文献によってしかわからなかった。
国内で日常的にサメを食べる地域が年々減少している。あまりにも極端なサメのイメージが横行しているせいだし、あのジョーズのせいでもある。サメは古代より至って平凡な食用魚である。昔はアンモリアなどが身に混在して臭いものもあったが、現在流通するもので臭味のあるものは存在しない。なんの根拠もなく忌避されているサメは長年、日本列島の重要なたんぱく源であったし、人々を飢餓から救っていたのだ。1945年の敗戦後食糧難の時代、東京都多摩地区などでは需要が多すぎて、供給が追いつかなかったくらいだ。このサメの恐怖感を煽る人間は下劣である。さて、サメ食といってもサメの種類は地域によって違っている。サメ食というと広島県備北の庄原市、三次市がまず挙がるくらい、この地域は有名である。盆と正月に欠かせない魚でもある。この備北の山間部に送っていたのは、サメ漁を行っている島根県五十猛だとする説もある。この五十猛(現島根県大田市)から石見銀山の銀山街道をたどると三次に至る。江戸時代はこの流通経路が使われていたのだろう。現在、島根県の山間の地、奥出雲などでもサメが売られている。この流通経路でサメの食文化が広がったに違いない。当然、備北というよりも日本海から遠い地域と考えた方がいいのかも知れない。この地域のサメ食文化をになっていた鮮魚店が急激に閉店しているのも気になる。ここでは主に刺身で食べられている。煮凝りが作られているし、当然煮つけにもなる。ただ、この地域で食べられているサメの種が文献によってしかわからなかった。 ここ十年来、東京都内での「煮凝り」を調べている。都内に昔、たくさんあった蒲鉾店(おでん種など練り製品を作る店)や食品加工の会社では、寒くなると煮凝りを作り始め、師走になると正月用として魚屋、スーパー、市場にあふれかえっていた。本来の煮凝りは魚の煮つけを作って、煮汁に染み出してきたコラーゲン(ゼラチン)が自然に冷えて固まったもので、料理ではなく、料理の状態といったものだ。ここでいう煮凝りはコラーゲンの多い魚の部位を煮だして、コラーゲンの多い煮汁を作り。そのコラーゲンの素となる魚の部位を食べやすい大きさに切り、コラーゲンの多い煮汁に戻し、もう一度煮て味つけする。これを形に入れて固めるという料理であり、料理名である。これとまったく同じことが遙か離れた新潟県上越市高田、妙高市で行われているのである。12月前後になると魚屋やスーパーに「ふかざめ(ネズミザメ)の煮凝り」が並び始め。また「煮凝り」の材料である「ふかざめの皮」が売られる。海から離れたこの一帯で作られている「煮凝り」は東京のものとまったく同じ物だ。原料が宮城県で水揚げされている、ネズミザメの皮であること。(都内ではフグ皮、ヨシキリザメの皮でも少ないながら作られている)年取(正月の膳)の肴であることも同じである。不思議なことにサメの産地である宮城県で、正月に煮凝りを食べるという話を聞かない。とすると「サメの煮凝り」は東京の郷土料理と考えるべきだ。それが新潟県上越市で、しかも正月に食べられている。こんな偶然あるのだろうか?ちなみに東京都だけではなく埼玉県など周辺でも「煮凝り」が正月用品として出回っている。ただこれは明らかに東京からの影響である。上越地方は東京からすると実に遠い。なぜ同じ食文化がここにあるのだろう。ちなみに正月に「サメの煮凝り」を食べる地域はもっと多い可能性もある。
ここ十年来、東京都内での「煮凝り」を調べている。都内に昔、たくさんあった蒲鉾店(おでん種など練り製品を作る店)や食品加工の会社では、寒くなると煮凝りを作り始め、師走になると正月用として魚屋、スーパー、市場にあふれかえっていた。本来の煮凝りは魚の煮つけを作って、煮汁に染み出してきたコラーゲン(ゼラチン)が自然に冷えて固まったもので、料理ではなく、料理の状態といったものだ。ここでいう煮凝りはコラーゲンの多い魚の部位を煮だして、コラーゲンの多い煮汁を作り。そのコラーゲンの素となる魚の部位を食べやすい大きさに切り、コラーゲンの多い煮汁に戻し、もう一度煮て味つけする。これを形に入れて固めるという料理であり、料理名である。これとまったく同じことが遙か離れた新潟県上越市高田、妙高市で行われているのである。12月前後になると魚屋やスーパーに「ふかざめ(ネズミザメ)の煮凝り」が並び始め。また「煮凝り」の材料である「ふかざめの皮」が売られる。海から離れたこの一帯で作られている「煮凝り」は東京のものとまったく同じ物だ。原料が宮城県で水揚げされている、ネズミザメの皮であること。(都内ではフグ皮、ヨシキリザメの皮でも少ないながら作られている)年取(正月の膳)の肴であることも同じである。不思議なことにサメの産地である宮城県で、正月に煮凝りを食べるという話を聞かない。とすると「サメの煮凝り」は東京の郷土料理と考えるべきだ。それが新潟県上越市で、しかも正月に食べられている。こんな偶然あるのだろうか?ちなみに東京都だけではなく埼玉県など周辺でも「煮凝り」が正月用品として出回っている。ただこれは明らかに東京からの影響である。上越地方は東京からすると実に遠い。なぜ同じ食文化がここにあるのだろう。ちなみに正月に「サメの煮凝り」を食べる地域はもっと多い可能性もある。 糸魚川市と上越市直江津を除く上越地方山間部(上越市高田と妙高市)では、普段から「ふかざめ(ネズミザメ)」を食べているが、特に年取・正月には欠かせない。普段から食べているのは「煮つけ」とフライである。年取・正月だけに作るのが「煮凝り」と「ぬた」だ。正月の膳には「煮凝り」と「ぬた」、そして「煮つけ」が欠かせない。この3つは伝統的な料理で、正月三大料理と考えるとわかりやすい。余談だが、同じ上越市でも日本海に面している直江津では「棒ざめ(アブラツノザメ)」を好む。こちらはあくまでも日常に食べるためのもので、ハレの日に食べるものではない。年の暮れ27日に、上越市にある一印 上越魚市場で、宮城県気仙沼産の丸のままの「ふかざめ(ネズミザメ)」の競売が行われているのもこの地域のためだ。山間部でも「ふかざめ(ネズミザメ)」の身は一年を通して販売されている。こちらは主に煮つけとフライなど日々の総菜用である。皮と、刺身で食べられるくらい鮮度のいいものは明らかに正月用で、11月下旬から12月、1月の初旬くらいまで流通する。なぜ、この上越地方の山間部で「ふかざめ(ネズミザメ)」を食べるようになったのか、は別項を立てる。正月にサメを食べるのは、この上越地方、栃木県、茨城県と群馬県の一部地域、広島県備北地方である。共通するのは海から離れていることだ。
糸魚川市と上越市直江津を除く上越地方山間部(上越市高田と妙高市)では、普段から「ふかざめ(ネズミザメ)」を食べているが、特に年取・正月には欠かせない。普段から食べているのは「煮つけ」とフライである。年取・正月だけに作るのが「煮凝り」と「ぬた」だ。正月の膳には「煮凝り」と「ぬた」、そして「煮つけ」が欠かせない。この3つは伝統的な料理で、正月三大料理と考えるとわかりやすい。余談だが、同じ上越市でも日本海に面している直江津では「棒ざめ(アブラツノザメ)」を好む。こちらはあくまでも日常に食べるためのもので、ハレの日に食べるものではない。年の暮れ27日に、上越市にある一印 上越魚市場で、宮城県気仙沼産の丸のままの「ふかざめ(ネズミザメ)」の競売が行われているのもこの地域のためだ。山間部でも「ふかざめ(ネズミザメ)」の身は一年を通して販売されている。こちらは主に煮つけとフライなど日々の総菜用である。皮と、刺身で食べられるくらい鮮度のいいものは明らかに正月用で、11月下旬から12月、1月の初旬くらいまで流通する。なぜ、この上越地方の山間部で「ふかざめ(ネズミザメ)」を食べるようになったのか、は別項を立てる。正月にサメを食べるのは、この上越地方、栃木県、茨城県と群馬県の一部地域、広島県備北地方である。共通するのは海から離れていることだ。 今も岐阜県飛騨地方で手に入れることができる、「塩もーか(塩もうか)」、「塩さわら」はネズミザメのころ(塊)を塩づけにした保存食で、夏の味である。ここでいう飛騨地方は飛騨川に沿って下呂市から北上、高山市、さらに北上して飛騨国の国府があった古川(現飛驒市)、高山市から丹生川沿いに東に丹生川町あたりまでのことだと考えている。この食文化のある地域に関してはまだ見当の余地がある。塩分濃度が高く、そのまま焼いて食べると塩が吹き出してくる。高山市で聞くと、昔、夏に食べるととても飯が進み、おいしかったと言うが、大量に汗をかき塩分をおいしく感じたからだ。北陸や富山湾でとれたサメを浜で塩蔵して飛騨地方に運ぶというのは、冬の塩ブリと同じである。塩ブリは一度、飛騨に集められて、飛騨ブリと名をかえて、飛騨山脈を越えて松本平に送られていた。「塩もーか」、「塩さわら」も同じ経路をたどっていたのだと思う。ただし今現在、飛騨高山市から丹生川方面にはあるが、その先、松本平では見ていない。その分、「塩ぶり」よりもローカルな存在だったのだろう。「塩もーか」は「塩真鱶」で明らかにネズミザメの塩蔵品だとわかる。でもわからないのが「塩さわら」という言葉である。今現在、「塩もーか」、「塩さわら」はまったく同じ物で、原材料はネズミザメだ。ただ、なぜ「さわら」なのか? 白身なので標準和名のサワラになぞらえた、もしくは偽装したと考えると簡単である。ただ、飛騨地方で標準和名のサワラになぞらえるはずがない。ほんの20年くらい前までサワラがとれる地域は西日本が主で、飛騨地方の水産物の供給地、日本海の山陰以北ではほぼとれなかった。標準和名のサワラとは縁遠いところなのだ。この答えは、地方名を調べるとわかる。飛騨地方の水産物の供給元は北陸石川県、富山県であるが、この地域で「さわら」はシロカジキ、マカジキのことなのである。北陸では「さわら」と呼ばれていたカジキ類が御馳走だったので、わざわざ「塩さわら」と名づけたのだろう。このことからも、「塩さわら」の方が古い呼び名で、「塩もーか」が新しいことがわかる。もともとは北陸で揚がったサメ類を飛騨地方に送っていたのだろう。北陸で揚がるサメ類はネズミザメもあるだろうが、アオザメやシュモクザメ類、メジロザメなどだろう。北陸で揚がり、飛騨地方に輸送するには数日を要したはずだが、サメは筋肉に尿素とトリチルアミンオキシドをもち、時間がたつと尿素はアンモニアにトリチルアミンオキシドはトリチルアミンに変化する。ともに悪臭の原因物質だが、筋肉の腐敗を防止する。生の状態でも飛騨地方まで運べた可能性が高いが、「塩もーか」、「塩さわら」は夏に食べるもので、より高い保存性が求められる。また飛騨地方で塩は貴重なものだった可能性もある。だから塩漬けにしたのだろう。また塩漬けにした方が臭わない。現在のように宮城県産をはじめ三陸のネズミザメが原料になったのは、北陸のサメの水揚げが減ったからでもあり、産地である三陸から飛騨地方まで、大正時代に鉄道が繋がったからだろう。これは同じようにサメ食文化のある新潟県上越市高田、妙高市新井のネズミザメの供給地が明治時代から三陸だったのと同じだ。ネズミザメは三陸から宮城県仙台まで運び、仙台から東北本線で東京(東京市場駅)に運ぶ。東京はサメをよく食べる地域なので、一部は下ろし、残りを信越本線で高田駅(現上越市)まで運んだ。飛騨地方に運ぶときにも東京(東京市場駅)、高田駅(現上越市)経由、北陸本線を通って富山駅、富山駅から高山本線で高山駅だったのではないかと思っている。明治期開業の信越本線での高田駅までの流通が明治時代に始まり、飛騨地方は遅れて大正時代に始まったのではないか。鉄道史を知らないので、想像でしかないがいかがだろう。
今も岐阜県飛騨地方で手に入れることができる、「塩もーか(塩もうか)」、「塩さわら」はネズミザメのころ(塊)を塩づけにした保存食で、夏の味である。ここでいう飛騨地方は飛騨川に沿って下呂市から北上、高山市、さらに北上して飛騨国の国府があった古川(現飛驒市)、高山市から丹生川沿いに東に丹生川町あたりまでのことだと考えている。この食文化のある地域に関してはまだ見当の余地がある。塩分濃度が高く、そのまま焼いて食べると塩が吹き出してくる。高山市で聞くと、昔、夏に食べるととても飯が進み、おいしかったと言うが、大量に汗をかき塩分をおいしく感じたからだ。北陸や富山湾でとれたサメを浜で塩蔵して飛騨地方に運ぶというのは、冬の塩ブリと同じである。塩ブリは一度、飛騨に集められて、飛騨ブリと名をかえて、飛騨山脈を越えて松本平に送られていた。「塩もーか」、「塩さわら」も同じ経路をたどっていたのだと思う。ただし今現在、飛騨高山市から丹生川方面にはあるが、その先、松本平では見ていない。その分、「塩ぶり」よりもローカルな存在だったのだろう。「塩もーか」は「塩真鱶」で明らかにネズミザメの塩蔵品だとわかる。でもわからないのが「塩さわら」という言葉である。今現在、「塩もーか」、「塩さわら」はまったく同じ物で、原材料はネズミザメだ。ただ、なぜ「さわら」なのか? 白身なので標準和名のサワラになぞらえた、もしくは偽装したと考えると簡単である。ただ、飛騨地方で標準和名のサワラになぞらえるはずがない。ほんの20年くらい前までサワラがとれる地域は西日本が主で、飛騨地方の水産物の供給地、日本海の山陰以北ではほぼとれなかった。標準和名のサワラとは縁遠いところなのだ。この答えは、地方名を調べるとわかる。飛騨地方の水産物の供給元は北陸石川県、富山県であるが、この地域で「さわら」はシロカジキ、マカジキのことなのである。北陸では「さわら」と呼ばれていたカジキ類が御馳走だったので、わざわざ「塩さわら」と名づけたのだろう。このことからも、「塩さわら」の方が古い呼び名で、「塩もーか」が新しいことがわかる。もともとは北陸で揚がったサメ類を飛騨地方に送っていたのだろう。北陸で揚がるサメ類はネズミザメもあるだろうが、アオザメやシュモクザメ類、メジロザメなどだろう。北陸で揚がり、飛騨地方に輸送するには数日を要したはずだが、サメは筋肉に尿素とトリチルアミンオキシドをもち、時間がたつと尿素はアンモニアにトリチルアミンオキシドはトリチルアミンに変化する。ともに悪臭の原因物質だが、筋肉の腐敗を防止する。生の状態でも飛騨地方まで運べた可能性が高いが、「塩もーか」、「塩さわら」は夏に食べるもので、より高い保存性が求められる。また飛騨地方で塩は貴重なものだった可能性もある。だから塩漬けにしたのだろう。また塩漬けにした方が臭わない。現在のように宮城県産をはじめ三陸のネズミザメが原料になったのは、北陸のサメの水揚げが減ったからでもあり、産地である三陸から飛騨地方まで、大正時代に鉄道が繋がったからだろう。これは同じようにサメ食文化のある新潟県上越市高田、妙高市新井のネズミザメの供給地が明治時代から三陸だったのと同じだ。ネズミザメは三陸から宮城県仙台まで運び、仙台から東北本線で東京(東京市場駅)に運ぶ。東京はサメをよく食べる地域なので、一部は下ろし、残りを信越本線で高田駅(現上越市)まで運んだ。飛騨地方に運ぶときにも東京(東京市場駅)、高田駅(現上越市)経由、北陸本線を通って富山駅、富山駅から高山本線で高山駅だったのではないかと思っている。明治期開業の信越本線での高田駅までの流通が明治時代に始まり、飛騨地方は遅れて大正時代に始まったのではないか。鉄道史を知らないので、想像でしかないがいかがだろう。 新潟県上越市、『一印 上越魚市場』で、毎年12月27日に「ふかざめ(もうかとも。ネズミザメのこと)」の競売が行われている。ちなみに「鱶(ふか)」とは、サメ類の中でも大きなものを指す。100kg以上になるネズミザメを「ふかざめ」というのは、この地でもともと揚がっていた食用ザメの中でも大きいという意味になる。新聞社やテレビも来てなかなか盛況、地味ではあるがイベントと化している。上越市・妙高市では年取(大晦日と正月)に「ふかざめ」を食べる習慣がある。「ふかざめ」で年取をするのは主に海から離れた地域と山間部で、上越市高田、妙高市新井・関山・妙高高原だ。また、新潟県西蒲原郡岩室村(現新潟市西蒲原区岩室)では、サメの種は不明だが、 〈神主さんから、この地では正月にサメを食べねばならぬ習慣があったと聞いた。海から一里ほど離れたここでは年の暮にサメを買ってきて雪の中に入れておき、正月料理にとり出して田楽や酢のあえものにしたそうだ。〉『ものと人間との文化史 鮫』(矢野憲一 法政大学出版局 1979)ちなみに海沿いの上越市直江津では「棒ざめ」は食べるが、「ふかざめ」はあまり食べない。同じように西の糸魚川市でも、「さめぬた(たぶんアブラツノザメの)」を正月に食べることはあっても、「ふかざめ」は食べないようである。「ふかざめ」の競売は、本来直江津以外の地域の需要をまかなうためのものだ。当然、競売に参加するのは、年取に「ふかざめ」を食べる習慣のある地域の鮮魚店と上越市・妙高市でも広域な商圏を持つスーパーとなる。
新潟県上越市、『一印 上越魚市場』で、毎年12月27日に「ふかざめ(もうかとも。ネズミザメのこと)」の競売が行われている。ちなみに「鱶(ふか)」とは、サメ類の中でも大きなものを指す。100kg以上になるネズミザメを「ふかざめ」というのは、この地でもともと揚がっていた食用ザメの中でも大きいという意味になる。新聞社やテレビも来てなかなか盛況、地味ではあるがイベントと化している。上越市・妙高市では年取(大晦日と正月)に「ふかざめ」を食べる習慣がある。「ふかざめ」で年取をするのは主に海から離れた地域と山間部で、上越市高田、妙高市新井・関山・妙高高原だ。また、新潟県西蒲原郡岩室村(現新潟市西蒲原区岩室)では、サメの種は不明だが、 〈神主さんから、この地では正月にサメを食べねばならぬ習慣があったと聞いた。海から一里ほど離れたここでは年の暮にサメを買ってきて雪の中に入れておき、正月料理にとり出して田楽や酢のあえものにしたそうだ。〉『ものと人間との文化史 鮫』(矢野憲一 法政大学出版局 1979)ちなみに海沿いの上越市直江津では「棒ざめ」は食べるが、「ふかざめ」はあまり食べない。同じように西の糸魚川市でも、「さめぬた(たぶんアブラツノザメの)」を正月に食べることはあっても、「ふかざめ」は食べないようである。「ふかざめ」の競売は、本来直江津以外の地域の需要をまかなうためのものだ。当然、競売に参加するのは、年取に「ふかざめ」を食べる習慣のある地域の鮮魚店と上越市・妙高市でも広域な商圏を持つスーパーとなる。 2000年を迎えてすぐ、東京都八王子市の市場で見つけたアブラツノザメのむき鮫から、青森市の田向商店にたどりついた。青森県を始め、国内でのサメを食べる文化に関していろいろ教わった。田向商店の田向常城さんに教わった中に、サメの肝油の作り方がある。サメの肝臓の脂、肝油にはビタミンAやビタミンD、スクワレンなどを含まれている。これが免疫力増強や殺菌作用、また肌荒れにもきくという。探しに探してやっと、丸のままのアブラツノザメが手に入ったので、教わった通りに肝油を作ってみる。ちなみに、田向常城さん曰く、「タラを扱っていると手が荒れるが、サメをさばいているとすぐなおる」という。
2000年を迎えてすぐ、東京都八王子市の市場で見つけたアブラツノザメのむき鮫から、青森市の田向商店にたどりついた。青森県を始め、国内でのサメを食べる文化に関していろいろ教わった。田向商店の田向常城さんに教わった中に、サメの肝油の作り方がある。サメの肝臓の脂、肝油にはビタミンAやビタミンD、スクワレンなどを含まれている。これが免疫力増強や殺菌作用、また肌荒れにもきくという。探しに探してやっと、丸のままのアブラツノザメが手に入ったので、教わった通りに肝油を作ってみる。ちなみに、田向常城さん曰く、「タラを扱っていると手が荒れるが、サメをさばいているとすぐなおる」という。 分類学的にはサメ区になる、サメを食べる地域は全国に散らばっているが、刺身でたべる地域は非常に狭い。地域地域で小集団、個人的に食べている地域は数知れずあるが、刺身用として表示されスーパーなどに普通に並んでいる(流通する)地域は国内でも非常に希なのだと思っている。生で食べるサメとして一般的なものはアオザメ、ネズミザメの2種しか確認していない。確認次第、種と地域を増やしていきたい。国内新潟県上越市・妙高市 「ふかざめのぬた」。この地域では鮮度のいい「ふかざめ(ネズミザメ)」を刺身状に切り、酢みそで食べる。表面を霜降り状にする人もいるが、スーパーなどの表示、「ぬた用」は生食を意味する。岐阜県飛騨地方この地方では塩蔵品である、「塩もーか」、「塩さわら」を主に食べている。ただ宮城県から生ぼた(生の塊)で来たものは刺身にしても食べていた。生をフライ、煮つけなどにもする。島根県奥出雲 「わに刺身」。2024年現在でも売られている。広島県備北地域の庄原市、三次市 「わに刺身」。写真は広島県三次市の「いらぎわにの刺身」。「いらぎ」とはアオザメのことだ。
分類学的にはサメ区になる、サメを食べる地域は全国に散らばっているが、刺身でたべる地域は非常に狭い。地域地域で小集団、個人的に食べている地域は数知れずあるが、刺身用として表示されスーパーなどに普通に並んでいる(流通する)地域は国内でも非常に希なのだと思っている。生で食べるサメとして一般的なものはアオザメ、ネズミザメの2種しか確認していない。確認次第、種と地域を増やしていきたい。国内新潟県上越市・妙高市 「ふかざめのぬた」。この地域では鮮度のいい「ふかざめ(ネズミザメ)」を刺身状に切り、酢みそで食べる。表面を霜降り状にする人もいるが、スーパーなどの表示、「ぬた用」は生食を意味する。岐阜県飛騨地方この地方では塩蔵品である、「塩もーか」、「塩さわら」を主に食べている。ただ宮城県から生ぼた(生の塊)で来たものは刺身にしても食べていた。生をフライ、煮つけなどにもする。島根県奥出雲 「わに刺身」。2024年現在でも売られている。広島県備北地域の庄原市、三次市 「わに刺身」。写真は広島県三次市の「いらぎわにの刺身」。「いらぎ」とはアオザメのことだ。 初めてアブラツノザメの棒ざめ(剥き身、むきサメ)を見たのは東京築地場外だった。場外から場内に入ったときにも、並んでいて、奥で切り身にしていたのを見ている。その切身を見て初めて東京の東、新小岩や小岩で買った謎の切り身(物体)の正体がわかった。アブラツノザメだったのである。北隆館の図鑑を暗記しているときだったので、非常に嬉しかった。ちなみにこの棒ざめは東京都内下町だけではなく、吉祥寺、武蔵小金井、世田谷、八王子と、どこにでもあるありふれたものだった。それが今、都内では探さないと手に入らない。1990年代、八王子にあった東市(築地魚市場)には、小山になっており、商圏の魚屋、スーパーなどが箱買いしていたものだ。その棒ざめを送り出していたのが、田向商店である。田向商店の発泡は細長く特殊な形だった。大型のアブラツノザメの「むき鮫」だからだ。棒ざめの荷には必ず、田向商店の文字があった。我が家に丸のままのアブラツノザメを送ってくれたのは田向商店、田向常城(敬称略)である。それまで宮城県塩釜で買った、ぼろぼろになったアブラツノザメのフィルム画像しか持っていなかったので、深く感謝したものである。
初めてアブラツノザメの棒ざめ(剥き身、むきサメ)を見たのは東京築地場外だった。場外から場内に入ったときにも、並んでいて、奥で切り身にしていたのを見ている。その切身を見て初めて東京の東、新小岩や小岩で買った謎の切り身(物体)の正体がわかった。アブラツノザメだったのである。北隆館の図鑑を暗記しているときだったので、非常に嬉しかった。ちなみにこの棒ざめは東京都内下町だけではなく、吉祥寺、武蔵小金井、世田谷、八王子と、どこにでもあるありふれたものだった。それが今、都内では探さないと手に入らない。1990年代、八王子にあった東市(築地魚市場)には、小山になっており、商圏の魚屋、スーパーなどが箱買いしていたものだ。その棒ざめを送り出していたのが、田向商店である。田向商店の発泡は細長く特殊な形だった。大型のアブラツノザメの「むき鮫」だからだ。棒ざめの荷には必ず、田向商店の文字があった。我が家に丸のままのアブラツノザメを送ってくれたのは田向商店、田向常城(敬称略)である。それまで宮城県塩釜で買った、ぼろぼろになったアブラツノザメのフィルム画像しか持っていなかったので、深く感謝したものである。 世の中には腹の立つことが多すぎる。中でも大げさな表現をするヤツは嫌いである。内臓を食べなければ問題ないはずのソウシハギを猛毒魚と言ったり、サメが全部人食いだとばかり驚いたり。日本列島にも危険なサメもいると思うけど、非常に少数派だし、地球上でのサメの被害なんて水俣病など公害の被害と比べると耳垢程度でしかない。むしろ日々の糧として活用されていることの方が多いのだ。はっきりいいたい、サメはうまい! 近いうちにエネルギーの大量消費時代は終わるし、食べ物を資本主義の考え方で流通させる時代は終わると思う。サメはもちろん資源の保全をしながらだけど、ちゃんと食べていかなければならぬ時代が目の前に来ているのだ。売名行為や視聴率獲得のためにサメを悪者扱いするな!サメをジョーズ化するな、といいたい。さて、日本全国のスーパーめぐりをしながらサメ食について調べている。東京都など、ほんの四半世紀前までは国内でももっともサメ(ネズミザメ)を食べていたところなのである。関東で言えば栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県と敗戦直後などサメの配給分配が行われていたくらいだ。新潟県上越市、長野県、岐阜県など全国各地で食べられていた。国内のサメ食には「ゆでる地域」と「煮つける地域」、少ないながら「生食する地域」に分かれる。山梨県はネズミザメとアブラツノザメ流通圏なので「煮つける地域」に当たる。久しぶりに山梨でスーパー巡りをしてきて、北杜市白州のスーパーに「もろ(ネズミザメ)」の切り身があった。今現在急激な魚価の高騰の中にあって、非常に安く売られていた。サメは食べたらわかることだけどとてもうまいし、値段からして庶民の味方、ナウシカである。
世の中には腹の立つことが多すぎる。中でも大げさな表現をするヤツは嫌いである。内臓を食べなければ問題ないはずのソウシハギを猛毒魚と言ったり、サメが全部人食いだとばかり驚いたり。日本列島にも危険なサメもいると思うけど、非常に少数派だし、地球上でのサメの被害なんて水俣病など公害の被害と比べると耳垢程度でしかない。むしろ日々の糧として活用されていることの方が多いのだ。はっきりいいたい、サメはうまい! 近いうちにエネルギーの大量消費時代は終わるし、食べ物を資本主義の考え方で流通させる時代は終わると思う。サメはもちろん資源の保全をしながらだけど、ちゃんと食べていかなければならぬ時代が目の前に来ているのだ。売名行為や視聴率獲得のためにサメを悪者扱いするな!サメをジョーズ化するな、といいたい。さて、日本全国のスーパーめぐりをしながらサメ食について調べている。東京都など、ほんの四半世紀前までは国内でももっともサメ(ネズミザメ)を食べていたところなのである。関東で言えば栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県と敗戦直後などサメの配給分配が行われていたくらいだ。新潟県上越市、長野県、岐阜県など全国各地で食べられていた。国内のサメ食には「ゆでる地域」と「煮つける地域」、少ないながら「生食する地域」に分かれる。山梨県はネズミザメとアブラツノザメ流通圏なので「煮つける地域」に当たる。久しぶりに山梨でスーパー巡りをしてきて、北杜市白州のスーパーに「もろ(ネズミザメ)」の切り身があった。今現在急激な魚価の高騰の中にあって、非常に安く売られていた。サメは食べたらわかることだけどとてもうまいし、値段からして庶民の味方、ナウシカである。 明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。
明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。 神奈川県小田原市、江の安、ワタルさんにホシザメをいただく。なんと活魚である。むんむんするような、蒸し暑い朝だったので、ホシザメといえば、というあの料理を思い浮かべて、うほほと笑い、お礼もそこそこにとっとと帰ってきた。ホシザメと言えば、西日本で作られる料理の「湯引き」である。「湯がき」ともいうし、「湯ざらし」などともいう。酢みそで食べるというのも同じである。主に小型の軟骨魚類であるサメやエイが使われている。初めて食べたのは長崎県だったが、サメの種類は不明だった。次いで広島県でホシザメを仕入れている人に会い、「湯引き」の作り方を教わった。サカタザメでもいいというところから、要するに沿岸域のサメのようなもの、ならなんでもよかったのだ。ホシザメで作る、湯引きがいちばんうまいという。確かに同属で瓜二つのシロザメで作るものよりも味がある。でもごくわずかな差でしかない。むしろサカタザメの方がホシザメよりもうまいと思ったこともあるが、こちらもごくごくわずかな差でしかない。山口県ではニュージーランド産のギンザメで作ったものを買い求めていることから、くせのない魚ならなんでもいいのかも知れない。
神奈川県小田原市、江の安、ワタルさんにホシザメをいただく。なんと活魚である。むんむんするような、蒸し暑い朝だったので、ホシザメといえば、というあの料理を思い浮かべて、うほほと笑い、お礼もそこそこにとっとと帰ってきた。ホシザメと言えば、西日本で作られる料理の「湯引き」である。「湯がき」ともいうし、「湯ざらし」などともいう。酢みそで食べるというのも同じである。主に小型の軟骨魚類であるサメやエイが使われている。初めて食べたのは長崎県だったが、サメの種類は不明だった。次いで広島県でホシザメを仕入れている人に会い、「湯引き」の作り方を教わった。サカタザメでもいいというところから、要するに沿岸域のサメのようなもの、ならなんでもよかったのだ。ホシザメで作る、湯引きがいちばんうまいという。確かに同属で瓜二つのシロザメで作るものよりも味がある。でもごくわずかな差でしかない。むしろサカタザメの方がホシザメよりもうまいと思ったこともあるが、こちらもごくごくわずかな差でしかない。山口県ではニュージーランド産のギンザメで作ったものを買い求めていることから、くせのない魚ならなんでもいいのかも知れない。 三重県以西の太平洋側、瀬戸内海、九州では基本的にゆでて酢みそで食べる。鹿児島県志布志ではこれを「せんさら(千皿)」という。とりたててうまいわけではないが、なぜか毎日食べても食べ飽きない。多くの人が一度食べると、また無性に食べたくなる料理である。魚の切り身をゆでて食べることから、「なます」の一種と考えたい。酢みそを使うことから「ぬた」と考えてもいいだろう。基本的に西日本の海辺で行われていた料理だが、広島県備北では食べているらしいとは聞取しているだけ。作り方や食べ方はほとんど同じだが、地域によって呼び名が違う。「ふか」、「さめ」というが、全頭亜綱のギンザメや、エイ上目(エイ)のサカタザメなども含まれている。軟骨魚類ならなんでもいいのである。
三重県以西の太平洋側、瀬戸内海、九州では基本的にゆでて酢みそで食べる。鹿児島県志布志ではこれを「せんさら(千皿)」という。とりたててうまいわけではないが、なぜか毎日食べても食べ飽きない。多くの人が一度食べると、また無性に食べたくなる料理である。魚の切り身をゆでて食べることから、「なます」の一種と考えたい。酢みそを使うことから「ぬた」と考えてもいいだろう。基本的に西日本の海辺で行われていた料理だが、広島県備北では食べているらしいとは聞取しているだけ。作り方や食べ方はほとんど同じだが、地域によって呼び名が違う。「ふか」、「さめ」というが、全頭亜綱のギンザメや、エイ上目(エイ)のサカタザメなども含まれている。軟骨魚類ならなんでもいいのである。 東京都周辺では正月に「煮凝り」は欠かせない。蒲鉾店(おでんだねを作る店)や食品製造業者が作るもので、原材料には、ふか皮(ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ)、フグ皮などがある。量的にはネズミザメのものが多く、続いてヨシキリザメの煮凝りが多い。昔から、年末が近づくと築地市場に「煮凝り」が大量に並んでいた。2010年くらいの築地では塩乾惣菜などの店に山のように積まれていたものだ。それが近年(2024年)、めっきりすくなくなっている。暮れの豊洲場内で聞くと、売れなくなったからだという。実際、豊洲市場内でも探さないと見つからない。年取、正月のお節に「煮凝り」という食文化自体が廃れているのだ。今回のものは八王子総合卸売センター、福泉で見つけたもので、市場で見かける機会のもっとも多いものだ。久しぶりに食べてみたら、口溶け感といい、「ふか皮」の食感といいとても味わい深いものであった。これなら年末年始だけではなく、日常的も食べたいと思う。さて、大正7年(1918)年門前仲町生まれの男性の話では、駄菓子屋や屋台で煎餅、飴などとともに鮫の煮こごりが売られていたという。『江東区の民俗 深川編』(江東区教育委員会)しょうゆ味の素朴な味わいで、甘く作ると確かに子供のおやつにもなりそう。大正時代にはお節だけではなく、日常的にも食べられ、また子供のおやつでもあったのだ。そんな身近な存在であった「煮凝り」が今、存在自体が忘れられつつある。写真は、千葉県市川市『丸勇水産』のもの。
東京都周辺では正月に「煮凝り」は欠かせない。蒲鉾店(おでんだねを作る店)や食品製造業者が作るもので、原材料には、ふか皮(ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ)、フグ皮などがある。量的にはネズミザメのものが多く、続いてヨシキリザメの煮凝りが多い。昔から、年末が近づくと築地市場に「煮凝り」が大量に並んでいた。2010年くらいの築地では塩乾惣菜などの店に山のように積まれていたものだ。それが近年(2024年)、めっきりすくなくなっている。暮れの豊洲場内で聞くと、売れなくなったからだという。実際、豊洲市場内でも探さないと見つからない。年取、正月のお節に「煮凝り」という食文化自体が廃れているのだ。今回のものは八王子総合卸売センター、福泉で見つけたもので、市場で見かける機会のもっとも多いものだ。久しぶりに食べてみたら、口溶け感といい、「ふか皮」の食感といいとても味わい深いものであった。これなら年末年始だけではなく、日常的も食べたいと思う。さて、大正7年(1918)年門前仲町生まれの男性の話では、駄菓子屋や屋台で煎餅、飴などとともに鮫の煮こごりが売られていたという。『江東区の民俗 深川編』(江東区教育委員会)しょうゆ味の素朴な味わいで、甘く作ると確かに子供のおやつにもなりそう。大正時代にはお節だけではなく、日常的にも食べられ、また子供のおやつでもあったのだ。そんな身近な存在であった「煮凝り」が今、存在自体が忘れられつつある。写真は、千葉県市川市『丸勇水産』のもの。全18件中 全レコードを表示しています