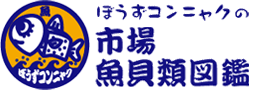コラム検索
検索条件
該当するコラムが多い為ページを分割して表示します。
全183コラム中 1番目~100番目までを表示中
- 1
- 2
 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。うまいもん揃いだとも言えるだろう。その最たるものがコナガニシである。日本海に多い巻き貝であるが、唾液腺にテトラミンを持ち、内臓に苦みがあるなど、非常にやっかいな存在だ。日本海側では鳥取県、石川県では食べているが、他の地域では見向きもしない。ただし、刺身にするとこれ以上の美味は望めない、と思っている。歩留まりは最低である。食べる部分はふたのついた足の部分だけ、あとは洗い流す。ぬめりはほとんどないので、水分をきって適当に切るだけだ。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。うまいもん揃いだとも言えるだろう。その最たるものがコナガニシである。日本海に多い巻き貝であるが、唾液腺にテトラミンを持ち、内臓に苦みがあるなど、非常にやっかいな存在だ。日本海側では鳥取県、石川県では食べているが、他の地域では見向きもしない。ただし、刺身にするとこれ以上の美味は望めない、と思っている。歩留まりは最低である。食べる部分はふたのついた足の部分だけ、あとは洗い流す。ぬめりはほとんどないので、水分をきって適当に切るだけだ。 〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。
〈小魚の塩いり 《材料》ババガレイ(ムシガレイとあるがヒレグロの間違いだと思われる)、アカラ(イトヨリとあるがハツメの間違い)、ハタハタ、甘エビ、塩、酒その日とれた小魚類を塩味だけでいり煮した、いたって素朴なお惣菜である。一部略〉『味のふるさと 福井の味』(角川書店 1978)このシリーズの本はプロの割り付けがなされ、しっかり監修もされていて、大きな間違いがないなどとても優秀である。「越前・海の幸」とあるので、福井県三国(坂井市)から越前町あたりの料理と言うことになる。今回の作り方は、書籍の記述だけではなく、三国同様「塩いり」を作る石川県加賀市塩屋での話も参考にした。といっても料理法などというような複雑なものではない。少量の水にやや多めの塩とほんの少しの酒を加える。煮立った中に、ざっと水洗いした「甘エビ(ホッコクアカエビ)」をいれて箸で動かしながらいり煮する。ほんの1分かからず火が通る。火を通しすぎると身が痩せる。酒を加えたのと加えていないのを両方作ったが酒は必ずしも誓う必要はないとみた。 三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。
三重県尾鷲市、岩田昭人さんとのつき合いも長い。お世話にもなり、いろんなことを教えてもらっているので、足を尾鷲に向けて眠ったことはない。岩田さんは尾鷲の地元民であり、土の人である。普段食べているものは尾鷲市周辺の食そのものだ。その岩田さんがFBに載せていた、「茶じふ」を作ってみた。尾鷲など東紀州で「じふ」というと、サバ類やマンボウを使ったすき焼き風の「じふ」もある。魚の茶漬けも「じふ」、というのが郷土料理ならでは、で面白い。新鮮なカツオの刺身を熱いご飯に乗せて、茶をかけ、醤油を垂らして食らうというものだ。ちなみに醤油は茶をかける前にたらしてもいいと思う。これ東京神田生まれの古今亭志ん生の好物である、「まぐ茶(志ん生のはクロマグロ)」のカツオ判とでもいったもので作り方はほぼ同じ。料理ではなく食べ方で、非常に日常的なものでもある。 「茶がゆ」を初めて食べたのは、学生の時で、夏真っ盛りの晴れた日、多武峰談山神社(奈良県桜井市)から桜井駅まで歩いた、その途中で、だ。今、地図を見ると崇峻天皇陵のあたりだと推測する。当時は文献地図帖を持っての旅で、一本道を下りながら、ゆるやかに遭難したのだ。あのとき、農家らしい家の方が、大量の水と茶がゆを恵んでくれなかったら、死んでいたのかも知れない。当時は熱中症という言葉はなく、熱射病だった。あのときの水のおいしかったことと、梅干しと茶がゆが喉を通ったときの感覚は今でもおぼえている。以来、「茶がゆ」は夏の味である。さて、遅摘みの茶をしんなりさせて、釜で煎るタイプのお茶は、西日本各地にあるが、不思議なことに、ボクが勝手に「茶がゆ圏」としている奈良県、三重県西部、和歌山県のものは独特である。焙じる前の製法はわからないが、例えば同じ番茶と言われるものでも島根県伯太町(現米子市)のものとは似ても似つかないものだ。茶がゆ圏の番茶は苦味が強くどっしりと重い感じがする。伯太町の伯太番茶など限りなく軽く優しい味である。この、「茶がゆ圏」の古いタイプの番茶を探す旅がしてみたい。今回はその崇峻天皇陵近くで教わった通りのやり方で茶がゆをたいてみた。濃く煮だした奈良県十津川村の番茶に洗わない米を投入してたく、という奈良県ではもっとも一般的なやり方である。洗った米を投入すると、さらさらと軽い味になるし、茶色に染まる米粒の色も淡い。洗わないで入れると濃い茶色に米粒が染まり、かゆ自体が重い味になる。非常に濃く入れた茶の苦味が口にも喉にも残るが、この苦味が夏バテの薬なのではなかろうか。三重県伊賀市で会った赤目(三重県名張市)出身の大正生まれの女性は、「茶がゆ」は、「さいら(サンマ)」の丸干しと食べることが多かったという。当時の丸干しは木槌でよく叩かないと硬くて食べられなかったといが、この日合わせた三重県尾鷲市、『丸清北村商店』の丸干しは硬干しではあるけど、そのまま焼けば食べられる。
「茶がゆ」を初めて食べたのは、学生の時で、夏真っ盛りの晴れた日、多武峰談山神社(奈良県桜井市)から桜井駅まで歩いた、その途中で、だ。今、地図を見ると崇峻天皇陵のあたりだと推測する。当時は文献地図帖を持っての旅で、一本道を下りながら、ゆるやかに遭難したのだ。あのとき、農家らしい家の方が、大量の水と茶がゆを恵んでくれなかったら、死んでいたのかも知れない。当時は熱中症という言葉はなく、熱射病だった。あのときの水のおいしかったことと、梅干しと茶がゆが喉を通ったときの感覚は今でもおぼえている。以来、「茶がゆ」は夏の味である。さて、遅摘みの茶をしんなりさせて、釜で煎るタイプのお茶は、西日本各地にあるが、不思議なことに、ボクが勝手に「茶がゆ圏」としている奈良県、三重県西部、和歌山県のものは独特である。焙じる前の製法はわからないが、例えば同じ番茶と言われるものでも島根県伯太町(現米子市)のものとは似ても似つかないものだ。茶がゆ圏の番茶は苦味が強くどっしりと重い感じがする。伯太町の伯太番茶など限りなく軽く優しい味である。この、「茶がゆ圏」の古いタイプの番茶を探す旅がしてみたい。今回はその崇峻天皇陵近くで教わった通りのやり方で茶がゆをたいてみた。濃く煮だした奈良県十津川村の番茶に洗わない米を投入してたく、という奈良県ではもっとも一般的なやり方である。洗った米を投入すると、さらさらと軽い味になるし、茶色に染まる米粒の色も淡い。洗わないで入れると濃い茶色に米粒が染まり、かゆ自体が重い味になる。非常に濃く入れた茶の苦味が口にも喉にも残るが、この苦味が夏バテの薬なのではなかろうか。三重県伊賀市で会った赤目(三重県名張市)出身の大正生まれの女性は、「茶がゆ」は、「さいら(サンマ)」の丸干しと食べることが多かったという。当時の丸干しは木槌でよく叩かないと硬くて食べられなかったといが、この日合わせた三重県尾鷲市、『丸清北村商店』の丸干しは硬干しではあるけど、そのまま焼けば食べられる。 岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。
岡山県の郷土料理に「かけ汁」、「かけ飯」というのがある。児島湾などをはじめ、汽水域や浅場にいる魚を材料とするもので、岡山県を代表するものである。過去に様々な魚で作っているが今回作ったのはコノシロのかけ汁である。「このしろ(標準和名コノシロの成魚)」もしくは、「つなし(コノシロの若い個体、小型)」のミンチ(細かく叩いた身)からは非常に濃厚で味わい深いだしがでる。豊かなうま味があるのに、後味がよく軽い味わいで、食べ始めるととまらなくなる。ご飯がなくなると新たによそい、「かけ汁」をかけてかきこむと箸が止まらなくなる。ごぼう、にんじんなどの根菜が非常にいい役をこなしているのもわかる。日常的な安い魚を使って、これほどの味わい深い料理を生み出すとは、岡山県の食文化の奥深さを感じる。 あわただしいときによく作る、切り干し大根と薩摩揚げの煮物を小鉢に入れて、ご飯を食べながら、ときどき文字文字する。旅の準備中である。ボクの旅は水産生物を調べる旅だけど、旅先では四次元的にも調べるし、風土が作り出すありとあらゆるものを調べに行く。食に関する情報だけで、脳みそが破裂しそうになるくらい持ち帰ってくる。水産物以外の食べものも大量買いする。水産生物を見て買ってだけでは、水産生物と人との関わりはなにもわからない。短い旅だけど、少し勉強をしている。武田家はかの河内源氏の末裔で由緒ただしいし、金山を持っていたけど、中世的でありすぎた、とか、今川義元は国衆との結びつきの上で名家意識が強すぎたんじゃないかな? とかだ。遠江の中世史も読んでおきたかった、とかとか。行き先の人に昔何を食べていたなんてケータイを入れたりもする。
あわただしいときによく作る、切り干し大根と薩摩揚げの煮物を小鉢に入れて、ご飯を食べながら、ときどき文字文字する。旅の準備中である。ボクの旅は水産生物を調べる旅だけど、旅先では四次元的にも調べるし、風土が作り出すありとあらゆるものを調べに行く。食に関する情報だけで、脳みそが破裂しそうになるくらい持ち帰ってくる。水産物以外の食べものも大量買いする。水産生物を見て買ってだけでは、水産生物と人との関わりはなにもわからない。短い旅だけど、少し勉強をしている。武田家はかの河内源氏の末裔で由緒ただしいし、金山を持っていたけど、中世的でありすぎた、とか、今川義元は国衆との結びつきの上で名家意識が強すぎたんじゃないかな? とかだ。遠江の中世史も読んでおきたかった、とかとか。行き先の人に昔何を食べていたなんてケータイを入れたりもする。 『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)は机周りにおいて、ときどき拾い読みをしている。中でも「懐かしのカドザメ」にある「酢の物」の作り方は、非常に合理的で、しかもおいしい。ちなみに木村守克は1936年生まれなので戦中・戦後を生きている。この書籍はとても貴重である。家庭料理の出来上がるまでの時間は短ければ短いほどよく、できるだけ単純でなければならない。できるだけ手間を省いて、しかもおいしくなければならない。この点からしても、弘前の「酢の物」は、料理屋の料理人の料理よりも優れていると思っている。この「酢の物」が非常にうまいのである。見た目は大根おろしの白に、ゆでたネズミザメ(カドザメ。モウカザメとも)も白なので料理自体が白一色、地味なことこの上ないものだが、最近、家庭料理は格好つけすぎなのだ。見た目の割りにまずいレシピが雑誌などを見ていても多すぎる。この見た目の地味さに反してのおいしさには感動できる。食卓の一隅にあると、アン・ドゥ・トロワの次くらいに箸が伸びる。ネズミザメの身はまったくくせがない。しかも柔らかく、後から甘味を伴ったうま味がくる。そして大根おろしが甘酸っぱい。料理の考え方としておぼえておくと、他の素材にも生かせそうである。
『みちのく食物誌』(木村守克 路上社)は机周りにおいて、ときどき拾い読みをしている。中でも「懐かしのカドザメ」にある「酢の物」の作り方は、非常に合理的で、しかもおいしい。ちなみに木村守克は1936年生まれなので戦中・戦後を生きている。この書籍はとても貴重である。家庭料理の出来上がるまでの時間は短ければ短いほどよく、できるだけ単純でなければならない。できるだけ手間を省いて、しかもおいしくなければならない。この点からしても、弘前の「酢の物」は、料理屋の料理人の料理よりも優れていると思っている。この「酢の物」が非常にうまいのである。見た目は大根おろしの白に、ゆでたネズミザメ(カドザメ。モウカザメとも)も白なので料理自体が白一色、地味なことこの上ないものだが、最近、家庭料理は格好つけすぎなのだ。見た目の割りにまずいレシピが雑誌などを見ていても多すぎる。この見た目の地味さに反してのおいしさには感動できる。食卓の一隅にあると、アン・ドゥ・トロワの次くらいに箸が伸びる。ネズミザメの身はまったくくせがない。しかも柔らかく、後から甘味を伴ったうま味がくる。そして大根おろしが甘酸っぱい。料理の考え方としておぼえておくと、他の素材にも生かせそうである。 2024年8月19日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室産11kgのブリを、もちろん丸ごとではなく、半身を買う。ちなみに最近、北海道のブリのほとんどが活ジメである。外れがない。刺身にして背の1㎏上を塩蔵する。塩鰤である。我が家の塩鰤は松本の市場で出合った方達と、市内の魚屋、岐阜県飛騨地方の魚屋で聞いたとおりのやり方である。本来は浜で作るものだが、最近、松本平や飛騨地方では家庭や魚屋で切り身で作ることが多いという。大量の塩でまぶし、翌日水が出たら塩を足してまたまぶす。これを1週間繰り返して、密閉する。以上は前回、前々回も書いた。塩ブリはときどき、気がついたように切り取って食べている。塩の中で回転させて長々と塩蔵にしたので、切り身の芯の部分にまで塩が入っている。
2024年8月19日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室産11kgのブリを、もちろん丸ごとではなく、半身を買う。ちなみに最近、北海道のブリのほとんどが活ジメである。外れがない。刺身にして背の1㎏上を塩蔵する。塩鰤である。我が家の塩鰤は松本の市場で出合った方達と、市内の魚屋、岐阜県飛騨地方の魚屋で聞いたとおりのやり方である。本来は浜で作るものだが、最近、松本平や飛騨地方では家庭や魚屋で切り身で作ることが多いという。大量の塩でまぶし、翌日水が出たら塩を足してまたまぶす。これを1週間繰り返して、密閉する。以上は前回、前々回も書いた。塩ブリはときどき、気がついたように切り取って食べている。塩の中で回転させて長々と塩蔵にしたので、切り身の芯の部分にまで塩が入っている。 先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。くどいようだが、1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域本来の食文化が破壊される前である。郷土料理は急速に失われつつある。実際、小田原魚市場で「魚玉茶漬」を知っているか、聞いてもだれも知りはしない。さて、ご飯をチンするところから。
先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。くどいようだが、1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域本来の食文化が破壊される前である。郷土料理は急速に失われつつある。実際、小田原魚市場で「魚玉茶漬」を知っているか、聞いてもだれも知りはしない。さて、ご飯をチンするところから。 どんちっちあじは脂がのっていた。ただ、それにしても刺身ばかりでは飽きる。そこで作ったのが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という魚玉茶漬だ。1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域の本来の食文化が破壊される前である。卵と醤油で作る漬けは、愛媛県南部の「鯛飯」の食べ方に似ているが、あちらは生醤油ではなく、加減醤油を使うし、あちらは漬けではなく、即席で作る。要するに玉子(卵)と醤油の地に漬け込んだものをご飯にのせて、熱い番茶にのせて食べるものなので、小田原のものは家庭料理の延長線にあるのだろう。正確には醤油卵で、醤油の比率の方が高い。この地で漬けにしただけのもので、それだけで食べておいしいとは予想できなかった。脂が乗ったマアジだからかも知れないが、単なる漬けよりも味の奥行きを感じる。意外性のある、味である。これを熱々のご飯の上に乗せて、番茶をそそぐ。あとは茶漬けなのでしゃばしゃばと。もの足りなかったら、ちょっと醤油卵を足して、味を調えて食べる。今回は辛味は使わなかったけど、わさびが合うと思う。小田原に行ったら、みなに食べたことがあるか、聞かなくては。それにしても、小田原にこんな名物があったなんて。
どんちっちあじは脂がのっていた。ただ、それにしても刺身ばかりでは飽きる。そこで作ったのが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という魚玉茶漬だ。1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域の本来の食文化が破壊される前である。卵と醤油で作る漬けは、愛媛県南部の「鯛飯」の食べ方に似ているが、あちらは生醤油ではなく、加減醤油を使うし、あちらは漬けではなく、即席で作る。要するに玉子(卵)と醤油の地に漬け込んだものをご飯にのせて、熱い番茶にのせて食べるものなので、小田原のものは家庭料理の延長線にあるのだろう。正確には醤油卵で、醤油の比率の方が高い。この地で漬けにしただけのもので、それだけで食べておいしいとは予想できなかった。脂が乗ったマアジだからかも知れないが、単なる漬けよりも味の奥行きを感じる。意外性のある、味である。これを熱々のご飯の上に乗せて、番茶をそそぐ。あとは茶漬けなのでしゃばしゃばと。もの足りなかったら、ちょっと醤油卵を足して、味を調えて食べる。今回は辛味は使わなかったけど、わさびが合うと思う。小田原に行ったら、みなに食べたことがあるか、聞かなくては。それにしても、小田原にこんな名物があったなんて。 個人的に料理はできるだけ簡単に、時間は短く、こだわりを捨てて作りたい。料理の距離は1ミクロンでも短く、だ。意外にそのような、どうでもいい感じの料理の方がうまい。遙か昔の昔、親戚のおばちゃんが作った、竹の子のたいたんが、いまだに心に残っているが、作っているところなんざー、見ていられませんといったいい加減なものなのである。だけど、竹の子1本食い切るくらいにうまい。これが家庭料理の神髄なのだ。さて、酢のもん(酢のもの)の話だ。ボクの故郷は徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)だが、親戚の多くは、吉野川の対岸にある美馬町(現美馬市美馬町)に住んでいた。だから再三再四、美馬町に、赤い美馬橋を渡って行ったいたものである。さて、そんな美馬町も我が貞光町でも、日常的にも冠婚葬祭のときにも作っていたのが、じゃこ(ちりめんじゃこ/カタクチイワシの稚魚をゆでて干したもの)と鳴門ワカメと、きゅうりの酢のもんである。作り置きすると10日間くらい食べ続けられる。食卓にあるとありがたいもので、要するに保存食だ。
個人的に料理はできるだけ簡単に、時間は短く、こだわりを捨てて作りたい。料理の距離は1ミクロンでも短く、だ。意外にそのような、どうでもいい感じの料理の方がうまい。遙か昔の昔、親戚のおばちゃんが作った、竹の子のたいたんが、いまだに心に残っているが、作っているところなんざー、見ていられませんといったいい加減なものなのである。だけど、竹の子1本食い切るくらいにうまい。これが家庭料理の神髄なのだ。さて、酢のもん(酢のもの)の話だ。ボクの故郷は徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)だが、親戚の多くは、吉野川の対岸にある美馬町(現美馬市美馬町)に住んでいた。だから再三再四、美馬町に、赤い美馬橋を渡って行ったいたものである。さて、そんな美馬町も我が貞光町でも、日常的にも冠婚葬祭のときにも作っていたのが、じゃこ(ちりめんじゃこ/カタクチイワシの稚魚をゆでて干したもの)と鳴門ワカメと、きゅうりの酢のもんである。作り置きすると10日間くらい食べ続けられる。食卓にあるとありがたいもので、要するに保存食だ。 ミクリガイの仲間(エゾバイ科ミクリガイ属)は、主に煮て食べる巻き貝である。煮て食べる巻き貝には、同じエゾバイ科の「磯つぶ(エゾバイ)」、「白ばい(エッチュウバイ)」、バイ科のバイなどがあるが、味の点ではこれらを凌ぐと思っている。比較的通好みの、知る人ぞ知る、といった巻き貝だが、この小さな巻き貝のことも知って置いて損はないだろう。ミクリガイの仲間の巻き貝はみな小さいく、模様が様々でとても美しい。本州、四国、九州の比較的暖かい浅い海域で至って普通に見られる。食用となるミクリガイ属はミクリガイ、九州東シナ海側のクロスジミクリ(ミクリガイとされることが多い)、ミオツクシ、シマアラレミクリ、トウイトガイ、マユツクリガイなどだ。ときどき市場流通もするが、産地周辺で消費されることが多い。このわずかに市場流通していたものが、ここ十年来、より希なものとなっている。明らかに生息数が減少しているのだと思うし、浅場のカゴ漁など貝をとる漁が衰退しているのもある。そして最大の、減少の原因は、日本列島の海岸線の乱開発だと思っている。沿岸域の浅場では、今、巻き貝など軟体類だけではなく、魚類も減少傾向にある。ミクリガイの仲間で比較的見かける機会が多いのはミクリガイだ。ときどき全国流通もするが、同種内での色・模様や形の変化が大きい上に、非常に地方名が多いため、貝専門の仲卸(市場の魚屋)にすら認知度が低い。また、近年、プロの料理人の水産物への関心が、ますます薄れている気がする。今やプロといえども、目立つものには強い関心を示すのに、地味なものには無関心なのである。流通が不安定なものは儲からないので、ミクリガイの仲間には興味がわかないというのもあるだろう。■写真は愛知県西尾市一色産ミクリガイ。
ミクリガイの仲間(エゾバイ科ミクリガイ属)は、主に煮て食べる巻き貝である。煮て食べる巻き貝には、同じエゾバイ科の「磯つぶ(エゾバイ)」、「白ばい(エッチュウバイ)」、バイ科のバイなどがあるが、味の点ではこれらを凌ぐと思っている。比較的通好みの、知る人ぞ知る、といった巻き貝だが、この小さな巻き貝のことも知って置いて損はないだろう。ミクリガイの仲間の巻き貝はみな小さいく、模様が様々でとても美しい。本州、四国、九州の比較的暖かい浅い海域で至って普通に見られる。食用となるミクリガイ属はミクリガイ、九州東シナ海側のクロスジミクリ(ミクリガイとされることが多い)、ミオツクシ、シマアラレミクリ、トウイトガイ、マユツクリガイなどだ。ときどき市場流通もするが、産地周辺で消費されることが多い。このわずかに市場流通していたものが、ここ十年来、より希なものとなっている。明らかに生息数が減少しているのだと思うし、浅場のカゴ漁など貝をとる漁が衰退しているのもある。そして最大の、減少の原因は、日本列島の海岸線の乱開発だと思っている。沿岸域の浅場では、今、巻き貝など軟体類だけではなく、魚類も減少傾向にある。ミクリガイの仲間で比較的見かける機会が多いのはミクリガイだ。ときどき全国流通もするが、同種内での色・模様や形の変化が大きい上に、非常に地方名が多いため、貝専門の仲卸(市場の魚屋)にすら認知度が低い。また、近年、プロの料理人の水産物への関心が、ますます薄れている気がする。今やプロといえども、目立つものには強い関心を示すのに、地味なものには無関心なのである。流通が不安定なものは儲からないので、ミクリガイの仲間には興味がわかないというのもあるだろう。■写真は愛知県西尾市一色産ミクリガイ。 秋田県男鹿市船川の漁師、近藤亮さんにワカメをいただいた。男鹿のワカメは、鮮度がいいことはもちろん、葉先・茎は柔らかく、めかぶはよくねばり、でとてもいいワカメだ。荷物の中に出来上がった「とろとろわかめ(とろとろワカメ)」が入っていた。秋田県男鹿半島だけのもので、男鹿名物といってもいいだろう。「めかぶ」のようなねばりけではなく、名前のように「とろとろ」としている。ボクにはまったく新しい味覚である。朝ご飯にあると実にありがたい。
秋田県男鹿市船川の漁師、近藤亮さんにワカメをいただいた。男鹿のワカメは、鮮度がいいことはもちろん、葉先・茎は柔らかく、めかぶはよくねばり、でとてもいいワカメだ。荷物の中に出来上がった「とろとろわかめ(とろとろワカメ)」が入っていた。秋田県男鹿半島だけのもので、男鹿名物といってもいいだろう。「めかぶ」のようなねばりけではなく、名前のように「とろとろ」としている。ボクにはまったく新しい味覚である。朝ご飯にあると実にありがたい。 今回も神奈川県小田原魚市場、二宮定置のみなさんに体長21cm〜22cmのマアジをいただいてきた。まことに感謝感激、とてもありがとう。まだ脂の乗りはイマイチだけど、うま味は豊かである。帰宅後に昼ご飯のおかず、煮つけを作った。たまり醤油・濃口醤油と砂糖・酒のこってこってのご飯用煮つけだ。
今回も神奈川県小田原魚市場、二宮定置のみなさんに体長21cm〜22cmのマアジをいただいてきた。まことに感謝感激、とてもありがとう。まだ脂の乗りはイマイチだけど、うま味は豊かである。帰宅後に昼ご飯のおかず、煮つけを作った。たまり醤油・濃口醤油と砂糖・酒のこってこってのご飯用煮つけだ。 ここ数日、使っている福島県只見町、目黒麹店のみそが非常によい。みそ仕立ての「どんこ汁」は汁からすするのだけど、このみそ、甘味がほとんどなく、あっさりしていながら味がある。生でも汁にしてもいい。「どんこ(チゴダラ)」のだしが、「どんこ」の味として楽しめる。じゃまをしない。「どんこ汁」は肝と一緒にひとすすりすると、やけに重圧な味で、おいしさが大きいのに、後味がきわめていい。寒い朝に胃袋のあたりにカイロを当てたような感じになる。くせのない上品な白身が、みそと一緒になって、味わいのあるものに変身する。根切りの九条ねぎがやけにおいしいのも不思議だ。汁なのにごちそうである。しかもたぶん酒にも合うだろう。そしてご飯には合いすぎる。汁だけで大盛りご飯が食べられる。デブなので5勺の飯で我慢する、のは滅法つらい。
ここ数日、使っている福島県只見町、目黒麹店のみそが非常によい。みそ仕立ての「どんこ汁」は汁からすするのだけど、このみそ、甘味がほとんどなく、あっさりしていながら味がある。生でも汁にしてもいい。「どんこ(チゴダラ)」のだしが、「どんこ」の味として楽しめる。じゃまをしない。「どんこ汁」は肝と一緒にひとすすりすると、やけに重圧な味で、おいしさが大きいのに、後味がきわめていい。寒い朝に胃袋のあたりにカイロを当てたような感じになる。くせのない上品な白身が、みそと一緒になって、味わいのあるものに変身する。根切りの九条ねぎがやけにおいしいのも不思議だ。汁なのにごちそうである。しかもたぶん酒にも合うだろう。そしてご飯には合いすぎる。汁だけで大盛りご飯が食べられる。デブなので5勺の飯で我慢する、のは滅法つらい。 磯周りにいるメジナ、クロメジナ、イシダイ、イシガキダイ、イサキ、タカノハダイ、ニザダイなどを皮付きのまま、皮の方を焼いて切りつけたものを、高知県などでは「焼き切り(焼き切れ)」という。熱が通っているのは皮周辺だけで、明らかに魚の生食だ。高知県室戸などでは主に漁師の料理だという。一部の地域でサバ科の魚も使うが、ここでは切り放して考えていきたい。食物民族学者の近藤弘はこれを「ヤキギリ文化」としている。「焼き切り」、「焼き切れ」、「焼きたたき」、「たたき」など様々な呼び名があるが、この「ヤキギリ文化」とすると確かに整理しやすい。また、近藤弘は〈薩摩(鹿児島県)から土佐(高知県)の一切、柏島(ともに幡多郡大月町)を経て足摺岬まで分布していた。〉に「ヤキギリ文化」が存在すると考えていたようだ。実際は高知県室戸市三津・東洋町、徳島県海部郡海陽町宍喰にも存在している。また島根県隠岐諸島中ノ島では「皮焼き」というらしい。近藤弘は鮮度がよすぎる魚を食べるための料理法だとしている。とれたてはアデノシン三リン酸がイノシンに分解していない、これを熱を通すことでうま味を引き出すためだとしている。現在のところ、確認できているのは、徳島県(たたき)、高知県(焼き切れ)、愛媛県(焼き切り)、宮崎県(焼き切り)、鹿児島県(焼き切り)である。徳島県と室戸市のは焼いて、並べて塩・柚子を手に付けて叩くというのが入る。この手順が加わることを近藤弘はまた〈数歩進歩した生食の仕方。〉といっている。産地の漁師さんなどに、この磯にいる白身魚の「ヤキギリ」を聞き取りしているが、整理のための土台がない。以後、本コラムを土台として整理していくつもりである。■写真は大分県日田市で出会った佐伯市の方に教わったものだが、土着的なものであるのかは不明である。
磯周りにいるメジナ、クロメジナ、イシダイ、イシガキダイ、イサキ、タカノハダイ、ニザダイなどを皮付きのまま、皮の方を焼いて切りつけたものを、高知県などでは「焼き切り(焼き切れ)」という。熱が通っているのは皮周辺だけで、明らかに魚の生食だ。高知県室戸などでは主に漁師の料理だという。一部の地域でサバ科の魚も使うが、ここでは切り放して考えていきたい。食物民族学者の近藤弘はこれを「ヤキギリ文化」としている。「焼き切り」、「焼き切れ」、「焼きたたき」、「たたき」など様々な呼び名があるが、この「ヤキギリ文化」とすると確かに整理しやすい。また、近藤弘は〈薩摩(鹿児島県)から土佐(高知県)の一切、柏島(ともに幡多郡大月町)を経て足摺岬まで分布していた。〉に「ヤキギリ文化」が存在すると考えていたようだ。実際は高知県室戸市三津・東洋町、徳島県海部郡海陽町宍喰にも存在している。また島根県隠岐諸島中ノ島では「皮焼き」というらしい。近藤弘は鮮度がよすぎる魚を食べるための料理法だとしている。とれたてはアデノシン三リン酸がイノシンに分解していない、これを熱を通すことでうま味を引き出すためだとしている。現在のところ、確認できているのは、徳島県(たたき)、高知県(焼き切れ)、愛媛県(焼き切り)、宮崎県(焼き切り)、鹿児島県(焼き切り)である。徳島県と室戸市のは焼いて、並べて塩・柚子を手に付けて叩くというのが入る。この手順が加わることを近藤弘はまた〈数歩進歩した生食の仕方。〉といっている。産地の漁師さんなどに、この磯にいる白身魚の「ヤキギリ」を聞き取りしているが、整理のための土台がない。以後、本コラムを土台として整理していくつもりである。■写真は大分県日田市で出会った佐伯市の方に教わったものだが、土着的なものであるのかは不明である。 ネズミザメの食の歴史は有史以前からだと思うが詳しくはわからないが、明治時代以前から重要な食用魚であったことは間違いない。実際、1945年の敗戦後も国内中部千布の一部、北陸地方の一部、東日本ではもっとも一般的な食用魚だった。このネズミザメの食文化は衰退気味であるが、それでも根強く日本各地に残っている。中でも岐阜県飛騨地方(現高山市・飛驒市・下呂市がそれに当たると考えている)でのネズミザメの食文化は独特の進化を遂げている。例えば夏場の塩分補給の意味で「塩もーか(ネズミザメの塩蔵品)」や、生で送られて来たものを刺身にしたり、鍋ものにしたりもする。今回は飛騨地方の郷土料理「ぼた鍋」を作ってみた。生の「ぼた」、ネズミザメの塊が入荷したときに作るものである。単純に切り身と野菜などを鍋にしたもので、一般的には「水炊き」といったところだろう。生のネズミザメを買ってきて、適当に切る。これを最初水だけで煮て、あくをすくい、野菜などと煮てみた。これでも充分おいしいけど、つけたポン酢の味に負けている気がした。鍋を替えて昆布だし・酒・塩であくをすくいながら煮る。ここに野菜とか豆腐を加えて煮ながら食べたら、実に味わい深い。鶏のささみを思わせる食感だが、もっと味は軽い。柔らかいのでだしと一緒くたになって食べられるのがうれしい。この鍋なら日を明かさず食べられるし、寒い時季など毎日食べても飽きない味でもある。飛騨地方で愛されてきたわけもわかる。今現在、多くの人に受け入れられる味でもあり、郷土料理として絶やして欲しくはない。
ネズミザメの食の歴史は有史以前からだと思うが詳しくはわからないが、明治時代以前から重要な食用魚であったことは間違いない。実際、1945年の敗戦後も国内中部千布の一部、北陸地方の一部、東日本ではもっとも一般的な食用魚だった。このネズミザメの食文化は衰退気味であるが、それでも根強く日本各地に残っている。中でも岐阜県飛騨地方(現高山市・飛驒市・下呂市がそれに当たると考えている)でのネズミザメの食文化は独特の進化を遂げている。例えば夏場の塩分補給の意味で「塩もーか(ネズミザメの塩蔵品)」や、生で送られて来たものを刺身にしたり、鍋ものにしたりもする。今回は飛騨地方の郷土料理「ぼた鍋」を作ってみた。生の「ぼた」、ネズミザメの塊が入荷したときに作るものである。単純に切り身と野菜などを鍋にしたもので、一般的には「水炊き」といったところだろう。生のネズミザメを買ってきて、適当に切る。これを最初水だけで煮て、あくをすくい、野菜などと煮てみた。これでも充分おいしいけど、つけたポン酢の味に負けている気がした。鍋を替えて昆布だし・酒・塩であくをすくいながら煮る。ここに野菜とか豆腐を加えて煮ながら食べたら、実に味わい深い。鶏のささみを思わせる食感だが、もっと味は軽い。柔らかいのでだしと一緒くたになって食べられるのがうれしい。この鍋なら日を明かさず食べられるし、寒い時季など毎日食べても飽きない味でもある。飛騨地方で愛されてきたわけもわかる。今現在、多くの人に受け入れられる味でもあり、郷土料理として絶やして欲しくはない。 新潟県上越市直江津と、上越市高田と妙高市全域はともによくサメを食べるものの、違うサメ食文化である。海辺の直江津で食べるのは主に「むきざめ(アブラツノザメ)」であり、上越高田・妙高では「むきざめ」も食べるが「ふかざめ(ネズミザメ)」の比率が高い。ネズミザメ科のネズミザメ・アオザメと、ツノザメ科のアブラツノザメなどとの食べ方の違いはなにか?生食するか否かである。ツノザメ科のサメは希に生で食べることもあるが、一般的に生で食べる地域はない。ネズミザメ科のサメは少ないながら、好んで生で食べる地域がある。そしてそれが現在にまで続いている地域は、新潟県上越市と広島県備北地方だけだと思う。上越市の年越しにもっとも広範囲に作られているのが「ふかざめ」料理であるが、ここに「ぬた」がある。「ぬた」なのでゆでて酢みそで和えるのだな、と思っていたら、もっと多彩であった。妙高市・上越市高田で聞取をしたら、まったくの生を酢みそで、表面を霜降り状にして酢みそで、かなりしっかりゆでて酢みそでの3通りであった。酢みそで食べるものの、まったく生ということは刺身である。刺身になるほど鮮度のいい「ふかざめ」を手に入れるために年末、宮城県気仙沼から丸のまま「ふかざめ」を送ってもらい、競売が行われているといっても過言ではない。これは明治時代も同様であるようだ。ネズミザメは日本海でも揚がる。上越市から糸魚川市で揚がったサメは海辺では積極的食べられることなく、山間部に送られて、様々な料理になり、刺身にもなっていたことになる。
新潟県上越市直江津と、上越市高田と妙高市全域はともによくサメを食べるものの、違うサメ食文化である。海辺の直江津で食べるのは主に「むきざめ(アブラツノザメ)」であり、上越高田・妙高では「むきざめ」も食べるが「ふかざめ(ネズミザメ)」の比率が高い。ネズミザメ科のネズミザメ・アオザメと、ツノザメ科のアブラツノザメなどとの食べ方の違いはなにか?生食するか否かである。ツノザメ科のサメは希に生で食べることもあるが、一般的に生で食べる地域はない。ネズミザメ科のサメは少ないながら、好んで生で食べる地域がある。そしてそれが現在にまで続いている地域は、新潟県上越市と広島県備北地方だけだと思う。上越市の年越しにもっとも広範囲に作られているのが「ふかざめ」料理であるが、ここに「ぬた」がある。「ぬた」なのでゆでて酢みそで和えるのだな、と思っていたら、もっと多彩であった。妙高市・上越市高田で聞取をしたら、まったくの生を酢みそで、表面を霜降り状にして酢みそで、かなりしっかりゆでて酢みそでの3通りであった。酢みそで食べるものの、まったく生ということは刺身である。刺身になるほど鮮度のいい「ふかざめ」を手に入れるために年末、宮城県気仙沼から丸のまま「ふかざめ」を送ってもらい、競売が行われているといっても過言ではない。これは明治時代も同様であるようだ。ネズミザメは日本海でも揚がる。上越市から糸魚川市で揚がったサメは海辺では積極的食べられることなく、山間部に送られて、様々な料理になり、刺身にもなっていたことになる。 栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の利根川水系周辺で初午の日に作るのが「しもつかれ」である。塩ザケの頭と大豆、にんじん、大根、油揚げ、酒粕、ときに酢を入れる人もいる。これを大鍋で煮るという料理で、この地域のものはほとんど変わらぬ作り方と、味だ。ところが福島県南会津町(旧舘岩村・伊南村・南郷村)では「つむづかり」と訛り、作り方も具材も違っている。基本的に南会津町岩下で分けていただいたものなので、南会津町全域が同じとは思えないものの、栃木県の「しもつかれ」とは似て非なるものである。南会津は栃木県の湯西川や日光、大田原市などと郷里が近く、当然、関わりも深い。「出稼ぎの地」でもある。「つむづかり」は栃木県から伝わったとされているが、取り分けこの「出稼ぎの地」から伝わった可能性が高い。聞取した限りでも栃木県から伝わったのは明治時代にまではたどれそうである。本来、栃木県の「しもつかれ」は旧暦の初午の日に作られていた。南会津では最初から新暦で作られているところにも明治時代以降の伝播だからではないかと思っている。■写真は2月の南会津町岩下。
栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の利根川水系周辺で初午の日に作るのが「しもつかれ」である。塩ザケの頭と大豆、にんじん、大根、油揚げ、酒粕、ときに酢を入れる人もいる。これを大鍋で煮るという料理で、この地域のものはほとんど変わらぬ作り方と、味だ。ところが福島県南会津町(旧舘岩村・伊南村・南郷村)では「つむづかり」と訛り、作り方も具材も違っている。基本的に南会津町岩下で分けていただいたものなので、南会津町全域が同じとは思えないものの、栃木県の「しもつかれ」とは似て非なるものである。南会津は栃木県の湯西川や日光、大田原市などと郷里が近く、当然、関わりも深い。「出稼ぎの地」でもある。「つむづかり」は栃木県から伝わったとされているが、取り分けこの「出稼ぎの地」から伝わった可能性が高い。聞取した限りでも栃木県から伝わったのは明治時代にまではたどれそうである。本来、栃木県の「しもつかれ」は旧暦の初午の日に作られていた。南会津では最初から新暦で作られているところにも明治時代以降の伝播だからではないかと思っている。■写真は2月の南会津町岩下。 ワタ煮は数日に亘って食べる。もちろん酒の肴である。消化管はこりこりして、ちょっとだけにょごっ、とする。噛みしめるとうま味が染み出してくる。肝はほくっとして甘く、舌にざらざらとうま味を残す。この内臓巡りの旅、こそが「わた煮」のよさだ。ブリのサイズも産地もわからない。ちゃんと魚屋に言えば、真子・白子入りもあるけど、次回持ち越し。酒は新潟県上越市、雪中梅の普通酒だ。
ワタ煮は数日に亘って食べる。もちろん酒の肴である。消化管はこりこりして、ちょっとだけにょごっ、とする。噛みしめるとうま味が染み出してくる。肝はほくっとして甘く、舌にざらざらとうま味を残す。この内臓巡りの旅、こそが「わた煮」のよさだ。ブリのサイズも産地もわからない。ちゃんと魚屋に言えば、真子・白子入りもあるけど、次回持ち越し。酒は新潟県上越市、雪中梅の普通酒だ。 毎年のことだけど2月の市場は客が少なく、魚介類も少ない。こんなときはイカだ、となる。昔はスルメイカが安かったので一択だったけど、最近、イカ全種が高いので、その日にいちばんお買い得なイカを買う。この朝、比較的お買い得だったのは、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にあったのは産地不明の雄のヤリイカである。最近、早朝に和菓子、11時くらいに朝昼兼用のご飯なので、使いたくない言語ではあるがブランチかも知れない。飯のおかずは作り方が簡単で、コツと言えるほどのコツがなく、皿に盛るまでが10分程度で作れるものがいい。
毎年のことだけど2月の市場は客が少なく、魚介類も少ない。こんなときはイカだ、となる。昔はスルメイカが安かったので一択だったけど、最近、イカ全種が高いので、その日にいちばんお買い得なイカを買う。この朝、比較的お買い得だったのは、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にあったのは産地不明の雄のヤリイカである。最近、早朝に和菓子、11時くらいに朝昼兼用のご飯なので、使いたくない言語ではあるがブランチかも知れない。飯のおかずは作り方が簡単で、コツと言えるほどのコツがなく、皿に盛るまでが10分程度で作れるものがいい。 国内で日常的にサメを食べる地域が年々減少している。あまりにも極端なサメのイメージが横行しているせいだし、あのジョーズのせいでもある。サメは古代より至って平凡な食用魚である。昔はアンモリアなどが身に混在して臭いものもあったが、現在流通するもので臭味のあるものは存在しない。なんの根拠もなく忌避されているサメは長年、日本列島の重要なたんぱく源であったし、人々を飢餓から救っていたのだ。1945年の敗戦後食糧難の時代、東京都多摩地区などでは需要が多すぎて、供給が追いつかなかったくらいだ。このサメの恐怖感を煽る人間は下劣である。さて、サメ食といってもサメの種類は地域によって違っている。サメ食というと広島県備北の庄原市、三次市がまず挙がるくらい、この地域は有名である。盆と正月に欠かせない魚でもある。この備北の山間部に送っていたのは、サメ漁を行っている島根県五十猛だとする説もある。この五十猛(現島根県大田市)から石見銀山の銀山街道をたどると三次に至る。江戸時代はこの流通経路が使われていたのだろう。現在、島根県の山間の地、奥出雲などでもサメが売られている。この流通経路でサメの食文化が広がったに違いない。当然、備北というよりも日本海から遠い地域と考えた方がいいのかも知れない。この地域のサメ食文化をになっていた鮮魚店が急激に閉店しているのも気になる。ここでは主に刺身で食べられている。煮凝りが作られているし、当然煮つけにもなる。ただ、この地域で食べられているサメの種が文献によってしかわからなかった。
国内で日常的にサメを食べる地域が年々減少している。あまりにも極端なサメのイメージが横行しているせいだし、あのジョーズのせいでもある。サメは古代より至って平凡な食用魚である。昔はアンモリアなどが身に混在して臭いものもあったが、現在流通するもので臭味のあるものは存在しない。なんの根拠もなく忌避されているサメは長年、日本列島の重要なたんぱく源であったし、人々を飢餓から救っていたのだ。1945年の敗戦後食糧難の時代、東京都多摩地区などでは需要が多すぎて、供給が追いつかなかったくらいだ。このサメの恐怖感を煽る人間は下劣である。さて、サメ食といってもサメの種類は地域によって違っている。サメ食というと広島県備北の庄原市、三次市がまず挙がるくらい、この地域は有名である。盆と正月に欠かせない魚でもある。この備北の山間部に送っていたのは、サメ漁を行っている島根県五十猛だとする説もある。この五十猛(現島根県大田市)から石見銀山の銀山街道をたどると三次に至る。江戸時代はこの流通経路が使われていたのだろう。現在、島根県の山間の地、奥出雲などでもサメが売られている。この流通経路でサメの食文化が広がったに違いない。当然、備北というよりも日本海から遠い地域と考えた方がいいのかも知れない。この地域のサメ食文化をになっていた鮮魚店が急激に閉店しているのも気になる。ここでは主に刺身で食べられている。煮凝りが作られているし、当然煮つけにもなる。ただ、この地域で食べられているサメの種が文献によってしかわからなかった。 ここ十年来、東京都内での「煮凝り」を調べている。都内に昔、たくさんあった蒲鉾店(おでん種など練り製品を作る店)や食品加工の会社では、寒くなると煮凝りを作り始め、師走になると正月用として魚屋、スーパー、市場にあふれかえっていた。本来の煮凝りは魚の煮つけを作って、煮汁に染み出してきたコラーゲン(ゼラチン)が自然に冷えて固まったもので、料理ではなく、料理の状態といったものだ。ここでいう煮凝りはコラーゲンの多い魚の部位を煮だして、コラーゲンの多い煮汁を作り。そのコラーゲンの素となる魚の部位を食べやすい大きさに切り、コラーゲンの多い煮汁に戻し、もう一度煮て味つけする。これを形に入れて固めるという料理であり、料理名である。これとまったく同じことが遙か離れた新潟県上越市高田、妙高市で行われているのである。12月前後になると魚屋やスーパーに「ふかざめ(ネズミザメ)の煮凝り」が並び始め。また「煮凝り」の材料である「ふかざめの皮」が売られる。海から離れたこの一帯で作られている「煮凝り」は東京のものとまったく同じ物だ。原料が宮城県で水揚げされている、ネズミザメの皮であること。(都内ではフグ皮、ヨシキリザメの皮でも少ないながら作られている)年取(正月の膳)の肴であることも同じである。不思議なことにサメの産地である宮城県で、正月に煮凝りを食べるという話を聞かない。とすると「サメの煮凝り」は東京の郷土料理と考えるべきだ。それが新潟県上越市で、しかも正月に食べられている。こんな偶然あるのだろうか?ちなみに東京都だけではなく埼玉県など周辺でも「煮凝り」が正月用品として出回っている。ただこれは明らかに東京からの影響である。上越地方は東京からすると実に遠い。なぜ同じ食文化がここにあるのだろう。ちなみに正月に「サメの煮凝り」を食べる地域はもっと多い可能性もある。
ここ十年来、東京都内での「煮凝り」を調べている。都内に昔、たくさんあった蒲鉾店(おでん種など練り製品を作る店)や食品加工の会社では、寒くなると煮凝りを作り始め、師走になると正月用として魚屋、スーパー、市場にあふれかえっていた。本来の煮凝りは魚の煮つけを作って、煮汁に染み出してきたコラーゲン(ゼラチン)が自然に冷えて固まったもので、料理ではなく、料理の状態といったものだ。ここでいう煮凝りはコラーゲンの多い魚の部位を煮だして、コラーゲンの多い煮汁を作り。そのコラーゲンの素となる魚の部位を食べやすい大きさに切り、コラーゲンの多い煮汁に戻し、もう一度煮て味つけする。これを形に入れて固めるという料理であり、料理名である。これとまったく同じことが遙か離れた新潟県上越市高田、妙高市で行われているのである。12月前後になると魚屋やスーパーに「ふかざめ(ネズミザメ)の煮凝り」が並び始め。また「煮凝り」の材料である「ふかざめの皮」が売られる。海から離れたこの一帯で作られている「煮凝り」は東京のものとまったく同じ物だ。原料が宮城県で水揚げされている、ネズミザメの皮であること。(都内ではフグ皮、ヨシキリザメの皮でも少ないながら作られている)年取(正月の膳)の肴であることも同じである。不思議なことにサメの産地である宮城県で、正月に煮凝りを食べるという話を聞かない。とすると「サメの煮凝り」は東京の郷土料理と考えるべきだ。それが新潟県上越市で、しかも正月に食べられている。こんな偶然あるのだろうか?ちなみに東京都だけではなく埼玉県など周辺でも「煮凝り」が正月用品として出回っている。ただこれは明らかに東京からの影響である。上越地方は東京からすると実に遠い。なぜ同じ食文化がここにあるのだろう。ちなみに正月に「サメの煮凝り」を食べる地域はもっと多い可能性もある。 飯綱町で滝澤農園を営んでいる滝澤卓さんが、なぜ、滝澤賢さんになったのだろうか、はともかく……。飯綱町では、「ふきのとうみそ」でお握りを作ってリンゴ作りの合間に、畑で食べているという。もちろん農作業の合間に畑で食べた方がおいしかろう。
飯綱町で滝澤農園を営んでいる滝澤卓さんが、なぜ、滝澤賢さんになったのだろうか、はともかく……。飯綱町では、「ふきのとうみそ」でお握りを作ってリンゴ作りの合間に、畑で食べているという。もちろん農作業の合間に畑で食べた方がおいしかろう。 「浜から山(里)へ」は水産流通の基本である。海でとれたものを塩をするか、焼くかして山に向かって売りに行くことでこの国の食料の循環が行われていたのである。例えば塩をするか、焼くかしたサバ(マサバ)を山に運び、米や米ぬかと交換することで浜は糖質を補給していた。山の人は動物たんぱくを得られた。この浜から山へ、山から浜へを考えていきたい。新潟の浜では古くから魚を早朝から炭火で焼き上げ、山間部に運んでいた。いったいどんな魚を焼いていたのか?新潟市本町での、炭火に串に刺された光景は絵になるので、多くの書籍に写真はあるが、その魚の種類までは載っていない。農文協の聞き書きシリーズにもない。1988年の『新潟料理 ふるさとの味』(桜井薫 新潟日報事業社)に〈イカ、サバ、カレイ、アナゴ、ギス〉とある。それぞれスルメイカ、マサバ、マガレイ、クロメクラウナギ、ニギスである。カレイは日本海側では青森県から富山県まではマガレイ、石川県、福井県がアカガレイだと思っている。みな地先の浜でたっぷりとれていたものばかりである。ちなみにマガレイを海辺の魚屋で焼いて売るというのは、新発田市や村上市にもある。山形県でも同じである。新潟市の浜焼きは、何度も買い求めている。その光景以上に魅力的なのが、その香りである。見ていると食べたくなのは、この香りのせいだ。とても丸々一尾は食べられないが、冷めてもおいしいところも魅力である。寺泊は今や観光地と化しているが、ここも浜焼きが有名である。もうひとつの浜焼きの町が出雲崎である。1980年代に二度も行って、二度とも買っているが、ただ単に買って食べただけで終わっている。2004年にも浜焼きを買っているものの、なぜか画像がない。残念なことに焼いている時間には一度も行き会わせていない。4度目の出雲崎なので、今回こそは焼いているところを見てみたかった。細長い出雲崎の海岸線の集落に沿って南北にバイパスが、しかも海側にできていた。出雲崎の集落と狭い道は相変わらずつげ義春が好きそうな影の多い家並みで、一安心したが、こんな道路、ほんとうに必要なんだろうか?いい道路を造ったら人が来る、そう思っているのは土建屋さんと行政、政治家だけだろう。古い町並みを少し歩いてみたが、町は完全に寝静まっていて、車さえ通らない。
「浜から山(里)へ」は水産流通の基本である。海でとれたものを塩をするか、焼くかして山に向かって売りに行くことでこの国の食料の循環が行われていたのである。例えば塩をするか、焼くかしたサバ(マサバ)を山に運び、米や米ぬかと交換することで浜は糖質を補給していた。山の人は動物たんぱくを得られた。この浜から山へ、山から浜へを考えていきたい。新潟の浜では古くから魚を早朝から炭火で焼き上げ、山間部に運んでいた。いったいどんな魚を焼いていたのか?新潟市本町での、炭火に串に刺された光景は絵になるので、多くの書籍に写真はあるが、その魚の種類までは載っていない。農文協の聞き書きシリーズにもない。1988年の『新潟料理 ふるさとの味』(桜井薫 新潟日報事業社)に〈イカ、サバ、カレイ、アナゴ、ギス〉とある。それぞれスルメイカ、マサバ、マガレイ、クロメクラウナギ、ニギスである。カレイは日本海側では青森県から富山県まではマガレイ、石川県、福井県がアカガレイだと思っている。みな地先の浜でたっぷりとれていたものばかりである。ちなみにマガレイを海辺の魚屋で焼いて売るというのは、新発田市や村上市にもある。山形県でも同じである。新潟市の浜焼きは、何度も買い求めている。その光景以上に魅力的なのが、その香りである。見ていると食べたくなのは、この香りのせいだ。とても丸々一尾は食べられないが、冷めてもおいしいところも魅力である。寺泊は今や観光地と化しているが、ここも浜焼きが有名である。もうひとつの浜焼きの町が出雲崎である。1980年代に二度も行って、二度とも買っているが、ただ単に買って食べただけで終わっている。2004年にも浜焼きを買っているものの、なぜか画像がない。残念なことに焼いている時間には一度も行き会わせていない。4度目の出雲崎なので、今回こそは焼いているところを見てみたかった。細長い出雲崎の海岸線の集落に沿って南北にバイパスが、しかも海側にできていた。出雲崎の集落と狭い道は相変わらずつげ義春が好きそうな影の多い家並みで、一安心したが、こんな道路、ほんとうに必要なんだろうか?いい道路を造ったら人が来る、そう思っているのは土建屋さんと行政、政治家だけだろう。古い町並みを少し歩いてみたが、町は完全に寝静まっていて、車さえ通らない。 「たら汁」は日本各北陸以北、東北で作られているものだが。青森県の「じゃっぱ汁」、秋田県の「たら汁」、山形県の「どんがら汁」などはマダラで作る。新潟県以西は主に「たら(「すけそ」とも。スケトウダラ)」で作る。塩味の汁、醤油味、みそ味などいろいろあるが、新潟県はなんだろう? と思っていたら、上越市では「粕汁」だという。「粕汁」と初めて出合ったのは秋田県横手市だが、あまりにも塩辛いのでビックリして味がよくわからなかった。以来粕汁とは長々と縁がなかった。だいたいみそ汁に酒粕を入れる文化は、ボクの生まれた四国の町にはなかった。実際、上越市内のスーパーに行くと、酒粕がたらの切り身の横に置いてある。「ばら粕」というばらけた酒粕で、ちょうど手に取っていたバアチャンに作り方を聞いたら、最初に湯の中で酒粕を溶かしておくのがコツで、あとは「たらのみそ汁を作ればいい」のだという。大根やニンジンを入れるといいと聞いたけど、やめた。とにかく大量に作って正月を越そうと思ったのだ。作りたてはみそと酒粕のせいで、ちょっと濃厚な味わいではあるが、さほど感心できる味ではなかった。酒粕のアルコールが残っている気がして、少し煮込んでみたが、やはり味は平凡だった。想像したよりは、うまい、といったところだ。
「たら汁」は日本各北陸以北、東北で作られているものだが。青森県の「じゃっぱ汁」、秋田県の「たら汁」、山形県の「どんがら汁」などはマダラで作る。新潟県以西は主に「たら(「すけそ」とも。スケトウダラ)」で作る。塩味の汁、醤油味、みそ味などいろいろあるが、新潟県はなんだろう? と思っていたら、上越市では「粕汁」だという。「粕汁」と初めて出合ったのは秋田県横手市だが、あまりにも塩辛いのでビックリして味がよくわからなかった。以来粕汁とは長々と縁がなかった。だいたいみそ汁に酒粕を入れる文化は、ボクの生まれた四国の町にはなかった。実際、上越市内のスーパーに行くと、酒粕がたらの切り身の横に置いてある。「ばら粕」というばらけた酒粕で、ちょうど手に取っていたバアチャンに作り方を聞いたら、最初に湯の中で酒粕を溶かしておくのがコツで、あとは「たらのみそ汁を作ればいい」のだという。大根やニンジンを入れるといいと聞いたけど、やめた。とにかく大量に作って正月を越そうと思ったのだ。作りたてはみそと酒粕のせいで、ちょっと濃厚な味わいではあるが、さほど感心できる味ではなかった。酒粕のアルコールが残っている気がして、少し煮込んでみたが、やはり味は平凡だった。想像したよりは、うまい、といったところだ。 「しか煮」はソウダガツオ属と玉ねぎを使って作る、「すき焼き」風の煮物で、神奈川県小田原・真鶴の郷土料理だ。高い牛肉・豚肉ではなく、海に近いところなので安い魚で代用したものだ。このソウダガツオを使った「すき焼き風惣菜」に対して「しか煮」という言語がなぜ生まれたのかはわからない。漢字は「鹿煮」だという人がいる。鹿肉のような味がするためらしい。また四角く切って作るので「四角煮」が「しか煮」になったとも。基本的には「うずわ(マルソウダ)」で作るらしく、「『うずわ』でなければおいしくない」、「『うずわ』で作るから『しか煮』だ」という人もいる。もちろん、「そうだ(ヒラソウダ)」でもいいという人もいる。確かに「うずわ(マルソウダ)」で作ると煮て硬く締まり、この硬さが肉(鹿肉)を思わせる。うま味も豊かである。対するに「そうだ(ヒラソウダ)」は煮ると軟らかく、うま味は「うずわ」と比べると少ない。「うずわ(マルソウダ)」よりも魚の煮つけ的な味だ。比較しなければどちらもおいしいが、水揚げされているのを見て、どちらを選ぶかと言われると、「うずわ(マルソウダ)」を手に取ることになる。今のところ、神奈川県小田原市・真鶴町だけの料理のようだが、調べていく内に作っている地域が広がったり、逆に狭まったりする可能性がある。本料理は小田原市鴨宮にある鮮魚店『魚竹』さんと、小田原市江之浦、江の安 ワタルさん夫婦に教わったもの。また、『魚竹』さんはジャガイモを入れて、「肉じゃが風」にするというので、こちらも作ってみた。協力に感謝します。
「しか煮」はソウダガツオ属と玉ねぎを使って作る、「すき焼き」風の煮物で、神奈川県小田原・真鶴の郷土料理だ。高い牛肉・豚肉ではなく、海に近いところなので安い魚で代用したものだ。このソウダガツオを使った「すき焼き風惣菜」に対して「しか煮」という言語がなぜ生まれたのかはわからない。漢字は「鹿煮」だという人がいる。鹿肉のような味がするためらしい。また四角く切って作るので「四角煮」が「しか煮」になったとも。基本的には「うずわ(マルソウダ)」で作るらしく、「『うずわ』でなければおいしくない」、「『うずわ』で作るから『しか煮』だ」という人もいる。もちろん、「そうだ(ヒラソウダ)」でもいいという人もいる。確かに「うずわ(マルソウダ)」で作ると煮て硬く締まり、この硬さが肉(鹿肉)を思わせる。うま味も豊かである。対するに「そうだ(ヒラソウダ)」は煮ると軟らかく、うま味は「うずわ」と比べると少ない。「うずわ(マルソウダ)」よりも魚の煮つけ的な味だ。比較しなければどちらもおいしいが、水揚げされているのを見て、どちらを選ぶかと言われると、「うずわ(マルソウダ)」を手に取ることになる。今のところ、神奈川県小田原市・真鶴町だけの料理のようだが、調べていく内に作っている地域が広がったり、逆に狭まったりする可能性がある。本料理は小田原市鴨宮にある鮮魚店『魚竹』さんと、小田原市江之浦、江の安 ワタルさん夫婦に教わったもの。また、『魚竹』さんはジャガイモを入れて、「肉じゃが風」にするというので、こちらも作ってみた。協力に感謝します。 ホウボウは年の瀬になるとじょじょに脂をため込んでいき、3月から5月の産卵とともに味が急落する。この産卵期が産地で違っている。今回の茨城県産は、北茨城市の大津漁港から来たのではないかと思われる。意外にこのあたりのホウボウを食べていない。ホウボウは平凡な食用魚だが、平凡な魚だからこそ年間を通して地域を変えて買ってみて、食べてみることは非常に重要なのだ。さて、旬とは言えないが、ホウボウには味の豊かさがある。そのうま味の多くが皮にあるのである。だから湯引きがいい。今回は辛子たっぷりの柚子風味の酢みそで食べた。柚子を加えるだけで冬の味になる。それにしても表面だけに熱を通すだけで上品な白身の食感が豊かになり、味わいも深くなる。湯引きのいいところはいくら食べても食べ飽きないことだろう。辛子たっぷりの柚子みその刺激に、クリスマスも、おおつごもりもあるものか、がんばるしかないぞ、わしは、なんて正一合を自分に追加する。
ホウボウは年の瀬になるとじょじょに脂をため込んでいき、3月から5月の産卵とともに味が急落する。この産卵期が産地で違っている。今回の茨城県産は、北茨城市の大津漁港から来たのではないかと思われる。意外にこのあたりのホウボウを食べていない。ホウボウは平凡な食用魚だが、平凡な魚だからこそ年間を通して地域を変えて買ってみて、食べてみることは非常に重要なのだ。さて、旬とは言えないが、ホウボウには味の豊かさがある。そのうま味の多くが皮にあるのである。だから湯引きがいい。今回は辛子たっぷりの柚子風味の酢みそで食べた。柚子を加えるだけで冬の味になる。それにしても表面だけに熱を通すだけで上品な白身の食感が豊かになり、味わいも深くなる。湯引きのいいところはいくら食べても食べ飽きないことだろう。辛子たっぷりの柚子みその刺激に、クリスマスも、おおつごもりもあるものか、がんばるしかないぞ、わしは、なんて正一合を自分に追加する。 「いもじく」の炒め煮は、炒め煮界のトップというか、他に類を見ないうまさなのである。しゃきしゃきっとしていて、ほどよく青臭くて、蕗とは違う味がある。ちなみに南方で過酷な戦争体験をした、加東大介は来る日も来る日も、サツマイモとその茎ばかりで飢えをしのいだと書いている。サツマイモの茎はおいしいじゃない、と一瞬思ったが、醤油も油揚げもない南方でどのように料理していたのだろう。やたらにうまいのに、もっとたくさん買って来ればよかった、と思わないのは、手間がかかるからだ。この「いもじく」の皮を剥いてくれる優しい女性、いるわけないよな。
「いもじく」の炒め煮は、炒め煮界のトップというか、他に類を見ないうまさなのである。しゃきしゃきっとしていて、ほどよく青臭くて、蕗とは違う味がある。ちなみに南方で過酷な戦争体験をした、加東大介は来る日も来る日も、サツマイモとその茎ばかりで飢えをしのいだと書いている。サツマイモの茎はおいしいじゃない、と一瞬思ったが、醤油も油揚げもない南方でどのように料理していたのだろう。やたらにうまいのに、もっとたくさん買って来ればよかった、と思わないのは、手間がかかるからだ。この「いもじく」の皮を剥いてくれる優しい女性、いるわけないよな。 我が家ではいたって日常的な秋の味である。こんな料理で一喜一憂しているなんてボクだけかも。その憂を生み出すのはいつも里芋である。いい里芋を見つけるのは、いいスルメイカを見つけることよりも難しい。今回近所のスーパーで買ったスルメイカに喜んで、里芋にほんの少しだけ泣く。11月最初の里芋煮は半喜半憂だ。さて、スルメイカと里芋煮は国内ではありきたりな料理だが、多摩地域では秋祭に作ることが多い。檜原村の老人曰く、ごちそうで楽しみにしていたという。まあ、一見普通の料理だが、すこぶるつきにうまい、これぞ真のごちそうだろう。久しぶりに作る味が優しいね。ご飯も食べ食べ、里芋もスルメイカも食べるとお腹が膨満してくる。けどスルメイカ独特の風味とうま味、それを吸い込んだ里芋がまずいわけがない。今年の里芋はいかがなりや。もっとうまい里芋食いたいな。
我が家ではいたって日常的な秋の味である。こんな料理で一喜一憂しているなんてボクだけかも。その憂を生み出すのはいつも里芋である。いい里芋を見つけるのは、いいスルメイカを見つけることよりも難しい。今回近所のスーパーで買ったスルメイカに喜んで、里芋にほんの少しだけ泣く。11月最初の里芋煮は半喜半憂だ。さて、スルメイカと里芋煮は国内ではありきたりな料理だが、多摩地域では秋祭に作ることが多い。檜原村の老人曰く、ごちそうで楽しみにしていたという。まあ、一見普通の料理だが、すこぶるつきにうまい、これぞ真のごちそうだろう。久しぶりに作る味が優しいね。ご飯も食べ食べ、里芋もスルメイカも食べるとお腹が膨満してくる。けどスルメイカ独特の風味とうま味、それを吸い込んだ里芋がまずいわけがない。今年の里芋はいかがなりや。もっとうまい里芋食いたいな。 北海道根室市は国内で唯一、オオノガイ漁が行われているところ。2024年6月24日の北海道根室市温根沼や春国岱でのオオノガイ漁解禁日(解禁日は年2回)に漁を見に行った。オオノガイは干潟の泥の中にもぐり込んでいるので、動力船などでの漁はできない。すべて手掘りである。この手掘り漁を、干潟を駆けずり回って見せて頂いた。オオノガイの料理に関しても聞いて回ったが、水管を刺身で食べるという人は少なく、常備菜とか保存食にする人ばかりだった。塩辛を作る、もしくは作っていたという人は取り分け多かったが、今でも毎年作るという人は少なかった。仕方がないので作り方を教わって、わたを譲り受けて作ってみた。
北海道根室市は国内で唯一、オオノガイ漁が行われているところ。2024年6月24日の北海道根室市温根沼や春国岱でのオオノガイ漁解禁日(解禁日は年2回)に漁を見に行った。オオノガイは干潟の泥の中にもぐり込んでいるので、動力船などでの漁はできない。すべて手掘りである。この手掘り漁を、干潟を駆けずり回って見せて頂いた。オオノガイの料理に関しても聞いて回ったが、水管を刺身で食べるという人は少なく、常備菜とか保存食にする人ばかりだった。塩辛を作る、もしくは作っていたという人は取り分け多かったが、今でも毎年作るという人は少なかった。仕方がないので作り方を教わって、わたを譲り受けて作ってみた。 久しぶりの「氷頭なます」にどうにも箸が止まらない。日本酒にも合うので、ついつい杯を重ねることになり、終いにはコップ酒になる。心地よくなって、この「氷頭(上顎の先端と目の間の皮と軟骨)を食べようと思った始まりの地はどこだろう?」なんて考えてしまう。きっと村上市の人は、うちだ、といい。岩手の人も、うちだ、といいそうだ。こりっこりっとして噛みしめると髄液のような、不思議な液体が出てくる。軟骨なのにうま味がとても強いのはこの正体不明の液体のせいだろう。分厚い皮に微かに脂と甘味があるのもいい。ちなみに市販の「氷頭なます」で、うまいものに出合ったことがない。また作るしかないけど、来季かも知れぬ。
久しぶりの「氷頭なます」にどうにも箸が止まらない。日本酒にも合うので、ついつい杯を重ねることになり、終いにはコップ酒になる。心地よくなって、この「氷頭(上顎の先端と目の間の皮と軟骨)を食べようと思った始まりの地はどこだろう?」なんて考えてしまう。きっと村上市の人は、うちだ、といい。岩手の人も、うちだ、といいそうだ。こりっこりっとして噛みしめると髄液のような、不思議な液体が出てくる。軟骨なのにうま味がとても強いのはこの正体不明の液体のせいだろう。分厚い皮に微かに脂と甘味があるのもいい。ちなみに市販の「氷頭なます」で、うまいものに出合ったことがない。また作るしかないけど、来季かも知れぬ。 学生時代以来の神保町(東京都千代田区神保町で、本の街)族だったので、名物だった天丼はよく食べた。1週間に何度も『天丼のいもや』に行き、希に佐野周二御用達の『はちまき』にも行った。安くて満足度の高い天丼ばかりで、天ぷら定食なんてめったに食べなかった。天丼を食べにだけで神保町に行くわけにもいかないので、ときどき自分で作る。今回の「あしあか(脚赤/クマエビ)」など上等の部類である。一に「まき(小型のクルマエビ)」、二に「芝蝦(しばえび)」で、「あしあか」は東京では三のひとつといったところか。精進ものは避けて、ちゃんと東京風に仕立てる。できればごま油で揚げたかったが、普通のサラダ油で我慢する。油の香り弱くちょっと上品過ぎるが、天ぷらには大きすぎるくらいの「あしあか」が実にうまい。濃厚なエビの風味に、プリッとした強い食感が実に心地よい。甘辛い天丼つゆと油っけありの衣がご飯に合う。久しぶりにほぼ1合飯をえび天と香の物だけで食らったら、都心に出られない憂さが晴れた。
学生時代以来の神保町(東京都千代田区神保町で、本の街)族だったので、名物だった天丼はよく食べた。1週間に何度も『天丼のいもや』に行き、希に佐野周二御用達の『はちまき』にも行った。安くて満足度の高い天丼ばかりで、天ぷら定食なんてめったに食べなかった。天丼を食べにだけで神保町に行くわけにもいかないので、ときどき自分で作る。今回の「あしあか(脚赤/クマエビ)」など上等の部類である。一に「まき(小型のクルマエビ)」、二に「芝蝦(しばえび)」で、「あしあか」は東京では三のひとつといったところか。精進ものは避けて、ちゃんと東京風に仕立てる。できればごま油で揚げたかったが、普通のサラダ油で我慢する。油の香り弱くちょっと上品過ぎるが、天ぷらには大きすぎるくらいの「あしあか」が実にうまい。濃厚なエビの風味に、プリッとした強い食感が実に心地よい。甘辛い天丼つゆと油っけありの衣がご飯に合う。久しぶりにほぼ1合飯をえび天と香の物だけで食らったら、都心に出られない憂さが晴れた。 年取魚(大晦日から新年にかけて食べる魚)のブリはすべて塩鰤であった。新潟から富山、石川、山陰、玄海灘にかけて揚がったら、すべて塩蔵して保存していた。これを旧暦の正月前に売っていた。旧暦の正月は太陽暦の1月下旬から2月前半くらいまでなので、ブリは新暦の11月から1月にかけてとって塩蔵した。ブリ漁の最盛期は新暦の1月以降なので、新暦の年取・正月には間に合わない。そのため、2010年代初めまでは、岐阜県飛騨高山の安い塩鰤は養殖もの、高いものは富山湾などの天然ものであった。天然ものが、すごく高いのは氷見産であったり、時季外れに塩鰤を作るからだ。そして今、飛騨高山の塩鰤は養殖ものが下級品、北海道産が高級品となっている。
年取魚(大晦日から新年にかけて食べる魚)のブリはすべて塩鰤であった。新潟から富山、石川、山陰、玄海灘にかけて揚がったら、すべて塩蔵して保存していた。これを旧暦の正月前に売っていた。旧暦の正月は太陽暦の1月下旬から2月前半くらいまでなので、ブリは新暦の11月から1月にかけてとって塩蔵した。ブリ漁の最盛期は新暦の1月以降なので、新暦の年取・正月には間に合わない。そのため、2010年代初めまでは、岐阜県飛騨高山の安い塩鰤は養殖もの、高いものは富山湾などの天然ものであった。天然ものが、すごく高いのは氷見産であったり、時季外れに塩鰤を作るからだ。そして今、飛騨高山の塩鰤は養殖ものが下級品、北海道産が高級品となっている。 仕事が行き詰まっているので、暫し寄り道的なことを。秋になり気温が下がると「かつおぶし削り節(以後単にカツオ節もしくは削り節)」を買う。「削り節買う」はボクの秋の季語だ。今回は、東京都足立市場内の『伊勢重』という店で削りたてを買うことができた。ちなみに削り節は、基本冷蔵保存である。冷蔵庫が小さいので、保冷するものが多い夏の間は保管できない。だから夏は煮干し類一辺倒でだしをとる。ちなみに疲れているときはだしの素も使っているわけで、だしの素も嫌いではない、ということも忘れないで言っておく。
仕事が行き詰まっているので、暫し寄り道的なことを。秋になり気温が下がると「かつおぶし削り節(以後単にカツオ節もしくは削り節)」を買う。「削り節買う」はボクの秋の季語だ。今回は、東京都足立市場内の『伊勢重』という店で削りたてを買うことができた。ちなみに削り節は、基本冷蔵保存である。冷蔵庫が小さいので、保冷するものが多い夏の間は保管できない。だから夏は煮干し類一辺倒でだしをとる。ちなみに疲れているときはだしの素も使っているわけで、だしの素も嫌いではない、ということも忘れないで言っておく。 アカエイの郷土料理は数知れずあると思っている。とりあえず農文協の聞き書シリーズの料理をじょじょに作り始めている。三重県伊勢地方の「えいのどろぼう焼き」もそのひとつだ。伊勢地方(伊勢市)は巨大な伊勢湾の、南の端にあって、宮川、五十鈴川が流れ込み、豊かな干潟が広がっている。このような水域に多いのがアカエイである。この干潟のある水域は日本中にあり、多くが都市の前海なのである。だからアカエイは大量漁獲され、大量に食べられていたのだ。伊勢地方と古墳時代からの都である奈良県、大阪府との関わりが深い。そして有名な伊勢神宮がある。この地が大和王権と深く結びついたのは飛鳥地方と北緯が同じ位置にあり、古くから街道があったためである。奈良県の郷土料理にアカエイが登場するのも伊勢湾との繋がりを感じる。初夏に産卵のために浅瀬に来るアカエイで作る。ぶつ切りにして串焼きにし味噌をつけたもの。こんがり串焼きにして軟骨が香ばしい。〈泥をつけた棒ということで、料理の姿から名づけられたもの。〉『聞書き 三重の食事』(農山漁村文化協会)
アカエイの郷土料理は数知れずあると思っている。とりあえず農文協の聞き書シリーズの料理をじょじょに作り始めている。三重県伊勢地方の「えいのどろぼう焼き」もそのひとつだ。伊勢地方(伊勢市)は巨大な伊勢湾の、南の端にあって、宮川、五十鈴川が流れ込み、豊かな干潟が広がっている。このような水域に多いのがアカエイである。この干潟のある水域は日本中にあり、多くが都市の前海なのである。だからアカエイは大量漁獲され、大量に食べられていたのだ。伊勢地方と古墳時代からの都である奈良県、大阪府との関わりが深い。そして有名な伊勢神宮がある。この地が大和王権と深く結びついたのは飛鳥地方と北緯が同じ位置にあり、古くから街道があったためである。奈良県の郷土料理にアカエイが登場するのも伊勢湾との繋がりを感じる。初夏に産卵のために浅瀬に来るアカエイで作る。ぶつ切りにして串焼きにし味噌をつけたもの。こんがり串焼きにして軟骨が香ばしい。〈泥をつけた棒ということで、料理の姿から名づけられたもの。〉『聞書き 三重の食事』(農山漁村文化協会) 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが新島沖で釣り上げたヒメを撮影しながら考えた。標準和名のヒメは体長20cm前後の比較的原始的な魚で、本州から九州の比較的暖かい海域の沖合いに生息している。国内海域以外では台湾や韓国釜山で見つかっているだけで、魚類の中でも生息域の狭い種である。近縁種にイトヒキヒメがいるが、こちらは国内海域では珍しい魚といってもいいが、生息海域は南半球にも及ぶ。系統的に似たもの同士は生息域が南北にずれていて、少しだけ生息域が重なることがあるが、この両種も同様である。江戸時代が終わり、明治になってドイツから近代的な博物学が入ってくる。鉱物や生物などごちゃ混ぜの博物学は、それでも江戸時代と比べると系統立っていて科学的だった。そんな博物学(生物学)は国内にいる生物の、実際に使われている呼び名集めから始まる。名のないものは存在しないからで、名がばらばらだと研究できないからだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが新島沖で釣り上げたヒメを撮影しながら考えた。標準和名のヒメは体長20cm前後の比較的原始的な魚で、本州から九州の比較的暖かい海域の沖合いに生息している。国内海域以外では台湾や韓国釜山で見つかっているだけで、魚類の中でも生息域の狭い種である。近縁種にイトヒキヒメがいるが、こちらは国内海域では珍しい魚といってもいいが、生息海域は南半球にも及ぶ。系統的に似たもの同士は生息域が南北にずれていて、少しだけ生息域が重なることがあるが、この両種も同様である。江戸時代が終わり、明治になってドイツから近代的な博物学が入ってくる。鉱物や生物などごちゃ混ぜの博物学は、それでも江戸時代と比べると系統立っていて科学的だった。そんな博物学(生物学)は国内にいる生物の、実際に使われている呼び名集めから始まる。名のないものは存在しないからで、名がばらばらだと研究できないからだ。 長崎県長崎市、魚喰民族 石田拓治さんに送って頂いた新種記載ほやほやのツキノワメイチダイではいろんな料理を作った。その中にムニエルがある。魚料理の基本にソテーがあるが、和食の塩焼きに対してフレンチなどではムニエルがそれにあたると思う。塩コショウして小麦粉をまぶしてソテーすると、バターを使わず、どんなソースにしても、どんな油を使ってもムニエルと考えたい。要するに魚でも貝でもイカでも、エビだってムニエルになる。魚介類をよく食べる、この国でムニエルはもっと食べられてもいい、という話でもある。メイチダイ類(メイチダイ、サザナミダイ、シロダイ、本種などメイチダイ属)はソテーしてもとてもうまい。もちろん臭味が出やすい魚なので、ていねいに水揚げしたものに限るが、ムニエルにするとトップクラスだと思っている。三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。塩コショウして小麦粉をつけて多めの油でソテーする。片身を取り出して皿に移して、バターを加えて泡立て少し煮つめソースにする。
長崎県長崎市、魚喰民族 石田拓治さんに送って頂いた新種記載ほやほやのツキノワメイチダイではいろんな料理を作った。その中にムニエルがある。魚料理の基本にソテーがあるが、和食の塩焼きに対してフレンチなどではムニエルがそれにあたると思う。塩コショウして小麦粉をまぶしてソテーすると、バターを使わず、どんなソースにしても、どんな油を使ってもムニエルと考えたい。要するに魚でも貝でもイカでも、エビだってムニエルになる。魚介類をよく食べる、この国でムニエルはもっと食べられてもいい、という話でもある。メイチダイ類(メイチダイ、サザナミダイ、シロダイ、本種などメイチダイ属)はソテーしてもとてもうまい。もちろん臭味が出やすい魚なので、ていねいに水揚げしたものに限るが、ムニエルにするとトップクラスだと思っている。三枚に下ろし、腹骨と血合い骨を取る。塩コショウして小麦粉をつけて多めの油でソテーする。片身を取り出して皿に移して、バターを加えて泡立て少し煮つめソースにする。 貝屋(貝の収集家)ではないが、基本的に生き物が好きなので、貝を見るのも触るのも、食べるのも好きだ。産地不明のホタテガイがあって、べっとりくっ付いているものがある。普通はホタテガイが主役だけど、ボクにはべっとりくっ付いている方が主役だ。市場ではボクのそんな行動が変に見えるらしいが気にしない。
貝屋(貝の収集家)ではないが、基本的に生き物が好きなので、貝を見るのも触るのも、食べるのも好きだ。産地不明のホタテガイがあって、べっとりくっ付いているものがある。普通はホタテガイが主役だけど、ボクにはべっとりくっ付いている方が主役だ。市場ではボクのそんな行動が変に見えるらしいが気にしない。 ボクは季節に従順でありたい。季節に争うなんてやりたくもない。今や亜熱帯となってしまったが、わずかでも季節をありのままに感じたい。ということでイワガキは今季は終い、マガキが来るまで待ちたい。今季最後のイワガキは新潟県産となる。年をとるごとに発見が多くなり、忙しくなる。これは老人の友人の言葉だけど、しかり、だ。あまりにもたくさんの水産生物が来たので、結局、夏の間、豊洲に行けなかった。当然、日本各地のイワガキを食べたいという願いは叶わなかった。さて、新潟県産のイワガキは特有の濃厚なうま味が感じられた。ただし最盛期を過ぎているために食感は今イチである。毎年同じだが、産卵期のこともあるし、そろそろ名残の時季となりにける、だ。結果、新潟県産は今季最後としては上々かも知れぬ。
ボクは季節に従順でありたい。季節に争うなんてやりたくもない。今や亜熱帯となってしまったが、わずかでも季節をありのままに感じたい。ということでイワガキは今季は終い、マガキが来るまで待ちたい。今季最後のイワガキは新潟県産となる。年をとるごとに発見が多くなり、忙しくなる。これは老人の友人の言葉だけど、しかり、だ。あまりにもたくさんの水産生物が来たので、結局、夏の間、豊洲に行けなかった。当然、日本各地のイワガキを食べたいという願いは叶わなかった。さて、新潟県産のイワガキは特有の濃厚なうま味が感じられた。ただし最盛期を過ぎているために食感は今イチである。毎年同じだが、産卵期のこともあるし、そろそろ名残の時季となりにける、だ。結果、新潟県産は今季最後としては上々かも知れぬ。 7月はじめに魚のパスタを作り始めて、目から鱗というと月並みだが、魚魚しいパスタがこんなにもおいしいのかと、作るたびにデカイ腹を突き出しのけぞっている。そして、スマ、だー。比較してはいけないかも知れないが、食べているときには正しい評価が出来ないものだが、ここに魚魚しいパスタの頂点をみた気がする。(もちろんどんどん評価は変わるけど)ソテーしたスマの中落ちがやけにうまいだけではなく、中からにじみ出てきたうま味が非常に豊かだ。最近、できるだけ塩を使わないのに濃厚に思えるのは、スマのうま味成分がぎょうさん出ているためだろう。ここに今回のひらめきで入れたヒメグルミのこくが追加される。ナッツ系の濃厚な油分ありのうま味と香ばしさって、足しても余計ではなく、うまさが倍増する役割を担うのだ。うま味を含んだ油とスパゲッティだけでも、ごっついええな、と思う。そこにケーパーの酸味と塩気がくるのもいい。こんなに魚のうま味と、ケーパーの酸味が合うなんて思わなかった。しかもしかもプラスティックのケースに入って高かったスイートバジルではなく、袋にどばっと入って安い直売所のものを、どんどんちぎり入れたら、これもええ、ではないか。ハーブとか香りのものは高値だからと、ケチケチ使っていたのではよさがちっともわからないってのも最近わかってきた。ネットで調べると、イタリア語で、おいしいは、〈delizioso〉らしいけど、この一皿で感じることは、それだな。〈delizioso〉でボクの腹が、また一回り膨らんだ。早く昼ワインを飲んでも、仕事が継続できる体にもどりたい。
7月はじめに魚のパスタを作り始めて、目から鱗というと月並みだが、魚魚しいパスタがこんなにもおいしいのかと、作るたびにデカイ腹を突き出しのけぞっている。そして、スマ、だー。比較してはいけないかも知れないが、食べているときには正しい評価が出来ないものだが、ここに魚魚しいパスタの頂点をみた気がする。(もちろんどんどん評価は変わるけど)ソテーしたスマの中落ちがやけにうまいだけではなく、中からにじみ出てきたうま味が非常に豊かだ。最近、できるだけ塩を使わないのに濃厚に思えるのは、スマのうま味成分がぎょうさん出ているためだろう。ここに今回のひらめきで入れたヒメグルミのこくが追加される。ナッツ系の濃厚な油分ありのうま味と香ばしさって、足しても余計ではなく、うまさが倍増する役割を担うのだ。うま味を含んだ油とスパゲッティだけでも、ごっついええな、と思う。そこにケーパーの酸味と塩気がくるのもいい。こんなに魚のうま味と、ケーパーの酸味が合うなんて思わなかった。しかもしかもプラスティックのケースに入って高かったスイートバジルではなく、袋にどばっと入って安い直売所のものを、どんどんちぎり入れたら、これもええ、ではないか。ハーブとか香りのものは高値だからと、ケチケチ使っていたのではよさがちっともわからないってのも最近わかってきた。ネットで調べると、イタリア語で、おいしいは、〈delizioso〉らしいけど、この一皿で感じることは、それだな。〈delizioso〉でボクの腹が、また一回り膨らんだ。早く昼ワインを飲んでも、仕事が継続できる体にもどりたい。 三重県鳥羽市周辺、愛知県三河湾篠島に「にし汁(螺汁)」という郷土料理がある。この周辺だけではなく、国内各地に普通に見られる磯の小型の巻き貝である「にし」を使った、汁とも、なんとも、いえそうにない料理だ。今回は、三重県鳥羽市周辺で作られている「にし汁」を地元の方に聞いて作ってみた。思った以上に時間を要した末に出来上がったものはどろっとしたもので、決して見た目がいいとは言えそうにない。まずは汁を飲んでみる。中に混ざった「にし」の足(筋肉)の部分の部分に甘味があるものの、肝膵臓や生殖巣などが含まれる液状の部分が少々生臭い。しかも舌だけではなく、口の天井から脇、舌の裏側までぴりぴりする。今回使ったレイシガイは別名、「辛螺(からにし)」、「煙草螺(たばこにし)」というが、そんな呼び名通りの辛味というか、いがらっぽさがある。ちなみに汁と足に味があることはある。むしろ非常に豊かにあると言ってもいいだろう。ただし、おいしさ以前に刺激が口中から喉に移り、胃の腑に入ると、なんだか胃袋が熱っぽく感じられる。この口の中から胃袋にかけての刺激的な味がなかなか去ってくれない。汁だけで飲むよりも、と思ってご飯と一緒に食べたが、同じだった。食べた後、喉のあたりにいがらっぽさが強く残った。鳥羽に住んでいる人からも聞いたとおり、好きな人は好き、だめな人はなめるのもだめ、といったものだ。個人的には決して好きだとは言えそうにないが、地元の人と、もう一度試してみたい気もする。協力/出間リカさん(三重県鳥羽市)、岩尾豊紀さん(鳥羽市水産研究所)
三重県鳥羽市周辺、愛知県三河湾篠島に「にし汁(螺汁)」という郷土料理がある。この周辺だけではなく、国内各地に普通に見られる磯の小型の巻き貝である「にし」を使った、汁とも、なんとも、いえそうにない料理だ。今回は、三重県鳥羽市周辺で作られている「にし汁」を地元の方に聞いて作ってみた。思った以上に時間を要した末に出来上がったものはどろっとしたもので、決して見た目がいいとは言えそうにない。まずは汁を飲んでみる。中に混ざった「にし」の足(筋肉)の部分の部分に甘味があるものの、肝膵臓や生殖巣などが含まれる液状の部分が少々生臭い。しかも舌だけではなく、口の天井から脇、舌の裏側までぴりぴりする。今回使ったレイシガイは別名、「辛螺(からにし)」、「煙草螺(たばこにし)」というが、そんな呼び名通りの辛味というか、いがらっぽさがある。ちなみに汁と足に味があることはある。むしろ非常に豊かにあると言ってもいいだろう。ただし、おいしさ以前に刺激が口中から喉に移り、胃の腑に入ると、なんだか胃袋が熱っぽく感じられる。この口の中から胃袋にかけての刺激的な味がなかなか去ってくれない。汁だけで飲むよりも、と思ってご飯と一緒に食べたが、同じだった。食べた後、喉のあたりにいがらっぽさが強く残った。鳥羽に住んでいる人からも聞いたとおり、好きな人は好き、だめな人はなめるのもだめ、といったものだ。個人的には決して好きだとは言えそうにないが、地元の人と、もう一度試してみたい気もする。協力/出間リカさん(三重県鳥羽市)、岩尾豊紀さん(鳥羽市水産研究所) 常備している酢のものはいつも精進そのもので、基本はきゅうりと海藻なのである。そこに動物質のものが入ると俄然、味わい深くなる。酒の合いの手に箸をのばすものが、酢のものが酒の肴の主役になる。なによりも酢に混ぜ込んだ焼いたアカササノハベラの脂とうま味が、満足度を高めてくれる。きゅうりの食感と爽やかな青い味わいもいい。それにしても高知県宿毛市のオッカサン達の焼いた魚や、塩ゆでにした魚を酢に溶かし込むという考え方は優れている。すし酢だけではなく、酢のものに使うだけで、どこかしら御馳走めく。
常備している酢のものはいつも精進そのもので、基本はきゅうりと海藻なのである。そこに動物質のものが入ると俄然、味わい深くなる。酒の合いの手に箸をのばすものが、酢のものが酒の肴の主役になる。なによりも酢に混ぜ込んだ焼いたアカササノハベラの脂とうま味が、満足度を高めてくれる。きゅうりの食感と爽やかな青い味わいもいい。それにしても高知県宿毛市のオッカサン達の焼いた魚や、塩ゆでにした魚を酢に溶かし込むという考え方は優れている。すし酢だけではなく、酢のものに使うだけで、どこかしら御馳走めく。 曜日の感覚がボクには存在しないので、駅前まで打ち合わせで出てはじめて今日が日曜日であることを知る。下る坂道に陽炎が立つ。腰に下げている、温度計のアラームが鳴る。路上温度ではあるがまさかの40℃である。やってきた相手も顔が赤い。こんなとき仕事をしちゃーいかんと話しながらも、ちゃんと打ち合わせて帰ってきた。帰り着いて張りついたTシャツを脱いで、冷たいシャワーを浴びても体から熱が出ていかない。横になっても落ち着かないので、考えに考えた末に、魚のみそ汁を作ることにした。最近、沖縄が本州よりも暑いなんてとても思えないが、ほんの数年前まで圧倒的に沖縄の方が暑かった。そんな沖縄の郷土料理が魚汁である。「いまいゆの魚汁」は沖縄の定番的な食堂メニューだ。「いまいゆ」は新鮮な生魚のことで、魚汁とは魚のみそ汁のことである。沖縄県で魚汁が汁以上の存在であることは、定食の主菜となっていることからもわかる。魚汁を頼むと、ご飯に漬物、小鉢が自動的についてくる。この「魚汁定食」は食事でもあるし、体から熱を追い払うための薬でもあるのだ。実際沖縄で魚汁を食べると、元気になる。あまりにも息苦しいので、本能で作った魚汁ともいえそうだ。幸運なことに、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが釣り上げてきたタチウオのあらがまだ3分の1くらい冷凍庫で眠っている。保存袋のまま流水で解凍して、湯通しして冷水に取り、水分を切ったものを鍋に放り込む。ここに水を張り、刺し昆布(小さな昆布)をして、ことこと煮だして福島県相馬市山形屋のみそをちょっと多めに溶く。みその塩気がいいのだろう。熱々なのに体が冷めていく。タチウオのだしがいっぱいでており、汁としてこの上なくうまい。あまりにも体に熱がたまりすぎていたら、魚汁を作るに限る。
曜日の感覚がボクには存在しないので、駅前まで打ち合わせで出てはじめて今日が日曜日であることを知る。下る坂道に陽炎が立つ。腰に下げている、温度計のアラームが鳴る。路上温度ではあるがまさかの40℃である。やってきた相手も顔が赤い。こんなとき仕事をしちゃーいかんと話しながらも、ちゃんと打ち合わせて帰ってきた。帰り着いて張りついたTシャツを脱いで、冷たいシャワーを浴びても体から熱が出ていかない。横になっても落ち着かないので、考えに考えた末に、魚のみそ汁を作ることにした。最近、沖縄が本州よりも暑いなんてとても思えないが、ほんの数年前まで圧倒的に沖縄の方が暑かった。そんな沖縄の郷土料理が魚汁である。「いまいゆの魚汁」は沖縄の定番的な食堂メニューだ。「いまいゆ」は新鮮な生魚のことで、魚汁とは魚のみそ汁のことである。沖縄県で魚汁が汁以上の存在であることは、定食の主菜となっていることからもわかる。魚汁を頼むと、ご飯に漬物、小鉢が自動的についてくる。この「魚汁定食」は食事でもあるし、体から熱を追い払うための薬でもあるのだ。実際沖縄で魚汁を食べると、元気になる。あまりにも息苦しいので、本能で作った魚汁ともいえそうだ。幸運なことに、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが釣り上げてきたタチウオのあらがまだ3分の1くらい冷凍庫で眠っている。保存袋のまま流水で解凍して、湯通しして冷水に取り、水分を切ったものを鍋に放り込む。ここに水を張り、刺し昆布(小さな昆布)をして、ことこと煮だして福島県相馬市山形屋のみそをちょっと多めに溶く。みその塩気がいいのだろう。熱々なのに体が冷めていく。タチウオのだしがいっぱいでており、汁としてこの上なくうまい。あまりにも体に熱がたまりすぎていたら、魚汁を作るに限る。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。余談だが関東でマルソウダは安すぎる。もっと鮮魚で利用して欲しいものだ。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。余談だが関東でマルソウダは安すぎる。もっと鮮魚で利用して欲しいものだ。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。 今年はホタルイカが安い上に、まだ魚屋に並んでいる。スーパーにもあるので、ついつい手が出る。これをイタリアンな料理に使ってみた。といっても面倒な料理ではない。袋に中途半端に残っていたペンネを消費するためのイタリアーンでもある。ペンネのゆで時間は10分。ゆではじめたらフライパンにたっぷりのオリーブオイルとにんにく、鷹の爪をいれて熱する。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて、トマトを刻んだものを放り込む。ここに生ホタルイカを加えて、徹底的にどつく。体がばらばらになるくらいどつくが、ぬるニョロとしているのでなかなかパンチがきかない。トマトは煮過ぎると甘さが飛び、長時間煮込んでいる内にふたたび甘くなる。ここで注意しなければならないのは煮すぎないことである。パスタとのゆで時間を考えて甘味がいちばん強いときに火を止める。あとは味見をして塩コショウする。ソースがどろっとし過ぎていたらゆで汁で加減する。この場合、塩は不要。あとはペンネと和えるだけ。
今年はホタルイカが安い上に、まだ魚屋に並んでいる。スーパーにもあるので、ついつい手が出る。これをイタリアンな料理に使ってみた。といっても面倒な料理ではない。袋に中途半端に残っていたペンネを消費するためのイタリアーンでもある。ペンネのゆで時間は10分。ゆではじめたらフライパンにたっぷりのオリーブオイルとにんにく、鷹の爪をいれて熱する。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて、トマトを刻んだものを放り込む。ここに生ホタルイカを加えて、徹底的にどつく。体がばらばらになるくらいどつくが、ぬるニョロとしているのでなかなかパンチがきかない。トマトは煮過ぎると甘さが飛び、長時間煮込んでいる内にふたたび甘くなる。ここで注意しなければならないのは煮すぎないことである。パスタとのゆで時間を考えて甘味がいちばん強いときに火を止める。あとは味見をして塩コショウする。ソースがどろっとし過ぎていたらゆで汁で加減する。この場合、塩は不要。あとはペンネと和えるだけ。 福島県相馬市では主に旧城下の中村でスーパーを回ってみた。休日にも開いているスーパーは旅人にはまことにありがたい。【話の寄り道、旅の土産はスーパーで買うべし。同じ土産品が値が安い上に、地元でしか買えないものが発見できる。】相馬市は藩政時代から城のある中村と、漁港がある原釜に分かれていた。古くから、原釜でとれた魚を城下で消費する、という形が出来上がっていたのだと思う。スーパーに並ぶ、魚のラベルに「原釜水揚げ」がとても多いことにも、そんな歴史が偲ばれる。今回の相馬行で改めて感じたのはこの地のカレイ類が豊富であることだ。見つけた原釜産カレイ類は、「あおめがれい(マコガレイ)」、「にくもちがれい(ミギガレイ)」、「なめた(ババガレイ)」、「石がれい(イシガレイ)」「黒やなぎ(ヒレグロ)」、「柳かれい(ヤナギムシガレイ)」、「水がれい(ムシガレイ)」、「真がれい(マガレイ)」だ。江戸(東京)の前海江戸湾(東京湾)は昔からカレイ類の宝庫であった。江戸時代の江戸っ子はカレイ類をよく食べていたはずだ。明治期になって東北本線、常磐線ができるとそこに茨城県、福島県、宮城県からどっと新顔のカレイ類がおしよせてくる。後に北海道が加わる。国内でももっとも多種のカレイを食べていたのが東京なのだ。カレイ類は昔、もっとも人気の高い魚だったが、最近人気低落気味である。この最大の原因が煮つけを作らなくなったためで、その根本には米を食べなくなったことが挙げられる。ちなみに関東の市場人で、「原釜」を知らないという人は震災後に市場人となったのだと思う。原釜は関東にとって最大級の供給地だったし、関東の市場人ならおしなべて元の状態に復して欲しいと思っているはずである。さて、「あおめがれい」の切り身を市内『中島ストア』で買った。この小さなスーパーは実に楽しかったという話は後々に述べる。宮城県、福島県での呼び名、「あおめがれい」の漢字、意味がわからないので困っている。単純に考えると「青目鰈」だけど、目は青くないのだ。「あおめがれい」、すなわちマコガレイの面白いところは寒い時季は大衆魚で、気温が上昇すると高級魚に変身することだ。この高級魚の時季が温暖化で長くなっている気がする。4月の末、まだ、「あおめがれい」が活魚槽の主役になるのはもう少し後のことになる。今はまだ生殖巣が膨らんでいるので、庶民的な魚でしかない。
福島県相馬市では主に旧城下の中村でスーパーを回ってみた。休日にも開いているスーパーは旅人にはまことにありがたい。【話の寄り道、旅の土産はスーパーで買うべし。同じ土産品が値が安い上に、地元でしか買えないものが発見できる。】相馬市は藩政時代から城のある中村と、漁港がある原釜に分かれていた。古くから、原釜でとれた魚を城下で消費する、という形が出来上がっていたのだと思う。スーパーに並ぶ、魚のラベルに「原釜水揚げ」がとても多いことにも、そんな歴史が偲ばれる。今回の相馬行で改めて感じたのはこの地のカレイ類が豊富であることだ。見つけた原釜産カレイ類は、「あおめがれい(マコガレイ)」、「にくもちがれい(ミギガレイ)」、「なめた(ババガレイ)」、「石がれい(イシガレイ)」「黒やなぎ(ヒレグロ)」、「柳かれい(ヤナギムシガレイ)」、「水がれい(ムシガレイ)」、「真がれい(マガレイ)」だ。江戸(東京)の前海江戸湾(東京湾)は昔からカレイ類の宝庫であった。江戸時代の江戸っ子はカレイ類をよく食べていたはずだ。明治期になって東北本線、常磐線ができるとそこに茨城県、福島県、宮城県からどっと新顔のカレイ類がおしよせてくる。後に北海道が加わる。国内でももっとも多種のカレイを食べていたのが東京なのだ。カレイ類は昔、もっとも人気の高い魚だったが、最近人気低落気味である。この最大の原因が煮つけを作らなくなったためで、その根本には米を食べなくなったことが挙げられる。ちなみに関東の市場人で、「原釜」を知らないという人は震災後に市場人となったのだと思う。原釜は関東にとって最大級の供給地だったし、関東の市場人ならおしなべて元の状態に復して欲しいと思っているはずである。さて、「あおめがれい」の切り身を市内『中島ストア』で買った。この小さなスーパーは実に楽しかったという話は後々に述べる。宮城県、福島県での呼び名、「あおめがれい」の漢字、意味がわからないので困っている。単純に考えると「青目鰈」だけど、目は青くないのだ。「あおめがれい」、すなわちマコガレイの面白いところは寒い時季は大衆魚で、気温が上昇すると高級魚に変身することだ。この高級魚の時季が温暖化で長くなっている気がする。4月の末、まだ、「あおめがれい」が活魚槽の主役になるのはもう少し後のことになる。今はまだ生殖巣が膨らんでいるので、庶民的な魚でしかない。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。 打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。
打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。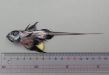 ボクは魚類学者ではない。魚類学者になるために不可欠な数学がダメだし、不可欠な英語もだめだし、ペアになってくれる分子生物学者もいない。魚に関して、食文化の分野ではかなりイケテルと思っているが、魚類学的にはパープリンである。福島県郡山水産の田母神真広さんからメッセージがきて、岩手県宮古の須藤水産さんがギンザメの赤ちゃんを確保してくれているという。それが本日やってきた。見たところ、明らかに標準和名のギンザメではないと思われる。さて、なんだろう? なんてよくわからない壁にぶち当たる。このボクの壁を語るには、まずは、魚類学とはなんだろう? から。ボクに最低限できることは、形態学という魚類学の一分野でしかない。これだけでもやたらに時間がかかる。例えば、山梨県西湖で見つかった魚にクニマスというのがある。これがボクにはわからない。ベニザケの陸風型、ヒメマスじゃねーか、と言ったら関わりをもっているのか、生命の星、Sさんは解剖学的にもクニマスでいいという。とするとすでにSさんのグループ、京大のNさんのグループは個体の生理を研究し、解剖し、骨格を調べ、DNAも調べていることになる。今回のギンザメは非常に原始的な魚類である。スズキやマダイなどよりも遙かに原始的な(この言語はネオダーウィニズムでは否定されていた気がする)、サメやエイよりも、さらに遙かに原始的だ。ギンザメの仲間は魚類学の父、田中茂穂(明治、大正、昭和にまたがり魚類の研究をした)の段階でかなり研究が進んでいた。田中茂穂自ら記載したものもあり、彼が学んだアメリカのスタンフォード大学の魚類学者、ジョルダンなどが記載したものもあるからである。ギンザメ類は、今現在、再整理している気がする。ギンザメ類の基礎的な存在、種として記載するもとになった、タイプ標本にもあたっているのではないか。ギンザメのタイプ標本は国内にもあり、アメリカにあるので場合によってはアメリカに行ったのだろうか? 魚類学には途方もなく労力がいる。以上、ギンザメというだけでもいろんな話が浮かんでくる。残念ながら我が家には、ギンザメの稚魚の個体画像がない。かなり前から、0歳のギンザメの個体画像もしっかり撮っておくべきだと思っていたが果たせていない。
ボクは魚類学者ではない。魚類学者になるために不可欠な数学がダメだし、不可欠な英語もだめだし、ペアになってくれる分子生物学者もいない。魚に関して、食文化の分野ではかなりイケテルと思っているが、魚類学的にはパープリンである。福島県郡山水産の田母神真広さんからメッセージがきて、岩手県宮古の須藤水産さんがギンザメの赤ちゃんを確保してくれているという。それが本日やってきた。見たところ、明らかに標準和名のギンザメではないと思われる。さて、なんだろう? なんてよくわからない壁にぶち当たる。このボクの壁を語るには、まずは、魚類学とはなんだろう? から。ボクに最低限できることは、形態学という魚類学の一分野でしかない。これだけでもやたらに時間がかかる。例えば、山梨県西湖で見つかった魚にクニマスというのがある。これがボクにはわからない。ベニザケの陸風型、ヒメマスじゃねーか、と言ったら関わりをもっているのか、生命の星、Sさんは解剖学的にもクニマスでいいという。とするとすでにSさんのグループ、京大のNさんのグループは個体の生理を研究し、解剖し、骨格を調べ、DNAも調べていることになる。今回のギンザメは非常に原始的な魚類である。スズキやマダイなどよりも遙かに原始的な(この言語はネオダーウィニズムでは否定されていた気がする)、サメやエイよりも、さらに遙かに原始的だ。ギンザメの仲間は魚類学の父、田中茂穂(明治、大正、昭和にまたがり魚類の研究をした)の段階でかなり研究が進んでいた。田中茂穂自ら記載したものもあり、彼が学んだアメリカのスタンフォード大学の魚類学者、ジョルダンなどが記載したものもあるからである。ギンザメ類は、今現在、再整理している気がする。ギンザメ類の基礎的な存在、種として記載するもとになった、タイプ標本にもあたっているのではないか。ギンザメのタイプ標本は国内にもあり、アメリカにあるので場合によってはアメリカに行ったのだろうか? 魚類学には途方もなく労力がいる。以上、ギンザメというだけでもいろんな話が浮かんでくる。残念ながら我が家には、ギンザメの稚魚の個体画像がない。かなり前から、0歳のギンザメの個体画像もしっかり撮っておくべきだと思っていたが果たせていない。 新潟県新潟市は阿賀野川、信濃川が流れ込むところで、沖には佐渡が、思った以上に大きくうずくまっている。新潟市がいかに水産資源に恵まれたところか、一目瞭然である。ここで秋と春に水揚げをみるのがアキアミである。新潟市では「赤ヒゲ」という。アミとはつくがアミの仲間ではなく、れっきとしたエビの仲間(十脚目)で、サクラエビの仲間(サクラエビ科)である。小さなエビなので、じっくり見ないととてもエビだとは思えないはずである。目をこらしてみると実に眼が麗しいのがわかると思う。まるで少女漫画のヒロインのようだ。信濃川・阿賀野川河口域で漁が行われ、すぐに新潟漁業協同組合の競り場に並べられる。新しく明るい競り場に並ぶ、アキアミは非常に美しい。アキアミを盛んに食べるところで有名なのは児島湾があった岡山県、豊前海、有明海周辺である。意外に新潟市のアキアミは知られていない気がするが、鮮度のよさなどは群を抜いて素晴らしい。ちなみにアキアミの生は非常に珍しい。なかなか手に入らない。産地周辺だけで手に入るという意味では貴重なものだ。むしろ、塩辛の方が一般的である。新潟市、岡山県、有明海周辺などで年間を通じて手に入る。国内では酒の肴であり、ご飯のおかずになる。同じアキアミの仲間で見た目はそっくりなエビが朝鮮半島、中国にもいる。韓国ではキムチの材料として重要である。国内以上に水揚げ量が多いようで、韓国内の市場には樽に入って量り売りされている。ちなみにアキアミの漁獲量は年々減少傾向にある。これは温暖化のせいではなく、河川や内湾の自然破壊が原因である。もう遙か昔から、ヒトは自然破壊から、自然を保全する、に切り替えるべきであった。それが何年経っても愚かにも、自然はヒトだけのものと考えているヤカラが多すぎるからだ。
新潟県新潟市は阿賀野川、信濃川が流れ込むところで、沖には佐渡が、思った以上に大きくうずくまっている。新潟市がいかに水産資源に恵まれたところか、一目瞭然である。ここで秋と春に水揚げをみるのがアキアミである。新潟市では「赤ヒゲ」という。アミとはつくがアミの仲間ではなく、れっきとしたエビの仲間(十脚目)で、サクラエビの仲間(サクラエビ科)である。小さなエビなので、じっくり見ないととてもエビだとは思えないはずである。目をこらしてみると実に眼が麗しいのがわかると思う。まるで少女漫画のヒロインのようだ。信濃川・阿賀野川河口域で漁が行われ、すぐに新潟漁業協同組合の競り場に並べられる。新しく明るい競り場に並ぶ、アキアミは非常に美しい。アキアミを盛んに食べるところで有名なのは児島湾があった岡山県、豊前海、有明海周辺である。意外に新潟市のアキアミは知られていない気がするが、鮮度のよさなどは群を抜いて素晴らしい。ちなみにアキアミの生は非常に珍しい。なかなか手に入らない。産地周辺だけで手に入るという意味では貴重なものだ。むしろ、塩辛の方が一般的である。新潟市、岡山県、有明海周辺などで年間を通じて手に入る。国内では酒の肴であり、ご飯のおかずになる。同じアキアミの仲間で見た目はそっくりなエビが朝鮮半島、中国にもいる。韓国ではキムチの材料として重要である。国内以上に水揚げ量が多いようで、韓国内の市場には樽に入って量り売りされている。ちなみにアキアミの漁獲量は年々減少傾向にある。これは温暖化のせいではなく、河川や内湾の自然破壊が原因である。もう遙か昔から、ヒトは自然破壊から、自然を保全する、に切り替えるべきであった。それが何年経っても愚かにも、自然はヒトだけのものと考えているヤカラが多すぎるからだ。 新潟県新潟市のスーパーでスケソ(スケトウダラ)の切身を買って来た。わがデータベースのスケトウダラの画像を見直してみると、上越市、新潟市、長岡市などで買った切り身パックの画像がある。日本各地に行って水産生物のことを調べているが、単に「たら」といったとき、マダラと考える地域と、スケトウダラと考える地域があるのか、ないのか、意外に重要だと思うがはっきりしない。ただ新潟市は明らかにスケトウダラが「たら」だ。新潟市民は他の地域では考えられないくらいスケソウダラがすきだ。旧蒲原郡(現上越市)、新発田市や長岡市、十日町市などでも同様だろう。頸城海岸(現上越市)では「ごはんがわりにすけそうだらを焼いて、一人が三本も四本も食べることがある。」とある。『聞書き 新潟の食事』(農文協)理由は簡単である、佐渡も含めた新潟沖でたくさんとれていたからだ。新潟市では「すけそ(助宗)」ということが多い。ちなみに流通上でも、例えば関東の食堂などでも「すけそうだら」で、スケトウダラとは言わない。標準和名がスケトウダラとなったのは江戸時代の本草学の書からとったためだ。川路聖謨が佐渡奉行だったときの『島根のすさみ』でも「すけとうだら」だったはず。さて、北海道、東北、新潟との繋がりの深い東京都でも、とてもよくスケトウダラを食べていた。例えば八王子の市場などには、大量のスケトウダラと、スケトウダラのドレス(頭部と内蔵を取り去ったもの)がきていた。江戸川区に住んでいたとき、甘辛く煮た「すけその煮つけ」を、魚臭くなく、ご飯に合うのでときどき食べていたものだ。スーパーの惣菜売り場にも煮つけが並んでいて、よく買っていた記憶があるのは安かったからだろう。本種とマダラは生息域も生息水深も重なる。ただ漁に2種が混ざることは少ないのではないかと考えている。今、新潟市沖、佐渡周辺ではとてもたくさんとれていたスケトウダラがあまりとれなくなり、マダラがあくまでも比較しての話だが増えているようだ。今回は新潟市、十日町市、阿賀野市でスケソの切身を探すと、5軒すべてに切身が置かれていたが、すべて北海道産だった。これも新潟沖のスケトウダラが減っているためだろう。ただ、スーパーで会った方に聞いた限りでも、新潟市周辺でのスケソ愛はかわらないようだ。
新潟県新潟市のスーパーでスケソ(スケトウダラ)の切身を買って来た。わがデータベースのスケトウダラの画像を見直してみると、上越市、新潟市、長岡市などで買った切り身パックの画像がある。日本各地に行って水産生物のことを調べているが、単に「たら」といったとき、マダラと考える地域と、スケトウダラと考える地域があるのか、ないのか、意外に重要だと思うがはっきりしない。ただ新潟市は明らかにスケトウダラが「たら」だ。新潟市民は他の地域では考えられないくらいスケソウダラがすきだ。旧蒲原郡(現上越市)、新発田市や長岡市、十日町市などでも同様だろう。頸城海岸(現上越市)では「ごはんがわりにすけそうだらを焼いて、一人が三本も四本も食べることがある。」とある。『聞書き 新潟の食事』(農文協)理由は簡単である、佐渡も含めた新潟沖でたくさんとれていたからだ。新潟市では「すけそ(助宗)」ということが多い。ちなみに流通上でも、例えば関東の食堂などでも「すけそうだら」で、スケトウダラとは言わない。標準和名がスケトウダラとなったのは江戸時代の本草学の書からとったためだ。川路聖謨が佐渡奉行だったときの『島根のすさみ』でも「すけとうだら」だったはず。さて、北海道、東北、新潟との繋がりの深い東京都でも、とてもよくスケトウダラを食べていた。例えば八王子の市場などには、大量のスケトウダラと、スケトウダラのドレス(頭部と内蔵を取り去ったもの)がきていた。江戸川区に住んでいたとき、甘辛く煮た「すけその煮つけ」を、魚臭くなく、ご飯に合うのでときどき食べていたものだ。スーパーの惣菜売り場にも煮つけが並んでいて、よく買っていた記憶があるのは安かったからだろう。本種とマダラは生息域も生息水深も重なる。ただ漁に2種が混ざることは少ないのではないかと考えている。今、新潟市沖、佐渡周辺ではとてもたくさんとれていたスケトウダラがあまりとれなくなり、マダラがあくまでも比較しての話だが増えているようだ。今回は新潟市、十日町市、阿賀野市でスケソの切身を探すと、5軒すべてに切身が置かれていたが、すべて北海道産だった。これも新潟沖のスケトウダラが減っているためだろう。ただ、スーパーで会った方に聞いた限りでも、新潟市周辺でのスケソ愛はかわらないようだ。 2月になり、八王子総合卸売協同組合、舵丸水産に神奈川県横須賀市佐島から小赤イカ(ケンサキイカの子供)が来ていた、というのは何度も書いている.。小イカは使い勝手がよく、やたらにうまいので、一度にまとまって買うべし、だと思っているので、このときも1㎏以上買った。これを水洗いして大きさごとに分けて、小分けにして冷凍して何日もかけて食べた。買った初日はあまりていねいに洗わず、小さいのを集めてパスタに使った。戸棚からあと2つしか残っていないタリアテッレを見つけて、あとは青菜だけのシンプルなものだ。面白いものでパスタには頭足類ツツイカ目の軟体生物がよく合う。
2月になり、八王子総合卸売協同組合、舵丸水産に神奈川県横須賀市佐島から小赤イカ(ケンサキイカの子供)が来ていた、というのは何度も書いている.。小イカは使い勝手がよく、やたらにうまいので、一度にまとまって買うべし、だと思っているので、このときも1㎏以上買った。これを水洗いして大きさごとに分けて、小分けにして冷凍して何日もかけて食べた。買った初日はあまりていねいに洗わず、小さいのを集めてパスタに使った。戸棚からあと2つしか残っていないタリアテッレを見つけて、あとは青菜だけのシンプルなものだ。面白いものでパスタには頭足類ツツイカ目の軟体生物がよく合う。 なんども書くが関東平野に群馬・栃木・茨城・埼玉が接する場所がある。面白いことにここをちょっと歩くと4県ぐるりと回ることができる。ここに水郷地帯がある。群馬県館林市で買った「えび大根」のエビはサクラエビを使っていた。冷凍の小エビも入って豪華である。この「えび大根」はボクには貴重な資料だけど、この貴重さがなかなかわかってくれない。我がデータベースの根幹をなす部分なのだけど、世の中は派手派手しいものには飛びつくが、地味で日常的なものには見向きもしない。「えび大根」は関東平野では栃木県でも茨城県でも、群馬県でも埼玉県でも日常的な惣菜である。1960年前後まで洪水に悩まされていた、東京都の隅田川の東側でも作られていたようだ。あえていうと平野部の、広い淡水域のある日本中の町で作られていると考えるべきかも知れない。また、「えび大根」は淡水魚食でも平野型の郷土料理だ。ボクの生まれた徳島県西部は渓流・清流型淡水魚食で、アユ、アマゴ、オイカワ、ヨシノボリで多彩さに欠ける。これに対して徳島県東部吉野川下流域では淡水エビ・淡水魚を多彩に食べていた。この構図が国内全域で当てはまる気がする。2010年前後から群馬県板倉町にはなんどか淡水生物を調べに行っている。現在、十数年経って、急激に淡水生物を食べる食文化が消えつつある。2010年に板倉町で霞ヶ浦産の「干しえび」を買った。どう使うか直売所で聞いて、親切な老人がいて、作り方を再確認して、少しだけエビの話をしたのだ。板倉町、館林市には本流である利根川に沿うように谷田川が流れている。このあたりで淡水魚食が盛んなのは、利根川ではなく谷田川から広がる水路によってだ。老人達の話では「えび大根のエビは昔は溜池のようなところでつかまえていた」という、谷田川のものは買い、ときどき霞ヶ浦から干したものを売りに来た。とすると溜池のエビはほとんど流れのない水域にいるヌカエビ、谷田川のは少しだけ流れのあるところにいるスジエビ、霞ヶ浦のはほぼ感潮域(少しだけ海水の入り込む)に多いテナガエビでスジエビも混ざると言ったものだったはずだ。写真は館林市、板倉町を流れる谷田川。
なんども書くが関東平野に群馬・栃木・茨城・埼玉が接する場所がある。面白いことにここをちょっと歩くと4県ぐるりと回ることができる。ここに水郷地帯がある。群馬県館林市で買った「えび大根」のエビはサクラエビを使っていた。冷凍の小エビも入って豪華である。この「えび大根」はボクには貴重な資料だけど、この貴重さがなかなかわかってくれない。我がデータベースの根幹をなす部分なのだけど、世の中は派手派手しいものには飛びつくが、地味で日常的なものには見向きもしない。「えび大根」は関東平野では栃木県でも茨城県でも、群馬県でも埼玉県でも日常的な惣菜である。1960年前後まで洪水に悩まされていた、東京都の隅田川の東側でも作られていたようだ。あえていうと平野部の、広い淡水域のある日本中の町で作られていると考えるべきかも知れない。また、「えび大根」は淡水魚食でも平野型の郷土料理だ。ボクの生まれた徳島県西部は渓流・清流型淡水魚食で、アユ、アマゴ、オイカワ、ヨシノボリで多彩さに欠ける。これに対して徳島県東部吉野川下流域では淡水エビ・淡水魚を多彩に食べていた。この構図が国内全域で当てはまる気がする。2010年前後から群馬県板倉町にはなんどか淡水生物を調べに行っている。現在、十数年経って、急激に淡水生物を食べる食文化が消えつつある。2010年に板倉町で霞ヶ浦産の「干しえび」を買った。どう使うか直売所で聞いて、親切な老人がいて、作り方を再確認して、少しだけエビの話をしたのだ。板倉町、館林市には本流である利根川に沿うように谷田川が流れている。このあたりで淡水魚食が盛んなのは、利根川ではなく谷田川から広がる水路によってだ。老人達の話では「えび大根のエビは昔は溜池のようなところでつかまえていた」という、谷田川のものは買い、ときどき霞ヶ浦から干したものを売りに来た。とすると溜池のエビはほとんど流れのない水域にいるヌカエビ、谷田川のは少しだけ流れのあるところにいるスジエビ、霞ヶ浦のはほぼ感潮域(少しだけ海水の入り込む)に多いテナガエビでスジエビも混ざると言ったものだったはずだ。写真は館林市、板倉町を流れる谷田川。 我がサイトというかデータベースはたくさんの問題点を抱えている。最初にデジタルカメラを買ったのが、1999年なのは写真データを見るとわかる。オリンパスの、電源が電池の重いカメラだ。その前のフィルム時代にはフィルムそのまま保存したものと、スキャニングし、データ化して保存したものとがある。そのフィルム時代のデータには実に見にくい、という問題点があり、明らかに負の遺産である。さて、我がデータベースのサバ属のフォルダーに料理名「バルメ」というフォルダーがある。フィルムをスキャニングした不鮮明な料理画像と、料理をお教えてくれた友人の名と、簡単な料理法のメモがある。その本人に聞いてみたが忘れている。要するに魚とくにサバ科の切り身のサンドイッチであるが、料理名も詳しい料理法もわからない。たぶん10年振りに、写真の見た目通りに、サバ サンドイッチで、検索したら、トルコ料理のサバのサンドイッチ、「Balik Ekmek」が出て来て、やっと謎がとけた。「バルメ」は「Balik Ekmek」のことだったのだ。1990年代に日本の航空会社が中近東への旅を企画して、それについて行ったのが友人だったのだ。トルコのイスタンブールの料理だとある。イスタンブールは黒海に面しているので、サバサンドのサバはサバでも、Scomber colias Gmelin, 1789 でトルコ語は不明だが、英名をAtlantic chub mackerel という。
我がサイトというかデータベースはたくさんの問題点を抱えている。最初にデジタルカメラを買ったのが、1999年なのは写真データを見るとわかる。オリンパスの、電源が電池の重いカメラだ。その前のフィルム時代にはフィルムそのまま保存したものと、スキャニングし、データ化して保存したものとがある。そのフィルム時代のデータには実に見にくい、という問題点があり、明らかに負の遺産である。さて、我がデータベースのサバ属のフォルダーに料理名「バルメ」というフォルダーがある。フィルムをスキャニングした不鮮明な料理画像と、料理をお教えてくれた友人の名と、簡単な料理法のメモがある。その本人に聞いてみたが忘れている。要するに魚とくにサバ科の切り身のサンドイッチであるが、料理名も詳しい料理法もわからない。たぶん10年振りに、写真の見た目通りに、サバ サンドイッチで、検索したら、トルコ料理のサバのサンドイッチ、「Balik Ekmek」が出て来て、やっと謎がとけた。「バルメ」は「Balik Ekmek」のことだったのだ。1990年代に日本の航空会社が中近東への旅を企画して、それについて行ったのが友人だったのだ。トルコのイスタンブールの料理だとある。イスタンブールは黒海に面しているので、サバサンドのサバはサバでも、Scomber colias Gmelin, 1789 でトルコ語は不明だが、英名をAtlantic chub mackerel という。 この料理名を初めて聞いたのは、1980年前後のことだ。まだおんぼろシビックに乗っているとき、滋賀県安土あたりで大迷いに迷っていたとき田園のど真ん中で、地獄で仏、若い夫婦にやっと出会え、道を聞くことができた。二人は、弁当をつかっていた。ナビのない時代ならでは行き着いた人気のまったくない畑、もしくは水抜きした田んぼの周りは実にのどかだったし、きれいなところであった。「昼ご飯が食べたいので店を探している」と言ったら、近江八幡市の食堂の場所を教わり、少しだけ話し込んだ。ついでに梅干し入りのお握りを恵んでくれたのは、懐かしい想い出である。そのとき、「●●●なんとか入りの方がいいけど、もうない(意訳)」という話だった。この「●●●」が気になってしゃないけれど、やや塩加減のきついお握りのうまかったことの方が印象に残っている。それから30年後に、滋賀県長浜市余呉川で魚取りをしていたときに会った、聞いたことにはぜんぜん答えてくれない、語りまくるバアサマ達が、その「●●●●●●」のヒントをくれたのだ。要するにすき焼きの残りである。たった2名から聞いた話で判断してはいけないけど、このユニークな料理名が日常的に作られていて、残ったものをお握りの種に使うのは1人だけではない、ようだ。滋賀県ではすき焼きのことを「じゅんじゅん」という。牛肉で作ることが多いようだが、湖魚のイサザ(ハゼの仲間)、ナマズ、モロコ(ホンモロコ)、ウナギなどでも作る。「じゅんじゅん」と知り、自分でもで作り始めたのは、1991年に『聞書き 滋賀の食事』(農文協)に作り方が載っていたからだ。滋賀県の素晴らしいところは、この聞書きシリーズの後にも、日常的な食事の歴史と現状を調べ続けたことである。
この料理名を初めて聞いたのは、1980年前後のことだ。まだおんぼろシビックに乗っているとき、滋賀県安土あたりで大迷いに迷っていたとき田園のど真ん中で、地獄で仏、若い夫婦にやっと出会え、道を聞くことができた。二人は、弁当をつかっていた。ナビのない時代ならでは行き着いた人気のまったくない畑、もしくは水抜きした田んぼの周りは実にのどかだったし、きれいなところであった。「昼ご飯が食べたいので店を探している」と言ったら、近江八幡市の食堂の場所を教わり、少しだけ話し込んだ。ついでに梅干し入りのお握りを恵んでくれたのは、懐かしい想い出である。そのとき、「●●●なんとか入りの方がいいけど、もうない(意訳)」という話だった。この「●●●」が気になってしゃないけれど、やや塩加減のきついお握りのうまかったことの方が印象に残っている。それから30年後に、滋賀県長浜市余呉川で魚取りをしていたときに会った、聞いたことにはぜんぜん答えてくれない、語りまくるバアサマ達が、その「●●●●●●」のヒントをくれたのだ。要するにすき焼きの残りである。たった2名から聞いた話で判断してはいけないけど、このユニークな料理名が日常的に作られていて、残ったものをお握りの種に使うのは1人だけではない、ようだ。滋賀県ではすき焼きのことを「じゅんじゅん」という。牛肉で作ることが多いようだが、湖魚のイサザ(ハゼの仲間)、ナマズ、モロコ(ホンモロコ)、ウナギなどでも作る。「じゅんじゅん」と知り、自分でもで作り始めたのは、1991年に『聞書き 滋賀の食事』(農文協)に作り方が載っていたからだ。滋賀県の素晴らしいところは、この聞書きシリーズの後にも、日常的な食事の歴史と現状を調べ続けたことである。 高知県大月町はなんとしても再訪したい地ナンバーワンである。水産生物を人との関わりから調べている人間としては、ここほど興味深いところがあるとは思えない。2015年に行ったものの、ほとんど時間がなかったのが残念でならない。いくつかの貴重な話が聞取できたが、取り分け興味深かったのがニザダイの利用法である。大月町ではクロハゲという。道の駅大月というボクが道の駅ランキングをつけるとしたら第1位といった、最高の道の駅の魚売り場にたくさん並んでいた。気になったのが皮付きの「たたき」だ。ニザダイの皮はサンドペーパーのようで硬く、鱗は引くに引けない。皮がうまいという話は、同じニザダイ科のクロハギ属の話として、南半球の熱帯域で聞取している。これと同様のことが、この国の高知県でもありえるのか、知りたくて知りたくて身もだえるほどだ。とりあえずは、同じ物を作ってみるしかない。ちなみに今回のニザダイは活魚をしめて、帰宅後すぐに内臓を抜いたもので作っている。大月町でもニザダイは内臓を抜いた状態で売っている。道の駅で、この売り方が気にくわないという老人がいて、「クロハゲは臭い方がうまい」らしい。この世代的な嗜好の変化も面白いのである。余談になるが、本日で4日目になるが、刺身にして非常においしく、もちろん臭味はまったくない。
高知県大月町はなんとしても再訪したい地ナンバーワンである。水産生物を人との関わりから調べている人間としては、ここほど興味深いところがあるとは思えない。2015年に行ったものの、ほとんど時間がなかったのが残念でならない。いくつかの貴重な話が聞取できたが、取り分け興味深かったのがニザダイの利用法である。大月町ではクロハゲという。道の駅大月というボクが道の駅ランキングをつけるとしたら第1位といった、最高の道の駅の魚売り場にたくさん並んでいた。気になったのが皮付きの「たたき」だ。ニザダイの皮はサンドペーパーのようで硬く、鱗は引くに引けない。皮がうまいという話は、同じニザダイ科のクロハギ属の話として、南半球の熱帯域で聞取している。これと同様のことが、この国の高知県でもありえるのか、知りたくて知りたくて身もだえるほどだ。とりあえずは、同じ物を作ってみるしかない。ちなみに今回のニザダイは活魚をしめて、帰宅後すぐに内臓を抜いたもので作っている。大月町でもニザダイは内臓を抜いた状態で売っている。道の駅で、この売り方が気にくわないという老人がいて、「クロハゲは臭い方がうまい」らしい。この世代的な嗜好の変化も面白いのである。余談になるが、本日で4日目になるが、刺身にして非常においしく、もちろん臭味はまったくない。 琉球列島以南はいざしらず、日本列島でコイ食わぬところは少ない。食べない地区はあるが、例えば県とか、流域を考えるとコイは全国的な食い物と考えていい。一度食えばわかることだが、コイに恋するほどコイはうまい。この場合のコイはヤマトゴイとされる中国や台湾などから養殖用に輸入されて、大大的に養殖され、また野生化が進んだもののことだ。ヤマトゴイの由来は一説には奈良県大和郡山市で養殖用に作り出されたので、大和郡山の大和を冠したのだとされている。大和郡山は今では、観賞用の金魚で有名だが、古くは食用のコイやフナを養殖していたのだろう。この養殖されたヤマトゴイは冷蔵庫のない時代、貴重な保存しておける生きたたんぱく源だった。飛鳥時代・奈良時代を通して官人に対して動物たんぱくの供給はないに等しい。それに銭(平安前期までの銭は使える地域が非常に狭かったので、平安後期の銭とは別物)だが、銭でサケの干ものなど少ないながらたんぱく源を買い、また奈良盆地ではウナギ、コイ(在来種かも)などを含めて採取して食べていたのだろう。そうしないと、ヒトは生きていけない。コイはヒトが生きていくためにも需要だったはずである。このコイを食べる習慣のある地域を少しずつ探している。コイを食べる地域には供給地が存在する。群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の四県が接する水郷地帯を中心に放射線状にコイを食べる地域が広がる。だから関東平野のウナギ屋の多くがコイの洗いを出す。これをコイに最適な生息環境に広がるコイを食べる地域という。この四県が接する水郷地帯以上に関東での巨大な供給地が霞ヶ浦・利根川である。この平野型に対して山間部型がある。生産の場となっているのが山間地にある田であり、溜池であった。これを産業に進化させた地域が長野県佐久である。佐久のコイ養殖業者は生きたままのコイを長野県内だけではなく、軽井沢を越えて群馬県にまで売って歩いていたようである。だから群馬県松井田町の老人達は「佐久鯉」という言語を今でも使う。佐久は歴史的に見ても非常に重要な地といってもいい。ちなみに京料理が現在のように洗練されたのも、コイ・フナをはじめ琵琶湖の淡水生物があったからだ。さて、群馬県に行ったらコイを買わずには帰って来れない、と考えている。今回も筒切り1尾分ほかを買って来た。もう真子がついている。いつも館林市か板倉町で買っているが、この地では鱗を引くのが特徴だと思う。個人的には鱗付きのほうが好きだが、コイであるだけでありがたい。
琉球列島以南はいざしらず、日本列島でコイ食わぬところは少ない。食べない地区はあるが、例えば県とか、流域を考えるとコイは全国的な食い物と考えていい。一度食えばわかることだが、コイに恋するほどコイはうまい。この場合のコイはヤマトゴイとされる中国や台湾などから養殖用に輸入されて、大大的に養殖され、また野生化が進んだもののことだ。ヤマトゴイの由来は一説には奈良県大和郡山市で養殖用に作り出されたので、大和郡山の大和を冠したのだとされている。大和郡山は今では、観賞用の金魚で有名だが、古くは食用のコイやフナを養殖していたのだろう。この養殖されたヤマトゴイは冷蔵庫のない時代、貴重な保存しておける生きたたんぱく源だった。飛鳥時代・奈良時代を通して官人に対して動物たんぱくの供給はないに等しい。それに銭(平安前期までの銭は使える地域が非常に狭かったので、平安後期の銭とは別物)だが、銭でサケの干ものなど少ないながらたんぱく源を買い、また奈良盆地ではウナギ、コイ(在来種かも)などを含めて採取して食べていたのだろう。そうしないと、ヒトは生きていけない。コイはヒトが生きていくためにも需要だったはずである。このコイを食べる習慣のある地域を少しずつ探している。コイを食べる地域には供給地が存在する。群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の四県が接する水郷地帯を中心に放射線状にコイを食べる地域が広がる。だから関東平野のウナギ屋の多くがコイの洗いを出す。これをコイに最適な生息環境に広がるコイを食べる地域という。この四県が接する水郷地帯以上に関東での巨大な供給地が霞ヶ浦・利根川である。この平野型に対して山間部型がある。生産の場となっているのが山間地にある田であり、溜池であった。これを産業に進化させた地域が長野県佐久である。佐久のコイ養殖業者は生きたままのコイを長野県内だけではなく、軽井沢を越えて群馬県にまで売って歩いていたようである。だから群馬県松井田町の老人達は「佐久鯉」という言語を今でも使う。佐久は歴史的に見ても非常に重要な地といってもいい。ちなみに京料理が現在のように洗練されたのも、コイ・フナをはじめ琵琶湖の淡水生物があったからだ。さて、群馬県に行ったらコイを買わずには帰って来れない、と考えている。今回も筒切り1尾分ほかを買って来た。もう真子がついている。いつも館林市か板倉町で買っているが、この地では鱗を引くのが特徴だと思う。個人的には鱗付きのほうが好きだが、コイであるだけでありがたい。 もちろん関東にも地酒はあったにはあったが、江戸の酒の主流は江戸時代を通じて下りものであった。江戸時代中期までは伊丹、池田から、その後、灘の酒にとってかわるが、下り酒であったことは間違いがない。同じように江戸時代に始まった居酒屋(酒屋に居ながらにして飲む)での基本は安い温めた豆腐と、こなから(二合半)の酒であった。要するに居酒屋は下り酒を飲むための場所だったのだ。「目黒」と呼ばれたクロマグロの3尺以下のサイズが文化文政時代、天保時代(1804-1844)に日本橋魚河岸に大量に揚がり、江戸の町でこの「目黒」を食べる文化がより強く刻まれていく。居酒屋でも「目黒」の刺身や煮込み料理の「ねぎま」が盛んに提供されるようになる。天保期(1830-44)には「ねぎま」は居酒屋定番の品書きである豆腐よりも安くなったとされている。これがために、大岡越前をしてあれほどに苦しんだ豆腐の価格が下がったという。それではその「ねぎま」とはどんなものだろう。今現在でも「ねぎま鍋」は都内居酒屋でも食すことができるが、もっと遙かに簡単なものである「ねぎま」は食べたことがない。「ねぎま」はマグロの煮込み料理だろう。しかも文化文政以後に盛んに作られるようになったとすると、どんなものかと考えてみた。醤油は関東周辺で17世紀から作られていた。みりんが関東で大量に作られるようになったのは、文化期の流山の白味醂以後のことだろう。醤油とみりんが揃えば、煮込みは簡単にできる。醤油・みりんは同量。ここに水を加えて加減する。温めた中にサイコロ状に切ったマグロを放り込んで、しょうがとともにことこと煮込む。江戸時代、客の注文があれば大量に煮込まれている「ねぎま」の、もう一つの主役である白ねぎを投入する。ちなみに関東で土を寄せて作る「白ねぎ」が誕生するのは気候のせいである。関西と関東で土ものでの栽培方法の違いと言えば霜柱対策ではないか? 1977年の農閑期(11月後半と12月)に、群馬県太田市の農業調査に行ったことがある。朝起きてびっくりしたのが霜柱の長さだった。明らかに15cm以上(当時測っている)あり、作物といえばねぎ、植えたばかりの麦しか残っていなかった。ねぎは大量の土に守られることで関東平野で栽培できたのだと考えた。というか農家の方に教わった気がする。醤油とみりん味で煮込んだマグロに白いねぎをたくさん乗せたのが、江戸時代以来の「ねぎま」だ。今回は生の切り身を煮汁に投入するときれいではないので、湯引きしてから投入したが、煮込めば煮込むほどうまい。酒が進む。今回は剣菱を5勺。剣菱は、下り酒発祥の地、伊丹で誕生し、後に灘(神戸市御影)に移る。
もちろん関東にも地酒はあったにはあったが、江戸の酒の主流は江戸時代を通じて下りものであった。江戸時代中期までは伊丹、池田から、その後、灘の酒にとってかわるが、下り酒であったことは間違いがない。同じように江戸時代に始まった居酒屋(酒屋に居ながらにして飲む)での基本は安い温めた豆腐と、こなから(二合半)の酒であった。要するに居酒屋は下り酒を飲むための場所だったのだ。「目黒」と呼ばれたクロマグロの3尺以下のサイズが文化文政時代、天保時代(1804-1844)に日本橋魚河岸に大量に揚がり、江戸の町でこの「目黒」を食べる文化がより強く刻まれていく。居酒屋でも「目黒」の刺身や煮込み料理の「ねぎま」が盛んに提供されるようになる。天保期(1830-44)には「ねぎま」は居酒屋定番の品書きである豆腐よりも安くなったとされている。これがために、大岡越前をしてあれほどに苦しんだ豆腐の価格が下がったという。それではその「ねぎま」とはどんなものだろう。今現在でも「ねぎま鍋」は都内居酒屋でも食すことができるが、もっと遙かに簡単なものである「ねぎま」は食べたことがない。「ねぎま」はマグロの煮込み料理だろう。しかも文化文政以後に盛んに作られるようになったとすると、どんなものかと考えてみた。醤油は関東周辺で17世紀から作られていた。みりんが関東で大量に作られるようになったのは、文化期の流山の白味醂以後のことだろう。醤油とみりんが揃えば、煮込みは簡単にできる。醤油・みりんは同量。ここに水を加えて加減する。温めた中にサイコロ状に切ったマグロを放り込んで、しょうがとともにことこと煮込む。江戸時代、客の注文があれば大量に煮込まれている「ねぎま」の、もう一つの主役である白ねぎを投入する。ちなみに関東で土を寄せて作る「白ねぎ」が誕生するのは気候のせいである。関西と関東で土ものでの栽培方法の違いと言えば霜柱対策ではないか? 1977年の農閑期(11月後半と12月)に、群馬県太田市の農業調査に行ったことがある。朝起きてびっくりしたのが霜柱の長さだった。明らかに15cm以上(当時測っている)あり、作物といえばねぎ、植えたばかりの麦しか残っていなかった。ねぎは大量の土に守られることで関東平野で栽培できたのだと考えた。というか農家の方に教わった気がする。醤油とみりん味で煮込んだマグロに白いねぎをたくさん乗せたのが、江戸時代以来の「ねぎま」だ。今回は生の切り身を煮汁に投入するときれいではないので、湯引きしてから投入したが、煮込めば煮込むほどうまい。酒が進む。今回は剣菱を5勺。剣菱は、下り酒発祥の地、伊丹で誕生し、後に灘(神戸市御影)に移る。 木曽三川といわれる木曽川、長良川、揖斐川の下流域を輪中地帯という。岐阜県、愛知県、三重県にまたがり水郷地帯というよりも河川の氾濫地帯と言った方がいいだろう。平安時代、荘園としては三河の方が重要視されていたようだし、鎌倉時代になってじょじょに治水が行われて、江戸時代18世紀には薩摩藩などによって、尾張側(木曽三川の東)の平地が安定的な耕地になるが、現在の海津市や愛西市、弥富市、長島(現桑名市)などはおいてけぼりになり、1960年代(1970年代かも)になっても氾濫の危険をかかえていた。ちなみに鹿児島、薩摩藩が幕末に飛躍するのは、この治水工事で、藩主、大御所で酷薄な島津重豪がどん底を見たからだ。この地域こそは国内で淡水魚食を調べている人間にとって外せない地域でもある。ちなみにこの尾張・南美濃は基本的たんぱく源は淡水魚という地域だった。とすると織田信長も豊臣秀吉も、加藤清正も淡水魚で育ったといっても間違いではないと思う。ちなみに尾張人はこの輪中地帯と同じようなものを食べていたが、この輪中地帯の人々の土地にたいする執着心がわからなかったのではないか? これがために織田信長は長島攻めに苦労したのだと思う。河川・水路が交通の動脈のごときものであった時代に、この河川が交わり、周辺の平野に灌漑を施し、堤防を築くということが築城につながり、また交易(貿易)に目を向けさせることになる。戦国時代に合戦が消耗戦になることにいち早く気づいたのも、織田信長など交易に長けた尾張人である。余談だがこの木曽三川の、より原始的なバージョンが江戸時代以前の江戸だ。干潟、江戸湾からの汽水・海水生物も食べているが、それ以上に淡水生物へのタンパク質依存が高いということで共通している。さてその輪中地帯にあるのが海津市で、ここに唐突にあるのが千代保稲荷(おちょぼさん)だ。鉄道のない地域であり、取り立てて市街化された場所がないところに、忽然と参道という商店街がある。名物の串カツやどて焼き、和菓子もあるが、それ以上にこの千代保稲荷を特徴付けるのが淡水魚なのである。ウナギやナマズ、コイなどの料理が楽しめ、「ふなみそ(フナと大豆の煮込み料理)」、佃煮などの加工品なども買える。今回、愛知県人なのに先島諸島住民という若い衆にいただいたのが千代保稲荷、大周屋の「新バエの佃煮」と「いなごの佃煮」だ。イナゴはともかく、新バエは我がサイトの調べているもののひとつなので、実に興味深い。「はえ」というのは多くの地方でオイカワの呼び名であったりするが、この輪中地帯周辺では小ブナのことである。フナにはいろんな種類がいると思うが、たぶんギンブナだろう。フナの小型を「新バエ」というのは愛知県津島市、そして三重県桑名市、そして海津市で確認しているが、もっと広範囲に愛知県西部、南美濃、伊勢で使われている呼び名だと考えている。小ブナの加工品は日本各地に残る。関東にも多く、長野県佐久などにもある。愛知県・岐阜県・三重県があって、岡山県にも今も残る。ちなみに佃煮は醤油を使うが、本来はゆで干し、塩煮だろう。それが江戸時代になり醤油が普及して佃煮に変化する。佃煮という江戸っぽい名前がいかに変か、というのが、このあたりからわかると思う。淡水の小型魚を加工するのはこちらの方が先だと思うのだ。さて千代保稲荷、大周屋の「新バエ」がうまい。炊きたてご飯に合う。非常に均質に柔らかく炊けているのも魅力的である。強烈に輪中地帯への熱量が高まってきて困る。先島諸島の若い衆に感謝する。
木曽三川といわれる木曽川、長良川、揖斐川の下流域を輪中地帯という。岐阜県、愛知県、三重県にまたがり水郷地帯というよりも河川の氾濫地帯と言った方がいいだろう。平安時代、荘園としては三河の方が重要視されていたようだし、鎌倉時代になってじょじょに治水が行われて、江戸時代18世紀には薩摩藩などによって、尾張側(木曽三川の東)の平地が安定的な耕地になるが、現在の海津市や愛西市、弥富市、長島(現桑名市)などはおいてけぼりになり、1960年代(1970年代かも)になっても氾濫の危険をかかえていた。ちなみに鹿児島、薩摩藩が幕末に飛躍するのは、この治水工事で、藩主、大御所で酷薄な島津重豪がどん底を見たからだ。この地域こそは国内で淡水魚食を調べている人間にとって外せない地域でもある。ちなみにこの尾張・南美濃は基本的たんぱく源は淡水魚という地域だった。とすると織田信長も豊臣秀吉も、加藤清正も淡水魚で育ったといっても間違いではないと思う。ちなみに尾張人はこの輪中地帯と同じようなものを食べていたが、この輪中地帯の人々の土地にたいする執着心がわからなかったのではないか? これがために織田信長は長島攻めに苦労したのだと思う。河川・水路が交通の動脈のごときものであった時代に、この河川が交わり、周辺の平野に灌漑を施し、堤防を築くということが築城につながり、また交易(貿易)に目を向けさせることになる。戦国時代に合戦が消耗戦になることにいち早く気づいたのも、織田信長など交易に長けた尾張人である。余談だがこの木曽三川の、より原始的なバージョンが江戸時代以前の江戸だ。干潟、江戸湾からの汽水・海水生物も食べているが、それ以上に淡水生物へのタンパク質依存が高いということで共通している。さてその輪中地帯にあるのが海津市で、ここに唐突にあるのが千代保稲荷(おちょぼさん)だ。鉄道のない地域であり、取り立てて市街化された場所がないところに、忽然と参道という商店街がある。名物の串カツやどて焼き、和菓子もあるが、それ以上にこの千代保稲荷を特徴付けるのが淡水魚なのである。ウナギやナマズ、コイなどの料理が楽しめ、「ふなみそ(フナと大豆の煮込み料理)」、佃煮などの加工品なども買える。今回、愛知県人なのに先島諸島住民という若い衆にいただいたのが千代保稲荷、大周屋の「新バエの佃煮」と「いなごの佃煮」だ。イナゴはともかく、新バエは我がサイトの調べているもののひとつなので、実に興味深い。「はえ」というのは多くの地方でオイカワの呼び名であったりするが、この輪中地帯周辺では小ブナのことである。フナにはいろんな種類がいると思うが、たぶんギンブナだろう。フナの小型を「新バエ」というのは愛知県津島市、そして三重県桑名市、そして海津市で確認しているが、もっと広範囲に愛知県西部、南美濃、伊勢で使われている呼び名だと考えている。小ブナの加工品は日本各地に残る。関東にも多く、長野県佐久などにもある。愛知県・岐阜県・三重県があって、岡山県にも今も残る。ちなみに佃煮は醤油を使うが、本来はゆで干し、塩煮だろう。それが江戸時代になり醤油が普及して佃煮に変化する。佃煮という江戸っぽい名前がいかに変か、というのが、このあたりからわかると思う。淡水の小型魚を加工するのはこちらの方が先だと思うのだ。さて千代保稲荷、大周屋の「新バエ」がうまい。炊きたてご飯に合う。非常に均質に柔らかく炊けているのも魅力的である。強烈に輪中地帯への熱量が高まってきて困る。先島諸島の若い衆に感謝する。 関東や日本海などで暮らしていると思いも寄らないが、タカラガイは多産する地域では普通の食用貝のひとつでしかない。熱帯域では大型のホシダカラなどが食べられていたが、同じタカラガイ科でも食べていい種と食べない種があるなど、調べると奥の深さを感じる。鹿児島県屋久島一湊では、磯の貝を盛んに採取して食べている。主な獲物はイボアナゴで、これを「磯もん」という。「磯もん」は非常に多く、食べられる部分が大きく、また味がいいので、他の貝類はあまりとらないというが、古くはウマンコ(ハナマルユキ)もとって食べていたという。同じ場所にいるキイロダカラは食べないことからタカラガイ科でも選択的に採取していたことになる。
関東や日本海などで暮らしていると思いも寄らないが、タカラガイは多産する地域では普通の食用貝のひとつでしかない。熱帯域では大型のホシダカラなどが食べられていたが、同じタカラガイ科でも食べていい種と食べない種があるなど、調べると奥の深さを感じる。鹿児島県屋久島一湊では、磯の貝を盛んに採取して食べている。主な獲物はイボアナゴで、これを「磯もん」という。「磯もん」は非常に多く、食べられる部分が大きく、また味がいいので、他の貝類はあまりとらないというが、古くはウマンコ(ハナマルユキ)もとって食べていたという。同じ場所にいるキイロダカラは食べないことからタカラガイ科でも選択的に採取していたことになる。 魚のみそ汁はたぶん国内全域で作られていると思っている。特に漁師さんにとっては日常食に近いものだろう。そのせいか、漁師さんに「みそ汁を作りますか?」、「どんな魚で作りますか?」と聞いてもなかなか返事が返ってこない。魚のみそ汁はなかなか表舞台に出てこない地味な存在なのかも知れぬ。だが、みそ汁こそは、魚料理でもっとも優れているもののひとつなのだ。基本的に汁であるが、実は菜(さい)でもある。みそ汁を作ると、あとはご飯だけで一食になるし、満足感も得られる。しかも魚の可食部を無駄なく食べ尽くすことができる。重要な郷土料理なのだけど、先にも述べたようにあまりにも日常的なために、郷土料理として浮かび上がってこないのが残念でならない。沖縄のように食堂などで、汁以上に主菜ならクローズアップされるところだが、毎朝食べるとか、酒の友にするとかだと、作って食べていること自体に気がづかないのだと思う。長崎県平戸市度島の福畑敏光さんのお宅では、ホウボウのみそ汁をよく作るようだ。とすると平戸周辺でホウボウが昔からよく揚がっていた証拠にもなる。前海は岩と砂地が入り交じっているのかも知れない、などと想像するのも楽しい。作り方は聞くまでもないが、豆腐を加えるというので、豆腐入りホウボウのみそ汁を作ってみた。平戸は麦みそ圏なので近所で長崎県の麦みそを購う。わけぎが欲しかったのだが、東京では手に入れにくいので小ネギで代用する。
魚のみそ汁はたぶん国内全域で作られていると思っている。特に漁師さんにとっては日常食に近いものだろう。そのせいか、漁師さんに「みそ汁を作りますか?」、「どんな魚で作りますか?」と聞いてもなかなか返事が返ってこない。魚のみそ汁はなかなか表舞台に出てこない地味な存在なのかも知れぬ。だが、みそ汁こそは、魚料理でもっとも優れているもののひとつなのだ。基本的に汁であるが、実は菜(さい)でもある。みそ汁を作ると、あとはご飯だけで一食になるし、満足感も得られる。しかも魚の可食部を無駄なく食べ尽くすことができる。重要な郷土料理なのだけど、先にも述べたようにあまりにも日常的なために、郷土料理として浮かび上がってこないのが残念でならない。沖縄のように食堂などで、汁以上に主菜ならクローズアップされるところだが、毎朝食べるとか、酒の友にするとかだと、作って食べていること自体に気がづかないのだと思う。長崎県平戸市度島の福畑敏光さんのお宅では、ホウボウのみそ汁をよく作るようだ。とすると平戸周辺でホウボウが昔からよく揚がっていた証拠にもなる。前海は岩と砂地が入り交じっているのかも知れない、などと想像するのも楽しい。作り方は聞くまでもないが、豆腐を加えるというので、豆腐入りホウボウのみそ汁を作ってみた。平戸は麦みそ圏なので近所で長崎県の麦みそを購う。わけぎが欲しかったのだが、東京では手に入れにくいので小ネギで代用する。 金曜日の朝、探したのはサンノジ(ニザダイ)とメジナだった。箱根颪が体にじわじわと染みてくる。今夜こそは鍋だとだ決めたのは、メジナを連れて帰るつもりだったからだ。事実、日渉丸、ワタルさんのところに素晴らしいメジナがあった。これを競り落とした人に分けてもらおうと思ったら、ヤオマサのナイトウさんだったのだ。ついでにニザダイもナイトウさんが落としているではないか。ちょうどそこに漁協定置の草野さんが珍魚中の珍魚をくれた。まったく同定できない魚にメジナもニザダイも頭から吹っ飛んでしまったのである。このあたりがボクのダメなところだけど、それくらいの珍魚だったのだ。
金曜日の朝、探したのはサンノジ(ニザダイ)とメジナだった。箱根颪が体にじわじわと染みてくる。今夜こそは鍋だとだ決めたのは、メジナを連れて帰るつもりだったからだ。事実、日渉丸、ワタルさんのところに素晴らしいメジナがあった。これを競り落とした人に分けてもらおうと思ったら、ヤオマサのナイトウさんだったのだ。ついでにニザダイもナイトウさんが落としているではないか。ちょうどそこに漁協定置の草野さんが珍魚中の珍魚をくれた。まったく同定できない魚にメジナもニザダイも頭から吹っ飛んでしまったのである。このあたりがボクのダメなところだけど、それくらいの珍魚だったのだ。 もうずいぶん昔の話だが、静岡県焼津市、長兼丸の船上で富士山を眺めながら、元カツオ漁師の長谷川久志さん、長谷川さんの義理のお兄さんとカツオの話をしたことがある。たしか、長谷川久志さんが、お母さんのカツオの角煮の作り方は手が込んでいて、前夜から漬け込みをして煮る、という話だった。そーっと聞いて、以後真似しているが、前夜からなので12時間くらいかなと考えていて、漬け込んだ翌日に煮ていた。作ってみてびっくり、漬け込まないで作るものとは比べものにならないくらいにうまい。
もうずいぶん昔の話だが、静岡県焼津市、長兼丸の船上で富士山を眺めながら、元カツオ漁師の長谷川久志さん、長谷川さんの義理のお兄さんとカツオの話をしたことがある。たしか、長谷川久志さんが、お母さんのカツオの角煮の作り方は手が込んでいて、前夜から漬け込みをして煮る、という話だった。そーっと聞いて、以後真似しているが、前夜からなので12時間くらいかなと考えていて、漬け込んだ翌日に煮ていた。作ってみてびっくり、漬け込まないで作るものとは比べものにならないくらいにうまい。 カツオの旬がだんだんわからなくなってきている。11月初旬には太平洋側の下りガツオもとれているだろうし、鹿児島県でも揚がっている。そして日本海だ。島根県浜田市などあの巨大な競り場にずらりとカツオが並んでいる。そして今回のものは若狭湾北部敦賀産なのだ。太平洋側のカツオは鹿児島県沖などの居続けのカツオもいるが、基本的に北上(上り)してまた南下(下る)してくる。下りの方が脂はのっていて旬がわかりやすい。個人的には日本海のカツオは回遊経路がわからないためもあって旬がいまだにわからない。ちなみに日本海で揚がるカツオを迷いガツオなんて変な言いかたするのは止めた方がいい。人間は迷うけどカツオは温かい海に沿って北上する。日本海の温暖化から回遊域が広がっただけの話である。さて、福井県は嶺南と嶺北でまるで別の県のようである。嶺南敦賀は若狭湾にめんし、滋賀県の真北であり、京都府の隣だ。嶺北が北陸なのに対して近畿とか畿内といった感じがする。あの敦賀からカツオがくるんだと思うと感慨深い。余談になるが市場流通の魚にはこのような【心の中での旅の時間】が持てるのがいいのである。
カツオの旬がだんだんわからなくなってきている。11月初旬には太平洋側の下りガツオもとれているだろうし、鹿児島県でも揚がっている。そして日本海だ。島根県浜田市などあの巨大な競り場にずらりとカツオが並んでいる。そして今回のものは若狭湾北部敦賀産なのだ。太平洋側のカツオは鹿児島県沖などの居続けのカツオもいるが、基本的に北上(上り)してまた南下(下る)してくる。下りの方が脂はのっていて旬がわかりやすい。個人的には日本海のカツオは回遊経路がわからないためもあって旬がいまだにわからない。ちなみに日本海で揚がるカツオを迷いガツオなんて変な言いかたするのは止めた方がいい。人間は迷うけどカツオは温かい海に沿って北上する。日本海の温暖化から回遊域が広がっただけの話である。さて、福井県は嶺南と嶺北でまるで別の県のようである。嶺南敦賀は若狭湾にめんし、滋賀県の真北であり、京都府の隣だ。嶺北が北陸なのに対して近畿とか畿内といった感じがする。あの敦賀からカツオがくるんだと思うと感慨深い。余談になるが市場流通の魚にはこのような【心の中での旅の時間】が持てるのがいいのである。 慣用句、「猫に鰹節」を小学生のとき教えられて、「いんじゃこ(いりこ)」と思ったことがある。ときどき家に巣くう猫にやる御馳走は「いんじゃこ」だったからだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の商店街のボクの家に「いんじゃこ(徳島県西部では最低限いりこで、煮干しと言わないはず)」は常にあったが、カツオ節は見た記憶がない。寒い時季に教室に入ったらストーブがたかれていてとても温かかった。「杉玉鉄砲(細い竹とひごで作る水鉄砲のミニ版で杉の実を飛ばす。寒い時季のもの)」などの話をしていたら、同級生の息に「いんじゃこ」の匂いがした。ボクは典型的な学習障害児童だったので、好きなことしか興味がなく、勉強などはまったくしなかったが、やたらに食べ物のことが好きで興味があった。覚えていることも食べ物のことが多い。要するにボクの町の貞光小学校に通っていた家では、ほぼ「いんじゃこ」だったと思っている。今でもやたらに日常的に「いんじゃこ」を使っているので、ボクの体のかなりの部分が「いんじゃこ」で出来上がっていそうだ。去年暮れ、愛知県豊橋市で節類を大量買いしている。愛知県は「めじか節(マルソウダ)」の種類(節自体の大きさと削り節なので厚み)が多く、混合節にも「めじか節」比率が高い気がする。基本的に削り節は100g単位に分けて冷凍保存する。保存法としてはベストではないがあまり劣化しないと考えている。愛知県で買った「めじか節」と混合節をそろそろ使い切らないと、と思っていたら、今度は大阪市木津の市場で買ってきてもらった、和歌山県産(?)だという「いりこ」が底をついていた。「いりこ」がないと生きていけないので、八王子総合卸売センター、総市商事部で探したら、いちばん在り来たりな愛媛県伊予市の『ヤマキ』のものがあった。産地不明ながら、ボク好みの普通の煮干しで実際に使ってみたら、上々以上にいい感じだった。ちなみに「いりこ(煮干し)」は新鮮なものを、新鮮な内に鮮度管理も完璧な状態で作られたものの方がいい、という人が多いが例外も少なくない。かなり問題がある外見なのに素晴らしいものもあるし、見た目がいいのにダメなものもある。要するに買ってみないとわからない。例えば、千葉県産を悪く言う人に会ったことがあるが、なんて愚かなと思ったものだ。大きくて黒いけれど、だしの取り方によっては非常にうまいではないか。また、「いりこ(煮干し)」は大産地で大量生産するものももちろんいいが、むしろ狭い地域地域で地元で揚がったもの、自分の住まう地域の近くで作られているものを使うべきだと思っている。その地元産が切れたときに大産地で補えばいい。またこの地元の製造業者が消滅しているケースも多いだろう。今、国内の水産業において最大の問題は、地域地域で定置網などで揚がった魚を無駄なく使うシステムが崩壊しつつあることだ。干もの・乾物類だけではなく練り製品、缶詰など様々な水産加工業が漁港周辺になければならない。
慣用句、「猫に鰹節」を小学生のとき教えられて、「いんじゃこ(いりこ)」と思ったことがある。ときどき家に巣くう猫にやる御馳走は「いんじゃこ」だったからだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の商店街のボクの家に「いんじゃこ(徳島県西部では最低限いりこで、煮干しと言わないはず)」は常にあったが、カツオ節は見た記憶がない。寒い時季に教室に入ったらストーブがたかれていてとても温かかった。「杉玉鉄砲(細い竹とひごで作る水鉄砲のミニ版で杉の実を飛ばす。寒い時季のもの)」などの話をしていたら、同級生の息に「いんじゃこ」の匂いがした。ボクは典型的な学習障害児童だったので、好きなことしか興味がなく、勉強などはまったくしなかったが、やたらに食べ物のことが好きで興味があった。覚えていることも食べ物のことが多い。要するにボクの町の貞光小学校に通っていた家では、ほぼ「いんじゃこ」だったと思っている。今でもやたらに日常的に「いんじゃこ」を使っているので、ボクの体のかなりの部分が「いんじゃこ」で出来上がっていそうだ。去年暮れ、愛知県豊橋市で節類を大量買いしている。愛知県は「めじか節(マルソウダ)」の種類(節自体の大きさと削り節なので厚み)が多く、混合節にも「めじか節」比率が高い気がする。基本的に削り節は100g単位に分けて冷凍保存する。保存法としてはベストではないがあまり劣化しないと考えている。愛知県で買った「めじか節」と混合節をそろそろ使い切らないと、と思っていたら、今度は大阪市木津の市場で買ってきてもらった、和歌山県産(?)だという「いりこ」が底をついていた。「いりこ」がないと生きていけないので、八王子総合卸売センター、総市商事部で探したら、いちばん在り来たりな愛媛県伊予市の『ヤマキ』のものがあった。産地不明ながら、ボク好みの普通の煮干しで実際に使ってみたら、上々以上にいい感じだった。ちなみに「いりこ(煮干し)」は新鮮なものを、新鮮な内に鮮度管理も完璧な状態で作られたものの方がいい、という人が多いが例外も少なくない。かなり問題がある外見なのに素晴らしいものもあるし、見た目がいいのにダメなものもある。要するに買ってみないとわからない。例えば、千葉県産を悪く言う人に会ったことがあるが、なんて愚かなと思ったものだ。大きくて黒いけれど、だしの取り方によっては非常にうまいではないか。また、「いりこ(煮干し)」は大産地で大量生産するものももちろんいいが、むしろ狭い地域地域で地元で揚がったもの、自分の住まう地域の近くで作られているものを使うべきだと思っている。その地元産が切れたときに大産地で補えばいい。またこの地元の製造業者が消滅しているケースも多いだろう。今、国内の水産業において最大の問題は、地域地域で定置網などで揚がった魚を無駄なく使うシステムが崩壊しつつあることだ。干もの・乾物類だけではなく練り製品、缶詰など様々な水産加工業が漁港周辺になければならない。 島根県で作られている鍋ものに「へか焼き」がある。「いり焼き」、「煮食い」とも言う。魚を主役とした醤油味の鍋で、大阪の「魚すき」にあたる。兵庫県日本海側但馬地方の「じゃう」、三重県尾鷲市の「じふ」なども基本は同じで、このしょうゆ味の鍋は、日本各地で作られているのだろうと思われる。2008年、島根県大田市和江では、底曳き網でとれたばかりの魚を夕方に競りにかけていた。これを夕市(現在は廃止)という。底曳き網には様々な魚がはいるが、売っても高値がつかない魚や、カレイ類の若い個体(小型)で作るのが、「へか焼き」である。カナガシラ、キダイ、ソウハチガレイ、ヤナギムシガレイなど、使われる魚の種類は日々変わり、多彩であった。これを福島県相馬市原釜産のミギガレイで作ってみた。大田市和江の元組合長であった月森元市さんに教わったやり方は、鍋に水と醤油を煮立たせて、そこにとれたばかり、水洗いしたばかりの魚を入れて、煮えたそばから食べると言ったもの。必ず入れるのはこんにゃくで、野菜はあるものを使い、豆腐も好みで入れるという鍋である。
島根県で作られている鍋ものに「へか焼き」がある。「いり焼き」、「煮食い」とも言う。魚を主役とした醤油味の鍋で、大阪の「魚すき」にあたる。兵庫県日本海側但馬地方の「じゃう」、三重県尾鷲市の「じふ」なども基本は同じで、このしょうゆ味の鍋は、日本各地で作られているのだろうと思われる。2008年、島根県大田市和江では、底曳き網でとれたばかりの魚を夕方に競りにかけていた。これを夕市(現在は廃止)という。底曳き網には様々な魚がはいるが、売っても高値がつかない魚や、カレイ類の若い個体(小型)で作るのが、「へか焼き」である。カナガシラ、キダイ、ソウハチガレイ、ヤナギムシガレイなど、使われる魚の種類は日々変わり、多彩であった。これを福島県相馬市原釜産のミギガレイで作ってみた。大田市和江の元組合長であった月森元市さんに教わったやり方は、鍋に水と醤油を煮立たせて、そこにとれたばかり、水洗いしたばかりの魚を入れて、煮えたそばから食べると言ったもの。必ず入れるのはこんにゃくで、野菜はあるものを使い、豆腐も好みで入れるという鍋である。 鹿児島県鹿児島魚市場、恵水産さんからミハラハナダイがきた。最近、珍しくもない魚をみて極端なリアクションをする人とか、極端な言語を並べる人がいるが、ほとんどはややマイナー程度で、その魚たるや珍しくもなんともないといったものであることが多い。それからすると本種は正真正銘の珍魚と言ってもいいだろう。探してもなかなか手に入らないのだ。阿部宗明は築地市場に大量入荷したことがあると述べているので、広い海の中のどこかに群れを作っているのかもしれないが、現豊洲市場に移ってからもボク個人は1個体しか見ていない。記載者である片山正夫はタイプ標本を伊豆大島近海で手に入れているが、相模湾でも、伊豆諸島でもめったに揚がる魚ではない。余談だが、魚類学者は素晴らしい業績を残しながら、目立たない人が多い。まあ隣の県の蝶マニアの御仁もそうだし、この片山正夫などもそうだ。画期的なことをやり遂げた、益田一など生い立ちからして魚類学界の井原高忠といってもいいのに魚類学の世界以外では、知名度はイマイチだと思う。もちろん京都大学のあの方など偉大すぎて困る。伊豆大島なので三原山でミハラハナダイというのは標準和名としても、かなりイケテルと思っている。さて、ミハラハナダイ科のミハラハナダイはかなりハナダイ科に近い姿をしていて、身質もハナダイ科の魚に似ている。旬と外れの差が大きいのだ。我が家には静岡県沼津魚市場で最初に手に入れたもの(写真的に問題がある)から7個体が来ているが、早春の個体など脂が抜けてまったく味がなかったのだ。
鹿児島県鹿児島魚市場、恵水産さんからミハラハナダイがきた。最近、珍しくもない魚をみて極端なリアクションをする人とか、極端な言語を並べる人がいるが、ほとんどはややマイナー程度で、その魚たるや珍しくもなんともないといったものであることが多い。それからすると本種は正真正銘の珍魚と言ってもいいだろう。探してもなかなか手に入らないのだ。阿部宗明は築地市場に大量入荷したことがあると述べているので、広い海の中のどこかに群れを作っているのかもしれないが、現豊洲市場に移ってからもボク個人は1個体しか見ていない。記載者である片山正夫はタイプ標本を伊豆大島近海で手に入れているが、相模湾でも、伊豆諸島でもめったに揚がる魚ではない。余談だが、魚類学者は素晴らしい業績を残しながら、目立たない人が多い。まあ隣の県の蝶マニアの御仁もそうだし、この片山正夫などもそうだ。画期的なことをやり遂げた、益田一など生い立ちからして魚類学界の井原高忠といってもいいのに魚類学の世界以外では、知名度はイマイチだと思う。もちろん京都大学のあの方など偉大すぎて困る。伊豆大島なので三原山でミハラハナダイというのは標準和名としても、かなりイケテルと思っている。さて、ミハラハナダイ科のミハラハナダイはかなりハナダイ科に近い姿をしていて、身質もハナダイ科の魚に似ている。旬と外れの差が大きいのだ。我が家には静岡県沼津魚市場で最初に手に入れたもの(写真的に問題がある)から7個体が来ているが、早春の個体など脂が抜けてまったく味がなかったのだ。 15年前、午前3時の那覇市農連市場でおばあの朝ご飯を見せてもらった。沖縄らしい味つけした魚の天ぷらがタッパーに入っていて、何人かで分けて食べていた。うるま市の農連市場でも同じものを食べていたが、こちらは自家製ではなく市内の天ぷら店の天ぷらだった。魚の天ぷらならグルクン(タカサゴ)やグルクマー、キハダあたりかなと思ったら、意外すぎるものだったのでビックリした。サンマの天ぷらだったのだ。沖縄本島中のスーパーを片っ端に見て歩くと、確かに解凍サンマが普通に置いてある。総菜売り場にもサンマの天ぷらがあった。いかにも旅のもんですが、といった感じでサンマのことを聞いたら、島の魚よりも人気があり、天ぷらも作るという。サンマの不漁に「サンマが食べられなくなる」とこの国の人間は突然降って湧いたかのように宣い、テレビでも報道する。これには強い違和感を感じないではいられない。本来サンマを食べない地域にも売り込み、本来サンマ漁をやっていなかった臺灣にサンマ漁を導入させたのも、この国の仕業ではないのかな?漁業と自由主義経済は切り放して、厳格化しないとダメだと思うな。自由経済は明らかに破綻していて、ある意味、弁証法のように大きな視点で考えるときが来ていると思う。ちなみに我がサイトは多様な生物を多様な料理法で食べることが、自然には優しいということからはじまっている。そろそろ生きること、食べることは自然と直結することだと、思って欲しいものである。いろんな自然保護のイベントや活動をやって目立っている人達は無数にいるけど、この日常的なことをから自然を考えようと思っている人が少なすぎる。イベント的な自然保護活動は否定しないけど、日常的に自然保護を考える方が地球を救う効果は数十倍ある。
15年前、午前3時の那覇市農連市場でおばあの朝ご飯を見せてもらった。沖縄らしい味つけした魚の天ぷらがタッパーに入っていて、何人かで分けて食べていた。うるま市の農連市場でも同じものを食べていたが、こちらは自家製ではなく市内の天ぷら店の天ぷらだった。魚の天ぷらならグルクン(タカサゴ)やグルクマー、キハダあたりかなと思ったら、意外すぎるものだったのでビックリした。サンマの天ぷらだったのだ。沖縄本島中のスーパーを片っ端に見て歩くと、確かに解凍サンマが普通に置いてある。総菜売り場にもサンマの天ぷらがあった。いかにも旅のもんですが、といった感じでサンマのことを聞いたら、島の魚よりも人気があり、天ぷらも作るという。サンマの不漁に「サンマが食べられなくなる」とこの国の人間は突然降って湧いたかのように宣い、テレビでも報道する。これには強い違和感を感じないではいられない。本来サンマを食べない地域にも売り込み、本来サンマ漁をやっていなかった臺灣にサンマ漁を導入させたのも、この国の仕業ではないのかな?漁業と自由主義経済は切り放して、厳格化しないとダメだと思うな。自由経済は明らかに破綻していて、ある意味、弁証法のように大きな視点で考えるときが来ていると思う。ちなみに我がサイトは多様な生物を多様な料理法で食べることが、自然には優しいということからはじまっている。そろそろ生きること、食べることは自然と直結することだと、思って欲しいものである。いろんな自然保護のイベントや活動をやって目立っている人達は無数にいるけど、この日常的なことをから自然を考えようと思っている人が少なすぎる。イベント的な自然保護活動は否定しないけど、日常的に自然保護を考える方が地球を救う効果は数十倍ある。 ボクの周りには奥多摩出身の方が多い。現在も暮らしている人、都会(八王子)に出て来た人などさまざまだ。今でこそ奥多摩は観光地だけど、古くは山奥のまた奥であった。奥多摩は東京都の方はともかく、全国的にみると非常にマイナーな地域だと思っているので説明しておきたい。東京都の西、山梨県に接する地域である。厳密に言うと青梅市とあきる野市から西の山間部だと考えている。東京檜原村はときどき生き物を見に出掛けていたところ。ここで様々な人に話を聞いた。マタタビの酒(薬)のこと、イタドリを食べていたらしいことや、山菜などの保存方法・塩抜き、木の皮は薬だとか、クマの話、祭のとき八王子まで2日かけて歩いたこと、学徒動員で始めて電車に乗ったことなどなどだ。市場にも檜原生まれの方がいて、秋祭に「いかと里芋」を作ったと教わっている。実に素朴なイカと里芋だけの煮物である。これが八王子にくるとにんじんやゴボウが加わり、こんにゃくを入れたりする。念のために、里芋とイカを煮合わせる料理は日本全国にあると思う。ボクは上京して始めて江戸川区小岩という下町で食べたが、たぶん東京都ではありふれたものだろう。檜原村では古くは塩イカ(長野県とは違って開いて塩漬けにしたもので、今も手に入る)を使ったようだが、戦後(1945年)になって生のイカを使うようになったという。八王子綜合協同卸売組合、マル幸に日本海産のバライカ(スルメイカの若い個体)があった。昔はありふれた存在であったが、スルメイカの急激な減少を受けて最近では貴重なものとなっている。思ったよりも安かったが、それでも昔と比べると、と思わずにはいられない値段である。
ボクの周りには奥多摩出身の方が多い。現在も暮らしている人、都会(八王子)に出て来た人などさまざまだ。今でこそ奥多摩は観光地だけど、古くは山奥のまた奥であった。奥多摩は東京都の方はともかく、全国的にみると非常にマイナーな地域だと思っているので説明しておきたい。東京都の西、山梨県に接する地域である。厳密に言うと青梅市とあきる野市から西の山間部だと考えている。東京檜原村はときどき生き物を見に出掛けていたところ。ここで様々な人に話を聞いた。マタタビの酒(薬)のこと、イタドリを食べていたらしいことや、山菜などの保存方法・塩抜き、木の皮は薬だとか、クマの話、祭のとき八王子まで2日かけて歩いたこと、学徒動員で始めて電車に乗ったことなどなどだ。市場にも檜原生まれの方がいて、秋祭に「いかと里芋」を作ったと教わっている。実に素朴なイカと里芋だけの煮物である。これが八王子にくるとにんじんやゴボウが加わり、こんにゃくを入れたりする。念のために、里芋とイカを煮合わせる料理は日本全国にあると思う。ボクは上京して始めて江戸川区小岩という下町で食べたが、たぶん東京都ではありふれたものだろう。檜原村では古くは塩イカ(長野県とは違って開いて塩漬けにしたもので、今も手に入る)を使ったようだが、戦後(1945年)になって生のイカを使うようになったという。八王子綜合協同卸売組合、マル幸に日本海産のバライカ(スルメイカの若い個体)があった。昔はありふれた存在であったが、スルメイカの急激な減少を受けて最近では貴重なものとなっている。思ったよりも安かったが、それでも昔と比べると、と思わずにはいられない値段である。 八王子綜合卸売協同組合『マル幸』に島根県産スマがきていた。2kg上もあって脂がありそうだったので買い求めた。意外にスマの旬はわかりにくい。例えばこの時季は生殖巣が膨らんだ個体が多く、初夏ほどには脂が乗っていないことが多い。2000年以前はとてもローカルな食用魚だった。西日本の太平洋側に多く、あまり関東にはやって来なかった。それが今では北海道でも揚がり始めている。東京都豊洲市場では大きくて鮮度のいいものが普通に並んでいる。こうなるとますます水揚げ地が北に広がり、旬がわからなくなりそうである。標準和名、スマは東京での呼び名だとしているが、明治・大正と活躍した動物学者岸上鎌吉が提唱した「やいと」の方が地方名などを見る限り、混乱は少なかったように思える。
八王子綜合卸売協同組合『マル幸』に島根県産スマがきていた。2kg上もあって脂がありそうだったので買い求めた。意外にスマの旬はわかりにくい。例えばこの時季は生殖巣が膨らんだ個体が多く、初夏ほどには脂が乗っていないことが多い。2000年以前はとてもローカルな食用魚だった。西日本の太平洋側に多く、あまり関東にはやって来なかった。それが今では北海道でも揚がり始めている。東京都豊洲市場では大きくて鮮度のいいものが普通に並んでいる。こうなるとますます水揚げ地が北に広がり、旬がわからなくなりそうである。標準和名、スマは東京での呼び名だとしているが、明治・大正と活躍した動物学者岸上鎌吉が提唱した「やいと」の方が地方名などを見る限り、混乱は少なかったように思える。 「三平汁」は近世江戸時代に「にしん漁場」で作り始められたもの。ニシンの「塩漬け(魚自体も使うとは思うが現在の魚醬のようなものか)」と野菜を煮た汁のこと。「さんべ汁」、「さんぺ」、「まくり汁」、「かぼし汁」ともいうが、語源は不明であるようだ。三平という人物が存在して、おいしい汁を考え出したので、「三平汁」という説を聞いたことがあるが、なんら根拠はない。これが「塩漬けニシン」から「すしにしん(ニシンのぬか漬け)」に代わる。野菜はあり合わせのものでよく、ニシンの塩気があるので材料も少なくてすむ。非常に合理的なものである。古くは保存食である「塩漬けにしん」や「すしにしん」を使ったものが、鮮魚を使うようになる。今現在、「塩漬けにしん」は手に入らないので「すしにしん」で三平汁を作る。また魚は鮮魚も使うようになり、サケ、タラ類、メバル類など手に入るものはことごとく使っていたようである。参考/『聞書き 北海道の食事』(農文協)
「三平汁」は近世江戸時代に「にしん漁場」で作り始められたもの。ニシンの「塩漬け(魚自体も使うとは思うが現在の魚醬のようなものか)」と野菜を煮た汁のこと。「さんべ汁」、「さんぺ」、「まくり汁」、「かぼし汁」ともいうが、語源は不明であるようだ。三平という人物が存在して、おいしい汁を考え出したので、「三平汁」という説を聞いたことがあるが、なんら根拠はない。これが「塩漬けニシン」から「すしにしん(ニシンのぬか漬け)」に代わる。野菜はあり合わせのものでよく、ニシンの塩気があるので材料も少なくてすむ。非常に合理的なものである。古くは保存食である「塩漬けにしん」や「すしにしん」を使ったものが、鮮魚を使うようになる。今現在、「塩漬けにしん」は手に入らないので「すしにしん」で三平汁を作る。また魚は鮮魚も使うようになり、サケ、タラ類、メバル類など手に入るものはことごとく使っていたようである。参考/『聞書き 北海道の食事』(農文協) 8月7日に買った福島県産スズキ1.89kgは、料理法を考えながら下ろした。スズキと決める以前に、そろそろ残り少なくなった我が故郷の名品、半田素麺を一気に消費してしまおうと考えていたこともあり、煮つけにしてうまい魚を探していたのもある。魚の煮つけで素麺を食べるというのは、日本各地で行われている。例えば愛媛県松山市に「鯛素麺」があるが、あれは家庭料理を豪華にしてやたらに宣伝しただけで、本来の形ではない。だいたい松山市でも魚市場のある三津では、むしろ「ちぬ(クロダイ)」で作ることの方が多いという。同様の料理は徳島にもあるし、大阪市にもある。ちなみにボクの魚の調べ始めは淡水魚で、海の魚は上京してからだ。スズキの煮つけは、塩焼きほど知名度はない。生まれて初めてスズキを食べたのは東京都江戸川区小岩の食堂だが、塩焼きだった。当時、やっと魚が身近な存在になってきていたので、このような初物食いはうれしい限り、とてもおいしかった。今思えば、当時(1970年代末)、スズキを食べる人は都内にはあまりいなかった。たぶんスズキにとってはどん底時代といってもいいだろう。いかに葛飾小岩とはいえ、スズキを食べることができたのはラッキーだったと考えている。これに関しては江戸時代の高速道路をたどっているので、そのときに述べたい。スズキの煮つけをやたらに食べたのは俗に「ちばらき」とされる霞ヶ浦、利根川方面に通っていたときだ。漁師の魚料理の基本は煮つけなのである。漁師さんがスズキをくれるときも「煮つけにしなよ」だった。余談だが、千葉県、茨城県の水郷地帯は国内屈指の醤油どころだ。本当か嘘かわからないが、醤油に亀甲は、土浦藩(茨城県土浦市)、土屋家の城が通称、亀城と呼ばれるのに由来するという。このあたりの漁師の煮つけがそんなに甘くないのは、醤油がいいからだという人もいる。スズキを見て、煮つけが浮かんでしまうのは、大小様々なスズキをあっさり味で散々食べているからだ。スズキには淡水魚を思わせる風味がある。これが好き嫌いが出るところだが、ていねいに湯引きして臭味をとって煮つけると実に味わい深いのである。
8月7日に買った福島県産スズキ1.89kgは、料理法を考えながら下ろした。スズキと決める以前に、そろそろ残り少なくなった我が故郷の名品、半田素麺を一気に消費してしまおうと考えていたこともあり、煮つけにしてうまい魚を探していたのもある。魚の煮つけで素麺を食べるというのは、日本各地で行われている。例えば愛媛県松山市に「鯛素麺」があるが、あれは家庭料理を豪華にしてやたらに宣伝しただけで、本来の形ではない。だいたい松山市でも魚市場のある三津では、むしろ「ちぬ(クロダイ)」で作ることの方が多いという。同様の料理は徳島にもあるし、大阪市にもある。ちなみにボクの魚の調べ始めは淡水魚で、海の魚は上京してからだ。スズキの煮つけは、塩焼きほど知名度はない。生まれて初めてスズキを食べたのは東京都江戸川区小岩の食堂だが、塩焼きだった。当時、やっと魚が身近な存在になってきていたので、このような初物食いはうれしい限り、とてもおいしかった。今思えば、当時(1970年代末)、スズキを食べる人は都内にはあまりいなかった。たぶんスズキにとってはどん底時代といってもいいだろう。いかに葛飾小岩とはいえ、スズキを食べることができたのはラッキーだったと考えている。これに関しては江戸時代の高速道路をたどっているので、そのときに述べたい。スズキの煮つけをやたらに食べたのは俗に「ちばらき」とされる霞ヶ浦、利根川方面に通っていたときだ。漁師の魚料理の基本は煮つけなのである。漁師さんがスズキをくれるときも「煮つけにしなよ」だった。余談だが、千葉県、茨城県の水郷地帯は国内屈指の醤油どころだ。本当か嘘かわからないが、醤油に亀甲は、土浦藩(茨城県土浦市)、土屋家の城が通称、亀城と呼ばれるのに由来するという。このあたりの漁師の煮つけがそんなに甘くないのは、醤油がいいからだという人もいる。スズキを見て、煮つけが浮かんでしまうのは、大小様々なスズキをあっさり味で散々食べているからだ。スズキには淡水魚を思わせる風味がある。これが好き嫌いが出るところだが、ていねいに湯引きして臭味をとって煮つけると実に味わい深いのである。 北海道羅臼町、野家のオバアチャンから、ガヤ(エゾメバル)でも三平汁を作っていたという話を聞いた。三平汁は古くは保存食である塩漬けの魚や「すしにしん(ぬか漬けのニシン)」と季節ごとの野菜を組み合わせて作られていたもの。今、これが塩漬けなど保存しておいた魚から鮮魚へ、わざわざ塩味をつけて作る汁となって作り続けられている。北海道の水産物というとサケ類やタラ類、キンキなど主役級がずらりと並び、なかなか脇役にまで話が及ばない。ただし、考えてみると北海道の厳しい開拓の歴史からしても、魚など種を選んでいられない時代が長かったはずなのだ。昔、室蘭で「ウグイだって食べたもんよ」という老人に出会っている。動物性のタンパク質はヒトにはなくてはならぬものだ。ましてや味のいいガヤなど御馳走だったのかも知れない。北海道羅臼町では時間をみつけては釣り糸を垂れた。垂れたというよりも底までなかなか落ちていかなかった。途中で邪魔する悪魔のようなヤツがいたのだ。そのボクの様子を見て地元の人が笑い、遠くに投げろと言われて投げたら、それでも悪魔が釣れたのだ。しかも3本針に3尾とは、いなかるものか? だからガヤは北海道では嫌われているのだ。ボクもそんなガヤ嫌い症候群にかかる。そんな釣果の中から2尾だけ持ち帰ってきた。ガヤの三平汁を作るためだ。
北海道羅臼町、野家のオバアチャンから、ガヤ(エゾメバル)でも三平汁を作っていたという話を聞いた。三平汁は古くは保存食である塩漬けの魚や「すしにしん(ぬか漬けのニシン)」と季節ごとの野菜を組み合わせて作られていたもの。今、これが塩漬けなど保存しておいた魚から鮮魚へ、わざわざ塩味をつけて作る汁となって作り続けられている。北海道の水産物というとサケ類やタラ類、キンキなど主役級がずらりと並び、なかなか脇役にまで話が及ばない。ただし、考えてみると北海道の厳しい開拓の歴史からしても、魚など種を選んでいられない時代が長かったはずなのだ。昔、室蘭で「ウグイだって食べたもんよ」という老人に出会っている。動物性のタンパク質はヒトにはなくてはならぬものだ。ましてや味のいいガヤなど御馳走だったのかも知れない。北海道羅臼町では時間をみつけては釣り糸を垂れた。垂れたというよりも底までなかなか落ちていかなかった。途中で邪魔する悪魔のようなヤツがいたのだ。そのボクの様子を見て地元の人が笑い、遠くに投げろと言われて投げたら、それでも悪魔が釣れたのだ。しかも3本針に3尾とは、いなかるものか? だからガヤは北海道では嫌われているのだ。ボクもそんなガヤ嫌い症候群にかかる。そんな釣果の中から2尾だけ持ち帰ってきた。ガヤの三平汁を作るためだ。 フレンチではポシェ、ブランシール(霜降りにする)、エチュベ(蒸し煮)と、液体による食材の、火の通し方にははっきりとした区別がある。また同じポシェ、ブランシールでも細々とした指示が加わる。「湯煮」はフレンチではポシェ(液体で火を通す)にあたるのではないか? ポシェの場合、食材を冷たい液体から入れて煮る、温度を高めてから煮るなど素材や料理によって決まり事があるが、火を完全に通す料理法であることには違いはない。通すまでの温度管理で味が変わる。まるで物理の法則のように素材ごとにやり方、温度管理が異なる。その点、日本料理にははっきりした温度管理の決まりはないと思っている。その微妙な違いは、いわゆる職人技とか、秘伝などというもので語られてしまっている。これがフレンチと和の大きな違いだろう。「湯煮」は明らかにポシェなのに、過去に料理店で食べたものの、どことなく生な火の通し方に違和感を覚えたものだ。今回、野家で食べた湯煮は「めんめ(キチジ)」に完全に火が通っているものの、ふんわりとまるでババロアのような舌触りで、しかも「めんめ」自体のエキス(うま味と脂)が満ちている。余談になるが、「湯煮」と同じ調理法の郷土料理は日本各地にあるはずである。三陸の「湯だき」、山形県庄内の「湯あげ」などだ。面白いことに、湯煮とは逆の考え方に北陸・越前の「塩いり」、「浜いり」、沖縄の「まーす煮」がある作り方は羅臼町特産の羅臼昆布と塩だけだろう。酒の気配はないようである。ある程度温めた湯の中に頭部を除いた丸々1尾を入れて煮立たせないように時間をかけて火を通す。食材は、例えば豚骨スープ鶏の水炊きのように高温で煮ると、素材からうま味成分も脂も液体に出尽くしてしまう。極力煮立たせないで火を通すと魚のうま味は身自体に閉じ込められて、しかも熱で筋肉がほどよく膨らむのである。野家のものは脂の豊かなキチジの脂も、そのうま味も、すべて閉じ込めたものだ。生醤油やポン酢で食べるものだけど、意外に調味料なしがいちばんボク好みだった。今回は天然の羅臼昆布を持ち帰ってきているので、我が家でも、と思っているが、同じレベルを作るといくらかかるものやら。野圭太さんおよびご家族の方たちに大大感謝!
フレンチではポシェ、ブランシール(霜降りにする)、エチュベ(蒸し煮)と、液体による食材の、火の通し方にははっきりとした区別がある。また同じポシェ、ブランシールでも細々とした指示が加わる。「湯煮」はフレンチではポシェ(液体で火を通す)にあたるのではないか? ポシェの場合、食材を冷たい液体から入れて煮る、温度を高めてから煮るなど素材や料理によって決まり事があるが、火を完全に通す料理法であることには違いはない。通すまでの温度管理で味が変わる。まるで物理の法則のように素材ごとにやり方、温度管理が異なる。その点、日本料理にははっきりした温度管理の決まりはないと思っている。その微妙な違いは、いわゆる職人技とか、秘伝などというもので語られてしまっている。これがフレンチと和の大きな違いだろう。「湯煮」は明らかにポシェなのに、過去に料理店で食べたものの、どことなく生な火の通し方に違和感を覚えたものだ。今回、野家で食べた湯煮は「めんめ(キチジ)」に完全に火が通っているものの、ふんわりとまるでババロアのような舌触りで、しかも「めんめ」自体のエキス(うま味と脂)が満ちている。余談になるが、「湯煮」と同じ調理法の郷土料理は日本各地にあるはずである。三陸の「湯だき」、山形県庄内の「湯あげ」などだ。面白いことに、湯煮とは逆の考え方に北陸・越前の「塩いり」、「浜いり」、沖縄の「まーす煮」がある作り方は羅臼町特産の羅臼昆布と塩だけだろう。酒の気配はないようである。ある程度温めた湯の中に頭部を除いた丸々1尾を入れて煮立たせないように時間をかけて火を通す。食材は、例えば豚骨スープ鶏の水炊きのように高温で煮ると、素材からうま味成分も脂も液体に出尽くしてしまう。極力煮立たせないで火を通すと魚のうま味は身自体に閉じ込められて、しかも熱で筋肉がほどよく膨らむのである。野家のものは脂の豊かなキチジの脂も、そのうま味も、すべて閉じ込めたものだ。生醤油やポン酢で食べるものだけど、意外に調味料なしがいちばんボク好みだった。今回は天然の羅臼昆布を持ち帰ってきているので、我が家でも、と思っているが、同じレベルを作るといくらかかるものやら。野圭太さんおよびご家族の方たちに大大感謝! 魚を買って、期待していた味ではない、ということがボクには少なからずある。知り合いの魚屋に面と向かって「(魚選びが)雑だな」と言われたことがあるので、問題は総てボクにある。今回はかなり真剣に選び、期待が大きかったこともあって、ダメージも大きかった。おいしくない、わけではないが平凡な味だったのだ。特に落ち込んだのは徳島県人がやたらに好きな、イボダイでのつまずきだったためだ。失敗の原因はもっとちゃんと指の感触を確かめなかったところにある。さて、刺身で食べて、味は及第点だったが、期待の割りに、といったものだったので、夏らしい焼き物にする。水洗い、卵巣の大きさから、産卵はまだ先であると確認する。
魚を買って、期待していた味ではない、ということがボクには少なからずある。知り合いの魚屋に面と向かって「(魚選びが)雑だな」と言われたことがあるので、問題は総てボクにある。今回はかなり真剣に選び、期待が大きかったこともあって、ダメージも大きかった。おいしくない、わけではないが平凡な味だったのだ。特に落ち込んだのは徳島県人がやたらに好きな、イボダイでのつまずきだったためだ。失敗の原因はもっとちゃんと指の感触を確かめなかったところにある。さて、刺身で食べて、味は及第点だったが、期待の割りに、といったものだったので、夏らしい焼き物にする。水洗い、卵巣の大きさから、産卵はまだ先であると確認する。 神奈川県小田原市、江の安、ワタルさんにホシザメをいただく。なんと活魚である。むんむんするような、蒸し暑い朝だったので、ホシザメといえば、というあの料理を思い浮かべて、うほほと笑い、お礼もそこそこにとっとと帰ってきた。ホシザメと言えば、西日本で作られる料理の「湯引き」である。「湯がき」ともいうし、「湯ざらし」などともいう。酢みそで食べるというのも同じである。主に小型の軟骨魚類であるサメやエイが使われている。初めて食べたのは長崎県だったが、サメの種類は不明だった。次いで広島県でホシザメを仕入れている人に会い、「湯引き」の作り方を教わった。サカタザメでもいいというところから、要するに沿岸域のサメのようなもの、ならなんでもよかったのだ。ホシザメで作る、湯引きがいちばんうまいという。確かに同属で瓜二つのシロザメで作るものよりも味がある。でもごくわずかな差でしかない。むしろサカタザメの方がホシザメよりもうまいと思ったこともあるが、こちらもごくごくわずかな差でしかない。山口県ではニュージーランド産のギンザメで作ったものを買い求めていることから、くせのない魚ならなんでもいいのかも知れない。
神奈川県小田原市、江の安、ワタルさんにホシザメをいただく。なんと活魚である。むんむんするような、蒸し暑い朝だったので、ホシザメといえば、というあの料理を思い浮かべて、うほほと笑い、お礼もそこそこにとっとと帰ってきた。ホシザメと言えば、西日本で作られる料理の「湯引き」である。「湯がき」ともいうし、「湯ざらし」などともいう。酢みそで食べるというのも同じである。主に小型の軟骨魚類であるサメやエイが使われている。初めて食べたのは長崎県だったが、サメの種類は不明だった。次いで広島県でホシザメを仕入れている人に会い、「湯引き」の作り方を教わった。サカタザメでもいいというところから、要するに沿岸域のサメのようなもの、ならなんでもよかったのだ。ホシザメで作る、湯引きがいちばんうまいという。確かに同属で瓜二つのシロザメで作るものよりも味がある。でもごくわずかな差でしかない。むしろサカタザメの方がホシザメよりもうまいと思ったこともあるが、こちらもごくごくわずかな差でしかない。山口県ではニュージーランド産のギンザメで作ったものを買い求めていることから、くせのない魚ならなんでもいいのかも知れない。 神奈川県小田原市、二宮定置で出荷できない小イサキを、もちろんことわって、ダンベ(大型容器)から拾い上げる。尾鷲風の「たたき」を作るためだ。「たたき」というと土佐風のあぶって切りつけるものが有名だが、実は小魚などを細かくたたき切って生で食べるから、「たたき」とされるものの方が全国的には一般的である。この「たたき」→「カツオ」→「土佐風」という言語の不用意な使い方は絶対にやってはいけない。また本来の形の「たたき」を単に「たたき」と呼んでいた地域に、マスコミ登場回数の多い、「なめろう」ががん細胞のように浸潤してきている。ついでにいうと「たたき」以外にも呼び名がありそうなので要注意である。繰り返すが、やたら郷土料理の一地方の名前を連呼するのはオロカモノのやることだ。ちなみにこの「たたき」の元の言語は「たたきなます」であるようだ。これは地域地域で比較的新しく生まれた言語ではなく、非常に古い、例えば日本料理の誕生した室町時代に生まれたものだと考えている。この言語が文化の中心地である畿内から全国に広がったのだ。さて、「たたき」にはいろんな魚が使われるが、もっとも頻度の高いのがマアジ、次いでイサキだろう。両方とも「たたき」にして非常にうまいとは思うが、どちらかというとボクはマアジ派である。これに対して三重県尾鷲市の魚の大人、岩田さんはイサキ派なのだ。しかも最初に教わった尾鷲の「たたき」よりも、もっとワイルドな造りであるようだ。
神奈川県小田原市、二宮定置で出荷できない小イサキを、もちろんことわって、ダンベ(大型容器)から拾い上げる。尾鷲風の「たたき」を作るためだ。「たたき」というと土佐風のあぶって切りつけるものが有名だが、実は小魚などを細かくたたき切って生で食べるから、「たたき」とされるものの方が全国的には一般的である。この「たたき」→「カツオ」→「土佐風」という言語の不用意な使い方は絶対にやってはいけない。また本来の形の「たたき」を単に「たたき」と呼んでいた地域に、マスコミ登場回数の多い、「なめろう」ががん細胞のように浸潤してきている。ついでにいうと「たたき」以外にも呼び名がありそうなので要注意である。繰り返すが、やたら郷土料理の一地方の名前を連呼するのはオロカモノのやることだ。ちなみにこの「たたき」の元の言語は「たたきなます」であるようだ。これは地域地域で比較的新しく生まれた言語ではなく、非常に古い、例えば日本料理の誕生した室町時代に生まれたものだと考えている。この言語が文化の中心地である畿内から全国に広がったのだ。さて、「たたき」にはいろんな魚が使われるが、もっとも頻度の高いのがマアジ、次いでイサキだろう。両方とも「たたき」にして非常にうまいとは思うが、どちらかというとボクはマアジ派である。これに対して三重県尾鷲市の魚の大人、岩田さんはイサキ派なのだ。しかも最初に教わった尾鷲の「たたき」よりも、もっとワイルドな造りであるようだ。 最近、魚を見てきゃーとか大騒ぎするヤカラとか、究極の美味なんて意味不明のことをいうヤカラがいるが、このあたりの人間が気持ち悪くて困る。食用魚はあくまでも食用魚で日常食べるものでしかない。こんなに大騒ぎするから魚の消費が伸びない気がする。この点、韓国東海岸は、例えば名物を出す食堂で、アベック(今どきはなんていうんだろう)が名物を食べていても、至って普通で、ただ単にうまいものを食いに来ているだけという感じがとてもよかった。しかも韓国の方達は魚を食べるのが、もちろん見た限りであるけどとても上手だ。今回はタケノコメバルで、その韓国東海岸風(ボクの勝手な思い込み)の鍋を作る。あくまでも「ボクは」ということだけど、姿造りが嫌いだ。刺身がこのイカニモ的な状態で出てくるとガッカリする。口には出さないけど、低級だとさえ思う。韓国東岸、三陟市でたまたま見つけた海鮮食堂 바다횟집(パダフェッチッ)で、刺身をお願いすると、勝手に鍋がついてきた。これは三陟市だけの事ではないだろう。その鍋が非常においしかったのである。海辺の普通の住宅地だったので魚の種類は少なかった。韓国の特徴は刺身用の魚はすべて活魚だということだが、ブリのイナダサイズとクロソイしか泳いでいなかったので、この2種を刺身にしてもらう。刺身の他に何にしようと考えていたら、あらが見事な鍋になって出て来たのだ。刺身との時差がほとんどないということは刺身を造りながらあらの処理を同時にやっていたことになる。ボクはかねてより料理は見た目も大切だけど、合理的でなければならないと思っているので、さもありなんと喜びすら感じた。あまりにもうまいので、ソジュを飲みすぎてしまったくらいだ。韓国東岸では臨院(임원)でタラの鍋も食べているが、明らかにだしと塩だけの非常に単純なつゆであった。だしは節ではなく煮干し系ではないか、韓国は魚と獣肉のだしを合わせる文化があるようだが、東海岸では獣肉系の味はしなかった。でも何か、気がつかないものが加わっているようにも感じる。こんなことだって、調べる価値が大、大にある。また行きたい韓国、なのだ。
最近、魚を見てきゃーとか大騒ぎするヤカラとか、究極の美味なんて意味不明のことをいうヤカラがいるが、このあたりの人間が気持ち悪くて困る。食用魚はあくまでも食用魚で日常食べるものでしかない。こんなに大騒ぎするから魚の消費が伸びない気がする。この点、韓国東海岸は、例えば名物を出す食堂で、アベック(今どきはなんていうんだろう)が名物を食べていても、至って普通で、ただ単にうまいものを食いに来ているだけという感じがとてもよかった。しかも韓国の方達は魚を食べるのが、もちろん見た限りであるけどとても上手だ。今回はタケノコメバルで、その韓国東海岸風(ボクの勝手な思い込み)の鍋を作る。あくまでも「ボクは」ということだけど、姿造りが嫌いだ。刺身がこのイカニモ的な状態で出てくるとガッカリする。口には出さないけど、低級だとさえ思う。韓国東岸、三陟市でたまたま見つけた海鮮食堂 바다횟집(パダフェッチッ)で、刺身をお願いすると、勝手に鍋がついてきた。これは三陟市だけの事ではないだろう。その鍋が非常においしかったのである。海辺の普通の住宅地だったので魚の種類は少なかった。韓国の特徴は刺身用の魚はすべて活魚だということだが、ブリのイナダサイズとクロソイしか泳いでいなかったので、この2種を刺身にしてもらう。刺身の他に何にしようと考えていたら、あらが見事な鍋になって出て来たのだ。刺身との時差がほとんどないということは刺身を造りながらあらの処理を同時にやっていたことになる。ボクはかねてより料理は見た目も大切だけど、合理的でなければならないと思っているので、さもありなんと喜びすら感じた。あまりにもうまいので、ソジュを飲みすぎてしまったくらいだ。韓国東岸では臨院(임원)でタラの鍋も食べているが、明らかにだしと塩だけの非常に単純なつゆであった。だしは節ではなく煮干し系ではないか、韓国は魚と獣肉のだしを合わせる文化があるようだが、東海岸では獣肉系の味はしなかった。でも何か、気がつかないものが加わっているようにも感じる。こんなことだって、調べる価値が大、大にある。また行きたい韓国、なのだ。 八王子総合卸売協同組合、マル幸に小振りのハモが来ていた。それだけなら通り過ぎるのだが、なんと相模湾三浦半島にある神奈川県佐島産なのである。漁法がわからない。定置網、刺網であるはずもなく、延縄だろうと考え、今度聞いてみようと思って買い求める。というとで、今季初ハモは佐島産とあいなる。まだ卵巣は未熟で、脂ののりは今ひとつながら初物としては上々だった。
八王子総合卸売協同組合、マル幸に小振りのハモが来ていた。それだけなら通り過ぎるのだが、なんと相模湾三浦半島にある神奈川県佐島産なのである。漁法がわからない。定置網、刺網であるはずもなく、延縄だろうと考え、今度聞いてみようと思って買い求める。というとで、今季初ハモは佐島産とあいなる。まだ卵巣は未熟で、脂ののりは今ひとつながら初物としては上々だった。 八王子総合卸売協同組合、マル幸でわけてもらった魚にナンヨウカイワリがある。全長60cm前後になるアジ科の魚で、国内では伊豆諸島以南に多い。熱帯系の魚の特徴は1種あたりの個体数が少ないことなので、水揚げ量はさほど多くない。ただ東京都の島嶼部から紀伊半島、高知県、九州南部、沖縄などでは珍しくもなし、といった魚である。「魚に興味のない人」に、このような魚の説明は難しい。ちなみにこの魚、最近まで分類的に不明な点が多く、魚類学者が悪戦苦闘していたことだけは伝えておくつもり。門外漢ではあるが、まことにたいへんだったろう、お疲れ様なのだ。非常にうまい魚であるとともに、沖縄県の「がーら」のひとつでもある。「がーら」は沖縄県でのアジ類に対する呼び名・総称であるが、もっとも一般的な料理が「(魚)汁」なのである。魚と青み(ねぎやフーチバー)だけのみそ汁が本来だけど、近年、豆腐などを入れることもある。「魚汁」として、那覇などの食堂では「いまいゆ」の「さかなしる」、奄美大島では「魚汁」として「いゅん汁」という。ちなみに那覇などのオバアは「さかなしる」とも「さかなじる」でもなく、「しる」ということが多く、あえて聞くと「いおしる」もしくは「いよしる」と発音していた。ちなみに現在のところ、我がサイトの情報としてはあいまいな状況にある。鹿児島県島嶼部、沖縄での本料理に関しては教えて欲しいくらいである。この地域だけではなく、魚料理の中でももっとも重要なものがみそ汁である。魚料理の最高峰だと思っているが、主役級ではない。喜劇人の三木のり平が主役はいなくなっても替えが利くが、うまい役者は替えが利かないと述べていたが、そのうまい役者がみそ汁なのだ。日本全国で作られている普通の料理だが、沖縄県や奄美大島などの鹿児島県島嶼部以外では衰退している気がする。北海道など古くはカジカなどのみそ汁をよく作っていたと言うが、みその消費量の減少とともに作らなくなった、と室蘭の市場で聞いている。作り方は簡単すぎるほど簡単である。魚は小さいものは水洗いしてぶつ切りに、大きなものはあらでいい。我が方は魚の生臭みに敏感なので、これを湯通しする。氷水などに落として残った鱗やぬめりをとる。(これは必須ではない)水分をよくきり、必ず水から煮出してみそを溶く。今回はウミンチュにフーチバーをいただいたので、あしらったが、ねぎでも青菜でもなんでもいい。ここに酒を加えたりするが邪道だと思う。こんなことをするくらいなら沖縄のオバアの真似をして味の素を振る方が増し。この魚汁の重大な問題点は汁ではなく、おかずだということだ。沖縄で「いまいゆの汁」をお願いすると勝手にご飯と小鉢などがついてくる。要するに汁は主菜なのだ。我ながら魚のみそ汁で飯を食うことだけは止められない。腹が立つくらいにうまい、ので腹が出る。三条中納言を笑えない。
八王子総合卸売協同組合、マル幸でわけてもらった魚にナンヨウカイワリがある。全長60cm前後になるアジ科の魚で、国内では伊豆諸島以南に多い。熱帯系の魚の特徴は1種あたりの個体数が少ないことなので、水揚げ量はさほど多くない。ただ東京都の島嶼部から紀伊半島、高知県、九州南部、沖縄などでは珍しくもなし、といった魚である。「魚に興味のない人」に、このような魚の説明は難しい。ちなみにこの魚、最近まで分類的に不明な点が多く、魚類学者が悪戦苦闘していたことだけは伝えておくつもり。門外漢ではあるが、まことにたいへんだったろう、お疲れ様なのだ。非常にうまい魚であるとともに、沖縄県の「がーら」のひとつでもある。「がーら」は沖縄県でのアジ類に対する呼び名・総称であるが、もっとも一般的な料理が「(魚)汁」なのである。魚と青み(ねぎやフーチバー)だけのみそ汁が本来だけど、近年、豆腐などを入れることもある。「魚汁」として、那覇などの食堂では「いまいゆ」の「さかなしる」、奄美大島では「魚汁」として「いゅん汁」という。ちなみに那覇などのオバアは「さかなしる」とも「さかなじる」でもなく、「しる」ということが多く、あえて聞くと「いおしる」もしくは「いよしる」と発音していた。ちなみに現在のところ、我がサイトの情報としてはあいまいな状況にある。鹿児島県島嶼部、沖縄での本料理に関しては教えて欲しいくらいである。この地域だけではなく、魚料理の中でももっとも重要なものがみそ汁である。魚料理の最高峰だと思っているが、主役級ではない。喜劇人の三木のり平が主役はいなくなっても替えが利くが、うまい役者は替えが利かないと述べていたが、そのうまい役者がみそ汁なのだ。日本全国で作られている普通の料理だが、沖縄県や奄美大島などの鹿児島県島嶼部以外では衰退している気がする。北海道など古くはカジカなどのみそ汁をよく作っていたと言うが、みその消費量の減少とともに作らなくなった、と室蘭の市場で聞いている。作り方は簡単すぎるほど簡単である。魚は小さいものは水洗いしてぶつ切りに、大きなものはあらでいい。我が方は魚の生臭みに敏感なので、これを湯通しする。氷水などに落として残った鱗やぬめりをとる。(これは必須ではない)水分をよくきり、必ず水から煮出してみそを溶く。今回はウミンチュにフーチバーをいただいたので、あしらったが、ねぎでも青菜でもなんでもいい。ここに酒を加えたりするが邪道だと思う。こんなことをするくらいなら沖縄のオバアの真似をして味の素を振る方が増し。この魚汁の重大な問題点は汁ではなく、おかずだということだ。沖縄で「いまいゆの汁」をお願いすると勝手にご飯と小鉢などがついてくる。要するに汁は主菜なのだ。我ながら魚のみそ汁で飯を食うことだけは止められない。腹が立つくらいにうまい、ので腹が出る。三条中納言を笑えない。 鹿児島県川辺町(南九州市)で会った老人と宮崎県飫肥(日南市)の直売所で聞いた料理に「湯なます」がある。聞取ではイワシ(ウルメイワシかも)でもアジ(マアジ)、キビナゴでもいいので、大根と一緒に油で炒めて醤油・砂糖・酢で味つけする、という料理だった。料理法も油を使ってもいいし、ただ煮てもいいというので、帰宅して書籍で整理し直そうと思ったら意外にも情報がない。鹿児島の「湯なます」は知覧のものが『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている。大根やにんじんと塩いわしの筒切と油で炒めて、酢やみかん汁を加えるものや、完全に汁ものもある。宮崎県の「湯なます」は大根をせん切りにする。いりこを砕いたものと大根のせん切り、唐辛子を油で炒めて醤油と砂糖で味つけするというのがある。ここでは酢を加えていないが、編集時に書き落としたのではないかと考えている。『聞書き 宮崎の食事』(農文協)。また「湯なます」は「煮なます」と同じものであるとしている。両県ともに「湯なます」はアジ(マアジ)もしくはニシン目の魚であるキビナゴ、ウルメイワシやマイワシなどを使うこと。醤油・砂糖に必ず酢を加えることが基本のようである。写真は『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている汁ものの「煮なます」である。ここではマアジを使ったがイワシ(ウルメイワシなど)などでもいい。適当に切り、湯をかけてくさみを取る。冷水に落として汚れやぬめりを流す。適当に切り、だし・薄口醤油・みりんの中で大根とにんじんのせん切り、魚を煮る。仕上げに酢を加える。
鹿児島県川辺町(南九州市)で会った老人と宮崎県飫肥(日南市)の直売所で聞いた料理に「湯なます」がある。聞取ではイワシ(ウルメイワシかも)でもアジ(マアジ)、キビナゴでもいいので、大根と一緒に油で炒めて醤油・砂糖・酢で味つけする、という料理だった。料理法も油を使ってもいいし、ただ煮てもいいというので、帰宅して書籍で整理し直そうと思ったら意外にも情報がない。鹿児島の「湯なます」は知覧のものが『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている。大根やにんじんと塩いわしの筒切と油で炒めて、酢やみかん汁を加えるものや、完全に汁ものもある。宮崎県の「湯なます」は大根をせん切りにする。いりこを砕いたものと大根のせん切り、唐辛子を油で炒めて醤油と砂糖で味つけするというのがある。ここでは酢を加えていないが、編集時に書き落としたのではないかと考えている。『聞書き 宮崎の食事』(農文協)。また「湯なます」は「煮なます」と同じものであるとしている。両県ともに「湯なます」はアジ(マアジ)もしくはニシン目の魚であるキビナゴ、ウルメイワシやマイワシなどを使うこと。醤油・砂糖に必ず酢を加えることが基本のようである。写真は『日本の味のふるさと 鹿児島郷土料理全書』(今村和子 南日本新聞開発センター 1979)に掲載されている汁ものの「煮なます」である。ここではマアジを使ったがイワシ(ウルメイワシなど)などでもいい。適当に切り、湯をかけてくさみを取る。冷水に落として汚れやぬめりを流す。適当に切り、だし・薄口醤油・みりんの中で大根とにんじんのせん切り、魚を煮る。仕上げに酢を加える。 「なます」は本膳料理(室町時代に生まれた武家の形式立てた料理の提供法)での小鉢などにもって提供するもので、火を通した素材を酢などで和えたもの。野菜だけのものを「膾」、魚を使ったものを「鱠」という漢字を当てる。島根県出雲地方の「煮なます」は「鱠」のひとつである。「煮なます」は島根県出雲地方の郷土料理だ。魚の内臓、魚を酢・酒・砂糖・醤油の味つけで大根とともに煮た料理である。宍道湖・中海の汽水域ではスズキ、ワカサギで作り、島根半島ではブリを使う。個人的にはこれほどうまい料理はないと思っている。スズキ・ブリの「煮なます」は身を使うのではなく内臓を使って作る。島根県出雲地方西部にはバショウカジキの内臓を使った料理もある。これと島根半島のブリのわたで作る、「煮なます」、宍道湖・中海のスズキの内臓で作る「煮なます」との関係も考えておくべきだろう。もともとは漁師料理なのかも知れない。ただそれだけでは地域的に広がる可能性は低い。宍道湖東部にある松江市は、城下町でもあり、商業や家内工業、水産業の町でもある。この汽水域に囲まれた町屋でもっともよく食べられたのがスズキであり、夏などは刺身に塩焼きにとよく食べられていた。ただし古くから白身魚は高級なもので、なかなか庶民の食卓に上るというものではなかった。そんな中、松江の町では日常的に内臓が安く売られていたのだと思っている。だからこそ生まれた料理なのではないだろうか。(写真はスズキで身は塩焼き、刺身などに内臓は別にして売られていた)宍道湖・中海で揚がるアマサギ(ワカサギ)を焼いたもので作った「煮なます」は、根菜類といい保存食で作れる便利な一品だったはずだ。宮崎県、鹿児島県には「湯なます」というものがある。基本的な料理法は魚と大根、にんじんなどの根菜類。油で魚以外の材料を炒り、魚を加えて醤油・砂糖・酒(本来は使わないのかも)で味つけするもの。水を加えて汁気を多めにした煮もの、水がたっぷりでなますというよりも汁といった方がいいようなものもある。宮崎県などでは「煮なます」という場合もあるようで、もともとは島根県の「煮なます」と同様の起源なのかもしれない。「なます」という言葉が指す料理は多様である。ほとんど刺身に近いもの、酢を使った和えもの、そして酢を使った煮ものも「なます」のひとつなのである。参考文献/『味のふるさと 17 島根の味』(角川書店 1978)、『聞書き 島根の食事』(農文協)、松江市、安来市では聞取もした。
「なます」は本膳料理(室町時代に生まれた武家の形式立てた料理の提供法)での小鉢などにもって提供するもので、火を通した素材を酢などで和えたもの。野菜だけのものを「膾」、魚を使ったものを「鱠」という漢字を当てる。島根県出雲地方の「煮なます」は「鱠」のひとつである。「煮なます」は島根県出雲地方の郷土料理だ。魚の内臓、魚を酢・酒・砂糖・醤油の味つけで大根とともに煮た料理である。宍道湖・中海の汽水域ではスズキ、ワカサギで作り、島根半島ではブリを使う。個人的にはこれほどうまい料理はないと思っている。スズキ・ブリの「煮なます」は身を使うのではなく内臓を使って作る。島根県出雲地方西部にはバショウカジキの内臓を使った料理もある。これと島根半島のブリのわたで作る、「煮なます」、宍道湖・中海のスズキの内臓で作る「煮なます」との関係も考えておくべきだろう。もともとは漁師料理なのかも知れない。ただそれだけでは地域的に広がる可能性は低い。宍道湖東部にある松江市は、城下町でもあり、商業や家内工業、水産業の町でもある。この汽水域に囲まれた町屋でもっともよく食べられたのがスズキであり、夏などは刺身に塩焼きにとよく食べられていた。ただし古くから白身魚は高級なもので、なかなか庶民の食卓に上るというものではなかった。そんな中、松江の町では日常的に内臓が安く売られていたのだと思っている。だからこそ生まれた料理なのではないだろうか。(写真はスズキで身は塩焼き、刺身などに内臓は別にして売られていた)宍道湖・中海で揚がるアマサギ(ワカサギ)を焼いたもので作った「煮なます」は、根菜類といい保存食で作れる便利な一品だったはずだ。宮崎県、鹿児島県には「湯なます」というものがある。基本的な料理法は魚と大根、にんじんなどの根菜類。油で魚以外の材料を炒り、魚を加えて醤油・砂糖・酒(本来は使わないのかも)で味つけするもの。水を加えて汁気を多めにした煮もの、水がたっぷりでなますというよりも汁といった方がいいようなものもある。宮崎県などでは「煮なます」という場合もあるようで、もともとは島根県の「煮なます」と同様の起源なのかもしれない。「なます」という言葉が指す料理は多様である。ほとんど刺身に近いもの、酢を使った和えもの、そして酢を使った煮ものも「なます」のひとつなのである。参考文献/『味のふるさと 17 島根の味』(角川書店 1978)、『聞書き 島根の食事』(農文協)、松江市、安来市では聞取もした。 魚は市場とスーパーと魚屋で買う。すべての業態が水産物を調べる上で重要である。近所に新しいスーパーが出来て、さっそく見つけたのが千葉県産カツオである。刺身用1尾の4分の1で245g、498円はまあまあ高いけど、昨今の高騰からするとがんばっているな、と思わずにはいられない。元の大きさは1㎏少しだろう。ほぼ同じ物を八王子の市場でも豊洲でも見ている。たぶん江戸時代に目に青葉の晩春、旧暦の4月(太陽暦の5月)に食べていたのも、このサイズだったはず。この千葉県勝浦産のカツオが関東での初カツオに近いものだとしたら、江戸時代よりも1ヶ月以上早い。寒冷な気候であった江戸時代でも、太陽暦の5月下旬のカツオは危険だっただろうなと思うこともある。これで山口県の郷土料理「ちしゃなます風」を作る。ほんらいは炒ったいりこを酢みそに混ぜ込んでちしゃと混ぜて作る。これをカツオに置きかえる。ちなみにちしゃはボクが子供の頃には普通の野菜だった。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の家の舎園地(平安時代からある言葉で家の敷地内にあるから舎園、すなわち小さな畑のこと)で作る野菜のひとつだった。ちしゃ=レタスといってもいいが、茎が伸び、そこから出てくる葉を摘みながら食べる。かきちしゃともいい、韓国などの市場にはサンチュというよりも国内で作られていたような古いちしゃが見られる。かきちしゃなどあるはずもないので、ここでは仕方がないのでサニーレタスを使う。本来のちしゃはかなり渋苦い。あの懐かしい、子供の頃嫌いだったちしゃをもう一度食べてみたい。酢みそは山口県の郷土料理の名著、『防長味の春夏秋冬』(貞永美沙子 マツノ書店 1981)に従い、みそ・酢・砂糖を合わせてすり鉢ですったもの。
魚は市場とスーパーと魚屋で買う。すべての業態が水産物を調べる上で重要である。近所に新しいスーパーが出来て、さっそく見つけたのが千葉県産カツオである。刺身用1尾の4分の1で245g、498円はまあまあ高いけど、昨今の高騰からするとがんばっているな、と思わずにはいられない。元の大きさは1㎏少しだろう。ほぼ同じ物を八王子の市場でも豊洲でも見ている。たぶん江戸時代に目に青葉の晩春、旧暦の4月(太陽暦の5月)に食べていたのも、このサイズだったはず。この千葉県勝浦産のカツオが関東での初カツオに近いものだとしたら、江戸時代よりも1ヶ月以上早い。寒冷な気候であった江戸時代でも、太陽暦の5月下旬のカツオは危険だっただろうなと思うこともある。これで山口県の郷土料理「ちしゃなます風」を作る。ほんらいは炒ったいりこを酢みそに混ぜ込んでちしゃと混ぜて作る。これをカツオに置きかえる。ちなみにちしゃはボクが子供の頃には普通の野菜だった。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の家の舎園地(平安時代からある言葉で家の敷地内にあるから舎園、すなわち小さな畑のこと)で作る野菜のひとつだった。ちしゃ=レタスといってもいいが、茎が伸び、そこから出てくる葉を摘みながら食べる。かきちしゃともいい、韓国などの市場にはサンチュというよりも国内で作られていたような古いちしゃが見られる。かきちしゃなどあるはずもないので、ここでは仕方がないのでサニーレタスを使う。本来のちしゃはかなり渋苦い。あの懐かしい、子供の頃嫌いだったちしゃをもう一度食べてみたい。酢みそは山口県の郷土料理の名著、『防長味の春夏秋冬』(貞永美沙子 マツノ書店 1981)に従い、みそ・酢・砂糖を合わせてすり鉢ですったもの。 石川県、福井県で作られている「塩いり」、「浜いり」は呼び名は違うが同じ調理法だ。「塩いり」は石川・福井両県でみられるもので、資料としても残っている。浜(漁港)でとれたばかりの魚の保存性を高めるために作られていたものと、家庭などで作られていたものに二分する。明らかに浜で生まれた料理が一般家庭にも広がったのだと考えている。料理店、一般家庭で作られているものは塩分濃度がとても低く、保存性も低い。「浜いり」という言語は今のところ、石川県加賀市塩屋でしか採取していない。強い塩水で水分を飛ばしながら火を通し、完全に水気をなくしたものだ。一般家庭で作っているという人には出会えていない。基本的に漁港周辺で作られる四十物で保存性を高めるために作られる。この四十物としての「塩いり」、「浜いり」は海から遠い地域へ送られたり、行商していたはずだが、このあたりの資料は見つかっていない。また新潟県から島根県にかけて浜焼きがある。こちらも山間部へ運ぶための四十物である。塩辛、塩漬け、ぬか漬けなどとともに、日本海で生まれた四十物のひとつが「塩いり」、「浜いり」なのだと思っている。同じような料理が鹿児島県奄美諸島、沖縄県にもある。「塩煮(まーす煮)」である。冷蔵庫のない時代にはいかに魚を長持ちさせるかが、もっとも重要なことであった。それが家庭料理にも浸透していくなど同じような広がり方をしている。
石川県、福井県で作られている「塩いり」、「浜いり」は呼び名は違うが同じ調理法だ。「塩いり」は石川・福井両県でみられるもので、資料としても残っている。浜(漁港)でとれたばかりの魚の保存性を高めるために作られていたものと、家庭などで作られていたものに二分する。明らかに浜で生まれた料理が一般家庭にも広がったのだと考えている。料理店、一般家庭で作られているものは塩分濃度がとても低く、保存性も低い。「浜いり」という言語は今のところ、石川県加賀市塩屋でしか採取していない。強い塩水で水分を飛ばしながら火を通し、完全に水気をなくしたものだ。一般家庭で作っているという人には出会えていない。基本的に漁港周辺で作られる四十物で保存性を高めるために作られる。この四十物としての「塩いり」、「浜いり」は海から遠い地域へ送られたり、行商していたはずだが、このあたりの資料は見つかっていない。また新潟県から島根県にかけて浜焼きがある。こちらも山間部へ運ぶための四十物である。塩辛、塩漬け、ぬか漬けなどとともに、日本海で生まれた四十物のひとつが「塩いり」、「浜いり」なのだと思っている。同じような料理が鹿児島県奄美諸島、沖縄県にもある。「塩煮(まーす煮)」である。冷蔵庫のない時代にはいかに魚を長持ちさせるかが、もっとも重要なことであった。それが家庭料理にも浸透していくなど同じような広がり方をしている。 兵庫県但馬地方の「じゃう」は魚を水洗いして適当に切り、野菜と一緒に煮て作る醤油味の煮もの、汁、もしくは鍋だ。1960年代以前の食生活を聞書いた、『聞き書 兵庫の食事』(農文協)にも1行ほど「さばのじゃう」が載っていて、写真を見る限りは煮ものそのものだ。合わせる野菜は聞取した限りではゴボウ、ネギが基本形であるようだ。これ一品を作るだけでおかずにもなり、汁にもなり、酒の肴にもなる。手間いらずな料理でもあるようだ。よく「じゃう」を「すき焼き」のことだとしている書があるが、たぶん間違いだと思う。獣肉などを少量の液体で調理するのが「すき焼き」で、「じゃう」は鍋にするにしても液体の量が多いのである。要するに知名度が上がり一人歩きしはじめた「すき焼き」という言葉を多くの地域でそれらしい料理に当てはめた。それをまた見識のない人が広めたのだと思う。実際、西日本の家庭で作られる「すき焼き」の多くが液体の多い醤油味の鍋である。料理名「じゃう」 同様の料理は日本各地にありそうである。大阪府のもっとも古い形の「うおすき」、滋賀県の「じゅんじゅん」、三重県尾鷲市の「じふ」、島根県石見地方の「煮食い(にぐい)」などだ。作り方などもそっくりなので魚がとれるところで自然発生的に生まれた可能性もある。醤油以前は「みそたまり(みそから染み出る液体)」で作った可能性が高いと考えられる。料理の理念 どの地方でも言えることだが、漁で揚がった売れないいろんな魚を使い作ること、また様々な作り方があることなども同じである。言うなれば魚を煮て食べるという単純な料理だから今に続いているのだ。このような売れない魚を使った料理は、例えばフランスのブイヤベース、イタリアのカッチュッコ、ロシアのウハーなどとも共通する。写真は鍋の「さばのじゃう」だ。昔、兵庫県の日本海側、但馬地方は国内屈指のマサバの産地であった。産地でもっともたくさんとれる魚を使うのが「じゃう」なのである。また鍋でもあるというのは寒い時季の料理だからだ。汁や煮ものよりも煮ながら食べる鍋の方が効率的だし、また家族が食べたいだけ食べられるなどの利点がある聞取した限りでは、日本海に面した但馬地方では、今現在も「山がれい(ヒレグロ)」、「はた(ハタハタ)」で作られているという。この2種は寒い時季にあるていどまとまってとれ、また「山がれい」の小型は売り物にならない魚の漁師さんの家庭での自家消費といえる。また国内で長年問題となっていたリジン欠乏症には特効薬的なものだったのではないか。当然優れた料理なので漁業のある海辺から、山間部への広がりもあったはずだ。
兵庫県但馬地方の「じゃう」は魚を水洗いして適当に切り、野菜と一緒に煮て作る醤油味の煮もの、汁、もしくは鍋だ。1960年代以前の食生活を聞書いた、『聞き書 兵庫の食事』(農文協)にも1行ほど「さばのじゃう」が載っていて、写真を見る限りは煮ものそのものだ。合わせる野菜は聞取した限りではゴボウ、ネギが基本形であるようだ。これ一品を作るだけでおかずにもなり、汁にもなり、酒の肴にもなる。手間いらずな料理でもあるようだ。よく「じゃう」を「すき焼き」のことだとしている書があるが、たぶん間違いだと思う。獣肉などを少量の液体で調理するのが「すき焼き」で、「じゃう」は鍋にするにしても液体の量が多いのである。要するに知名度が上がり一人歩きしはじめた「すき焼き」という言葉を多くの地域でそれらしい料理に当てはめた。それをまた見識のない人が広めたのだと思う。実際、西日本の家庭で作られる「すき焼き」の多くが液体の多い醤油味の鍋である。料理名「じゃう」 同様の料理は日本各地にありそうである。大阪府のもっとも古い形の「うおすき」、滋賀県の「じゅんじゅん」、三重県尾鷲市の「じふ」、島根県石見地方の「煮食い(にぐい)」などだ。作り方などもそっくりなので魚がとれるところで自然発生的に生まれた可能性もある。醤油以前は「みそたまり(みそから染み出る液体)」で作った可能性が高いと考えられる。料理の理念 どの地方でも言えることだが、漁で揚がった売れないいろんな魚を使い作ること、また様々な作り方があることなども同じである。言うなれば魚を煮て食べるという単純な料理だから今に続いているのだ。このような売れない魚を使った料理は、例えばフランスのブイヤベース、イタリアのカッチュッコ、ロシアのウハーなどとも共通する。写真は鍋の「さばのじゃう」だ。昔、兵庫県の日本海側、但馬地方は国内屈指のマサバの産地であった。産地でもっともたくさんとれる魚を使うのが「じゃう」なのである。また鍋でもあるというのは寒い時季の料理だからだ。汁や煮ものよりも煮ながら食べる鍋の方が効率的だし、また家族が食べたいだけ食べられるなどの利点がある聞取した限りでは、日本海に面した但馬地方では、今現在も「山がれい(ヒレグロ)」、「はた(ハタハタ)」で作られているという。この2種は寒い時季にあるていどまとまってとれ、また「山がれい」の小型は売り物にならない魚の漁師さんの家庭での自家消費といえる。また国内で長年問題となっていたリジン欠乏症には特効薬的なものだったのではないか。当然優れた料理なので漁業のある海辺から、山間部への広がりもあったはずだ。 千葉県内房竹岡産に味をしめたので、地元、八王子の市場で、こんどは活け締めのクロダイを買う。産地不明で1.5kgもある。刺身にして、煮つけにして、塩焼きにしてと食べて、おいしいにはおいしいものの、味ではひとまわり小さい竹岡産に軍配が上がる。やはり活魚がいいのか、もしくは卵巣の膨らみは今回の方が大きく、そこに味の優劣が出たともいえる。春のクロダイは生殖巣の成熟度で味が決まる。あまり成熟が進んだものはおいしくない。2月もあと数日という日である。昼間は暖かいが、朝夕は寒い。まだまだ冬の鍋がよいと、鯛は鯛でもクロダイで「鯛ちり」にする。「ちり」は関西の料理だろう。同じく山陽、四国の一部では同様の鍋を「水炊き」という。昆布だしに酒・塩の単純な味つけの汁で煮ながら食べる。素材そのものの味が楽しめる。「鯛ちり」の「ちり」は、汁に魚の切り身を落とすと、ちりっと縮むので「ちり」だというが、個人的には素材を「いろいろちりばめた」ので「ちり」だと考えている。
千葉県内房竹岡産に味をしめたので、地元、八王子の市場で、こんどは活け締めのクロダイを買う。産地不明で1.5kgもある。刺身にして、煮つけにして、塩焼きにしてと食べて、おいしいにはおいしいものの、味ではひとまわり小さい竹岡産に軍配が上がる。やはり活魚がいいのか、もしくは卵巣の膨らみは今回の方が大きく、そこに味の優劣が出たともいえる。春のクロダイは生殖巣の成熟度で味が決まる。あまり成熟が進んだものはおいしくない。2月もあと数日という日である。昼間は暖かいが、朝夕は寒い。まだまだ冬の鍋がよいと、鯛は鯛でもクロダイで「鯛ちり」にする。「ちり」は関西の料理だろう。同じく山陽、四国の一部では同様の鍋を「水炊き」という。昆布だしに酒・塩の単純な味つけの汁で煮ながら食べる。素材そのものの味が楽しめる。「鯛ちり」の「ちり」は、汁に魚の切り身を落とすと、ちりっと縮むので「ちり」だというが、個人的には素材を「いろいろちりばめた」ので「ちり」だと考えている。 京都の料理は京料理と言うらしい。京料理はその上、登録無形文化財だそうだ。そこにどんな意味があるのかと思ったら内容らしい内容がない。どうしてこんなに内容がないのだろう?つらつら考えるに京都の食の歴史が抜けているではないか? 京都の料理は水産物でいえば、四十物(海や琵琶湖から焼いたり塩をしたり漬けたりしてもたらされたもの)と、生簀が重要だと考えている。京料理は登録無形文化財なのに、観光客に受けそうなもので、あえて言えばフォトジェニックはモンばっかり、低級じゃねーか、とヤナ気持ちになる。京都だけではなく、関東、三河・尾張・岐阜などの天下をとった地域、京都、大阪などの料理は淡水魚から始まっているのである。ちなみに角倉了以は江戸時代初期に鴨川の水を京の街に引き込んだ。この高瀬川が多くの水路を生んだのが京の生簀の始まりである。関東には広大な過疎地、平野が広がっていて、そこに徳川家が入り大量の人が流入する。水は農業にも生きるためにも必須である。関東平野に水路が多く、また取り残された河川が多いのも人口流入の結果である。この人口の水域が生み出すのが膨大な淡水魚だ。これは遙かに水に恵まれている尾張・美濃など木曽三川地帯にも言える。河川はたたかう対象であるとともに、関東などと比べると遙かに水路が作りやすく、複雑な水域を作ることができる。そこから多種多様、膨大な淡水魚を生み出す。大阪が大坂だった頃、大阪城が豊臣秀吉によって築かれた時代に鮒や鯉を売る市場があり、食用フナとして重要なカワチブナを作りだしたのも大阪である。長すぎるけど、鳥取、島根(両県は並べると嫌がる人がいるのはなぜ?)の汽水湖周辺、岡山の児島湾(今では児島湖)周辺、九州筑後川、鹿児島など淡水魚を食べる地域は決して今でも少なくない。日本料理を生み出した最初が淡水魚なら、もっと淡水魚は食べられてもいいはずだ。久しぶりの千葉県神崎町で「鯉の洗い」を買った。洗いは作ったそばから食いたいとは思うが、さすがにそうもいかない。たぶん料理して12時間後くらいに食べたが十二分においしかった。洗いを食べながら浮かんできたものをつれづれに書くと以上になる。千葉県神崎町のオッチャンなど「海の魚はまずくて食えない」と言う。そこまでは思わないけど、フナの洗い・刺身、コイの洗い・刺身などを食べると、いつもながらに素晴らしい食感、豊かなうま味に感動する。確かに海の魚の刺身など味気ない気がする。千葉県神崎町、鯉洗いに合わせたのは、宮城県石巻の日高見で口中冷え冷えしてうまかった。
京都の料理は京料理と言うらしい。京料理はその上、登録無形文化財だそうだ。そこにどんな意味があるのかと思ったら内容らしい内容がない。どうしてこんなに内容がないのだろう?つらつら考えるに京都の食の歴史が抜けているではないか? 京都の料理は水産物でいえば、四十物(海や琵琶湖から焼いたり塩をしたり漬けたりしてもたらされたもの)と、生簀が重要だと考えている。京料理は登録無形文化財なのに、観光客に受けそうなもので、あえて言えばフォトジェニックはモンばっかり、低級じゃねーか、とヤナ気持ちになる。京都だけではなく、関東、三河・尾張・岐阜などの天下をとった地域、京都、大阪などの料理は淡水魚から始まっているのである。ちなみに角倉了以は江戸時代初期に鴨川の水を京の街に引き込んだ。この高瀬川が多くの水路を生んだのが京の生簀の始まりである。関東には広大な過疎地、平野が広がっていて、そこに徳川家が入り大量の人が流入する。水は農業にも生きるためにも必須である。関東平野に水路が多く、また取り残された河川が多いのも人口流入の結果である。この人口の水域が生み出すのが膨大な淡水魚だ。これは遙かに水に恵まれている尾張・美濃など木曽三川地帯にも言える。河川はたたかう対象であるとともに、関東などと比べると遙かに水路が作りやすく、複雑な水域を作ることができる。そこから多種多様、膨大な淡水魚を生み出す。大阪が大坂だった頃、大阪城が豊臣秀吉によって築かれた時代に鮒や鯉を売る市場があり、食用フナとして重要なカワチブナを作りだしたのも大阪である。長すぎるけど、鳥取、島根(両県は並べると嫌がる人がいるのはなぜ?)の汽水湖周辺、岡山の児島湾(今では児島湖)周辺、九州筑後川、鹿児島など淡水魚を食べる地域は決して今でも少なくない。日本料理を生み出した最初が淡水魚なら、もっと淡水魚は食べられてもいいはずだ。久しぶりの千葉県神崎町で「鯉の洗い」を買った。洗いは作ったそばから食いたいとは思うが、さすがにそうもいかない。たぶん料理して12時間後くらいに食べたが十二分においしかった。洗いを食べながら浮かんできたものをつれづれに書くと以上になる。千葉県神崎町のオッチャンなど「海の魚はまずくて食えない」と言う。そこまでは思わないけど、フナの洗い・刺身、コイの洗い・刺身などを食べると、いつもながらに素晴らしい食感、豊かなうま味に感動する。確かに海の魚の刺身など味気ない気がする。千葉県神崎町、鯉洗いに合わせたのは、宮城県石巻の日高見で口中冷え冷えしてうまかった。 船場とは大阪市中区の北は土佐堀川、南は長堀通、西は御堂筋、東は東横堀川までの広い地域のことだ。典型的な大阪といった場所で丼池の繊維街、薬を扱う道修町、証券会社の集まる北浜などがある。今でも上品な大阪言葉が残っていたりする場所で、今どきの大阪弁であるごっつい泥臭さとは無縁の地なのだ。この船場と言われるところを歩いてみたが往時の商人町の面影はほとんど残っていない。あえていえば北浜の適塾(幕末にあった緒方洪庵の医術塾)や古い薬問屋、丼池の繊維街の喧噪くらいかも知れない。大阪中心部のこのあたりは大商人の町なので、丁稚どんに番頭どん、などたくさんの働き手が暮らしていた。多くは共同生活、集団での食事である。大正時代、船場平野町の薬問屋、安田市兵衛商店で丁稚だった日本演劇界の巨人、菊田一夫は、食事も完全なる階級制であり、大番頭は畳敷きの場所で座って食事を摂り、中番頭以下は土間に沿った板の間で食べたという。菊田一夫は身長が低く、食べるのが遅かった。ゆっくり食べていると十分に食べられない。そこで編み出したのが汁と飯を熱々の状態でかき込むということだ。汁がおかずでもあった証拠といえるだろう。大阪の商人町の食事は極端に動物性たんぱくが少なかったようだ。そんな中でも登場回数の多かったのが塩サバだった。関西のマサバの供給地は日本海の北陸・山陰で、太平洋側では紀伊水道、熊野灘だった。これが大阪の地に送られて来ていたのだ。当時のマサバの流通は鮮魚もあっただろうが、ほとんどが塩蔵品、もしくは干ものだったと思われる。しかも今では考えられない程の塩分濃度の濃いもの。この体幹部分は焼き、あらの部分を大根とたいて作ったのが「船場汁」、「船場煮」だ。汁といっても大根を煮て、塩蔵サバのあらを入れるだけ。塩味は塩蔵サバから出るし、あら自体も塩辛い。厳しい商家の生活にはなくてはならなかったものだろう。寒い時季に食べるもので、ときには生(鮮魚)を使って作られることもあるという。また重要なのは「船場汁」というのは大阪市の言葉だということ。他の地域でも同じような料理が作られている可能性が高い。地元の料理は地元の言葉で作り、食べて欲しい。参考/『聞き書 大阪の食事』(農文協)、『船場道修町』(三島佑一 人文書院 1990)、『評伝 菊田一夫』(小幡欣治 岩波書店 2008)
船場とは大阪市中区の北は土佐堀川、南は長堀通、西は御堂筋、東は東横堀川までの広い地域のことだ。典型的な大阪といった場所で丼池の繊維街、薬を扱う道修町、証券会社の集まる北浜などがある。今でも上品な大阪言葉が残っていたりする場所で、今どきの大阪弁であるごっつい泥臭さとは無縁の地なのだ。この船場と言われるところを歩いてみたが往時の商人町の面影はほとんど残っていない。あえていえば北浜の適塾(幕末にあった緒方洪庵の医術塾)や古い薬問屋、丼池の繊維街の喧噪くらいかも知れない。大阪中心部のこのあたりは大商人の町なので、丁稚どんに番頭どん、などたくさんの働き手が暮らしていた。多くは共同生活、集団での食事である。大正時代、船場平野町の薬問屋、安田市兵衛商店で丁稚だった日本演劇界の巨人、菊田一夫は、食事も完全なる階級制であり、大番頭は畳敷きの場所で座って食事を摂り、中番頭以下は土間に沿った板の間で食べたという。菊田一夫は身長が低く、食べるのが遅かった。ゆっくり食べていると十分に食べられない。そこで編み出したのが汁と飯を熱々の状態でかき込むということだ。汁がおかずでもあった証拠といえるだろう。大阪の商人町の食事は極端に動物性たんぱくが少なかったようだ。そんな中でも登場回数の多かったのが塩サバだった。関西のマサバの供給地は日本海の北陸・山陰で、太平洋側では紀伊水道、熊野灘だった。これが大阪の地に送られて来ていたのだ。当時のマサバの流通は鮮魚もあっただろうが、ほとんどが塩蔵品、もしくは干ものだったと思われる。しかも今では考えられない程の塩分濃度の濃いもの。この体幹部分は焼き、あらの部分を大根とたいて作ったのが「船場汁」、「船場煮」だ。汁といっても大根を煮て、塩蔵サバのあらを入れるだけ。塩味は塩蔵サバから出るし、あら自体も塩辛い。厳しい商家の生活にはなくてはならなかったものだろう。寒い時季に食べるもので、ときには生(鮮魚)を使って作られることもあるという。また重要なのは「船場汁」というのは大阪市の言葉だということ。他の地域でも同じような料理が作られている可能性が高い。地元の料理は地元の言葉で作り、食べて欲しい。参考/『聞き書 大阪の食事』(農文協)、『船場道修町』(三島佑一 人文書院 1990)、『評伝 菊田一夫』(小幡欣治 岩波書店 2008) 新潟県では魚のあら(中骨・腹骨の他、肝、白子、腹部の膜、腸などの内臓を含む)を「がら」、「どんがら」という。例えばサケの「がら」は中骨であったりする。新潟県で「たら」といえばスケトウダラなので、「たらのどんがら汁」、「たらのがら汁」はスケトウダラの汁となる。ちなみに新潟県以南はマダラも食べるけれど、どちらかというとスケトウダラ圏なのである 山形県で「どんがら」は魚のあら(内臓を含む)のことだが、主にマダラのあらを「どんがら」というようだ。当然、「どんがら汁」はマダラのあら汁のことになる。 秋田県ではあら(内臓を含む)を「じゃっぱ」、「ざっぱ」という。郷土料理店で食べたマダラの汁は「しょっつる仕立て」の「たら汁」であった。 青森県で魚のあら(内臓を含む)は県全域で「じゃっぱ」だと思っている。ただ県西部と東部では作り方がまったく違っている。津軽のみそ仕立て、下北の塩仕立てなどといい。濃厚で泥臭く体が芯から温まるのが津軽風、さっぱりして後味がいいのが下北風である。 どの県の汁も重要なのは肝(肝臓)、雄であれば白子である。肝が汁の味にこくを出し、肝の脂が汁の表面を覆うので、汁がいつまでも冷めないのだという。写真は山形県庄内、鼠ヶ関の「どんがら汁」でみそ仕立て。
新潟県では魚のあら(中骨・腹骨の他、肝、白子、腹部の膜、腸などの内臓を含む)を「がら」、「どんがら」という。例えばサケの「がら」は中骨であったりする。新潟県で「たら」といえばスケトウダラなので、「たらのどんがら汁」、「たらのがら汁」はスケトウダラの汁となる。ちなみに新潟県以南はマダラも食べるけれど、どちらかというとスケトウダラ圏なのである 山形県で「どんがら」は魚のあら(内臓を含む)のことだが、主にマダラのあらを「どんがら」というようだ。当然、「どんがら汁」はマダラのあら汁のことになる。 秋田県ではあら(内臓を含む)を「じゃっぱ」、「ざっぱ」という。郷土料理店で食べたマダラの汁は「しょっつる仕立て」の「たら汁」であった。 青森県で魚のあら(内臓を含む)は県全域で「じゃっぱ」だと思っている。ただ県西部と東部では作り方がまったく違っている。津軽のみそ仕立て、下北の塩仕立てなどといい。濃厚で泥臭く体が芯から温まるのが津軽風、さっぱりして後味がいいのが下北風である。 どの県の汁も重要なのは肝(肝臓)、雄であれば白子である。肝が汁の味にこくを出し、肝の脂が汁の表面を覆うので、汁がいつまでも冷めないのだという。写真は山形県庄内、鼠ヶ関の「どんがら汁」でみそ仕立て。 農林水産省が「ぶり大根」を富山県の郷土料理に選定している。なんて愚かな、としか言いようがない。例えばライスカレーを特定の県の郷土料理とするようなもの。典型的なお役所仕事だ。「鰤大根」は郷土料理ではないと考えている。養殖が盛んになりブリの頭が単独流通するなどして、別にブリを仕入れなくても料理店で提供ができる。一般家庭でも普通の日常的な料理だと思っている。最初に。「鰤大根(ブリだいこん)」は冬に作られるものだが、年取とは無関係だということを述べておきたい。年取魚としてのブリはあくまでも塩蔵、もしくは塩蔵して干したものである。しょうゆ味の総菜、「鰤大根」は生のブリでなければ作れない。当然、産地でもない限り正月に食べるものではない。「鰤大根」という料理名が定着したのは最近のことだ。同様の料理に名前がなかったり、別の料理名であったかも知れない。郷土料理などの料理名が急激に消滅し始めるのは1970年代からだと思う。この頃、ラジオの料理の番組がテレビに移行する。この時期以降の料理番組、料理家(料理研究家ではない)には、地域性に関しても配慮が明らかに欠けている。地域での呼び名としての「鰤大根」は、1984年から刊行開始された『聞書き 日本の食事全集』をみる限り『聞書き 石川の食事』の金沢市、『聞書き 福井の食事』の福井平野にあり、ブリのあらと大根をしょう油で煮つけたものものとしている。蛇足になるが古い版の広辞苑、歳時記、『飲食事典』(山本荻舟 平凡社 1958)などにも「鰤大根」は出てこない。ちなみに『聞書き 富山の食事』に氷見地方の料理として「ぶりの残と大根の煮もん」が出てくるがみそ味だ。石川県と富山県は言葉など共通する部分が多いので、富山県にもしょう油味の鰤と大根の煮つけは存在するはずである。『聞書き 日本の食事全集』は優れた出版物だが、日常的にその地域で食されてきたほんの一部しか掲載していないということも忘れてはならない。
農林水産省が「ぶり大根」を富山県の郷土料理に選定している。なんて愚かな、としか言いようがない。例えばライスカレーを特定の県の郷土料理とするようなもの。典型的なお役所仕事だ。「鰤大根」は郷土料理ではないと考えている。養殖が盛んになりブリの頭が単独流通するなどして、別にブリを仕入れなくても料理店で提供ができる。一般家庭でも普通の日常的な料理だと思っている。最初に。「鰤大根(ブリだいこん)」は冬に作られるものだが、年取とは無関係だということを述べておきたい。年取魚としてのブリはあくまでも塩蔵、もしくは塩蔵して干したものである。しょうゆ味の総菜、「鰤大根」は生のブリでなければ作れない。当然、産地でもない限り正月に食べるものではない。「鰤大根」という料理名が定着したのは最近のことだ。同様の料理に名前がなかったり、別の料理名であったかも知れない。郷土料理などの料理名が急激に消滅し始めるのは1970年代からだと思う。この頃、ラジオの料理の番組がテレビに移行する。この時期以降の料理番組、料理家(料理研究家ではない)には、地域性に関しても配慮が明らかに欠けている。地域での呼び名としての「鰤大根」は、1984年から刊行開始された『聞書き 日本の食事全集』をみる限り『聞書き 石川の食事』の金沢市、『聞書き 福井の食事』の福井平野にあり、ブリのあらと大根をしょう油で煮つけたものものとしている。蛇足になるが古い版の広辞苑、歳時記、『飲食事典』(山本荻舟 平凡社 1958)などにも「鰤大根」は出てこない。ちなみに『聞書き 富山の食事』に氷見地方の料理として「ぶりの残と大根の煮もん」が出てくるがみそ味だ。石川県と富山県は言葉など共通する部分が多いので、富山県にもしょう油味の鰤と大根の煮つけは存在するはずである。『聞書き 日本の食事全集』は優れた出版物だが、日常的にその地域で食されてきたほんの一部しか掲載していないということも忘れてはならない。 湖東天野川ほとりに世継ぎという不思議な名の集落がある。天野川河口域は昔からハスの宝庫で、その昔「ハス料理」を名物にする料亭が軒を並べていたという。そして今に残るのはたった一軒のみ。それが『やまに料理店』である。江戸時代には二条城に魚を納めていて、そこから山に二条城の「二」をいただいたものだとのこと。2008年で9代目、10代目とともに店を営んでいる。ちなみに京料理の根源は日本海からの塩乾魚貝類と滋賀県琵琶湖の湖魚である。大型のハスを料理するのはとても難しい。湖魚を扱う店で買い求め、いざ料理しても小骨が多いこともあってなかなか上手に料れないのだ。この難敵を見事に提供しているのが、『やまに料理店』である。滋賀県琵琶湖周辺でもハスの成魚の水揚げはあり、鮮魚は手に入るものの、提供している料理店はほぼないのではないかと思っている。この貴重な「ハス料理」を末永く継承していただきたいものである。
湖東天野川ほとりに世継ぎという不思議な名の集落がある。天野川河口域は昔からハスの宝庫で、その昔「ハス料理」を名物にする料亭が軒を並べていたという。そして今に残るのはたった一軒のみ。それが『やまに料理店』である。江戸時代には二条城に魚を納めていて、そこから山に二条城の「二」をいただいたものだとのこと。2008年で9代目、10代目とともに店を営んでいる。ちなみに京料理の根源は日本海からの塩乾魚貝類と滋賀県琵琶湖の湖魚である。大型のハスを料理するのはとても難しい。湖魚を扱う店で買い求め、いざ料理しても小骨が多いこともあってなかなか上手に料れないのだ。この難敵を見事に提供しているのが、『やまに料理店』である。滋賀県琵琶湖周辺でもハスの成魚の水揚げはあり、鮮魚は手に入るものの、提供している料理店はほぼないのではないかと思っている。この貴重な「ハス料理」を末永く継承していただきたいものである。 古くは浜で揚がった魚貝類の多くは鮮魚ではなく、加工して山間部や近くの都市部に送られていた。無塩(ぶえん)ものなどと呼ばれている鮮魚などは冬だけのものだったのだ。塩もの、干ものは今でも一般的だが、魚やイカを焼いて山間部や都市に売りに行くという地域は非常に少なくなっている。東北宮城県、日本海の新潟県から島根県などに残るが年々減少傾向にある。今でも比較的多く見かけるのは「焼きさば」である。サバ類以外で会社組織で成り立っているのは宮城県とこの兵庫県だけかも知れない。福井県以西では今、魚屋さんが朝方焼き上げて売ってることが多い。この中にあって沖ギス(ニギス)に特化しているのが浜貞商店、濱上栄作さんとそのお母様である民子さんである。工場内にはとてもいい香りが充満している。これだけで飯一膳といったもので、焼き上がるのを見ているだけでご馳走を食べているかのようである。『浜貞商店』の創業は昭和27年(1952年)だという。魚を焼いて加工する山陰にあって、ニギスに特化したのは大正解だと思っている。今や「焼きさば」の原材料マサバは日本海では加工用に回るほど水揚げされていない上に、全国的に見ても国産ではとても間に合わない状況にある。ニギスだけが地物で足りるのである。地産地消というが、「焼にぎす」は関西をはじめ、奥播磨などで人気がある。そのまま食べるだけではなく山間部など煮物などにも利用されている模様である。浜貞商店 兵庫県美方郡香美町香住区香住1806−4
古くは浜で揚がった魚貝類の多くは鮮魚ではなく、加工して山間部や近くの都市部に送られていた。無塩(ぶえん)ものなどと呼ばれている鮮魚などは冬だけのものだったのだ。塩もの、干ものは今でも一般的だが、魚やイカを焼いて山間部や都市に売りに行くという地域は非常に少なくなっている。東北宮城県、日本海の新潟県から島根県などに残るが年々減少傾向にある。今でも比較的多く見かけるのは「焼きさば」である。サバ類以外で会社組織で成り立っているのは宮城県とこの兵庫県だけかも知れない。福井県以西では今、魚屋さんが朝方焼き上げて売ってることが多い。この中にあって沖ギス(ニギス)に特化しているのが浜貞商店、濱上栄作さんとそのお母様である民子さんである。工場内にはとてもいい香りが充満している。これだけで飯一膳といったもので、焼き上がるのを見ているだけでご馳走を食べているかのようである。『浜貞商店』の創業は昭和27年(1952年)だという。魚を焼いて加工する山陰にあって、ニギスに特化したのは大正解だと思っている。今や「焼きさば」の原材料マサバは日本海では加工用に回るほど水揚げされていない上に、全国的に見ても国産ではとても間に合わない状況にある。ニギスだけが地物で足りるのである。地産地消というが、「焼にぎす」は関西をはじめ、奥播磨などで人気がある。そのまま食べるだけではなく山間部など煮物などにも利用されている模様である。浜貞商店 兵庫県美方郡香美町香住区香住1806−4 高知県の居酒屋さんでカツオの刺身についてきたもの。カツオだけではなくブリでもヒラソウダなどにもあう、万能調味料である。材料は、葉ニンニク、ごま(入れないという人もいる)、みそ、酢、砂糖で作る合わせみそだ。ただし高知県の食関連の書籍にはどこを探しても見つからない。高知県は葉ニンニクの栽培が盛んなので、意外に新しい食品なのかも知れない。とても簡単に作れて、しかもいろんな魚貝類につけて食べることができる。他の地方でも取り入れてもいいのでは、と考えている。自家製すると葉ニンニクなどのきめが粗いものとなるが、市販品のようにクリーミーなものよりもおいしいと思う。
高知県の居酒屋さんでカツオの刺身についてきたもの。カツオだけではなくブリでもヒラソウダなどにもあう、万能調味料である。材料は、葉ニンニク、ごま(入れないという人もいる)、みそ、酢、砂糖で作る合わせみそだ。ただし高知県の食関連の書籍にはどこを探しても見つからない。高知県は葉ニンニクの栽培が盛んなので、意外に新しい食品なのかも知れない。とても簡単に作れて、しかもいろんな魚貝類につけて食べることができる。他の地方でも取り入れてもいいのでは、と考えている。自家製すると葉ニンニクなどのきめが粗いものとなるが、市販品のようにクリーミーなものよりもおいしいと思う。 「じふ」は三重県西部・東紀州の、紀伊長島や尾鷲で作られている家庭料理である。地元の漁港で水揚げされる様々な魚で作られているが、言うなれば魚のすき焼き、大阪などの「魚すき」と同じものだ。尾鷲市の家庭で比較的使われる頻度の高い魚は、マサバ、ゴマサバ、サンマ、マンボウ、ブダイ、マダイ、ブリ、サワラなどだというが、あえて言うとなんでもいいのだという。季節季節に揚がる魚が、臨機応変に使われているようなので、鍋ものとはいえ寒い時季だけのものではないようだ。「じふ」という奇妙な名は、石川県金沢の「じぶ煮」や兵庫県但馬地方の「じゃう」に音が似ていて、料理法も「何かを煮る」、もしくは「煮ながら食べる鍋」という意味で共通している。また名前は違えど、同じ料理に大阪府や兵庫県などの「魚すき」、島根県の「へか焼き」、「煮食い」などがある。ともに水産物の産地だからこそ生まれる、料理だと考えてもいいだろう。協力/岩田昭人さん(三重県尾鷲市)
「じふ」は三重県西部・東紀州の、紀伊長島や尾鷲で作られている家庭料理である。地元の漁港で水揚げされる様々な魚で作られているが、言うなれば魚のすき焼き、大阪などの「魚すき」と同じものだ。尾鷲市の家庭で比較的使われる頻度の高い魚は、マサバ、ゴマサバ、サンマ、マンボウ、ブダイ、マダイ、ブリ、サワラなどだというが、あえて言うとなんでもいいのだという。季節季節に揚がる魚が、臨機応変に使われているようなので、鍋ものとはいえ寒い時季だけのものではないようだ。「じふ」という奇妙な名は、石川県金沢の「じぶ煮」や兵庫県但馬地方の「じゃう」に音が似ていて、料理法も「何かを煮る」、もしくは「煮ながら食べる鍋」という意味で共通している。また名前は違えど、同じ料理に大阪府や兵庫県などの「魚すき」、島根県の「へか焼き」、「煮食い」などがある。ともに水産物の産地だからこそ生まれる、料理だと考えてもいいだろう。協力/岩田昭人さん(三重県尾鷲市) 「沖鱠(おきなます)」という言語は非常に古く、全国的に使われていた言語だと思われる。「鱠」は魚貝類だけではなく陸上の動物なども細かく切ってたたいて食べること。「沖」は漁の合間という意味もあり、手早くということだろう。漁のときに沖合いで取れた魚を手早く下ろし、皮を引く。板の上にのせて細かくたたいたもの。好みで香辛野菜(しょうが、ねぎ、青じそ、みょうが)や調味料(みそ、醤油、酢、二杯酢)などを加える。また沖でとれた魚を料理すること自体をさすともいい、また沖の魚を土産に家族に持ち帰ること自体もいうとある。今現在、「たたき」と呼ぶ地域の方が多い。神奈川県小田原の「たたきなます」はマアジなどを細かくたたいてねぎなどを和える。三重県鳥羽市、尾鷲の「たたき」は、マアジ、「いさぎ」を三枚に下ろして皮を引き、腹骨・血合い骨などを取らないでかなり細かくたたく。しょうがや大葉を加え、みそで調味することもある。鳥羽市ではみそと調理しても醤油で食べる。尾鷲市では酢醤油で食べることが多い。三陸などではマルタ、ウミタナゴなどを細かくたたき、みそで調味するので「みそたたき」。千葉県、徳島県の「なめろう」は鱠をみそで調味したもののことだ。たぶん、この地域でも「沖なます(たたき)」があり、みそを入れたものを特に「なめろう」としていたのだと思う。千葉県の「さんが焼き」は沖で作った「なめろう」を浜で待つ漁の手伝いをする人や家族のために持ち帰り、焼いて食べたのが起源かも知れない。千葉県の「水なます」は鱠を冷たいみそ汁に入れたもので、鱠はだしの役割もする。歴史的にはもっと集めていかなければいけない。正岡子規の俳句に「はね鯛をとっておさえて沖鱠」、「涼しさや酢にもよごれぬ沖鱠」などがある。夏の季語だが、実際には沖でとった魚がすぐにだめになる時季に作られたのではないかと考える。写真/三重県尾鷲の、いさぎのたたき
「沖鱠(おきなます)」という言語は非常に古く、全国的に使われていた言語だと思われる。「鱠」は魚貝類だけではなく陸上の動物なども細かく切ってたたいて食べること。「沖」は漁の合間という意味もあり、手早くということだろう。漁のときに沖合いで取れた魚を手早く下ろし、皮を引く。板の上にのせて細かくたたいたもの。好みで香辛野菜(しょうが、ねぎ、青じそ、みょうが)や調味料(みそ、醤油、酢、二杯酢)などを加える。また沖でとれた魚を料理すること自体をさすともいい、また沖の魚を土産に家族に持ち帰ること自体もいうとある。今現在、「たたき」と呼ぶ地域の方が多い。神奈川県小田原の「たたきなます」はマアジなどを細かくたたいてねぎなどを和える。三重県鳥羽市、尾鷲の「たたき」は、マアジ、「いさぎ」を三枚に下ろして皮を引き、腹骨・血合い骨などを取らないでかなり細かくたたく。しょうがや大葉を加え、みそで調味することもある。鳥羽市ではみそと調理しても醤油で食べる。尾鷲市では酢醤油で食べることが多い。三陸などではマルタ、ウミタナゴなどを細かくたたき、みそで調味するので「みそたたき」。千葉県、徳島県の「なめろう」は鱠をみそで調味したもののことだ。たぶん、この地域でも「沖なます(たたき)」があり、みそを入れたものを特に「なめろう」としていたのだと思う。千葉県の「さんが焼き」は沖で作った「なめろう」を浜で待つ漁の手伝いをする人や家族のために持ち帰り、焼いて食べたのが起源かも知れない。千葉県の「水なます」は鱠を冷たいみそ汁に入れたもので、鱠はだしの役割もする。歴史的にはもっと集めていかなければいけない。正岡子規の俳句に「はね鯛をとっておさえて沖鱠」、「涼しさや酢にもよごれぬ沖鱠」などがある。夏の季語だが、実際には沖でとった魚がすぐにだめになる時季に作られたのではないかと考える。写真/三重県尾鷲の、いさぎのたたき 煮つけの煮汁でおからを炒り煮する。この煮汁でおからの煮る、は日本各地で行われている、家庭料理だ。関東などでは煮汁を保存して、魚の煮つけに何度も使うが、これをときにおからに使うというのもありだろう。1970年代に上京して行きつけの食堂ができて、その一皿におからがあった。おから炒り(炒り煮)は家庭料理の基本のキなのだけど、なかなかこの食堂のおからのような味にはならなかった。農文協の『聞き書』シリーズにもアカエイの煮つけの汁でおからを作ると言うのが出てくるくらいだから、歴史的にも古い料理なのだと思われる。ボクが初めて出会ったおいしい食堂のおからにも煮魚の煮汁が使われていたのでは、と推測している。煮汁を保存して置くだけなので、経済的だし、とても簡単だし、そしておいしいし、で言うことなしの総菜である。
煮つけの煮汁でおからを炒り煮する。この煮汁でおからの煮る、は日本各地で行われている、家庭料理だ。関東などでは煮汁を保存して、魚の煮つけに何度も使うが、これをときにおからに使うというのもありだろう。1970年代に上京して行きつけの食堂ができて、その一皿におからがあった。おから炒り(炒り煮)は家庭料理の基本のキなのだけど、なかなかこの食堂のおからのような味にはならなかった。農文協の『聞き書』シリーズにもアカエイの煮つけの汁でおからを作ると言うのが出てくるくらいだから、歴史的にも古い料理なのだと思われる。ボクが初めて出会ったおいしい食堂のおからにも煮魚の煮汁が使われていたのでは、と推測している。煮汁を保存して置くだけなので、経済的だし、とても簡単だし、そしておいしいし、で言うことなしの総菜である。該当するコラムが多い為ページを分割して表示します。
全183コラム中 1番目~100番目までを表示中
- 1
- 2