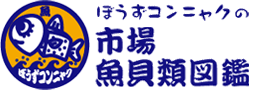コラム検索
検索条件
全47件中 全レコードを表示しています
 9月1日、早朝から鈴木重雄さんの刺し網漁に乗船させていただき、新川の猛者達と海岸線で生き物を探した。これにて詰め込みすぎの4日間がやっと終わった。途端に、異常に腹が減っていることに気がつく。午前中でもろもろが終わったので、越後新川の仲間達に教わった、超オススメの『味の八珍亭』を目指す。ちなみに二番手におすすめなのは『こまどり』だった。先行く車が右折したら、そこが『味の八珍亭』だったものの、なんと定休日だった。疲れと腹ヘリで体がふやけてきた。仕方なく、もうひと踏ん張り、もう一軒の『こまどり』へ。店は実に地味だが、駐車場はやたらに広い。しかも空きがない。困っていたらクラクションが鳴って、ここよ、ここよ、と知らない人が空いたばかりの空間を教えてくれた。駐車場の混み具合をみて、「混んでいそうなのでやめます」と言ったら、「待つかも知れませんが、きっとすぐ入れますよ」と教えてくれる。これから新しい店を探す気にもなれず。熱暑の、店前の空間で待つ。確かにたいして待つこともなく、店に入れたと思ったら、こんどは店内が非常に広いのに驚かされる。昼酒をしている人もいるけど、ほとんどが麺類を食べている。やって来た店員さんに言われた通りに味噌ラーメンにする。これが、信じられないくらいに腹ヘリだったためか、ウルトラ級においしい。スープの塩気で、ふやけた体がしゃきっとして、丼に残ったスープ一滴も残さず平らげた。とすると、噂の『味の八珍亭』はどれほどうまいんだろう?
9月1日、早朝から鈴木重雄さんの刺し網漁に乗船させていただき、新川の猛者達と海岸線で生き物を探した。これにて詰め込みすぎの4日間がやっと終わった。途端に、異常に腹が減っていることに気がつく。午前中でもろもろが終わったので、越後新川の仲間達に教わった、超オススメの『味の八珍亭』を目指す。ちなみに二番手におすすめなのは『こまどり』だった。先行く車が右折したら、そこが『味の八珍亭』だったものの、なんと定休日だった。疲れと腹ヘリで体がふやけてきた。仕方なく、もうひと踏ん張り、もう一軒の『こまどり』へ。店は実に地味だが、駐車場はやたらに広い。しかも空きがない。困っていたらクラクションが鳴って、ここよ、ここよ、と知らない人が空いたばかりの空間を教えてくれた。駐車場の混み具合をみて、「混んでいそうなのでやめます」と言ったら、「待つかも知れませんが、きっとすぐ入れますよ」と教えてくれる。これから新しい店を探す気にもなれず。熱暑の、店前の空間で待つ。確かにたいして待つこともなく、店に入れたと思ったら、こんどは店内が非常に広いのに驚かされる。昼酒をしている人もいるけど、ほとんどが麺類を食べている。やって来た店員さんに言われた通りに味噌ラーメンにする。これが、信じられないくらいに腹ヘリだったためか、ウルトラ級においしい。スープの塩気で、ふやけた体がしゃきっとして、丼に残ったスープ一滴も残さず平らげた。とすると、噂の『味の八珍亭』はどれほどうまいんだろう? 居酒屋で半分討ち死にをし、ホテルまで戻ろうとしたとき見つけたのがステーキの店だった。まさかステーキはないだろう、と思ったらハンバーグがあった。『ドスビーバー』という店で、家族ずれが出て来たのを見て店内に入る。外観通り狭い店だけど、匂いからして正解だと思った。
居酒屋で半分討ち死にをし、ホテルまで戻ろうとしたとき見つけたのがステーキの店だった。まさかステーキはないだろう、と思ったらハンバーグがあった。『ドスビーバー』という店で、家族ずれが出て来たのを見て店内に入る。外観通り狭い店だけど、匂いからして正解だと思った。 8月30日、ホテルにたどりついたら体がゆらゆらする。それでももったいない気がして外出する。非常に空腹なのは午前2時から動いているためで、腹にかなり詰め込んでも、詰め込んでも腹が減るのは、情報処理をしながら動いているからだ。ボクの頭部には大量のソケットが生えていて繋がるソケットを探している。歩きながら情報を整理して繋がるソケットを探す、と、とても疲れるし、腹が減るのだ。さて、古町を目指す。居酒屋的な、がさつだけどがさつすぎない店が好きなので、探し歩くが、歩くのが辛くなってきた。そのとき見つけた静かそうな居酒屋に入る。入ってすぐ、だめだ、と思ったけど、もう遅い。仕方ないのでビール、日本酒に刺身などをお願いする。刺身は地物のようだしぎりぎり合格点ではあるが、たぶんこの板前さん、プロではない。しかも注文して出てくるなどのタイミングが悪い。
8月30日、ホテルにたどりついたら体がゆらゆらする。それでももったいない気がして外出する。非常に空腹なのは午前2時から動いているためで、腹にかなり詰め込んでも、詰め込んでも腹が減るのは、情報処理をしながら動いているからだ。ボクの頭部には大量のソケットが生えていて繋がるソケットを探している。歩きながら情報を整理して繋がるソケットを探す、と、とても疲れるし、腹が減るのだ。さて、古町を目指す。居酒屋的な、がさつだけどがさつすぎない店が好きなので、探し歩くが、歩くのが辛くなってきた。そのとき見つけた静かそうな居酒屋に入る。入ってすぐ、だめだ、と思ったけど、もう遅い。仕方ないのでビール、日本酒に刺身などをお願いする。刺身は地物のようだしぎりぎり合格点ではあるが、たぶんこの板前さん、プロではない。しかも注文して出てくるなどのタイミングが悪い。 出稼ぎのとき、昼時にこんな店に当たるといいなという、まさに、そんな、そば屋だった。湯河原は知り合いが住んでいるのでわかるが、熱海よりも古くからの隠棲の地である。ボクの知っている限り、熱海同様に多くの成功した人間、生粋のお金持ちが都心から移り住んでいる。明治時代から多くの文人墨客に愛されたということもある。それにしてもこの、そば屋は完璧であった。天丼の天ぷらがうまいし、ご飯がいい。期待しないで食べたそばがボク好みであった。たまには出稼ぎもいいな、と思った次第だ。
出稼ぎのとき、昼時にこんな店に当たるといいなという、まさに、そんな、そば屋だった。湯河原は知り合いが住んでいるのでわかるが、熱海よりも古くからの隠棲の地である。ボクの知っている限り、熱海同様に多くの成功した人間、生粋のお金持ちが都心から移り住んでいる。明治時代から多くの文人墨客に愛されたということもある。それにしてもこの、そば屋は完璧であった。天丼の天ぷらがうまいし、ご飯がいい。期待しないで食べたそばがボク好みであった。たまには出稼ぎもいいな、と思った次第だ。 新暦の初午の日は2月6日、二の午は2月18日である。南会津、午の日に行われる行事に欠かせない郷土料理「つむづかり」の、材料の主役は大根である。福島県会津地方でも南会津町は山の中であり、雪深いところであるが、「つむづかり」の大根はこの時季、雪の積もる前に収穫して保存して置いたものを使う。その雪の下の大根を、二の午の日に、岩下の『みどりや』さんに分けてもらって来た。原産地のわからない大根の、国内への移入時期は非常に古い。歴史時代以前からある。寒冷なところでも作れる。歩留まりがよく、生でも食べられるし、煮ておいしいなど、これほど優れた野菜は他にはない。歴史のある野菜なので、その土地土地で生まれた品種が無数にある。今でも地方に行くと日本各地に在来種が散らばっていて、買うのが楽しみである。土地土地の在来種を手に入ると、大根という野菜の奥深さを感じずにはいられない。東京都内では、最近、愛知系のF1ばかりで在来種はなかなか手に入らない。F1がダメだというわけでないが、程よい大きさで、あくが少なく、筋がなく均質な、今どきの大根ばかりを食べている気がする。今回は地元のみなさんにとてもお世話になったが、この大根など予想外のものでありがたいとしかいいようがない。今回いただいた大根はなんと2㎏以上の大大根である。地元では煮崩れないので「おでん大根」というらしい。ずんどうで直径が15cm前後もある。表面は泥で汚れているようだったので、タワシでこすったが一向に取れない。染みついているようなのだ。今どきこんな大大根はスーパーで売っていても、牛乳パック2本分の重さでは誰も買わないだろう。
新暦の初午の日は2月6日、二の午は2月18日である。南会津、午の日に行われる行事に欠かせない郷土料理「つむづかり」の、材料の主役は大根である。福島県会津地方でも南会津町は山の中であり、雪深いところであるが、「つむづかり」の大根はこの時季、雪の積もる前に収穫して保存して置いたものを使う。その雪の下の大根を、二の午の日に、岩下の『みどりや』さんに分けてもらって来た。原産地のわからない大根の、国内への移入時期は非常に古い。歴史時代以前からある。寒冷なところでも作れる。歩留まりがよく、生でも食べられるし、煮ておいしいなど、これほど優れた野菜は他にはない。歴史のある野菜なので、その土地土地で生まれた品種が無数にある。今でも地方に行くと日本各地に在来種が散らばっていて、買うのが楽しみである。土地土地の在来種を手に入ると、大根という野菜の奥深さを感じずにはいられない。東京都内では、最近、愛知系のF1ばかりで在来種はなかなか手に入らない。F1がダメだというわけでないが、程よい大きさで、あくが少なく、筋がなく均質な、今どきの大根ばかりを食べている気がする。今回は地元のみなさんにとてもお世話になったが、この大根など予想外のものでありがたいとしかいいようがない。今回いただいた大根はなんと2㎏以上の大大根である。地元では煮崩れないので「おでん大根」というらしい。ずんどうで直径が15cm前後もある。表面は泥で汚れているようだったので、タワシでこすったが一向に取れない。染みついているようなのだ。今どきこんな大大根はスーパーで売っていても、牛乳パック2本分の重さでは誰も買わないだろう。 2025年2月18日、深夜2時前に我が家を出発して、那須塩原までは順調な旅であった。問題は南会津町に入ってからで、雪道の運転に緊張しっぱなし。岩下で最低限の目的を果たして、1泊旅を日帰り旅に変更、せめて只見までと思ったのが大間違いだった。両脇は雪の壁だし、北上するにしたがい雪の壁がずんずん高くなるし。只見駅の手前、融雪パイプが途切れたところで除雪車とトラックの間に挟まれ、立ち往生したところで旅を終えることにする。開いている店がなく、外食できそうな店もない。だいたい店などの入り口がわからない。せめてもと思っていた旧伊南村にある山田ストアーの稲荷ずしもこの雪のためになかった。ここでトンカツなど惣菜を買って撤退する。帰宅するや、体のふしぶしが痛み、そのままダウン。翌日は朝寝坊して山田ストアーのトンカツを使って、ソースかつ丼を作る。トンカツはフッ素加工のフライパンでゆっくり温める。ウスターソース・ケチャップ・砂糖でいちばん簡単なソースを作る。チンしたご飯に、水さらししないでそのままのキャベツのせん切りを乗せる。温めたトンカツを食べやすく切り、ソースをたっぷりかけ回す。このいい加減に作ったソースかつ丼が意外にうまい。南会津の旅にもならなかった旅を思いだして、また行くぞ! と独りごちてまた眠る。
2025年2月18日、深夜2時前に我が家を出発して、那須塩原までは順調な旅であった。問題は南会津町に入ってからで、雪道の運転に緊張しっぱなし。岩下で最低限の目的を果たして、1泊旅を日帰り旅に変更、せめて只見までと思ったのが大間違いだった。両脇は雪の壁だし、北上するにしたがい雪の壁がずんずん高くなるし。只見駅の手前、融雪パイプが途切れたところで除雪車とトラックの間に挟まれ、立ち往生したところで旅を終えることにする。開いている店がなく、外食できそうな店もない。だいたい店などの入り口がわからない。せめてもと思っていた旧伊南村にある山田ストアーの稲荷ずしもこの雪のためになかった。ここでトンカツなど惣菜を買って撤退する。帰宅するや、体のふしぶしが痛み、そのままダウン。翌日は朝寝坊して山田ストアーのトンカツを使って、ソースかつ丼を作る。トンカツはフッ素加工のフライパンでゆっくり温める。ウスターソース・ケチャップ・砂糖でいちばん簡単なソースを作る。チンしたご飯に、水さらししないでそのままのキャベツのせん切りを乗せる。温めたトンカツを食べやすく切り、ソースをたっぷりかけ回す。このいい加減に作ったソースかつ丼が意外にうまい。南会津の旅にもならなかった旅を思いだして、また行くぞ! と独りごちてまた眠る。 待つのが仕事のような出稼ぎのとき、熱海にいるのはとてもありがたい。熱海には、もちろん知名度の高い、観光客が群れるような店もあるけれど、地元の人がこっそり食べる、そんな店もある。熱海の魅力は表面だけではわからない。地元の方に教わった初めても店だけど、地元の人が通う店で、ご飯お代わり、はしなかった。
待つのが仕事のような出稼ぎのとき、熱海にいるのはとてもありがたい。熱海には、もちろん知名度の高い、観光客が群れるような店もあるけれど、地元の人がこっそり食べる、そんな店もある。熱海の魅力は表面だけではわからない。地元の方に教わった初めても店だけど、地元の人が通う店で、ご飯お代わり、はしなかった。 天然キノコに関してはまったくの門外漢だけど、ときどき買ってみたくなる。新潟県妙高市新井の朝市にあったのは、瓶入りの「やぶたけ」というキノコだ。瓶入りの中身を見て、どこかで見た事があると思ったけど思い出せない。それなりの値段なので、思案していたら、「ナラタケだよ、おいしいよ」と教わって買って来る。別にナラタケの味を知っているわけでもないのに。
天然キノコに関してはまったくの門外漢だけど、ときどき買ってみたくなる。新潟県妙高市新井の朝市にあったのは、瓶入りの「やぶたけ」というキノコだ。瓶入りの中身を見て、どこかで見た事があると思ったけど思い出せない。それなりの値段なので、思案していたら、「ナラタケだよ、おいしいよ」と教わって買って来る。別にナラタケの味を知っているわけでもないのに。 昆布巻きと言っても漬物で、にんじんやごぼう、大根やなすを昆布で巻いて、みそ漬けにしたものだ。新潟県妙高市『太田醸造』のオリジナルのものかと思ったら、妙高市新井、上越市高田の朝市でも売られていた。こんなに手の込んだ、みそ漬けを作るのは上越地方ならではなのかも。切ってみるときれいな断面が出る。なんて美しいんだろうと感心していると、昆布が長すぎて食べられない。食べにくいといってもいいだろう。
昆布巻きと言っても漬物で、にんじんやごぼう、大根やなすを昆布で巻いて、みそ漬けにしたものだ。新潟県妙高市『太田醸造』のオリジナルのものかと思ったら、妙高市新井、上越市高田の朝市でも売られていた。こんなに手の込んだ、みそ漬けを作るのは上越地方ならではなのかも。切ってみるときれいな断面が出る。なんて美しいんだろうと感心していると、昆布が長すぎて食べられない。食べにくいといってもいいだろう。 新潟旅といっても帰り道の、だ。妙高高原のスーパーで凄く元気なバアチャンに会った。人が歩かないところにはボクのへそあたりまで雪が積もっている。「歩いてきたんですか?」と聞いたら、「こんくらいの雪なら歩く歩く」と言わた。高速に乗って一般道から離れようとしていた気持ちが、そのまま一般道という気持ちに変わる。「峠越えて行きなさいよ(以上総て意訳)」どれが峠なのかわからないまま、峠を超えたら同じスーパーがあって、帰宅時間を考えてすぐに食べられるものを買った。そこで見つけたのが「一茶納豆」である。このスーパーのある長野県信濃町のものか、と思ったら長野市のものだった。
新潟旅といっても帰り道の、だ。妙高高原のスーパーで凄く元気なバアチャンに会った。人が歩かないところにはボクのへそあたりまで雪が積もっている。「歩いてきたんですか?」と聞いたら、「こんくらいの雪なら歩く歩く」と言わた。高速に乗って一般道から離れようとしていた気持ちが、そのまま一般道という気持ちに変わる。「峠越えて行きなさいよ(以上総て意訳)」どれが峠なのかわからないまま、峠を超えたら同じスーパーがあって、帰宅時間を考えてすぐに食べられるものを買った。そこで見つけたのが「一茶納豆」である。このスーパーのある長野県信濃町のものか、と思ったら長野市のものだった。 ボクの旅は目的以外は行き当たりばったりで、下調べはしない主義、なのである。2024年12月27日、一印上越魚市場サメ競売の日は午前2時半には吹きさらしの市場にいて、それから5時間場内を右往左往する。あまりにも発見が多くて知識が脳から噴き出しそうになったので、テキスト化する。それから高田の朝市に向かい、雪の舞う中買い物をする。直江津まで戻り、直売所に行き、スーパー2軒を回ったところ、大きな交差点手前に食堂のような赤い派手な店を発見した。車の時計は11時半となっている。次の約束が1時だなと考えたら、腹の虫が鳴く。なんと18時間近く水しか飲んでいない。夜明け前からしゃべって、メモして、テキスト化して、考えて、だ。駐車スペースがない、と思っていたら一台出た。つられてそこに車を入れる。チェーン店では食べない、と決めているが、明らかに違う気がする。
ボクの旅は目的以外は行き当たりばったりで、下調べはしない主義、なのである。2024年12月27日、一印上越魚市場サメ競売の日は午前2時半には吹きさらしの市場にいて、それから5時間場内を右往左往する。あまりにも発見が多くて知識が脳から噴き出しそうになったので、テキスト化する。それから高田の朝市に向かい、雪の舞う中買い物をする。直江津まで戻り、直売所に行き、スーパー2軒を回ったところ、大きな交差点手前に食堂のような赤い派手な店を発見した。車の時計は11時半となっている。次の約束が1時だなと考えたら、腹の虫が鳴く。なんと18時間近く水しか飲んでいない。夜明け前からしゃべって、メモして、テキスト化して、考えて、だ。駐車スペースがない、と思っていたら一台出た。つられてそこに車を入れる。チェーン店では食べない、と決めているが、明らかに違う気がする。 高田城からとぼとぼ歩き始めたら、遠くの方でどーーーんがどーん、と凄い音がした。木がバキバキ折れるような音までする。そのときまだボクはこの冬の雷の怖さを知らなかったのだ。雷が近づいてきているな、と思った途端、歩道に白いものが点々と弾ける。点々とだったのはほんの少しだけで、どどどざざざと大きな氷の塊が頭を叩く。大急ぎで車にもどり傘を差したときにはずぶ濡れだった。
高田城からとぼとぼ歩き始めたら、遠くの方でどーーーんがどーん、と凄い音がした。木がバキバキ折れるような音までする。そのときまだボクはこの冬の雷の怖さを知らなかったのだ。雷が近づいてきているな、と思った途端、歩道に白いものが点々と弾ける。点々とだったのはほんの少しだけで、どどどざざざと大きな氷の塊が頭を叩く。大急ぎで車にもどり傘を差したときにはずぶ濡れだった。 ボクの生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の家の食卓には必ず、「しょいのみ(ひしお)」が置かれていた。よく「しょいのみばっかりでご飯食べたらいかんでぇ」と言われたものである。好きなので、旅に出ると必ず「しょうゆのみ」を探す。
ボクの生まれた徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の家の食卓には必ず、「しょいのみ(ひしお)」が置かれていた。よく「しょいのみばっかりでご飯食べたらいかんでぇ」と言われたものである。好きなので、旅に出ると必ず「しょうゆのみ」を探す。 新潟県妙高市は人口3万人弱、海がなく、北国街道ぞいの宿場町だったところだ。日本海から信濃に向かい標高の高い山々の入り口に当たる。そのまま北国街道を南下すると妙高高原、長野県に入り、一茶で有名な信濃町、飯綱町になる。
新潟県妙高市は人口3万人弱、海がなく、北国街道ぞいの宿場町だったところだ。日本海から信濃に向かい標高の高い山々の入り口に当たる。そのまま北国街道を南下すると妙高高原、長野県に入り、一茶で有名な信濃町、飯綱町になる。 今回の新潟県妙高市・上越市の旅で残念だったのは朝市の、どら焼きが買えなかったこと。妙高市新井の朝市で行列ができていたので、上越市高田の朝市で買おうと思ったのが大失敗だった。高田の朝市には、どら焼きの屋台がなかったのだ。何軒かあったどら焼きの店が、減っているらしい。どら焼きといっても、どちらかというと今川焼きそっくりで、ともえ型のくぼみがある。銅鑼を鳴らすの銅鑼に似ているから、だという人もいる。
今回の新潟県妙高市・上越市の旅で残念だったのは朝市の、どら焼きが買えなかったこと。妙高市新井の朝市で行列ができていたので、上越市高田の朝市で買おうと思ったのが大失敗だった。高田の朝市には、どら焼きの屋台がなかったのだ。何軒かあったどら焼きの店が、減っているらしい。どら焼きといっても、どちらかというと今川焼きそっくりで、ともえ型のくぼみがある。銅鑼を鳴らすの銅鑼に似ているから、だという人もいる。 天保13年(1842)の江戸三座、浅草聖天町移転とか、中村勘三郎家についてとか、江戸時代の文化、食文化の完成期の書籍を読んでいる。読むだけでは理解できないので、近ければ実際に歩いてみるのがボク流。猿若町の中程に立って、聖天町(猿若町)が山谷堀に近いこと、新吉原にも近いこと、江戸三座、浄瑠璃などの小屋があった時代の名残はみじんも残っていないこと、などを見た。これじゃ、お貞ちゃん(おていちゃんで、沢村貞子の貞子は「ていこ」)がひょっこり現れる、なんて想像できない。それにしても戦前の軍部も政治家も、現在のプーチンと同じ、アホとしかいいようがない。せっかくなのでお昼を猿若町で食べようと、酒屋のオヤジサンに教わったのが、中村座跡にある洋食『いいま』だ。素直に開店まで待って、自分がいちばん食べたいトンカツを食べて帰ってきた。ボクの外食や買い物はいつも、なりゆき、なのだ。酒屋のオヤジサンと同じ、さしすせそのない人たちの会話が飛び交っているのがいい。飲みごろ温度の生ビールがすこぶるつきにうまい。これは三ノ輪からジグザグに5キロ近く歩いたせい、だけではないとみたが違うかな。
天保13年(1842)の江戸三座、浅草聖天町移転とか、中村勘三郎家についてとか、江戸時代の文化、食文化の完成期の書籍を読んでいる。読むだけでは理解できないので、近ければ実際に歩いてみるのがボク流。猿若町の中程に立って、聖天町(猿若町)が山谷堀に近いこと、新吉原にも近いこと、江戸三座、浄瑠璃などの小屋があった時代の名残はみじんも残っていないこと、などを見た。これじゃ、お貞ちゃん(おていちゃんで、沢村貞子の貞子は「ていこ」)がひょっこり現れる、なんて想像できない。それにしても戦前の軍部も政治家も、現在のプーチンと同じ、アホとしかいいようがない。せっかくなのでお昼を猿若町で食べようと、酒屋のオヤジサンに教わったのが、中村座跡にある洋食『いいま』だ。素直に開店まで待って、自分がいちばん食べたいトンカツを食べて帰ってきた。ボクの外食や買い物はいつも、なりゆき、なのだ。酒屋のオヤジサンと同じ、さしすせそのない人たちの会話が飛び交っているのがいい。飲みごろ温度の生ビールがすこぶるつきにうまい。これは三ノ輪からジグザグに5キロ近く歩いたせい、だけではないとみたが違うかな。 今回の新潟県の旅は、朝市は楽しすぎる、ということも含めて書いていきたい。妙高市新井の朝市で、見つけたのが赤い「ふきのとう」だ。赤いのは雪の下に埋もれた状態だからだと思っているが、確かめたわけではない。ボクは極々田舎である徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)で育った。「ふきのとう」は上京するまで食べたことがなかった。吉野川を挟んで北側、美馬町(現美馬市)、親戚の家の、畑の斜面に毎年出るので、剪定バサミを持たされて取っていたものだが、我が家では食べた記憶がない。あまり山菜類を食べないのは、商家だったためか、それとも徳島県はあまり山菜類を食べないのか、今以てわからない。初めて食べたのはお茶の水駿河台、学校の隣の居酒屋で、だ。不思議な味だけどおいしいなと思ったものだが、3、4個しか皿にはなく、むしろ高い食い物だと思った印象の方が強い。この赤く硬い「ふきのとう」は、1月、2月に新潟でも群馬でも、関東周辺の直売所でも、必ずではないが高い確率で出合える。生のまま割ると非常に香りが強い。最近ではこの香りだけで元が取れたと思うし、いい匂いなのでぽわーんと、うっとりする。今回のものは、12月26日に買ったので、とても春のものと言えない。それでも春を感じるのは、完全に体が冬になっているためだろう。
今回の新潟県の旅は、朝市は楽しすぎる、ということも含めて書いていきたい。妙高市新井の朝市で、見つけたのが赤い「ふきのとう」だ。赤いのは雪の下に埋もれた状態だからだと思っているが、確かめたわけではない。ボクは極々田舎である徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)で育った。「ふきのとう」は上京するまで食べたことがなかった。吉野川を挟んで北側、美馬町(現美馬市)、親戚の家の、畑の斜面に毎年出るので、剪定バサミを持たされて取っていたものだが、我が家では食べた記憶がない。あまり山菜類を食べないのは、商家だったためか、それとも徳島県はあまり山菜類を食べないのか、今以てわからない。初めて食べたのはお茶の水駿河台、学校の隣の居酒屋で、だ。不思議な味だけどおいしいなと思ったものだが、3、4個しか皿にはなく、むしろ高い食い物だと思った印象の方が強い。この赤く硬い「ふきのとう」は、1月、2月に新潟でも群馬でも、関東周辺の直売所でも、必ずではないが高い確率で出合える。生のまま割ると非常に香りが強い。最近ではこの香りだけで元が取れたと思うし、いい匂いなのでぽわーんと、うっとりする。今回のものは、12月26日に買ったので、とても春のものと言えない。それでも春を感じるのは、完全に体が冬になっているためだろう。 旧西頸城郡西山、長嶺大池で白鳥を見ながら、考えたこと。新潟市周辺、旧蒲原郡は湖沼を「潟」という。この湖沼を「潟」と呼ぶ地域は新潟県、石川県、福井県である。潟は潟湖のことであり、潮の満ち干に影響される水域でもある。新潟市から長岡市方面・新発田市方面に車で走っているとき、ナビのない時代、土地の人はよく、「あそこの潟の手前を右に行け」だとか、「潟の向こう側」だとか、よそ者にはとんと見当のつかない道教えをしてくれたものだ。理解できないので聞き返すと、「潟は池だな」などを言う。大きな潟としては福島潟、鳥屋野潟などがある。旧蒲原郡は潟だらけというか、土地がなく潟ばっかりの地で、後に埋め立てて陸を作った。福島潟で話を聞くと1950年代くらいまで田んぼで胸までつかって田植えをしていたという。その内、排水が進み、埋め立てて膨大な耕作地を作って穀倉地帯になったが、それでも点々と地図にものならない潟が存在する。もちろん昔は現新潟市中心部にさえも土地はなく、埋め立てによって町が作り出されたのである。だから「新潟」なのだ。当然、旧蒲原郡には有力な国衆も大名もいなかった。これが。旧東頸城郡、柏崎市から西に来ると「潟」ではなく「池」になる。ここから旧頸城郡まではもともと陸地であり、湖沼は池として存在していたのだと思う。例えば柏崎市西山、長嶺大池である。途中、大潟村(現上越市)がある。ここは明らかに多くの潟があり、そこを総て埋め立てた地なのだと思う。この大潟のそばにあるのは「池」でしかない。その、もともと陸地だった現上越市、妙高市は信濃の国へ抜ける街道がある。上越市には越後の国も国府もあった。長尾景虎(上杉謙信)がここに割拠して、大きな軍を備えることが出来たのも、中世以来の荘園地であり、交通の要衝であったためだ。この荘園地の重要性は、『中世荘園の様相』(網野善彦 岩波文庫)に詳しい。ちなみに長尾家は守護代であり、明らかに中世の仕組みの中にある。長尾家が上杉家になったのは中世(ボクは勝手に12世紀後半から豊臣秀吉が天下を取るまでだと思っている)の仕組み上の一段上、足利家の名跡である上杉の名が欲しかったためだ。これは伊勢家が北条家(北条早雲の)に変わったのと同じだ。ここに上杉謙信の見通しのあまさが垣間見える。平安時代になると守護・地頭の地方統治時代は徐々に衰退する。むしろ国(律令制の行政区分)にもともと勢力を築いていた、運送業者のような地下や武士(源平藤橘ではなく)が統治するようになる。その先にあるのが長尾家なのだと思う。「池」という言語にも現上越・妙高が中世において越後の国の中でも重要なところであったことがわかる。
旧西頸城郡西山、長嶺大池で白鳥を見ながら、考えたこと。新潟市周辺、旧蒲原郡は湖沼を「潟」という。この湖沼を「潟」と呼ぶ地域は新潟県、石川県、福井県である。潟は潟湖のことであり、潮の満ち干に影響される水域でもある。新潟市から長岡市方面・新発田市方面に車で走っているとき、ナビのない時代、土地の人はよく、「あそこの潟の手前を右に行け」だとか、「潟の向こう側」だとか、よそ者にはとんと見当のつかない道教えをしてくれたものだ。理解できないので聞き返すと、「潟は池だな」などを言う。大きな潟としては福島潟、鳥屋野潟などがある。旧蒲原郡は潟だらけというか、土地がなく潟ばっかりの地で、後に埋め立てて陸を作った。福島潟で話を聞くと1950年代くらいまで田んぼで胸までつかって田植えをしていたという。その内、排水が進み、埋め立てて膨大な耕作地を作って穀倉地帯になったが、それでも点々と地図にものならない潟が存在する。もちろん昔は現新潟市中心部にさえも土地はなく、埋め立てによって町が作り出されたのである。だから「新潟」なのだ。当然、旧蒲原郡には有力な国衆も大名もいなかった。これが。旧東頸城郡、柏崎市から西に来ると「潟」ではなく「池」になる。ここから旧頸城郡まではもともと陸地であり、湖沼は池として存在していたのだと思う。例えば柏崎市西山、長嶺大池である。途中、大潟村(現上越市)がある。ここは明らかに多くの潟があり、そこを総て埋め立てた地なのだと思う。この大潟のそばにあるのは「池」でしかない。その、もともと陸地だった現上越市、妙高市は信濃の国へ抜ける街道がある。上越市には越後の国も国府もあった。長尾景虎(上杉謙信)がここに割拠して、大きな軍を備えることが出来たのも、中世以来の荘園地であり、交通の要衝であったためだ。この荘園地の重要性は、『中世荘園の様相』(網野善彦 岩波文庫)に詳しい。ちなみに長尾家は守護代であり、明らかに中世の仕組みの中にある。長尾家が上杉家になったのは中世(ボクは勝手に12世紀後半から豊臣秀吉が天下を取るまでだと思っている)の仕組み上の一段上、足利家の名跡である上杉の名が欲しかったためだ。これは伊勢家が北条家(北条早雲の)に変わったのと同じだ。ここに上杉謙信の見通しのあまさが垣間見える。平安時代になると守護・地頭の地方統治時代は徐々に衰退する。むしろ国(律令制の行政区分)にもともと勢力を築いていた、運送業者のような地下や武士(源平藤橘ではなく)が統治するようになる。その先にあるのが長尾家なのだと思う。「池」という言語にも現上越・妙高が中世において越後の国の中でも重要なところであったことがわかる。 今回の新潟県の旅で、朝市は楽しすぎる、ことをば書いていきたい。上越市高田の朝市、妙高市新井の朝市で、今回もまた買えてうれしかったものが、藤五郎という品種の梅で作った梅干しである。初めて新潟に行ったのは1980年代半ば、分水町(現燕市)、岩室(現新潟市)、新潟市などを車で回った。そのとき朝市で見つけた梅干しがボクの故郷徳島県西部のものでもなく、関西ものもでもない。一般的な梅干しとどこか少し違うものだった。同じようなものが山形県にもある。山形県の山間部で会った人が、普通の梅は寒いところには育たない。それでアンズやスモモと掛け合わせて、寒冷地用に作ったものだと話していたが、確かめていない。南高梅のように大型で、果肉が非常に柔らかく、酸味もやや弱い。比較的水分(梅酢)多めに作っているのも山形県山間部のものと似ている。梅干しが苦手なボクにも食べやすいので見つけると買っているが、今回、この藤五郎という品種で作った梅干しを売っていたのは1軒だけだった。夏にも新潟に行くので、また買ってきたいものだと思っているが、じょじょに作る人が減っているのかも知れぬ。
今回の新潟県の旅で、朝市は楽しすぎる、ことをば書いていきたい。上越市高田の朝市、妙高市新井の朝市で、今回もまた買えてうれしかったものが、藤五郎という品種の梅で作った梅干しである。初めて新潟に行ったのは1980年代半ば、分水町(現燕市)、岩室(現新潟市)、新潟市などを車で回った。そのとき朝市で見つけた梅干しがボクの故郷徳島県西部のものでもなく、関西ものもでもない。一般的な梅干しとどこか少し違うものだった。同じようなものが山形県にもある。山形県の山間部で会った人が、普通の梅は寒いところには育たない。それでアンズやスモモと掛け合わせて、寒冷地用に作ったものだと話していたが、確かめていない。南高梅のように大型で、果肉が非常に柔らかく、酸味もやや弱い。比較的水分(梅酢)多めに作っているのも山形県山間部のものと似ている。梅干しが苦手なボクにも食べやすいので見つけると買っているが、今回、この藤五郎という品種で作った梅干しを売っていたのは1軒だけだった。夏にも新潟に行くので、また買ってきたいものだと思っているが、じょじょに作る人が減っているのかも知れぬ。 天保13年(1842)、徳川幕府は、それまで堺町、葺屋町(東京都中央区人形町)、木挽町にあった中村座、市村座、薩摩座(浄瑠璃)、結城座(浄瑠璃)を浅草聖天町に移転させる。後に河原崎座が移転してきたことで江戸三座が並び立った。このとき聖天町から猿若町に町名が変更されたのだ。「猿若」は、猿若勘三郎(中村勘三郎)にちなむ。猿若勘三郎は1924年、江戸で最初の常設の芝居小屋である「猿若座」を作る。江戸歌舞伎の始まりは狂言師であった猿若勘三郎が京から江戸に流れ着き、江戸に座を作ったことに始まるのだ。テレビでしか歌舞伎を見た事のないボクがいうのも変だけど、歌舞伎の演目が狂言と呼ばれること、歌舞伎には舞、長唄など多彩な面があるのも、猿若勘三郎の流れかも。余談になるが、中村勘三郎家は江戸時代、歌舞伎俳優でもあり、座主でもあり、興行師でもあった。市川團十郎や中村仲蔵、大阪の中村鴈治郎とはまったく違う、特異な存在である。天保期、江戸三座の廃止をもくろんだ水野忠邦を押しとどめて、移転させたので有名なのが、遠山景元(遠山金四郎)だとされている。江戸の街にあった最大級の娯楽施設の移転先に、この待乳山聖天に隣接する地が選ばれたのか?そのボクなりの答えが、全然無関係な、沢村貞子の『私の浅草』を読んでいていきなり整理整頓された。浅草→浅草寺→(新)吉原→江戸三座→魚屋(魚河岸、漁港)だ。沢村貞子が加東大介(ボクが子供の頃とても人気があった)が育った町、猿若町に江戸の食文化を考えるヒントがあったのだ。念のために沢村貞子は林芙美子、武田百合子と並ぶ、文章の達人である。この待乳山聖天から猿若町にかけて、魚屋や淡水魚を売る店が多かったのではないか、と。
天保13年(1842)、徳川幕府は、それまで堺町、葺屋町(東京都中央区人形町)、木挽町にあった中村座、市村座、薩摩座(浄瑠璃)、結城座(浄瑠璃)を浅草聖天町に移転させる。後に河原崎座が移転してきたことで江戸三座が並び立った。このとき聖天町から猿若町に町名が変更されたのだ。「猿若」は、猿若勘三郎(中村勘三郎)にちなむ。猿若勘三郎は1924年、江戸で最初の常設の芝居小屋である「猿若座」を作る。江戸歌舞伎の始まりは狂言師であった猿若勘三郎が京から江戸に流れ着き、江戸に座を作ったことに始まるのだ。テレビでしか歌舞伎を見た事のないボクがいうのも変だけど、歌舞伎の演目が狂言と呼ばれること、歌舞伎には舞、長唄など多彩な面があるのも、猿若勘三郎の流れかも。余談になるが、中村勘三郎家は江戸時代、歌舞伎俳優でもあり、座主でもあり、興行師でもあった。市川團十郎や中村仲蔵、大阪の中村鴈治郎とはまったく違う、特異な存在である。天保期、江戸三座の廃止をもくろんだ水野忠邦を押しとどめて、移転させたので有名なのが、遠山景元(遠山金四郎)だとされている。江戸の街にあった最大級の娯楽施設の移転先に、この待乳山聖天に隣接する地が選ばれたのか?そのボクなりの答えが、全然無関係な、沢村貞子の『私の浅草』を読んでいていきなり整理整頓された。浅草→浅草寺→(新)吉原→江戸三座→魚屋(魚河岸、漁港)だ。沢村貞子が加東大介(ボクが子供の頃とても人気があった)が育った町、猿若町に江戸の食文化を考えるヒントがあったのだ。念のために沢村貞子は林芙美子、武田百合子と並ぶ、文章の達人である。この待乳山聖天から猿若町にかけて、魚屋や淡水魚を売る店が多かったのではないか、と。 関西ではよく見かけるものだし、種子が売られているので関東の直売所にも日野菜の漬物はある。また日野菜自体も売っている。それでも関東で日野菜を買おうとは思わない。我がデータを見る限りでも関西でも青果を京都市内で一回買っているだけで、ほぼ滋賀県内で買い求めている。しかも漬物は、近江八幡市、野洲市、草津市と南部地域がほとんどで、北部では安曇川で青果を一度買っているだけだ。日野菜は基本的に発祥の地、日野町周辺の滋賀県南部のものなのだろうか。この日野菜にも南北滋賀県内の違いを見た気がしてきた。
関西ではよく見かけるものだし、種子が売られているので関東の直売所にも日野菜の漬物はある。また日野菜自体も売っている。それでも関東で日野菜を買おうとは思わない。我がデータを見る限りでも関西でも青果を京都市内で一回買っているだけで、ほぼ滋賀県内で買い求めている。しかも漬物は、近江八幡市、野洲市、草津市と南部地域がほとんどで、北部では安曇川で青果を一度買っているだけだ。日野菜は基本的に発祥の地、日野町周辺の滋賀県南部のものなのだろうか。この日野菜にも南北滋賀県内の違いを見た気がしてきた。 関西(滋賀県・三重県北部・京都府南部・大阪府北部)に行って見つけると買ってしまうもののひとつが「赤こんにゃく」だ。スーパーなどにあれば買うけど、そんなに気にしているわけでもない。滋賀県名物で、近江八幡市が発祥らしい。近江の有名人、豊臣秀次とか、織田信長とかの伝説があって、なぜ赤なのか? なぜ弁柄をいれたのか? が語られるが、だれでも作りそうなわかりやすい嘘ばかりだと思っている。こんにゃくが一般的になるのは18世紀からで、普通の食品となったのも18世紀からではないか? と考えているからだ。さて、その歴史はいかがわしいものの味はいい。赤い色素である弁柄の味は感じられるような、感じられないような。この滋賀県に展開するスーパー、平和堂で買った近江八幡市の『乃利松』のものは取り分けよくみる。他のメーカーと比較するほど食べていないが、とてもおいしい赤こんにゃくだと思っている。
関西(滋賀県・三重県北部・京都府南部・大阪府北部)に行って見つけると買ってしまうもののひとつが「赤こんにゃく」だ。スーパーなどにあれば買うけど、そんなに気にしているわけでもない。滋賀県名物で、近江八幡市が発祥らしい。近江の有名人、豊臣秀次とか、織田信長とかの伝説があって、なぜ赤なのか? なぜ弁柄をいれたのか? が語られるが、だれでも作りそうなわかりやすい嘘ばかりだと思っている。こんにゃくが一般的になるのは18世紀からで、普通の食品となったのも18世紀からではないか? と考えているからだ。さて、その歴史はいかがわしいものの味はいい。赤い色素である弁柄の味は感じられるような、感じられないような。この滋賀県に展開するスーパー、平和堂で買った近江八幡市の『乃利松』のものは取り分けよくみる。他のメーカーと比較するほど食べていないが、とてもおいしい赤こんにゃくだと思っている。 下町という言語はいつから世間に流布したのか? 東京都内を飛び出して全国的な言語になったのか?1963年の映画『下町の太陽』からだと思っている。本来、下町とは小林信彦が述べているように中央区を指す言葉だった。この3区で、隅田川両国橋の西の「両国(本来の両国のことで現在の両国は葛飾。現東日本橋たり)」という地名が消えたために、最も下町だった中央区が下町でなくなる。そして、もっとも一般人の下町感を変えたのは映画だ。映画によって下町は東へ、東へと広がり、移動していく。映画『下町の太陽』で隅田川を越える。『男はつらいよ』(1970)で荒川・中川も越えたことを明確化する。考えて見ると、渥美清の台詞に「私、生まれも育ちも葛飾柴又です」があったはずで、主人公は葛飾在と言っているのに、下町の代表になる。蛇足だけど、『下町の太陽』は、あまりにも倍賞千恵子が可憐かつ美しすぎて、ほかの俳優は2度も見たのにぜんぜん記憶に残っていない。取り分け勝呂誉などいなくてもよかったかも。京成の路線図を見ていると、山田洋次(1931〜)の社会学的意味は大きい。
下町という言語はいつから世間に流布したのか? 東京都内を飛び出して全国的な言語になったのか?1963年の映画『下町の太陽』からだと思っている。本来、下町とは小林信彦が述べているように中央区を指す言葉だった。この3区で、隅田川両国橋の西の「両国(本来の両国のことで現在の両国は葛飾。現東日本橋たり)」という地名が消えたために、最も下町だった中央区が下町でなくなる。そして、もっとも一般人の下町感を変えたのは映画だ。映画によって下町は東へ、東へと広がり、移動していく。映画『下町の太陽』で隅田川を越える。『男はつらいよ』(1970)で荒川・中川も越えたことを明確化する。考えて見ると、渥美清の台詞に「私、生まれも育ちも葛飾柴又です」があったはずで、主人公は葛飾在と言っているのに、下町の代表になる。蛇足だけど、『下町の太陽』は、あまりにも倍賞千恵子が可憐かつ美しすぎて、ほかの俳優は2度も見たのにぜんぜん記憶に残っていない。取り分け勝呂誉などいなくてもよかったかも。京成の路線図を見ていると、山田洋次(1931〜)の社会学的意味は大きい。 『木皿食堂』に熱中している。ベッドでは、曲亭馬琴やベルツの世界にいないといけないし、ちょっとだけ平安時代なのに、読んではいけない禁断の世界に落ち込んでしまっている。著者の女鹿年季子は神戸在住で、ポークチャップ(ポークチョップ)を食べているときのことが出ている。これだけでも今どきの、人ではないことがわかる。「ポークチャップ」は昔、2つの顔を持つ尼崎(兵庫県尼崎市)のざわざわした方の食堂で一度だけ食べている。ついで書いておくが、尼崎はこのざわざわした阪神めいた南の方が、パルナスの喫茶店もあるし(今もあるかわからないけど)、で好きだ。商店街に阪神の歌(たぶん)ががんがんに流れて、マジック70とかあって意味不明なところもいいし、オバチャン、オッチャン、バアチャン、ジイチャンの野球帽比率が高いのもすごい。商店街にあるへんな物体を眺めていると、肩に抱きついてきたオッチャンに、「旅の人でっか?」と聞かれてうなずくと、「阪神タイガースは大阪ちゃいます、尼崎です(ともに意訳)」とか、言われて、ビックリして逃げたことがあるのも、南の尼崎の魅力だろう。閑話休題。おいしいかったのか、といったら「?」だった。どこかしらもの足りない思いしかボクの脳みそには残っていない。たぶんこの料理、関西では普通だけど、関東にはない、のではないか? とすると関西発祥(大げさだけど)かもしれない。味はケチャップそのものだった気がする。ケチャップを使っているだけでオシャレ、といった時代があったんだと思う。
『木皿食堂』に熱中している。ベッドでは、曲亭馬琴やベルツの世界にいないといけないし、ちょっとだけ平安時代なのに、読んではいけない禁断の世界に落ち込んでしまっている。著者の女鹿年季子は神戸在住で、ポークチャップ(ポークチョップ)を食べているときのことが出ている。これだけでも今どきの、人ではないことがわかる。「ポークチャップ」は昔、2つの顔を持つ尼崎(兵庫県尼崎市)のざわざわした方の食堂で一度だけ食べている。ついで書いておくが、尼崎はこのざわざわした阪神めいた南の方が、パルナスの喫茶店もあるし(今もあるかわからないけど)、で好きだ。商店街に阪神の歌(たぶん)ががんがんに流れて、マジック70とかあって意味不明なところもいいし、オバチャン、オッチャン、バアチャン、ジイチャンの野球帽比率が高いのもすごい。商店街にあるへんな物体を眺めていると、肩に抱きついてきたオッチャンに、「旅の人でっか?」と聞かれてうなずくと、「阪神タイガースは大阪ちゃいます、尼崎です(ともに意訳)」とか、言われて、ビックリして逃げたことがあるのも、南の尼崎の魅力だろう。閑話休題。おいしいかったのか、といったら「?」だった。どこかしらもの足りない思いしかボクの脳みそには残っていない。たぶんこの料理、関西では普通だけど、関東にはない、のではないか? とすると関西発祥(大げさだけど)かもしれない。味はケチャップそのものだった気がする。ケチャップを使っているだけでオシャレ、といった時代があったんだと思う。 北海道根室市で買った「ラワンぶき」と青森県の名品、イゲタの焼き竹輪を煮合わせてみた。「ラワンぶき」はとても柔らかく、ちゃんとフキらしい味がする。イゲタの竹輪のうま味を染み染みさせて実にうまい。北海道では必ずフキの水煮を買ってきているが、買わないと忘れ物をしたような気分になる。それほどおいしい食材だと思っている。
北海道根室市で買った「ラワンぶき」と青森県の名品、イゲタの焼き竹輪を煮合わせてみた。「ラワンぶき」はとても柔らかく、ちゃんとフキらしい味がする。イゲタの竹輪のうま味を染み染みさせて実にうまい。北海道では必ずフキの水煮を買ってきているが、買わないと忘れ物をしたような気分になる。それほどおいしい食材だと思っている。 市場魚貝類図鑑は複雑な要素で出来上がっているがとりとめもなく……。わがサイトが目指すところはぼんやりとしたものだけど、食のぐるりの総まとめだ。伝統、季節、自然がとても重要だと考えている。だからできるだけ1970年という破壊年以前を感じるものを集めている。生物や料理もそうだが、周りのもの、例えば器もそうだ。駒場東大前の『べにや民芸店』の池本惣一さんの器に興奮してしまった。それまでも何度も写真では見てきたが、写真ではわからない何か? にびっくりしたのだ。そこにあるのは「朝鮮の風」のようなもの。『べにや民藝店』のリョウさんの写真というコマセに誘われて、ボクは小アジちゃんのように欲しいものを欲しいだけ買い求めてきた。池本惣一さんは愛媛県砥部町の人だけど、四国には多くの朝鮮文化が残っている。これなどは九州と同じである。器を見ていて、同じ四国生まれのボクの中に「朝鮮の風」が吹いている、と感じた。歴史考古学の世界からも日本列島には台湾経由でたどりついたヒト、ユーラシア大陸から来たヒト、そして比較的新しく紀元後に朝鮮半島から来たヒトがいる。原始ではなく日本列島の古代文化史は朝鮮半島からのヒトによって多くが築かれ、そして戦国時代に朝鮮半島の陶工が来たことによって陶磁の世界が急激に進化する。戦国大名が朝鮮半島の陶工を連れ帰ったのも、自らの朝鮮への憧れと、「朝鮮の風」を感じたためだ。同じように柳宗悦も明らかに自分の中の「朝鮮の風」を感じた。これも民藝運動という帆船の風だと思う。ボクは、からっちゃの息子なので、器に強く惹かれて惑溺してしまう。今回も新たな器を収納していて食器棚が壊れる。壊れるくらい買うなよ、とは思わない。
市場魚貝類図鑑は複雑な要素で出来上がっているがとりとめもなく……。わがサイトが目指すところはぼんやりとしたものだけど、食のぐるりの総まとめだ。伝統、季節、自然がとても重要だと考えている。だからできるだけ1970年という破壊年以前を感じるものを集めている。生物や料理もそうだが、周りのもの、例えば器もそうだ。駒場東大前の『べにや民芸店』の池本惣一さんの器に興奮してしまった。それまでも何度も写真では見てきたが、写真ではわからない何か? にびっくりしたのだ。そこにあるのは「朝鮮の風」のようなもの。『べにや民藝店』のリョウさんの写真というコマセに誘われて、ボクは小アジちゃんのように欲しいものを欲しいだけ買い求めてきた。池本惣一さんは愛媛県砥部町の人だけど、四国には多くの朝鮮文化が残っている。これなどは九州と同じである。器を見ていて、同じ四国生まれのボクの中に「朝鮮の風」が吹いている、と感じた。歴史考古学の世界からも日本列島には台湾経由でたどりついたヒト、ユーラシア大陸から来たヒト、そして比較的新しく紀元後に朝鮮半島から来たヒトがいる。原始ではなく日本列島の古代文化史は朝鮮半島からのヒトによって多くが築かれ、そして戦国時代に朝鮮半島の陶工が来たことによって陶磁の世界が急激に進化する。戦国大名が朝鮮半島の陶工を連れ帰ったのも、自らの朝鮮への憧れと、「朝鮮の風」を感じたためだ。同じように柳宗悦も明らかに自分の中の「朝鮮の風」を感じた。これも民藝運動という帆船の風だと思う。ボクは、からっちゃの息子なので、器に強く惹かれて惑溺してしまう。今回も新たな器を収納していて食器棚が壊れる。壊れるくらい買うなよ、とは思わない。 関東の醤油醸造は17世紀に銚子で初まり、土浦(土屋家で、茨城県土浦市)でも作られる。この時代、江戸のハイウェーである利根川、江戸川、新川、小名木川が機能し始めていたときである。一代目、市川段十郎(後に團十郎 1660-1704)は両親の里である成田まで、このハイウェーを利用して日本橋、行徳、松戸、関宿、佐原まで舟運で行く。銚子、土浦の醤油もこれとは反対だけど輸送経路は変わらない。ただしこの時代、利根川と江戸川には難所があった。関宿である。室町時代かずかずの戦乱の場となった地ではあるが、川砂がたまりやすく舟運に支障が出た。次ぎに醤油の産地となったのが関宿を通らなくても済む、江戸川沿いの野田である。豊かな水があり、関東で作られた大豆と醤油を集めるのもたやすかった。今や国内随一の醤油の産地だ。この利根川、江戸川で盛んに作られた醤油と流山市のみりんが江戸前ウナギを完成に導いたのだ。こんなことを思いながら野田の町を歩き、せっかくなので蒲鉾店のオネエサンに教わった町ウナギで贅沢をする。「有名じゃないと思いますけど」というのでゆっくり昼過ぎに行ったらテーブル席はいっぱいだった。座敷に上がり、まずはノンアルコールビールと「コイの洗い」をお願いする。関東平野のウナギ屋の特徴は必ず「コイの洗い」があること。またざっこ煮(煮ざっこ)があることも特徴である。久しぶりのコイの洗いがやたらにうまい。
関東の醤油醸造は17世紀に銚子で初まり、土浦(土屋家で、茨城県土浦市)でも作られる。この時代、江戸のハイウェーである利根川、江戸川、新川、小名木川が機能し始めていたときである。一代目、市川段十郎(後に團十郎 1660-1704)は両親の里である成田まで、このハイウェーを利用して日本橋、行徳、松戸、関宿、佐原まで舟運で行く。銚子、土浦の醤油もこれとは反対だけど輸送経路は変わらない。ただしこの時代、利根川と江戸川には難所があった。関宿である。室町時代かずかずの戦乱の場となった地ではあるが、川砂がたまりやすく舟運に支障が出た。次ぎに醤油の産地となったのが関宿を通らなくても済む、江戸川沿いの野田である。豊かな水があり、関東で作られた大豆と醤油を集めるのもたやすかった。今や国内随一の醤油の産地だ。この利根川、江戸川で盛んに作られた醤油と流山市のみりんが江戸前ウナギを完成に導いたのだ。こんなことを思いながら野田の町を歩き、せっかくなので蒲鉾店のオネエサンに教わった町ウナギで贅沢をする。「有名じゃないと思いますけど」というのでゆっくり昼過ぎに行ったらテーブル席はいっぱいだった。座敷に上がり、まずはノンアルコールビールと「コイの洗い」をお願いする。関東平野のウナギ屋の特徴は必ず「コイの洗い」があること。またざっこ煮(煮ざっこ)があることも特徴である。久しぶりのコイの洗いがやたらにうまい。 奈良県十津川村平谷、『ふくおか』から「番茶」を取り寄せた。取り寄せは、よほどのことがないとやらないので異例だ。同村の松寶純子さんがチャノキの葉をやや野性的につみ、よくよく揉んで作ったものだ。十津川を縦断したのはサンマのことを調べるためだ。国内でもっとも早くからサンマを流通させたのは熊野(三重県・和歌山県)と奈良県、後に畿内、美濃である。サンマの歴史にとってもっとも重要な地域と言えるだろう。そんな旅の途中、小さなスーパーというかコンビニのような店、『ふくおか』で見つけたのがこのお茶である。
奈良県十津川村平谷、『ふくおか』から「番茶」を取り寄せた。取り寄せは、よほどのことがないとやらないので異例だ。同村の松寶純子さんがチャノキの葉をやや野性的につみ、よくよく揉んで作ったものだ。十津川を縦断したのはサンマのことを調べるためだ。国内でもっとも早くからサンマを流通させたのは熊野(三重県・和歌山県)と奈良県、後に畿内、美濃である。サンマの歴史にとってもっとも重要な地域と言えるだろう。そんな旅の途中、小さなスーパーというかコンビニのような店、『ふくおか』で見つけたのがこのお茶である。 食器に限りなく惹かれるのは、ボクが「からっちゃ(唐津屋)」に生まれたからだ。食器店のことを東日本で瀬戸物屋、西日本で唐津屋と呼んだ言語の地方性が失われて久しいのは残念でならない。相馬市内を歩いていて、「相馬焼」の文字に惹かれて食器店に吸い込まれた。
食器に限りなく惹かれるのは、ボクが「からっちゃ(唐津屋)」に生まれたからだ。食器店のことを東日本で瀬戸物屋、西日本で唐津屋と呼んだ言語の地方性が失われて久しいのは残念でならない。相馬市内を歩いていて、「相馬焼」の文字に惹かれて食器店に吸い込まれた。 鼻水攻撃で1日棒に振り、貴重な時間が消えてなくなる。今年もなんの収穫もなしに過ぎていくんだろうなと思いながら、埼玉県川島町、大河戸製麺の太焼きそば麺で焼きそばを作る。ときどき焼きそばを無性に食べたくなるボクだけど、今年になって、ずーっと「あとがけ」である。「あとがけ焼きそば」は山形県酒田市の名物でもあるが、調理の途中、ソースをからめ、ソースを焦がすという工程がない。味つけはテーブルのソースで好きにやってくれ、といった投げやりさが逆にいい。ソースをかけすぎると大変なことになるが、自己責任なので、文句のいいようがない。いろいろ上にのってゴージャスだったが、逆に麺は平凡だった。焼きそばとか、お好み焼きとかは明らかに1945年の戦後のものである。いろいろ歴史を語る向きがあるが、基本的に新しいと考えないとダメだと思っている。1945年以前にたどるのは歴史を複雑化して面白いけど、本質から大はずれしている気がする。江東区の老人は、小麦粉が世に氾濫したのは敗戦後、アメリカ軍によるという。関東平野の土壌とか小麦の生産量とかいろんなことを関東の名物焼きそばを語るときにつけ加えるが、戦後の粉食は意外に単純かも。当然、1960年前後の酒田市の「あとがけ焼きそば」も同様だと思う。ただ、中華の焼きそばと、この国の庶民が作り出したソースの焼きそばの違いは、調べると面白いと思う。さて、ボクが作るのは、あり合わせのものだけで作り、何も乗っけないで、とてもシンプルなものだ。味のいい埼玉の麺で作るので香ばしくソテーして麺そのものの味を楽しんでいる。ソースは千葉県で買ったカゴメのウスターソース。カゴメソースとブルドッグはどちらかというと酸味が薄く、優等生的な味だ。ソースに関しては。イカリソース、名前が出てこない北海道で買ったソースなど、ちょっとずつ地域によって違いがあるのが楽しい。こんな日常的なものの違いを楽しむのも旅だと考えている。
鼻水攻撃で1日棒に振り、貴重な時間が消えてなくなる。今年もなんの収穫もなしに過ぎていくんだろうなと思いながら、埼玉県川島町、大河戸製麺の太焼きそば麺で焼きそばを作る。ときどき焼きそばを無性に食べたくなるボクだけど、今年になって、ずーっと「あとがけ」である。「あとがけ焼きそば」は山形県酒田市の名物でもあるが、調理の途中、ソースをからめ、ソースを焦がすという工程がない。味つけはテーブルのソースで好きにやってくれ、といった投げやりさが逆にいい。ソースをかけすぎると大変なことになるが、自己責任なので、文句のいいようがない。いろいろ上にのってゴージャスだったが、逆に麺は平凡だった。焼きそばとか、お好み焼きとかは明らかに1945年の戦後のものである。いろいろ歴史を語る向きがあるが、基本的に新しいと考えないとダメだと思っている。1945年以前にたどるのは歴史を複雑化して面白いけど、本質から大はずれしている気がする。江東区の老人は、小麦粉が世に氾濫したのは敗戦後、アメリカ軍によるという。関東平野の土壌とか小麦の生産量とかいろんなことを関東の名物焼きそばを語るときにつけ加えるが、戦後の粉食は意外に単純かも。当然、1960年前後の酒田市の「あとがけ焼きそば」も同様だと思う。ただ、中華の焼きそばと、この国の庶民が作り出したソースの焼きそばの違いは、調べると面白いと思う。さて、ボクが作るのは、あり合わせのものだけで作り、何も乗っけないで、とてもシンプルなものだ。味のいい埼玉の麺で作るので香ばしくソテーして麺そのものの味を楽しんでいる。ソースは千葉県で買ったカゴメのウスターソース。カゴメソースとブルドッグはどちらかというと酸味が薄く、優等生的な味だ。ソースに関しては。イカリソース、名前が出てこない北海道で買ったソースなど、ちょっとずつ地域によって違いがあるのが楽しい。こんな日常的なものの違いを楽しむのも旅だと考えている。 あんまりにも同じ物を見つめすぎると身体が熱くなる。巻き貝の世界は非常に難しい。取り分け形態的な連続性を考え始めると、きりがない。別に病気でもないのに身体が熱くなり、冷たい床に腹ばいになるのが、ボクの対処法。憂さ晴らしに埼玉県まで野菜や地域ならではのものを買いに行ってきた。そしてまた埼玉県川島町の直売所で、太巻き手打ちうどん弁当(うどんつき弁当)を買った。川島町のある埼玉県など関東平野は古くからの畑作地帯で小麦粉文化圏だ。1590年、徳川家が江戸入り後すぐから徳川家は米(戦国時代に耕地が増え、米の収穫量が増えると、米本位制となる。米は食料でもあり、金と同等のものでもある)の確保に苦しんだ。徳川家家臣団、江戸幕府を築く流入民に分け与える米が不足していたのだ。この米不足は1670年代に河村瑞賢が東北からの米廻船の新航路を見出すまで続く。考えてみると関東平野は古くは秩父平氏、次いで鎌倉幕府ができ、室町期に鎌倉公方、関東管領が統治する。鎌倉公方、関東管領の享徳の乱の後、この足利の支配が消えると、後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が、享徳の乱の続きを始める。後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が天下を取れなかったのは関東平野にこだわったからだ。ものなりの悪い土地の争奪戦にこの戦国武将達はなぜにこだわったのだろう。さて、旧比企郡にある川島町は旧川越藩の領地だ。川越は太田道灌の太田氏との繋がりがあり、江戸時代には小田原藩とともに特別な藩だった。川島町周辺では江戸時代から米はとれていたものの、伊達藩、仙台米と比べると質が落ちた。ある意味、米は藩に税として収めて、主食は麦だったのではないか。ちなみに戦後になっても埼玉県の米は東京での評価は低く、安かった。江東区の民俗学資料の米穀店の聞き書きに埼玉米は煎餅屋に下ろすために仕入れているもので、決して一般家庭では食べなかったとある。埼玉県北部や群馬県にみられるゆでうどん付き弁当は、その米不足の名残である。不思議な取り合わせで決して身体にはよくないと思うけど、いろんな味が楽しめるのでついつい手が出てしまう。
あんまりにも同じ物を見つめすぎると身体が熱くなる。巻き貝の世界は非常に難しい。取り分け形態的な連続性を考え始めると、きりがない。別に病気でもないのに身体が熱くなり、冷たい床に腹ばいになるのが、ボクの対処法。憂さ晴らしに埼玉県まで野菜や地域ならではのものを買いに行ってきた。そしてまた埼玉県川島町の直売所で、太巻き手打ちうどん弁当(うどんつき弁当)を買った。川島町のある埼玉県など関東平野は古くからの畑作地帯で小麦粉文化圏だ。1590年、徳川家が江戸入り後すぐから徳川家は米(戦国時代に耕地が増え、米の収穫量が増えると、米本位制となる。米は食料でもあり、金と同等のものでもある)の確保に苦しんだ。徳川家家臣団、江戸幕府を築く流入民に分け与える米が不足していたのだ。この米不足は1670年代に河村瑞賢が東北からの米廻船の新航路を見出すまで続く。考えてみると関東平野は古くは秩父平氏、次いで鎌倉幕府ができ、室町期に鎌倉公方、関東管領が統治する。鎌倉公方、関東管領の享徳の乱の後、この足利の支配が消えると、後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が、享徳の乱の続きを始める。後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が天下を取れなかったのは関東平野にこだわったからだ。ものなりの悪い土地の争奪戦にこの戦国武将達はなぜにこだわったのだろう。さて、旧比企郡にある川島町は旧川越藩の領地だ。川越は太田道灌の太田氏との繋がりがあり、江戸時代には小田原藩とともに特別な藩だった。川島町周辺では江戸時代から米はとれていたものの、伊達藩、仙台米と比べると質が落ちた。ある意味、米は藩に税として収めて、主食は麦だったのではないか。ちなみに戦後になっても埼玉県の米は東京での評価は低く、安かった。江東区の民俗学資料の米穀店の聞き書きに埼玉米は煎餅屋に下ろすために仕入れているもので、決して一般家庭では食べなかったとある。埼玉県北部や群馬県にみられるゆでうどん付き弁当は、その米不足の名残である。不思議な取り合わせで決して身体にはよくないと思うけど、いろんな味が楽しめるのでついつい手が出てしまう。 穀醤である醤(ひしお)、醤油の実(しょうゆの実)、もろみ、のない地域は少ないと思っている。穀醤とは別系統の、醤油のことをもっと深く知りたいと思っているので、我が家にある穀醤のデータを整理中だ。まだ我がデータベース内の「製造されている分布域」すらはっきりしないが、醤油の伝来以前からあるものなので、たぶん名前は違えども全国にあると思われる。ちなみに穀醤は大豆・麦・塩・水と麹で発酵させたもの。調味料ではなく、食べるためのものである。今回の福島県・新潟県の旅では、福島県内では見つけられなかった。探し回った挙げ句、新潟県内では大手の十日町市、『高長醸造場』のものを買い求めてきた。十日町市のある魚沼地域では盛んに「しょうゆの実」が作られており、小さな醸造所も多いことからして残念ではある。新潟県の「しょうゆの実」は比較的辛口で甘味がほとんど感じられない。水分が多いのも特徴だと思われる。ちなみに醤油伝来以前には調味料という概念がなかった可能性が高い。料理は、調味することは特殊で、調味しないで火を通しただけの料理だった。食べるときにつけて食べた、そのつけだれの役割を果たしていたのが、もちろん現在のものとはまったくの別物だとは思うが、穀醤である。ちなみにこの塩分濃度の高い、「『しょうゆの実』だけでご飯を食べるのが好きで他にはなにもいらない」という話を超高齢のご婦人に小千谷市の地スーパー、『たかのスーパー』で聞いたことがある。昔はそれが当たり前だったのかも知れない。新潟県でもそうだが、意外に穀醤を調味料として使う地域は少ない。
穀醤である醤(ひしお)、醤油の実(しょうゆの実)、もろみ、のない地域は少ないと思っている。穀醤とは別系統の、醤油のことをもっと深く知りたいと思っているので、我が家にある穀醤のデータを整理中だ。まだ我がデータベース内の「製造されている分布域」すらはっきりしないが、醤油の伝来以前からあるものなので、たぶん名前は違えども全国にあると思われる。ちなみに穀醤は大豆・麦・塩・水と麹で発酵させたもの。調味料ではなく、食べるためのものである。今回の福島県・新潟県の旅では、福島県内では見つけられなかった。探し回った挙げ句、新潟県内では大手の十日町市、『高長醸造場』のものを買い求めてきた。十日町市のある魚沼地域では盛んに「しょうゆの実」が作られており、小さな醸造所も多いことからして残念ではある。新潟県の「しょうゆの実」は比較的辛口で甘味がほとんど感じられない。水分が多いのも特徴だと思われる。ちなみに醤油伝来以前には調味料という概念がなかった可能性が高い。料理は、調味することは特殊で、調味しないで火を通しただけの料理だった。食べるときにつけて食べた、そのつけだれの役割を果たしていたのが、もちろん現在のものとはまったくの別物だとは思うが、穀醤である。ちなみにこの塩分濃度の高い、「『しょうゆの実』だけでご飯を食べるのが好きで他にはなにもいらない」という話を超高齢のご婦人に小千谷市の地スーパー、『たかのスーパー』で聞いたことがある。昔はそれが当たり前だったのかも知れない。新潟県でもそうだが、意外に穀醤を調味料として使う地域は少ない。 スーパーに行くのも、ボクにとっては旅である。いろんな刺激があっちこっちから飛んで来る。普段は行かない、駅前のスーパーに飲み物を買いに入ったら、懐かしすぎる「マースカレー」があった!1945年の敗戦後、新しい家庭料理をこの国とGHQは国策として広めていた。中にカレーがある。このあたりに関しては小菅桂子の『カレーの誕生』に詳しい。国民の体形の向上と主婦の家事負担の軽減である。当時、料理は主婦が作るもので、農家などで主婦はもっとも早く起きて朝食を作り、もっとも遅くまで家事をこなすのが普通だった。今でも昔の主婦はよく働いたものだ、なんて懐かしそうに言う愚か者がいるが、これは明らかな虐待である。料理は「ご飯に一汁一菜」にしても、当座食べるものを作っていても手間がかかる。ライスカレーはそれだけで、ご飯であり、おかずであり、汁でもあり、と完結しているのである。コロッケなどの戦前からのものではなく、戦後の新しい家庭料理の普及はちゃんとした目的があってのことなのだ。
スーパーに行くのも、ボクにとっては旅である。いろんな刺激があっちこっちから飛んで来る。普段は行かない、駅前のスーパーに飲み物を買いに入ったら、懐かしすぎる「マースカレー」があった!1945年の敗戦後、新しい家庭料理をこの国とGHQは国策として広めていた。中にカレーがある。このあたりに関しては小菅桂子の『カレーの誕生』に詳しい。国民の体形の向上と主婦の家事負担の軽減である。当時、料理は主婦が作るもので、農家などで主婦はもっとも早く起きて朝食を作り、もっとも遅くまで家事をこなすのが普通だった。今でも昔の主婦はよく働いたものだ、なんて懐かしそうに言う愚か者がいるが、これは明らかな虐待である。料理は「ご飯に一汁一菜」にしても、当座食べるものを作っていても手間がかかる。ライスカレーはそれだけで、ご飯であり、おかずであり、汁でもあり、と完結しているのである。コロッケなどの戦前からのものではなく、戦後の新しい家庭料理の普及はちゃんとした目的があってのことなのだ。 ドイツ文学者の西義之は1922年台湾生まれ。内地(1945年以前の言語)に来たのは、「四校」と呼ばれた、旧制第四高等学校に入るためだろう。ということは彼の国内での故郷は金沢ということになる。「四校」というと井上靖の「夏草冬濤」の世界である。『定年教授の食卓』(春秋社)に、雑誌やラジオで何度も話題になったことのある「ドリコノ」とともに「炒り粉」の話が出てくる。〈田舎(たぶん石川県金沢市)で「炒り粉」を冷たい水で溶かして、塩と砂糖で味つけをして飲んでいた〉「炒り粉」は、ボクが小さい時は「はったい粉」。他には「麦こがし」、「香煎」、「おちらし」ともいう。麦を香ばしく炒って粉状にした食品で、中世以前からの食品である可能性が高い。徳島県美馬郡貞光町(つるぎ町貞光)の家では、お湯で錬って食べていた。どろっとしつつも飲めるくらい薄く溶いて、甘い味つけをして飲むというのはまったく未知の世界である
ドイツ文学者の西義之は1922年台湾生まれ。内地(1945年以前の言語)に来たのは、「四校」と呼ばれた、旧制第四高等学校に入るためだろう。ということは彼の国内での故郷は金沢ということになる。「四校」というと井上靖の「夏草冬濤」の世界である。『定年教授の食卓』(春秋社)に、雑誌やラジオで何度も話題になったことのある「ドリコノ」とともに「炒り粉」の話が出てくる。〈田舎(たぶん石川県金沢市)で「炒り粉」を冷たい水で溶かして、塩と砂糖で味つけをして飲んでいた〉「炒り粉」は、ボクが小さい時は「はったい粉」。他には「麦こがし」、「香煎」、「おちらし」ともいう。麦を香ばしく炒って粉状にした食品で、中世以前からの食品である可能性が高い。徳島県美馬郡貞光町(つるぎ町貞光)の家では、お湯で錬って食べていた。どろっとしつつも飲めるくらい薄く溶いて、甘い味つけをして飲むというのはまったく未知の世界である 十日町市の「十日」は十のつく日に市が開かれていたためだ。今でも新潟県では巻町や三条など各地で日にちごとの市が開かれている。残念ながら十日町市では市が開かれていない。北魚沼で、2月末なのに雪がないというのも予想外だった。新潟県十日町市の商店街は長い。雪国ならではの雁木はアーケードに変わり、シャッターを下ろした店が目立つ。江戸時代には越後上布、越後縮の産地(江戸時代から昭和になっても織物は一大産業だった)であって、ある意味、北越雪譜に描かれているとおりのところだったのだろう。織物産業があって商業も盛ん。繁栄した町であった名残がそこここに見られる。加うるに、十日町市は信濃川に沿ってある。この町はコイをよく食べる地域だったという。考えて見ると新潟県は阿賀野川があり、信濃川、また旧蒲原郡に多い潟(平地の湿地帯の中の湖、池のこと)があるなど、淡水魚が重要なたんぱく源であったはずだ。十日町市にはウナギとコイの店があるが、この日は定休日だった。まあ今回の十日町は下見と思えば惜しくはない。商店街を十日町らしいものを探して歩くがなにもない。雁木は露地に少しだけ残っているだけだ。だいたい歩いている人が少なすぎる。時刻は1時過ぎ、せめて十日町市で昼飯をと、ふたたび商店街を歩く。新しい店には入りたくない。『小嶋屋』という長岡市にもあるのと同じ屋号のそば店があって、「へぎそば」も同じである。「へぎそば」はフノリをつなぎに使ったもので、ときどき食べたくなるが、この日は長時間労働のあとなのだ。余談になるが市場の旅は、だいたい午前2時くらいに始まり、魚(水産生物)の並ぶ競り場でみて、午前8時くらいに終了する。市場にいること今回は6時間。しかも新潟市はそのとき冷凍庫の中のようだった。とてもそばという気にはなれない。どんなに飢えてもチェーン店では食べないのがモットー、しかもネットは見ないので、ずんずん歩くしかない。向こうに洗いざらした紺色ののれんを見つけたときには涙がちょろりとした。
十日町市の「十日」は十のつく日に市が開かれていたためだ。今でも新潟県では巻町や三条など各地で日にちごとの市が開かれている。残念ながら十日町市では市が開かれていない。北魚沼で、2月末なのに雪がないというのも予想外だった。新潟県十日町市の商店街は長い。雪国ならではの雁木はアーケードに変わり、シャッターを下ろした店が目立つ。江戸時代には越後上布、越後縮の産地(江戸時代から昭和になっても織物は一大産業だった)であって、ある意味、北越雪譜に描かれているとおりのところだったのだろう。織物産業があって商業も盛ん。繁栄した町であった名残がそこここに見られる。加うるに、十日町市は信濃川に沿ってある。この町はコイをよく食べる地域だったという。考えて見ると新潟県は阿賀野川があり、信濃川、また旧蒲原郡に多い潟(平地の湿地帯の中の湖、池のこと)があるなど、淡水魚が重要なたんぱく源であったはずだ。十日町市にはウナギとコイの店があるが、この日は定休日だった。まあ今回の十日町は下見と思えば惜しくはない。商店街を十日町らしいものを探して歩くがなにもない。雁木は露地に少しだけ残っているだけだ。だいたい歩いている人が少なすぎる。時刻は1時過ぎ、せめて十日町市で昼飯をと、ふたたび商店街を歩く。新しい店には入りたくない。『小嶋屋』という長岡市にもあるのと同じ屋号のそば店があって、「へぎそば」も同じである。「へぎそば」はフノリをつなぎに使ったもので、ときどき食べたくなるが、この日は長時間労働のあとなのだ。余談になるが市場の旅は、だいたい午前2時くらいに始まり、魚(水産生物)の並ぶ競り場でみて、午前8時くらいに終了する。市場にいること今回は6時間。しかも新潟市はそのとき冷凍庫の中のようだった。とてもそばという気にはなれない。どんなに飢えてもチェーン店では食べないのがモットー、しかもネットは見ないので、ずんずん歩くしかない。向こうに洗いざらした紺色ののれんを見つけたときには涙がちょろりとした。 打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。
打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。 会津・越後の旅の初日、福島県喜多方市に宿泊することにしたのは偶然である。雪国の寒さに限界を感じホテルを探し、その挙げ句、市内のホテルに行き当たっただけ。ついでに言えば、ラーメンは好きだけど、それほど興味があるわけではない。会津若松市(会津の中心)は蘆名氏、伊達氏、蒲生氏郷などがいて中世史に何度も登場する。平安時代の貴族から武士(輸送業者)への土地支配の歴史からも重要だと思うが、喜多方は歴史も産業も勉強不足のせいかてんでわからない。さて、夜の喜多方で軽く飲んだら眠くなり、湯船に入ったところまでは記憶にあるが、ベッドにもぐり込んだ記憶すらない。しかも翌朝目覚めて時計を見ると、なんと午前6時を過ぎていた。熟睡10時間余りはボクの年では危険だと思う。ホテル飯は食わないので、猪苗代への道を角を1本曲がり曲り間違えたら、いきなりC(青)×M(マゼンタで赤)ではなく、C×Y(黄)色の暖簾が目に飛び込んできたのだ。東京ののれんの基本色はC×Mだ。東北地方ののれんの特徴は色が多様だということ。食文化を探す旅では、のれんの色だけを見て回っても充分楽しめる。青森県ではY100×C30なんてのもあったはずだ。このとき午前7時15分過ぎで、やっていなくてもいいや、と思ったらやっていた。店に入ったらビックリするほど、粗野な店だった。逃げようとして、そこにいたオバチャンの雰囲気で逃げられなかった。詳しくは述べぬが、やって来たコップにはラベルがついたままだった。
会津・越後の旅の初日、福島県喜多方市に宿泊することにしたのは偶然である。雪国の寒さに限界を感じホテルを探し、その挙げ句、市内のホテルに行き当たっただけ。ついでに言えば、ラーメンは好きだけど、それほど興味があるわけではない。会津若松市(会津の中心)は蘆名氏、伊達氏、蒲生氏郷などがいて中世史に何度も登場する。平安時代の貴族から武士(輸送業者)への土地支配の歴史からも重要だと思うが、喜多方は歴史も産業も勉強不足のせいかてんでわからない。さて、夜の喜多方で軽く飲んだら眠くなり、湯船に入ったところまでは記憶にあるが、ベッドにもぐり込んだ記憶すらない。しかも翌朝目覚めて時計を見ると、なんと午前6時を過ぎていた。熟睡10時間余りはボクの年では危険だと思う。ホテル飯は食わないので、猪苗代への道を角を1本曲がり曲り間違えたら、いきなりC(青)×M(マゼンタで赤)ではなく、C×Y(黄)色の暖簾が目に飛び込んできたのだ。東京ののれんの基本色はC×Mだ。東北地方ののれんの特徴は色が多様だということ。食文化を探す旅では、のれんの色だけを見て回っても充分楽しめる。青森県ではY100×C30なんてのもあったはずだ。このとき午前7時15分過ぎで、やっていなくてもいいや、と思ったらやっていた。店に入ったらビックリするほど、粗野な店だった。逃げようとして、そこにいたオバチャンの雰囲気で逃げられなかった。詳しくは述べぬが、やって来たコップにはラベルがついたままだった。 ボクの旅は、昔ながらの食文化を探す旅なので、ある意味特殊である。少数派という以前にひょっとしたらボク一人っきりの旅の形かも知れない。水産物だと、例えば山間部に行ってフグを食べたり、輸入ものの水産物などは食べたくない。できる限りその地を感じるものを食べたい。我が故郷、徳島でキチジ(キンキ)が出て来たときには思わず涙が出そうになった。そんな不愉快な眼にはもう二度と会いたくない。新潟県は淡水魚食の盛んなところである。特にコイとフナは非常によく食べていたことが文献ではわかっている。十日町市で十日町市らしいといえばコイとそばと野菜、保存食ではないかと思う。ついでに少しくらいは雁木(商店などの前に見られる雪よけのひさし)があるだろうと思って行ったものの、「明るい未来を感じていたときの遺産」、アルミ製のものに取って代わられており、ほんのわずかしか残っていなかった。しかも、コイは店が定休日らしく食べられなかった。
ボクの旅は、昔ながらの食文化を探す旅なので、ある意味特殊である。少数派という以前にひょっとしたらボク一人っきりの旅の形かも知れない。水産物だと、例えば山間部に行ってフグを食べたり、輸入ものの水産物などは食べたくない。できる限りその地を感じるものを食べたい。我が故郷、徳島でキチジ(キンキ)が出て来たときには思わず涙が出そうになった。そんな不愉快な眼にはもう二度と会いたくない。新潟県は淡水魚食の盛んなところである。特にコイとフナは非常によく食べていたことが文献ではわかっている。十日町市で十日町市らしいといえばコイとそばと野菜、保存食ではないかと思う。ついでに少しくらいは雁木(商店などの前に見られる雪よけのひさし)があるだろうと思って行ったものの、「明るい未来を感じていたときの遺産」、アルミ製のものに取って代わられており、ほんのわずかしか残っていなかった。しかも、コイは店が定休日らしく食べられなかった。 ボクはからっちゃの息子で、よく近所のオッチャンに「からっちゃのおとんぼはできんぼでよ」と言われていた。訳すと、「からっちゃ」は「唐津屋」のことで、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)では食器店のことをこういった。この「唐津屋」が食器店である地域は広島県で見つけているが、ほかではあまり知らない。関東では「瀬戸物屋」だ。「おとんぼ」は末っ子のことで、「できんぼでよ」は訳したくない。そのせいとばかりは言えないが、やたらに器が好きだ。ちなみにボクの町は小さな小さな徳島県でも、もっとも小さな町だったが、それでも時代の風を食器や雑貨に感じたものだった。だから旅に出て、食器店があったら必ず立ち寄る。食器店には時代の残り香のようなものがある。福島県南会津町田島は四方を山に囲まれている。粉雪が舞い、四方の山から重い冷気がこの町に沈殿しているみたいだ。たぶん会津西街道だと思われる大通りを、西へ西へとずんずん歩く。この冷たさは四国生まれにはきつい。食器店を見つけて一度通り過ぎた。本屋があり、造り酒屋があり、旅館があり、閉店しているもののたくさんの看板建築がある。町の端っこまでたどり着いて戻ってくる。食器店の看板に『ショップおおたけ』とある看板部分が比較的新しく万博以降(1970)であることがわかる。調べてみるともともとは『大竹陶器店』だったらしい。歩いていたバアチャンに聞くと、この通りにはいくつもの食器や雑貨を売る店があったようだ。こんなところにも田島という地が周辺地域から買い出しにくる場所であったことがわかる。ここには会津祇園祭という大きな祭もある。商店があり、大きな祭がありで、周辺の山間部から人が集まってくる典型的な町だ。確か、瀬川清子(偉大な民俗学者。1895〜1984年)は、千葉県久留里をその典型だとしていたはず。ボクの故郷も規模は小さいがそのひとつで、日本全国にこんな町がある。
ボクはからっちゃの息子で、よく近所のオッチャンに「からっちゃのおとんぼはできんぼでよ」と言われていた。訳すと、「からっちゃ」は「唐津屋」のことで、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)では食器店のことをこういった。この「唐津屋」が食器店である地域は広島県で見つけているが、ほかではあまり知らない。関東では「瀬戸物屋」だ。「おとんぼ」は末っ子のことで、「できんぼでよ」は訳したくない。そのせいとばかりは言えないが、やたらに器が好きだ。ちなみにボクの町は小さな小さな徳島県でも、もっとも小さな町だったが、それでも時代の風を食器や雑貨に感じたものだった。だから旅に出て、食器店があったら必ず立ち寄る。食器店には時代の残り香のようなものがある。福島県南会津町田島は四方を山に囲まれている。粉雪が舞い、四方の山から重い冷気がこの町に沈殿しているみたいだ。たぶん会津西街道だと思われる大通りを、西へ西へとずんずん歩く。この冷たさは四国生まれにはきつい。食器店を見つけて一度通り過ぎた。本屋があり、造り酒屋があり、旅館があり、閉店しているもののたくさんの看板建築がある。町の端っこまでたどり着いて戻ってくる。食器店の看板に『ショップおおたけ』とある看板部分が比較的新しく万博以降(1970)であることがわかる。調べてみるともともとは『大竹陶器店』だったらしい。歩いていたバアチャンに聞くと、この通りにはいくつもの食器や雑貨を売る店があったようだ。こんなところにも田島という地が周辺地域から買い出しにくる場所であったことがわかる。ここには会津祇園祭という大きな祭もある。商店があり、大きな祭がありで、周辺の山間部から人が集まってくる典型的な町だ。確か、瀬川清子(偉大な民俗学者。1895〜1984年)は、千葉県久留里をその典型だとしていたはず。ボクの故郷も規模は小さいがそのひとつで、日本全国にこんな町がある。 福島県南会津町田島は2006年までは田島町であった。市町村合併はもともと大嫌いだけど、それにしても南会津町の合併は無理があると思う。1718あるとされる市町村の中でも45番目に広く、886.47㎢もある。ボクの生まれた徳島県美馬郡つるぎ町は194.8 km²なので4倍以上だ。
福島県南会津町田島は2006年までは田島町であった。市町村合併はもともと大嫌いだけど、それにしても南会津町の合併は無理があると思う。1718あるとされる市町村の中でも45番目に広く、886.47㎢もある。ボクの生まれた徳島県美馬郡つるぎ町は194.8 km²なので4倍以上だ。 まだ、整理が出来ていないが市場だけで通じる言語は少なくない。これを集めて、徐々に分類していきたいと思っている。例えば今、「赤魚の粕漬」と呼ばれているものを「たいかす(鯛粕)」という人は少なくない。これはアラスカメヌケとか輸入ものの赤いメバル科の魚の粕漬けである。最初は国産のアコウダイで作っていたもので、アコウダイの粕漬けが縮められて「鯛粕」になる。そのアコウダイがとれなくなり、高騰して使えなくなったので、輸入魚を使うようになる。たぶん、その遙かに昔は本当に鯛(マダイ)で作っていたのかも知れぬ。福井県三国にある『日海水産』の名品、ボイルホタテ(ホタテガイのたぶん稚貝を塩ゆでにしたもの)もそのひとつ。市場の、年寄りの多くが「いたや」という。東京、豊洲市場を歩いていても、いまだに「いたや」という言語が生きているのがわかる。今では「いたや」=イタヤガイではないが、昔は日本海でたくさん揚がったイタヤガイ(鳥取県気高町の貝殻節にうたわれるのはイタヤガイ)をゆでて出荷していたのだと思う。その内、イタヤガイが揚がらなくなり、青森県産のホタテガイに活路を見出す。この『日海水産』のボイルホタテを「いたや」といまだに呼んでいる事実には、昔、信じられないくらいにたくさんのイタヤガイが日本海山陰・北陸などで揚がっていた、その歴史が保存されているのだ。この『日海水産』のボイルホタテのすごいところは、これがないと困るという飲食店が少なくないことだと思う。
まだ、整理が出来ていないが市場だけで通じる言語は少なくない。これを集めて、徐々に分類していきたいと思っている。例えば今、「赤魚の粕漬」と呼ばれているものを「たいかす(鯛粕)」という人は少なくない。これはアラスカメヌケとか輸入ものの赤いメバル科の魚の粕漬けである。最初は国産のアコウダイで作っていたもので、アコウダイの粕漬けが縮められて「鯛粕」になる。そのアコウダイがとれなくなり、高騰して使えなくなったので、輸入魚を使うようになる。たぶん、その遙かに昔は本当に鯛(マダイ)で作っていたのかも知れぬ。福井県三国にある『日海水産』の名品、ボイルホタテ(ホタテガイのたぶん稚貝を塩ゆでにしたもの)もそのひとつ。市場の、年寄りの多くが「いたや」という。東京、豊洲市場を歩いていても、いまだに「いたや」という言語が生きているのがわかる。今では「いたや」=イタヤガイではないが、昔は日本海でたくさん揚がったイタヤガイ(鳥取県気高町の貝殻節にうたわれるのはイタヤガイ)をゆでて出荷していたのだと思う。その内、イタヤガイが揚がらなくなり、青森県産のホタテガイに活路を見出す。この『日海水産』のボイルホタテを「いたや」といまだに呼んでいる事実には、昔、信じられないくらいにたくさんのイタヤガイが日本海山陰・北陸などで揚がっていた、その歴史が保存されているのだ。この『日海水産』のボイルホタテのすごいところは、これがないと困るという飲食店が少なくないことだと思う。 イサキとはひとりぼっちで悲しい魚だという話をしたい。本州、四国、九州にいる魚で、漁獲量は多獲性魚類(サバ類、マアジ、サンマなど)であるマイワシなどと比べると少ないが、決して魚全体からみると決して少なくはない。外洋に面した磯(岩などが多い浅いところ)にいる魚で、漁港や岩場などから海をのぞくと小型なら見られるくらい在り来たりの存在である。しごくおとなしい顔をしており、歯は小さく、エサは甲殻類や小さな軟体類であるイカタコなどで、食い殺すのではなく飲み込むタイプである。小エビなどにとっては優しい悪魔だ。ここまではイサキの解説だが、まずは食用魚イサキって知ってますか? から始めなくてはいけない。たぶんだけど、この国に住むほとんどの人は知らないだろう。昔、マスコミ関係の話し合いで、食の専門家ですらイサキを知らない人がいてビックリしたが、これが現実だろうなと思ったものだ。ちなみにこの国の料理研究家は最低限の植物(野菜)と、鶏肉と豚肉、牛肉だけ知っていて、ご飯が炊けて、パンでも焼ければなれそうだと思う。間違いなく水産物の知識はゼロでもやっていける。この国のほとんどの人が食べ歩きには興味があるが、料理にも食材にも興味がないのだから、仕方がないだろう。
イサキとはひとりぼっちで悲しい魚だという話をしたい。本州、四国、九州にいる魚で、漁獲量は多獲性魚類(サバ類、マアジ、サンマなど)であるマイワシなどと比べると少ないが、決して魚全体からみると決して少なくはない。外洋に面した磯(岩などが多い浅いところ)にいる魚で、漁港や岩場などから海をのぞくと小型なら見られるくらい在り来たりの存在である。しごくおとなしい顔をしており、歯は小さく、エサは甲殻類や小さな軟体類であるイカタコなどで、食い殺すのではなく飲み込むタイプである。小エビなどにとっては優しい悪魔だ。ここまではイサキの解説だが、まずは食用魚イサキって知ってますか? から始めなくてはいけない。たぶんだけど、この国に住むほとんどの人は知らないだろう。昔、マスコミ関係の話し合いで、食の専門家ですらイサキを知らない人がいてビックリしたが、これが現実だろうなと思ったものだ。ちなみにこの国の料理研究家は最低限の植物(野菜)と、鶏肉と豚肉、牛肉だけ知っていて、ご飯が炊けて、パンでも焼ければなれそうだと思う。間違いなく水産物の知識はゼロでもやっていける。この国のほとんどの人が食べ歩きには興味があるが、料理にも食材にも興味がないのだから、仕方がないだろう。 コウイカ科のイカの特徴は「貝のような姿の動物」であった名残である、貝殻を体に有していることだ。貝殻は一般的には甲という。甲を持っているイカなので甲烏賊となり、科名(コウイカ科)種名(コウイカ)になっている。山間部に育ったボクに甲は珍しく、子供の頃、魚屋にお使いに行って、甲をもらって、うれしかった想い出がある。生物学者・谷田専治(1908年生まれ)は粉末にして歯磨き粉に用いる、…甲に彫刻して飾りものにする…止淋散と称して墨客に利用されると述べている。止淋散は不明。魚屋の中に乾燥して粉末にして血止めにするという人もいる。鯣(するめ)はイカの開いて干したもののことであるが、比較的大形の食用イカすべてで作られている。スルメイカは国内でたくさんとれ、鯣にもっともよく加工されるために、鯣烏賊と呼ばれるようになった。鯣に加工される主なイカは多い順にスルメイカ、ケンサキイカ、アオリイカのツツイカ類(体がスマートで貝殻がフィルム状)。シリヤケイカ、コウイカ、カミナリイカのコウイカ類である。ツツイカ類の鯣はスーパーなどでもよく売られているので、探せば手に入るが、コウイカ類の鯣を手に入れるのはなかなか難しい。コウイカ(ハリイカ)の干ものは徳島県鳴門市、阿南市で食べているのに、撮影し忘れるという失態をおかしているが、非常にローカルな食材である。そのコウイカ類の干ものに「甲つきするめ」がある。先に述べた谷田専治、軟体類学者・奥谷喬司の著書にあるし、塩乾加工の書籍にもある。長崎県雲仙市の佐藤厚さんはシリヤケイカ、コウイカで実際に作っていたとのことで、味はシリヤケイカの方がいいという。とすると「甲つきするめ」は主にシリヤケイカで作られていたのだろう。これは奥谷喬司がシリヤケイカは東シナ海でたくさんとれていた。「甲付するめ」にも製されていたということと一致する。
コウイカ科のイカの特徴は「貝のような姿の動物」であった名残である、貝殻を体に有していることだ。貝殻は一般的には甲という。甲を持っているイカなので甲烏賊となり、科名(コウイカ科)種名(コウイカ)になっている。山間部に育ったボクに甲は珍しく、子供の頃、魚屋にお使いに行って、甲をもらって、うれしかった想い出がある。生物学者・谷田専治(1908年生まれ)は粉末にして歯磨き粉に用いる、…甲に彫刻して飾りものにする…止淋散と称して墨客に利用されると述べている。止淋散は不明。魚屋の中に乾燥して粉末にして血止めにするという人もいる。鯣(するめ)はイカの開いて干したもののことであるが、比較的大形の食用イカすべてで作られている。スルメイカは国内でたくさんとれ、鯣にもっともよく加工されるために、鯣烏賊と呼ばれるようになった。鯣に加工される主なイカは多い順にスルメイカ、ケンサキイカ、アオリイカのツツイカ類(体がスマートで貝殻がフィルム状)。シリヤケイカ、コウイカ、カミナリイカのコウイカ類である。ツツイカ類の鯣はスーパーなどでもよく売られているので、探せば手に入るが、コウイカ類の鯣を手に入れるのはなかなか難しい。コウイカ(ハリイカ)の干ものは徳島県鳴門市、阿南市で食べているのに、撮影し忘れるという失態をおかしているが、非常にローカルな食材である。そのコウイカ類の干ものに「甲つきするめ」がある。先に述べた谷田専治、軟体類学者・奥谷喬司の著書にあるし、塩乾加工の書籍にもある。長崎県雲仙市の佐藤厚さんはシリヤケイカ、コウイカで実際に作っていたとのことで、味はシリヤケイカの方がいいという。とすると「甲つきするめ」は主にシリヤケイカで作られていたのだろう。これは奥谷喬司がシリヤケイカは東シナ海でたくさんとれていた。「甲付するめ」にも製されていたということと一致する。 多くの文学作品に出てくるのが東京都内、千葉県西部の佃煮である。山本周五郎の『青べか物語』などをみても、庶民にとっての基本的な菜(副菜)だったことがわかる。東京都をはじめ東京湾周辺には無数の海辺漁業(造語です)があった。汽水域ではたくさんの二枚貝が取れ、アミ類、シラタエビ、テナガエビ、スジエビなどに、アマノリ(アサクサノリ)、青のり(ヒトエグサやスジアオノリ)がとれていた。小魚としてはフナにモツゴや小型のハゼ類などもとる。これを江戸時代初期などは塩で煮て軽く干し、やがて醤油が使われるようになり、19世紀になると上等な品にはみりんが使われるようになる。東京湾周辺には汽水域や内湾の小型の水産生物を無駄なく使う食文化が生まれて、今に続いているのだ。この小魚文化の主役的な存在である佃煮屋が急激になくなってきている。佃煮好きとしてはゆゆしき問題だし、汽水域が暮らしの場から、自然保護とか自然観察だけの場になるのもイヤダネーと思う。だから今や貴重な佃煮屋めぐりをしている。台東区上野、下谷から浅草にかけては取り分け佃煮屋の多い地域で、ボクが上京したての頃には無数の佃煮店があったと記憶する。家族が浅草暮らしをしていたので、田原町を中心に念入りに歩き回っているが、佃煮屋は普通の町に溶け込んでいた。それが今や2軒、3軒と数えるほどになっている。今回台東区北上野、『湯葢』で買った佃煮は、あみ、あさり、雑魚佃煮、昆布、おまけのスジエビ(テナガエビ)だ。どれもいい炊き加減で保ちがよい割りにそれだけを食べても、箸が止まらなくなるほど味わい深い。無意味に、この店、22世紀まで残したいと思ったほどだ。
多くの文学作品に出てくるのが東京都内、千葉県西部の佃煮である。山本周五郎の『青べか物語』などをみても、庶民にとっての基本的な菜(副菜)だったことがわかる。東京都をはじめ東京湾周辺には無数の海辺漁業(造語です)があった。汽水域ではたくさんの二枚貝が取れ、アミ類、シラタエビ、テナガエビ、スジエビなどに、アマノリ(アサクサノリ)、青のり(ヒトエグサやスジアオノリ)がとれていた。小魚としてはフナにモツゴや小型のハゼ類などもとる。これを江戸時代初期などは塩で煮て軽く干し、やがて醤油が使われるようになり、19世紀になると上等な品にはみりんが使われるようになる。東京湾周辺には汽水域や内湾の小型の水産生物を無駄なく使う食文化が生まれて、今に続いているのだ。この小魚文化の主役的な存在である佃煮屋が急激になくなってきている。佃煮好きとしてはゆゆしき問題だし、汽水域が暮らしの場から、自然保護とか自然観察だけの場になるのもイヤダネーと思う。だから今や貴重な佃煮屋めぐりをしている。台東区上野、下谷から浅草にかけては取り分け佃煮屋の多い地域で、ボクが上京したての頃には無数の佃煮店があったと記憶する。家族が浅草暮らしをしていたので、田原町を中心に念入りに歩き回っているが、佃煮屋は普通の町に溶け込んでいた。それが今や2軒、3軒と数えるほどになっている。今回台東区北上野、『湯葢』で買った佃煮は、あみ、あさり、雑魚佃煮、昆布、おまけのスジエビ(テナガエビ)だ。どれもいい炊き加減で保ちがよい割りにそれだけを食べても、箸が止まらなくなるほど味わい深い。無意味に、この店、22世紀まで残したいと思ったほどだ。 東京湾(江戸湾)ならではの脚立釣りは江戸時代より続く伝統釣法である。昭和38年7月(1963)、海苔、貝の漁場である十万坪(現浦安市今川・高洲で東京ディズニーランドの東)でのアオギス脚立釣りの光景。脚立は今ではアルミ製だが、この時代までは木製で、大阪では「クラカケ(鞍掛)」というと、魚類学者の田中茂穂は述べている。船宿で釣り人はよい釣り場を確保するためにクジをひく。釣り場が決まれば、港から脚立と釣り人を乗せて沖に向かう。次々に釣り場を巡り、脚立を設置して、釣り人を下ろしていく。昼になると船宿から弁当を取り寄せるなど、長々と海の上での釣りを楽しんでいた。(写真は浦安市郷土博物館 所蔵のものをお借りした)浦安の沖の十万坪といえば、山本周五郎の「青べか物語」にも登場する。東京湾の豊かさを感じる場所(浅瀬)でもあった。一般的なキスであるシロギスと比べると長さで倍以上もある大型魚であり、釣り味を楽しんだ。脚立釣りは食べるための釣りではなく、スポーツフィッシングといったものだったようだ。脚立釣りが好きだった、三代目三遊亭金馬(1894年(明治27年)〜1964年(昭和39)は著書で〈食べちゃ青ギスより白ギスのほうがうまい。職業釣り師は青ギスにめをつけない。だから町の魚屋には青ギスは売ってない。白ギスばかりだ〉『江戸前の釣り』(三代目三遊亭金馬)音に敏感なアオギスは船では釣れないので、海に脚立を立てるようになったという。脚立周りを1本の竿、道糸ハリスで釣り上げるので、アオギス専用の船釣りと比べると長い竿を使い、魚籠も網の部分が非常に長い独特のものだった。シロギスがやや外洋性であるのに対して、アオギスは川の河口域である汽水域や内湾を好むので、東京湾はアオギス釣りのメッカであったことがわかる。江戸時代や幸田露伴の明治には大川(隅田川)で行われていた脚立釣りが、昭和になると江戸川の向こう側、浦安などが主流になってくる。本種がいかに環境の変化に弱いかが、この事実からもわかる。脚立釣りは高度成長期にアオギスの減少とともに行われなくなり、やがてアオギスは東京湾から姿を消す。
東京湾(江戸湾)ならではの脚立釣りは江戸時代より続く伝統釣法である。昭和38年7月(1963)、海苔、貝の漁場である十万坪(現浦安市今川・高洲で東京ディズニーランドの東)でのアオギス脚立釣りの光景。脚立は今ではアルミ製だが、この時代までは木製で、大阪では「クラカケ(鞍掛)」というと、魚類学者の田中茂穂は述べている。船宿で釣り人はよい釣り場を確保するためにクジをひく。釣り場が決まれば、港から脚立と釣り人を乗せて沖に向かう。次々に釣り場を巡り、脚立を設置して、釣り人を下ろしていく。昼になると船宿から弁当を取り寄せるなど、長々と海の上での釣りを楽しんでいた。(写真は浦安市郷土博物館 所蔵のものをお借りした)浦安の沖の十万坪といえば、山本周五郎の「青べか物語」にも登場する。東京湾の豊かさを感じる場所(浅瀬)でもあった。一般的なキスであるシロギスと比べると長さで倍以上もある大型魚であり、釣り味を楽しんだ。脚立釣りは食べるための釣りではなく、スポーツフィッシングといったものだったようだ。脚立釣りが好きだった、三代目三遊亭金馬(1894年(明治27年)〜1964年(昭和39)は著書で〈食べちゃ青ギスより白ギスのほうがうまい。職業釣り師は青ギスにめをつけない。だから町の魚屋には青ギスは売ってない。白ギスばかりだ〉『江戸前の釣り』(三代目三遊亭金馬)音に敏感なアオギスは船では釣れないので、海に脚立を立てるようになったという。脚立周りを1本の竿、道糸ハリスで釣り上げるので、アオギス専用の船釣りと比べると長い竿を使い、魚籠も網の部分が非常に長い独特のものだった。シロギスがやや外洋性であるのに対して、アオギスは川の河口域である汽水域や内湾を好むので、東京湾はアオギス釣りのメッカであったことがわかる。江戸時代や幸田露伴の明治には大川(隅田川)で行われていた脚立釣りが、昭和になると江戸川の向こう側、浦安などが主流になってくる。本種がいかに環境の変化に弱いかが、この事実からもわかる。脚立釣りは高度成長期にアオギスの減少とともに行われなくなり、やがてアオギスは東京湾から姿を消す。 おはじき(御弾、お弾、オハジキ)は、大言海に〈細螺ノ介殻ヲ指先ニテ弾ク、小兒ノ遊戯〉とある。古くから浜の落ちている貝殻の美しい物を拾い、指ではじいて遊んだもの。本来日本各地で身近にある小型の貝などで遊んだものだが、今ではガラス製となっている。ガラス製のものは、1960年代くらいまではいたって普通の玩具で、夜店やおもちゃ屋、文具店などで売られていた。実際に女児、女性が指ではじいて遊んでいたのをおぼえている。今では100円ショップなどにもあるが、実際に遊ぶために売られているのかわからない。〈幾左古 正字は未詳 思うに幾左古は状蝸牛に似ているが、厚く堅くて彩文がある。殻の中には寄居虫(ごうな/ヤドカリ)のような虫がいる。伊勢・尾張および東海の諸浜に多くいる。土地の人は虫を取り去って洗浄し、これを玩具とする。〉『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)おはじきに使われた貝類は、〈シャゴ(キサゴ)《伊予大三島北部》 スヰビウシ(ハナマルユキ)《奄美》 ネコジャ(メダカラ、オミナエシダカラ)《千葉県安房郡鋸南町岩井袋》〉『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社 1988)たくさんとれて小さいもので遊んでいたことがわかる。〈この頃のこどもはどうか知らないが、年配の方なら大てい小さいころ、キサゴ(標準和名のキサゴ)のおはじきで遊んだ記憶がおありだろう〉。『原色・自然の手帳 日本の貝』(奥谷喬司、竹村嘉夫 講談社 1967) 奥谷喬司は1930年福岡県北九州市門司出身である。
おはじき(御弾、お弾、オハジキ)は、大言海に〈細螺ノ介殻ヲ指先ニテ弾ク、小兒ノ遊戯〉とある。古くから浜の落ちている貝殻の美しい物を拾い、指ではじいて遊んだもの。本来日本各地で身近にある小型の貝などで遊んだものだが、今ではガラス製となっている。ガラス製のものは、1960年代くらいまではいたって普通の玩具で、夜店やおもちゃ屋、文具店などで売られていた。実際に女児、女性が指ではじいて遊んでいたのをおぼえている。今では100円ショップなどにもあるが、実際に遊ぶために売られているのかわからない。〈幾左古 正字は未詳 思うに幾左古は状蝸牛に似ているが、厚く堅くて彩文がある。殻の中には寄居虫(ごうな/ヤドカリ)のような虫がいる。伊勢・尾張および東海の諸浜に多くいる。土地の人は虫を取り去って洗浄し、これを玩具とする。〉『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)おはじきに使われた貝類は、〈シャゴ(キサゴ)《伊予大三島北部》 スヰビウシ(ハナマルユキ)《奄美》 ネコジャ(メダカラ、オミナエシダカラ)《千葉県安房郡鋸南町岩井袋》〉『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社 1988)たくさんとれて小さいもので遊んでいたことがわかる。〈この頃のこどもはどうか知らないが、年配の方なら大てい小さいころ、キサゴ(標準和名のキサゴ)のおはじきで遊んだ記憶がおありだろう〉。『原色・自然の手帳 日本の貝』(奥谷喬司、竹村嘉夫 講談社 1967) 奥谷喬司は1930年福岡県北九州市門司出身である。全47件中 全レコードを表示しています