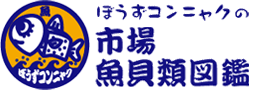コラム検索
検索条件
全11件中 全レコードを表示しています
 明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。
明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。 1970年前後、マアジの価値を上げたとされているのが、「あじのたたき」である。神奈川県小田原市周辺の料理で、「あじのたたきなます」ともいう。マアジを三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取り皮を聞く。これを細かく切ったものである。「みそたたき」、「なめろう」との違いは、サイコロ状の形が残った状態であること、味つけしていないところだ。しょうが、ねぎやみょうがなどの香辛野菜を使うなど徐々に変化しているが、もともとは漁師が船の上で作っていたものだ。一説に釣りのとき、コマセ(寄せエサ)がなくなり、釣れたアジ(マアジ)を細かく叩いてコマセに使ったとき、つまんでみたら美味であったので、作るようになったとも。小田原と東京との繋がりは深く、この「あじのたたき」が東京でも作られるようになり、あっと言う間に都内全域に広がる。■写真はもっとも基本的な「あじのたたき」。
1970年前後、マアジの価値を上げたとされているのが、「あじのたたき」である。神奈川県小田原市周辺の料理で、「あじのたたきなます」ともいう。マアジを三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取り皮を聞く。これを細かく切ったものである。「みそたたき」、「なめろう」との違いは、サイコロ状の形が残った状態であること、味つけしていないところだ。しょうが、ねぎやみょうがなどの香辛野菜を使うなど徐々に変化しているが、もともとは漁師が船の上で作っていたものだ。一説に釣りのとき、コマセ(寄せエサ)がなくなり、釣れたアジ(マアジ)を細かく叩いてコマセに使ったとき、つまんでみたら美味であったので、作るようになったとも。小田原と東京との繋がりは深く、この「あじのたたき」が東京でも作られるようになり、あっと言う間に都内全域に広がる。■写真はもっとも基本的な「あじのたたき」。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に岩手県宮古からキチジ(岩手県ではメイセンともキンキともいう)がきていた。漁業的には千葉県銚子以北の太平洋、オホーツク海で揚がる魚である。水深200m以深に多いので正真正銘の深海魚だ。甲殻類や棘皮動物、特に深海底にいるクモヒトデを飽食している。口に入れるとじゃりじゃりするクモヒトデで、なぜあの上質の脂が身につくのか、不思議でならない。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に岩手県宮古からキチジ(岩手県ではメイセンともキンキともいう)がきていた。漁業的には千葉県銚子以北の太平洋、オホーツク海で揚がる魚である。水深200m以深に多いので正真正銘の深海魚だ。甲殻類や棘皮動物、特に深海底にいるクモヒトデを飽食している。口に入れるとじゃりじゃりするクモヒトデで、なぜあの上質の脂が身につくのか、不思議でならない。 年明けに、愛知県人なのに先島諸島住民で、しかも京言葉を使う若い衆にいただいたものの中に京都市、『松葉』の「しんそば」があった。初めて京都に行ったときは、まだ市電があった。家族にお金を渡せされて、京都で頼まれた買い物をして帰郷した。『いずう』でやたら高い「さばずし」を買い、デパートで漬物を買い、四条下がって南座横の『松葉』で「みがきにしん」のたいたものを買い、ついでに『松葉』で「にしんそば」を食べた。東京の黒い黒い醤油のつゆでもなく、徳島・香川のしゃきっとした塩味がちなつゆでもない、丸みのある味に驚いた。「みがきにしん」は弱冠二十歳のボクにはよさがわからなかった。ここ15年ほど、京都の夜は居酒屋ではなく、西陣のそば・うどん店で酒を飲み、しめに「にしんそば」と「にしんうどん」を食べることが多い。「みがきにしん」はうどんには合わないことを知り、西陣の『えびや』の「みがきにしん」は京都でもいちばんうまいなんて思っていたのだ。2018年にもういちど『松葉』に立ち寄って恥ずかしげもなく「にしんそば」を食べたら、つゆの味が西陣の馴染みのそば・うどん店よりも丸味があることに驚いた。それに「みがきにしん」もおいしいではないか?そして今回、いただいたお持ち帰り用の「にしんそば」が、思った以上に南座隣のあまりにも普通の店である『松葉』そのものの味であることに、これまたもっと驚いた。お持ち帰りなのにここまでの味とはさすがに老舗である。
年明けに、愛知県人なのに先島諸島住民で、しかも京言葉を使う若い衆にいただいたものの中に京都市、『松葉』の「しんそば」があった。初めて京都に行ったときは、まだ市電があった。家族にお金を渡せされて、京都で頼まれた買い物をして帰郷した。『いずう』でやたら高い「さばずし」を買い、デパートで漬物を買い、四条下がって南座横の『松葉』で「みがきにしん」のたいたものを買い、ついでに『松葉』で「にしんそば」を食べた。東京の黒い黒い醤油のつゆでもなく、徳島・香川のしゃきっとした塩味がちなつゆでもない、丸みのある味に驚いた。「みがきにしん」は弱冠二十歳のボクにはよさがわからなかった。ここ15年ほど、京都の夜は居酒屋ではなく、西陣のそば・うどん店で酒を飲み、しめに「にしんそば」と「にしんうどん」を食べることが多い。「みがきにしん」はうどんには合わないことを知り、西陣の『えびや』の「みがきにしん」は京都でもいちばんうまいなんて思っていたのだ。2018年にもういちど『松葉』に立ち寄って恥ずかしげもなく「にしんそば」を食べたら、つゆの味が西陣の馴染みのそば・うどん店よりも丸味があることに驚いた。それに「みがきにしん」もおいしいではないか?そして今回、いただいたお持ち帰り用の「にしんそば」が、思った以上に南座隣のあまりにも普通の店である『松葉』そのものの味であることに、これまたもっと驚いた。お持ち帰りなのにここまでの味とはさすがに老舗である。 徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光町)で「そろ」と呼ばれていた竹製の道具がある。同地では子供がジンゾク(カワヨシノボリ)などの小魚をとる道具であった。筆者が4、5歳くらいから小学校低学年くらいまで魚とりに使っていたが、これが同町では当たり前のことだった。また著者の家は荒物雑貨などを売る商店だったが、「そろ」も商品として売っていた。我が家の商圏は現つるぎ町と美馬町(現美馬市美馬町)なので、「そろ」という言語は最低でも美馬郡全域で使われていたのだと考えている。写真は大分県日田市で購入したものだが、「えびしょうけ」という。これが我が故郷の「そろ」だ。古く「笊籠」を「そうり」と呼んだという。北陸・西日本で「そうけ」、「そーけ」、九州で「しょうけ」、「しょけ」、沖縄で「そーき」、「じょーき」という。「そろ」は、北陸・西日本の「そうけ」、「そーけ」の変化のひとつだと思われる。以上は、すべて笊(ざる)の呼称で、竹で編んだ容器の総称でもある。丸いものを盆笊、とか四角いものを角笊とかいうし、大型の箕(み)もある。水を切ったり、作物を入れたり、運んだりする。「そろ」は非常に頑丈で1960年前後には土木作業のじゃりを運ぶのにも使われていた。手を入れる四角い穴があるのも特徴である。九州大分県日田のものは、貞光町のものとまったく同じものである。「えびしょうけ」は「エビをとるための笊」という意味だろう。貞光町では「そろ」というが、同鷲敷町(現那賀町)南川・中山川周辺では「つつみ」と言う。徳島県阿南市羽ノ浦町古庄では「米けんど」というのかも知れない。羽ノ浦町では盛んに淡水魚を食べていて、岸辺の葦の間にいる魚をすくうのに使用していたようだ。貞光町ではもっぱら子供の漁具であり、大人が魚をとるために使っていたという記憶がない。とった淡水生物は家庭によっては食べていたのかも知れない。「そろ」でとれる魚を鶏の餌にしていた家もある。羽ノ浦町では用水路のエビ(テナガエビもしくはスジエビ)、フナなど小魚をとり、食用としていた。子供が使う漁具でもあっただろうと思うが、大人が日常の食べ物である淡水魚をとる漁具でもあったのだ。参考文献/『民具の事典』(監修/岩井宏實、編/工藤員功、作画/中林啓治 河出書房新社 2008)、『聞書き 徳島の食事』(農文協)
徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光町)で「そろ」と呼ばれていた竹製の道具がある。同地では子供がジンゾク(カワヨシノボリ)などの小魚をとる道具であった。筆者が4、5歳くらいから小学校低学年くらいまで魚とりに使っていたが、これが同町では当たり前のことだった。また著者の家は荒物雑貨などを売る商店だったが、「そろ」も商品として売っていた。我が家の商圏は現つるぎ町と美馬町(現美馬市美馬町)なので、「そろ」という言語は最低でも美馬郡全域で使われていたのだと考えている。写真は大分県日田市で購入したものだが、「えびしょうけ」という。これが我が故郷の「そろ」だ。古く「笊籠」を「そうり」と呼んだという。北陸・西日本で「そうけ」、「そーけ」、九州で「しょうけ」、「しょけ」、沖縄で「そーき」、「じょーき」という。「そろ」は、北陸・西日本の「そうけ」、「そーけ」の変化のひとつだと思われる。以上は、すべて笊(ざる)の呼称で、竹で編んだ容器の総称でもある。丸いものを盆笊、とか四角いものを角笊とかいうし、大型の箕(み)もある。水を切ったり、作物を入れたり、運んだりする。「そろ」は非常に頑丈で1960年前後には土木作業のじゃりを運ぶのにも使われていた。手を入れる四角い穴があるのも特徴である。九州大分県日田のものは、貞光町のものとまったく同じものである。「えびしょうけ」は「エビをとるための笊」という意味だろう。貞光町では「そろ」というが、同鷲敷町(現那賀町)南川・中山川周辺では「つつみ」と言う。徳島県阿南市羽ノ浦町古庄では「米けんど」というのかも知れない。羽ノ浦町では盛んに淡水魚を食べていて、岸辺の葦の間にいる魚をすくうのに使用していたようだ。貞光町ではもっぱら子供の漁具であり、大人が魚をとるために使っていたという記憶がない。とった淡水生物は家庭によっては食べていたのかも知れない。「そろ」でとれる魚を鶏の餌にしていた家もある。羽ノ浦町では用水路のエビ(テナガエビもしくはスジエビ)、フナなど小魚をとり、食用としていた。子供が使う漁具でもあっただろうと思うが、大人が日常の食べ物である淡水魚をとる漁具でもあったのだ。参考文献/『民具の事典』(監修/岩井宏實、編/工藤員功、作画/中林啓治 河出書房新社 2008)、『聞書き 徳島の食事』(農文協) 東京湾(江戸湾)ならではの脚立釣りは江戸時代より続く伝統釣法である。昭和38年7月(1963)、海苔、貝の漁場である十万坪(現浦安市今川・高洲で東京ディズニーランドの東)でのアオギス脚立釣りの光景。脚立は今ではアルミ製だが、この時代までは木製で、大阪では「クラカケ(鞍掛)」というと、魚類学者の田中茂穂は述べている。船宿で釣り人はよい釣り場を確保するためにクジをひく。釣り場が決まれば、港から脚立と釣り人を乗せて沖に向かう。次々に釣り場を巡り、脚立を設置して、釣り人を下ろしていく。昼になると船宿から弁当を取り寄せるなど、長々と海の上での釣りを楽しんでいた。(写真は浦安市郷土博物館 所蔵のものをお借りした)浦安の沖の十万坪といえば、山本周五郎の「青べか物語」にも登場する。東京湾の豊かさを感じる場所(浅瀬)でもあった。一般的なキスであるシロギスと比べると長さで倍以上もある大型魚であり、釣り味を楽しんだ。脚立釣りは食べるための釣りではなく、スポーツフィッシングといったものだったようだ。脚立釣りが好きだった、三代目三遊亭金馬(1894年(明治27年)〜1964年(昭和39)は著書で〈食べちゃ青ギスより白ギスのほうがうまい。職業釣り師は青ギスにめをつけない。だから町の魚屋には青ギスは売ってない。白ギスばかりだ〉『江戸前の釣り』(三代目三遊亭金馬)音に敏感なアオギスは船では釣れないので、海に脚立を立てるようになったという。脚立周りを1本の竿、道糸ハリスで釣り上げるので、アオギス専用の船釣りと比べると長い竿を使い、魚籠も網の部分が非常に長い独特のものだった。シロギスがやや外洋性であるのに対して、アオギスは川の河口域である汽水域や内湾を好むので、東京湾はアオギス釣りのメッカであったことがわかる。江戸時代や幸田露伴の明治には大川(隅田川)で行われていた脚立釣りが、昭和になると江戸川の向こう側、浦安などが主流になってくる。本種がいかに環境の変化に弱いかが、この事実からもわかる。脚立釣りは高度成長期にアオギスの減少とともに行われなくなり、やがてアオギスは東京湾から姿を消す。
東京湾(江戸湾)ならではの脚立釣りは江戸時代より続く伝統釣法である。昭和38年7月(1963)、海苔、貝の漁場である十万坪(現浦安市今川・高洲で東京ディズニーランドの東)でのアオギス脚立釣りの光景。脚立は今ではアルミ製だが、この時代までは木製で、大阪では「クラカケ(鞍掛)」というと、魚類学者の田中茂穂は述べている。船宿で釣り人はよい釣り場を確保するためにクジをひく。釣り場が決まれば、港から脚立と釣り人を乗せて沖に向かう。次々に釣り場を巡り、脚立を設置して、釣り人を下ろしていく。昼になると船宿から弁当を取り寄せるなど、長々と海の上での釣りを楽しんでいた。(写真は浦安市郷土博物館 所蔵のものをお借りした)浦安の沖の十万坪といえば、山本周五郎の「青べか物語」にも登場する。東京湾の豊かさを感じる場所(浅瀬)でもあった。一般的なキスであるシロギスと比べると長さで倍以上もある大型魚であり、釣り味を楽しんだ。脚立釣りは食べるための釣りではなく、スポーツフィッシングといったものだったようだ。脚立釣りが好きだった、三代目三遊亭金馬(1894年(明治27年)〜1964年(昭和39)は著書で〈食べちゃ青ギスより白ギスのほうがうまい。職業釣り師は青ギスにめをつけない。だから町の魚屋には青ギスは売ってない。白ギスばかりだ〉『江戸前の釣り』(三代目三遊亭金馬)音に敏感なアオギスは船では釣れないので、海に脚立を立てるようになったという。脚立周りを1本の竿、道糸ハリスで釣り上げるので、アオギス専用の船釣りと比べると長い竿を使い、魚籠も網の部分が非常に長い独特のものだった。シロギスがやや外洋性であるのに対して、アオギスは川の河口域である汽水域や内湾を好むので、東京湾はアオギス釣りのメッカであったことがわかる。江戸時代や幸田露伴の明治には大川(隅田川)で行われていた脚立釣りが、昭和になると江戸川の向こう側、浦安などが主流になってくる。本種がいかに環境の変化に弱いかが、この事実からもわかる。脚立釣りは高度成長期にアオギスの減少とともに行われなくなり、やがてアオギスは東京湾から姿を消す。 山陰でホソトビウオを「ニュウバイトビ(入梅飛)」などという。ツクシトビウオの角飛と同じ、6月くらいからまとまってとれるもので、産卵を控えて生殖巣を膨らませている。山陰などでは真子をパック詰めで売っていたりする本州日本海側は青森県くらいまでで産卵回遊の2種のトビウオが揚がる。まとまって揚がるので煮干しや焼き干しなども作られている。島根県松江市の名物「あご野焼(焼き竹輪)」などもあるし、各種練り製品の原料にもなる。国内のトビウオの食文化といえば昔はこの、産卵回遊群がもたらすものだとばかり思っていた。この考え方は鹿児島屋久島に行くまで心の隅から離れなかった。屋久島行以前には鹿児島市内で「七島とび(トビウオの塩干)」を発見している。干ものというよりも塩の塊のようで、明らかに冷蔵庫以前の時代からの加工品である。屋久島では種類の多さに圧倒され、当然のことだが、日常的にトビウオが食べられていることにも驚かされた。今年は、長崎県平戸市の漁師、福畑敏光さんに夏から秋の「小トビ漁」のトビウオ類を送って頂き、長崎県でのトビウオの世界の、幅の広さに驚かされた。漁の後半にさしかかったときに送ってもらったところ、すべてが小振りで、ホソアオトビ、バショウトビウオ、シロフチトビウオ、アリアケトビウオの4種類が入っていたのだ。8月25日から10月半ばの漁期にはもっと多彩な種の比較的若いトビウオ類が入る模様である。これを平戸市では練り製品を作り、干ものにし、焼きあごにする。いろいろ試してみたいが、まず今回は煮干しを買ってみた。実はこの煮干しこそ、カツオ節を生む母体であり、国内水産加工業のなかでも重要な鍵となるものだと考えている。ボクは子供の頃から煮干し文化圏にいたので、いい煮干しを見るだけで嬉しくなる。今回の林水産の煮干しなど香りからして素晴らしい。同定してみると、ホソアオトビとシロフチトビウオまではわかったが、あとは同定不能だった。想像になるが、ツクシトビウオとホソトビウオの若い個体、ホソアオトビ、シロフチトビウオ、アリアケトビウオが平戸の煮干し原料だと思うのだが、できれば加工前に確かめたい。
山陰でホソトビウオを「ニュウバイトビ(入梅飛)」などという。ツクシトビウオの角飛と同じ、6月くらいからまとまってとれるもので、産卵を控えて生殖巣を膨らませている。山陰などでは真子をパック詰めで売っていたりする本州日本海側は青森県くらいまでで産卵回遊の2種のトビウオが揚がる。まとまって揚がるので煮干しや焼き干しなども作られている。島根県松江市の名物「あご野焼(焼き竹輪)」などもあるし、各種練り製品の原料にもなる。国内のトビウオの食文化といえば昔はこの、産卵回遊群がもたらすものだとばかり思っていた。この考え方は鹿児島屋久島に行くまで心の隅から離れなかった。屋久島行以前には鹿児島市内で「七島とび(トビウオの塩干)」を発見している。干ものというよりも塩の塊のようで、明らかに冷蔵庫以前の時代からの加工品である。屋久島では種類の多さに圧倒され、当然のことだが、日常的にトビウオが食べられていることにも驚かされた。今年は、長崎県平戸市の漁師、福畑敏光さんに夏から秋の「小トビ漁」のトビウオ類を送って頂き、長崎県でのトビウオの世界の、幅の広さに驚かされた。漁の後半にさしかかったときに送ってもらったところ、すべてが小振りで、ホソアオトビ、バショウトビウオ、シロフチトビウオ、アリアケトビウオの4種類が入っていたのだ。8月25日から10月半ばの漁期にはもっと多彩な種の比較的若いトビウオ類が入る模様である。これを平戸市では練り製品を作り、干ものにし、焼きあごにする。いろいろ試してみたいが、まず今回は煮干しを買ってみた。実はこの煮干しこそ、カツオ節を生む母体であり、国内水産加工業のなかでも重要な鍵となるものだと考えている。ボクは子供の頃から煮干し文化圏にいたので、いい煮干しを見るだけで嬉しくなる。今回の林水産の煮干しなど香りからして素晴らしい。同定してみると、ホソアオトビとシロフチトビウオまではわかったが、あとは同定不能だった。想像になるが、ツクシトビウオとホソトビウオの若い個体、ホソアオトビ、シロフチトビウオ、アリアケトビウオが平戸の煮干し原料だと思うのだが、できれば加工前に確かめたい。 松尾芭蕉(青桃)が延宝5年(1677)冬に吟じた【あら何ともなや昨日は過ぎてふくと汁】は江戸で行われた句会のときのもので、『江戸三吟』として出版されている。「三吟」は松尾芭蕉、山口素堂、伊藤信徳である。江戸時代にフグは「ふくと」、「ふくべ」などと呼ばれていた。この句はフグという魚の危険性を表すときによく引用されるが、むしろ杉山杉風など魚河岸にも弟子がいた芭蕉なので、普段からフグを食べつけていたのではないかと思われる。江戸時代は今よりも寒冷だったので江戸湾をはじめ周辺海域では秋から冬にはショウサイフグ、春にはヒガンフグがとれていたはずである。今現在のように相模湾でしばしばトラフグが揚がるような状況ではなかった。トラフグは昭和になっても西の魚で、江戸の魚河岸には並ぶことは希だったと思われる。中でも取り分けショウサイフグは江戸湾にたくさんいた魚なので江戸前の魚そのもので、この「ふくと汁」は決して上等なものではなく、下手なものではなかったか? だから芭蕉は微かにはにかんで句を吟じ、一緒にいた山口素堂などもそのあたりがわかっていた。ちなみにあっさり薄味ではなく、濃厚な塩辛いみそを溶き込んだ、フグ類のみそ汁はやたらにうまいし、体が温まる。「ふくと汁」が最初に出てくるだけで、座に温か味が生まれたのではないか、と思う。また、江戸時代前期、江戸の街で醤油は一般的ではなかった。民俗学者、瀬川清子は昭和になっても地方で醤油は高級だったとしている。とすると調味料は塩かみそだ。直感でしかないがみそと考えた。江戸時代前期から江戸の街で冬に食べられていた「ふくと汁」は、ショウサイフグのみそ汁で間違いないと考えている
松尾芭蕉(青桃)が延宝5年(1677)冬に吟じた【あら何ともなや昨日は過ぎてふくと汁】は江戸で行われた句会のときのもので、『江戸三吟』として出版されている。「三吟」は松尾芭蕉、山口素堂、伊藤信徳である。江戸時代にフグは「ふくと」、「ふくべ」などと呼ばれていた。この句はフグという魚の危険性を表すときによく引用されるが、むしろ杉山杉風など魚河岸にも弟子がいた芭蕉なので、普段からフグを食べつけていたのではないかと思われる。江戸時代は今よりも寒冷だったので江戸湾をはじめ周辺海域では秋から冬にはショウサイフグ、春にはヒガンフグがとれていたはずである。今現在のように相模湾でしばしばトラフグが揚がるような状況ではなかった。トラフグは昭和になっても西の魚で、江戸の魚河岸には並ぶことは希だったと思われる。中でも取り分けショウサイフグは江戸湾にたくさんいた魚なので江戸前の魚そのもので、この「ふくと汁」は決して上等なものではなく、下手なものではなかったか? だから芭蕉は微かにはにかんで句を吟じ、一緒にいた山口素堂などもそのあたりがわかっていた。ちなみにあっさり薄味ではなく、濃厚な塩辛いみそを溶き込んだ、フグ類のみそ汁はやたらにうまいし、体が温まる。「ふくと汁」が最初に出てくるだけで、座に温か味が生まれたのではないか、と思う。また、江戸時代前期、江戸の街で醤油は一般的ではなかった。民俗学者、瀬川清子は昭和になっても地方で醤油は高級だったとしている。とすると調味料は塩かみそだ。直感でしかないがみそと考えた。江戸時代前期から江戸の街で冬に食べられていた「ふくと汁」は、ショウサイフグのみそ汁で間違いないと考えている おはじき(御弾、お弾、オハジキ)は、大言海に〈細螺ノ介殻ヲ指先ニテ弾ク、小兒ノ遊戯〉とある。古くから浜の落ちている貝殻の美しい物を拾い、指ではじいて遊んだもの。本来日本各地で身近にある小型の貝などで遊んだものだが、今ではガラス製となっている。ガラス製のものは、1960年代くらいまではいたって普通の玩具で、夜店やおもちゃ屋、文具店などで売られていた。実際に女児、女性が指ではじいて遊んでいたのをおぼえている。今では100円ショップなどにもあるが、実際に遊ぶために売られているのかわからない。〈幾左古 正字は未詳 思うに幾左古は状蝸牛に似ているが、厚く堅くて彩文がある。殻の中には寄居虫(ごうな/ヤドカリ)のような虫がいる。伊勢・尾張および東海の諸浜に多くいる。土地の人は虫を取り去って洗浄し、これを玩具とする。〉『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)おはじきに使われた貝類は、〈シャゴ(キサゴ)《伊予大三島北部》 スヰビウシ(ハナマルユキ)《奄美》 ネコジャ(メダカラ、オミナエシダカラ)《千葉県安房郡鋸南町岩井袋》〉『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社 1988)たくさんとれて小さいもので遊んでいたことがわかる。〈この頃のこどもはどうか知らないが、年配の方なら大てい小さいころ、キサゴ(標準和名のキサゴ)のおはじきで遊んだ記憶がおありだろう〉。『原色・自然の手帳 日本の貝』(奥谷喬司、竹村嘉夫 講談社 1967) 奥谷喬司は1930年福岡県北九州市門司出身である。
おはじき(御弾、お弾、オハジキ)は、大言海に〈細螺ノ介殻ヲ指先ニテ弾ク、小兒ノ遊戯〉とある。古くから浜の落ちている貝殻の美しい物を拾い、指ではじいて遊んだもの。本来日本各地で身近にある小型の貝などで遊んだものだが、今ではガラス製となっている。ガラス製のものは、1960年代くらいまではいたって普通の玩具で、夜店やおもちゃ屋、文具店などで売られていた。実際に女児、女性が指ではじいて遊んでいたのをおぼえている。今では100円ショップなどにもあるが、実際に遊ぶために売られているのかわからない。〈幾左古 正字は未詳 思うに幾左古は状蝸牛に似ているが、厚く堅くて彩文がある。殻の中には寄居虫(ごうな/ヤドカリ)のような虫がいる。伊勢・尾張および東海の諸浜に多くいる。土地の人は虫を取り去って洗浄し、これを玩具とする。〉『和漢三才図会』(寺島良安 正徳3年/1713 東洋文庫 平凡社)おはじきに使われた貝類は、〈シャゴ(キサゴ)《伊予大三島北部》 スヰビウシ(ハナマルユキ)《奄美》 ネコジャ(メダカラ、オミナエシダカラ)《千葉県安房郡鋸南町岩井袋》〉『日本貝類方言集 民俗・分布・由来』(川名興 未来社 1988)たくさんとれて小さいもので遊んでいたことがわかる。〈この頃のこどもはどうか知らないが、年配の方なら大てい小さいころ、キサゴ(標準和名のキサゴ)のおはじきで遊んだ記憶がおありだろう〉。『原色・自然の手帳 日本の貝』(奥谷喬司、竹村嘉夫 講談社 1967) 奥谷喬司は1930年福岡県北九州市門司出身である。 山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる。東北や新潟県では大黒様が嫁を取りの日ともされており、「大黒様の嫁取り」、「大黒様の祝言」ともいう。大黒は豊穣の神として民間信仰の対象である。豆や豆腐、大根などには五穀豊穣・子孫繁栄を祈るという意味があるのだろう。ちなみに庄内地方の「まっか大根」は二股になった大根のことで、お供えにする。膳には主に豆料理と大根を使ったなます、そしてハタハタの田楽が並ぶ。スーパーなどには数日前から「ハタハタの田楽」と豆料理、また「大黒様のお年夜」用のセットが売られる。古くは家庭で作ったものかも知れないが、今では鮮魚店・スーパーなどで買うものとなっている。■左上から「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」、「黒豆煮」、中央中「黒豆のなます」、「豆腐の田楽」、下左「黒豆ごはん」、「納豆汁」。膳の右側にあるのが「こめいり(おこしともいう。これをを固めたもの、ばらのものもある)」。明らかに子孫繁栄をいのる祭事である。
山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる。東北や新潟県では大黒様が嫁を取りの日ともされており、「大黒様の嫁取り」、「大黒様の祝言」ともいう。大黒は豊穣の神として民間信仰の対象である。豆や豆腐、大根などには五穀豊穣・子孫繁栄を祈るという意味があるのだろう。ちなみに庄内地方の「まっか大根」は二股になった大根のことで、お供えにする。膳には主に豆料理と大根を使ったなます、そしてハタハタの田楽が並ぶ。スーパーなどには数日前から「ハタハタの田楽」と豆料理、また「大黒様のお年夜」用のセットが売られる。古くは家庭で作ったものかも知れないが、今では鮮魚店・スーパーなどで買うものとなっている。■左上から「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」、「黒豆煮」、中央中「黒豆のなます」、「豆腐の田楽」、下左「黒豆ごはん」、「納豆汁」。膳の右側にあるのが「こめいり(おこしともいう。これをを固めたもの、ばらのものもある)」。明らかに子孫繁栄をいのる祭事である。全11件中 全レコードを表示しています