コラム検索
検索条件
該当するコラムが多い為ページを分割して表示します。
全111コラム中 1番目~100番目までを表示中
- 1
- 2
 2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。放射線量は0.2μSv/hとかだけど、これはほぼゼロに近い数値だと思われる。原発事故は未だに続いているが、放射線の脅威は現状ではないということだろう。さて相馬市の相馬という言語、また言語のもとになった相馬氏の歴史は古い。相馬氏は国内でももっとも古い家だ。桓武平氏で、平安時代、後三年の役(1083-1087)に戦功をたて下総千葉郡に下って千葉氏が生まれるが、その庶流になる。房総平氏(平家ではない)は関東に広がった平氏の一群でほかには秩父平氏、相模平氏の武士群が存在した。もちろん源義家とその弟、義満、藤原秀郷などの子孫が関東に勢力を持つ。相馬氏の祖は下総相馬郡をおさめて相馬を名乗り、奥州合戦(奥州藤原氏と源頼朝のたたかい)、南北朝の闘いで手柄を立てて現在の南相馬市、相馬市に定着する相馬氏は平安時代、鎌倉時代源氏・北条執権時代を生き抜き、南北朝時代の戦乱も、戦乱に次ぐ戦乱の室町時代も息抜き、徳川時代になって相馬、中村藩の藩主となり明治まで続く。
2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。放射線量は0.2μSv/hとかだけど、これはほぼゼロに近い数値だと思われる。原発事故は未だに続いているが、放射線の脅威は現状ではないということだろう。さて相馬市の相馬という言語、また言語のもとになった相馬氏の歴史は古い。相馬氏は国内でももっとも古い家だ。桓武平氏で、平安時代、後三年の役(1083-1087)に戦功をたて下総千葉郡に下って千葉氏が生まれるが、その庶流になる。房総平氏(平家ではない)は関東に広がった平氏の一群でほかには秩父平氏、相模平氏の武士群が存在した。もちろん源義家とその弟、義満、藤原秀郷などの子孫が関東に勢力を持つ。相馬氏の祖は下総相馬郡をおさめて相馬を名乗り、奥州合戦(奥州藤原氏と源頼朝のたたかい)、南北朝の闘いで手柄を立てて現在の南相馬市、相馬市に定着する相馬氏は平安時代、鎌倉時代源氏・北条執権時代を生き抜き、南北朝時代の戦乱も、戦乱に次ぐ戦乱の室町時代も息抜き、徳川時代になって相馬、中村藩の藩主となり明治まで続く。 胎内市中条は街歩きのできる貴重なところだった。商店街が生きているのがいい。こんなところに来たら、何をやるのか?ただただ歩くだけ、それで充分楽しい。歩きながら和菓子屋を見つけたら片っ端から買い求めようとしたが、なんだか中条町の和菓子屋は和菓子屋のようで和菓子屋のようでなく、洋菓子屋のようで、洋菓子屋のようでもない。これと同じ感じは根室にもあった。そろそろ新潟市に向かおうかと中心地から少し外れたところに、また和菓子屋があって、入ると洋菓子屋だった。新潟県の菓子店の特徴は和洋がはっきりしないこと、かも知れない。そこで買ったのが、久しぶりに出合った「たぬきケーキ」、そして「ロックケーキ」だ。考えてみると「たぬきケーキ」は千葉県以来ではないか。要するにタヌキの形をしていれば、「たぬきケーキ」だということがわかってきた。周りが少し硬い生地で中がカステラ、上にクリーム(これなんていうんだろう)で頭を造り、繋がった目と鼻と尾がある。そんなに出合っているわけではないが、このタイプは初めてだ。
胎内市中条は街歩きのできる貴重なところだった。商店街が生きているのがいい。こんなところに来たら、何をやるのか?ただただ歩くだけ、それで充分楽しい。歩きながら和菓子屋を見つけたら片っ端から買い求めようとしたが、なんだか中条町の和菓子屋は和菓子屋のようで和菓子屋のようでなく、洋菓子屋のようで、洋菓子屋のようでもない。これと同じ感じは根室にもあった。そろそろ新潟市に向かおうかと中心地から少し外れたところに、また和菓子屋があって、入ると洋菓子屋だった。新潟県の菓子店の特徴は和洋がはっきりしないこと、かも知れない。そこで買ったのが、久しぶりに出合った「たぬきケーキ」、そして「ロックケーキ」だ。考えてみると「たぬきケーキ」は千葉県以来ではないか。要するにタヌキの形をしていれば、「たぬきケーキ」だということがわかってきた。周りが少し硬い生地で中がカステラ、上にクリーム(これなんていうんだろう)で頭を造り、繋がった目と鼻と尾がある。そんなに出合っているわけではないが、このタイプは初めてだ。 あじ(マアジ)の開き干しの頭は開いた方がいいのか、そのままの方がいいのか?どちらでもいいのだけど、頭を割らない開き干しを見ると西日本のものだろうと思ったりする、この地域性がとても重要だ。高知県の開き干しは頭を落として開いたりもするが、この頭そのままが多いようだ。しかもこの黒潮町の開き干しは絶品なのだ。塩加減がまさにちょうどいいし、鮮度がいいもので作ったのか、ボクの苦手な酸化による苦みがない。塩慣れしているので、うま味が増していて、ご飯に乗せて食うとやたらにいい。甘味のあるご飯と相乗効果を産む。ちなみに高知県の干ものに土佐市白木果樹園の「ぶっしゅかん(モチユ)」をたっぷり搾る。干ものに酢みかんとはいい夫婦のようなものだ。
あじ(マアジ)の開き干しの頭は開いた方がいいのか、そのままの方がいいのか?どちらでもいいのだけど、頭を割らない開き干しを見ると西日本のものだろうと思ったりする、この地域性がとても重要だ。高知県の開き干しは頭を落として開いたりもするが、この頭そのままが多いようだ。しかもこの黒潮町の開き干しは絶品なのだ。塩加減がまさにちょうどいいし、鮮度がいいもので作ったのか、ボクの苦手な酸化による苦みがない。塩慣れしているので、うま味が増していて、ご飯に乗せて食うとやたらにいい。甘味のあるご飯と相乗効果を産む。ちなみに高知県の干ものに土佐市白木果樹園の「ぶっしゅかん(モチユ)」をたっぷり搾る。干ものに酢みかんとはいい夫婦のようなものだ。 吉野川の支流である貞光川(徳島県美馬郡つるぎ町)は今、明らかに不健康というか重い病気にかかった状況にある。たぶんもう取り返しがつかないと思うが、今に残るものを少しずつ整理してきたい。非常に健全であったときの貞光川を知っている人は今やほとんどいない。ただ1960年代、小さい川であるが長い上流域があり、短い中流域があり、吉野川との合流近くは下流域に近い環境であった。それが今やかなり奥(上流)の旧端山村あたりまで行かないと中流域の環境ではなくなっている。山が荒れているので吉野川合流地点から貞光市街地の端、木綿麻橋(ゆうまばし)くらいまでの川原が荒廃してしまっている。この市街地周辺の流域にもいたオオヨシノボリは、木綿麻橋の上流域に行かないと見られないのだと思う。岸に植えられた竹の枝がたわむくらいいたホタルはまだいるのだろうか?吉野川の大川に対して小川(こがわ)と呼ばれていた貞光川にいなかったニゴイが、わんさかいるのも不気味だ。この原因は明らかである。剣山周辺の森林の荒廃と自然環境を考えない護岸である。人間は自分の住む区域(生活圏)を暴力的に広げ、針葉樹の無理な植林をし、森林管理を放棄している。その結果、川の生き物の種類が減り、川原も川底も泥だらけになった。現在の貞光川には歴史的遺産が残り、美しかったときの名残はわずかしかない。過去に見つけたのは2つ。そのひとつが「かんのう」、そして青石の構造物だ。
吉野川の支流である貞光川(徳島県美馬郡つるぎ町)は今、明らかに不健康というか重い病気にかかった状況にある。たぶんもう取り返しがつかないと思うが、今に残るものを少しずつ整理してきたい。非常に健全であったときの貞光川を知っている人は今やほとんどいない。ただ1960年代、小さい川であるが長い上流域があり、短い中流域があり、吉野川との合流近くは下流域に近い環境であった。それが今やかなり奥(上流)の旧端山村あたりまで行かないと中流域の環境ではなくなっている。山が荒れているので吉野川合流地点から貞光市街地の端、木綿麻橋(ゆうまばし)くらいまでの川原が荒廃してしまっている。この市街地周辺の流域にもいたオオヨシノボリは、木綿麻橋の上流域に行かないと見られないのだと思う。岸に植えられた竹の枝がたわむくらいいたホタルはまだいるのだろうか?吉野川の大川に対して小川(こがわ)と呼ばれていた貞光川にいなかったニゴイが、わんさかいるのも不気味だ。この原因は明らかである。剣山周辺の森林の荒廃と自然環境を考えない護岸である。人間は自分の住む区域(生活圏)を暴力的に広げ、針葉樹の無理な植林をし、森林管理を放棄している。その結果、川の生き物の種類が減り、川原も川底も泥だらけになった。現在の貞光川には歴史的遺産が残り、美しかったときの名残はわずかしかない。過去に見つけたのは2つ。そのひとつが「かんのう」、そして青石の構造物だ。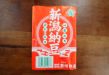 納豆は上京して初めて見たなんていうボクがいうのもなんだけど、地納豆が好きだ。大手もいいけど、地納豆が消えたら嫌だと思っている。ボクは昔々から、地域と地域性と地域力を調べている。東日本では食の地域力という点で、納豆は欠かすことが出来ない。新潟県は取り分け納豆製造業者が多かったようだ。それが激減したといっても、スーパーには必ず地納豆があるのがいい。県庁所在地新潟市の中心地域に3つも業者があるなんて新潟以外にはない。新潟納豆 高橋商店 新潟県新潟市
納豆は上京して初めて見たなんていうボクがいうのもなんだけど、地納豆が好きだ。大手もいいけど、地納豆が消えたら嫌だと思っている。ボクは昔々から、地域と地域性と地域力を調べている。東日本では食の地域力という点で、納豆は欠かすことが出来ない。新潟県は取り分け納豆製造業者が多かったようだ。それが激減したといっても、スーパーには必ず地納豆があるのがいい。県庁所在地新潟市の中心地域に3つも業者があるなんて新潟以外にはない。新潟納豆 高橋商店 新潟県新潟市 10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。この年で子供と夢中で遊んで、その果てに疲れすぎて、楽しすぎてぼろぼろになる、なんてやってていいのかどうかわからないが、とにかく疲れた。それでも400キロ以上の距離を自宅に帰らなければならない。ボクの場合、できるだけ旅先でものを買う。高速道路上では食べない、飲料水を買わない、が基本なので、旅先で食べ物を持ち帰る。
10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。この年で子供と夢中で遊んで、その果てに疲れすぎて、楽しすぎてぼろぼろになる、なんてやってていいのかどうかわからないが、とにかく疲れた。それでも400キロ以上の距離を自宅に帰らなければならない。ボクの場合、できるだけ旅先でものを買う。高速道路上では食べない、飲料水を買わない、が基本なので、旅先で食べ物を持ち帰る。 緑茶の番茶(遅摘みで枝なども入っている)や、早い摘みでも葉の大きさを揃えず枝などが入っているものを「柳茶」というのだ、ということを知らなかった。文字の専門家に聞いたら、それは一般的な言語だというので、恥じ入る思いがした。ボクが普段飲んでいるお茶もこの柳茶である。我が家で飲んでいるお茶はこのタイプが年5㎏くらい、上煎茶は1㎏弱、ほうじ茶も1㎏弱だ。凍頂ウーロン茶に、紅茶も飲むが、非常に少ない。この柳茶は淹れる最適温度の幅が広く、いい加減でもいい。上煎茶ほど刺激が強くないので、上煎茶やコーヒーを朝から飲むと障害が出るボクにはこれ以上のものはない。
緑茶の番茶(遅摘みで枝なども入っている)や、早い摘みでも葉の大きさを揃えず枝などが入っているものを「柳茶」というのだ、ということを知らなかった。文字の専門家に聞いたら、それは一般的な言語だというので、恥じ入る思いがした。ボクが普段飲んでいるお茶もこの柳茶である。我が家で飲んでいるお茶はこのタイプが年5㎏くらい、上煎茶は1㎏弱、ほうじ茶も1㎏弱だ。凍頂ウーロン茶に、紅茶も飲むが、非常に少ない。この柳茶は淹れる最適温度の幅が広く、いい加減でもいい。上煎茶ほど刺激が強くないので、上煎茶やコーヒーを朝から飲むと障害が出るボクにはこれ以上のものはない。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。浅い砂地にいるのがアサリだ。アサリは琉球列島以外の干潟や浅い内湾に普通に見られる。国内でもっとも人気のある二枚貝である。残念なことに年々国内での生息数が減っている。新川漁港周辺にはどうやらそんなにたくさんはいないようだが、面白い色をしている。写真は五十嵐浜のものだが、成長が悪いようで貝殻の長さが短い。ちなみにアサリは横から見て円に近いほど生育が悪く、ラグビーボールのような楕円形の方が生育がいい。念のために、砂地でアサリの生育が悪いと言うことは、そこの水質がいいということに他ならない。たぶん真水が流れ込む新川に近いところにいるアサリは、貝殻が長いと想像する。次回は新川寄りで生き物探しをしいたいものである。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。浅い砂地にいるのがアサリだ。アサリは琉球列島以外の干潟や浅い内湾に普通に見られる。国内でもっとも人気のある二枚貝である。残念なことに年々国内での生息数が減っている。新川漁港周辺にはどうやらそんなにたくさんはいないようだが、面白い色をしている。写真は五十嵐浜のものだが、成長が悪いようで貝殻の長さが短い。ちなみにアサリは横から見て円に近いほど生育が悪く、ラグビーボールのような楕円形の方が生育がいい。念のために、砂地でアサリの生育が悪いと言うことは、そこの水質がいいということに他ならない。たぶん真水が流れ込む新川に近いところにいるアサリは、貝殻が長いと想像する。次回は新川寄りで生き物探しをしいたいものである。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、あじ煮干し(マアジ煮干し)大と小を1袋ずつかった。小は見た目は悪いが、見た目のいい大よりも上とみた。値段は2つとも変わらないが、小でとっただしの方がうまい。煮干しは見て、1つ2つ食べてみて買うことにしているが、当日は時間がなかったのでそれが出来なかった。ただ、金曜市の煮干しはぜんぶよかった。日曜市にも店を出しているようなので、次回もこの店で買おう。あじ煮干しは頭と内臓を取る。2つ割りにする。我が家はから煎りしないが、煎ってもいい。これは好みの問題。ボクは煎ると煎った香りが余計な気がするだけ、昔昔は煎っていた。これを昆布と一緒に12時間以上浸しておく。これをゆるゆると温め、昆布を取りだして沸点手前まで熱くする。
9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、あじ煮干し(マアジ煮干し)大と小を1袋ずつかった。小は見た目は悪いが、見た目のいい大よりも上とみた。値段は2つとも変わらないが、小でとっただしの方がうまい。煮干しは見て、1つ2つ食べてみて買うことにしているが、当日は時間がなかったのでそれが出来なかった。ただ、金曜市の煮干しはぜんぶよかった。日曜市にも店を出しているようなので、次回もこの店で買おう。あじ煮干しは頭と内臓を取る。2つ割りにする。我が家はから煎りしないが、煎ってもいい。これは好みの問題。ボクは煎ると煎った香りが余計な気がするだけ、昔昔は煎っていた。これを昆布と一緒に12時間以上浸しておく。これをゆるゆると温め、昆布を取りだして沸点手前まで熱くする。 その町がまだ健在であることは、和菓子店、洋菓子店、パン屋があるかないかでわかる。内野町には和菓子店と、洋菓子店もあり、パン屋もある。駅そばにある『ブーランジェ ヨネヤマ』は、創業年はわからないが、とても懐かしいパンもあるし、初めて聞く名のパンもある。懐かし、新し、のパン屋だし、まるで洋菓子店のような感じもある。
その町がまだ健在であることは、和菓子店、洋菓子店、パン屋があるかないかでわかる。内野町には和菓子店と、洋菓子店もあり、パン屋もある。駅そばにある『ブーランジェ ヨネヤマ』は、創業年はわからないが、とても懐かしいパンもあるし、初めて聞く名のパンもある。懐かし、新し、のパン屋だし、まるで洋菓子店のような感じもある。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。そんなところにいるのがイボニシである。写真の個体はフジツボだらけでわからないが、貝殻はいぼいぼの突起が目立つので「疣螺(いぼにし)」という。江戸時代に作られた貝の図鑑である『目八譜』(1843年、武蔵石寿)にはきれいな呼び名が多いのに、なぜか本種だけはそのものズバリの名がついている。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。新川漁港の周辺には磯や護岸もある。そんなところにいるのがイボニシである。写真の個体はフジツボだらけでわからないが、貝殻はいぼいぼの突起が目立つので「疣螺(いぼにし)」という。江戸時代に作られた貝の図鑑である『目八譜』(1843年、武蔵石寿)にはきれいな呼び名が多いのに、なぜか本種だけはそのものズバリの名がついている。 10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。子供とその家族を自然とふれ合っていただくための催しだったが、ボクの方が遊んでもらったようだった。さて、夕闇迫る頃、疲れを取るためにスーパー ichimanの前で地元新潟市のアイスを食べた。改めて見ると、店の前でソフトクリームを食べている女子中学生らしきや、近所の主婦、金髪の若い衆などが集まっては散り、集まっては散っていく。ボクにもこんなときがあったものだ。地スーパーとしては理想的だと思っている。ボクの場合、たった一人ではあるが、地スーパーを応援している。例えば、新潟県下越には下越のものがあって、それこそがお土産になると思っている。地方で土産を買うなら、個人商店もしくは地スーパーがいい。
10月4日、越後新川、五十嵐浜で午前と午後、遊びに遊んだ。子供とその家族を自然とふれ合っていただくための催しだったが、ボクの方が遊んでもらったようだった。さて、夕闇迫る頃、疲れを取るためにスーパー ichimanの前で地元新潟市のアイスを食べた。改めて見ると、店の前でソフトクリームを食べている女子中学生らしきや、近所の主婦、金髪の若い衆などが集まっては散り、集まっては散っていく。ボクにもこんなときがあったものだ。地スーパーとしては理想的だと思っている。ボクの場合、たった一人ではあるが、地スーパーを応援している。例えば、新潟県下越には下越のものがあって、それこそがお土産になると思っている。地方で土産を買うなら、個人商店もしくは地スーパーがいい。 高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。「はぶ茶」の「はぶ草」の正体はわからない。ネットで調べると、マメ科ジャケツイバラ亜科センナ属のハブソウ、もしくは同じ属のエビスグサとなっている。専門家ではないので、原材料は不明のままとしたい。高知県にマメ科の「茶」は「きし豆茶」と「はぶ茶」があることがわかる。
高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。「はぶ茶」の「はぶ草」の正体はわからない。ネットで調べると、マメ科ジャケツイバラ亜科センナ属のハブソウ、もしくは同じ属のエビスグサとなっている。専門家ではないので、原材料は不明のままとしたい。高知県にマメ科の「茶」は「きし豆茶」と「はぶ茶」があることがわかる。 9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。通販をほとんど使わないボクには、段ボールから量り売りで買う煮干しがいちばんいい。味見できるし、好きな量買える。四国や西日本では当たり前のことだが、関東にはほぼない。せっかくなので売られている煮干しを全種類買い求めてきた。ボクが調べているのは地域と、地域性と、地域力だけど、高知を始め四国には多彩な煮干しという目立たないけど他の地域にはないものがある。これも重要な高知県を始めとする、四国の地域力だ。煮干しは日常的なものなので、帰宅してすぐからこの煮干し類を使い始める。まずは「あじ煮干し(マアジ煮干し)」から。大小合って大の方から使うが、大の方が安い。
9月半ば、高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。通販をほとんど使わないボクには、段ボールから量り売りで買う煮干しがいちばんいい。味見できるし、好きな量買える。四国や西日本では当たり前のことだが、関東にはほぼない。せっかくなので売られている煮干しを全種類買い求めてきた。ボクが調べているのは地域と、地域性と、地域力だけど、高知を始め四国には多彩な煮干しという目立たないけど他の地域にはないものがある。これも重要な高知県を始めとする、四国の地域力だ。煮干しは日常的なものなので、帰宅してすぐからこの煮干し類を使い始める。まずは「あじ煮干し(マアジ煮干し)」から。大小合って大の方から使うが、大の方が安い。 10月初旬の新潟の旅ではおいしいものをいっぱい買ってきたし、食べた。おいしい、以上に驚いたものもあった。それがイタリアンという食べ物である。見た目からしてあまりイタリアを感じさせるものはなく、あえていえばトマトソースがイタリアンなのかもしれないが、ソースの下にあるのは焼きそばに見える。しかも、ソースの中にぽつんぽつんとあるのがコーンで、そのわきにあるのがしょうがの酢漬けなのだ。
10月初旬の新潟の旅ではおいしいものをいっぱい買ってきたし、食べた。おいしい、以上に驚いたものもあった。それがイタリアンという食べ物である。見た目からしてあまりイタリアを感じさせるものはなく、あえていえばトマトソースがイタリアンなのかもしれないが、ソースの下にあるのは焼きそばに見える。しかも、ソースの中にぽつんぽつんとあるのがコーンで、そのわきにあるのがしょうがの酢漬けなのだ。 赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。板にのった赤い蒲鉾を「板つけ」と言った。徳島県ではうどんに「板つけ」はつきものだった。基本的に「板つけ」は赤い蒸し蒲鉾のことだけど、決して上等ではない、下手なものをさした。香川でも「板つけ」、高知でも「板つけ」だけど愛媛県ではなんというのだろう。全国的にどうなのかはわからないが、高知県宿毛市で買った『八馬かまぼこ』と『大原かまぼこ』の赤い蒲鉾は「板つけ」そのものであるが、表記は単に「蒲鉾」である。またうどんの具として使うのか否かは不明だ。
赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。板にのった赤い蒲鉾を「板つけ」と言った。徳島県ではうどんに「板つけ」はつきものだった。基本的に「板つけ」は赤い蒸し蒲鉾のことだけど、決して上等ではない、下手なものをさした。香川でも「板つけ」、高知でも「板つけ」だけど愛媛県ではなんというのだろう。全国的にどうなのかはわからないが、高知県宿毛市で買った『八馬かまぼこ』と『大原かまぼこ』の赤い蒲鉾は「板つけ」そのものであるが、表記は単に「蒲鉾」である。またうどんの具として使うのか否かは不明だ。 合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。今では新潟市西区内野町、でしかないが、合併前までは内野町だった。合併は大失敗だという人が少なからずいるが、ボクなど暴挙だと思っている。自治体(小さな行政)と行政区(大規模な行政)を分ければいいだけなのに、乱暴なことをやる。さて、内野駅周辺は明らかに新潟市中心部への住宅地といったところだろうか。例えば京王線だと調布とか、中央線だとすると荻窪だとか。夕闇迫る頃、商店の灯りが点々と見える。こんなところにはいい居酒屋がありがちである。今回、越後新川の面々と訪ったのは『旬菜 籐や』という居酒屋である。どうやら内野町にはいい居酒屋が少なからずあるようだが、そのひとつだ。店内は満席に近い。話が主となり、料理はおいしい記憶しか残らなかったが、一皿一皿外れなしだった。
合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。今では新潟市西区内野町、でしかないが、合併前までは内野町だった。合併は大失敗だという人が少なからずいるが、ボクなど暴挙だと思っている。自治体(小さな行政)と行政区(大規模な行政)を分ければいいだけなのに、乱暴なことをやる。さて、内野駅周辺は明らかに新潟市中心部への住宅地といったところだろうか。例えば京王線だと調布とか、中央線だとすると荻窪だとか。夕闇迫る頃、商店の灯りが点々と見える。こんなところにはいい居酒屋がありがちである。今回、越後新川の面々と訪ったのは『旬菜 籐や』という居酒屋である。どうやら内野町にはいい居酒屋が少なからずあるようだが、そのひとつだ。店内は満席に近い。話が主となり、料理はおいしい記憶しか残らなかったが、一皿一皿外れなしだった。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回はカズラガイである。新潟県・房総半島以南の比較的浅い砂地や泥場に棲息している。今回のものは新川漁港の沖合、水深10m前後でとれたものだ。貝を集めるという趣味がある。コレクターという言葉は使いたくないが、いたって身近なところにいる軟体類である巻貝や二枚貝を集めるのは、すぐ始められるし、とても楽しい。それぞれの貝には「手に入れやすいもの」、「手に入れるのが大変なもの」など多彩である。中で巻き貝の種類は膨大で、未だに名前のない種もいる。そんな中でもカズラガイはビーチコーミングでも刺網の混獲物としても手に入れやすいもののひとつ。とても美しい貝なので、貝集めを本種から初めてもいいだろう。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回はカズラガイである。新潟県・房総半島以南の比較的浅い砂地や泥場に棲息している。今回のものは新川漁港の沖合、水深10m前後でとれたものだ。貝を集めるという趣味がある。コレクターという言葉は使いたくないが、いたって身近なところにいる軟体類である巻貝や二枚貝を集めるのは、すぐ始められるし、とても楽しい。それぞれの貝には「手に入れやすいもの」、「手に入れるのが大変なもの」など多彩である。中で巻き貝の種類は膨大で、未だに名前のない種もいる。そんな中でもカズラガイはビーチコーミングでも刺網の混獲物としても手に入れやすいもののひとつ。とても美しい貝なので、貝集めを本種から初めてもいいだろう。協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 10月3日、午後5時前、新潟駅のホームに上る。下校時のラッシュは過ぎているようで学生の数は多くない。多くがスマートフォンを見ていて昔の騒がしさはない。高校生らしいとは思ったものの、平日なのに学生服姿は一人もいない。越後線に乗って南下する。新潟県の面積は47都道府県中5位で、北から下越、中越、上越と別れるが、捉えどころがないくらいに広い。下越の新潟市から中越の柏崎市までを繋ぐのが越後線である。ほとんど鉄路のない四国生まれなので4路線が通る新潟駅が複雑に思える。
10月3日、午後5時前、新潟駅のホームに上る。下校時のラッシュは過ぎているようで学生の数は多くない。多くがスマートフォンを見ていて昔の騒がしさはない。高校生らしいとは思ったものの、平日なのに学生服姿は一人もいない。越後線に乗って南下する。新潟県の面積は47都道府県中5位で、北から下越、中越、上越と別れるが、捉えどころがないくらいに広い。下越の新潟市から中越の柏崎市までを繋ぐのが越後線である。ほとんど鉄路のない四国生まれなので4路線が通る新潟駅が複雑に思える。 高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。もっとも一般的なのは土佐番茶といわれるものらしい。チャノキの茶を焙じたものと、きし豆(カワラケツメイ)の葉を焙じたものを混ぜたもの。安芸市や黒潮町の直売所で買ったものは、きし豆(カワラケツメイ)の比率が多く、甘味がある。高知県高知市帯屋町『森木翠香園』のものはチャノキの葉が多めで、きし豆が少ない。
高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。もっとも一般的なのは土佐番茶といわれるものらしい。チャノキの茶を焙じたものと、きし豆(カワラケツメイ)の葉を焙じたものを混ぜたもの。安芸市や黒潮町の直売所で買ったものは、きし豆(カワラケツメイ)の比率が多く、甘味がある。高知県高知市帯屋町『森木翠香園』のものはチャノキの葉が多めで、きし豆が少ない。 午後2時過ぎに新潟市に戻る。昨夜から睡眠時間2時間弱なので、この時間帯に疲れの大波が来る、ここで眠ってしまうと体が余計にだるくなるの予定通りに銭湯に行く。新潟市東区秋葉通にある小松湯は驚くなかれ、午前8時半からやっている。最近、ボク好みの普通の銭湯が全国的に消えてしまいつつある中、新潟市内には10店舗近くある。新潟市は銭湯のある町と言ってもいいだろう。小松湯は昔ながらの設備の、昔ながらの銭湯である。シャワーが出なくて困っていたら、「開けたり閉じたりすると出るから(身振りで)」と教えてくれる。常連さんが優しいのがいい。じっくりゆっくりと湯船に浸かり、ジェットを背中に受けて上がったら、体がクラゲ状態になっていた。ぼうずコンニャクなのでコンニャク状態かも。
午後2時過ぎに新潟市に戻る。昨夜から睡眠時間2時間弱なので、この時間帯に疲れの大波が来る、ここで眠ってしまうと体が余計にだるくなるの予定通りに銭湯に行く。新潟市東区秋葉通にある小松湯は驚くなかれ、午前8時半からやっている。最近、ボク好みの普通の銭湯が全国的に消えてしまいつつある中、新潟市内には10店舗近くある。新潟市は銭湯のある町と言ってもいいだろう。小松湯は昔ながらの設備の、昔ながらの銭湯である。シャワーが出なくて困っていたら、「開けたり閉じたりすると出るから(身振りで)」と教えてくれる。常連さんが優しいのがいい。じっくりゆっくりと湯船に浸かり、ジェットを背中に受けて上がったら、体がクラゲ状態になっていた。ぼうずコンニャクなのでコンニャク状態かも。 新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。店の中が比較的明るいのがいい。店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。食堂のチャーハンもいい、気がする。考えてみると食堂で焼きそばもある。焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。ラーメンとのセットは珍しい気がする。やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。
新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。店の中が比較的明るいのがいい。店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。食堂のチャーハンもいい、気がする。考えてみると食堂で焼きそばもある。焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。ラーメンとのセットは珍しい気がする。やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。 胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。大方見終わろうとしているとき、「9時になったら魚屋が来るから待ってな(意訳)」と言われた。少し町を見て帰ってきたら、有名だという焼き肉店の前にライトバンがとまっていた。
胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。大方見終わろうとしているとき、「9時になったら魚屋が来るから待ってな(意訳)」と言われた。少し町を見て帰ってきたら、有名だという焼き肉店の前にライトバンがとまっていた。 8時前に胎内市中条の朝市、熊野若宮神社前に着いた。3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。新潟県は朝市県といってもいいほど朝市だらけである。これは里(商工業地)と農家・漁業者がはっきり分かれていたためだ。少しだけ専門的になるが、庶民交易史の世界では、この異業種間の交流こそが中世以来の「交易」の姿なのである。1980年代、新潟県の朝市は歩くのがたいへんといった混み具合だった。人気のある農家の露店などには人だかりが出来ていた。鍛冶・刃物、和菓子やこんにゃく、寒天(ところてん)つきなど様々な業種がひしめき合っていた。占いなのかなんなのか、怪しいくじに並ぶ人もいた。新潟県にしかない、というものがいっぱいだったが、今や見る影もない。
8時前に胎内市中条の朝市、熊野若宮神社前に着いた。3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。新潟県は朝市県といってもいいほど朝市だらけである。これは里(商工業地)と農家・漁業者がはっきり分かれていたためだ。少しだけ専門的になるが、庶民交易史の世界では、この異業種間の交流こそが中世以来の「交易」の姿なのである。1980年代、新潟県の朝市は歩くのがたいへんといった混み具合だった。人気のある農家の露店などには人だかりが出来ていた。鍛冶・刃物、和菓子やこんにゃく、寒天(ところてん)つきなど様々な業種がひしめき合っていた。占いなのかなんなのか、怪しいくじに並ぶ人もいた。新潟県にしかない、というものがいっぱいだったが、今や見る影もない。 10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。水揚げされている水産生物をすべてチェックして、今度は海から遠い田園地帯にある中央市場に行く。ここは水産大卸が新潟冷蔵、山津水産の2社あり、日本海側屈指の大型の市場である。新潟市の人口は76万人あまり、考えてみると我が故郷徳島県の人口よりも多い。しかも県内だけではなく阿賀野川をさかのぼり、福島県にも荷を送り出している。
10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。水揚げされている水産生物をすべてチェックして、今度は海から遠い田園地帯にある中央市場に行く。ここは水産大卸が新潟冷蔵、山津水産の2社あり、日本海側屈指の大型の市場である。新潟市の人口は76万人あまり、考えてみると我が故郷徳島県の人口よりも多い。しかも県内だけではなく阿賀野川をさかのぼり、福島県にも荷を送り出している。 10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。新潟県の水産物は南北に長い河岸線と、佐渡、そして日本海に広がる大和堆がある。1種類の魚の量が多いのが日本海の特徴である。底曳きが始まっているのでアカムツの量が多く、また新潟市名物「ふなべた(タマガンゾウビラメ)」がていねいな荷の作りで並んでいる。オオエッチュウバイにチヂミエゾボラ(エゾボラモドキ)、カガバイ、ツバイなども新潟名物である。まとまった量のズワイガニにも夏の終わりを感じる。
10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。新潟県の水産物は南北に長い河岸線と、佐渡、そして日本海に広がる大和堆がある。1種類の魚の量が多いのが日本海の特徴である。底曳きが始まっているのでアカムツの量が多く、また新潟市名物「ふなべた(タマガンゾウビラメ)」がていねいな荷の作りで並んでいる。オオエッチュウバイにチヂミエゾボラ(エゾボラモドキ)、カガバイ、ツバイなども新潟名物である。まとまった量のズワイガニにも夏の終わりを感じる。 高知県宿毛市・大月町での水揚げを見て歩くのは、他県と比べると楽である。温かいし、しかも時間が遅い。東北など午前2時、3時から魚貝類が並びはじめるところがざらにある。それでも6時からずーっと脳みそをフル回転させ、あっちこっち歩いて、メモをとると疲れてくる。ちょっとだけでも座りたくなる。競り場が一段落ついたとき、宿毛市街に朝ご飯を食べに行く。与力水産、有田輝一さんおすすめの、『カフェレスト 花時間』という可愛らしい名前の喫茶店である。名前とは裏腹に店内にいるのはご近所の普通のオバサンとオジサンで、ボクなど実に薄汚いデブなので安心する。この朝ご飯を喫茶店で、というのは高知県全域での普通である。愛知県の喫茶店朝ご飯文化は有名だが、ボクの勝手な意見だけれど、高知県の喫茶店朝ご飯文化の方が上だと思っている。高知県の方がストレートに朝ご飯だからだ。ちなみに愛知に行ったら逆に思える可能性だってある、ので、ボクはボク自体を信用していない。
高知県宿毛市・大月町での水揚げを見て歩くのは、他県と比べると楽である。温かいし、しかも時間が遅い。東北など午前2時、3時から魚貝類が並びはじめるところがざらにある。それでも6時からずーっと脳みそをフル回転させ、あっちこっち歩いて、メモをとると疲れてくる。ちょっとだけでも座りたくなる。競り場が一段落ついたとき、宿毛市街に朝ご飯を食べに行く。与力水産、有田輝一さんおすすめの、『カフェレスト 花時間』という可愛らしい名前の喫茶店である。名前とは裏腹に店内にいるのはご近所の普通のオバサンとオジサンで、ボクなど実に薄汚いデブなので安心する。この朝ご飯を喫茶店で、というのは高知県全域での普通である。愛知県の喫茶店朝ご飯文化は有名だが、ボクの勝手な意見だけれど、高知県の喫茶店朝ご飯文化の方が上だと思っている。高知県の方がストレートに朝ご飯だからだ。ちなみに愛知に行ったら逆に思える可能性だってある、ので、ボクはボク自体を信用していない。 古満目から宿毛市、すくも湾中央市場の競り場に移動する。ここは昼近くまで水揚げが続く、フライト時間があるので見ることができたのはほんの一部だ。今回は同定不能という魚はいなかったが、やはり興奮すること多し。
古満目から宿毛市、すくも湾中央市場の競り場に移動する。ここは昼近くまで水揚げが続く、フライト時間があるので見ることができたのはほんの一部だ。今回は同定不能という魚はいなかったが、やはり興奮すること多し。 9月27日の朝、水揚げが大方終わったあとに『古満目水主大敷組合』、福見真路さんが隅の方で何かをやっている。割り箸、竹のヘラ、ラジオペンチでクロホシフエダイの内臓を抜いているのだ。聞くと「かけのいお」を作っているのだという。「掛けの魚」のことで、「掛魚」ともいう。2尾腹合わせにした魚を家内、もしくは建物のどこかに掛けて供物とする。掛けるのは干した魚であることもあるし、生の魚を掛けることもある。大皿などに2尾の魚を抱き合わせただけで済ませる地域もある。農家や、漁家、商家などで行われているが、農家は五穀豊穣、商家は商売繁盛、漁師の場合、豊漁を祈願し、また豊漁の礼として供える。年内のえびす講、正月、小正月など行われるが、職業で時期は違っている。古満目では年度替わりの10月に新しいものに替えるのだという。今回はクロホシフエダイだが魚はなんでもいい。塩漬けにしてからからに干して「おみきすずり」に掛ける。「おみきすずり」の「お神酒」はわかるが「すずり」がわからない。
9月27日の朝、水揚げが大方終わったあとに『古満目水主大敷組合』、福見真路さんが隅の方で何かをやっている。割り箸、竹のヘラ、ラジオペンチでクロホシフエダイの内臓を抜いているのだ。聞くと「かけのいお」を作っているのだという。「掛けの魚」のことで、「掛魚」ともいう。2尾腹合わせにした魚を家内、もしくは建物のどこかに掛けて供物とする。掛けるのは干した魚であることもあるし、生の魚を掛けることもある。大皿などに2尾の魚を抱き合わせただけで済ませる地域もある。農家や、漁家、商家などで行われているが、農家は五穀豊穣、商家は商売繁盛、漁師の場合、豊漁を祈願し、また豊漁の礼として供える。年内のえびす講、正月、小正月など行われるが、職業で時期は違っている。古満目では年度替わりの10月に新しいものに替えるのだという。今回はクロホシフエダイだが魚はなんでもいい。塩漬けにしてからからに干して「おみきすずり」に掛ける。「おみきすずり」の「お神酒」はわかるが「すずり」がわからない。 午前6時半、古満目の入江に入ると、まるで桃源郷のようなところだった。複雑な地形で水面を見ると多種類のスズメダイ科、ムレハタタテダイ(?)の魚が岸壁に寄って群れている。古満目漁協が見渡せる場所から漁港を撮影していたら、素直でいい感じの高校生と合う。家族のために「めじか(マルソウダ)」を釣りに来たのだという。お家は煙草農家だというが、煙草栽培はとても重労働である。家業を継ぐのか否かはわからないががんばって欲しいな。古満目漁港には7時に到着。
午前6時半、古満目の入江に入ると、まるで桃源郷のようなところだった。複雑な地形で水面を見ると多種類のスズメダイ科、ムレハタタテダイ(?)の魚が岸壁に寄って群れている。古満目漁協が見渡せる場所から漁港を撮影していたら、素直でいい感じの高校生と合う。家族のために「めじか(マルソウダ)」を釣りに来たのだという。お家は煙草農家だというが、煙草栽培はとても重労働である。家業を継ぐのか否かはわからないががんばって欲しいな。古満目漁港には7時に到着。 宿毛市に入る。宿毛市は室町時代から戦国時代にかけて土佐一条家の第二の城下といったところで、歴史的にも面白い。今回いろいろお世話になる与力水産さんで、明日の古満目や宿毛漁協での打ち合わせをする。与力水産は2008年創業の新しい会社である。社長は吉村典彦さんもずいぶん若い。予め連絡をとっていた有田輝一専務ともども初対面の挨拶をする。与力水産は、すくも湾中央市場にとっては新規参入をされたわけだし、貝ノ川に定置網も持っている。翌日の競りを見ていても、宿毛という地に新しい風を起こしていることがよくわかる。与力水産さん(■https://yorikisuisan.co.jp/)にはお世話になりました。
宿毛市に入る。宿毛市は室町時代から戦国時代にかけて土佐一条家の第二の城下といったところで、歴史的にも面白い。今回いろいろお世話になる与力水産さんで、明日の古満目や宿毛漁協での打ち合わせをする。与力水産は2008年創業の新しい会社である。社長は吉村典彦さんもずいぶん若い。予め連絡をとっていた有田輝一専務ともども初対面の挨拶をする。与力水産は、すくも湾中央市場にとっては新規参入をされたわけだし、貝ノ川に定置網も持っている。翌日の競りを見ていても、宿毛という地に新しい風を起こしていることがよくわかる。与力水産さん(■https://yorikisuisan.co.jp/)にはお世話になりました。 須崎市を出て、四万十町内に入る。柴田さんの案内で、『土佐打刃物 黒鳥』をのぞく。いかにも刃物好きが来そうなところだと思ったら、豈図らんや非常に日常的でいい刃物が揃っている。これは趣味的なものではなく、ほぼボク好みの包丁たちである。
須崎市を出て、四万十町内に入る。柴田さんの案内で、『土佐打刃物 黒鳥』をのぞく。いかにも刃物好きが来そうなところだと思ったら、豈図らんや非常に日常的でいい刃物が揃っている。これは趣味的なものではなく、ほぼボク好みの包丁たちである。 『白木果樹園』を後にして、須崎市の『うつわ日月』に向かう。魚貝類料理を撮影するときにもっとも使用頻度の高いのが、『うつわ日月』のもので、故、小坂明さんのものである。あまりにも使いやすいので、三日をおかず使い続けている。小坂さんの器は非常によく考えられているし、しかも独創性が高い。現在は、妻のゆみこさんが『うつわ日月』を受け継いでいる。東京都国分寺の頃はたびたび足を運んでいたが、須崎市の半島に移ってからは初めてである。
『白木果樹園』を後にして、須崎市の『うつわ日月』に向かう。魚貝類料理を撮影するときにもっとも使用頻度の高いのが、『うつわ日月』のもので、故、小坂明さんのものである。あまりにも使いやすいので、三日をおかず使い続けている。小坂さんの器は非常によく考えられているし、しかも独創性が高い。現在は、妻のゆみこさんが『うつわ日月』を受け継いでいる。東京都国分寺の頃はたびたび足を運んでいたが、須崎市の半島に移ってからは初めてである。 さて高知県3日目、9月26日に土佐市の『白木果樹園』に向かう。高知市から高速を使ってあっと言う間の土佐市であった。四国の高速道路はまだまだ完全ではないし、基本1車線だが、東西に長い高知県がやけに狭く感じられた。高速を降りて斜面を登ると柑橘農家が多い。
さて高知県3日目、9月26日に土佐市の『白木果樹園』に向かう。高知市から高速を使ってあっと言う間の土佐市であった。四国の高速道路はまだまだ完全ではないし、基本1車線だが、東西に長い高知県がやけに狭く感じられた。高速を降りて斜面を登ると柑橘農家が多い。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回、星野さんが手に持っているのがシロボヤ(シロボヤ類とすべきかも)である。ていねいに洗うと白くてぬらりひょんの顔そっくりの物体なのがわかる。シロボヤは韓国では普通に食べているし、非常においしいこともわかっている。でも国内では食用であること自体を知らない。漁具にも生物にもなんにでもくっつくやっかいものでしかない。成長するとごつごつして不気味だけど、幼生期には自由に動けるし、ボクたちと同じ脊索(脊椎ではなく単なる棒のようなもの)があるので、決して原始的な生き物ではない。「ほや(マボヤ)」を食べたことがある人が食べたら、似た味だなと思うはずだけど、むしろシロボヤの方が苦みや渋味が薄い。鍋ものなどに入れると、絶品である。無性に食べたくなったけど、残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。海のシロボヤに片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。今回、星野さんが手に持っているのがシロボヤ(シロボヤ類とすべきかも)である。ていねいに洗うと白くてぬらりひょんの顔そっくりの物体なのがわかる。シロボヤは韓国では普通に食べているし、非常においしいこともわかっている。でも国内では食用であること自体を知らない。漁具にも生物にもなんにでもくっつくやっかいものでしかない。成長するとごつごつして不気味だけど、幼生期には自由に動けるし、ボクたちと同じ脊索(脊椎ではなく単なる棒のようなもの)があるので、決して原始的な生き物ではない。「ほや(マボヤ)」を食べたことがある人が食べたら、似た味だなと思うはずだけど、むしろシロボヤの方が苦みや渋味が薄い。鍋ものなどに入れると、絶品である。無性に食べたくなったけど、残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。海のシロボヤに片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。ここ新川漁港周辺には磯もある。日本海で磯と言えばサザエなので、サザエも少なからずとれる。日本海に多い角なしのサザエだ。日本海の北海道西部から九州まであまねくいるのがサザエなので、日本海に行ったらサザエを食わなくちゃと思ってしまうのはボクだけか。星野さんが見せてくれたのは、大人のこぶし大のものもあり、刺身にもできそうでもある。残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。磯のサザエの片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。ここ新川漁港周辺には磯もある。日本海で磯と言えばサザエなので、サザエも少なからずとれる。日本海に多い角なしのサザエだ。日本海の北海道西部から九州まであまねくいるのがサザエなので、日本海に行ったらサザエを食わなくちゃと思ってしまうのはボクだけか。星野さんが見せてくれたのは、大人のこぶし大のものもあり、刺身にもできそうでもある。残念ながら今回のものは新潟市中心部で行われるイベント用のもの。磯のサザエの片思い、は間違いだけど、後ろ髪ひかれて帰ってきた。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 高知県といえば釣りウルメだろう。日本広といえどもウルメイワシ専門の釣り漁があるのは高知県だけだ。小振りの丸干しは高知県以外にもいいものがたくさんあるが、大きいのはやはり高知だと思う。干しているのに全長20cmを超えるので、干す前はさぞや大きかろう。漁を見に行っていないのが残念だが、丸干しを見つけると、高いのを承知でついつい手が出る。
高知県といえば釣りウルメだろう。日本広といえどもウルメイワシ専門の釣り漁があるのは高知県だけだ。小振りの丸干しは高知県以外にもいいものがたくさんあるが、大きいのはやはり高知だと思う。干しているのに全長20cmを超えるので、干す前はさぞや大きかろう。漁を見に行っていないのが残念だが、丸干しを見つけると、高いのを承知でついつい手が出る。 3日目はサッポロビールの柴田さんの運転で西に向かう。高知市内から高速に乗る前に市内愛宕町の金曜市んび寄ってくれた。残念ながら野菜が中心で、少しだけ塩乾があるだけ。日曜市のお祭り騒ぎとは打って変わって日常的な露店が並ぶ。
3日目はサッポロビールの柴田さんの運転で西に向かう。高知市内から高速に乗る前に市内愛宕町の金曜市んび寄ってくれた。残念ながら野菜が中心で、少しだけ塩乾があるだけ。日曜市のお祭り騒ぎとは打って変わって日常的な露店が並ぶ。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。新川漁協やその周辺には自然にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者と一緒に波打ち際で見つけた生物の7番目はムラサキウニである。ムラサキウニは、一般的に「紫うに」と呼ばれているキタムラサキウニとは縁もゆかりもない。棘はキタムラサキウニよりも太く、表面が比較的つるつるとして滑らか。棘の長さもキタムラサキウニはほぼ同じだが、ムラサキウニは中に極端に長いのがある。一般的な食用ウニではなく、地域性の高い食用ウニである。太平洋側では主に初夏に旬を迎えるが、新潟県での旬は不明だ。新潟県はムラサキウニとキタムラサキウニともにとれる地域なので、こんどはキタムラサキウニを探したい。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。新川漁協やその周辺には自然にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者と一緒に波打ち際で見つけた生物の7番目はムラサキウニである。ムラサキウニは、一般的に「紫うに」と呼ばれているキタムラサキウニとは縁もゆかりもない。棘はキタムラサキウニよりも太く、表面が比較的つるつるとして滑らか。棘の長さもキタムラサキウニはほぼ同じだが、ムラサキウニは中に極端に長いのがある。一般的な食用ウニではなく、地域性の高い食用ウニである。太平洋側では主に初夏に旬を迎えるが、新潟県での旬は不明だ。新潟県はムラサキウニとキタムラサキウニともにとれる地域なので、こんどはキタムラサキウニを探したい。協力/島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川) 時間が限られているので、三津・高岡をやめて室戸漁港に寄る。水揚げはなく、ここでは魚の呼び名などを採取する。そのまま浦戸屋に寄るが、最強の魚屋といえども時化には勝てず。直売所に寄りながら高知市にもどってもらう。濵町諒介さんにつき合ってもらって申し訳ない。ただできる限り伝統的なものを今のうちに買っておかないと、いつ消えてしまうか知れたものではない。などと濵町さんに話したがわかってくれただろうか?余談だけど徳島では「しきみ」だけど高知では「しきび」などなど、知らない老人と無駄話する。お茶、柑橘類などを徹底的に買って、高知市内にもどる。高知市にもどり、時間が出来たので、『葉牡丹』にオムライスを食べに行く。意外にも酒の後にはおいしいのに、昼ご飯として食べたら平凡だった。
時間が限られているので、三津・高岡をやめて室戸漁港に寄る。水揚げはなく、ここでは魚の呼び名などを採取する。そのまま浦戸屋に寄るが、最強の魚屋といえども時化には勝てず。直売所に寄りながら高知市にもどってもらう。濵町諒介さんにつき合ってもらって申し訳ない。ただできる限り伝統的なものを今のうちに買っておかないと、いつ消えてしまうか知れたものではない。などと濵町さんに話したがわかってくれただろうか?余談だけど徳島では「しきみ」だけど高知では「しきび」などなど、知らない老人と無駄話する。お茶、柑橘類などを徹底的に買って、高知市内にもどる。高知市にもどり、時間が出来たので、『葉牡丹』にオムライスを食べに行く。意外にも酒の後にはおいしいのに、昼ご飯として食べたら平凡だった。 5時過ぎに高知県水産振興課、濵町諒介さんが迎えに来てくれた。室戸岬の東側に向かう。高知県室戸市の大敷網でいちばん北にある推名漁港に到着する。徳島県阿南市椿泊から、高知県東洋町、そして室戸市と一直線に太平洋に面している。930年・931年に紀貫之が海賊の来襲に怯えながら北上したところでもある。推名漁港を訪うと推名大敷組合組合長・橋本健さんが迎えてくれた。大敷網が上げられるかどうか双眼鏡でのぞいている。推名、三津、高岡と大敷網が並んでいる。推名漁港から南に、室戸岬東側の全大敷網が総て見ることが出来る。
5時過ぎに高知県水産振興課、濵町諒介さんが迎えに来てくれた。室戸岬の東側に向かう。高知県室戸市の大敷網でいちばん北にある推名漁港に到着する。徳島県阿南市椿泊から、高知県東洋町、そして室戸市と一直線に太平洋に面している。930年・931年に紀貫之が海賊の来襲に怯えながら北上したところでもある。推名漁港を訪うと推名大敷組合組合長・橋本健さんが迎えてくれた。大敷網が上げられるかどうか双眼鏡でのぞいている。推名、三津、高岡と大敷網が並んでいる。推名漁港から南に、室戸岬東側の全大敷網が総て見ることが出来る。 高知県ではきし豆(岸豆。川原などに生えているカワラケツメイ)のお茶があり、チャノキを枝ごとつんだ番茶もある。ともに焙じたものを淹れる。単独でも飲むが、ふたつを合わせたものが「土佐番茶」である。単に「番茶」という表示で「きし豆」入りという表示もある。高知県各所で「きし豆」入りの番茶を買っているが、どうやら作る人により「きし豆」比率が違っているようだと思えてきた。今回の晩茶(高知県幡多郡黒潮町)は「きし豆」が比率が高いためだろう、高知市内で買ったものよりも甘味が強い。
高知県ではきし豆(岸豆。川原などに生えているカワラケツメイ)のお茶があり、チャノキを枝ごとつんだ番茶もある。ともに焙じたものを淹れる。単独でも飲むが、ふたつを合わせたものが「土佐番茶」である。単に「番茶」という表示で「きし豆」入りという表示もある。高知県各所で「きし豆」入りの番茶を買っているが、どうやら作る人により「きし豆」比率が違っているようだと思えてきた。今回の晩茶(高知県幡多郡黒潮町)は「きし豆」が比率が高いためだろう、高知市内で買ったものよりも甘味が強い。 高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。「かますの煮干し」は日本の各地で作られていると思うが、高知県もそのひとつだ。市内にある市(日曜市・金曜市など)では定番的なものだと思われる。問題はアカカマスかヤマトカマスか、だが、今回のものはアカカマスのようだ。過去にはっきりヤマトカマスだと思われるものは見ていない。
高知県高知市愛宕町の金曜市の塩乾などを売る店で、買ったものだ。「かますの煮干し」は日本の各地で作られていると思うが、高知県もそのひとつだ。市内にある市(日曜市・金曜市など)では定番的なものだと思われる。問題はアカカマスかヤマトカマスか、だが、今回のものはアカカマスのようだ。過去にはっきりヤマトカマスだと思われるものは見ていない。 9月下旬、高知龍馬空港に下りたってバスに乗り、高知市まで。下りたのは「はりまや橋」のたもとだった。「はりまや橋」が昔よりもちょっと橋らしくなっていた。この橋のようで橋ではない橋は、民謡として有名になったわけではなく、ペギー葉山の『南国土佐を後にして』と小林旭の同名の映画のせいだ。小学校の修学旅行で行った高知のコースには含まれていなかった気がするが、当時の教師が無意味だと思っていたせいかも知れぬ。都内では晴れ間すら出ていたのに本降りの雨で、非常に暑いし湿っぽい。バスで植物学なのか環境学なのかをやっている方に声をかけられた。せっかくなので植物学的な疑問を教わる。
9月下旬、高知龍馬空港に下りたってバスに乗り、高知市まで。下りたのは「はりまや橋」のたもとだった。「はりまや橋」が昔よりもちょっと橋らしくなっていた。この橋のようで橋ではない橋は、民謡として有名になったわけではなく、ペギー葉山の『南国土佐を後にして』と小林旭の同名の映画のせいだ。小学校の修学旅行で行った高知のコースには含まれていなかった気がするが、当時の教師が無意味だと思っていたせいかも知れぬ。都内では晴れ間すら出ていたのに本降りの雨で、非常に暑いし湿っぽい。バスで植物学なのか環境学なのかをやっている方に声をかけられた。せっかくなので植物学的な疑問を教わる。 高知に行ったら必ず買ってしまうものに「てつ干し」がある。今回買ったのは「まいら鉄干し」で、『いずま海産(高知県室戸市)』のものだ。「まいら」とはアオザメのことである。角材状で微かに赤みを帯びている。塩加減がほどよくとてもボク好み。高知県東部の室戸市や安芸市などなどの「てつ干し」は、どれもこれもよく出来ている。はずれがないのがうれしい。しっかり焼き目がつくくらい焼くのが好きなので、じっくり四方八方から火を当て時間をかけながら焼き上げた。これを手でむしりながら野性的に食らう。高知県で買った土佐鶴にも合うし、ビールにも合う。いずれにしても酒の友なのは高知県だからかも。
高知に行ったら必ず買ってしまうものに「てつ干し」がある。今回買ったのは「まいら鉄干し」で、『いずま海産(高知県室戸市)』のものだ。「まいら」とはアオザメのことである。角材状で微かに赤みを帯びている。塩加減がほどよくとてもボク好み。高知県東部の室戸市や安芸市などなどの「てつ干し」は、どれもこれもよく出来ている。はずれがないのがうれしい。しっかり焼き目がつくくらい焼くのが好きなので、じっくり四方八方から火を当て時間をかけながら焼き上げた。これを手でむしりながら野性的に食らう。高知県で買った土佐鶴にも合うし、ビールにも合う。いずれにしても酒の友なのは高知県だからかも。 『古川鮮魚』、8月30日の昼の定食は、やたらに盛りだくさんであった。お客さんで立て込んでいた中、先ず出て来たものは新潟名産とも言えそうな茶豆だ。新潟県で食べる枝豆はいつ食べても最上級の味がする。アジの南蛮漬け(?)に「ばい(ツバイ)」の小鉢もいい。ツバイは日本海特産の小型のエゾバイ科の巻き貝で、煮る巻き貝の中でも味は最上級といえるものだ。古川鮮魚の大女将が煮ているのだろうが、煮加減もいい。
『古川鮮魚』、8月30日の昼の定食は、やたらに盛りだくさんであった。お客さんで立て込んでいた中、先ず出て来たものは新潟名産とも言えそうな茶豆だ。新潟県で食べる枝豆はいつ食べても最上級の味がする。アジの南蛮漬け(?)に「ばい(ツバイ)」の小鉢もいい。ツバイは日本海特産の小型のエゾバイ科の巻き貝で、煮る巻き貝の中でも味は最上級といえるものだ。古川鮮魚の大女将が煮ているのだろうが、煮加減もいい。 2025年8月30日、午前2時に新潟市漁協の競り場・中央卸売市場を回り、8時過ぎにホテルにもどりメモを整理する。9時過ぎに本町を目指す。1980年前後に新潟市の本町通を歩いている。目的は朝市だった。新潟市の朝市は本町(本町通とその周辺)と白山が有名で観光名所でもあった。並んでいるものが多彩で、新潟を感じられるものだらけだった。何時間でもいて飽きないところだった。ただ、今、昔のにぎやかさはない。本町には浜焼きの店があり、農産物を売る露店も多かった。それが今や見る影もない。新潟市の新潟市らしさは朝市にあり、だと思うのだけど、これでは消滅してしまう。唯一の救いは、未だに元気のいい魚屋が何軒もあって繁盛していることかも。写真は本町下市場。
2025年8月30日、午前2時に新潟市漁協の競り場・中央卸売市場を回り、8時過ぎにホテルにもどりメモを整理する。9時過ぎに本町を目指す。1980年前後に新潟市の本町通を歩いている。目的は朝市だった。新潟市の朝市は本町(本町通とその周辺)と白山が有名で観光名所でもあった。並んでいるものが多彩で、新潟を感じられるものだらけだった。何時間でもいて飽きないところだった。ただ、今、昔のにぎやかさはない。本町には浜焼きの店があり、農産物を売る露店も多かった。それが今や見る影もない。新潟市の新潟市らしさは朝市にあり、だと思うのだけど、これでは消滅してしまう。唯一の救いは、未だに元気のいい魚屋が何軒もあって繁盛していることかも。写真は本町下市場。 最初に漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。ついでにいうと私事ではあるが、ゴミ拾いセットを持っていく。最小限でもいいのでゴミを拾ってくる。釣りにはマナーが大切なのである。
最初に漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。ついでにいうと私事ではあるが、ゴミ拾いセットを持っていく。最小限でもいいのでゴミを拾ってくる。釣りにはマナーが大切なのである。 7時前に新潟市内のホテルにチェックイン。ぼろ切れのようだったので湯船につかる。つかりながら眠気の大波に襲われる。それにしても面白いと夢中になるのは、年を取っても同じである。お昼にカツ丼を食べたのに、夕方、お腹と背中がくっつきそうだったのは、走行距離500キロ以上、午前0時に出発してから面白すぎて興奮に次ぐ興奮、そしてテキスト化までして、街歩きまでしたせいだ。腹の虫をなだめるために、新潟県新潟市西区内野町、スーパー『ichiman』で買った「ふなべたの刺身(タマガンゾウビラメの刺身)」、「身欠きニシン煮」、「鶏の唐揚げ」と、『ブーランジェ・ヨネヤマ』のパンでビール。救いはスーパー『ichiman』の惣菜の味と、これまた『ブーランジェ・ヨネヤマ』のパンの味だ。惣菜の味つけがいいし、パンにも味がある。惣菜とパンを食べながら、内野町ってまだまだ生きている町なのだ、と思う。新川漁港の活性化を目指しているが、町を取り残しての活性化はないと思っている。漁業と商業を一つと考えないと真の意味での地域おこしはできない。心の中にまだざわざわ感が残っていたので、いつもバッグに放り込んでいる菊水の白缶を飲んでしまう。6時半過ぎまでは意識があったはず。
7時前に新潟市内のホテルにチェックイン。ぼろ切れのようだったので湯船につかる。つかりながら眠気の大波に襲われる。それにしても面白いと夢中になるのは、年を取っても同じである。お昼にカツ丼を食べたのに、夕方、お腹と背中がくっつきそうだったのは、走行距離500キロ以上、午前0時に出発してから面白すぎて興奮に次ぐ興奮、そしてテキスト化までして、街歩きまでしたせいだ。腹の虫をなだめるために、新潟県新潟市西区内野町、スーパー『ichiman』で買った「ふなべたの刺身(タマガンゾウビラメの刺身)」、「身欠きニシン煮」、「鶏の唐揚げ」と、『ブーランジェ・ヨネヤマ』のパンでビール。救いはスーパー『ichiman』の惣菜の味と、これまた『ブーランジェ・ヨネヤマ』のパンの味だ。惣菜の味つけがいいし、パンにも味がある。惣菜とパンを食べながら、内野町ってまだまだ生きている町なのだ、と思う。新川漁港の活性化を目指しているが、町を取り残しての活性化はないと思っている。漁業と商業を一つと考えないと真の意味での地域おこしはできない。心の中にまだざわざわ感が残っていたので、いつもバッグに放り込んでいる菊水の白缶を飲んでしまう。6時半過ぎまでは意識があったはず。 新潟県西区五十嵐新川漁港では朝、水揚げと同時に魚貝類が買える。まだシステムとして成り立っていないが、新川漁港周辺では評判となっている。国内各地で同様のことが行われているが、漁船から直接買うので鮮度はこれ以上望めないし、しかも安い。午前7時から8時過ぎくらいまで、新川漁港で船が帰ってくるのを待っている人たちがいるが、問題は時間と場所がまちまちであること。これを解決すれば、新川漁港最大の魅力となるだろう。
新潟県西区五十嵐新川漁港では朝、水揚げと同時に魚貝類が買える。まだシステムとして成り立っていないが、新川漁港周辺では評判となっている。国内各地で同様のことが行われているが、漁船から直接買うので鮮度はこれ以上望めないし、しかも安い。午前7時から8時過ぎくらいまで、新川漁港で船が帰ってくるのを待っている人たちがいるが、問題は時間と場所がまちまちであること。これを解決すれば、新川漁港最大の魅力となるだろう。 2025年秋、新潟旅日記05 新潟市内野町へ昼過ぎ上越市を後にして、新潟市西区内野町に向かう。内野町に入って気がついた。1980年前後、おんぼろシビックで日本各地を走っていた頃、不幸に不幸が重なってたどり着いたのが内野駅だ。海岸線を、車を走らせていて砂浜にエゴノリ取りの人たちに会って話をしている内に、大間違いをやらかせていることに気がついた。地図を見て道を左折、にぎやかな街に入って、とそれが内野町だったことになる。にぎやかだった記憶しかないが、今や人影まばらとなっている。くるりと街を回って、『やしち酒店』で内野町の酒を買う。この店、酒屋らしく清潔で無駄な飾りがないのがいい。酒の扱いもていねいと見た。内野町には4軒酒蔵があったが、能登半島地震で2軒が廃業を余儀なくされている。新潟県でも新潟市周辺の街は潟(沼や湖)の上に出来ている。地震によわい地域なのである。ここで樋木酒造の鶴友、塩川酒造の越の関を買う。その土地に行ったらその土地の酒を買うのが、ボク流なのである。この2つの酒蔵の酒はともにボク好みでもあった。
2025年秋、新潟旅日記05 新潟市内野町へ昼過ぎ上越市を後にして、新潟市西区内野町に向かう。内野町に入って気がついた。1980年前後、おんぼろシビックで日本各地を走っていた頃、不幸に不幸が重なってたどり着いたのが内野駅だ。海岸線を、車を走らせていて砂浜にエゴノリ取りの人たちに会って話をしている内に、大間違いをやらかせていることに気がついた。地図を見て道を左折、にぎやかな街に入って、とそれが内野町だったことになる。にぎやかだった記憶しかないが、今や人影まばらとなっている。くるりと街を回って、『やしち酒店』で内野町の酒を買う。この店、酒屋らしく清潔で無駄な飾りがないのがいい。酒の扱いもていねいと見た。内野町には4軒酒蔵があったが、能登半島地震で2軒が廃業を余儀なくされている。新潟県でも新潟市周辺の街は潟(沼や湖)の上に出来ている。地震によわい地域なのである。ここで樋木酒造の鶴友、塩川酒造の越の関を買う。その土地に行ったらその土地の酒を買うのが、ボク流なのである。この2つの酒蔵の酒はともにボク好みでもあった。 新潟県上越市公文書センターで古文書をコピーさせてもらう。センターに向かう道すがら左右に広がる田を見て、悲しくなる。それにしても上越市の田の状況は異常だと思う。高田城市公園にもどりしばしテキストを打つ。散歩中のご夫婦に一番近い食堂の名前を聞いて向かう。教わった『食堂なかしま』という店は見た目からして真新しい。少々不安に感じたが、中はいたって普通の食堂だった。お腹と背中がくっついた末の、朝昼兼用なので、かつ丼と冷や奴にする。客の前に必ずあったのを見て取った冷や奴は、びっくりするほど安かった。それにしても腹の中が空っぽになると、ついついかつ丼とは、我ながら平凡な男よな、……。
新潟県上越市公文書センターで古文書をコピーさせてもらう。センターに向かう道すがら左右に広がる田を見て、悲しくなる。それにしても上越市の田の状況は異常だと思う。高田城市公園にもどりしばしテキストを打つ。散歩中のご夫婦に一番近い食堂の名前を聞いて向かう。教わった『食堂なかしま』という店は見た目からして真新しい。少々不安に感じたが、中はいたって普通の食堂だった。お腹と背中がくっついた末の、朝昼兼用なので、かつ丼と冷や奴にする。客の前に必ずあったのを見て取った冷や奴は、びっくりするほど安かった。それにしても腹の中が空っぽになると、ついついかつ丼とは、我ながら平凡な男よな、……。 2025年8月29日、10時前に上越市南本町の『高橋孫左衛門商店』に立ち寄る。少しだけ歩いてみたかった南本町だが、時間がなかったので笹飴だけを買った。『高橋孫左衛門商店』は1624年創業という。となると徳川三代将軍家光の時代で、貨幣経済はまだ不完全な時代である。また、十返舎一九(明和2年〜天保2年/1765-1831)も立ち寄ったことがあるという。東海道中膝栗毛が売れに売れた後、生活のためもあって、死ぬまで道中記を書いていた。その一九が『越後紀行集』を書くにあたって立ち寄っていたらしい。そしていちばん有名なのは、夏目漱石の『坊ちゃん』(明治39/1906)に出てくる越後の笹飴である。小説の筋とは無関係に唐突に下女の清の好物として越後の笹飴が登場し、笹ごと飴を食べる清の姿が坊ちゃんの夢に出る。
2025年8月29日、10時前に上越市南本町の『高橋孫左衛門商店』に立ち寄る。少しだけ歩いてみたかった南本町だが、時間がなかったので笹飴だけを買った。『高橋孫左衛門商店』は1624年創業という。となると徳川三代将軍家光の時代で、貨幣経済はまだ不完全な時代である。また、十返舎一九(明和2年〜天保2年/1765-1831)も立ち寄ったことがあるという。東海道中膝栗毛が売れに売れた後、生活のためもあって、死ぬまで道中記を書いていた。その一九が『越後紀行集』を書くにあたって立ち寄っていたらしい。そしていちばん有名なのは、夏目漱石の『坊ちゃん』(明治39/1906)に出てくる越後の笹飴である。小説の筋とは無関係に唐突に下女の清の好物として越後の笹飴が登場し、笹ごと飴を食べる清の姿が坊ちゃんの夢に出る。 最初に、漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。浮かんでいるだけで助かる可能性が高い。さて新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っているが、漁港内にもいろんな魚がいるのである。ヒイラギは隣で釣っていた高校生がダブルで揚げていたので、魚影が濃いのかも知れない。潮時と関係なく釣れるのもありがたい。浅場にいるので、防波堤釣り(波止釣り)をしていると結構釣れる魚ではあるが、マアジなどとは違い持ち帰らない人が多い。棘があるしヌメリがあるけれど、マアジよりもおいしいんだよ、と言いたい。島根県中海周辺では高級魚だし、高知県でも好んで食べる。持って帰ってねといいたい。しかもしかもこの魚、シイカシイカっと光るのである。食道にいる発光細菌の光りなのでそんなに強い光ではない。でもこのかそけき光が幻想的なのだ。浅場で見ていると、惹かれて魅了される。ついでにこの魚かなり愚痴っぽい。ぐちぐちは言わないけど、ギギギーと鳴く。そーっと観察して御覧、なのだ。
最初に、漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。浮かんでいるだけで助かる可能性が高い。さて新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っているが、漁港内にもいろんな魚がいるのである。ヒイラギは隣で釣っていた高校生がダブルで揚げていたので、魚影が濃いのかも知れない。潮時と関係なく釣れるのもありがたい。浅場にいるので、防波堤釣り(波止釣り)をしていると結構釣れる魚ではあるが、マアジなどとは違い持ち帰らない人が多い。棘があるしヌメリがあるけれど、マアジよりもおいしいんだよ、と言いたい。島根県中海周辺では高級魚だし、高知県でも好んで食べる。持って帰ってねといいたい。しかもしかもこの魚、シイカシイカっと光るのである。食道にいる発光細菌の光りなのでそんなに強い光ではない。でもこのかそけき光が幻想的なのだ。浅場で見ていると、惹かれて魅了される。ついでにこの魚かなり愚痴っぽい。ぐちぐちは言わないけど、ギギギーと鳴く。そーっと観察して御覧、なのだ。 2025年8月29日、8時半過ぎに上越市高田の朝市に向かう。上越市は高田の朝市が3,4、7、9のつく日、直江津が3、8のつく日にある。新潟県の魅力のひとつが県内各地に散らばる朝市である。ボクなど朝市が好きで新潟に行く。ところが年々、新潟の朝市が寂しくなるが上越市もその例に漏れない。専業農家が少なくなり、兼業農家ばかりになり、現金収入があるために市に来なくなったのかも。主役となる農家の出店が消えている。しかも名物、「どらやき」がない。
2025年8月29日、8時半過ぎに上越市高田の朝市に向かう。上越市は高田の朝市が3,4、7、9のつく日、直江津が3、8のつく日にある。新潟県の魅力のひとつが県内各地に散らばる朝市である。ボクなど朝市が好きで新潟に行く。ところが年々、新潟の朝市が寂しくなるが上越市もその例に漏れない。専業農家が少なくなり、兼業農家ばかりになり、現金収入があるために市に来なくなったのかも。主役となる農家の出店が消えている。しかも名物、「どらやき」がない。 新潟県でよく見かけるのが「伊勢ひじき」である。赤い縁取りをした紙のパッケージに入っていて、昔ながらの文様が描かれている。山陰以北の日本海ではヒジキがとれないので、新潟県では古くより伊勢(三重県伊勢地方)からヒジキを取り寄せて流通させていたのかな? などと思ったりする。今回、「伊勢ひじき」を買った新潟県西区内野町『ichiman』は、新潟市の地スーパーといったところで、新潟を感じさせるものがたくさん売られていた。「伊勢ひじき」、『角平商会』(三重県多気郡明和町大淀乙655)は三重県伊勢地方のものだけど新潟らしいと感じて買ってしまう、ものでもあるのだ。
新潟県でよく見かけるのが「伊勢ひじき」である。赤い縁取りをした紙のパッケージに入っていて、昔ながらの文様が描かれている。山陰以北の日本海ではヒジキがとれないので、新潟県では古くより伊勢(三重県伊勢地方)からヒジキを取り寄せて流通させていたのかな? などと思ったりする。今回、「伊勢ひじき」を買った新潟県西区内野町『ichiman』は、新潟市の地スーパーといったところで、新潟を感じさせるものがたくさん売られていた。「伊勢ひじき」、『角平商会』(三重県多気郡明和町大淀乙655)は三重県伊勢地方のものだけど新潟らしいと感じて買ってしまう、ものでもあるのだ。 最初に漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。さて新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。新川漁港の漁港内は釣り初心者には一日遊べるところだし、横を流れる新川側などでは上級者にとっても大物が狙える場所である。また漁港内にもいろんな魚、ホヤ類、甲殻類などがいる。網ですくうといろんな生き物がとれる。
最初に漁港で遊ぶときは救命胴衣を着用してほしい。漁港内で落ちたらまず助からない。子供用など2000円以下のものもある。さて新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。新川漁港の漁港内は釣り初心者には一日遊べるところだし、横を流れる新川側などでは上級者にとっても大物が狙える場所である。また漁港内にもいろんな魚、ホヤ類、甲殻類などがいる。網ですくうといろんな生き物がとれる。 2025年8月29日、早朝5時から上越市、一印上越魚市場で、挨拶もしないまま並んでいる水産生物を調べる。徹底的に産地と水産生物を撮影、気になるものは後々テキスト化できるようにメモを取る。横道世之介、ときどき視察という名目で背広組が市場を見学しているのに出くわすことがあるけれど、100%税金の無駄である。メモも取っているわけでもないし、何も見ていない。差別用語が含まれるが群盲象を評す以上に意味がない。市場で物事が見られるようになるためには熟練を要す。背広組の市場視察は背広組だけでは無理、やめなさいといいたい。背広組と違ってボクの市場は超過酷、かつ重労働なのだ。競りが終わったあと高田城址公園で暫しまどろむ、というか意識をなくす。目覚ましがなって堀まで歩いたら、曇り空の下そこは極楽浄土だった。夜を徹しての新潟行なので疲れはとれないが、極楽へのエレベ−ターに乗った気分になる。
2025年8月29日、早朝5時から上越市、一印上越魚市場で、挨拶もしないまま並んでいる水産生物を調べる。徹底的に産地と水産生物を撮影、気になるものは後々テキスト化できるようにメモを取る。横道世之介、ときどき視察という名目で背広組が市場を見学しているのに出くわすことがあるけれど、100%税金の無駄である。メモも取っているわけでもないし、何も見ていない。差別用語が含まれるが群盲象を評す以上に意味がない。市場で物事が見られるようになるためには熟練を要す。背広組の市場視察は背広組だけでは無理、やめなさいといいたい。背広組と違ってボクの市場は超過酷、かつ重労働なのだ。競りが終わったあと高田城址公園で暫しまどろむ、というか意識をなくす。目覚ましがなって堀まで歩いたら、曇り空の下そこは極楽浄土だった。夜を徹しての新潟行なので疲れはとれないが、極楽へのエレベ−ターに乗った気分になる。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁港の漁港内は初心者には一日遊べるところだし、横を流れる新川側などでは上級者にとっても大物が狙える場所である。新川漁港内では小物が、横を流れる新川側では大物が釣れるのだが、地元の高校生が新川側に行ったり、漁港内に行ったりして次々に釣り上げていたのがクロダイである。新川側で釣り上げたのが20cmクラス、漁港内のサビキに来たのが9cmほどである。あまりにもきれいなので撮影させてもらった。要するにこれは高校生の釣果の横取りというやつだ。新川側では大物が来るようだが、さすがに日が昇り潮止まりとあってはそれは望むべくもない。それでも飽きない程度に釣れるのがいい。近所に新川釣具があって便利な釣り場でもある。釣りマナーを守れる人はぜひ、新川漁港へ。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁港の漁港内は初心者には一日遊べるところだし、横を流れる新川側などでは上級者にとっても大物が狙える場所である。新川漁港内では小物が、横を流れる新川側では大物が釣れるのだが、地元の高校生が新川側に行ったり、漁港内に行ったりして次々に釣り上げていたのがクロダイである。新川側で釣り上げたのが20cmクラス、漁港内のサビキに来たのが9cmほどである。あまりにもきれいなので撮影させてもらった。要するにこれは高校生の釣果の横取りというやつだ。新川側では大物が来るようだが、さすがに日が昇り潮止まりとあってはそれは望むべくもない。それでも飽きない程度に釣れるのがいい。近所に新川釣具があって便利な釣り場でもある。釣りマナーを守れる人はぜひ、新川漁港へ。 まさか新潟の市場にハマグリがあるとは思わなかった。一時は絶滅危惧種であったほどなので、まさかまさか新潟で出合えるなんて。さっそく手に入れて持ち帰った。手に取ってみるとまさしくハマグリなので、大いに感激する。帰宅した日に吸物にした。料理以前の料理で、差し昆布(昆布の切れ端を入れる)をした水に洗ったハマグリを沈めて火をつける。殻が開いたら出来上がりだけど、火を通しながら身がふくらんできているのがわかる。ふっくらと柔らかくハマグリらしいうま味に満ちている。チョウセンハマグリとの微妙な差はわからないけど、この吸物は絶品である。
まさか新潟の市場にハマグリがあるとは思わなかった。一時は絶滅危惧種であったほどなので、まさかまさか新潟で出合えるなんて。さっそく手に入れて持ち帰った。手に取ってみるとまさしくハマグリなので、大いに感激する。帰宅した日に吸物にした。料理以前の料理で、差し昆布(昆布の切れ端を入れる)をした水に洗ったハマグリを沈めて火をつける。殻が開いたら出来上がりだけど、火を通しながら身がふくらんできているのがわかる。ふっくらと柔らかくハマグリらしいうま味に満ちている。チョウセンハマグリとの微妙な差はわからないけど、この吸物は絶品である。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。今回は新川漁協で水揚げされる代表的な魚のひとつ「ねずり」と呼ばれている、アカシタビラメである。1尾だけだったので入念に同定して、水洗いする。アカシタビラメの定番料理と言えばムニエルである。皮が剥きやすいのが特徴で、ある意味、まな板を汚さない魚である。今回は産卵期なのか比較的大きな卵巣が入っていた。剥いて塩コショウする。小麦粉をつけて、じっくりとソテーし、仕上げにバターで風味づけする。鰭際の香ばしさが際立つ。不思議なもので中心部分よりも鰭と鰭筋にうま味がある。この鰭際だけでもゴージャスな味である。そこに真子の甘味が加わるのだから言うこと無し。少しだけ醤油を垂らして、ご飯を食べた。じっくりソテーしていて骨があまり気にならないので格好のおかずである。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っている。今回は新川漁協で水揚げされる代表的な魚のひとつ「ねずり」と呼ばれている、アカシタビラメである。1尾だけだったので入念に同定して、水洗いする。アカシタビラメの定番料理と言えばムニエルである。皮が剥きやすいのが特徴で、ある意味、まな板を汚さない魚である。今回は産卵期なのか比較的大きな卵巣が入っていた。剥いて塩コショウする。小麦粉をつけて、じっくりとソテーし、仕上げにバターで風味づけする。鰭際の香ばしさが際立つ。不思議なもので中心部分よりも鰭と鰭筋にうま味がある。この鰭際だけでもゴージャスな味である。そこに真子の甘味が加わるのだから言うこと無し。少しだけ醤油を垂らして、ご飯を食べた。じっくりソテーしていて骨があまり気にならないので格好のおかずである。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者と一緒に波打ち際で見つけた生物の4番目はキンセンガニである。日本各地の浅い砂地にいる小型のカニで、漁の対象ではなく、子供の遊び相手といった存在である。丸っこくて見た目が可愛いので、海辺暮らしをしていればだれもが必ず出合う存在といったものだろう。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者と一緒に波打ち際で見つけた生物の4番目はキンセンガニである。日本各地の浅い砂地にいる小型のカニで、漁の対象ではなく、子供の遊び相手といった存在である。丸っこくて見た目が可愛いので、海辺暮らしをしていればだれもが必ず出合う存在といったものだろう。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然界にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者とともに自然界、波打ち際で見つけた生物の3番目は砂浜にいるネズリの子だ。砂の上でぴたぴた跳ねているのを見るまで、まさか手づかみで波の中にいる魚をつかまえる人がいるとは思わなかった。全長70mmしかないので、ウシノシタ科の魚であることはわかったが、そこから先は見当がつかない。マクロ撮影して拡大してその正体がわかった。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然界にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者とともに自然界、波打ち際で見つけた生物の3番目は砂浜にいるネズリの子だ。砂の上でぴたぴた跳ねているのを見るまで、まさか手づかみで波の中にいる魚をつかまえる人がいるとは思わなかった。全長70mmしかないので、ウシノシタ科の魚であることはわかったが、そこから先は見当がつかない。マクロ撮影して拡大してその正体がわかった。 長野県には、そばやうどんを大根の搾り汁とみそで食べる文化がある。上田市や高遠ではそばを食べ、うどんはスーパーで「おしぼりうどん(古越製麺所 御代田町・滝沢食品 千曲市)」でしか知らない。農水省のサイトには長野県坂城町の郷土料理とあるので、「おしぼりうどん」の名を、御代田町と千曲市の会社がとったのかも知れないと、最初は思っていた。ただ農水省は郷土料理を深く掘り下げたりはしない。「おしぼり」というのは辛味大根を下ろして汁を搾ったもので、「おしぼり」で食べる「うどん」ということになる。あたりまえだけど、そばを食べると「おしぼりそば」である。長野県は、そばだけではなく、うどんもよく食べるところなので「おしぼり」でそばを食べるなら、当然、長野県の各地で、「おしぼり」でうどんも食べるはずという当然のことが、農水省には見えていない。だから農水省が坂城町を挙げると、まるで坂城町だけの郷土料理のように見えしまう。またゆで汁ごと出して熱いうどんを「おしぼり」で食べる、とするとそれが法律の如く一人歩きする。無意識でも無駄な法律を作り出すのは愚か者のやることである。本流などといういかがわしいことをいう人間が出てくる。松代町で買ったときなどは普通の冷やしうどんのように食べる、と聞いた。食べ方は家々で違う可能性がある。農水省のページには往々にして、このような他の地域に対する配慮に欠ける決めつけが見受けられる。農水省が郷土料理を大切に思うなら、この点、早急に改訂すべし。
長野県には、そばやうどんを大根の搾り汁とみそで食べる文化がある。上田市や高遠ではそばを食べ、うどんはスーパーで「おしぼりうどん(古越製麺所 御代田町・滝沢食品 千曲市)」でしか知らない。農水省のサイトには長野県坂城町の郷土料理とあるので、「おしぼりうどん」の名を、御代田町と千曲市の会社がとったのかも知れないと、最初は思っていた。ただ農水省は郷土料理を深く掘り下げたりはしない。「おしぼり」というのは辛味大根を下ろして汁を搾ったもので、「おしぼり」で食べる「うどん」ということになる。あたりまえだけど、そばを食べると「おしぼりそば」である。長野県は、そばだけではなく、うどんもよく食べるところなので「おしぼり」でそばを食べるなら、当然、長野県の各地で、「おしぼり」でうどんも食べるはずという当然のことが、農水省には見えていない。だから農水省が坂城町を挙げると、まるで坂城町だけの郷土料理のように見えしまう。またゆで汁ごと出して熱いうどんを「おしぼり」で食べる、とするとそれが法律の如く一人歩きする。無意識でも無駄な法律を作り出すのは愚か者のやることである。本流などといういかがわしいことをいう人間が出てくる。松代町で買ったときなどは普通の冷やしうどんのように食べる、と聞いた。食べ方は家々で違う可能性がある。農水省のページには往々にして、このような他の地域に対する配慮に欠ける決めつけが見受けられる。農水省が郷土料理を大切に思うなら、この点、早急に改訂すべし。 水産物とヒトとの関わりを調べた、その調べ始めの地が新潟県である。学生気分が抜けないときであったが、最初に新潟で感じたことはサケ比率が高いことだ。徳島から上京したとき、東京にはサケが多いと思ったものだが、新潟のサケ度は東京と比較できないほど高い。どこに行ってもサケがあり、マス(カラフトマス)があり、季節には本マス(サクラマス)がある。その頂点にあるのがサケで、庶民的なマス(カラフトマス)がある。季節限定の本マス(サクラマス)がある山形県よりも本マス(サクラマス)の地位が低いのも新潟県の特徴だろう。さて、北海道のサケ漁はトキシラズの初夏から始まるが、新潟県などでは9月中旬から始まり10月、11月が盛漁期である。今年、新潟市西区五十嵐新川にサケ漁を見に行きたいと思っているが、県内でのサケ漁の前、9月1日に、新潟市のスーパーでサケのブロックを買った。新潟中央市場、上越市一印にも北海道からたっぷりサケがやって来ていた。少なくなってはいるが、新潟県では今でもサケがとれている。でも、漁期前なのでスーパーのサケ売り場の主役は北海道産だ。これこそが産地間流通(産地はその産物をとるだけではなく、好む傾向があるので、ないときには別の産地からもってくる)というものだ。そして、新潟市のスーパーで買った北海道産サケが非常に上物であった。いいサケを見極める能力が新潟県人にはあり、それを流通のプロ達もよく知っているのだろう。
水産物とヒトとの関わりを調べた、その調べ始めの地が新潟県である。学生気分が抜けないときであったが、最初に新潟で感じたことはサケ比率が高いことだ。徳島から上京したとき、東京にはサケが多いと思ったものだが、新潟のサケ度は東京と比較できないほど高い。どこに行ってもサケがあり、マス(カラフトマス)があり、季節には本マス(サクラマス)がある。その頂点にあるのがサケで、庶民的なマス(カラフトマス)がある。季節限定の本マス(サクラマス)がある山形県よりも本マス(サクラマス)の地位が低いのも新潟県の特徴だろう。さて、北海道のサケ漁はトキシラズの初夏から始まるが、新潟県などでは9月中旬から始まり10月、11月が盛漁期である。今年、新潟市西区五十嵐新川にサケ漁を見に行きたいと思っているが、県内でのサケ漁の前、9月1日に、新潟市のスーパーでサケのブロックを買った。新潟中央市場、上越市一印にも北海道からたっぷりサケがやって来ていた。少なくなってはいるが、新潟県では今でもサケがとれている。でも、漁期前なのでスーパーのサケ売り場の主役は北海道産だ。これこそが産地間流通(産地はその産物をとるだけではなく、好む傾向があるので、ないときには別の産地からもってくる)というものだ。そして、新潟市のスーパーで買った北海道産サケが非常に上物であった。いいサケを見極める能力が新潟県人にはあり、それを流通のプロ達もよく知っているのだろう。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。うまいもん揃いだとも言えるだろう。その最たるものがコナガニシである。日本海に多い巻き貝であるが、唾液腺にテトラミンを持ち、内臓に苦みがあるなど、非常にやっかいな存在だ。日本海側では鳥取県、石川県では食べているが、他の地域では見向きもしない。ただし、刺身にするとこれ以上の美味は望めない、と思っている。歩留まりは最低である。食べる部分はふたのついた足の部分だけ、あとは洗い流す。ぬめりはほとんどないので、水分をきって適当に切るだけだ。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。うまいもん揃いだとも言えるだろう。その最たるものがコナガニシである。日本海に多い巻き貝であるが、唾液腺にテトラミンを持ち、内臓に苦みがあるなど、非常にやっかいな存在だ。日本海側では鳥取県、石川県では食べているが、他の地域では見向きもしない。ただし、刺身にするとこれ以上の美味は望めない、と思っている。歩留まりは最低である。食べる部分はふたのついた足の部分だけ、あとは洗い流す。ぬめりはほとんどないので、水分をきって適当に切るだけだ。 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然界にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者とともに見つけた生物の1番目は砂浜にいるフジノハナガイである。大きさ1cm前後の小さな小さな二枚貝だけど、実に美しい。形はスヌーピーのようだし、名前の通り「藤の花」の花弁のようだ。やたらに美しく、しかも可憐である。昔々は子供達の格好の遊び相手だった。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協やその周辺には自然界にも、食べ物にも詳しい猛者がたくさんいる。この猛者とともに見つけた生物の1番目は砂浜にいるフジノハナガイである。大きさ1cm前後の小さな小さな二枚貝だけど、実に美しい。形はスヌーピーのようだし、名前の通り「藤の花」の花弁のようだ。やたらに美しく、しかも可憐である。昔々は子供達の格好の遊び相手だった。 瀬戸内海周辺は「茶かゆ」をよく食べる。家島諸島(兵庫県姫路市)坊勢島でも、「茶かゆ」を食べているのだとばかり思っていた。実際に坊勢島に水揚げや水産物の話を聞きに行って、ついでと言ってはなんだが、「茶がゆ」のことを聞くと、島では「茶がゆ」ではなく「緑豆がゆ」だという。坊勢漁業協同組合で教わって、「どんなものだろう、食べたいな」と言ったら、島のオカアサンが持って来てくれた。朝煮て、冷たくして昼に食べようと思っていたものらしい。それほど冷えてはいないが、喉ごしがいいので涼やかな味がする。程よい塩味で、緑豆のもつ、青臭み(?)が実に好ましい。気がついたら、オカアサンのお昼ご飯を全部平らげてしまっていた。お昼ご飯、大丈夫だったかな?「緑豆の入ったかゆは食べても、すぐ腹が空きます」と言われたが、本当にすぐ腹が空いてきた。坊勢島にはすしの名店があり、旅館のご飯も矢鱈においしかった。鱈腹食べた後なのに、また「緑豆がゆ」が食べたくなった。
瀬戸内海周辺は「茶かゆ」をよく食べる。家島諸島(兵庫県姫路市)坊勢島でも、「茶かゆ」を食べているのだとばかり思っていた。実際に坊勢島に水揚げや水産物の話を聞きに行って、ついでと言ってはなんだが、「茶がゆ」のことを聞くと、島では「茶がゆ」ではなく「緑豆がゆ」だという。坊勢漁業協同組合で教わって、「どんなものだろう、食べたいな」と言ったら、島のオカアサンが持って来てくれた。朝煮て、冷たくして昼に食べようと思っていたものらしい。それほど冷えてはいないが、喉ごしがいいので涼やかな味がする。程よい塩味で、緑豆のもつ、青臭み(?)が実に好ましい。気がついたら、オカアサンのお昼ご飯を全部平らげてしまっていた。お昼ご飯、大丈夫だったかな?「緑豆の入ったかゆは食べても、すぐ腹が空きます」と言われたが、本当にすぐ腹が空いてきた。坊勢島にはすしの名店があり、旅館のご飯も矢鱈においしかった。鱈腹食べた後なのに、また「緑豆がゆ」が食べたくなった。 我がサイトの、テーマのひとつが季節と地域性である。群馬県といえば「もつ煮込み」が浮かぶが、なぜだろう? と思って過去の画像を渉猟する。群馬県のスーパー、直売所巡りは定期的にやっている。当然、朝ご飯もしくは昼ご飯を食べてくる。北は渋川市から南は館林市までの画像だが、朝ご飯、昼ご飯の画像整理していると、やたらに「もつ煮込み」が見つかるのである。太田市の食堂では、「群馬県は豚肉をよく食べるので、『豚もつ煮込み』もよく食べる」と教わった。肉には詳しくないが、この「もつ煮込み度」の高さは他の県には見られないのではないか。高崎市総合地方卸売市場の『市場食堂』には「もつ煮込み」の大盛りまである。群馬県内の「もつ煮込み」はどこで食べてもおいしいのもありがたい。
我がサイトの、テーマのひとつが季節と地域性である。群馬県といえば「もつ煮込み」が浮かぶが、なぜだろう? と思って過去の画像を渉猟する。群馬県のスーパー、直売所巡りは定期的にやっている。当然、朝ご飯もしくは昼ご飯を食べてくる。北は渋川市から南は館林市までの画像だが、朝ご飯、昼ご飯の画像整理していると、やたらに「もつ煮込み」が見つかるのである。太田市の食堂では、「群馬県は豚肉をよく食べるので、『豚もつ煮込み』もよく食べる」と教わった。肉には詳しくないが、この「もつ煮込み度」の高さは他の県には見られないのではないか。高崎市総合地方卸売市場の『市場食堂』には「もつ煮込み」の大盛りまである。群馬県内の「もつ煮込み」はどこで食べてもおいしいのもありがたい。 市場に来てみませんか? という話をしたい。関東を見回しても、一般客を受け入れない市場はなくなったと言っていいだろう。むしろ、一般客大歓迎といった市場ばかりである。市場では高級料理店でしか食べられない魚が、手に入る。もちろんお買い得なものもたっぷりある。野菜なども同じである。
市場に来てみませんか? という話をしたい。関東を見回しても、一般客を受け入れない市場はなくなったと言っていいだろう。むしろ、一般客大歓迎といった市場ばかりである。市場では高級料理店でしか食べられない魚が、手に入る。もちろんお買い得なものもたっぷりある。野菜なども同じである。 ナウなことには興味がないし、テレビもザッピングでしか見ないので、世の評判などとはまったく無縁である。あらゆる情報から離れたところにいる、といってもいいだろう。国内各地に行くと、店の位置まではネットを見るが、できる限り、その土地に根づいているものを探す。お昼ご飯を食べるときは、できれば個人経営の店を目指す。余談になるが、ボクは明らかに知名度ゼロの人間である。どこからどう見ても目立たない薄汚いデブオヤジだ。たまたまだろうが、浜松市で3組の方達から声をかけられた。希に、ごく希に「ですよね」と話しかけられることがあるが、複数の方に声をかけられたのは初めてだ。昼を過ぎていたので、その中のご夫婦の方に、「このあたりに昔ながらのものが食べられるところありますか?」と聞いたら、ついてきなさいと言ったので、ついて行った。ムムム、そこは思いもしなかったところ、ボクが絶対に足を踏み入れないところ、チェーン店だったのだ。仕方なく店内に入って席に着くやいなや、目撃したその光景にビックリ仰天した。出て来た料理と店員さんとで写真をとっている家族がいたのだ。とすると、これはこれで「昔ながらのもの」なのか?あとあとウィキで調べると、なんだかんだあって今の形の創業は1989年のようだ。どう考えても老舗とは言えないと思うが、悪意で教えてくれたわけでもないだろう。
ナウなことには興味がないし、テレビもザッピングでしか見ないので、世の評判などとはまったく無縁である。あらゆる情報から離れたところにいる、といってもいいだろう。国内各地に行くと、店の位置まではネットを見るが、できる限り、その土地に根づいているものを探す。お昼ご飯を食べるときは、できれば個人経営の店を目指す。余談になるが、ボクは明らかに知名度ゼロの人間である。どこからどう見ても目立たない薄汚いデブオヤジだ。たまたまだろうが、浜松市で3組の方達から声をかけられた。希に、ごく希に「ですよね」と話しかけられることがあるが、複数の方に声をかけられたのは初めてだ。昼を過ぎていたので、その中のご夫婦の方に、「このあたりに昔ながらのものが食べられるところありますか?」と聞いたら、ついてきなさいと言ったので、ついて行った。ムムム、そこは思いもしなかったところ、ボクが絶対に足を踏み入れないところ、チェーン店だったのだ。仕方なく店内に入って席に着くやいなや、目撃したその光景にビックリ仰天した。出て来た料理と店員さんとで写真をとっている家族がいたのだ。とすると、これはこれで「昔ながらのもの」なのか?あとあとウィキで調べると、なんだかんだあって今の形の創業は1989年のようだ。どう考えても老舗とは言えないと思うが、悪意で教えてくれたわけでもないだろう。 ボクが調べているのは水産生物でもあるし、地域性でもあるし、季節でもある。47都道府県のいろんな地域に行っているが、特色のあるものを、もちろん食品に限るが買って帰ってきている。静岡県に行くと必ず買ってくるのが、「金山寺みそ」である。意外に「金山寺みそ」とか、「醤油のみ(ひしお)」が好きなのだけど、静岡県に行くとどこのスーパーに寄っても「金山寺みそ」である。これほど「金山寺みそ」の多い県も少ない気がする。
ボクが調べているのは水産生物でもあるし、地域性でもあるし、季節でもある。47都道府県のいろんな地域に行っているが、特色のあるものを、もちろん食品に限るが買って帰ってきている。静岡県に行くと必ず買ってくるのが、「金山寺みそ」である。意外に「金山寺みそ」とか、「醤油のみ(ひしお)」が好きなのだけど、静岡県に行くとどこのスーパーに寄っても「金山寺みそ」である。これほど「金山寺みそ」の多い県も少ない気がする。 ボクの故郷、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)は県内、吉野川真ん中あたりで、都会に出るというと徳島市だった。香川県に出ることはほとんどなく、意外に遠い場所だった気がする。「香川」というと記憶が曖昧だけど丸亀(?)であって、家族がウチワを仕入れに行くとき何度かついて行った。ウチワの注文をして、名を入れる、とかいろんなことをやっている間、まだ子供のボクは、瓦煎餅とかまんじゅうでお茶を飲むのが楽しみだった。ウチワ屋のお茶は苦いけど軽くて口の中がすっきりした。これが、碁石茶だった気がする。碁石茶は高知県大豊町などで作っている国内では珍しい発酵茶で、高知県ではなく香川県海辺や離島で飲まれていた。海水浴で何度か行った、香川県海岸寺の海の家で飲んでいたお茶も同じ味だった気がする。ちなみに父は職人だったので、他にも何軒か回った。そのときのお茶は我が家と同じ緑茶で、ボクにはジュースが出た。ジュースとお茶をかわりばんこに飲むの見た、得意先のオバサンに笑われたりした。曖昧模糊で、はっきりしないけど、「めも」なのでお許しを。塩飽諸島など離島、漁師さんが飲むものという話があるが、このような家内工業の場や海の家などでも飲んでいたのだと思う。ちなみに碁石茶らしきものを意識したのは、サンテレビ(?)の伊丹十三の番組でだと記憶する。四国の山間部を歩くという番組だった。新聞のテレビ欄まで見て、合わせて帰宅していたくらい面白い番組だった。もしも録画が残っているなら、もう一度見てみたい。
ボクの故郷、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)は県内、吉野川真ん中あたりで、都会に出るというと徳島市だった。香川県に出ることはほとんどなく、意外に遠い場所だった気がする。「香川」というと記憶が曖昧だけど丸亀(?)であって、家族がウチワを仕入れに行くとき何度かついて行った。ウチワの注文をして、名を入れる、とかいろんなことをやっている間、まだ子供のボクは、瓦煎餅とかまんじゅうでお茶を飲むのが楽しみだった。ウチワ屋のお茶は苦いけど軽くて口の中がすっきりした。これが、碁石茶だった気がする。碁石茶は高知県大豊町などで作っている国内では珍しい発酵茶で、高知県ではなく香川県海辺や離島で飲まれていた。海水浴で何度か行った、香川県海岸寺の海の家で飲んでいたお茶も同じ味だった気がする。ちなみに父は職人だったので、他にも何軒か回った。そのときのお茶は我が家と同じ緑茶で、ボクにはジュースが出た。ジュースとお茶をかわりばんこに飲むの見た、得意先のオバサンに笑われたりした。曖昧模糊で、はっきりしないけど、「めも」なのでお許しを。塩飽諸島など離島、漁師さんが飲むものという話があるが、このような家内工業の場や海の家などでも飲んでいたのだと思う。ちなみに碁石茶らしきものを意識したのは、サンテレビ(?)の伊丹十三の番組でだと記憶する。四国の山間部を歩くという番組だった。新聞のテレビ欄まで見て、合わせて帰宅していたくらい面白い番組だった。もしも録画が残っているなら、もう一度見てみたい。 数量的にはわからないけど、浅いところの泥を網ですくっても貝が入ってこない。護岸を見ても貝類があまり見当たらないのはなぜだろう?大量についているはずのムラサキイガイがあまりいないし、昔、アサリ漁をやっていたことがあるという人に聞くと、タマガイ科の貝がいないという。「あけみがい(イソシジミ)」はもっと見ていないらしい。マガキの付着も少ない気がする。鷲津方面で落ちていないかと探したタマガイ科の巻き貝はやはり見つけられなかった。今回、落ちている貝殻の中でヒラフネガイも探したけど見つからず。今回は慌ただしくて、じっくり見て回れなかったが、次回は車中泊しながら水辺をじっくり観察したいと考えている。それにしても浜名湖にたくさんいたタマガイ科などなどは、どこに行ったんだろう。今の浜名湖は、どことなく不気味である。今回の参院選でひとりも自然保護や温暖化を叫ぶ立候補者がいない。生き物を見ていても明らかに危険な状況にある、と思うんだけど、自然保護は金にならないからやらないんだろうな。
数量的にはわからないけど、浅いところの泥を網ですくっても貝が入ってこない。護岸を見ても貝類があまり見当たらないのはなぜだろう?大量についているはずのムラサキイガイがあまりいないし、昔、アサリ漁をやっていたことがあるという人に聞くと、タマガイ科の貝がいないという。「あけみがい(イソシジミ)」はもっと見ていないらしい。マガキの付着も少ない気がする。鷲津方面で落ちていないかと探したタマガイ科の巻き貝はやはり見つけられなかった。今回、落ちている貝殻の中でヒラフネガイも探したけど見つからず。今回は慌ただしくて、じっくり見て回れなかったが、次回は車中泊しながら水辺をじっくり観察したいと考えている。それにしても浜名湖にたくさんいたタマガイ科などなどは、どこに行ったんだろう。今の浜名湖は、どことなく不気味である。今回の参院選でひとりも自然保護や温暖化を叫ぶ立候補者がいない。生き物を見ていても明らかに危険な状況にある、と思うんだけど、自然保護は金にならないからやらないんだろうな。 前回の浜名湖は11月で湖内の漁が終わろうとするときだった。いちばん楽なときに、何も考えないで行ったので、あまり意味のある浜名湖ではなかった。20年振りの浜名湖は、ゼロからの一歩となる。今回、聞取した情報量が多すぎ、脳内で処理できなかった。当然、メモの、移動中での整理が追いつかなかった。しかも暑い。今回の浜名湖旅は、不正確な情報だらけであるが、じょじょに整理して、テキスト化していく。今回の誤算は浜名湖の大きさと、地域性を考えなかったことだ。当然、もらった情報は曖昧になる。次回は地域を決めて、もっと予習してから行くこととする。写真は車の中でメモ整理中に飲んだ三ヶ日みかんジュース。値段以上で、体がゆるむ味だった。帰宅後はメモの再整理も、持ち帰ったものの整理も出来ず、そのままダウン。
前回の浜名湖は11月で湖内の漁が終わろうとするときだった。いちばん楽なときに、何も考えないで行ったので、あまり意味のある浜名湖ではなかった。20年振りの浜名湖は、ゼロからの一歩となる。今回、聞取した情報量が多すぎ、脳内で処理できなかった。当然、メモの、移動中での整理が追いつかなかった。しかも暑い。今回の浜名湖旅は、不正確な情報だらけであるが、じょじょに整理して、テキスト化していく。今回の誤算は浜名湖の大きさと、地域性を考えなかったことだ。当然、もらった情報は曖昧になる。次回は地域を決めて、もっと予習してから行くこととする。写真は車の中でメモ整理中に飲んだ三ヶ日みかんジュース。値段以上で、体がゆるむ味だった。帰宅後はメモの再整理も、持ち帰ったものの整理も出来ず、そのままダウン。 「浜から山(里)へ」は水産流通の基本である。海でとれたものを塩をするか、焼くかして山に向かって売りに行くことでこの国の食料の循環が行われていたのである。例えば塩をするか、焼くかしたサバ(マサバ)を山に運び、米や米ぬかと交換することで浜は糖質を補給していた。山の人は動物たんぱくを得られた。この浜から山へ、山から浜へを考えていきたい。新潟の浜では古くから魚を早朝から炭火で焼き上げ、山間部に運んでいた。いったいどんな魚を焼いていたのか?新潟市本町での、炭火に串に刺された光景は絵になるので、多くの書籍に写真はあるが、その魚の種類までは載っていない。農文協の聞き書きシリーズにもない。1988年の『新潟料理 ふるさとの味』(桜井薫 新潟日報事業社)に〈イカ、サバ、カレイ、アナゴ、ギス〉とある。それぞれスルメイカ、マサバ、マガレイ、クロメクラウナギ、ニギスである。カレイは日本海側では青森県から富山県まではマガレイ、石川県、福井県がアカガレイだと思っている。みな地先の浜でたっぷりとれていたものばかりである。ちなみにマガレイを海辺の魚屋で焼いて売るというのは、新発田市や村上市にもある。山形県でも同じである。新潟市の浜焼きは、何度も買い求めている。その光景以上に魅力的なのが、その香りである。見ていると食べたくなのは、この香りのせいだ。とても丸々一尾は食べられないが、冷めてもおいしいところも魅力である。寺泊は今や観光地と化しているが、ここも浜焼きが有名である。もうひとつの浜焼きの町が出雲崎である。1980年代に二度も行って、二度とも買っているが、ただ単に買って食べただけで終わっている。2004年にも浜焼きを買っているものの、なぜか画像がない。残念なことに焼いている時間には一度も行き会わせていない。4度目の出雲崎なので、今回こそは焼いているところを見てみたかった。細長い出雲崎の海岸線の集落に沿って南北にバイパスが、しかも海側にできていた。出雲崎の集落と狭い道は相変わらずつげ義春が好きそうな影の多い家並みで、一安心したが、こんな道路、ほんとうに必要なんだろうか?いい道路を造ったら人が来る、そう思っているのは土建屋さんと行政、政治家だけだろう。古い町並みを少し歩いてみたが、町は完全に寝静まっていて、車さえ通らない。
「浜から山(里)へ」は水産流通の基本である。海でとれたものを塩をするか、焼くかして山に向かって売りに行くことでこの国の食料の循環が行われていたのである。例えば塩をするか、焼くかしたサバ(マサバ)を山に運び、米や米ぬかと交換することで浜は糖質を補給していた。山の人は動物たんぱくを得られた。この浜から山へ、山から浜へを考えていきたい。新潟の浜では古くから魚を早朝から炭火で焼き上げ、山間部に運んでいた。いったいどんな魚を焼いていたのか?新潟市本町での、炭火に串に刺された光景は絵になるので、多くの書籍に写真はあるが、その魚の種類までは載っていない。農文協の聞き書きシリーズにもない。1988年の『新潟料理 ふるさとの味』(桜井薫 新潟日報事業社)に〈イカ、サバ、カレイ、アナゴ、ギス〉とある。それぞれスルメイカ、マサバ、マガレイ、クロメクラウナギ、ニギスである。カレイは日本海側では青森県から富山県まではマガレイ、石川県、福井県がアカガレイだと思っている。みな地先の浜でたっぷりとれていたものばかりである。ちなみにマガレイを海辺の魚屋で焼いて売るというのは、新発田市や村上市にもある。山形県でも同じである。新潟市の浜焼きは、何度も買い求めている。その光景以上に魅力的なのが、その香りである。見ていると食べたくなのは、この香りのせいだ。とても丸々一尾は食べられないが、冷めてもおいしいところも魅力である。寺泊は今や観光地と化しているが、ここも浜焼きが有名である。もうひとつの浜焼きの町が出雲崎である。1980年代に二度も行って、二度とも買っているが、ただ単に買って食べただけで終わっている。2004年にも浜焼きを買っているものの、なぜか画像がない。残念なことに焼いている時間には一度も行き会わせていない。4度目の出雲崎なので、今回こそは焼いているところを見てみたかった。細長い出雲崎の海岸線の集落に沿って南北にバイパスが、しかも海側にできていた。出雲崎の集落と狭い道は相変わらずつげ義春が好きそうな影の多い家並みで、一安心したが、こんな道路、ほんとうに必要なんだろうか?いい道路を造ったら人が来る、そう思っているのは土建屋さんと行政、政治家だけだろう。古い町並みを少し歩いてみたが、町は完全に寝静まっていて、車さえ通らない。 新潟県上越市・妙高市で、「ほくしん」という言語を何度か聞いた。上越市・妙高市の南、北信のことで、長野県の地方名である。長野には何度も行っているのに、どこに行ってもバラバラで理解できない部分が残ってしまうのは、要するに10もの地方に分かれるからだ。海のない長野県は必ず海と繋がりを持つ。そのとき長野県の地方地方で海が違うのである。北信では上越市の海辺。松本平・安曇野では富山県の富山湾になる。南信州・上伊那などは太平洋こそが海辺だ。新潟県とか日本海側に行くと、南が寒くて北が暖かいので、よく話がこんがらがるが、北国街道を南下すると急激に雪深くなる。今回、上越市・妙高市・北信地方(信濃町・飯綱町・長野市)が線として繋がったことによって、長野県の地域を調べるための入り口が発見できた。これが、今回最大の収穫である。この視点で長野に行ってみたくなった。
新潟県上越市・妙高市で、「ほくしん」という言語を何度か聞いた。上越市・妙高市の南、北信のことで、長野県の地方名である。長野には何度も行っているのに、どこに行ってもバラバラで理解できない部分が残ってしまうのは、要するに10もの地方に分かれるからだ。海のない長野県は必ず海と繋がりを持つ。そのとき長野県の地方地方で海が違うのである。北信では上越市の海辺。松本平・安曇野では富山県の富山湾になる。南信州・上伊那などは太平洋こそが海辺だ。新潟県とか日本海側に行くと、南が寒くて北が暖かいので、よく話がこんがらがるが、北国街道を南下すると急激に雪深くなる。今回、上越市・妙高市・北信地方(信濃町・飯綱町・長野市)が線として繋がったことによって、長野県の地域を調べるための入り口が発見できた。これが、今回最大の収穫である。この視点で長野に行ってみたくなった。 新潟市万代島にある市場は、長い歴史があり、新潟の地方性がいちばん感じられる場所だ。新潟市は地物が豊富な上に、陸送もあるという恵まれたところでもある。食というと石川県とか「きときと」で有名な富山県など浮かべる人が多いと思うが、実は新潟県はこの2県と比べても見劣りがしない。量はともかく、むしろ信濃川流域の水産生物もあるので、3県の中でも抜きいんでいる気がする。うまいものを食べたかったら、新潟だ、と思って欲しい、今日この頃でもある。ちなみに暮れも押し詰まってこれだけの荷があること自体素晴らしい。順不同。スサビノリ(岩のり 新潟市)、ぎんばそう(アカモク 新潟市?)マトウダイ(宮城県)、アカムツ(宮城県)、キアンコウ(宮城県)、山伏(ババガレイ 佐渡)、アカガレイ(佐渡)、メダイ(佐渡)、ヒラメ(佐渡)、イシガレイ?(佐渡)、キジハタ(佐渡)、ソウハチ(新潟)、マサバ?(佐渡)、カツオ(佐渡)、マンボウ?(佐渡)、クロダイ(佐渡)、どろやなぎ(ヒレグロ)、クロソイ(佐渡)、ホッケ(佐渡)、ウッカリカサゴ(佐渡)、アオハタ(佐渡)ハタハタ(新潟)、ヒラマサ(佐渡)、めじまぐろ(クロマグロ 佐渡)、サワラ(佐渡)、めばる(ウスメバル)アカアマダイ(新潟)、キダイ(新潟)、チダイ(新潟)、カイワリ(新潟)、シログチ(新潟)、アカムツ(新潟)、アラ(新潟)、ハツメ(新潟)、チゴダラ(新潟)マトウダイ(宮城県)、キアンコウ(宮城県)、タチウオ(宮城県)、ババガレイ(宮城)、カガミダイ(宮城)、シロメバル(宮城)本ずわい(ズワイガニ 新潟県佐渡水津など)、ケガニ(新潟県佐渡水津など)、なんばんえび(ホッコクアカエビ 新潟 小底)、クロザコエビ(新潟 小底)、赤ひげ(アキアミ 新潟市)、モクズガニ(新潟)。黒ばい(バイ 新潟)、カガバイ(比較的浅場 佐渡)、チヂミエゾボラ(比較的浅場 佐渡)、クロアワビ(不明)、ほっき(ウバガイ 茨城)、アオリイカ(佐渡)、ケンサキイカ(新潟市)、ミズダコ(佐渡)市場魚貝類図鑑へhttps://www.zukan-bouz.com/#新潟県 #新潟市 #佐渡
新潟市万代島にある市場は、長い歴史があり、新潟の地方性がいちばん感じられる場所だ。新潟市は地物が豊富な上に、陸送もあるという恵まれたところでもある。食というと石川県とか「きときと」で有名な富山県など浮かべる人が多いと思うが、実は新潟県はこの2県と比べても見劣りがしない。量はともかく、むしろ信濃川流域の水産生物もあるので、3県の中でも抜きいんでいる気がする。うまいものを食べたかったら、新潟だ、と思って欲しい、今日この頃でもある。ちなみに暮れも押し詰まってこれだけの荷があること自体素晴らしい。順不同。スサビノリ(岩のり 新潟市)、ぎんばそう(アカモク 新潟市?)マトウダイ(宮城県)、アカムツ(宮城県)、キアンコウ(宮城県)、山伏(ババガレイ 佐渡)、アカガレイ(佐渡)、メダイ(佐渡)、ヒラメ(佐渡)、イシガレイ?(佐渡)、キジハタ(佐渡)、ソウハチ(新潟)、マサバ?(佐渡)、カツオ(佐渡)、マンボウ?(佐渡)、クロダイ(佐渡)、どろやなぎ(ヒレグロ)、クロソイ(佐渡)、ホッケ(佐渡)、ウッカリカサゴ(佐渡)、アオハタ(佐渡)ハタハタ(新潟)、ヒラマサ(佐渡)、めじまぐろ(クロマグロ 佐渡)、サワラ(佐渡)、めばる(ウスメバル)アカアマダイ(新潟)、キダイ(新潟)、チダイ(新潟)、カイワリ(新潟)、シログチ(新潟)、アカムツ(新潟)、アラ(新潟)、ハツメ(新潟)、チゴダラ(新潟)マトウダイ(宮城県)、キアンコウ(宮城県)、タチウオ(宮城県)、ババガレイ(宮城)、カガミダイ(宮城)、シロメバル(宮城)本ずわい(ズワイガニ 新潟県佐渡水津など)、ケガニ(新潟県佐渡水津など)、なんばんえび(ホッコクアカエビ 新潟 小底)、クロザコエビ(新潟 小底)、赤ひげ(アキアミ 新潟市)、モクズガニ(新潟)。黒ばい(バイ 新潟)、カガバイ(比較的浅場 佐渡)、チヂミエゾボラ(比較的浅場 佐渡)、クロアワビ(不明)、ほっき(ウバガイ 茨城)、アオリイカ(佐渡)、ケンサキイカ(新潟市)、ミズダコ(佐渡)市場魚貝類図鑑へhttps://www.zukan-bouz.com/#新潟県 #新潟市 #佐渡 待ってるぞ、と言われて行ったのに、病院に行くのでダメだと言われ、それじゃ明日と言われたので行ったら、今日も病院だと言われる。ご老体、あきらかに、あれなのね、とわかったときにはもう遅い。脳みそがふやけた状態で、長浜市木ノ本にたどり着く。ボクの場合、食べ歩きはしないので、いいと思ったらそこだけでいい。それにしてもこの木ノ本駅近くの食堂はいい。人に振り回されてへとへとになった身体が、瓶ビールと店の湯気でひゅっと楽になる。
待ってるぞ、と言われて行ったのに、病院に行くのでダメだと言われ、それじゃ明日と言われたので行ったら、今日も病院だと言われる。ご老体、あきらかに、あれなのね、とわかったときにはもう遅い。脳みそがふやけた状態で、長浜市木ノ本にたどり着く。ボクの場合、食べ歩きはしないので、いいと思ったらそこだけでいい。それにしてもこの木ノ本駅近くの食堂はいい。人に振り回されてへとへとになった身体が、瓶ビールと店の湯気でひゅっと楽になる。 今回の目的は人だったのに、その方が行方不明となる。まさか、とは思ったがどうしようもない。これがボクの旅の現実なのである。この日には北風がやむということで、琵琶湖南湖東岸、西岸の漁港を回る。空振りだった。できれば南湖の水揚げを見たかったので、残念である。南湖で底曳き網の漁師さんに話を聞けたのだけが収穫。夕方に湖北に行ったが、やはり今回の主役には会えず。1945年以前生まれの漁師さんが、どんどん姿を消していく。唯一の収穫は情報をいただける漁師さんが増えたことだけ。なんと湖北も漁はないという。
今回の目的は人だったのに、その方が行方不明となる。まさか、とは思ったがどうしようもない。これがボクの旅の現実なのである。この日には北風がやむということで、琵琶湖南湖東岸、西岸の漁港を回る。空振りだった。できれば南湖の水揚げを見たかったので、残念である。南湖で底曳き網の漁師さんに話を聞けたのだけが収穫。夕方に湖北に行ったが、やはり今回の主役には会えず。1945年以前生まれの漁師さんが、どんどん姿を消していく。唯一の収穫は情報をいただける漁師さんが増えたことだけ。なんと湖北も漁はないという。 この日は朝日が昇るのを見ながら琵琶湖湖畔で魚すくいをした。細かな泥っぽい砂地に足を取られてたいへんだった。魚すくいは夢中になりがちなので、空腹感も、疲れも、やっているときは感じない。気がついたらバカ長が脱げないくらい疲れていた。甘いものが欲しくなったので朝ご飯に柿一つ。ボクの旅はいつもどろんこで、這いつくばって、食い物もギリギリなのだ。滋賀県今津から福島県小浜についたら10時前だった。どこか食堂を探そうとして、腹の虫が大騒ぎしたので諦めた。くどいようだが、ボクの旅は愛のない、悲しみと諦めの旅でもある。小浜市にあった直売所、若狭ふれあい市場で、地元食材を大量買いし、ついでに弁当を買う。いちばんもりもりのやつを選ぶ。車の中を温かくして、飢えに耐えながら前日の足の傷をウエットティッシュでキレイにし、絆創膏を替える。最近、傷の治りが遅い。これは年のせいかしら、と思う。手も傷も足回りも清潔に、ある意味、明窓浄机して、といった感じで弁当を食らう。温かい烏龍茶で口の中を湿らせ、一気に食らう唐揚げ大盛り弁当がうまい。腹が減っているときの一口に涙がぽろりしそうになる。竜田揚げのしょうゆ味がおいしいし、かりっと揚がっているのもいい。おかずがどれもうまいし、ご飯がうまいのは福井米を使っているせいか。若狭ふれあい市場にまた来ることがあったら、また弁当を買うだろう。そして発見があった。兵庫県は定食・弁当にみかんがつく比率が高いと思っている。ひょっとしたら福井県もそうではないか?こんなことを考えてしまうから旅は疲れてしまう。
この日は朝日が昇るのを見ながら琵琶湖湖畔で魚すくいをした。細かな泥っぽい砂地に足を取られてたいへんだった。魚すくいは夢中になりがちなので、空腹感も、疲れも、やっているときは感じない。気がついたらバカ長が脱げないくらい疲れていた。甘いものが欲しくなったので朝ご飯に柿一つ。ボクの旅はいつもどろんこで、這いつくばって、食い物もギリギリなのだ。滋賀県今津から福島県小浜についたら10時前だった。どこか食堂を探そうとして、腹の虫が大騒ぎしたので諦めた。くどいようだが、ボクの旅は愛のない、悲しみと諦めの旅でもある。小浜市にあった直売所、若狭ふれあい市場で、地元食材を大量買いし、ついでに弁当を買う。いちばんもりもりのやつを選ぶ。車の中を温かくして、飢えに耐えながら前日の足の傷をウエットティッシュでキレイにし、絆創膏を替える。最近、傷の治りが遅い。これは年のせいかしら、と思う。手も傷も足回りも清潔に、ある意味、明窓浄机して、といった感じで弁当を食らう。温かい烏龍茶で口の中を湿らせ、一気に食らう唐揚げ大盛り弁当がうまい。腹が減っているときの一口に涙がぽろりしそうになる。竜田揚げのしょうゆ味がおいしいし、かりっと揚がっているのもいい。おかずがどれもうまいし、ご飯がうまいのは福井米を使っているせいか。若狭ふれあい市場にまた来ることがあったら、また弁当を買うだろう。そして発見があった。兵庫県は定食・弁当にみかんがつく比率が高いと思っている。ひょっとしたら福井県もそうではないか?こんなことを考えてしまうから旅は疲れてしまう。 朝一番、琵琶湖畔で魚すくいをする。滋賀県今津から熊川宿を越えて小浜に出て、気になるところを見ながらふたたび滋賀県に帰ってきた。かたっぱしからスーパーに寄って、直売所も巡り、人に話を聞いた。収穫がありすぎる往復で知識のゲップがでるほどだった。いつのまにか夕闇が迫ってきていた。桓武帝を考える上でも、ぜひ寄りたいと思っていた塩津浜港を断念。久しぶりに歩いてみたいと思っていた木ノ本、北国街道も真っ暗だった。この日の最終地点、木ノ本駅の駐車場で、途方に暮れていたら、地元の方に駐車料金は無料であることと、ご飯が食べられる店を教えて頂く。教えてくれた方、ありがとう。北風が冷たく、闇が重く感じるほど濃い中、駐車場から歩いて数分のところに灯りが見え、暖簾らしきものが揺れているのを発見した。引き戸を開けると子供が椅子席にちょこんと座っている。湿度の高い店内がいい感じで、厨房の端、奥の方で湯気がもくもくと上がって白い。そこに晩ご飯が運ばれてきて、店のオバアチャンが前に座って話こんでいる。ここの子供らしい。ボクは、店の子供が店内でご飯を食べているような、飾りっ気のない店が大大大好きで、この店は大当たりだと確信した。
朝一番、琵琶湖畔で魚すくいをする。滋賀県今津から熊川宿を越えて小浜に出て、気になるところを見ながらふたたび滋賀県に帰ってきた。かたっぱしからスーパーに寄って、直売所も巡り、人に話を聞いた。収穫がありすぎる往復で知識のゲップがでるほどだった。いつのまにか夕闇が迫ってきていた。桓武帝を考える上でも、ぜひ寄りたいと思っていた塩津浜港を断念。久しぶりに歩いてみたいと思っていた木ノ本、北国街道も真っ暗だった。この日の最終地点、木ノ本駅の駐車場で、途方に暮れていたら、地元の方に駐車料金は無料であることと、ご飯が食べられる店を教えて頂く。教えてくれた方、ありがとう。北風が冷たく、闇が重く感じるほど濃い中、駐車場から歩いて数分のところに灯りが見え、暖簾らしきものが揺れているのを発見した。引き戸を開けると子供が椅子席にちょこんと座っている。湿度の高い店内がいい感じで、厨房の端、奥の方で湯気がもくもくと上がって白い。そこに晩ご飯が運ばれてきて、店のオバアチャンが前に座って話こんでいる。ここの子供らしい。ボクは、店の子供が店内でご飯を食べているような、飾りっ気のない店が大大大好きで、この店は大当たりだと確信した。 「ざっこの貝焼き」は「ざっこ」のみそ汁である。「貝焼き(かやき)」は東北や新潟県の言葉で、もともとはホタテガイの貝殻を鍋にして作る、醤油・みそ仕立ての料理のことだ。ヤツメウナギやホタテガイ、みそ仕立ての卵料理などがある。ここ秋田県旧館合村(現横手市雄物川町)でも、また古くは貝殻を鍋にして作っていたことから「貝焼き」なのだ、と思われる。
「ざっこの貝焼き」は「ざっこ」のみそ汁である。「貝焼き(かやき)」は東北や新潟県の言葉で、もともとはホタテガイの貝殻を鍋にして作る、醤油・みそ仕立ての料理のことだ。ヤツメウナギやホタテガイ、みそ仕立ての卵料理などがある。ここ秋田県旧館合村(現横手市雄物川町)でも、また古くは貝殻を鍋にして作っていたことから「貝焼き」なのだ、と思われる。 秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんが作ってくれた「ざっこ蒸」は「ためっこ漁」でとれた「ざっこ」の大方を使って作る。「ざっこ蒸」は「塩蒸しざっこ」ともいう。柔らかくほどよい塩味で、内臓に苦味がある。けっして食べやすいものではないが、残して置きたい雄物川の冬の味覚である。
秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんが作ってくれた「ざっこ蒸」は「ためっこ漁」でとれた「ざっこ」の大方を使って作る。「ざっこ蒸」は「塩蒸しざっこ」ともいう。柔らかくほどよい塩味で、内臓に苦味がある。けっして食べやすいものではないが、残して置きたい雄物川の冬の味覚である。 2017年1月21日、秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんの家に到着すると同時に川に向かう。佐藤政彦さんは1945年、旧館合村(雄物川の右岸、現薄井・大雄)で生まれる。農業を営みながら、春はウグイ漁、夏から秋にかけてはアユ漁、冬には「ためっこ漁」を行っている。雄物川方面を見ると一面の銀世界で冷たさに顔が凍る。除雪されている地域は人があるけるが、少し離れるととても歩いていけない、そんな雪深さだ。それでも佐藤さんたちは「暖かい日だな」などと笑っている。雄物川は直線距離にしたら目と鼻の先だが、川原まではとても歩いては行けない。大型トラックターに乗って向かう。「ためっこ漁」は佐藤さんを含めて3人で行う。秋田県山間部の厳冬期の漁で一人ではとてもできない集団で行うものだ。「ためっこ」は数カ所あるが、1日に1カ所ずつ上げていく。古くは雄物川の各所に、農家の人達の無数の「ためっこ」があったはずである。狙うのは「ざっこ」である。「ざっこ」とは「雑魚」のことで、主にコイ科の小魚のことで、特にウグイを指すのだと考えている。雄物川ではサケやコイに対しての言葉だと思う。貴重なたんぱく源である「ざっこ」をとる「ためっこ漁」はとても原始的なもので、歴史は非常に古いものと考えられる。コイ科の小魚は、石のくぼみや、水際の木が沈み込む周辺などにもぐり込む習性がある。これを利用したのが全国で行われているのが「柴漬け漁」である。「柴漬け漁」は木の枝などを束ねて沈めておき、魚がもぐり込みやすい環境を作る。これをゆっくり上げて、下にたも網などで受けて取る。この「柴漬け漁」を大がかりにし、固定化したものが「ためっこ漁」である。取り分け秋田などの北国では、冬季になると「ざっこ」は川の冷たさを避けて岸のよどみなどに集まる。そこに木の枝などを束ねたものがあると格好のねぐらだと思うのだろう。
2017年1月21日、秋田県横手市雄物川町、佐藤政彦さんの家に到着すると同時に川に向かう。佐藤政彦さんは1945年、旧館合村(雄物川の右岸、現薄井・大雄)で生まれる。農業を営みながら、春はウグイ漁、夏から秋にかけてはアユ漁、冬には「ためっこ漁」を行っている。雄物川方面を見ると一面の銀世界で冷たさに顔が凍る。除雪されている地域は人があるけるが、少し離れるととても歩いていけない、そんな雪深さだ。それでも佐藤さんたちは「暖かい日だな」などと笑っている。雄物川は直線距離にしたら目と鼻の先だが、川原まではとても歩いては行けない。大型トラックターに乗って向かう。「ためっこ漁」は佐藤さんを含めて3人で行う。秋田県山間部の厳冬期の漁で一人ではとてもできない集団で行うものだ。「ためっこ」は数カ所あるが、1日に1カ所ずつ上げていく。古くは雄物川の各所に、農家の人達の無数の「ためっこ」があったはずである。狙うのは「ざっこ」である。「ざっこ」とは「雑魚」のことで、主にコイ科の小魚のことで、特にウグイを指すのだと考えている。雄物川ではサケやコイに対しての言葉だと思う。貴重なたんぱく源である「ざっこ」をとる「ためっこ漁」はとても原始的なもので、歴史は非常に古いものと考えられる。コイ科の小魚は、石のくぼみや、水際の木が沈み込む周辺などにもぐり込む習性がある。これを利用したのが全国で行われているのが「柴漬け漁」である。「柴漬け漁」は木の枝などを束ねて沈めておき、魚がもぐり込みやすい環境を作る。これをゆっくり上げて、下にたも網などで受けて取る。この「柴漬け漁」を大がかりにし、固定化したものが「ためっこ漁」である。取り分け秋田などの北国では、冬季になると「ざっこ」は川の冷たさを避けて岸のよどみなどに集まる。そこに木の枝などを束ねたものがあると格好のねぐらだと思うのだろう。 滋賀県長浜市の直売所で買ったものだ。琵琶湖は今、ビワマスの時季ではない。養殖ものではなく、冷凍保存して置いたものとみた。ビワマスの刺身は滋賀県内の直売所でしばしば並んでいる。ビワマスの刺身は、例えばサクラマスに近い魚なので、味がとても似ているが、少しあっさりとして軽い味である。別に味気ないということではなく、上品な味と言った方が正しいだろう。琵琶湖周辺の人が「あめのいお」を愛してやまないわけがここに感じられる。琵琶湖に旅して当日にでも帰宅できるならお土産にもなるだろう。一度、淡水域だけど暮らしたサケ科の味も楽しんでもらいたい。
滋賀県長浜市の直売所で買ったものだ。琵琶湖は今、ビワマスの時季ではない。養殖ものではなく、冷凍保存して置いたものとみた。ビワマスの刺身は滋賀県内の直売所でしばしば並んでいる。ビワマスの刺身は、例えばサクラマスに近い魚なので、味がとても似ているが、少しあっさりとして軽い味である。別に味気ないということではなく、上品な味と言った方が正しいだろう。琵琶湖周辺の人が「あめのいお」を愛してやまないわけがここに感じられる。琵琶湖に旅して当日にでも帰宅できるならお土産にもなるだろう。一度、淡水域だけど暮らしたサケ科の味も楽しんでもらいたい。 日本海のサバの交易を調べに、前回、若狭高浜から名田庄を経て和知、丹波に出る経路の旅をしている。今回は、滋賀県高島市今津と福井県小浜市を往復した。少しずつでもいいので、京都周辺(滋賀県・京都府・兵庫県)のサバ(マサバ)の食文化を調べていきたいと思っている。滋賀県の湖北地方・余呉・朽木などのサバは主に日本海から来ていた。滋賀県南部米原以南湖東にサバをもたらしたのは主に三重県太平洋側だ。サバの来た道、経路だが、当たり前だけれどもっと、もっと多種多様な水産物の来た道でもある。滋賀県は京都市内への中継地点なので、京都で消費されるサバも、主に日本海と三重県太平洋側から来ていたことになる。「さばのなれずし」、「塩さば(塩蔵品)」は今でも滋賀県全域で手に入る。「さばのへしこ(糠漬け)」、「焼きさば」は滋賀県北部が主な消費地であるし、生産地でもある。この4つの加工品総てが揃うのは滋賀県北部だ。こんなことからも滋賀県の食文化は、サバ抜きには考えられないことがわかる。昔、京・滋賀に対しての日本海でのサバの代表的な供給地は若狭地方だった。1950年代くらいまで日本海のサバは豊漁で、佐渡島、能登半島、若狭湾、隠岐が4大漁場であった。三方(現福井県若狭町)、小浜(同小浜市)の高浜(同高浜町)に水揚げされた若狭湾のサバが滋賀県を経由して京に送られていた。産地からは馬などを使った比較的規模の大きい交易もあっただろうが、食文化を考えるとき重要なのは量的には少ないものの歩行(丹波などでは自転車、汽車に乗って)による交易である。マスコミでも、ときに単行本でも「鯖街道」が登場するが、みな内容が薄いというか、誤情報ばかりで困る。さばの来た道は毛細血管のように張り巡らされていたのだ。貨幣での取引もあったが、1945年(敗戦)以後も物々交換が行われていたことはとても重要だ。
日本海のサバの交易を調べに、前回、若狭高浜から名田庄を経て和知、丹波に出る経路の旅をしている。今回は、滋賀県高島市今津と福井県小浜市を往復した。少しずつでもいいので、京都周辺(滋賀県・京都府・兵庫県)のサバ(マサバ)の食文化を調べていきたいと思っている。滋賀県の湖北地方・余呉・朽木などのサバは主に日本海から来ていた。滋賀県南部米原以南湖東にサバをもたらしたのは主に三重県太平洋側だ。サバの来た道、経路だが、当たり前だけれどもっと、もっと多種多様な水産物の来た道でもある。滋賀県は京都市内への中継地点なので、京都で消費されるサバも、主に日本海と三重県太平洋側から来ていたことになる。「さばのなれずし」、「塩さば(塩蔵品)」は今でも滋賀県全域で手に入る。「さばのへしこ(糠漬け)」、「焼きさば」は滋賀県北部が主な消費地であるし、生産地でもある。この4つの加工品総てが揃うのは滋賀県北部だ。こんなことからも滋賀県の食文化は、サバ抜きには考えられないことがわかる。昔、京・滋賀に対しての日本海でのサバの代表的な供給地は若狭地方だった。1950年代くらいまで日本海のサバは豊漁で、佐渡島、能登半島、若狭湾、隠岐が4大漁場であった。三方(現福井県若狭町)、小浜(同小浜市)の高浜(同高浜町)に水揚げされた若狭湾のサバが滋賀県を経由して京に送られていた。産地からは馬などを使った比較的規模の大きい交易もあっただろうが、食文化を考えるとき重要なのは量的には少ないものの歩行(丹波などでは自転車、汽車に乗って)による交易である。マスコミでも、ときに単行本でも「鯖街道」が登場するが、みな内容が薄いというか、誤情報ばかりで困る。さばの来た道は毛細血管のように張り巡らされていたのだ。貨幣での取引もあったが、1945年(敗戦)以後も物々交換が行われていたことはとても重要だ。 最終日は湖北の水路で生き物を追いかける。結局、滋賀県では3回しか魚すくいが出来なかった。過密スケジュールのためだが、もっと多様な水辺で多様な生物と巡り会いたかった。魚/スナヤツメ、オウミヨシノボリ、ウキゴリ、ドジョウ甲殻類/スジエビ貝類/タテボシガイ、マツカサガイ、マルドブガイ、マシジミ
最終日は湖北の水路で生き物を追いかける。結局、滋賀県では3回しか魚すくいが出来なかった。過密スケジュールのためだが、もっと多様な水辺で多様な生物と巡り会いたかった。魚/スナヤツメ、オウミヨシノボリ、ウキゴリ、ドジョウ甲殻類/スジエビ貝類/タテボシガイ、マツカサガイ、マルドブガイ、マシジミ さんざん場所探しをして、滋賀県高島市湖岸の駐車場に車をとめる。夜が明けるのを待って湖岸に向かう。まだ完全に乾ききらないウェーダーが履きにくいし、どことなく臭うのが気になるものの、雨が上がって実に気持ちがいい。それにつけても早朝の湖岸の美しさよ。1時間と少し、ドロっぽい水路の流れ込みをせっせと生き物を探す。獲物の大方がヨシノボリ属とウキゴリ。南湖ではスジエビばかりだったのに、ここにはテナガエビが同じくらいとれた。あまりにもワンワンを連れた人が多くなってきたのでやめてしまったが、もっと長くやっていたかった、ぜ。魚/オウミヨシノボリ(?)、ヌマチチブ、ギンブナ(?)、ウキゴリ、ドジョウ甲殻類/スジエビ、テナガエビ
さんざん場所探しをして、滋賀県高島市湖岸の駐車場に車をとめる。夜が明けるのを待って湖岸に向かう。まだ完全に乾ききらないウェーダーが履きにくいし、どことなく臭うのが気になるものの、雨が上がって実に気持ちがいい。それにつけても早朝の湖岸の美しさよ。1時間と少し、ドロっぽい水路の流れ込みをせっせと生き物を探す。獲物の大方がヨシノボリ属とウキゴリ。南湖ではスジエビばかりだったのに、ここにはテナガエビが同じくらいとれた。あまりにもワンワンを連れた人が多くなってきたのでやめてしまったが、もっと長くやっていたかった、ぜ。魚/オウミヨシノボリ(?)、ヌマチチブ、ギンブナ(?)、ウキゴリ、ドジョウ甲殻類/スジエビ、テナガエビ さて、滋賀の旅は午前0時に我が家を出る。夜明けとともに野洲川で魚すくいをする。野洲川でおぼれ死にそうになったが、獲物の撮影まではこなす。そのとき琵琶湖では北風が吹いていて、湖東の漁港は漁がなかった。ポテチン、だ。この日の不幸1 おぼれそうになったことこの日の不幸2 琵琶湖が荒れて漁がなかったこと朝から水しか飲んでいないので、『JAおうみんち』で柿を買って、飢えをしのぎながら、湖西に渡る。渡る度に思う事だけど、琵琶湖大橋の通行料金80円はいらぬと思う。一般道にした方がいいんじゃないかな?堅田の魚屋をみて、北上しようとして、北上できなかった。この日の不幸3 予定が大狂いしたこと。人は難しいなと思って時計を見たら、2時だった。普段、チェーン店には入らない、食わないことにしているが、飢餓につき、堅田でゴージャスに大トンカツを食べる。こんなときデブなんだからお握り一個で我慢しよう、という気持ちにどうしてならないんだろう。ただ、チェーン店なのにこの大トンカツがやたらにうまかった。さくっと香ばしいだけではなく、ロース肉に汁気があり柔らかい。豚肉らしい風味が好ましいぞ!まわりの漬けもの、サラダもおいしいし、豚汁もいい。ご飯のお代わりなしがデブ唯一の矜持なのだ。
さて、滋賀の旅は午前0時に我が家を出る。夜明けとともに野洲川で魚すくいをする。野洲川でおぼれ死にそうになったが、獲物の撮影まではこなす。そのとき琵琶湖では北風が吹いていて、湖東の漁港は漁がなかった。ポテチン、だ。この日の不幸1 おぼれそうになったことこの日の不幸2 琵琶湖が荒れて漁がなかったこと朝から水しか飲んでいないので、『JAおうみんち』で柿を買って、飢えをしのぎながら、湖西に渡る。渡る度に思う事だけど、琵琶湖大橋の通行料金80円はいらぬと思う。一般道にした方がいいんじゃないかな?堅田の魚屋をみて、北上しようとして、北上できなかった。この日の不幸3 予定が大狂いしたこと。人は難しいなと思って時計を見たら、2時だった。普段、チェーン店には入らない、食わないことにしているが、飢餓につき、堅田でゴージャスに大トンカツを食べる。こんなときデブなんだからお握り一個で我慢しよう、という気持ちにどうしてならないんだろう。ただ、チェーン店なのにこの大トンカツがやたらにうまかった。さくっと香ばしいだけではなく、ロース肉に汁気があり柔らかい。豚肉らしい風味が好ましいぞ!まわりの漬けもの、サラダもおいしいし、豚汁もいい。ご飯のお代わりなしがデブ唯一の矜持なのだ。 元号は使いたくないが、便利なので。今回の旅は、なんどか漁獲物を見せてくれた漁師さんに会いに行くのも目的だった。昭和10年前後に生まれた世代は貴重である。会ってくれると言われてわざわざ行ったけど会えなかった。水産生物を調べているとこんなことは日常茶飯事、当たり前なので驚かない。そろそろ戦前生まれで話の聞ける方々も少なくなり、また明朗に答えてくれる人はもっと少なくなり、だ。気がついたら午後7時になっていたので、平和堂に走り込んで、萩の露とコイの子つけ、お握りを買って、駐車場を探す。そこでたき火(もちろん台の上で)をする。集めて置いた割り箸と紙だけなので、ちょろちょろたき火である。不思議なことにたき火をすると心が落ち着く。
元号は使いたくないが、便利なので。今回の旅は、なんどか漁獲物を見せてくれた漁師さんに会いに行くのも目的だった。昭和10年前後に生まれた世代は貴重である。会ってくれると言われてわざわざ行ったけど会えなかった。水産生物を調べているとこんなことは日常茶飯事、当たり前なので驚かない。そろそろ戦前生まれで話の聞ける方々も少なくなり、また明朗に答えてくれる人はもっと少なくなり、だ。気がついたら午後7時になっていたので、平和堂に走り込んで、萩の露とコイの子つけ、お握りを買って、駐車場を探す。そこでたき火(もちろん台の上で)をする。集めて置いた割り箸と紙だけなので、ちょろちょろたき火である。不思議なことにたき火をすると心が落ち着く。 この国の人間は淡水魚を口にしなくなって、淡水域の破壊を食い止めるための手段として自然保護だけで語るしかなくなっている。淡水魚を食料と考えていないせいだ。淡水魚も食料であり、自給率などを考えたとき、淡水生物も海水魚・海水生物同様重要なのだ、ということがわかっていない。温暖化の今、淡水生物を食べることで、ぐっと淡水域が近くなり、淡水域を破壊することがいかに、危険かが如実にわかるだろう。ちなみに雑食性のコイなどコイ亜目の養殖の方が、肉食性の海水魚の養殖よりも自然に優しい、ということもつけ加えておきたい。さて、最近、コイという淡水魚の中でも、もっとも身近な食用魚すら食べたことのある人は希だろう。コイはくせのない上品な白身で、味がある。これくらい万人向きな魚は、海水魚にもそんなに多くはない。なのにコイを食べない人だらけなのは、淡水魚の味を語るときに「泥臭い」という言語を使うバカモノが多すぎるからだ。滋賀の旅に出ると必ず立ち寄る、『川魚の西友 辻川店』で見つけたのが、コイの白子の煮つけである。念のために。東日本淡水魚の料理法と、滋賀県や京都市内の淡水魚の料理法・味つけはまったく別物である。ボク自身が四国生まれで、西の味に親しんできたせいで、滋賀県の淡水魚の味つけは口に合う。しかも『西友』の煮つけの味は、とりわけさらりとしてあっさりしている。淡水魚そのものの味が生きている。今回、コイの白子の煮つけは、惣菜としては初めて食べた。雄のコイを手に入れたこともあるので、白子のおいしさは知っていたが、こんなにおいしいとは思わなかった。ついでだから蛇足をば。例えばコイやフナの煮つけを手に入れたとする。もしも愛する人と食べるなら、ボクは身(筋肉)を食べて、愛する人には内臓や生殖巣(真子・白子)を食べさせる。このコイ亜目の魚は断然内臓がおいしくて、身が主役ではないからだ。
この国の人間は淡水魚を口にしなくなって、淡水域の破壊を食い止めるための手段として自然保護だけで語るしかなくなっている。淡水魚を食料と考えていないせいだ。淡水魚も食料であり、自給率などを考えたとき、淡水生物も海水魚・海水生物同様重要なのだ、ということがわかっていない。温暖化の今、淡水生物を食べることで、ぐっと淡水域が近くなり、淡水域を破壊することがいかに、危険かが如実にわかるだろう。ちなみに雑食性のコイなどコイ亜目の養殖の方が、肉食性の海水魚の養殖よりも自然に優しい、ということもつけ加えておきたい。さて、最近、コイという淡水魚の中でも、もっとも身近な食用魚すら食べたことのある人は希だろう。コイはくせのない上品な白身で、味がある。これくらい万人向きな魚は、海水魚にもそんなに多くはない。なのにコイを食べない人だらけなのは、淡水魚の味を語るときに「泥臭い」という言語を使うバカモノが多すぎるからだ。滋賀の旅に出ると必ず立ち寄る、『川魚の西友 辻川店』で見つけたのが、コイの白子の煮つけである。念のために。東日本淡水魚の料理法と、滋賀県や京都市内の淡水魚の料理法・味つけはまったく別物である。ボク自身が四国生まれで、西の味に親しんできたせいで、滋賀県の淡水魚の味つけは口に合う。しかも『西友』の煮つけの味は、とりわけさらりとしてあっさりしている。淡水魚そのものの味が生きている。今回、コイの白子の煮つけは、惣菜としては初めて食べた。雄のコイを手に入れたこともあるので、白子のおいしさは知っていたが、こんなにおいしいとは思わなかった。ついでだから蛇足をば。例えばコイやフナの煮つけを手に入れたとする。もしも愛する人と食べるなら、ボクは身(筋肉)を食べて、愛する人には内臓や生殖巣(真子・白子)を食べさせる。このコイ亜目の魚は断然内臓がおいしくて、身が主役ではないからだ。 滋賀県守山市、野洲川河口域で溺れかけて、びしょ濡れになる。それでもやらなければならないのが撮影である。撮影後、ただちにお帰り願わなければならぬ。バスタオルを持って来ていなかったのが大失敗。下着まで新しいのに着替えて、車の中で体を気持ち乾かす。上着を濡らしたので、寒い中、上着なしで撮影する。さっきまで気にならなかった川風が痛い。さて、今回もっとも苦しめてくれたのが、なんども撮影しているヌマチチブである。オウミヨシノボリが素直にポーズを決めてくれたのとは大違い。水槽を揺らしても反転してもあっちを向いて振り向かない。真横にならない。その感にも体が冷え冷えになる。人と会う約束の時間が迫る。淡水の旅はきびしいくて、悲しい。
滋賀県守山市、野洲川河口域で溺れかけて、びしょ濡れになる。それでもやらなければならないのが撮影である。撮影後、ただちにお帰り願わなければならぬ。バスタオルを持って来ていなかったのが大失敗。下着まで新しいのに着替えて、車の中で体を気持ち乾かす。上着を濡らしたので、寒い中、上着なしで撮影する。さっきまで気にならなかった川風が痛い。さて、今回もっとも苦しめてくれたのが、なんども撮影しているヌマチチブである。オウミヨシノボリが素直にポーズを決めてくれたのとは大違い。水槽を揺らしても反転してもあっちを向いて振り向かない。真横にならない。その感にも体が冷え冷えになる。人と会う約束の時間が迫る。淡水の旅はきびしいくて、悲しい。 滋賀県守山市、野洲川河口域ですくった生物のほとんどがオウミヨシノボリであった。急激に気温が下がったためにコイ目の小魚類などは深みに落ちたのではないかと思われる。魚/オウミヨシノボリ、ヌマチチブ甲殻類/ミナミヌマエビ、スジエビ、エビノコバン
滋賀県守山市、野洲川河口域ですくった生物のほとんどがオウミヨシノボリであった。急激に気温が下がったためにコイ目の小魚類などは深みに落ちたのではないかと思われる。魚/オウミヨシノボリ、ヌマチチブ甲殻類/ミナミヌマエビ、スジエビ、エビノコバン 琵琶湖周辺を移動していると、まず北と南での違いに気づくはずである。湖西は山が琵琶湖に迫り、比叡山、比良山地からの颪にさらされている。農地が少なく、物成での南北の違いは、現在のところボクにはよくわからないが、南北に限らず寒い。湖東は草津、守山から、彦根を越えるといきなり北国になる。こんな顕著な違いは京都盆地にも見られる。当たり前だけど車は北に行くほど、4WDが増える。昔、余呉で雪から出られなくなって事がある。長浜から北に来るなら普通車では無理と言われたものである。農産物でいえば南部である草津市、守山市では柿が出盛っていて、まだまだ先が長いと感じたが、長浜市では「そろそろ柿もしまいですね」なんて言われる。白菜の品種にも違いがあるのではないか? 道路脇から見ただけではあるが、旧湖北町では早生の耐病性ではなく晩成が結球しつつある。南の草津や守山の方が野菜が豊富で、北に行くほど多彩さがなくなっていた、のは2013年11月の滋賀の旅で感じたことだ。それが今年はそれほど顕著ではない。余談になるが長浜市湖北町の直売所にはまだスイカがあった。温室だとは思うけど、本当に地元のものだろうか?この季節の差と、流通の地域性が今回の旅の目的でもある。
琵琶湖周辺を移動していると、まず北と南での違いに気づくはずである。湖西は山が琵琶湖に迫り、比叡山、比良山地からの颪にさらされている。農地が少なく、物成での南北の違いは、現在のところボクにはよくわからないが、南北に限らず寒い。湖東は草津、守山から、彦根を越えるといきなり北国になる。こんな顕著な違いは京都盆地にも見られる。当たり前だけど車は北に行くほど、4WDが増える。昔、余呉で雪から出られなくなって事がある。長浜から北に来るなら普通車では無理と言われたものである。農産物でいえば南部である草津市、守山市では柿が出盛っていて、まだまだ先が長いと感じたが、長浜市では「そろそろ柿もしまいですね」なんて言われる。白菜の品種にも違いがあるのではないか? 道路脇から見ただけではあるが、旧湖北町では早生の耐病性ではなく晩成が結球しつつある。南の草津や守山の方が野菜が豊富で、北に行くほど多彩さがなくなっていた、のは2013年11月の滋賀の旅で感じたことだ。それが今年はそれほど顕著ではない。余談になるが長浜市湖北町の直売所にはまだスイカがあった。温室だとは思うけど、本当に地元のものだろうか?この季節の差と、流通の地域性が今回の旅の目的でもある。該当するコラムが多い為ページを分割して表示します。
全111コラム中 1番目~100番目までを表示中
- 1
- 2









