大阪の郷土料理、さばの船場汁と船場煮
船場汁から見えてくるもの

適塾

船場とは大阪市中区の北は土佐堀川、南は長堀通、西は御堂筋、東は東横堀川までの広い地域のことだ。典型的な大阪といった場所で丼池の繊維街、薬を扱う道修町、証券会社の集まる北浜などがある。今でも上品な大阪言葉が残っていたりする場所で、今どきの大阪弁であるごっつい泥臭さとは無縁の地なのだ。
この船場と言われるところを歩いてみたが往時の商人町の面影はほとんど残っていない。あえていえば北浜の適塾(幕末にあった緒方洪庵の医術塾)や古い薬問屋、丼池の繊維街の喧噪くらいかも知れない。
大阪中心部のこのあたりは大商人の町なので、丁稚どんに番頭どん、などたくさんの働き手が暮らしていた。多くは共同生活、集団での食事である。
大正時代、船場平野町の薬問屋、安田市兵衛商店で丁稚だった日本演劇界の巨人、菊田一夫は、食事も完全なる階級制であり、大番頭は畳敷きの場所で座って食事を摂り、中番頭以下は土間に沿った板の間で食べたという。菊田一夫は身長が低く、食べるのが遅かった。ゆっくり食べていると十分に食べられない。そこで編み出したのが汁と飯を熱々の状態でかき込むということだ。汁がおかずでもあった証拠といえるだろう。大阪の商人町の食事は極端に動物性たんぱくが少なかったようだ。
そんな中でも登場回数の多かったのが塩サバだった。関西のマサバの供給地は日本海の北陸・山陰で、太平洋側では紀伊水道、熊野灘だった。これが大阪の地に送られて来ていたのだ。
当時のマサバの流通は鮮魚もあっただろうが、ほとんどが塩蔵品、もしくは干ものだったと思われる。しかも今では考えられない程の塩分濃度の濃いもの。この体幹部分は焼き、あらの部分を大根とたいて作ったのが「船場汁」、「船場煮」だ。
汁といっても大根を煮て、塩蔵サバのあらを入れるだけ。塩味は塩蔵サバから出るし、あら自体も塩辛い。厳しい商家の生活にはなくてはならなかったものだろう。
寒い時季に食べるもので、ときには生(鮮魚)を使って作られることもあるという。
また重要なのは「船場汁」というのは大阪市の言葉だということ。他の地域でも同じような料理が作られている可能性が高い。地元の料理は地元の言葉で作り、食べて欲しい。
参考/『聞き書 大阪の食事』(農文協)、『船場道修町』(三島佑一 人文書院 1990)、『評伝 菊田一夫』(小幡欣治 岩波書店 2008)
船場汁から見えてくるもの

焼津産塩蔵サバ

大正時代、昭和になっても1960年代くらいまでマサバの流通は鮮魚よりも塩乾の方が多かったのでは・イカ? サバの生き腐れという言葉があるが、大量に網でとったマサバを貨車で送っていた時代は塩分濃度の強い塩サバ(塩蔵サバ)であって初めて流通できたのだろう。
写真は昔の人が値段を聞いたらビックリしそうな上物の塩蔵サバ。このレベルのサバを探すのは非常に難しい時代になっている。
船場汁は汁でもありおかずでもある

船場汁

本来は塩サバ(塩蔵さば)をおかずとして焼き、頭部や中骨などのあらをとっておいて、大根と煮て汁にしたものだ。これが一般家庭や後の時代になると鮮魚で作るようになったのだと考えている。
鮮魚出てくる場合は、丸のままぶつ切りにして使ってもいいが、大振りのマサバなどを買ったときなどは頭部、中骨や尾の部分を使って作るといい。あらは食べやすい大きさに切り、振り塩をして寝かせておく。これを湯通しして、もしくは湯をかけて、氷水に落として表面のぬめりや血液などを流して臭みを取る。
水分をよくきり、水から煮出して味見。味加減をする。
昆布だしを使ってもいいし、酒を加えてもいい。
実にうま味豊かな汁であるが、あっさりしているのでついついお代わりしてしまうはずだ。
ゴマサバを使ってもタイセイヨウサバを使ってもおいしい。
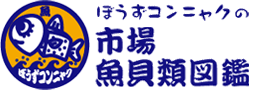









 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典






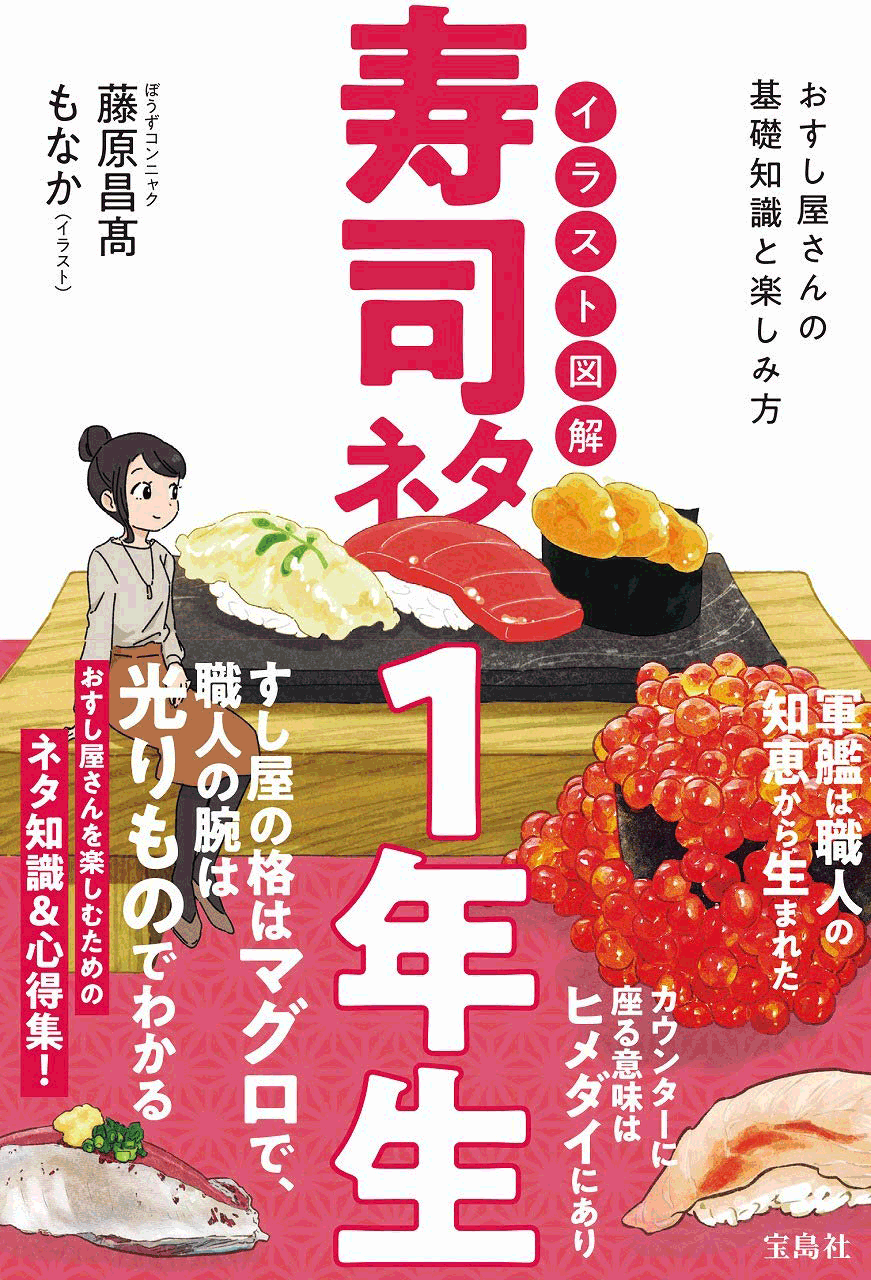 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



