コラム検索
検索条件
 いちょう切りのイタリアナスはソテーすると柔らかくとろっとするが、決して形くずれはしない。この上に一緒にソテーしたホッキガイ(ウバガイ)の水管・貝柱などをのせて食べると、とてもうま味の量が多く、複雑でゴージャスである。ごちそうといっても過言ではない。とても単純な料理で材料も最小限なのに、一切れでこんなに満足度が高いなんてことにも不思議さを感じる。貝のうま味を程よく吸ったナスとホッキが融合している。バタールで皿に残ったうま味豊かなオリーブオイルを拭き取りながら、飲む1パイの白ワインもいいものである。今回の失敗はオリーブオイルをけちったことだろう。オリーブオイルはTanto、たんとがいい。
いちょう切りのイタリアナスはソテーすると柔らかくとろっとするが、決して形くずれはしない。この上に一緒にソテーしたホッキガイ(ウバガイ)の水管・貝柱などをのせて食べると、とてもうま味の量が多く、複雑でゴージャスである。ごちそうといっても過言ではない。とても単純な料理で材料も最小限なのに、一切れでこんなに満足度が高いなんてことにも不思議さを感じる。貝のうま味を程よく吸ったナスとホッキが融合している。バタールで皿に残ったうま味豊かなオリーブオイルを拭き取りながら、飲む1パイの白ワインもいいものである。今回の失敗はオリーブオイルをけちったことだろう。オリーブオイルはTanto、たんとがいい。 前にも書いているが、北海道に来てから食べた飯は、弁当も含めてみな美味であった。特にコンビニ弁当がよかったのである。立ち話をした北海道バイク旅の若い衆が、朝一番に買える店を教えてくれた。『タイエー』というコンビニである。この若い衆、とても気さくで、ついでに店の位置まで車のナビに打ち込んでくれる。この手の作業がいちばん嫌いなので、ありがとうの三乗、といって感謝して別れた。今日中に羅臼、羅臼岳を超えて知床だという。若いって素晴らしい。たどり着いた『タイエー』はとても小さな店だったが、品揃えがとてもよかった。若い衆おすすめの「やきとり弁当」を注文すると、店内で焼き上げ、焼き上げたばかりをご飯の上に乗せてくれた。根室漁協の魚の搬入が見せる場所で取り出したら、なんと豚オヤジのイラストがかかれている。
前にも書いているが、北海道に来てから食べた飯は、弁当も含めてみな美味であった。特にコンビニ弁当がよかったのである。立ち話をした北海道バイク旅の若い衆が、朝一番に買える店を教えてくれた。『タイエー』というコンビニである。この若い衆、とても気さくで、ついでに店の位置まで車のナビに打ち込んでくれる。この手の作業がいちばん嫌いなので、ありがとうの三乗、といって感謝して別れた。今日中に羅臼、羅臼岳を超えて知床だという。若いって素晴らしい。たどり着いた『タイエー』はとても小さな店だったが、品揃えがとてもよかった。若い衆おすすめの「やきとり弁当」を注文すると、店内で焼き上げ、焼き上げたばかりをご飯の上に乗せてくれた。根室漁協の魚の搬入が見せる場所で取り出したら、なんと豚オヤジのイラストがかかれている。 小田原から帰った夜のコノシロの刺身(背ごし)はいいものなのだ。今回、冷やした刺身の頂点にはうす(幽門)を乗せてみた。幽門はボラでおいしさが知られているが、コノシロのも小さいが味は変わらない。独特の食感があり、少しだけ甘味がある。もちろん刺身は抜群にうまい。コノシロはマイワシと同じニシン科で青魚のうま味がとても豊かだからだ。とれたその日なので、まだしこしことした食感が感じられる。少しだけ血合い骨が当たるがこれもいい。
小田原から帰った夜のコノシロの刺身(背ごし)はいいものなのだ。今回、冷やした刺身の頂点にはうす(幽門)を乗せてみた。幽門はボラでおいしさが知られているが、コノシロのも小さいが味は変わらない。独特の食感があり、少しだけ甘味がある。もちろん刺身は抜群にうまい。コノシロはマイワシと同じニシン科で青魚のうま味がとても豊かだからだ。とれたその日なので、まだしこしことした食感が感じられる。少しだけ血合い骨が当たるがこれもいい。 ルーペや定規などが散らばった間で食べてもうまいのが天丼だな、とせわしなく箸を動かしながら思う。さくっと揚がったマイワシの天ぷらを食べて、頂き物の大葉(青じそ)の天ぷらをかじり。ワカメのみそ汁をすする。この時だけは次の撮影を忘れて飯食いに没頭する。
ルーペや定規などが散らばった間で食べてもうまいのが天丼だな、とせわしなく箸を動かしながら思う。さくっと揚がったマイワシの天ぷらを食べて、頂き物の大葉(青じそ)の天ぷらをかじり。ワカメのみそ汁をすする。この時だけは次の撮影を忘れて飯食いに没頭する。 根室3日目(6月25日)で、疲れが脚に来た。東梅という地区に行ったついでに水辺を見つけて、不用意に踏み込んだのが大間違いだった。出てこれなくなった。前日この地域でクマが目撃されている。あり得ないとは思ったけど、こんな状態でクマとご対面したらドナイショ、なんて不安がよぎった。こんなときに限って面白い生き物や植物が目に入るが、撮影する余裕もない。1時間近く(もっと短かったとは思うけど)かかって脱出できたが、胴長は2倍の重さになっていた。このとき、胴長ではなく長靴で入っていたらと想像すると恐くなる。夕方、根室市街地に帰り着き、銭湯の湯につかったときの極楽感は例えようもない。クリカラモンモンのオニイサンにおすすめの居酒屋を聞いたが、家に来いと言われた。もちろん遠慮して逃げた。疲れ果てると余計にアルコールが欲しくなる。風呂上がりに居酒屋を探して歩く。根室の夕暮れはあっと言う間に闇となる。雨がやんだのはありがたかったが、やたらに寒い。居酒屋を目指しながら野良犬同然のエゾジカを探すがいない。たぶんエゾジカも寒いんだろうな。
根室3日目(6月25日)で、疲れが脚に来た。東梅という地区に行ったついでに水辺を見つけて、不用意に踏み込んだのが大間違いだった。出てこれなくなった。前日この地域でクマが目撃されている。あり得ないとは思ったけど、こんな状態でクマとご対面したらドナイショ、なんて不安がよぎった。こんなときに限って面白い生き物や植物が目に入るが、撮影する余裕もない。1時間近く(もっと短かったとは思うけど)かかって脱出できたが、胴長は2倍の重さになっていた。このとき、胴長ではなく長靴で入っていたらと想像すると恐くなる。夕方、根室市街地に帰り着き、銭湯の湯につかったときの極楽感は例えようもない。クリカラモンモンのオニイサンにおすすめの居酒屋を聞いたが、家に来いと言われた。もちろん遠慮して逃げた。疲れ果てると余計にアルコールが欲しくなる。風呂上がりに居酒屋を探して歩く。根室の夕暮れはあっと言う間に闇となる。雨がやんだのはありがたかったが、やたらに寒い。居酒屋を目指しながら野良犬同然のエゾジカを探すがいない。たぶんエゾジカも寒いんだろうな。 皿の上で切りつけた刺身が縮緬状に縮むのが見える。そこにすだちを絞り込むと、さらにぎゅっと縮む。この凹凸が光をはじき返して、きれい、だ。この縮緬に縮れた一切れを口に放り込むと舌の上で、踊る。うま味豊かなのはマサバだから当然と言えば当然だが、そんなに大きくもないのに脂がのって口溶け感がある。口のなかの味を酒で流す気にもなれない。これを帰宅後の早めの昼ご飯で、深夜酒でと食べたが、深夜になっても食感はおとろえない。マサバの漁は不安定であるが、揚がると必ず、この飛びきりの個体が混ざる。それが相模湾の特徴かも知れない。小田原行の日だけで、丸々1尾を刺身で食べてしまえる、なんて思いもしなかった。
皿の上で切りつけた刺身が縮緬状に縮むのが見える。そこにすだちを絞り込むと、さらにぎゅっと縮む。この凹凸が光をはじき返して、きれい、だ。この縮緬に縮れた一切れを口に放り込むと舌の上で、踊る。うま味豊かなのはマサバだから当然と言えば当然だが、そんなに大きくもないのに脂がのって口溶け感がある。口のなかの味を酒で流す気にもなれない。これを帰宅後の早めの昼ご飯で、深夜酒でと食べたが、深夜になっても食感はおとろえない。マサバの漁は不安定であるが、揚がると必ず、この飛びきりの個体が混ざる。それが相模湾の特徴かも知れない。小田原行の日だけで、丸々1尾を刺身で食べてしまえる、なんて思いもしなかった。 【呼び名の由来の話だが、徐々に改訂していく、その土台のようなものだ】明治時代に西洋から来た科学のひとつが生物学で、その中のひとつに動物学が含まれていた。当然、動物学は分類から始まる。分類学で先ずやらなければいけないことは、国内にいる生き物の名と学名を照らし合わせることだ。手初めに全国で使われている魚の名をかたっぱしから集める。分類学で使う名を標準和名といい、世界中で共通して使う名を学名というのだが、まず最初に標準和名を決めなければ分類学は始まらないのだ。分類学の明治初めの拠点は東京にあったので、もっとも身近な場所で、例えば魚類が見られる場所から名の採取を始める。それが日本橋にあった魚河岸である。明治10年(1877)に来日したお雇い教師、アメリカ人のエドワード・モースが、来日すると同時に江の島に小屋を借りてシャミセンガイ(腕足類)の研究を始める。たぶんこの小屋はモースだけのものではなく、日本の分類学にも大きな意味を持つ。ハシキンメに学名をつけたのは、ドイツの動物学者でお雇い教師のルートヴィヒ・デーデルライン(国内の多くの生物を記載している)だが、彼も江の島に通ったひとりだ。標準和名も江の島で使われていた名を採用する。実際、標準和名の多くが江の島で採取された名であるのは、モースの小屋と明らかに関係があると思われるし、それを引き継いだ、デーデルラインとの関係もある。江の島で本種をハシキンメと呼んでいたのは、なぜだろう?参考文献/『全日本及び周辺地域に於ける魚の地方名』(高木正人 1970)
【呼び名の由来の話だが、徐々に改訂していく、その土台のようなものだ】明治時代に西洋から来た科学のひとつが生物学で、その中のひとつに動物学が含まれていた。当然、動物学は分類から始まる。分類学で先ずやらなければいけないことは、国内にいる生き物の名と学名を照らし合わせることだ。手初めに全国で使われている魚の名をかたっぱしから集める。分類学で使う名を標準和名といい、世界中で共通して使う名を学名というのだが、まず最初に標準和名を決めなければ分類学は始まらないのだ。分類学の明治初めの拠点は東京にあったので、もっとも身近な場所で、例えば魚類が見られる場所から名の採取を始める。それが日本橋にあった魚河岸である。明治10年(1877)に来日したお雇い教師、アメリカ人のエドワード・モースが、来日すると同時に江の島に小屋を借りてシャミセンガイ(腕足類)の研究を始める。たぶんこの小屋はモースだけのものではなく、日本の分類学にも大きな意味を持つ。ハシキンメに学名をつけたのは、ドイツの動物学者でお雇い教師のルートヴィヒ・デーデルライン(国内の多くの生物を記載している)だが、彼も江の島に通ったひとりだ。標準和名も江の島で使われていた名を採用する。実際、標準和名の多くが江の島で採取された名であるのは、モースの小屋と明らかに関係があると思われるし、それを引き継いだ、デーデルラインとの関係もある。江の島で本種をハシキンメと呼んでいたのは、なぜだろう?参考文献/『全日本及び周辺地域に於ける魚の地方名』(高木正人 1970) 同じ漁港の水揚げを長年見ていると、ときどき気になる、何か? を感じることがある。そのときには、それほどたいしたことだとは思っていないが、後々、ちゃんと、その何か? が分類学的(ほかの分野であることも)に証明されることがあるからバカに出来ない。ボクの疑問は鹿児島県鹿児島市、鹿児島魚市場にハチジョウアカムツが並んでいるときに感じたものだ。ハチジョウアカムツはまとまって揚がるので、ずらりと並べられていることが多い。そんなハチジョウアカムツと思える何か? が希に2、3個体だけ並ぶことがある。4年ほど前に、気になったのでその2個体の片割れを、清水の舞台から飛び降りるつもりだ買ってみた。ハチジョウアカムツは今や非常に高価なので、競ってもらうためには覚悟がいる。屋久島近海のもので、到着したものを徹底的に計測して、撮影し、我がデータベースの手堅い相談役、和田英俊さんを始め何人かに見てもらった。結果、現状では和名無しの国内新発見(あくまでも魚類学的に)の魚ということがわかる。これが後にオオアカムツと命名される魚である。意外に門外漢の感も捨てたものではないと思ったものだが、鹿児島の多くの市場人が気づいていたことがわかってきた。しかも鹿児島大学でいちばん市場に詳しい、大富潤さんが論文に参加しているのである。みな考えることは同じなのだ。念のために今回、国内海域での確認の論文には、ジョン・ビョルさん、大富潤さん、本村浩之さんの3人の著者がいる。第一著者はジョン・ビョルさんだろう。一度会ってみたいものである。今回が2個体目。前回気がつかなかった細部も調べて撮影する。頭部近くの鱗の形や鰓蓋(鰓蓋骨)の後縁の形などだが、明らかにハチジョウアカムツとは違っている。ちなみに小笠原諸島のハチジョウアカムツは、東京都内ではあたりまえの魚で、入荷するたびにチェックしているが、まだオオアカムツだと思える個体には出合っていない。
同じ漁港の水揚げを長年見ていると、ときどき気になる、何か? を感じることがある。そのときには、それほどたいしたことだとは思っていないが、後々、ちゃんと、その何か? が分類学的(ほかの分野であることも)に証明されることがあるからバカに出来ない。ボクの疑問は鹿児島県鹿児島市、鹿児島魚市場にハチジョウアカムツが並んでいるときに感じたものだ。ハチジョウアカムツはまとまって揚がるので、ずらりと並べられていることが多い。そんなハチジョウアカムツと思える何か? が希に2、3個体だけ並ぶことがある。4年ほど前に、気になったのでその2個体の片割れを、清水の舞台から飛び降りるつもりだ買ってみた。ハチジョウアカムツは今や非常に高価なので、競ってもらうためには覚悟がいる。屋久島近海のもので、到着したものを徹底的に計測して、撮影し、我がデータベースの手堅い相談役、和田英俊さんを始め何人かに見てもらった。結果、現状では和名無しの国内新発見(あくまでも魚類学的に)の魚ということがわかる。これが後にオオアカムツと命名される魚である。意外に門外漢の感も捨てたものではないと思ったものだが、鹿児島の多くの市場人が気づいていたことがわかってきた。しかも鹿児島大学でいちばん市場に詳しい、大富潤さんが論文に参加しているのである。みな考えることは同じなのだ。念のために今回、国内海域での確認の論文には、ジョン・ビョルさん、大富潤さん、本村浩之さんの3人の著者がいる。第一著者はジョン・ビョルさんだろう。一度会ってみたいものである。今回が2個体目。前回気がつかなかった細部も調べて撮影する。頭部近くの鱗の形や鰓蓋(鰓蓋骨)の後縁の形などだが、明らかにハチジョウアカムツとは違っている。ちなみに小笠原諸島のハチジョウアカムツは、東京都内ではあたりまえの魚で、入荷するたびにチェックしているが、まだオオアカムツだと思える個体には出合っていない。 小田原魚市場から帰り着き、疲れ取りの仮眠前、「やはりエビフライは根鰓亜目クルマエビ科がいい」と考えながらフトミゾエビのフライでビールを飲む。わかりにくいことを書いてしまったが、クルマエビ科の大型エビであるクルマエビ、クマエビ(足赤と呼ばれることが多い)、ウシエビ(外国産はブラックタイガー)はフライに使われることが多く、味のよさから人気抜群である。本種、フトミゾエビは前3種と比べるとマイナーではあるが、同じように大きくなるので同じようにフライにして非常にうまい、のである。東京の洋食屋を真似て細目パン粉で揚げ、久しぶりに酸味のあるウスターソース、リー・アンド・ペリンを合わせてみた。ソースにこだわりがあるわけではないが、細目パン粉のフライにはこれが合うと思っている。かじりついたときのエビらしい甘味をともなった香りと、プリっとして食感がたまらない。口中を冷やし、洗うビールがうまい。
小田原魚市場から帰り着き、疲れ取りの仮眠前、「やはりエビフライは根鰓亜目クルマエビ科がいい」と考えながらフトミゾエビのフライでビールを飲む。わかりにくいことを書いてしまったが、クルマエビ科の大型エビであるクルマエビ、クマエビ(足赤と呼ばれることが多い)、ウシエビ(外国産はブラックタイガー)はフライに使われることが多く、味のよさから人気抜群である。本種、フトミゾエビは前3種と比べるとマイナーではあるが、同じように大きくなるので同じようにフライにして非常にうまい、のである。東京の洋食屋を真似て細目パン粉で揚げ、久しぶりに酸味のあるウスターソース、リー・アンド・ペリンを合わせてみた。ソースにこだわりがあるわけではないが、細目パン粉のフライにはこれが合うと思っている。かじりついたときのエビらしい甘味をともなった香りと、プリっとして食感がたまらない。口中を冷やし、洗うビールがうまい。 クリーム色の肝と身で作ったタチウオの「みそたたき(なめろう)」は、にんにくを入れたこともあり、味は複雑かつ濃厚である。アクセントになるはずのねぎの香りが非常に薄く感じるほどだ。舌に乗せると、うま味が急激に広がり、しかも後味はけっして悪くない。こんなに脂が豊かで、こんなに濃厚なうま味があるのに嫌みがないのは、タチウオならではだろう。面白いことにいつもよりも多めに使ったみその存在感が弱い。冷たく冷やした酒が実にいい。酒と「みそたたき」、どちらが欠けてもよろしくねい、そんなカップリングである
クリーム色の肝と身で作ったタチウオの「みそたたき(なめろう)」は、にんにくを入れたこともあり、味は複雑かつ濃厚である。アクセントになるはずのねぎの香りが非常に薄く感じるほどだ。舌に乗せると、うま味が急激に広がり、しかも後味はけっして悪くない。こんなに脂が豊かで、こんなに濃厚なうま味があるのに嫌みがないのは、タチウオならではだろう。面白いことにいつもよりも多めに使ったみその存在感が弱い。冷たく冷やした酒が実にいい。酒と「みそたたき」、どちらが欠けてもよろしくねい、そんなカップリングである めったにやらない健康診断で、いろいろ言われた。専門家に自分が食べたものを見直しなさいと言われ、同じ日に友人に食べたものを書き出せ、と言われる。いちばんしっかり食べる朝ご飯を、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。6月初旬に小田原にいった日の翌々日に当たる。マルソウダのゆで節となす・車麩の煮つけ、やいこもどき、ゴマサバ煮生干しのみそ汁(さつまいも)、トマト、東京たくわん。【マルソウダのゆで節となす・車麩の煮つけ】 マルソウダの半身を強めの塩水で煮て、放冷したゆで節と、新潟県十日町市で買った車麩、なすをたき合わせたもの。ゆで節はともかく新潟県ではこのような煮つけをよく食べるようだ。【やえこもどき】 ゆで節をつぶしてみそ、すりごまとすりあわせたもの。湯をそそいで汁にしてもいいし、表面を焼いてもおいしい。【ゴマサバ煮生干しのみそ汁(さつまいも)】 ゴマサバの幼魚を強めの塩水でゆでて、干し上げた煮干しとサツマイモでみそ汁に。煮干しは刺し昆布をして、少し煮出す。サツマイモを加えて柔らかくなったらみそを溶く。煮干しは干しが弱いのでみそ汁の具にしても柔らかくて食べやすいし、とてもうま味豊かなだしが出る。地味だけど、健康診断で言われた通りの食事になっている気がする。
めったにやらない健康診断で、いろいろ言われた。専門家に自分が食べたものを見直しなさいと言われ、同じ日に友人に食べたものを書き出せ、と言われる。いちばんしっかり食べる朝ご飯を、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。6月初旬に小田原にいった日の翌々日に当たる。マルソウダのゆで節となす・車麩の煮つけ、やいこもどき、ゴマサバ煮生干しのみそ汁(さつまいも)、トマト、東京たくわん。【マルソウダのゆで節となす・車麩の煮つけ】 マルソウダの半身を強めの塩水で煮て、放冷したゆで節と、新潟県十日町市で買った車麩、なすをたき合わせたもの。ゆで節はともかく新潟県ではこのような煮つけをよく食べるようだ。【やえこもどき】 ゆで節をつぶしてみそ、すりごまとすりあわせたもの。湯をそそいで汁にしてもいいし、表面を焼いてもおいしい。【ゴマサバ煮生干しのみそ汁(さつまいも)】 ゴマサバの幼魚を強めの塩水でゆでて、干し上げた煮干しとサツマイモでみそ汁に。煮干しは刺し昆布をして、少し煮出す。サツマイモを加えて柔らかくなったらみそを溶く。煮干しは干しが弱いのでみそ汁の具にしても柔らかくて食べやすいし、とてもうま味豊かなだしが出る。地味だけど、健康診断で言われた通りの食事になっている気がする。 【学者にとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変で、ちょっとだけ珍しい、のを「隣の珍魚」という。】この魚を高知県の一部では「あおだいしょう」と呼ぶ。明らかにヘビの仲間のアオダイショウのことで、確かによくよくみるとヘビに似た顔つきをしている。念のために漁港でこの魚を前にして「ヘビに見えませんか?」と聞くと、みな「見える見える」とうなずく。言われると心底ヘビに思えるようで、見たくないものを見てしまったように後ずさりする。水木しげるのえがく妖怪は一見市井に普通にいる人のようで、振り向くとバケモノという一定の定義を持つ。本種はもっともっと食卓に上げて欲しい魚だが、そのような妖怪じみたところがあるので流通しないのではないか、と思っている。
【学者にとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変で、ちょっとだけ珍しい、のを「隣の珍魚」という。】この魚を高知県の一部では「あおだいしょう」と呼ぶ。明らかにヘビの仲間のアオダイショウのことで、確かによくよくみるとヘビに似た顔つきをしている。念のために漁港でこの魚を前にして「ヘビに見えませんか?」と聞くと、みな「見える見える」とうなずく。言われると心底ヘビに思えるようで、見たくないものを見てしまったように後ずさりする。水木しげるのえがく妖怪は一見市井に普通にいる人のようで、振り向くとバケモノという一定の定義を持つ。本種はもっともっと食卓に上げて欲しい魚だが、そのような妖怪じみたところがあるので流通しないのではないか、と思っている。 食べる直前にばらばらにする。骨もそのままににんにくとエキストラバージンオイルをたっぷりかけ回す。仮眠前のワインの友というか、軽い食事である。骨周りの皮や筋肉をしゃぶり、一緒に焼き上げたジャガイモを食べる。これを冷やした一升瓶ワインで洗い流す。皮や骨周りの身にこんなに豊かな味があることは、オリーブオイルをかいするとより鮮明にわかる。単に塩コショウしただけよりもぱきっと心に感じ取れる。にんにくとオリーブオイルという最強の味方をつけたといった感じである。クエの頭部を丸ごとじっくりしゃぶりつくせるのもいい。余談になるが、ときどきイギリスのモルトビネガーとか、国内で作られた赤酢、バルサミコなどを振って食べているが味変わりしておいしい。
食べる直前にばらばらにする。骨もそのままににんにくとエキストラバージンオイルをたっぷりかけ回す。仮眠前のワインの友というか、軽い食事である。骨周りの皮や筋肉をしゃぶり、一緒に焼き上げたジャガイモを食べる。これを冷やした一升瓶ワインで洗い流す。皮や骨周りの身にこんなに豊かな味があることは、オリーブオイルをかいするとより鮮明にわかる。単に塩コショウしただけよりもぱきっと心に感じ取れる。にんにくとオリーブオイルという最強の味方をつけたといった感じである。クエの頭部を丸ごとじっくりしゃぶりつくせるのもいい。余談になるが、ときどきイギリスのモルトビネガーとか、国内で作られた赤酢、バルサミコなどを振って食べているが味変わりしておいしい。 北海道に来てから食べた飯は、弁当も含めてみな美味であった。特にコンビニ弁当がよかったのである。着いた翌日の朝はセイコーマートの週替わり弁当である。この日が始まってから2時間、空腹感に耐えられなくなって店内に飛び込んで選ぶ間もなく買ってきた。主役のサケが養殖物だったらイヤだなとは思ったものの、じっくり選んでいる時間がない。根室の旅は1時間刻み以上にもっと細かく刻んで動いていた。根室漁協の水揚げは漁師さんがやってくるたびに場内にもどり、気になることをチェックしていたので、一段落つく間がなかった。競りが終わったら、すぐに向かわなければ向かわなければならないところもある。競り場を見ながらの朝ご飯だったが、なによりもご飯がおいしい。おかずもおいしくて、塩気のバランスがいいのも見事だ。これなら毎日食べてもいいかも。都内に帰ってきて、忙しくて大手コンビニの弁当を買ってきてもらって食べたら、悲しくなってきた。
北海道に来てから食べた飯は、弁当も含めてみな美味であった。特にコンビニ弁当がよかったのである。着いた翌日の朝はセイコーマートの週替わり弁当である。この日が始まってから2時間、空腹感に耐えられなくなって店内に飛び込んで選ぶ間もなく買ってきた。主役のサケが養殖物だったらイヤだなとは思ったものの、じっくり選んでいる時間がない。根室の旅は1時間刻み以上にもっと細かく刻んで動いていた。根室漁協の水揚げは漁師さんがやってくるたびに場内にもどり、気になることをチェックしていたので、一段落つく間がなかった。競りが終わったら、すぐに向かわなければ向かわなければならないところもある。競り場を見ながらの朝ご飯だったが、なによりもご飯がおいしい。おかずもおいしくて、塩気のバランスがいいのも見事だ。これなら毎日食べてもいいかも。都内に帰ってきて、忙しくて大手コンビニの弁当を買ってきてもらって食べたら、悲しくなってきた。 専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。きっとこれはボクにとってもいい傾向だろう。なんてがんばっていたのに、ぜんぜん自分の食事を見直す暇がない。久しぶりに、しかも1ヶ月以上遅れで。この日も撮影した魚をおかずにする。大量に撮影していたので、魚の撮影準備をやりながらのご飯。これじゃ体にいいわきゃないよ♪アオメエソの唐揚げ。我が家では唐揚げをおかずにご飯は、本来やらない。福島県いわき市、宮崎県延岡市など、アオメエソを名物にしているところではしばしば見かける。アオメエソの唐揚げには本来ビールかも。マイワシ丸干し。千葉県産が多いマイワシの丸干しだが、千葉県だけでなく関東のものは乾燥が弱いので1日冷蔵庫で干し直す。これを焼いたら、やっぱりマイワシの目ざしの味にノックアウトされる。ご飯とも合う。千葉県野田市、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬け。にんじんとエリンギなどなどのみそ汁。
専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。きっとこれはボクにとってもいい傾向だろう。なんてがんばっていたのに、ぜんぜん自分の食事を見直す暇がない。久しぶりに、しかも1ヶ月以上遅れで。この日も撮影した魚をおかずにする。大量に撮影していたので、魚の撮影準備をやりながらのご飯。これじゃ体にいいわきゃないよ♪アオメエソの唐揚げ。我が家では唐揚げをおかずにご飯は、本来やらない。福島県いわき市、宮崎県延岡市など、アオメエソを名物にしているところではしばしば見かける。アオメエソの唐揚げには本来ビールかも。マイワシ丸干し。千葉県産が多いマイワシの丸干しだが、千葉県だけでなく関東のものは乾燥が弱いので1日冷蔵庫で干し直す。これを焼いたら、やっぱりマイワシの目ざしの味にノックアウトされる。ご飯とも合う。千葉県野田市、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬け。にんじんとエリンギなどなどのみそ汁。 深夜に目が覚めてしまって、なんとなくアヒージョを作る。酒を飲みたかっただけだけど、空酒じゃ困ると言った感じだが、ここにバゲットがあったのを気づかなかったのか、気づかないふりをしたのか。熱々のオリーブオイルと一緒に少しずつ食べ食べ、本当は料理用に買っておいたジンをロックでやる。明らかに100度近い油の温度が急激に低下したと言っても、アチチといいながら食べて、ジンで冷やす。もう何十年も作っている料理だが、こんなに簡単で、こんなにうまい料理はない、なんて思う。問題は深夜なのだからバゲットはよせ、と自分に言い聞かせたのに、ダメだったことだ。やはりアヒージョは油を食べる料理だと思う。
深夜に目が覚めてしまって、なんとなくアヒージョを作る。酒を飲みたかっただけだけど、空酒じゃ困ると言った感じだが、ここにバゲットがあったのを気づかなかったのか、気づかないふりをしたのか。熱々のオリーブオイルと一緒に少しずつ食べ食べ、本当は料理用に買っておいたジンをロックでやる。明らかに100度近い油の温度が急激に低下したと言っても、アチチといいながら食べて、ジンで冷やす。もう何十年も作っている料理だが、こんなに簡単で、こんなにうまい料理はない、なんて思う。問題は深夜なのだからバゲットはよせ、と自分に言い聞かせたのに、ダメだったことだ。やはりアヒージョは油を食べる料理だと思う。 まことにもって久しぶりに焼き上がった糠と魚が入り交じった香りをかいでウットリする。焼き上がったら徹底的にばらして食べやすい状態にしてご飯の友にする。ほどよい塩辛さと糠の香ばさに白飯の甘さが合体して、息をつけないほど飯食いに熱中させられる。禁を犯して二杯飯となっても止められない。2パック、4本買っておいてよかった。
まことにもって久しぶりに焼き上がった糠と魚が入り交じった香りをかいでウットリする。焼き上がったら徹底的にばらして食べやすい状態にしてご飯の友にする。ほどよい塩辛さと糠の香ばさに白飯の甘さが合体して、息をつけないほど飯食いに熱中させられる。禁を犯して二杯飯となっても止められない。2パック、4本買っておいてよかった。 やはりイシガキガイ(エゾイシカゲガイ)を食べないと、夏が到来した気にならない。待ちに待ったといった味覚である。今回は素直に刺身にして食べた。江戸前寿司の仕込みである「湯引き」もいいけど、去年から完全な「生」に目覚めてしまった気がする。造ってすぐに食べないとならないのは欠点だけど、「生」の微かな渋味を伴った強い甘味、貝らしい風味の豊かさと他の貝に代えがたい美味だと思っている。
やはりイシガキガイ(エゾイシカゲガイ)を食べないと、夏が到来した気にならない。待ちに待ったといった味覚である。今回は素直に刺身にして食べた。江戸前寿司の仕込みである「湯引き」もいいけど、去年から完全な「生」に目覚めてしまった気がする。造ってすぐに食べないとならないのは欠点だけど、「生」の微かな渋味を伴った強い甘味、貝らしい風味の豊かさと他の貝に代えがたい美味だと思っている。 居酒屋放浪記なんてテレビ番組があるが、目的の居酒屋が決まっているのに放浪記とはちゃんちゃらおかしい。へそで湯が沸くくらいに変だと思う。ボクの場合、いつも行き当たりばったりなので、夜の町をひたすら放浪する。ただし翌日が早いので、飲むのは午後7時までと決めている。なかったら諦める。歩いて15分くらいで北の酒場通りに着く。疲れ果てて足にきているので教わった居酒屋に入ったら、席にライター(たぶん持ち帰っていいってもん)がおいてあった。しかも隣ですぱすぱと煙が立ちこめる。生まれてから一度もタバコを吸っていないので、こりゃたまらんと席を替えてもらったが、なんとなくヤーな気分が立ちこめる。まずくはないけど早々に去る。本降りの雨で、非常に冷たく寒い。帰ろうかな? そろそろ眠ろうかな? と根室で考えていたら目の前にラーメン屋があるではないか。いい感じだったので、引き戸をあけて入ったら、もっともっといい感じだった。もうひとつ飲み足りないので、コップ酒を飲みながらラーメンを待つ。話の寄り道をすると、ラーメンと酒、もしくは焼酎は、博多長浜でからんできたオヤジに無理強いされたことに始まる。無理強いされてよかったと思っている。ほどなくやってきたラーメンをゆったり食べながら、酒もやる。もちろん博多のようにラーメンに酒を入れたりはしない。あっさりしたスープなのに、味の奥深さがある。ラーメン通ではないが麺も上等だと思う。
居酒屋放浪記なんてテレビ番組があるが、目的の居酒屋が決まっているのに放浪記とはちゃんちゃらおかしい。へそで湯が沸くくらいに変だと思う。ボクの場合、いつも行き当たりばったりなので、夜の町をひたすら放浪する。ただし翌日が早いので、飲むのは午後7時までと決めている。なかったら諦める。歩いて15分くらいで北の酒場通りに着く。疲れ果てて足にきているので教わった居酒屋に入ったら、席にライター(たぶん持ち帰っていいってもん)がおいてあった。しかも隣ですぱすぱと煙が立ちこめる。生まれてから一度もタバコを吸っていないので、こりゃたまらんと席を替えてもらったが、なんとなくヤーな気分が立ちこめる。まずくはないけど早々に去る。本降りの雨で、非常に冷たく寒い。帰ろうかな? そろそろ眠ろうかな? と根室で考えていたら目の前にラーメン屋があるではないか。いい感じだったので、引き戸をあけて入ったら、もっともっといい感じだった。もうひとつ飲み足りないので、コップ酒を飲みながらラーメンを待つ。話の寄り道をすると、ラーメンと酒、もしくは焼酎は、博多長浜でからんできたオヤジに無理強いされたことに始まる。無理強いされてよかったと思っている。ほどなくやってきたラーメンをゆったり食べながら、酒もやる。もちろん博多のようにラーメンに酒を入れたりはしない。あっさりしたスープなのに、味の奥深さがある。ラーメン通ではないが麺も上等だと思う。 地スーパーや魚屋で、なにがうれしいといって、うまい魚の惣菜が買えることこそだろう。大きなスーパーの惣菜は押し並べてまずい。たぶん大量に仕入れて大量に仕込むからだろう。さて、千葉県君津市久留里、吉田屋で「へしこいわしの酢じめ」を買った。大小あったが、小で充分といった量だった。大渋滞の中、千葉から帰り着いて食べた、「へしこいわしの酢じめ」がうまかった。もちろん保存性を考えて強く締めたものだが、この酢を利かせすぎたものだってきらいではない。当日は同じく吉田屋で買ったカツオの刺身と、「へしこいわしの酢じめ」で九十九里ビールを飲んだが、意外にも酢の物とビールが合う。なんだか川本三郎気分にもなれた。
地スーパーや魚屋で、なにがうれしいといって、うまい魚の惣菜が買えることこそだろう。大きなスーパーの惣菜は押し並べてまずい。たぶん大量に仕入れて大量に仕込むからだろう。さて、千葉県君津市久留里、吉田屋で「へしこいわしの酢じめ」を買った。大小あったが、小で充分といった量だった。大渋滞の中、千葉から帰り着いて食べた、「へしこいわしの酢じめ」がうまかった。もちろん保存性を考えて強く締めたものだが、この酢を利かせすぎたものだってきらいではない。当日は同じく吉田屋で買ったカツオの刺身と、「へしこいわしの酢じめ」で九十九里ビールを飲んだが、意外にも酢の物とビールが合う。なんだか川本三郎気分にもなれた。 深夜、冷たい酒を用意して、小鉢に向かうと、中に盛り込んだ刺身の表面がギラついてきている。身に混在していた脂が溶け出して浮き上がって来ているのだ。淡路島のマアジは5月から始まり7月には第一群が終わる。そしてまた次の群れが釣れ始め、10月に一段落つく。今回のものはその先触れの個体群であるが、脂が豊かすぎて切りつけた刺身が鈍い色をしている。口に入れると真っ先に口溶け感からの甘さがくる。青魚の豊かなうま味もあって名状しがたい味としかいいようがない。冷やした酒で口中を洗うのがもったいない気がしてくる。
深夜、冷たい酒を用意して、小鉢に向かうと、中に盛り込んだ刺身の表面がギラついてきている。身に混在していた脂が溶け出して浮き上がって来ているのだ。淡路島のマアジは5月から始まり7月には第一群が終わる。そしてまた次の群れが釣れ始め、10月に一段落つく。今回のものはその先触れの個体群であるが、脂が豊かすぎて切りつけた刺身が鈍い色をしている。口に入れると真っ先に口溶け感からの甘さがくる。青魚の豊かなうま味もあって名状しがたい味としかいいようがない。冷やした酒で口中を洗うのがもったいない気がしてくる。 曜日の感覚がボクには存在しないので、駅前まで打ち合わせで出てはじめて今日が日曜日であることを知る。下る坂道に陽炎が立つ。腰に下げている、温度計のアラームが鳴る。路上温度ではあるがまさかの40℃である。やってきた相手も顔が赤い。こんなとき仕事をしちゃーいかんと話しながらも、ちゃんと打ち合わせて帰ってきた。帰り着いて張りついたTシャツを脱いで、冷たいシャワーを浴びても体から熱が出ていかない。横になっても落ち着かないので、考えに考えた末に、魚のみそ汁を作ることにした。最近、沖縄が本州よりも暑いなんてとても思えないが、ほんの数年前まで圧倒的に沖縄の方が暑かった。そんな沖縄の郷土料理が魚汁である。「いまいゆの魚汁」は沖縄の定番的な食堂メニューだ。「いまいゆ」は新鮮な生魚のことで、魚汁とは魚のみそ汁のことである。沖縄県で魚汁が汁以上の存在であることは、定食の主菜となっていることからもわかる。魚汁を頼むと、ご飯に漬物、小鉢が自動的についてくる。この「魚汁定食」は食事でもあるし、体から熱を追い払うための薬でもあるのだ。実際沖縄で魚汁を食べると、元気になる。あまりにも息苦しいので、本能で作った魚汁ともいえそうだ。幸運なことに、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが釣り上げてきたタチウオのあらがまだ3分の1くらい冷凍庫で眠っている。保存袋のまま流水で解凍して、湯通しして冷水に取り、水分を切ったものを鍋に放り込む。ここに水を張り、刺し昆布(小さな昆布)をして、ことこと煮だして福島県相馬市山形屋のみそをちょっと多めに溶く。みその塩気がいいのだろう。熱々なのに体が冷めていく。タチウオのだしがいっぱいでており、汁としてこの上なくうまい。あまりにも体に熱がたまりすぎていたら、魚汁を作るに限る。
曜日の感覚がボクには存在しないので、駅前まで打ち合わせで出てはじめて今日が日曜日であることを知る。下る坂道に陽炎が立つ。腰に下げている、温度計のアラームが鳴る。路上温度ではあるがまさかの40℃である。やってきた相手も顔が赤い。こんなとき仕事をしちゃーいかんと話しながらも、ちゃんと打ち合わせて帰ってきた。帰り着いて張りついたTシャツを脱いで、冷たいシャワーを浴びても体から熱が出ていかない。横になっても落ち着かないので、考えに考えた末に、魚のみそ汁を作ることにした。最近、沖縄が本州よりも暑いなんてとても思えないが、ほんの数年前まで圧倒的に沖縄の方が暑かった。そんな沖縄の郷土料理が魚汁である。「いまいゆの魚汁」は沖縄の定番的な食堂メニューだ。「いまいゆ」は新鮮な生魚のことで、魚汁とは魚のみそ汁のことである。沖縄県で魚汁が汁以上の存在であることは、定食の主菜となっていることからもわかる。魚汁を頼むと、ご飯に漬物、小鉢が自動的についてくる。この「魚汁定食」は食事でもあるし、体から熱を追い払うための薬でもあるのだ。実際沖縄で魚汁を食べると、元気になる。あまりにも息苦しいので、本能で作った魚汁ともいえそうだ。幸運なことに、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが釣り上げてきたタチウオのあらがまだ3分の1くらい冷凍庫で眠っている。保存袋のまま流水で解凍して、湯通しして冷水に取り、水分を切ったものを鍋に放り込む。ここに水を張り、刺し昆布(小さな昆布)をして、ことこと煮だして福島県相馬市山形屋のみそをちょっと多めに溶く。みその塩気がいいのだろう。熱々なのに体が冷めていく。タチウオのだしがいっぱいでており、汁としてこの上なくうまい。あまりにも体に熱がたまりすぎていたら、魚汁を作るに限る。 【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】ボウズギンポは、10年前までは珍魚中の珍魚だった。今じゃ、見た目の気持ち悪さに後ずさりしたくはなるものの、ちょっと珍しいだけの魚になってしまっている。初めて見たのは12年前(2024年現在)のこと、京都中央市場のレアなもん大好き魚屋で、だ。まるでアザラシの死体ようだと思ったら魚だった、というのも変な出合いである。ぱっと見たらアザラシだけど、よくよく見るともっと奇想天外、太い丸太ん棒のようで、どっかのオヤジサンの顔を思わせたり、円谷プロの怪獣のようでもある。これを最初に競り落として、売ってみたヤツはどこのどいつなんじゃいと思う。明治時代の魚類学の父たちもかなりコイツに悩まされたようだ。そこにいるのが魚類であることは間違いない。魚類を定義する条件である顎もあるし、鰭もあるのだから。でも似たような魚がどこにもいない。結局、近縁種と思われる魚はいないことがわかり、ちょっと専門的だが1種、1属、1科で孤立無援な魚であるとされている。ちなみに本種は広い意味ではゲンゲ亜目(ゲンゲの仲間)だが、この「げんげ」は下魚とか幻魚とかの漢字が当てられ、とれてもまずいので売れない魚とか、見た目が変な魚とかいう意味を持つ。魚類学の黎明期、「わからないものはとりあえず、ゲンゲの仲間として置こうじゃないかい」的なポジションだったようだ。
【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】ボウズギンポは、10年前までは珍魚中の珍魚だった。今じゃ、見た目の気持ち悪さに後ずさりしたくはなるものの、ちょっと珍しいだけの魚になってしまっている。初めて見たのは12年前(2024年現在)のこと、京都中央市場のレアなもん大好き魚屋で、だ。まるでアザラシの死体ようだと思ったら魚だった、というのも変な出合いである。ぱっと見たらアザラシだけど、よくよく見るともっと奇想天外、太い丸太ん棒のようで、どっかのオヤジサンの顔を思わせたり、円谷プロの怪獣のようでもある。これを最初に競り落として、売ってみたヤツはどこのどいつなんじゃいと思う。明治時代の魚類学の父たちもかなりコイツに悩まされたようだ。そこにいるのが魚類であることは間違いない。魚類を定義する条件である顎もあるし、鰭もあるのだから。でも似たような魚がどこにもいない。結局、近縁種と思われる魚はいないことがわかり、ちょっと専門的だが1種、1属、1科で孤立無援な魚であるとされている。ちなみに本種は広い意味ではゲンゲ亜目(ゲンゲの仲間)だが、この「げんげ」は下魚とか幻魚とかの漢字が当てられ、とれてもまずいので売れない魚とか、見た目が変な魚とかいう意味を持つ。魚類学の黎明期、「わからないものはとりあえず、ゲンゲの仲間として置こうじゃないかい」的なポジションだったようだ。 市場のよいところは、そこにプロがいることだ。甲殻類のエビや軟体類の貝やイカのパスタは至って簡単だが、魚のパスタの作り方が思い浮かばない。そこにフレンチのル・トンさん(八王子市で、市場ではみな屋号で呼び合う)がやってきた。飛んで火に入る夏の虫とはこのことである。魚のパスタに関してアドバイスしてもらって、これはいけると思ったので、お礼はさわやかな「ありがとう」で帰ってきた。魚の身をかりっとソテーして、パスタに混ぜ込んで刻んだケーパーを加えたら、実に夏向き。だいたい1㎏級のタチウオを使った時点で、イカしてるぜ! 的だと思う。カッペリーニにしたのはボクの思いつきだけど、これだって大正解だった。いいオリーブオイルを使ったので軽い味であり、しかもタチウオの濃厚なうま味がカッペリーニにもオリーブオイルにも染み、染みしている。ゴージャスな朝ご飯で王様気分、なーのだ。しかもイケないとは思いながらも、朝っぱらから勝沼の一升瓶ワインを1パイ。ちょっと田中小実昌気分にもなった。
市場のよいところは、そこにプロがいることだ。甲殻類のエビや軟体類の貝やイカのパスタは至って簡単だが、魚のパスタの作り方が思い浮かばない。そこにフレンチのル・トンさん(八王子市で、市場ではみな屋号で呼び合う)がやってきた。飛んで火に入る夏の虫とはこのことである。魚のパスタに関してアドバイスしてもらって、これはいけると思ったので、お礼はさわやかな「ありがとう」で帰ってきた。魚の身をかりっとソテーして、パスタに混ぜ込んで刻んだケーパーを加えたら、実に夏向き。だいたい1㎏級のタチウオを使った時点で、イカしてるぜ! 的だと思う。カッペリーニにしたのはボクの思いつきだけど、これだって大正解だった。いいオリーブオイルを使ったので軽い味であり、しかもタチウオの濃厚なうま味がカッペリーニにもオリーブオイルにも染み、染みしている。ゴージャスな朝ご飯で王様気分、なーのだ。しかもイケないとは思いながらも、朝っぱらから勝沼の一升瓶ワインを1パイ。ちょっと田中小実昌気分にもなった。 息苦しいくらいに暑く、窓をしめ、カーテンを引いているので、エアコンで室内温度的には快適であるが、定期的に鬱鬱とした気分に襲われる。日日(にちにち)、魚まみれだけど、こんなときこそ旬のよろこびを堪能したいものだと思っているとき、目の前にあるのが白いご飯と、旬真っ只中のアオダイの刺身なのである。これも幸せと言えば幸せやも……。アオダイの刺身はあまりにもストレートにうますぎるので文字に出来ない、そこがもどかしい。東京都では昔から、もちろんプロの間では、だが人気のある魚だ。実際、一度食べてみたらまた使いたくなるし、食べたくなる魚だと思う。
息苦しいくらいに暑く、窓をしめ、カーテンを引いているので、エアコンで室内温度的には快適であるが、定期的に鬱鬱とした気分に襲われる。日日(にちにち)、魚まみれだけど、こんなときこそ旬のよろこびを堪能したいものだと思っているとき、目の前にあるのが白いご飯と、旬真っ只中のアオダイの刺身なのである。これも幸せと言えば幸せやも……。アオダイの刺身はあまりにもストレートにうますぎるので文字に出来ない、そこがもどかしい。東京都では昔から、もちろんプロの間では、だが人気のある魚だ。実際、一度食べてみたらまた使いたくなるし、食べたくなる魚だと思う。 連日のように魚料理を作っていると、料理が多彩になる。たくさん作るので、「ご飯=魚料理」となる。6月になって、6月とは思えない暑さになったとき、今季初の魚の煮つけ素麺を作る。煮つけにゆでた素麺を添えただけのものと、煮つけを作り魚を取り出して、残った煮汁にからめて添える方法があるが、夏は前者に限る。青じそと青唐辛子を添えて、冷たい素麺と温かい魚の煮つけの対比が面白い。素麺の喉ごしに、煮つけの強いうま味がやたらに合う。こんな料理が食えるのも魚料理を作りまくっているせいである。ついでに煮つけを作り、室温まで冷まし、冷蔵庫でさらに冷やしたところに素麺を添えてもいい。エアコンがきかないくらいの暑さの日にはお試しあれ。
連日のように魚料理を作っていると、料理が多彩になる。たくさん作るので、「ご飯=魚料理」となる。6月になって、6月とは思えない暑さになったとき、今季初の魚の煮つけ素麺を作る。煮つけにゆでた素麺を添えただけのものと、煮つけを作り魚を取り出して、残った煮汁にからめて添える方法があるが、夏は前者に限る。青じそと青唐辛子を添えて、冷たい素麺と温かい魚の煮つけの対比が面白い。素麺の喉ごしに、煮つけの強いうま味がやたらに合う。こんな料理が食えるのも魚料理を作りまくっているせいである。ついでに煮つけを作り、室温まで冷まし、冷蔵庫でさらに冷やしたところに素麺を添えてもいい。エアコンがきかないくらいの暑さの日にはお試しあれ。 梅雨なのに、エアコンのきいている室内にいても地獄のようだ。まるでデンドロカカリアとか火星年代記の世界だ。こんなときでも揚げ物を食べたくなるボクには、まだまだ先がある。小出楢重ではあきまへん。今回のフライ種は千葉県銚子産の小中羽(15cm前後)で、刺身で食べるべきかなと思うほどの上物だった。揚げたてを八王子綜合卸売センター、八百角で買ったでかいエゴマの葉にのせて、千葉県で買ったお高い九十九里のペールエールで一時(いっとき)のオアシスを作り出す。カレーの香りをつけたフライの揚げたては、まだ脂が半液化した状態で濃厚にうまい。さっちゃんじゃないけど、フライが3つしか食べられないのにデブなボクが悲しい。エゴマの葉にキムチを挟んで、これぞ夏の〆、とする。
梅雨なのに、エアコンのきいている室内にいても地獄のようだ。まるでデンドロカカリアとか火星年代記の世界だ。こんなときでも揚げ物を食べたくなるボクには、まだまだ先がある。小出楢重ではあきまへん。今回のフライ種は千葉県銚子産の小中羽(15cm前後)で、刺身で食べるべきかなと思うほどの上物だった。揚げたてを八王子綜合卸売センター、八百角で買ったでかいエゴマの葉にのせて、千葉県で買ったお高い九十九里のペールエールで一時(いっとき)のオアシスを作り出す。カレーの香りをつけたフライの揚げたては、まだ脂が半液化した状態で濃厚にうまい。さっちゃんじゃないけど、フライが3つしか食べられないのにデブなボクが悲しい。エゴマの葉にキムチを挟んで、これぞ夏の〆、とする。 久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。以上は前回書いた。1㎏もあるといろんな料理が作れる。「太刀きゅう」もそのひとつだ。ウナギで作れば「うざく」、焼き穴子で作れば「穴子のざくざく」で、ざくもざくざくも関東の「きゅうりもみ」のことである。我が家では夏になると、基本的な「きゅうりもみ」を多めに作り置きする。作り方は簡単で、薄切りきゅうりに塩をして殺し、流水で余分な塩気を流す。よくよく水切りして、甘酢(酢・砂糖)につけて冷蔵保存する。これに焼いた油揚げを加えたり、魚の酢の物と合わせたりする。ときどき魚の干ものをほぐして入れたりもするし、そのまんまきゅうりだけで食べることもある。これに厚く焼き直した「うなぎの蒲焼き」を添わせたのが「うざく」だけど、タチウオのつけ焼きを添わせたのを「太刀ざく」では音が悪すぎるので、「太刀きゅう」と勝手に決め込んだ。さて、タチウオの尾っぽや腹の部分を素焼きにして、みりん・醤油同割りのたれをつけて仕上げる。「きゅうりもみ」を盛り付けたところに熱いうちに添わせ、山椒を振ったただけなので、夜中でもできる。甘辛くて香ばしいタチウオのつけ焼きは口に入れると、ほろりと崩れる。大好きな山椒の香りが猛暑のときに体を癒やしてくれる。おいしくはあるものの単調な味であるところに、「きゅうりもみ」が大活躍してくれる。口の中できりりと締まり、そこに酒でも流し込むと、暑い盛り、やっと一息つけた深夜酒にとても合うのだ。
久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。以上は前回書いた。1㎏もあるといろんな料理が作れる。「太刀きゅう」もそのひとつだ。ウナギで作れば「うざく」、焼き穴子で作れば「穴子のざくざく」で、ざくもざくざくも関東の「きゅうりもみ」のことである。我が家では夏になると、基本的な「きゅうりもみ」を多めに作り置きする。作り方は簡単で、薄切りきゅうりに塩をして殺し、流水で余分な塩気を流す。よくよく水切りして、甘酢(酢・砂糖)につけて冷蔵保存する。これに焼いた油揚げを加えたり、魚の酢の物と合わせたりする。ときどき魚の干ものをほぐして入れたりもするし、そのまんまきゅうりだけで食べることもある。これに厚く焼き直した「うなぎの蒲焼き」を添わせたのが「うざく」だけど、タチウオのつけ焼きを添わせたのを「太刀ざく」では音が悪すぎるので、「太刀きゅう」と勝手に決め込んだ。さて、タチウオの尾っぽや腹の部分を素焼きにして、みりん・醤油同割りのたれをつけて仕上げる。「きゅうりもみ」を盛り付けたところに熱いうちに添わせ、山椒を振ったただけなので、夜中でもできる。甘辛くて香ばしいタチウオのつけ焼きは口に入れると、ほろりと崩れる。大好きな山椒の香りが猛暑のときに体を癒やしてくれる。おいしくはあるものの単調な味であるところに、「きゅうりもみ」が大活躍してくれる。口の中できりりと締まり、そこに酒でも流し込むと、暑い盛り、やっと一息つけた深夜酒にとても合うのだ。 かれこれ1年振りにメイタガレイの刺身が堪能できた。東日本ではめったによいものが手に入らず、メイタといえば煮つけとか塩焼き用だと雑な扱いを受けているのだ。刺身のマコガレイにはない独特の風味、強いうま味は関西人ならずともわかるはずだと思うけど、いかがだろうこれが活け締めなら透明感のあるきれいな刺身になり、食感も心地かっただろう。
かれこれ1年振りにメイタガレイの刺身が堪能できた。東日本ではめったによいものが手に入らず、メイタといえば煮つけとか塩焼き用だと雑な扱いを受けているのだ。刺身のマコガレイにはない独特の風味、強いうま味は関西人ならずともわかるはずだと思うけど、いかがだろうこれが活け締めなら透明感のあるきれいな刺身になり、食感も心地かっただろう。 千葉県君津市久留里は実に景色(全体に)のいい町だと思っている。1980年前後、都内から千葉県鴨川市に抜ける道にあって、山また山の中にぽつんと城下町のあるといった感じがよかった。未舗装の区間もあったこの道でほっとできる空間でもあったと思う。面白いもので同じように市川市・千葉市など(下総)から勝浦市(上総)に抜ける途中にある大多喜に似ている。久留里がいい景色なのに魅力がない原因は国道410号線が町を南北に走っていることで、この町の観光地としての発展を阻害していたと考えている。曲亭馬琴(滝澤馬琴)の『南総里見八犬伝』は江戸時代以来のベストセラーであり、その主軸になる里見氏と深い繋がりのある久留里と考えると、今からでも遅くないので八犬伝の何かを作ってみてはいかがだろう。さて、この町にボクの好きなスーパーがある。近年、年々地スーパーが消えて行く。久留里から小櫃にかけては大型スーパーがなかった。そこにあったのが吉田屋で、ボクはここで数々の発見をしている。ボクの発見伝多しのスーパーである。今回は土を思わせるものではなく、千葉県ならではのもの、勝浦のカツオが売られていた。カツオ船の帰港地の条件は、風呂、遊郭、宿、酒だそうで、勝浦市にはその総がある。千葉県のカツオ船といえば勝浦である。久留里は勝浦から車でひとっ走りなので、売り場のカツオがぴっかぴっかに輝いていた。
千葉県君津市久留里は実に景色(全体に)のいい町だと思っている。1980年前後、都内から千葉県鴨川市に抜ける道にあって、山また山の中にぽつんと城下町のあるといった感じがよかった。未舗装の区間もあったこの道でほっとできる空間でもあったと思う。面白いもので同じように市川市・千葉市など(下総)から勝浦市(上総)に抜ける途中にある大多喜に似ている。久留里がいい景色なのに魅力がない原因は国道410号線が町を南北に走っていることで、この町の観光地としての発展を阻害していたと考えている。曲亭馬琴(滝澤馬琴)の『南総里見八犬伝』は江戸時代以来のベストセラーであり、その主軸になる里見氏と深い繋がりのある久留里と考えると、今からでも遅くないので八犬伝の何かを作ってみてはいかがだろう。さて、この町にボクの好きなスーパーがある。近年、年々地スーパーが消えて行く。久留里から小櫃にかけては大型スーパーがなかった。そこにあったのが吉田屋で、ボクはここで数々の発見をしている。ボクの発見伝多しのスーパーである。今回は土を思わせるものではなく、千葉県ならではのもの、勝浦のカツオが売られていた。カツオ船の帰港地の条件は、風呂、遊郭、宿、酒だそうで、勝浦市にはその総がある。千葉県のカツオ船といえば勝浦である。久留里は勝浦から車でひとっ走りなので、売り場のカツオがぴっかぴっかに輝いていた。 食べ歩きの人ではないので、いつもは行き当たりばったりの旅の食事だが、今回は根室名物の「エスカロップ」という、いったいなんなんだいそれは? といったものを食べてみる。ネット上でいろいろ調べたが、エスカロップの意味はわからなかった。1963年から広まったと言う。福井県発祥だとは、市内で会ったライダー(バイクにのった若い衆)の話。ようするにエスカロップはエスカロップとしか、いいようのないものやも知れぬ。地元の方の案内なので、向かったのは「エスカロップ」で有名だという『ドリアン』というしゃれた店だった。
食べ歩きの人ではないので、いつもは行き当たりばったりの旅の食事だが、今回は根室名物の「エスカロップ」という、いったいなんなんだいそれは? といったものを食べてみる。ネット上でいろいろ調べたが、エスカロップの意味はわからなかった。1963年から広まったと言う。福井県発祥だとは、市内で会ったライダー(バイクにのった若い衆)の話。ようするにエスカロップはエスカロップとしか、いいようのないものやも知れぬ。地元の方の案内なので、向かったのは「エスカロップ」で有名だという『ドリアン』というしゃれた店だった。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にカスベの切り身がきていた。バラバラになっていると同定しにくいので買っても意味がないと思っていたら、やけに切り方が雑だった。しかも吻部分が入っている。奇跡としか言いようがない。下氷(敷き詰めた氷)の上で繋ぎ合わせてみると、同定できそうだったので買ってみた。北海道日高地方浦河からきたものだ。ここは、北海道を生物の頭と見立てたとき、顎のように尖ったところで、北海道道東でも苫小牧から東、厚岸までは街らしい街がない。そのちょっと寂しい印象の地にある小さな町といった感じがする。水産物の産地としても非常に印象が薄いが、調べてみると面白い場所かも知れぬ。この北海道太平洋側の刺網などの水深は寒い時季に深く、温かい時季に浅いのだと思っている。寒い時季の深場にいるのがヒトツセビレカスベ科ソコガンギエイ属の魚たちで水カスベ、どぶカスベ。温かい時季、浅場にいるのがガンギエイ科の真カスベ(メガネカスベ)だ。メガネカスベが浅場で揚がるので古くから馴染みがあり、味がいいこともあっての「真カスベ」なのだと思っている。ちなみに水カスベ、ドブカスベもなんとなく淡々とわかってきているが、まだまだ道遠しだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にカスベの切り身がきていた。バラバラになっていると同定しにくいので買っても意味がないと思っていたら、やけに切り方が雑だった。しかも吻部分が入っている。奇跡としか言いようがない。下氷(敷き詰めた氷)の上で繋ぎ合わせてみると、同定できそうだったので買ってみた。北海道日高地方浦河からきたものだ。ここは、北海道を生物の頭と見立てたとき、顎のように尖ったところで、北海道道東でも苫小牧から東、厚岸までは街らしい街がない。そのちょっと寂しい印象の地にある小さな町といった感じがする。水産物の産地としても非常に印象が薄いが、調べてみると面白い場所かも知れぬ。この北海道太平洋側の刺網などの水深は寒い時季に深く、温かい時季に浅いのだと思っている。寒い時季の深場にいるのがヒトツセビレカスベ科ソコガンギエイ属の魚たちで水カスベ、どぶカスベ。温かい時季、浅場にいるのがガンギエイ科の真カスベ(メガネカスベ)だ。メガネカスベが浅場で揚がるので古くから馴染みがあり、味がいいこともあっての「真カスベ」なのだと思っている。ちなみに水カスベ、ドブカスベもなんとなく淡々とわかってきているが、まだまだ道遠しだ。 久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。以上は前回書いた。もちろん生でも食べた。1㎏上で、魚屋が活け締めにして血抜きしたものなので、探しても探せないレベルのタチウオである。
久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。以上は前回書いた。もちろん生でも食べた。1㎏上で、魚屋が活け締めにして血抜きしたものなので、探しても探せないレベルのタチウオである。 北海道根室市の旅は市内に到着したその日の夜から酔いどれる。もちろん朝が早いので午後7時までの飲みだけれど、このときだけ体が緩む。初日は日曜日だったので、地元の方に営業している店を予約して頂いた。根室市の繁華街といっても密集した飲み屋横丁があるわけでもなく、暗がりの中にぽつんと居酒屋の灯がともっていた。『遊食酒場 壱炉 本店』という店で、外観は真新しく、日曜日なので家族ずれで賑わっていた。とりあえずの生ビールは一日の終わりの始まりにやたらにうまい。この店の突き出しはたぶんマコンブを薄甘く煮たもので、初手はまずまずボク好みであった。
北海道根室市の旅は市内に到着したその日の夜から酔いどれる。もちろん朝が早いので午後7時までの飲みだけれど、このときだけ体が緩む。初日は日曜日だったので、地元の方に営業している店を予約して頂いた。根室市の繁華街といっても密集した飲み屋横丁があるわけでもなく、暗がりの中にぽつんと居酒屋の灯がともっていた。『遊食酒場 壱炉 本店』という店で、外観は真新しく、日曜日なので家族ずれで賑わっていた。とりあえずの生ビールは一日の終わりの始まりにやたらにうまい。この店の突き出しはたぶんマコンブを薄甘く煮たもので、初手はまずまずボク好みであった。 久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。最近、関東のタチウオに時季がないところをみると、年間複数回産卵しているのではないか。これでは昔の紀伊半島状態だ。持ち帰って計測したら115cm・1.09kgもあった。卵巣が大きふくらんでいて、触ると硬く、明らかにこれ以上ない状態とみた。
久しぶりに八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、デカいタチウオが並んでいた。隣でクマゴロウがわはっはと笑っている。たぶん東京湾で釣ったのだろう。いちばんデカいのを1尾連れ帰る。昔市場で伊豆半島以西と言われていたタチウオが相模湾でもたくさん揚がり始め、ついに東京湾横浜沖という湾奥まで侵入してきた。今や関東周辺はタチウオがとれてとれてコマッチャウ。TTK状態である。ちなみにTTKは今はなき、週刊朝日のパクリだ。MMKなんて時代は面白かったものである。最近、関東のタチウオに時季がないところをみると、年間複数回産卵しているのではないか。これでは昔の紀伊半島状態だ。持ち帰って計測したら115cm・1.09kgもあった。卵巣が大きふくらんでいて、触ると硬く、明らかにこれ以上ない状態とみた。 北海道根室市、温根沼、春国岱などの干潟を行ったり来たり、底なし沼にはまって出られなくなったり、クマが近くで目撃されたり。波瀾万丈の時間を干潟で過ごした。少しは痩せられたかも、という以前に寒いのと疲れとで人事不省となる。さて、ここでいろんな方達に話を聞いた。なかでもビックリしたのが、アサリの刺身である。刺身以上のアサリの食べ方はない、という。この温根沼周辺はアマモが大量に生えていて水がとてもキレイなのである。東京湾や愛知県三河でもアサリはとれると思うけど、そのまま生で食べるなんて思いも寄らない。アサリの刺身は北海道東部にある汽水域の、郷土料理と考えるといいのかも。ここのアサリなら刺身にしてうまそうだ、と思うのは、周りに護岸がなく、人家がほとんどないためだ。
北海道根室市、温根沼、春国岱などの干潟を行ったり来たり、底なし沼にはまって出られなくなったり、クマが近くで目撃されたり。波瀾万丈の時間を干潟で過ごした。少しは痩せられたかも、という以前に寒いのと疲れとで人事不省となる。さて、ここでいろんな方達に話を聞いた。なかでもビックリしたのが、アサリの刺身である。刺身以上のアサリの食べ方はない、という。この温根沼周辺はアマモが大量に生えていて水がとてもキレイなのである。東京湾や愛知県三河でもアサリはとれると思うけど、そのまま生で食べるなんて思いも寄らない。アサリの刺身は北海道東部にある汽水域の、郷土料理と考えるといいのかも。ここのアサリなら刺身にしてうまそうだ、と思うのは、周りに護岸がなく、人家がほとんどないためだ。 今旅もまた、あまりにも詰め込みすぎて、寸暇がなかった。根室半島と東梅(温根沼大橋の西側)を右往左往し、また市内のスーパー、魚屋を踏破した。やっと時間が出来たので、念願の竿を出すことができた。ボクは日本全国を股にかけ釣りまくる、さすらいの防波堤釣り師なのだ。仕掛けは北海道中標津で買った片天秤のカレイ仕掛けで、錘は15号だと思うが数字がつぶれていて見えない。エサはアオイソメだ。釣り師お勧めの堤防には作業車がとまっていたので、港内奥まったところで釣り始めた。せわしなく仕掛けを作り、波ひとつない堤防のきわに落とすと目分量で水深1.5mくらいしかない。こーりゃ浅すぎてダメだと水くみをしていたら、ぴんと張っていたテグスがゆるんで竿が跳ね上がっている。潮がとまっているのかな、と、まわりに落としてしまった仕掛けの紙や、ついでに誰かが捨てていった仕掛けの袋とテグスを拾う。ついでにセイコーマートで買ったお握りをぱくぱくやっていたら、今度は竿が沈んでいるように見える。しとしとと朝から降り続いていた雨が上がり、風が止まり凍えるように寒かったのが少しゆるんだのは奇跡だ。またまた竿先が跳ね上がったが、この竿の動きからするとアマモでも引っかかっているに違いない。車まで飲み物を取りに行って、ついでに竿を上げたら、実に重い。ゴミでもひっかけたのかなと思ったら、シュークリームのようなものが仕掛けにしがみついていて、わやわやと何かが動いている。えいやっと堤防に跳ね上げたら、やはりシュークリームのような物体で、よくよく見るとクリガニであろうカニである。まあまあ大きい。クリガニが釣れるとは幸先がいい。じっとしていたのでつかまえようとしたら、いきなり横にするすると堤防を走って海に落ちていった。なんてこったい! カニさんカニさん、どこいくんじゃい?緊張感に欠けていたボクは思わず曇り空を見た。
今旅もまた、あまりにも詰め込みすぎて、寸暇がなかった。根室半島と東梅(温根沼大橋の西側)を右往左往し、また市内のスーパー、魚屋を踏破した。やっと時間が出来たので、念願の竿を出すことができた。ボクは日本全国を股にかけ釣りまくる、さすらいの防波堤釣り師なのだ。仕掛けは北海道中標津で買った片天秤のカレイ仕掛けで、錘は15号だと思うが数字がつぶれていて見えない。エサはアオイソメだ。釣り師お勧めの堤防には作業車がとまっていたので、港内奥まったところで釣り始めた。せわしなく仕掛けを作り、波ひとつない堤防のきわに落とすと目分量で水深1.5mくらいしかない。こーりゃ浅すぎてダメだと水くみをしていたら、ぴんと張っていたテグスがゆるんで竿が跳ね上がっている。潮がとまっているのかな、と、まわりに落としてしまった仕掛けの紙や、ついでに誰かが捨てていった仕掛けの袋とテグスを拾う。ついでにセイコーマートで買ったお握りをぱくぱくやっていたら、今度は竿が沈んでいるように見える。しとしとと朝から降り続いていた雨が上がり、風が止まり凍えるように寒かったのが少しゆるんだのは奇跡だ。またまた竿先が跳ね上がったが、この竿の動きからするとアマモでも引っかかっているに違いない。車まで飲み物を取りに行って、ついでに竿を上げたら、実に重い。ゴミでもひっかけたのかなと思ったら、シュークリームのようなものが仕掛けにしがみついていて、わやわやと何かが動いている。えいやっと堤防に跳ね上げたら、やはりシュークリームのような物体で、よくよく見るとクリガニであろうカニである。まあまあ大きい。クリガニが釣れるとは幸先がいい。じっとしていたのでつかまえようとしたら、いきなり横にするすると堤防を走って海に落ちていった。なんてこったい! カニさんカニさん、どこいくんじゃい?緊張感に欠けていたボクは思わず曇り空を見た。 【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】2005年くらいまでは東京都内では手に入らない魚だった。東京都築地市場には来ていたが、年に1度来るか来ないかといった魚で、ボクにとって市場ですれ違ってばかりで幻の魚だった。困っていたら、2002年に動物カメラマンの宮崎学さんが北海道の漁師さんを通じて手に入れてくれた。泣けるほどうれしかった。改めて、学さんにありがとう!その面構えにどこかしら見覚えがあった。まさにそれはゴジラだったのである。ゴジラ映画を初めて見たのは小学校低学年のときで、ゴジラ映画としては2作目の『ゴジラの逆襲』である。続けて1作目を見たときはもっと恐くて、夜眠れなかった。トイレに行こうと、夜空を見上げると、ゴジラがいた気がしてお漏らししたくらいだ。このあまりにも似ている面相から推察するに、たぶんゴジラの着ぐるみを作った人はオオカミウオを知っていたのだと思っている。そうでもなければ、こんなにそっくりなわけがない。ちなみにゴジラを可愛いという人がいるが、オオカミウオだって可愛いと思う人も少なくないという。ちなみに漁師さんに聞くと顔は狼系だけど、性格は猫そのものだという。ただ、怒らせたら凶暴で危険だし手に負えないらしい。オオカミウオは触らぬ神に祟りなし、なのだ。似ている魚にウツボがいるが、こちらはのべつまくなしに凶暴で、のべつまくなしに危険である。
【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、見た目が変なので普通の人にとっては珍魚だったり、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】2005年くらいまでは東京都内では手に入らない魚だった。東京都築地市場には来ていたが、年に1度来るか来ないかといった魚で、ボクにとって市場ですれ違ってばかりで幻の魚だった。困っていたら、2002年に動物カメラマンの宮崎学さんが北海道の漁師さんを通じて手に入れてくれた。泣けるほどうれしかった。改めて、学さんにありがとう!その面構えにどこかしら見覚えがあった。まさにそれはゴジラだったのである。ゴジラ映画を初めて見たのは小学校低学年のときで、ゴジラ映画としては2作目の『ゴジラの逆襲』である。続けて1作目を見たときはもっと恐くて、夜眠れなかった。トイレに行こうと、夜空を見上げると、ゴジラがいた気がしてお漏らししたくらいだ。このあまりにも似ている面相から推察するに、たぶんゴジラの着ぐるみを作った人はオオカミウオを知っていたのだと思っている。そうでもなければ、こんなにそっくりなわけがない。ちなみにゴジラを可愛いという人がいるが、オオカミウオだって可愛いと思う人も少なくないという。ちなみに漁師さんに聞くと顔は狼系だけど、性格は猫そのものだという。ただ、怒らせたら凶暴で危険だし手に負えないらしい。オオカミウオは触らぬ神に祟りなし、なのだ。似ている魚にウツボがいるが、こちらはのべつまくなしに凶暴で、のべつまくなしに危険である。 北海道には何度も行っているが、去年の羅臼旅までセイコーマートのことは知らなかった。昔からあったのかしらん。羽田⇄中標津空港は1日一往復で、中標津着は午後2時前である。ここから根室までは2時間もかかる。旅の日の朝ご飯は食べないのが鉄則なので、現場(目的地)に着いた途端に腹が減る。中途半端な時間なので、おのずと軽い食べ物でもとコンビニに寄ることになる。到着した日だけではない。水産生物を追いかけていると朝が早い。だいたい朝は4時過ぎには浜にいて、クマを気にしながら水揚げを見る。ずーっと立ちっぱなしで、ときどき飛んだり跳ねたり、走ったりする。気になっていることを聞取、初めて見る生き物に興奮し、また聞取をする。終わるのが7時、8時なので、結局、またコンビニ頼りになる。
北海道には何度も行っているが、去年の羅臼旅までセイコーマートのことは知らなかった。昔からあったのかしらん。羽田⇄中標津空港は1日一往復で、中標津着は午後2時前である。ここから根室までは2時間もかかる。旅の日の朝ご飯は食べないのが鉄則なので、現場(目的地)に着いた途端に腹が減る。中途半端な時間なので、おのずと軽い食べ物でもとコンビニに寄ることになる。到着した日だけではない。水産生物を追いかけていると朝が早い。だいたい朝は4時過ぎには浜にいて、クマを気にしながら水揚げを見る。ずーっと立ちっぱなしで、ときどき飛んだり跳ねたり、走ったりする。気になっていることを聞取、初めて見る生き物に興奮し、また聞取をする。終わるのが7時、8時なので、結局、またコンビニ頼りになる。 北海道根室市、根室漁協で漁師さんにいただいた魚を見ていたら、どこかで見たような顔だと思い始めて、そうだ昔の芸人さんじゃないかな、なんて物思いに落ち込む。長い体にほとんど模様がなく、食用魚だとは思ってももらえず、漁師さんには邪険にされ、ただただ笑いを取ることに一生懸命な気がする。魚の顔面はやたらに面白い。
北海道根室市、根室漁協で漁師さんにいただいた魚を見ていたら、どこかで見たような顔だと思い始めて、そうだ昔の芸人さんじゃないかな、なんて物思いに落ち込む。長い体にほとんど模様がなく、食用魚だとは思ってももらえず、漁師さんには邪険にされ、ただただ笑いを取ることに一生懸命な気がする。魚の顔面はやたらに面白い。 今やいたって普通の食用二枚貝となっているイワガキを、もともと食べていた地域は非常に少なかった。なかでも東京都は、もっとも早くからイワガキを食べていた地域にあたる。イワガキの産地、千葉県が東京都最大の水産供給地だったからだ。昔、築地で並んでいるイワガキと言ったら千葉県産か茨城県産だった。それが今や日本各地のイワガキが並んでいる。これがイワガキ好きにはやたらうれしい。中でも目立つのが、手前みそではあるが徳島県産だと思っている。吉野川河口域のもので非常に大型である。徳島県の悲しいところは突出した水産物がとても少ないことだが、イワガキはハモとともに貴重な特産品となっている。今回のものは徳島市内川内町地先で揚がったもの。吉野川本流ではなく旧吉野川(今切川)河口のものではないかと思っている。吉野川が河口域に作り出す平野部には今やレンコン畑が広がっているが、戦国時代には三好氏の本拠地でもあり、本城でもある勝瑞城があった。長宗我部元親が阿波攻略のとき水で苦しんだところでもある。
今やいたって普通の食用二枚貝となっているイワガキを、もともと食べていた地域は非常に少なかった。なかでも東京都は、もっとも早くからイワガキを食べていた地域にあたる。イワガキの産地、千葉県が東京都最大の水産供給地だったからだ。昔、築地で並んでいるイワガキと言ったら千葉県産か茨城県産だった。それが今や日本各地のイワガキが並んでいる。これがイワガキ好きにはやたらうれしい。中でも目立つのが、手前みそではあるが徳島県産だと思っている。吉野川河口域のもので非常に大型である。徳島県の悲しいところは突出した水産物がとても少ないことだが、イワガキはハモとともに貴重な特産品となっている。今回のものは徳島市内川内町地先で揚がったもの。吉野川本流ではなく旧吉野川(今切川)河口のものではないかと思っている。吉野川が河口域に作り出す平野部には今やレンコン畑が広がっているが、戦国時代には三好氏の本拠地でもあり、本城でもある勝瑞城があった。長宗我部元親が阿波攻略のとき水で苦しんだところでもある。 若い頃作っていたのに作らなくなった料理は数知れずある。肝・にんにく入りの「みそたたき(なめろう)」もそうである。ポジフィルムしかなかったときで、デジタルでの撮影を始めてからは作っていない。これをいろんな魚で作ろうと思い立った。初手は、かれこれ40年以上前に作ってみたことのある、「目光の肝入りみそたたき」である。茨城県水戸から那珂湊と車で回り、浜の魚屋でバケツいっぱいの目光(アオメエソ)をいただいた。アイナメとかハマグリ(チョウセンハマグリ)とかのオマケにいただいたくらいなので、昔は本種も未利用魚だったことがわかる。そのときに教わったのは単に「みそたたき」だけど、後に肝やにんにくを入れた濃厚な味わいの虜になる。
若い頃作っていたのに作らなくなった料理は数知れずある。肝・にんにく入りの「みそたたき(なめろう)」もそうである。ポジフィルムしかなかったときで、デジタルでの撮影を始めてからは作っていない。これをいろんな魚で作ろうと思い立った。初手は、かれこれ40年以上前に作ってみたことのある、「目光の肝入りみそたたき」である。茨城県水戸から那珂湊と車で回り、浜の魚屋でバケツいっぱいの目光(アオメエソ)をいただいた。アイナメとかハマグリ(チョウセンハマグリ)とかのオマケにいただいたくらいなので、昔は本種も未利用魚だったことがわかる。そのときに教わったのは単に「みそたたき」だけど、後に肝やにんにくを入れた濃厚な味わいの虜になる。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産には1年を通してマイワシの入荷をみる。豊漁期を迎えているようで、1年で味の落ちる時季は短いようである。4月後半からほんの数日前までいいな、と思えるマイワシがなかった。それが6月も後半になってやっと北海道根室産がやってきた。触ったらここ数ヶ月のものとは別物であった。やっと来た来たピンのマイワシ、だ。都心に出る日だったので、味見用に2尾だけ買ってくる。帰宅して下ろしたら明らかに刺身が最善だと思ったが、本日中に食べられる可能性がない。時間がないので計測だけして頭部を落とし、生殖巣をチェックする。白子も真子もないのを確認して振り塩をする。これを冷蔵庫で寝かせる。都心に出たのに食事も摂らないで帰ってきた。切ないねーと思いながら複雑な話(あくまでも仕事上の)だったので疲れ果てた。シャワーを浴びてふて寝する。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産には1年を通してマイワシの入荷をみる。豊漁期を迎えているようで、1年で味の落ちる時季は短いようである。4月後半からほんの数日前までいいな、と思えるマイワシがなかった。それが6月も後半になってやっと北海道根室産がやってきた。触ったらここ数ヶ月のものとは別物であった。やっと来た来たピンのマイワシ、だ。都心に出る日だったので、味見用に2尾だけ買ってくる。帰宅して下ろしたら明らかに刺身が最善だと思ったが、本日中に食べられる可能性がない。時間がないので計測だけして頭部を落とし、生殖巣をチェックする。白子も真子もないのを確認して振り塩をする。これを冷蔵庫で寝かせる。都心に出たのに食事も摂らないで帰ってきた。切ないねーと思いながら複雑な話(あくまでも仕事上の)だったので疲れ果てた。シャワーを浴びてふて寝する。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの伊豆諸島通いのありがたいところは、関東では手に入らない魚が手に入ることだ。伊豆諸島三宅島や利島周辺に多いのがモンガラカワハギ科の魚と、スズメダイ科、ベラ科の魚である。なかでも取り分け多いのがアカササノハベラである。晩春から夏にかけて旬を迎え、体に厚みが出てくる。体長20cmほどの小魚で、おちょぼ口で乱ぐい歯なので普通はハリス10号、シマアジ用の針で釣り上げられるはずがない。それを釣り上げてくるのがクマゴロウの名人芸なのだ。さて、瀬戸内海あたりにいくと主にキュウセンだが、焼いたものがスーパーなどで売っている。見つけたら必ず買ってくるといったものだが、なかなか関東では手に入らない。釣り上げてくるたびこっそり持ち帰って、キュウセンの代わりに焼いている。最近、思うにキュウセンよりも身に厚みがあっておいしいかも。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの伊豆諸島通いのありがたいところは、関東では手に入らない魚が手に入ることだ。伊豆諸島三宅島や利島周辺に多いのがモンガラカワハギ科の魚と、スズメダイ科、ベラ科の魚である。なかでも取り分け多いのがアカササノハベラである。晩春から夏にかけて旬を迎え、体に厚みが出てくる。体長20cmほどの小魚で、おちょぼ口で乱ぐい歯なので普通はハリス10号、シマアジ用の針で釣り上げられるはずがない。それを釣り上げてくるのがクマゴロウの名人芸なのだ。さて、瀬戸内海あたりにいくと主にキュウセンだが、焼いたものがスーパーなどで売っている。見つけたら必ず買ってくるといったものだが、なかなか関東では手に入らない。釣り上げてくるたびこっそり持ち帰って、キュウセンの代わりに焼いている。最近、思うにキュウセンよりも身に厚みがあっておいしいかも。 関東の醤油醸造は17世紀に銚子で初まり、土浦(土屋家で、茨城県土浦市)でも作られる。この時代、江戸のハイウェーである利根川、江戸川、新川、小名木川が機能し始めていたときである。一代目、市川段十郎(後に團十郎 1660-1704)は両親の里である成田まで、このハイウェーを利用して日本橋、行徳、松戸、関宿、佐原まで舟運で行く。銚子、土浦の醤油もこれとは反対だけど輸送経路は変わらない。ただしこの時代、利根川と江戸川には難所があった。関宿である。室町時代かずかずの戦乱の場となった地ではあるが、川砂がたまりやすく舟運に支障が出た。次ぎに醤油の産地となったのが関宿を通らなくても済む、江戸川沿いの野田である。豊かな水があり、関東で作られた大豆と醤油を集めるのもたやすかった。今や国内随一の醤油の産地だ。この利根川、江戸川で盛んに作られた醤油と流山市のみりんが江戸前ウナギを完成に導いたのだ。こんなことを思いながら野田の町を歩き、せっかくなので蒲鉾店のオネエサンに教わった町ウナギで贅沢をする。「有名じゃないと思いますけど」というのでゆっくり昼過ぎに行ったらテーブル席はいっぱいだった。座敷に上がり、まずはノンアルコールビールと「コイの洗い」をお願いする。関東平野のウナギ屋の特徴は必ず「コイの洗い」があること。またざっこ煮(煮ざっこ)があることも特徴である。久しぶりのコイの洗いがやたらにうまい。
関東の醤油醸造は17世紀に銚子で初まり、土浦(土屋家で、茨城県土浦市)でも作られる。この時代、江戸のハイウェーである利根川、江戸川、新川、小名木川が機能し始めていたときである。一代目、市川段十郎(後に團十郎 1660-1704)は両親の里である成田まで、このハイウェーを利用して日本橋、行徳、松戸、関宿、佐原まで舟運で行く。銚子、土浦の醤油もこれとは反対だけど輸送経路は変わらない。ただしこの時代、利根川と江戸川には難所があった。関宿である。室町時代かずかずの戦乱の場となった地ではあるが、川砂がたまりやすく舟運に支障が出た。次ぎに醤油の産地となったのが関宿を通らなくても済む、江戸川沿いの野田である。豊かな水があり、関東で作られた大豆と醤油を集めるのもたやすかった。今や国内随一の醤油の産地だ。この利根川、江戸川で盛んに作られた醤油と流山市のみりんが江戸前ウナギを完成に導いたのだ。こんなことを思いながら野田の町を歩き、せっかくなので蒲鉾店のオネエサンに教わった町ウナギで贅沢をする。「有名じゃないと思いますけど」というのでゆっくり昼過ぎに行ったらテーブル席はいっぱいだった。座敷に上がり、まずはノンアルコールビールと「コイの洗い」をお願いする。関東平野のウナギ屋の特徴は必ず「コイの洗い」があること。またざっこ煮(煮ざっこ)があることも特徴である。久しぶりのコイの洗いがやたらにうまい。 専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。きっとこれはボクにとってもいい傾向だろう。この日は朝、同定不能の巻き貝があり息苦しいばかりで、救いがなかった。まことに生き物の同定は難しい。朝ご飯は、なんと1時過ぎなので、昼ご飯かも。ご飯、イサキの塩焼き、イサキの漬け、モロッコインゲンと油揚げ、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬け、ブルーベリー。モロッコインゲンと油揚げ。こんなもの説明不要だと思うけど、八王子綜合卸売センター八百角でみつけた、今季いちばんのモロッコインゲンを煮干し出しで煮つけたもの。千葉県野田市、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬けは近年稀に見る名品でもっと買って来ればよかった。イサキは八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げたもので、釣り上げて3日目。この日の刺身がいちばん味があった。刺身溜まりをかけ、青唐辛子を刻み、ごまをかけた。ご飯の甘味よりもイサキのうま味と脂が勝っていた。塩焼きは言うまでもなくウマシ。ワカメと豆腐のみそ汁は省略。
専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。きっとこれはボクにとってもいい傾向だろう。この日は朝、同定不能の巻き貝があり息苦しいばかりで、救いがなかった。まことに生き物の同定は難しい。朝ご飯は、なんと1時過ぎなので、昼ご飯かも。ご飯、イサキの塩焼き、イサキの漬け、モロッコインゲンと油揚げ、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬け、ブルーベリー。モロッコインゲンと油揚げ。こんなもの説明不要だと思うけど、八王子綜合卸売センター八百角でみつけた、今季いちばんのモロッコインゲンを煮干し出しで煮つけたもの。千葉県野田市、坂倉味噌醤油本店のしょうがのみそ漬けは近年稀に見る名品でもっと買って来ればよかった。イサキは八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げたもので、釣り上げて3日目。この日の刺身がいちばん味があった。刺身溜まりをかけ、青唐辛子を刻み、ごまをかけた。ご飯の甘味よりもイサキのうま味と脂が勝っていた。塩焼きは言うまでもなくウマシ。ワカメと豆腐のみそ汁は省略。 去年あたりから、信じられないくらい高騰してしまったのが真ツブ(エゾボラ)である。中国のせいだという人がいるが、水産物の輸出はしていないのではなかったか? それにしても大きなものは1個1万円以上、小さくても3千円くらいするととても手が出なかった。ふと、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の貝の場所を見たら、もとの値近くにもどっていた。あの暴騰は終わったのかも知れない。かねてより作ってみたかったものがあるので1個だけ買ってきた。真ツブ(Aツブとも)はエゾバイ科エゾボラ属の巻き貝で、足の部分(刺身などで食べる)にテトラミンという毒を持っているのが特徴である。そんなに強い毒ではなく、北海道何カ所かで食べていた人の話を聞いても、酒に酔った気分になるだけだという。ボクも数個食べているが、ほんの少しいい気分になっただけだ。まあ個人差があるので要注意。主に北半球の冷水域にいる。巻き貝の中でも大型であり、1㎏近いものもある。
去年あたりから、信じられないくらい高騰してしまったのが真ツブ(エゾボラ)である。中国のせいだという人がいるが、水産物の輸出はしていないのではなかったか? それにしても大きなものは1個1万円以上、小さくても3千円くらいするととても手が出なかった。ふと、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の貝の場所を見たら、もとの値近くにもどっていた。あの暴騰は終わったのかも知れない。かねてより作ってみたかったものがあるので1個だけ買ってきた。真ツブ(Aツブとも)はエゾバイ科エゾボラ属の巻き貝で、足の部分(刺身などで食べる)にテトラミンという毒を持っているのが特徴である。そんなに強い毒ではなく、北海道何カ所かで食べていた人の話を聞いても、酒に酔った気分になるだけだという。ボクも数個食べているが、ほんの少しいい気分になっただけだ。まあ個人差があるので要注意。主に北半球の冷水域にいる。巻き貝の中でも大型であり、1㎏近いものもある。 【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、普通の人にとっては珍魚、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】梅雨入り間近のある日、福岡県北九州市小倉の市場で小学校低学年くらいの男子が顔を近づけて、ある魚をなめるように見ていた。言わなきゃいいのに、「ヒゲがあるよね」と無駄な親切心で教えてあげたのだ。小学生は、「ヒゲなの?(意訳)」とボクを指さして聞いたのだ。これはヒゲなんだろうか?ボクはそのとき長旅でヒゲぼうぼうの情けない顔をしていた。うまく説明できなかった。
【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、普通の人にとっては珍魚、何気なく見ていると普通だけど、よくよく見ると変というのを「隣の珍魚」という。】梅雨入り間近のある日、福岡県北九州市小倉の市場で小学校低学年くらいの男子が顔を近づけて、ある魚をなめるように見ていた。言わなきゃいいのに、「ヒゲがあるよね」と無駄な親切心で教えてあげたのだ。小学生は、「ヒゲなの?(意訳)」とボクを指さして聞いたのだ。これはヒゲなんだろうか?ボクはそのとき長旅でヒゲぼうぼうの情けない顔をしていた。うまく説明できなかった。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。余談だが関東でマルソウダは安すぎる。もっと鮮魚で利用して欲しいものだ。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。余談だが関東でマルソウダは安すぎる。もっと鮮魚で利用して欲しいものだ。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。以上はなんども書いている。そのとき60g前後のゴッソリ(イサキ)をたくさん連れ帰って来て、いろいろ作ったが、おおかたは千葉県外房風の「みそたたき」にした。いちどにたくさん作り、器に盛り込んでは酢をかけまわして食べた。千葉県で「なめろう」を初めて食べたのは千倉港周辺の食堂のようなところだ。ビールを頼んだら一緒にきたのだけど、注文した記憶がない。マアジとか小型のイサキ、磯のムツ(ムツの若い個体)で作ったといわれ、最初から酢が回しかけていた。この魚を細かく包丁でみそとたたいたものは、三陸以南の太平洋側に広く分布しているが、酢を使うのは千葉県だけだと思っている。「なめろう」は千葉県固有の料理名ではないが、取り分け酢をかけたものを、外房風「なめろう」と言うことにしている。最近、イサキを近所のスーパーで買ったり、もらったりで何度か「なめろう」作っているが、このようなものを作るきっかけが前回の小田原のゴッソリである。これから小田原だけではなく、日本各地がこの小イサキの津波に襲われると思う。あまりの量に出荷不能になり、飼料になってしまうことが多いのは小田原だけの話ではない。食べたらビックリのうまさなのに、人の口に入らない。なんとももったいない話である。 【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、普通の人にとっては珍魚、というのを「隣の珍魚」という。】6月になり鹿児島県からやって来ているギンカガミなどもその最たるものだろう。「なんだこれ?」と思わないのは魚類学者だけだと思う。本当の珍魚というのは定置網などに数年に1度とか、年に1度とかしか入らないものだけど、こいつはとれ始めるとやたらにとれる。円盤投げの円盤のような形なので意外に扱いにくい。非常に薄いため食べるところがびっくりするほど少ない。安い上に扱いにくいので漁師さんにたいそう嫌われている。
【学者などにとってはちっとも珍魚ではないし、超深海や、南北両極にいるわけでもない。魚屋でもスーパーでもときどき見かける魚だが、普通の人にとっては珍魚、というのを「隣の珍魚」という。】6月になり鹿児島県からやって来ているギンカガミなどもその最たるものだろう。「なんだこれ?」と思わないのは魚類学者だけだと思う。本当の珍魚というのは定置網などに数年に1度とか、年に1度とかしか入らないものだけど、こいつはとれ始めるとやたらにとれる。円盤投げの円盤のような形なので意外に扱いにくい。非常に薄いため食べるところがびっくりするほど少ない。安い上に扱いにくいので漁師さんにたいそう嫌われている。 専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。それにしても撮影する場合に同じような料理を、一時に作るので塩焼きの時には塩焼きが2、3つ。煮つけのときには煮つけが2、3つ並ぶことがわかってきた。でもサイト運営が最優先なので仕方がない。ご飯と福神漬け以外は海産物である。淡竹とカツオ生利節の煮つけ。今季初の淡竹となまり節をたいたもので、言うなれば定番料理そのもの。カツオ血合いだんごとナスの煮つけ。カツオの血合いはざまざまに使えておいしいものだが、今回は野菜とたくのでだんごにした。うま味が豊かでご飯に合う。ところてん、ハギ子は八王子綜合卸売センター、福泉で買ったもの。ハギ子はカワハギの卵巣だと思うが産地不明である。ところてん。マクサを使った上物でとてもおいしかった。ハギ子煮つけはまだ卵粒が小さく、きめ細やかで煮つけにして絶品。ワカメと豆腐のみそ汁。説明不要だと思う。三重県産青のりの佃煮。都内茅場町、木村海草店で買った物で上等だった。
専門家に自分が食べたものを書き出しなさいと言われて、並べて撮影している内に面白くなってきたし、バランスを考えるようになってきた。それにしても撮影する場合に同じような料理を、一時に作るので塩焼きの時には塩焼きが2、3つ。煮つけのときには煮つけが2、3つ並ぶことがわかってきた。でもサイト運営が最優先なので仕方がない。ご飯と福神漬け以外は海産物である。淡竹とカツオ生利節の煮つけ。今季初の淡竹となまり節をたいたもので、言うなれば定番料理そのもの。カツオ血合いだんごとナスの煮つけ。カツオの血合いはざまざまに使えておいしいものだが、今回は野菜とたくのでだんごにした。うま味が豊かでご飯に合う。ところてん、ハギ子は八王子綜合卸売センター、福泉で買ったもの。ハギ子はカワハギの卵巣だと思うが産地不明である。ところてん。マクサを使った上物でとてもおいしかった。ハギ子煮つけはまだ卵粒が小さく、きめ細やかで煮つけにして絶品。ワカメと豆腐のみそ汁。説明不要だと思う。三重県産青のりの佃煮。都内茅場町、木村海草店で買った物で上等だった。 千葉県や近所のスーパーにシイラが並んでいる。不安定ではあるが、シイラは普通の食用魚となっている。我が家の近所のスーパーなどではシイラとあって、隣に大きな文字でマヒマヒと書いてある。最近、シイラよりもマヒマヒなのかも知れない。富山県、新潟県や山形県では秋の風物詩だ。沖合いで揚がるのでさかんに刺身で食べる。今でも山間部でよく食べられている魚でもある。これは大型魚で山間部に持ち込んで切り身にして大量に売れたからだ。無塩ものが珍しい山間部ではこれほど喜ばれたものはない。マサバ並みに鮮度落ちが早いので生で食べることには気を配らなければならないが、煮ても焼いてもソテーしてもこんなにうまい魚はないと思っている。もっと大きな都市部の消費地でも安いのだから食べるべきである。余談だが近所のスーパー、山梨県、千葉県のスーパーで切り身を100g、130円前後で売っていた。魚価が上昇しているので非常にお買い得である。切り身でつけ焼きにし、照焼にして、ムニエルにした。
千葉県や近所のスーパーにシイラが並んでいる。不安定ではあるが、シイラは普通の食用魚となっている。我が家の近所のスーパーなどではシイラとあって、隣に大きな文字でマヒマヒと書いてある。最近、シイラよりもマヒマヒなのかも知れない。富山県、新潟県や山形県では秋の風物詩だ。沖合いで揚がるのでさかんに刺身で食べる。今でも山間部でよく食べられている魚でもある。これは大型魚で山間部に持ち込んで切り身にして大量に売れたからだ。無塩ものが珍しい山間部ではこれほど喜ばれたものはない。マサバ並みに鮮度落ちが早いので生で食べることには気を配らなければならないが、煮ても焼いてもソテーしてもこんなにうまい魚はないと思っている。もっと大きな都市部の消費地でも安いのだから食べるべきである。余談だが近所のスーパー、山梨県、千葉県のスーパーで切り身を100g、130円前後で売っていた。魚価が上昇しているので非常にお買い得である。切り身でつけ焼きにし、照焼にして、ムニエルにした。 細谷紙店は八王子綜合卸売センターにも店を持つが、実は釣具の便利な釣り用の袋も作って売っている。その名を、『細谷紙店 恵比寿さまの大漁袋』という。ある朝のこと、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の釣り名人、クマゴロウが台車にクーラーを乗せて歩いて行く。勝手に開けて見ると『細谷紙店 恵比寿さまの大漁袋』の中にいい型のマアジが入っていて、1尾だけ外に出ていた。当然、釣り上げたのは恵比寿様でありんす。あああ、ボクのための1尾だな、と思って連れ帰ってきた。もう少し大きいのがいいと思ったけど、勝手に持って来たので文句は言えない。たぶん東京湾横浜沖で釣り上げたものだろう。小アジは体長20cm・126gなので、小さいことは小さいけど、身に張りがあり、つかんだらぬるっとする。いいマアジの条件を全部兼ね備えているではないか。日本各地にブランドアジがあるが、東京都に住んでいる人間には、近場の東京湾、三浦半島、相模湾の地物の方が上なのである。さてさて、こう言った拾いものがあるのも市場のいいところなのだ。この人情味溢れる市場には来なきゃそんそん♪ といいたい。ついでに恵比寿様ありがと。
細谷紙店は八王子綜合卸売センターにも店を持つが、実は釣具の便利な釣り用の袋も作って売っている。その名を、『細谷紙店 恵比寿さまの大漁袋』という。ある朝のこと、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産の釣り名人、クマゴロウが台車にクーラーを乗せて歩いて行く。勝手に開けて見ると『細谷紙店 恵比寿さまの大漁袋』の中にいい型のマアジが入っていて、1尾だけ外に出ていた。当然、釣り上げたのは恵比寿様でありんす。あああ、ボクのための1尾だな、と思って連れ帰ってきた。もう少し大きいのがいいと思ったけど、勝手に持って来たので文句は言えない。たぶん東京湾横浜沖で釣り上げたものだろう。小アジは体長20cm・126gなので、小さいことは小さいけど、身に張りがあり、つかんだらぬるっとする。いいマアジの条件を全部兼ね備えているではないか。日本各地にブランドアジがあるが、東京都に住んでいる人間には、近場の東京湾、三浦半島、相模湾の地物の方が上なのである。さてさて、こう言った拾いものがあるのも市場のいいところなのだ。この人情味溢れる市場には来なきゃそんそん♪ といいたい。ついでに恵比寿様ありがと。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、1.4kgの長崎産クエを買い求めた。クエは10kg前後から断然うまくなると思うけど、懐具合が許さない。下ろしてみると生殖巣が非常に小さい。今回の個体は成熟(3歳)以前かも知れない。成熟個体は産卵後の夏に味が短期間であるが落ちるが、未成熟個体は年間を通して味がいい。我がサイトでは、一定期間をおいて形態画像を撮っているので、今回はそのためだけの買いである。長崎県の個体は扱いが手慣れているのか、とてもきれいだった。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、1.4kgの長崎産クエを買い求めた。クエは10kg前後から断然うまくなると思うけど、懐具合が許さない。下ろしてみると生殖巣が非常に小さい。今回の個体は成熟(3歳)以前かも知れない。成熟個体は産卵後の夏に味が短期間であるが落ちるが、未成熟個体は年間を通して味がいい。我がサイトでは、一定期間をおいて形態画像を撮っているので、今回はそのためだけの買いである。長崎県の個体は扱いが手慣れているのか、とてもきれいだった。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。この小型の魚の大部分は直接人間の口に入らないという点で未利用魚である。ちなみに未利用魚という言語は曖昧すぎる。こんな曖昧な定義では未利用魚の活用は推進できない。選別すれば売れなくはない。これをなんとか選別できないかと考える人は漁業を知らないか、もしくは斬新なアイデアをもっている人かだ。ていねいに選別してもお金にならないし、過重労働を漁師に強いることになる。国はコンクリートよりも人にお金を使っていかなければならない。さて、体長10cm前後で、ウルメイワシ、カタクチイワシ、マイワシ、+タカベだった。タカベは二宮定置の若い衆がちょんと投げてくれたものだ。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置はたいへんだった。水揚げされた魚にたくさんのマイワシの破片が混ざっており、しかも小型の魚がわんさかあった。この小型の魚の大部分は直接人間の口に入らないという点で未利用魚である。ちなみに未利用魚という言語は曖昧すぎる。こんな曖昧な定義では未利用魚の活用は推進できない。選別すれば売れなくはない。これをなんとか選別できないかと考える人は漁業を知らないか、もしくは斬新なアイデアをもっている人かだ。ていねいに選別してもお金にならないし、過重労働を漁師に強いることになる。国はコンクリートよりも人にお金を使っていかなければならない。さて、体長10cm前後で、ウルメイワシ、カタクチイワシ、マイワシ、+タカベだった。タカベは二宮定置の若い衆がちょんと投げてくれたものだ。 5月後半になり、八王子の市場にも、また近所のスーパーにも「ぜんな(チョウセンハマグリの小型)」が並んでいる。チョウセンハマグリは千葉県では重要な二枚貝である。内房のアサリがやや低調なので漁獲規制が厳格なはずである。きっと小型をとる理由があるのだろう。なんども書いているが、朝鮮蛤は江戸時代後期に生まれた名で、この言葉に知識人の憧れの気持ちはあっても差別意識はない。「身近な」に対して「遠い」という意味がある。江戸時代から江戸前、江戸湾にいるのが標準和名ハマグリで、外洋に面した九十九里や外房でとれたのがチョウセンハマグリだ。輸送に強い二枚貝なので、九十九里で揚がると銚子を経て日本橋にある魚河岸まで運ばれていたはずだ。同じような例は内湾生のアカガイと外洋性のサトウガイにも当てはまる。昔は内湾生のハマグリを「本」、外洋性の本種などを「ばち(場違)」として、「本」と比べて安かったが、最近、二枚貝は大きさで価格が決まるので、本種は決して安くない。逆転現象も起きている。今回、朝ご飯のために八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で2握り買ってきた。
5月後半になり、八王子の市場にも、また近所のスーパーにも「ぜんな(チョウセンハマグリの小型)」が並んでいる。チョウセンハマグリは千葉県では重要な二枚貝である。内房のアサリがやや低調なので漁獲規制が厳格なはずである。きっと小型をとる理由があるのだろう。なんども書いているが、朝鮮蛤は江戸時代後期に生まれた名で、この言葉に知識人の憧れの気持ちはあっても差別意識はない。「身近な」に対して「遠い」という意味がある。江戸時代から江戸前、江戸湾にいるのが標準和名ハマグリで、外洋に面した九十九里や外房でとれたのがチョウセンハマグリだ。輸送に強い二枚貝なので、九十九里で揚がると銚子を経て日本橋にある魚河岸まで運ばれていたはずだ。同じような例は内湾生のアカガイと外洋性のサトウガイにも当てはまる。昔は内湾生のハマグリを「本」、外洋性の本種などを「ばち(場違)」として、「本」と比べて安かったが、最近、二枚貝は大きさで価格が決まるので、本種は決して安くない。逆転現象も起きている。今回、朝ご飯のために八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で2握り買ってきた。 八王子綜合卸売センター、『福泉』で三陸産湯通し塩蔵ワカメ(マルヤわかめ 愛知県豊橋市)を買う。非常にいいもので、買い足しをするほどだった。湯通し塩蔵ワカメのいいところは、水で塩を洗い流すだけでそのまま食べられることだ。最近の水に直接入れるだけで使えるワカメと比べ、ワカメ本来の食感、味がよりちゃんとわかる。梅雨も来ない内に7月後半の暑さが襲ってきている。夏がくると想い出す、子供の頃のことと、「きゅうりもみ」と、なのだ。子供の頃には存在理由がわからなかった「きゅうりもみ」が、今や欠かせぬものとなっている。その基本的なものがワカメとキュウリである。イカや酢で締めた魚などを使うのもいいし、竹輪で作ってもいい。いろいろ変化を望めるのも「きゅうりもみ」のよさである。今回の主役、湯通し塩蔵ワカメ以外で作るときはキュウリを薄く切り、やや強めの塩をする。水分が出て来たら流水でもみ洗いながら余分な塩気を流す。この塩加減と塩の洗い流し加減がおいしさを大きく左右する。最近のキュウリは苦味や青臭さがないので、塩してもむだけでもいい。主役のキュウリに脇役はいろんなものを使えるのがいい。もちろん主役脇役が判然としない点も魅力だろう。
八王子綜合卸売センター、『福泉』で三陸産湯通し塩蔵ワカメ(マルヤわかめ 愛知県豊橋市)を買う。非常にいいもので、買い足しをするほどだった。湯通し塩蔵ワカメのいいところは、水で塩を洗い流すだけでそのまま食べられることだ。最近の水に直接入れるだけで使えるワカメと比べ、ワカメ本来の食感、味がよりちゃんとわかる。梅雨も来ない内に7月後半の暑さが襲ってきている。夏がくると想い出す、子供の頃のことと、「きゅうりもみ」と、なのだ。子供の頃には存在理由がわからなかった「きゅうりもみ」が、今や欠かせぬものとなっている。その基本的なものがワカメとキュウリである。イカや酢で締めた魚などを使うのもいいし、竹輪で作ってもいい。いろいろ変化を望めるのも「きゅうりもみ」のよさである。今回の主役、湯通し塩蔵ワカメ以外で作るときはキュウリを薄く切り、やや強めの塩をする。水分が出て来たら流水でもみ洗いながら余分な塩気を流す。この塩加減と塩の洗い流し加減がおいしさを大きく左右する。最近のキュウリは苦味や青臭さがないので、塩してもむだけでもいい。主役のキュウリに脇役はいろんなものを使えるのがいい。もちろん主役脇役が判然としない点も魅力だろう。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。以上は以前書いた。さて、もらった目的は塩ゆでにしたいためだ。高知県で「ゆで節」、「煮節」などという。ボクの作り方は高知県中土佐町久礼の魚屋さんで教わったやり方である。作り方は非常に単純。今回は片身の血合い・腹骨周り・中骨、と片身を煮立った塩水の中で約8分くらいゆでる。完全に火を通すのがコツだ。久礼の人は一生懸命団扇で扇いで粗熱を取っていたという。ボクは扇風機で楽にやる。これを袋などに入れて冷蔵庫で完全に冷やし込む。煮節(塩ゆで)の完成である。カツオ節の工場などで作るなまり節とは別物で、もっと遙かに惣菜的なものだ。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えたマルソウダがたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ(マルソウダ)」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。以上は以前書いた。さて、もらった目的は塩ゆでにしたいためだ。高知県で「ゆで節」、「煮節」などという。ボクの作り方は高知県中土佐町久礼の魚屋さんで教わったやり方である。作り方は非常に単純。今回は片身の血合い・腹骨周り・中骨、と片身を煮立った塩水の中で約8分くらいゆでる。完全に火を通すのがコツだ。久礼の人は一生懸命団扇で扇いで粗熱を取っていたという。ボクは扇風機で楽にやる。これを袋などに入れて冷蔵庫で完全に冷やし込む。煮節(塩ゆで)の完成である。カツオ節の工場などで作るなまり節とは別物で、もっと遙かに惣菜的なものだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げたキビレカワハギをくれた。ありがとう。2020年くらいまでは、見つけただけでヤッホーと飛び上がっていたのに、今やアリガト程度のうれしさでしかない。最近では相模湾北部でもときどき揚がるので、感動が薄くなっているのだ。ちなみに1970年代までウマヅラハギも相模湾にはほとんどいなかったらしい。ウマヅラハギの大群がいきなり押し寄せて伊豆半島網代に干もの街道ができたのと比べると、キビレカワハギはじわじわと増えてきているといった感じがする。ウマヅラハギの突然の大量の説明はつかないが、キビレカワハギは明らかに水温の上昇による。ちなみにキビレカワハギは1979年まで国内海域で発見されていなかった。ただし発見海域が小笠原なので、これは未知の海域で、未知の魚を発見しただけだろう。銭州は伊豆諸島神津島の南西にある。小笠原と銭州は、東京と鹿児島くらいの距離離れている。また最近キビレハギが揚がる相模湾北部にまで北上していることからして、距離で水温を測るのも変だが、45年ほどで急激に海水温が上昇しているのが目に見える。さて本種の旬はよくわからない。珍しくなくなったと言っても写真撮影したのは26個体でしかない。やはりいまだに珍しい魚のひとつではある。この珍魚ではないが入手困難な魚の位置づけが難しい。体長32cm・753gなので比較的大きな個体である。皮を剥いた時点で上物とわかる。カワハギ科の魚はそんなに目立って脂がのらないが、身に張りがあり、身にうま味が増す時季がある。今のところ、旬と言えるのは初夏ではないかと考えているが、まだまだ食べた個体数が少なすぎる。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げたキビレカワハギをくれた。ありがとう。2020年くらいまでは、見つけただけでヤッホーと飛び上がっていたのに、今やアリガト程度のうれしさでしかない。最近では相模湾北部でもときどき揚がるので、感動が薄くなっているのだ。ちなみに1970年代までウマヅラハギも相模湾にはほとんどいなかったらしい。ウマヅラハギの大群がいきなり押し寄せて伊豆半島網代に干もの街道ができたのと比べると、キビレカワハギはじわじわと増えてきているといった感じがする。ウマヅラハギの突然の大量の説明はつかないが、キビレカワハギは明らかに水温の上昇による。ちなみにキビレカワハギは1979年まで国内海域で発見されていなかった。ただし発見海域が小笠原なので、これは未知の海域で、未知の魚を発見しただけだろう。銭州は伊豆諸島神津島の南西にある。小笠原と銭州は、東京と鹿児島くらいの距離離れている。また最近キビレハギが揚がる相模湾北部にまで北上していることからして、距離で水温を測るのも変だが、45年ほどで急激に海水温が上昇しているのが目に見える。さて本種の旬はよくわからない。珍しくなくなったと言っても写真撮影したのは26個体でしかない。やはりいまだに珍しい魚のひとつではある。この珍魚ではないが入手困難な魚の位置づけが難しい。体長32cm・753gなので比較的大きな個体である。皮を剥いた時点で上物とわかる。カワハギ科の魚はそんなに目立って脂がのらないが、身に張りがあり、身にうま味が増す時季がある。今のところ、旬と言えるのは初夏ではないかと考えているが、まだまだ食べた個体数が少なすぎる。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にクロマグロの血合いぎしをもらって塩マグロを作った。4月23日に塩に漬け込んで出来上がりは5月5日だった。東京都八王子市西八王子、『魚善』さんに教わったもので、魚屋の作る保存食である。少しずつ切り取っては焼いて茶漬けにし、サラダなどにも使った。いくつかの仕事をやって日々の糧を得ているので、慌ただしいときはご飯を作る暇もない。こんな朝は残り物を整理しがてら料理を作る。その残り物を調理する主役に塩マグロを据える。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にクロマグロの血合いぎしをもらって塩マグロを作った。4月23日に塩に漬け込んで出来上がりは5月5日だった。東京都八王子市西八王子、『魚善』さんに教わったもので、魚屋の作る保存食である。少しずつ切り取っては焼いて茶漬けにし、サラダなどにも使った。いくつかの仕事をやって日々の糧を得ているので、慌ただしいときはご飯を作る暇もない。こんな朝は残り物を整理しがてら料理を作る。その残り物を調理する主役に塩マグロを据える。 6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えた「ウズワ(マルソウダ)」がたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。ボクはマルソウダがやたらに好きだ。愛していると言ってもいいだろう。こーんなにうまい魚が他にあるだろうか? と思う事さえある。ちなみに日本全国を見渡しても、高知県以外では安い魚の代表格である。高知県だって、「新子」と呼ばれる秋の若い個体だけが高い。ただ、高知県久礼のオバチャン曰く、「味があるでよ」はまさにまさに言い得て妙なのだ。実にうま味豊かすぎる魚である。若い個体は生で食べるけど、成魚は食べないという地域が多い。このあたりが難しい。若い個体ですら血合いは避けて刺身にする。今回の個体は34.5cm・559g なのでマルソウダのベストサイズであるが、成魚であることに変わりない。ちなみにマルソウダの旬はわかりにくい。6月は産卵前で丸々と太っていて、明らかに旬ではあるが、少し先になると成熟が進みすぎて水っぽくなる。秋になり水温が下がり始めるとまた脂が乗ってきて身に張りが出るが、漁が不安定になる。
6月7日早朝、神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、日渉丸、ワタルさんのところに丸々とよう肥えた「ウズワ(マルソウダ)」がたくさん水揚げされていた。ワタルサンの前をうろうろしてたら、「なんだ?」というので、目を「ウズワ」の上に泳がせたら、「欲しいなら欲しいとちゃんと言いなさい」と言われたので破顔、早速もらってきた。ありがとう、ワタルさん。ボクはマルソウダがやたらに好きだ。愛していると言ってもいいだろう。こーんなにうまい魚が他にあるだろうか? と思う事さえある。ちなみに日本全国を見渡しても、高知県以外では安い魚の代表格である。高知県だって、「新子」と呼ばれる秋の若い個体だけが高い。ただ、高知県久礼のオバチャン曰く、「味があるでよ」はまさにまさに言い得て妙なのだ。実にうま味豊かすぎる魚である。若い個体は生で食べるけど、成魚は食べないという地域が多い。このあたりが難しい。若い個体ですら血合いは避けて刺身にする。今回の個体は34.5cm・559g なのでマルソウダのベストサイズであるが、成魚であることに変わりない。ちなみにマルソウダの旬はわかりにくい。6月は産卵前で丸々と太っていて、明らかに旬ではあるが、少し先になると成熟が進みすぎて水っぽくなる。秋になり水温が下がり始めるとまた脂が乗ってきて身に張りが出るが、漁が不安定になる。 世の中には腹の立つことが多すぎる。中でも大げさな表現をするヤツは嫌いである。内臓を食べなければ問題ないはずのソウシハギを猛毒魚と言ったり、サメが全部人食いだとばかり驚いたり。日本列島にも危険なサメもいると思うけど、非常に少数派だし、地球上でのサメの被害なんて水俣病など公害の被害と比べると耳垢程度でしかない。むしろ日々の糧として活用されていることの方が多いのだ。はっきりいいたい、サメはうまい! 近いうちにエネルギーの大量消費時代は終わるし、食べ物を資本主義の考え方で流通させる時代は終わると思う。サメはもちろん資源の保全をしながらだけど、ちゃんと食べていかなければならぬ時代が目の前に来ているのだ。売名行為や視聴率獲得のためにサメを悪者扱いするな!サメをジョーズ化するな、といいたい。さて、日本全国のスーパーめぐりをしながらサメ食について調べている。東京都など、ほんの四半世紀前までは国内でももっともサメ(ネズミザメ)を食べていたところなのである。関東で言えば栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県と敗戦直後などサメの配給分配が行われていたくらいだ。新潟県上越市、長野県、岐阜県など全国各地で食べられていた。国内のサメ食には「ゆでる地域」と「煮つける地域」、少ないながら「生食する地域」に分かれる。山梨県はネズミザメとアブラツノザメ流通圏なので「煮つける地域」に当たる。久しぶりに山梨でスーパー巡りをしてきて、北杜市白州のスーパーに「もろ(ネズミザメ)」の切り身があった。今現在急激な魚価の高騰の中にあって、非常に安く売られていた。サメは食べたらわかることだけどとてもうまいし、値段からして庶民の味方、ナウシカである。
世の中には腹の立つことが多すぎる。中でも大げさな表現をするヤツは嫌いである。内臓を食べなければ問題ないはずのソウシハギを猛毒魚と言ったり、サメが全部人食いだとばかり驚いたり。日本列島にも危険なサメもいると思うけど、非常に少数派だし、地球上でのサメの被害なんて水俣病など公害の被害と比べると耳垢程度でしかない。むしろ日々の糧として活用されていることの方が多いのだ。はっきりいいたい、サメはうまい! 近いうちにエネルギーの大量消費時代は終わるし、食べ物を資本主義の考え方で流通させる時代は終わると思う。サメはもちろん資源の保全をしながらだけど、ちゃんと食べていかなければならぬ時代が目の前に来ているのだ。売名行為や視聴率獲得のためにサメを悪者扱いするな!サメをジョーズ化するな、といいたい。さて、日本全国のスーパーめぐりをしながらサメ食について調べている。東京都など、ほんの四半世紀前までは国内でももっともサメ(ネズミザメ)を食べていたところなのである。関東で言えば栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県と敗戦直後などサメの配給分配が行われていたくらいだ。新潟県上越市、長野県、岐阜県など全国各地で食べられていた。国内のサメ食には「ゆでる地域」と「煮つける地域」、少ないながら「生食する地域」に分かれる。山梨県はネズミザメとアブラツノザメ流通圏なので「煮つける地域」に当たる。久しぶりに山梨でスーパー巡りをしてきて、北杜市白州のスーパーに「もろ(ネズミザメ)」の切り身があった。今現在急激な魚価の高騰の中にあって、非常に安く売られていた。サメは食べたらわかることだけどとてもうまいし、値段からして庶民の味方、ナウシカである。 八王子綜合卸売センター、『福泉』にBツブが来ている。噴火湾で揚がった典型的なエゾボラモドキである。この流通名と標準和名が違う点がこの刺身用の巻き貝を難しくしている。流通上はBツブだけど、北海道オホーツク海では真ツブなのだからやっかいである。「A、B」と、「真ツブ、真ツブ以外」という、2つの考え方があるのも混乱の原因だ。記載者のGeorge Brettingham Sowerby III は19世紀から20世紀にかけて活躍したイギリスの動物学者でありイラストレーターであるが、なぜ日本列島の北海道と本州に多い巻き貝の記載をしたのかがわからない。タイプの個数も未知の世界なので、貝類学的にもやっかいな御仁である。個人的にはエゾボラモドキは北海道噴火湾とオホーツク海の固有種ではないかと思っている。だから新種記載すべきである。というのは、専門的過ぎるかも。さて、最近、生食用の巻き貝はアワビ類、サザエよりもエゾバイ科の巻き貝の方が量的には多い。今や、刺身用巻き貝の主産地は北海道となっているのである。市場ではエゾボラという巻き貝をAツブ、本種やたぶんだれにもわからないと思うけど標準和名を挙げると、クリイロエゾボラ、フジイロエゾボラ、アツエゾボラなどをBツブという。そのBツブのなかではもっとも値が高い。ちなみにAツブは昨年から今年にかけて信じられないほどの高値をつけた。そのときもっとも強く影響を受け高値をつけたのも本種である。
八王子綜合卸売センター、『福泉』にBツブが来ている。噴火湾で揚がった典型的なエゾボラモドキである。この流通名と標準和名が違う点がこの刺身用の巻き貝を難しくしている。流通上はBツブだけど、北海道オホーツク海では真ツブなのだからやっかいである。「A、B」と、「真ツブ、真ツブ以外」という、2つの考え方があるのも混乱の原因だ。記載者のGeorge Brettingham Sowerby III は19世紀から20世紀にかけて活躍したイギリスの動物学者でありイラストレーターであるが、なぜ日本列島の北海道と本州に多い巻き貝の記載をしたのかがわからない。タイプの個数も未知の世界なので、貝類学的にもやっかいな御仁である。個人的にはエゾボラモドキは北海道噴火湾とオホーツク海の固有種ではないかと思っている。だから新種記載すべきである。というのは、専門的過ぎるかも。さて、最近、生食用の巻き貝はアワビ類、サザエよりもエゾバイ科の巻き貝の方が量的には多い。今や、刺身用巻き貝の主産地は北海道となっているのである。市場ではエゾボラという巻き貝をAツブ、本種やたぶんだれにもわからないと思うけど標準和名を挙げると、クリイロエゾボラ、フジイロエゾボラ、アツエゾボラなどをBツブという。そのBツブのなかではもっとも値が高い。ちなみにAツブは昨年から今年にかけて信じられないほどの高値をつけた。そのときもっとも強く影響を受け高値をつけたのも本種である。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道産のテニスボール大のホッキガイを買った。ホッキガイは標準和名ウバガイのことだが、この茨城県周辺の名は一般的にはほぼ使われていない。実は茨城県が南限のこの貝が、関東や山梨県にやってきたのはかなり古そうである。大型で海水がなくても数日生かしておけるので、冷蔵技術がなくても輸送しやすかったからだ。せいぜいアサリ、ハマグリしか見ていない関東・山梨の人が、こんなに大きな二枚貝を見て、さぞやおどろいただろう。昔(たぶん1945年前後から)は、鉄路での輸送だったので、関東への主産地は茨城県と福島県南部だった産地の呼び名が消費地の呼び名になる典型的なものなので、古くからウバガイで売り買いされ、またそれを採取して標準和名となる。これが、ホッキガイというアタリのいい言語にじょじょに関東でも置き換わる。地方名を集めている身には面白いのと、呼び名の消滅の危機とを同時に感じて複雑である。今回のホッキ買いは久しぶりに福島県相馬市に行った記念というと変だが、当地の郷土料理でもあるホッキの天ぷらを作りたかったからだ。ついでに天丼にしてお昼とする。ホッキガイのバカガイ科の、一般流通の二枚貝は天ぷらにしてすべてうまい。他には青柳(バカガイ)、シオフキ、ミルクイなどである。作り方は簡単。剥き身にして足とヒモや貝柱に分ける。足の中にあるワタを押し出して捨てる。塩水の中で汚れを流し。足は開き、ヒモなどは食べやすい大きさに切る。山菜の「ほんな(ヨブスマソウorヤマブキショウマ)」をざっと洗い適当に切る。足も、ヒモなども小麦粉をまぶして置く。足は衣をつけて高温で揚げる。「ほんな」とヒモなどは一緒にして衣と合わせかき揚げにする。熱々のご飯に乗せて完成である。我が家ではみりん1・醤油1を合わせ煮立てたものをかけ醤油にしている。これにカツオ節出し同量を加え、(全部同じ量)を煮立てて、追い鰹(カツオ削り節)し、天つゆにしてもいい。ちなみに、どぼっとつける天つゆの比率は関東と関西では違うし、結局のところ比率に関しては自分好みに作るしかない。ホッキガイの天ぷらをのせた天丼の困った点は、うますぎてじっくり味わえないことだ。普通、衣の香ばしさを先に感じるものだが、ホッキガイの天ぷらはなぜか同時に足の甘さが舌に感じられる。強いうま味もあって天ぷらとして最高の素材だという事がわかる。そこにヒモと「ほんな」の薄苦い味わいがいいアクセントになっている。最近、天ぷら屋に行けてない憂さを、ここで少しだけ晴らす。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道産のテニスボール大のホッキガイを買った。ホッキガイは標準和名ウバガイのことだが、この茨城県周辺の名は一般的にはほぼ使われていない。実は茨城県が南限のこの貝が、関東や山梨県にやってきたのはかなり古そうである。大型で海水がなくても数日生かしておけるので、冷蔵技術がなくても輸送しやすかったからだ。せいぜいアサリ、ハマグリしか見ていない関東・山梨の人が、こんなに大きな二枚貝を見て、さぞやおどろいただろう。昔(たぶん1945年前後から)は、鉄路での輸送だったので、関東への主産地は茨城県と福島県南部だった産地の呼び名が消費地の呼び名になる典型的なものなので、古くからウバガイで売り買いされ、またそれを採取して標準和名となる。これが、ホッキガイというアタリのいい言語にじょじょに関東でも置き換わる。地方名を集めている身には面白いのと、呼び名の消滅の危機とを同時に感じて複雑である。今回のホッキ買いは久しぶりに福島県相馬市に行った記念というと変だが、当地の郷土料理でもあるホッキの天ぷらを作りたかったからだ。ついでに天丼にしてお昼とする。ホッキガイのバカガイ科の、一般流通の二枚貝は天ぷらにしてすべてうまい。他には青柳(バカガイ)、シオフキ、ミルクイなどである。作り方は簡単。剥き身にして足とヒモや貝柱に分ける。足の中にあるワタを押し出して捨てる。塩水の中で汚れを流し。足は開き、ヒモなどは食べやすい大きさに切る。山菜の「ほんな(ヨブスマソウorヤマブキショウマ)」をざっと洗い適当に切る。足も、ヒモなども小麦粉をまぶして置く。足は衣をつけて高温で揚げる。「ほんな」とヒモなどは一緒にして衣と合わせかき揚げにする。熱々のご飯に乗せて完成である。我が家ではみりん1・醤油1を合わせ煮立てたものをかけ醤油にしている。これにカツオ節出し同量を加え、(全部同じ量)を煮立てて、追い鰹(カツオ削り節)し、天つゆにしてもいい。ちなみに、どぼっとつける天つゆの比率は関東と関西では違うし、結局のところ比率に関しては自分好みに作るしかない。ホッキガイの天ぷらをのせた天丼の困った点は、うますぎてじっくり味わえないことだ。普通、衣の香ばしさを先に感じるものだが、ホッキガイの天ぷらはなぜか同時に足の甘さが舌に感じられる。強いうま味もあって天ぷらとして最高の素材だという事がわかる。そこにヒモと「ほんな」の薄苦い味わいがいいアクセントになっている。最近、天ぷら屋に行けてない憂さを、ここで少しだけ晴らす。 体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。ということで、またまた朝ご飯をば。なにしろ魚の撮影は早朝からで、撮影してはチェックして、部分的な撮影もしながら、ついでに文献を見たりすると、いつのまにか11時近くになる。その間、まんじゅうなどで我慢するが、この甘い誘惑は意外に腹持ちが悪い。不思議なもので甘いものばかり食べると、塩気が欲しくなる。まずはさんざん魚を触り、分解した後なのでとりあえずシャワーで魚臭さを除去する。この撮影後のシャワーがとても気持ちよい。冷蔵庫からあるものを出してくる。やはりどうしても和になってしまうのは、魚料理が和だからだ。主菜は石巻産2.6kgのヒラメ真子のから煎り、沼津産ゴマサバのみそ煮だ。大急ぎで脇役を用意する。スナップエンドウの塩ゆで、奈良漬け、トマト・エリンギ・若布のみそ汁、ウワゴールドを剥く。石巻産2.6kgのヒラメ真子のから煎り。真子の大きさたるやたいへんなもので、アニサキス探しで損傷していたのに600gもあった。これをざっとゆでてほぐし、鉄鍋でから煎りする。仕上げに酒・塩で味つけする。少し焦がしてあるので香ばしい。沼津産ゴマサバのみそ煮。意外に脂がのっていたのでびっくり。片身は分解したので片身のみみそで煮る。三枚に下ろした身は切り身にして湯引きして冷水に取り、水分をよく切っておく。南会津町の梁取みそ・みりん・酒・水である。ご飯は少量、おかずで満腹を目指しているが虚しい。
体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。ということで、またまた朝ご飯をば。なにしろ魚の撮影は早朝からで、撮影してはチェックして、部分的な撮影もしながら、ついでに文献を見たりすると、いつのまにか11時近くになる。その間、まんじゅうなどで我慢するが、この甘い誘惑は意外に腹持ちが悪い。不思議なもので甘いものばかり食べると、塩気が欲しくなる。まずはさんざん魚を触り、分解した後なのでとりあえずシャワーで魚臭さを除去する。この撮影後のシャワーがとても気持ちよい。冷蔵庫からあるものを出してくる。やはりどうしても和になってしまうのは、魚料理が和だからだ。主菜は石巻産2.6kgのヒラメ真子のから煎り、沼津産ゴマサバのみそ煮だ。大急ぎで脇役を用意する。スナップエンドウの塩ゆで、奈良漬け、トマト・エリンギ・若布のみそ汁、ウワゴールドを剥く。石巻産2.6kgのヒラメ真子のから煎り。真子の大きさたるやたいへんなもので、アニサキス探しで損傷していたのに600gもあった。これをざっとゆでてほぐし、鉄鍋でから煎りする。仕上げに酒・塩で味つけする。少し焦がしてあるので香ばしい。沼津産ゴマサバのみそ煮。意外に脂がのっていたのでびっくり。片身は分解したので片身のみみそで煮る。三枚に下ろした身は切り身にして湯引きして冷水に取り、水分をよく切っておく。南会津町の梁取みそ・みりん・酒・水である。ご飯は少量、おかずで満腹を目指しているが虚しい。 最近、メキシコ産だらけだったアボカドだけど八王子綜合卸売センター、八百角に久しぶりにペルー産が来ていた。メキシコという国は田中小実昌という浮遊生物的作家が飲んだくれていたくらいで、いい国なのかなと思っていた。でも、隣町に住んでいるメキシカンに聞くと暮らすに堪えないところらしい。だいたいアメリカに逃げる人が多いというのも国としていかがなものか。国の良し悪しもそうだけど、平凡な暮らしをしているこの国の住人として、栽培のために自然破壊をし、犯罪も多発させているというメキシコ産アボカドを買ってもいいのか? 疑問符数億個なのだ。ペルーで同じ事が起こっていないことを祈る。アボカドを買ったので、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産まで戻る。アボカドに合う水産物というとエビ類、イカ類、二枚貝のホッキガイ(ウバガイ)、目の前で若い衆がせっせと裂いている穴子(マアナゴ)だろう。ボクは何にするか懊悩する。悶え苦しみながら若い衆から穴子1本ひったくる。買って始めて気がついた、穴子が高騰していることに。
最近、メキシコ産だらけだったアボカドだけど八王子綜合卸売センター、八百角に久しぶりにペルー産が来ていた。メキシコという国は田中小実昌という浮遊生物的作家が飲んだくれていたくらいで、いい国なのかなと思っていた。でも、隣町に住んでいるメキシカンに聞くと暮らすに堪えないところらしい。だいたいアメリカに逃げる人が多いというのも国としていかがなものか。国の良し悪しもそうだけど、平凡な暮らしをしているこの国の住人として、栽培のために自然破壊をし、犯罪も多発させているというメキシコ産アボカドを買ってもいいのか? 疑問符数億個なのだ。ペルーで同じ事が起こっていないことを祈る。アボカドを買ったので、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産まで戻る。アボカドに合う水産物というとエビ類、イカ類、二枚貝のホッキガイ(ウバガイ)、目の前で若い衆がせっせと裂いている穴子(マアナゴ)だろう。ボクは何にするか懊悩する。悶え苦しみながら若い衆から穴子1本ひったくる。買って始めて気がついた、穴子が高騰していることに。 体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。ということで、またまた朝ご飯をば。カンパチも4㎏を超えるとなかなか食い尽くせない。いろんな形で保存した。もっともスタンダードなものが、切り身にして塩コショウである。塩コショウして1時間くらい常温におく。あとはラップして冷凍する。使うときは自然解凍するといい。ご飯、カンパチのフライパン照焼、うどのきんぴら、トマト、レタス、東京たくわん、ダメになりそうな野菜の具だくさんみそ汁。フライパン照焼はたぶん『暮らしの手帖』の料理名だと思う。小学生から延々読者だったのでいつ頃に見た料理なのか、思い出せない。塩コショウしたカンパチの切り身は自然解凍しておく。多めの油でじっくり中火でソテーする。表面が香ばしくなったら取り出し、プレートに盛り付ける。プレートにご飯をよそい、野菜やきんぴらを盛り合わせる。火を止めて余分な油を保存缶に移す。そこに酒・みりんを加えて、ガスをつけてアルコール分をとばして醤油、しょうがの搾り汁を加えてふたたび煮立たせる。これをタレにして回しかける。ワンプレートなのに盛りだくさんだし、栄養バランスもいいんじゃないのかな。だいたいのっているもの総てうまい。皿はイタッラなのですいすい洗えて、あっと言う間に片づけ終了。
体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。ということで、またまた朝ご飯をば。カンパチも4㎏を超えるとなかなか食い尽くせない。いろんな形で保存した。もっともスタンダードなものが、切り身にして塩コショウである。塩コショウして1時間くらい常温におく。あとはラップして冷凍する。使うときは自然解凍するといい。ご飯、カンパチのフライパン照焼、うどのきんぴら、トマト、レタス、東京たくわん、ダメになりそうな野菜の具だくさんみそ汁。フライパン照焼はたぶん『暮らしの手帖』の料理名だと思う。小学生から延々読者だったのでいつ頃に見た料理なのか、思い出せない。塩コショウしたカンパチの切り身は自然解凍しておく。多めの油でじっくり中火でソテーする。表面が香ばしくなったら取り出し、プレートに盛り付ける。プレートにご飯をよそい、野菜やきんぴらを盛り合わせる。火を止めて余分な油を保存缶に移す。そこに酒・みりんを加えて、ガスをつけてアルコール分をとばして醤油、しょうがの搾り汁を加えてふたたび煮立たせる。これをタレにして回しかける。ワンプレートなのに盛りだくさんだし、栄養バランスもいいんじゃないのかな。だいたいのっているもの総てうまい。皿はイタッラなのですいすい洗えて、あっと言う間に片づけ終了。 神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置を見ていると、まさに夏到来と感じる魚が少なからず登場してきている。その魁のひとつが小イサキである。とれるときは半端な量ではなく、ごっそりとれるので「ごっそり」と呼ばれている。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置を見ていると、まさに夏到来と感じる魚が少なからず登場してきている。その魁のひとつが小イサキである。とれるときは半端な量ではなく、ごっそりとれるので「ごっそり」と呼ばれている。 体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。もちろん自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。さてもうかなり前の朝ご飯の主菜は八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げてきたでかいカンパチの粕漬け。大型魚のいいところは保存食などにして長々と食い繋ぐことができることだ。特に粕漬けは保存性が高い。みそ漬け、祐庵漬けなどは漬けすぎると硬くなるが、粕漬けは1週間くらいは平気で保つ。この日は小売業、定期的な仕事、サイト運営などの実に平凡な日だった。あまりにも起伏のない生活に逆に疲れ果てる。ご飯、ぶなしめじ・ワカメのみそ汁、サラダ小松菜とトマト、奈良漬け、熱海市の宇田勝さんにいただいたところてん。カンパチの粕漬け。福島県南会津町『ハローショップ みどりや』でいただいた練り粕とみりん、同町山内麹店の梁取みそ、みりんで漬け地を作る。カンパチの切り身に振り塩をする。水分が出て来たら拭き取り、漬け地につける。写真は食べ頃の3日目で、粕の甘味と香りが豊かで、結局1枚追加する。クサヤモロのさんが焼き。これも銭州でクマゴロウが釣り上げてきたもの。今回は刺身にして、みそたたき(なめろう)にした。残ったものをガスグリルで焼き上げた。旬で脂が乗っているので焼いても硬くならず実に豊潤。まことに和そのものの朝ご飯で、おかずが多いので、糖質をかなり控えることができた。それにしても粕漬けは飯に合う。
体のプロに「食べたものをメモしろ」と言われて、やっている内になんだか楽しくなってきた。もちろん自分が食べたものを振り返ると意外な発見があり、反省点も少なからずある。さてもうかなり前の朝ご飯の主菜は八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で釣り上げてきたでかいカンパチの粕漬け。大型魚のいいところは保存食などにして長々と食い繋ぐことができることだ。特に粕漬けは保存性が高い。みそ漬け、祐庵漬けなどは漬けすぎると硬くなるが、粕漬けは1週間くらいは平気で保つ。この日は小売業、定期的な仕事、サイト運営などの実に平凡な日だった。あまりにも起伏のない生活に逆に疲れ果てる。ご飯、ぶなしめじ・ワカメのみそ汁、サラダ小松菜とトマト、奈良漬け、熱海市の宇田勝さんにいただいたところてん。カンパチの粕漬け。福島県南会津町『ハローショップ みどりや』でいただいた練り粕とみりん、同町山内麹店の梁取みそ、みりんで漬け地を作る。カンパチの切り身に振り塩をする。水分が出て来たら拭き取り、漬け地につける。写真は食べ頃の3日目で、粕の甘味と香りが豊かで、結局1枚追加する。クサヤモロのさんが焼き。これも銭州でクマゴロウが釣り上げてきたもの。今回は刺身にして、みそたたき(なめろう)にした。残ったものをガスグリルで焼き上げた。旬で脂が乗っているので焼いても硬くならず実に豊潤。まことに和そのものの朝ご飯で、おかずが多いので、糖質をかなり控えることができた。それにしても粕漬けは飯に合う。 神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置でダンベ(大水槽で飼料などになる魚を入れる)行きの小魚を分けてもらってきた。この時季は小魚が多くて定置網漁師は大変なのである。とにかく一刻も早く売れる魚を選別しなければならない。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置でダンベ(大水槽で飼料などになる魚を入れる)行きの小魚を分けてもらってきた。この時季は小魚が多くて定置網漁師は大変なのである。とにかく一刻も早く売れる魚を選別しなければならない。 神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置でダンベ(大型水槽)行きの小魚を分けてもらってきた。これを“このまま食べる”ことが未来を明るくする。もちろん絶対ではないが目の前に魚不足というか食糧不足が待ち構えていると思っている。養殖魚の魚粉以外の餌の開発が急務となっているのはその証拠である。すでに魚を大量消費する時代は終わり、とった魚を大切に食べる時代が来ているのだ。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、二宮定置でダンベ(大型水槽)行きの小魚を分けてもらってきた。これを“このまま食べる”ことが未来を明るくする。もちろん絶対ではないが目の前に魚不足というか食糧不足が待ち構えていると思っている。養殖魚の魚粉以外の餌の開発が急務となっているのはその証拠である。すでに魚を大量消費する時代は終わり、とった魚を大切に食べる時代が来ているのだ。 奈良県十津川村平谷、『ふくおか』から「番茶」を取り寄せた。取り寄せは、よほどのことがないとやらないので異例だ。同村の松寶純子さんがチャノキの葉をやや野性的につみ、よくよく揉んで作ったものだ。十津川を縦断したのはサンマのことを調べるためだ。国内でもっとも早くからサンマを流通させたのは熊野(三重県・和歌山県)と奈良県、後に畿内、美濃である。サンマの歴史にとってもっとも重要な地域と言えるだろう。そんな旅の途中、小さなスーパーというかコンビニのような店、『ふくおか』で見つけたのがこのお茶である。
奈良県十津川村平谷、『ふくおか』から「番茶」を取り寄せた。取り寄せは、よほどのことがないとやらないので異例だ。同村の松寶純子さんがチャノキの葉をやや野性的につみ、よくよく揉んで作ったものだ。十津川を縦断したのはサンマのことを調べるためだ。国内でもっとも早くからサンマを流通させたのは熊野(三重県・和歌山県)と奈良県、後に畿内、美濃である。サンマの歴史にとってもっとも重要な地域と言えるだろう。そんな旅の途中、小さなスーパーというかコンビニのような店、『ふくおか』で見つけたのがこのお茶である。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に青森県産瓶入りの生ウニがきていた。岩手県などの牛乳瓶入りが有名だけど、瓶の形なんてボクにはどうでもええことなので、この広島県のふりかけが入っているような瓶でも瓶は瓶なのよと思っている。ときどき生ウニは「牛乳瓶入りが好き」と言う人に出会うことがあるが、牛乳瓶に惹かれて買うのは止めようよ、といいたい。ようするに瓶に密閉するのでミョウバンがいらないわけで、苦味のない剥き立ての味が楽しめるウニが好き、と言って欲しい。とりたててウニ好きというわけではないが、ときどき無性にウニが食べたくなるときがある。だいたい初夏というか最高気温が25度超えの、夏日が増えると食べたくなる。瓶入り仲卸価格でだいたい3000円前後でその年の好不漁で値が上下する。1瓶で180gも入っているので、高級すし店の1かんの値段だと思うと安いものだ。最近、そのまま生でとか、ご飯に乗せてというのも好きだけど、ちょっと変わった食べ方に執着している。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に青森県産瓶入りの生ウニがきていた。岩手県などの牛乳瓶入りが有名だけど、瓶の形なんてボクにはどうでもええことなので、この広島県のふりかけが入っているような瓶でも瓶は瓶なのよと思っている。ときどき生ウニは「牛乳瓶入りが好き」と言う人に出会うことがあるが、牛乳瓶に惹かれて買うのは止めようよ、といいたい。ようするに瓶に密閉するのでミョウバンがいらないわけで、苦味のない剥き立ての味が楽しめるウニが好き、と言って欲しい。とりたててウニ好きというわけではないが、ときどき無性にウニが食べたくなるときがある。だいたい初夏というか最高気温が25度超えの、夏日が増えると食べたくなる。瓶入り仲卸価格でだいたい3000円前後でその年の好不漁で値が上下する。1瓶で180gも入っているので、高級すし店の1かんの値段だと思うと安いものだ。最近、そのまま生でとか、ご飯に乗せてというのも好きだけど、ちょっと変わった食べ方に執着している。 いちばん近い都心である新宿まで出なくてはならない日だった。面白いもので八王子の市場人は新宿に出るとき、東京に行くという。最近、数えるほどしか都心に出ないので、ボクもときどき東京に行くというようになった。毎日、激混みの列車に揺られていたボクが、遙か昔のボクになっているのだ。近いんだから慌てる必要はないだろうと思われるかも知れないが、普通の日でも忙しい午前中が2倍忙しくなる。それでも、自宅では原則魚飯なので一瞬で食べられる魚飯を考える。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で前日に釣り上げたカンパチがあるので冷蔵庫から取り出し、中落ちをかき出し、食べやすい大きさに切る。少しだけみりんを落としたしょうが醤油に漬け込む。しょうがは近所でもらった試供品のチューブだ。刻みねぎを加え、ごまを振り、かき混ぜる。
いちばん近い都心である新宿まで出なくてはならない日だった。面白いもので八王子の市場人は新宿に出るとき、東京に行くという。最近、数えるほどしか都心に出ないので、ボクもときどき東京に行くというようになった。毎日、激混みの列車に揺られていたボクが、遙か昔のボクになっているのだ。近いんだから慌てる必要はないだろうと思われるかも知れないが、普通の日でも忙しい午前中が2倍忙しくなる。それでも、自宅では原則魚飯なので一瞬で食べられる魚飯を考える。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウが銭州で前日に釣り上げたカンパチがあるので冷蔵庫から取り出し、中落ちをかき出し、食べやすい大きさに切る。少しだけみりんを落としたしょうが醤油に漬け込む。しょうがは近所でもらった試供品のチューブだ。刻みねぎを加え、ごまを振り、かき混ぜる。 八王子綜合卸売センター、『八百角』にハチク(淡竹/はちく)が出ていた。たぶん長野県とか群馬県のものだと思う。比較的寒冷な土地に育つもので、東京都多摩地方や千葉県ではマダケが一般的でハチクはほとんどない。長野県、新潟県や山形県では今、市場や直売所はハチクだらけだと想像する。ハチクを見つけたら練り製品とか生利節(生節)が欲しくなる。市場中を探したが生利節がない。市場帰りに近所のスーパーにはなく、打ち合わせで出掛けた駅前の、スーパーをのぞくと今切れているところだと言われた。諦めていたところが、電気屋さんの隣のスーパーで発見する。竹輪以上に基本的な食材だと思っているのに、こんなにあっちこっち探さなくてはならぬとは、ヤな世の中になったものヨ。
八王子綜合卸売センター、『八百角』にハチク(淡竹/はちく)が出ていた。たぶん長野県とか群馬県のものだと思う。比較的寒冷な土地に育つもので、東京都多摩地方や千葉県ではマダケが一般的でハチクはほとんどない。長野県、新潟県や山形県では今、市場や直売所はハチクだらけだと想像する。ハチクを見つけたら練り製品とか生利節(生節)が欲しくなる。市場中を探したが生利節がない。市場帰りに近所のスーパーにはなく、打ち合わせで出掛けた駅前の、スーパーをのぞくと今切れているところだと言われた。諦めていたところが、電気屋さんの隣のスーパーで発見する。竹輪以上に基本的な食材だと思っているのに、こんなにあっちこっち探さなくてはならぬとは、ヤな世の中になったものヨ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの銭州行は、最近、本命ばかりでつまらぬ。シマアジなんてものはいりまへん、食っても食えぬ魚がええんだす。石なんて最高だす、と言ったものの、とりあえず見事なイサキがあったので連れ帰ってくる。32cm・675gはそこそこ大きい。イサキは外洋性の魚である。生息海域による違いはあまりないと思っていたが、大量に食べていると比較的岸近くにいる個体の方がよい気がしてきている。ボクの地元、小田原周辺のイサキの脂ののりは、例えば銭州や駿河湾金洲よりも上ではないか。まだ結論は出ていないが、市場で選ぶときはどちらかというとあからさまに外洋のイサキではなく、半外洋のイサキを選んでしまう。例えばリアス式海岸的な地形周辺でとれるイサキは味があると思っているが、いかがだろう。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの銭州行は、最近、本命ばかりでつまらぬ。シマアジなんてものはいりまへん、食っても食えぬ魚がええんだす。石なんて最高だす、と言ったものの、とりあえず見事なイサキがあったので連れ帰ってくる。32cm・675gはそこそこ大きい。イサキは外洋性の魚である。生息海域による違いはあまりないと思っていたが、大量に食べていると比較的岸近くにいる個体の方がよい気がしてきている。ボクの地元、小田原周辺のイサキの脂ののりは、例えば銭州や駿河湾金洲よりも上ではないか。まだ結論は出ていないが、市場で選ぶときはどちらかというとあからさまに外洋のイサキではなく、半外洋のイサキを選んでしまう。例えばリアス式海岸的な地形周辺でとれるイサキは味があると思っているが、いかがだろう。 アニサキス探しで大量に分解しているマサバを、全部捨てるのは飢餓の危機迫る(大げさではなく間違いなくやってくる危機)、今、許されないことだろう。この少々潰れ潰れした筋肉を集める。これでサバマヨを作り、撮影用に買ったバタールで遅い昼ご飯を作る。
アニサキス探しで大量に分解しているマサバを、全部捨てるのは飢餓の危機迫る(大げさではなく間違いなくやってくる危機)、今、許されないことだろう。この少々潰れ潰れした筋肉を集める。これでサバマヨを作り、撮影用に買ったバタールで遅い昼ご飯を作る。 自分の食べているものを記録しなさいよと、その道のプロに言われて、食べたものを全部撮影することにした。取り分け、朝ご飯はちゃんと食え、と言われたので、撮影したもの以外にも、例えばみそ汁などいろいろ作る。市場に行かない水曜日なので、一日中、文字打ちの日である。水産生物を調べるという事は、記録するという事だし、生きていくためにはたつき仕事もしなくてはならぬ。卵がダメになりそうだったので東京風卵焼きを作る。初めて上京して江戸川区で食べたとき、ビックリ仰天するほど醤油と砂糖の濃厚味だった。今や醤油も砂糖もちょっとだけよ、となっている。水菜はゆでて市販のドレッシング。昨日の厚揚げ煮は、ときどき作るものでだし以外は精進。普通の家庭の普通の味。だしは混合節で養殖の日高昆布。フクロフノリのみそ汁。フクロフノリは伊豆半島産で小田原のおっかさんにもらったもの。みそは福島県南会津町の梁取みそ。シログチの塩焼き。東京では「いしもち(シログチ)」は塩焼きと決まっているかのごとくだけど、事ほど左様にうまい。
自分の食べているものを記録しなさいよと、その道のプロに言われて、食べたものを全部撮影することにした。取り分け、朝ご飯はちゃんと食え、と言われたので、撮影したもの以外にも、例えばみそ汁などいろいろ作る。市場に行かない水曜日なので、一日中、文字打ちの日である。水産生物を調べるという事は、記録するという事だし、生きていくためにはたつき仕事もしなくてはならぬ。卵がダメになりそうだったので東京風卵焼きを作る。初めて上京して江戸川区で食べたとき、ビックリ仰天するほど醤油と砂糖の濃厚味だった。今や醤油も砂糖もちょっとだけよ、となっている。水菜はゆでて市販のドレッシング。昨日の厚揚げ煮は、ときどき作るものでだし以外は精進。普通の家庭の普通の味。だしは混合節で養殖の日高昆布。フクロフノリのみそ汁。フクロフノリは伊豆半島産で小田原のおっかさんにもらったもの。みそは福島県南会津町の梁取みそ。シログチの塩焼き。東京では「いしもち(シログチ)」は塩焼きと決まっているかのごとくだけど、事ほど左様にうまい。 勝手にデ・ハーンものと呼んでいる。19世紀前半にシーボルトとその後継者たちが日本で集めオランダに持ち帰った標本を研究したもの。『日本動物誌』に記載されているものだ。ウィレム・デ・ハーンは甲殻類、シュレーゲルやテミンクは脊椎動物を担当している。明治時代になり、いざ、国内の動物を調べようと思ったら、すでに非常に多くの動物が研究され記載済みだった、とわかったときの驚きは大きかっただろうと思う。これを、これまたボクは、勝手にシーボルトショックと呼んでいる。このカニの標準和名のヒラツメガニの出所や理由がまったくわからない。どこが平たいのだろう。酒井恒というカニの大家もそれに触れていない。学名のpunctatus は斑紋があるということだけど、これもどうなんだろうな?ゆでて食べるというよりも、みそ汁にされることの方が多い。昔、九十九里のはぐら瓜農家さんで買ったことがある。売っていたのが農家の方なのかどうかは不明だけど、みそ汁の試食つきだった。そこでの名前が「ほんだがに」で自動車会社のホンダのマークのHからだ。そのものすばり、「Hがに」とも「すけべがに」とも呼ぶ。
勝手にデ・ハーンものと呼んでいる。19世紀前半にシーボルトとその後継者たちが日本で集めオランダに持ち帰った標本を研究したもの。『日本動物誌』に記載されているものだ。ウィレム・デ・ハーンは甲殻類、シュレーゲルやテミンクは脊椎動物を担当している。明治時代になり、いざ、国内の動物を調べようと思ったら、すでに非常に多くの動物が研究され記載済みだった、とわかったときの驚きは大きかっただろうと思う。これを、これまたボクは、勝手にシーボルトショックと呼んでいる。このカニの標準和名のヒラツメガニの出所や理由がまったくわからない。どこが平たいのだろう。酒井恒というカニの大家もそれに触れていない。学名のpunctatus は斑紋があるということだけど、これもどうなんだろうな?ゆでて食べるというよりも、みそ汁にされることの方が多い。昔、九十九里のはぐら瓜農家さんで買ったことがある。売っていたのが農家の方なのかどうかは不明だけど、みそ汁の試食つきだった。そこでの名前が「ほんだがに」で自動車会社のホンダのマークのHからだ。そのものすばり、「Hがに」とも「すけべがに」とも呼ぶ。 江戸時代の飲食店の出現は貨幣の歴史でわかる。特に高級な食べ物であったウナギが一般人にとって馴染み深いものとなるには貨幣の創銭・改鋳があってこそなのだ。先日から寛永通宝を探して骨董市を歩いた。寛永通宝は江戸入り後、特に徳川家光時代、渡来銭(当時銭は中国から輸入していた。12世紀の最初の輸入銭である宋銭と平家の関係は重要。明銭は江戸時代初期の小額通貨だった)からの脱却を目指して作られる。寛永通宝は後に幕府だけではなく各藩で鋳造されてより経済が発展する。ただし100文の買い物をするためにはこの重さ4gの1文銭を100枚(400g)持ち歩かなくてはならない。銭緡(ぜにさし)といって100文の銭を1まとめにする仕事があり、賃金が4文(銭緡をした人の取り分はこの何割か)だったので、実は1緡96文だった。割れ銭などを選別しながら数えて100文を緡(さす)のは以外に大変だったかがわかる。
江戸時代の飲食店の出現は貨幣の歴史でわかる。特に高級な食べ物であったウナギが一般人にとって馴染み深いものとなるには貨幣の創銭・改鋳があってこそなのだ。先日から寛永通宝を探して骨董市を歩いた。寛永通宝は江戸入り後、特に徳川家光時代、渡来銭(当時銭は中国から輸入していた。12世紀の最初の輸入銭である宋銭と平家の関係は重要。明銭は江戸時代初期の小額通貨だった)からの脱却を目指して作られる。寛永通宝は後に幕府だけではなく各藩で鋳造されてより経済が発展する。ただし100文の買い物をするためにはこの重さ4gの1文銭を100枚(400g)持ち歩かなくてはならない。銭緡(ぜにさし)といって100文の銭を1まとめにする仕事があり、賃金が4文(銭緡をした人の取り分はこの何割か)だったので、実は1緡96文だった。割れ銭などを選別しながら数えて100文を緡(さす)のは以外に大変だったかがわかる。 自分の食べているものを記録しなさいよと、その道のプロに言われて、食べたものを全部撮影することにした。取り分け、朝ご飯はちゃんと食え、と言われたので、撮影したもの以外にも、例えばみそ汁などいろいろ作る。もちろん撮影後にあれこれ取りそろえるのは、体力的には苦しいのだが。さて、アニサキスのためにマサバ、ゴマサバを買っては買ってはバラして、アニサキス探しをしている。さすがに全部、身から何からつぶしていることにも気が引けて、塩サバにしたり、ゆでたりして保存することになる。ご飯、主菜は兵庫県淡路産マサバの塩焼き。兵庫県明石市明石浦漁協の味つけ海苔、ダメになりそうなにらで、ニラ玉、ニラ・若布のみそ汁。ピーマンごま油炒め(白ごま)。撮影したばかりのアイナメたたきを焼いたもの(さんが焼き)を添える。淡路島産マサバは分解するのが忍びないほどの上物だった。さほどではないが、脂がのっていたのだ。こんな時季にこれほどの脂ののりは経験したことがない。今回のものは、これを切り身にして振り塩、少し寝かせて冷凍保存しておいた。アイナメたたきを焼いたものは、マアジなどと比べると淡泊すぎるが、これもおかずの1品としては十二分にうまい。
自分の食べているものを記録しなさいよと、その道のプロに言われて、食べたものを全部撮影することにした。取り分け、朝ご飯はちゃんと食え、と言われたので、撮影したもの以外にも、例えばみそ汁などいろいろ作る。もちろん撮影後にあれこれ取りそろえるのは、体力的には苦しいのだが。さて、アニサキスのためにマサバ、ゴマサバを買っては買ってはバラして、アニサキス探しをしている。さすがに全部、身から何からつぶしていることにも気が引けて、塩サバにしたり、ゆでたりして保存することになる。ご飯、主菜は兵庫県淡路産マサバの塩焼き。兵庫県明石市明石浦漁協の味つけ海苔、ダメになりそうなにらで、ニラ玉、ニラ・若布のみそ汁。ピーマンごま油炒め(白ごま)。撮影したばかりのアイナメたたきを焼いたもの(さんが焼き)を添える。淡路島産マサバは分解するのが忍びないほどの上物だった。さほどではないが、脂がのっていたのだ。こんな時季にこれほどの脂ののりは経験したことがない。今回のものは、これを切り身にして振り塩、少し寝かせて冷凍保存しておいた。アイナメたたきを焼いたものは、マアジなどと比べると淡泊すぎるが、これもおかずの1品としては十二分にうまい。 田中小実昌(1925-2000)の文章が味わえるようになったとき、自分の文章読力が上がったな、と思ったものだ。文字を真面目に追っていくと、非常に稚拙であったり、どこにも修辞を感じられなかったり。無造作にほうり投げた文章の中にいろんな事象が散らばっていたりする。とりとめがなく、結句がない。山口瞳とは両極端にある。中学生にとっても面白くて仕方がなかった山口瞳的脳みそで田中小実昌を読むとは大変なことになる。今、枕周りに四五十冊の本が散らばっているが、昨日手に取った田中小実昌に、〈ホヤは北のほうにいくほど、ピンクに近い色だ。それが西(南)に下るにつれて色がうすれ、仙台湾あたりでは、ほとんど砂色だ。〉『ほろよい味の旅』(田中小実昌 中公文庫 単行本1988)という文章がある。
田中小実昌(1925-2000)の文章が味わえるようになったとき、自分の文章読力が上がったな、と思ったものだ。文字を真面目に追っていくと、非常に稚拙であったり、どこにも修辞を感じられなかったり。無造作にほうり投げた文章の中にいろんな事象が散らばっていたりする。とりとめがなく、結句がない。山口瞳とは両極端にある。中学生にとっても面白くて仕方がなかった山口瞳的脳みそで田中小実昌を読むとは大変なことになる。今、枕周りに四五十冊の本が散らばっているが、昨日手に取った田中小実昌に、〈ホヤは北のほうにいくほど、ピンクに近い色だ。それが西(南)に下るにつれて色がうすれ、仙台湾あたりでは、ほとんど砂色だ。〉『ほろよい味の旅』(田中小実昌 中公文庫 単行本1988)という文章がある。 書籍の整理をしていて、坪内祐三の1冊に足を取られてはかが行かない。神保町の人生劇場の前で一度だけすれ違っている。あっと思ったのはボクの方だけで、それだけのことだけど、この若き文芸評論家の死が返す返すも残念でならない。ページをめくっている内に、脳みそが慶応3年生まれの正岡子規の世界に持って行かれている。子規のまざまざとした表現力は天成の明るさから来るものなか、とか、明治27年からのこととか、いろいろ思っている内に疲れてきた。我が家にあるはずの子規の書籍を探したら、どうしても見つからない。書籍を処分するつもりが岩波文庫を大量に買うはめになる。子規が脳みそにへばりついて離れないので、故人を偲び、大好きだった堅魚の刺身を作り、残りは医者いらずのナスと合わせてご飯の友を作った。最近、惣菜作りが非常に楽しい。その日、八王子綜合卸売センター、八百角のバアチャンに、「なすの医者いらず」という諺を教わる。あんなへなへなした味の野菜に薬効があると思えないけど、90近くのバアチャンの言うことなので説得力がある。カツオを買うと、血合いは「みそたたき(なめろう)」とか煮つけにしてしまうが、たまには思いつき料理を作ってみることにした。血合いは骨ごと細かくたたく。少量のみそとしょうが、水溶きの小麦粉を合わせて、ふたたび徹底的にたたく。ナスは適当に切り、水に放っておく。ナスの水分を切り、油通しをする。血合いをたたいたものは香ばしく揚げる。鍋に酒・みりん・水を合わせて煮立て、アルコールを煮切る。醤油、化学調味料、下ろしにんにく、八角3分の1くらいを合わせて、甘辛味をみて味加減する。少し煮つめた中にナスと、血合いたたきを加えてからめ、火を止めて、粗挽き黒コショウを振る。あっと言う間の一品なのだけど文字にすると面倒くさそうなのはなぜだろう。これを常備菜として保存。折々にご飯の友とする。この甘辛醤油味、八角風味にカツオとナスという組み合わせは、ご飯にとって最良の夫かも知れない。どことなく新婚家庭のように、忙しいうまさである。岐阜の三千盛の肴としてが、やはり酒とは縁がない。
書籍の整理をしていて、坪内祐三の1冊に足を取られてはかが行かない。神保町の人生劇場の前で一度だけすれ違っている。あっと思ったのはボクの方だけで、それだけのことだけど、この若き文芸評論家の死が返す返すも残念でならない。ページをめくっている内に、脳みそが慶応3年生まれの正岡子規の世界に持って行かれている。子規のまざまざとした表現力は天成の明るさから来るものなか、とか、明治27年からのこととか、いろいろ思っている内に疲れてきた。我が家にあるはずの子規の書籍を探したら、どうしても見つからない。書籍を処分するつもりが岩波文庫を大量に買うはめになる。子規が脳みそにへばりついて離れないので、故人を偲び、大好きだった堅魚の刺身を作り、残りは医者いらずのナスと合わせてご飯の友を作った。最近、惣菜作りが非常に楽しい。その日、八王子綜合卸売センター、八百角のバアチャンに、「なすの医者いらず」という諺を教わる。あんなへなへなした味の野菜に薬効があると思えないけど、90近くのバアチャンの言うことなので説得力がある。カツオを買うと、血合いは「みそたたき(なめろう)」とか煮つけにしてしまうが、たまには思いつき料理を作ってみることにした。血合いは骨ごと細かくたたく。少量のみそとしょうが、水溶きの小麦粉を合わせて、ふたたび徹底的にたたく。ナスは適当に切り、水に放っておく。ナスの水分を切り、油通しをする。血合いをたたいたものは香ばしく揚げる。鍋に酒・みりん・水を合わせて煮立て、アルコールを煮切る。醤油、化学調味料、下ろしにんにく、八角3分の1くらいを合わせて、甘辛味をみて味加減する。少し煮つめた中にナスと、血合いたたきを加えてからめ、火を止めて、粗挽き黒コショウを振る。あっと言う間の一品なのだけど文字にすると面倒くさそうなのはなぜだろう。これを常備菜として保存。折々にご飯の友とする。この甘辛醤油味、八角風味にカツオとナスという組み合わせは、ご飯にとって最良の夫かも知れない。どことなく新婚家庭のように、忙しいうまさである。岐阜の三千盛の肴としてが、やはり酒とは縁がない。 予め断っておくが写真は遙か昔のものだ。本日、午前11時半に作ったトルコ風サンドではない。突然の停電でパニックに陥る。こんなときに限ってケータイのバッテリーが切れている。なすすべがないので止まった冷蔵庫の冷凍庫をあさってスルメイカのげそを出して、サンドイッチを作った。腹が減っては戦はできぬ。作っても停電中なので撮影できるはずもなく、ただただ食べたけど、せっかくなので前回に撮影した同じ物を登場させる。作り方はボクにも作れます、で簡単。げそはすぐに解凍するのでレタスを始め野菜などの材料を並べる。今回のスルメイカげそ以外の材料は、クレシオーネ コントルノというイタリア野菜、エリンギ、にんにくにトマトだ。前回の写真と違うのはマシュルームの代わりにエリンギと、レタスに代わってクレシオーネ コントルノであること。
予め断っておくが写真は遙か昔のものだ。本日、午前11時半に作ったトルコ風サンドではない。突然の停電でパニックに陥る。こんなときに限ってケータイのバッテリーが切れている。なすすべがないので止まった冷蔵庫の冷凍庫をあさってスルメイカのげそを出して、サンドイッチを作った。腹が減っては戦はできぬ。作っても停電中なので撮影できるはずもなく、ただただ食べたけど、せっかくなので前回に撮影した同じ物を登場させる。作り方はボクにも作れます、で簡単。げそはすぐに解凍するのでレタスを始め野菜などの材料を並べる。今回のスルメイカげそ以外の材料は、クレシオーネ コントルノというイタリア野菜、エリンギ、にんにくにトマトだ。前回の写真と違うのはマシュルームの代わりにエリンギと、レタスに代わってクレシオーネ コントルノであること。 いまだにプロの間でもマイナーな魚である。入荷が少ないわけでもないのに名前(標準和名)をおぼえてもらえない。その唯一の問題点は欠点がないことだろう。ナンヨウカイワリはできすぎるが故に目立たないのである。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの銭州通いは続いているが、釣果の中でウメイロとともに数が多いのがナンヨウカイワリである。昔は伊豆諸島に多くて船釣りよりも磯釣りの魚だった気がする。浅瀬にいると思ったら、船釣りでぼんぼん釣れる(釣り師曰く)のには驚かされた。最近では相模湾北部でも増えている。見た目はカイワリよりもシマアジに似ていて、非常に美しい。アジ科の分類は細分化されたので説明しても無意味だけど、もちろんカイワリとは同じアジ科というだけでそれほど縁はない。比較的安いのでときどき買ってみる。たぶん旬は初夏ではないかと思うのだけれど、同属のクロヒラアジと比べても取り立てて脂が乗るということがない。並んでいると当然のごとく、クロヒラアジに手が伸びる。ただし、脂の極端なのりはないものの味がある魚なのである。アジ科ならではのうま味成分がたっぷりで、微かに酸味があるので後味がいい。今回の個体は体長31cm・531gなので、やや小振りだ。これを素直に刺身にする。
いまだにプロの間でもマイナーな魚である。入荷が少ないわけでもないのに名前(標準和名)をおぼえてもらえない。その唯一の問題点は欠点がないことだろう。ナンヨウカイワリはできすぎるが故に目立たないのである。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウの銭州通いは続いているが、釣果の中でウメイロとともに数が多いのがナンヨウカイワリである。昔は伊豆諸島に多くて船釣りよりも磯釣りの魚だった気がする。浅瀬にいると思ったら、船釣りでぼんぼん釣れる(釣り師曰く)のには驚かされた。最近では相模湾北部でも増えている。見た目はカイワリよりもシマアジに似ていて、非常に美しい。アジ科の分類は細分化されたので説明しても無意味だけど、もちろんカイワリとは同じアジ科というだけでそれほど縁はない。比較的安いのでときどき買ってみる。たぶん旬は初夏ではないかと思うのだけれど、同属のクロヒラアジと比べても取り立てて脂が乗るということがない。並んでいると当然のごとく、クロヒラアジに手が伸びる。ただし、脂の極端なのりはないものの味がある魚なのである。アジ科ならではのうま味成分がたっぷりで、微かに酸味があるので後味がいい。今回の個体は体長31cm・531gなので、やや小振りだ。これを素直に刺身にする。 今、「深川飯」というのがあるが、あれはそんなに古い言語ではない。今、深川飯には炊き込みご飯と、ぶっかけ飯があるが、ともに剥き身を使う。殻付きよりも少し高くつくし、料理店で剥き身にするにも手間がかかる。あれは明らかに家庭料理ではなく、料理店の料理だろう。ちなみに深川とは現在の江東区佐賀町と深川不動周辺、“江戸の高速道路”小名木川大川(隅田川)より、のこと。このあたりは明暦の大火(1657)までは純粋な猟師町だったが、じょじょに宅地化や御家人の住居が作られる。江戸時代の初めには佐賀町から新荒川近くの大島までの海岸線でとれていたアサリも、徐々に東へ東へと産地が遠くなる。江戸時代江戸の町にきていた貝の行商はアサリ、シジミが基本で、まれにハマグリを売ることもあっただろう。アサリは生きたもの(貝殻のついたもの)だけではなく、剥き身もあった。もともと貝の行商は今現在の江東区の人達が産地直送していたのが、船橋など下総に移る。その内、上総、木更津、富津が本場になる。なぜか? 自然の海岸線を無闇にコンクリートで固め始めたからだ。明治、大正生まれの聞き書きを読むと、明治時代末から昭和の高度成長期まで、貝類は小名木川の舟運で現千葉県市川・船橋などから運んでいたらしい。その運河沿いに点々と飯を食べられる屋台があった。その基本がアサリのみそ汁と飯だ。アサリでご飯を食べる、この基本は炊き込みご飯やぶっかけ飯ではなく、殻付きアサリのみそ汁のかけ飯、もしくはみそ汁をおかずにご飯を食べるものだったことは明白である。要するに手っ取り早い忙しい飯だ。
今、「深川飯」というのがあるが、あれはそんなに古い言語ではない。今、深川飯には炊き込みご飯と、ぶっかけ飯があるが、ともに剥き身を使う。殻付きよりも少し高くつくし、料理店で剥き身にするにも手間がかかる。あれは明らかに家庭料理ではなく、料理店の料理だろう。ちなみに深川とは現在の江東区佐賀町と深川不動周辺、“江戸の高速道路”小名木川大川(隅田川)より、のこと。このあたりは明暦の大火(1657)までは純粋な猟師町だったが、じょじょに宅地化や御家人の住居が作られる。江戸時代の初めには佐賀町から新荒川近くの大島までの海岸線でとれていたアサリも、徐々に東へ東へと産地が遠くなる。江戸時代江戸の町にきていた貝の行商はアサリ、シジミが基本で、まれにハマグリを売ることもあっただろう。アサリは生きたもの(貝殻のついたもの)だけではなく、剥き身もあった。もともと貝の行商は今現在の江東区の人達が産地直送していたのが、船橋など下総に移る。その内、上総、木更津、富津が本場になる。なぜか? 自然の海岸線を無闇にコンクリートで固め始めたからだ。明治、大正生まれの聞き書きを読むと、明治時代末から昭和の高度成長期まで、貝類は小名木川の舟運で現千葉県市川・船橋などから運んでいたらしい。その運河沿いに点々と飯を食べられる屋台があった。その基本がアサリのみそ汁と飯だ。アサリでご飯を食べる、この基本は炊き込みご飯やぶっかけ飯ではなく、殻付きアサリのみそ汁のかけ飯、もしくはみそ汁をおかずにご飯を食べるものだったことは明白である。要するに手っ取り早い忙しい飯だ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に愛知県産のイワガキが来ていた。愛知県としか書いていないが伊良湖半島と知多半島の先端を線で繋げる、その線上にある愛知県の離島、篠島あたりでとれたものだろう。イワガキを昔々から食べていたのは秋田県、山形県、新潟県、鳥取県と千葉県・茨城県をはじめとする関東周辺だと思っている。その限定的な食文化が、今や全国区となっているのは、まことに喜ばしいものである。豊洲などで知らない産地のイワガキを見つけるとうれしくてたまらない。食いたくなったらむいて食えばいいだけなので、料理というよりも味見である。厳密には産地での味の違いは感じているけれど、ボクには順位がつけられない。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に愛知県産のイワガキが来ていた。愛知県としか書いていないが伊良湖半島と知多半島の先端を線で繋げる、その線上にある愛知県の離島、篠島あたりでとれたものだろう。イワガキを昔々から食べていたのは秋田県、山形県、新潟県、鳥取県と千葉県・茨城県をはじめとする関東周辺だと思っている。その限定的な食文化が、今や全国区となっているのは、まことに喜ばしいものである。豊洲などで知らない産地のイワガキを見つけるとうれしくてたまらない。食いたくなったらむいて食えばいいだけなので、料理というよりも味見である。厳密には産地での味の違いは感じているけれど、ボクには順位がつけられない。 八王子綜合卸売センター八百角に、たぶん地物(関東周辺)だと思われる山椒の葉が入荷してきている。栽培ものよりも遙かに葉が大きく、料理店では飾りには使いにくい。我が家ではこれを平気で飾りにも使い、木ノ芽味噌や木の芽焼きなど本来の使い方でも使う。同時に、このところ八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に見事なアイナメがやってきている。アイナメを買うなら活魚だと思っているので、少々贅沢だけど魚屋で血まみれのアイナメをためつすがめつする日々の到来である。
八王子綜合卸売センター八百角に、たぶん地物(関東周辺)だと思われる山椒の葉が入荷してきている。栽培ものよりも遙かに葉が大きく、料理店では飾りには使いにくい。我が家ではこれを平気で飾りにも使い、木ノ芽味噌や木の芽焼きなど本来の使い方でも使う。同時に、このところ八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に見事なアイナメがやってきている。アイナメを買うなら活魚だと思っているので、少々贅沢だけど魚屋で血まみれのアイナメをためつすがめつする日々の到来である。 つれづれなるままに。ほんの数年前までボクは、水産業とも動物学・植物学ともまったく関わりのない世界、非常に流行りとかトレンドとかを扱う世界の片隅にもいたのだ。学校を卒業して、そこで仕事を始めたとき、同時に水産生物をなんとなくではなく基礎から調べ始めた。そのとき神保町大学の先人から絶対に専門家になってはいけないと教わる。技術的な分野なら専門家になってもいいが、いわゆる文化をやるなら、「専門家=死」とも言われている。ということで、専門分野は死にものぐるいでやりながらも、まったく違う角度、素人・遠目の自分を存在させている、つもりだ。さてそこで、今回のイボダイの話に移る。標準和名イボダイは明治時代半ばには〈エボダイ〉が標準和名だった。田中茂穂はイボダイを標準和名としながらも、〈東京では訛ってエボダイということが多い〉とある。ちなみに「疣鯛」は体表から粘液を出すための名で、詳しくは述べない。ちなみにこの時代の標準和名が東京と神奈川なのは、動物学の本拠地でもある東京帝国大学理科大学が東京都本郷にあり、研究所が神奈川県江の島・三崎にあった。その周辺で呼び名を採取したからである。それにしても内村鑑三が魚類学者であったときの「エボダイ」を、東京の訛りだとしてイボダイにした犯人がわからない。【話の寄り道】 標準和名は国内での動物学の土台を作りあげた、箕作佳吉(安政4〜明治42/1858〜1909 14歳で大学南校からアメリカに渡米。日本人最初の動物学者)や石川千代松が、Standard Japanese name (標準和名)を決めることから始める。念のために、Standard Japanese name はあくまでも科学の分野での名前である。正しい名前などというものではない。これはモースと、動物学の教師ではないがヒルゲンドルフの時代から始まっていたはずだが、やはり本格的になるのは箕作佳吉以後だろう。
つれづれなるままに。ほんの数年前までボクは、水産業とも動物学・植物学ともまったく関わりのない世界、非常に流行りとかトレンドとかを扱う世界の片隅にもいたのだ。学校を卒業して、そこで仕事を始めたとき、同時に水産生物をなんとなくではなく基礎から調べ始めた。そのとき神保町大学の先人から絶対に専門家になってはいけないと教わる。技術的な分野なら専門家になってもいいが、いわゆる文化をやるなら、「専門家=死」とも言われている。ということで、専門分野は死にものぐるいでやりながらも、まったく違う角度、素人・遠目の自分を存在させている、つもりだ。さてそこで、今回のイボダイの話に移る。標準和名イボダイは明治時代半ばには〈エボダイ〉が標準和名だった。田中茂穂はイボダイを標準和名としながらも、〈東京では訛ってエボダイということが多い〉とある。ちなみに「疣鯛」は体表から粘液を出すための名で、詳しくは述べない。ちなみにこの時代の標準和名が東京と神奈川なのは、動物学の本拠地でもある東京帝国大学理科大学が東京都本郷にあり、研究所が神奈川県江の島・三崎にあった。その周辺で呼び名を採取したからである。それにしても内村鑑三が魚類学者であったときの「エボダイ」を、東京の訛りだとしてイボダイにした犯人がわからない。【話の寄り道】 標準和名は国内での動物学の土台を作りあげた、箕作佳吉(安政4〜明治42/1858〜1909 14歳で大学南校からアメリカに渡米。日本人最初の動物学者)や石川千代松が、Standard Japanese name (標準和名)を決めることから始める。念のために、Standard Japanese name はあくまでも科学の分野での名前である。正しい名前などというものではない。これはモースと、動物学の教師ではないがヒルゲンドルフの時代から始まっていたはずだが、やはり本格的になるのは箕作佳吉以後だろう。 自分の食べているものをちゃんとメモしておきな、と言ったのは、まさかこんなところで会いたくないなと思った顔見知りのさる職業の人だ。まあ人間の体のプロが言うことだし、せっかく生まれて初めての健康診断なのだから、やってみんべ、と思った次第である。1日の内で食事らしい食事は朝ご飯だけだ。他はものすごい量の魚介類料理を作っているので、ダラダラ食いとなる。早朝からだって魚料理を作っているので、やはり朝ご飯も魚介類が主役なのは悲しいけど、これが現実だ。この日の主役は高知県産シログチである。刺身にしてもっともおいしい魚だが、食文化的な理由で扱いが悪い。だいたい全国的に見ても、本種を生では食べない。昔、日生(岡山県備前市)でヒラ刺網を見ていたとき、見事な「ぐち(シログチ)」を見つけて、物欲しそうに見ていたら「ほらよ」といただいたことがある。「刺身にしたらこっち(ヒラ)より上ですよね」と言ったら、「バカ言うでない(意訳)」と言われた。あれだけ魚食いに長けた岡山でも、シログチの刺身はそんなに普通ではない、ようなのだ。ご飯、福島県相馬市タマゴヤの朝鮮漬、キウイ、ワカメの味噌汁以外をば。シログチの焼霜造り・刺身/実に脂が豊か、身に張りがありうま味も豊かで、ご飯の甘味と一緒になって無茶苦茶でござりまする、と言うくらいうまい。マサバのみそ煮/アニサキス探しのために大量にさばいたマサバの一部を、山内麹店(福島県南会津町只見)の梁取みそで煮たもの。塩分濃度の高いみそを少量使いにして作ったものだが、このみそ実に風味がいい。平凡な料理の方が飯に合う、と食べたものを振り返るたびに感じる。
自分の食べているものをちゃんとメモしておきな、と言ったのは、まさかこんなところで会いたくないなと思った顔見知りのさる職業の人だ。まあ人間の体のプロが言うことだし、せっかく生まれて初めての健康診断なのだから、やってみんべ、と思った次第である。1日の内で食事らしい食事は朝ご飯だけだ。他はものすごい量の魚介類料理を作っているので、ダラダラ食いとなる。早朝からだって魚料理を作っているので、やはり朝ご飯も魚介類が主役なのは悲しいけど、これが現実だ。この日の主役は高知県産シログチである。刺身にしてもっともおいしい魚だが、食文化的な理由で扱いが悪い。だいたい全国的に見ても、本種を生では食べない。昔、日生(岡山県備前市)でヒラ刺網を見ていたとき、見事な「ぐち(シログチ)」を見つけて、物欲しそうに見ていたら「ほらよ」といただいたことがある。「刺身にしたらこっち(ヒラ)より上ですよね」と言ったら、「バカ言うでない(意訳)」と言われた。あれだけ魚食いに長けた岡山でも、シログチの刺身はそんなに普通ではない、ようなのだ。ご飯、福島県相馬市タマゴヤの朝鮮漬、キウイ、ワカメの味噌汁以外をば。シログチの焼霜造り・刺身/実に脂が豊か、身に張りがありうま味も豊かで、ご飯の甘味と一緒になって無茶苦茶でござりまする、と言うくらいうまい。マサバのみそ煮/アニサキス探しのために大量にさばいたマサバの一部を、山内麹店(福島県南会津町只見)の梁取みそで煮たもの。塩分濃度の高いみそを少量使いにして作ったものだが、このみそ実に風味がいい。平凡な料理の方が飯に合う、と食べたものを振り返るたびに感じる。 静岡県熱海市熱海魚市場から『ぶーちゃんのたまご焼き』、そこから商店街をことこと歩いて最初にたどり着いたのが杉本鰹節店だ。店内に入るやいなやの削り節の香りがんともいえずいい。鰹節にさば節の削り節があり、そのとなりに目的のものを発見する。偶然にも「そうだ削り節」がなくなっていたのだ。削り節を量り売りしてくれる店は、今や東京都内にもほとんど見かけない。削り節はできれば200gずつ買いたいので、これは由々しきことなのだ。その上、スーパーで買えるメーカーものの袋入りは高すぎるのである。熱海市のすごいところは、商店街の一角に庶民的な削り節の店が残っていることかも知れない。我が家からいちばん近い削り節の店は川崎北部なので渋滞を考えると往復2時間以上、場合によっては3時間かかる。久しぶりの削り節店での買い物に少々舞い上がって300gも買ってしまった。しかも乾物屋の長居くらい好きなものはないのに数軒先のパン屋に気をとられて、じっくり店内を見ていない。店内に微かに引っかかる事があったのに、軽く流してしまったことが大失敗だったことに後で気がついた。さて、今回の「そうだ削り節薄削り」はとてもよいものだった。良識的な話になるが一般家庭では薄削りの方が使いやすい。今回は昆布だしに「そうだ削り節薄削り」中心でだしをとる。
静岡県熱海市熱海魚市場から『ぶーちゃんのたまご焼き』、そこから商店街をことこと歩いて最初にたどり着いたのが杉本鰹節店だ。店内に入るやいなやの削り節の香りがんともいえずいい。鰹節にさば節の削り節があり、そのとなりに目的のものを発見する。偶然にも「そうだ削り節」がなくなっていたのだ。削り節を量り売りしてくれる店は、今や東京都内にもほとんど見かけない。削り節はできれば200gずつ買いたいので、これは由々しきことなのだ。その上、スーパーで買えるメーカーものの袋入りは高すぎるのである。熱海市のすごいところは、商店街の一角に庶民的な削り節の店が残っていることかも知れない。我が家からいちばん近い削り節の店は川崎北部なので渋滞を考えると往復2時間以上、場合によっては3時間かかる。久しぶりの削り節店での買い物に少々舞い上がって300gも買ってしまった。しかも乾物屋の長居くらい好きなものはないのに数軒先のパン屋に気をとられて、じっくり店内を見ていない。店内に微かに引っかかる事があったのに、軽く流してしまったことが大失敗だったことに後で気がついた。さて、今回の「そうだ削り節薄削り」はとてもよいものだった。良識的な話になるが一般家庭では薄削りの方が使いやすい。今回は昆布だしに「そうだ削り節薄削り」中心でだしをとる。 明治三十三年(1900)十月十五、正岡子規は死の2年前であり、寝返りはおろか仰臥するか体を左に向けておくのが精一杯になる。そんな状態にあっても日光が窓に差し込んでくると、〈午時(正午)は近づきたり〉と飯を待つ気持ちが募るのが子規らしいところだ。ほどなく母、八重が長方形の膳に飯、一汁一菜をのせて来る。〈あたたかきやはらかき飯、堅魚の刺肉(さしみ)、薩摩芋の味噌汁の三種なり。皆好物なるが上に配合殊に善ければうまき事おびただし。飯二碗半、汁二椀、刺肉食ひ尽くす〉地獄のような苦しみを感じながら綴られる、正岡子規の文章の簡明さに恐れ入るしかない。さて、薩摩芋の味噌汁は学生時代に正岡子規の文章で知っていたことを、フロッピーを変換して判明した。記憶力が悪いのでいつもお初だと思ってしまう。ちなみに堅魚(カツオ)の刺肉と薩摩芋の味噌汁はとても合う。確かにこの組み合わせで食う飯はうまい。カツオは1900年にはまだ魚介類を氷で冷やしていなかったことからして、千葉県銚子産で舟運を使って一晩で日本橋の魚河岸に持ち込んだものだろう。このときすでに利根運河は完成しており、江戸時代以来の大動脈は関宿町まで北上しなくてよくなっている。ちなみに当時、新暦の10月は比較的涼しかった。群馬県や東京都多摩地区で初霜の降りる時季だ。相模湾からでも千葉県からでも、カツオを生の状態で運べる期間は春と秋に限られていたのである。秋のカツオを正岡子規が食べられるのは明治34年を残すのみ。『飯待つ間』(岩波文庫)
明治三十三年(1900)十月十五、正岡子規は死の2年前であり、寝返りはおろか仰臥するか体を左に向けておくのが精一杯になる。そんな状態にあっても日光が窓に差し込んでくると、〈午時(正午)は近づきたり〉と飯を待つ気持ちが募るのが子規らしいところだ。ほどなく母、八重が長方形の膳に飯、一汁一菜をのせて来る。〈あたたかきやはらかき飯、堅魚の刺肉(さしみ)、薩摩芋の味噌汁の三種なり。皆好物なるが上に配合殊に善ければうまき事おびただし。飯二碗半、汁二椀、刺肉食ひ尽くす〉地獄のような苦しみを感じながら綴られる、正岡子規の文章の簡明さに恐れ入るしかない。さて、薩摩芋の味噌汁は学生時代に正岡子規の文章で知っていたことを、フロッピーを変換して判明した。記憶力が悪いのでいつもお初だと思ってしまう。ちなみに堅魚(カツオ)の刺肉と薩摩芋の味噌汁はとても合う。確かにこの組み合わせで食う飯はうまい。カツオは1900年にはまだ魚介類を氷で冷やしていなかったことからして、千葉県銚子産で舟運を使って一晩で日本橋の魚河岸に持ち込んだものだろう。このときすでに利根運河は完成しており、江戸時代以来の大動脈は関宿町まで北上しなくてよくなっている。ちなみに当時、新暦の10月は比較的涼しかった。群馬県や東京都多摩地区で初霜の降りる時季だ。相模湾からでも千葉県からでも、カツオを生の状態で運べる期間は春と秋に限られていたのである。秋のカツオを正岡子規が食べられるのは明治34年を残すのみ。『飯待つ間』(岩波文庫) 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産は若い衆ががんばっている。日々こつこつと地道な努力を重ねているのが頼もしい。それが証拠に彼らが作るマアジや小肌(コノシロの若い個体)の開きがだんだん上等になってきているのだ。せっかくなのでお昼ご飯に開きを買って来る。本当は酢じめにすべきものだが、今回は天ぷらを作るつもりだ。もちろん文字の世界ではあるが、この日のボクは脳みそが江戸の町に飛んでしまっている。川端の安い天ぷら屋台の情景を描きながら、大きさを揃えて袋に放り込む。文字の世界のよいところは、前日まで1220年代、後鳥羽上皇の傍若無人から、その翌日には江戸時代後期の物価のこと、庶民の世界に迷い込むことができる、ことだ。そのときボクは四文銭二、三枚を懐に、じゃらじゃらさせて歩く江戸の町民そのものになりきっていたのだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産は若い衆ががんばっている。日々こつこつと地道な努力を重ねているのが頼もしい。それが証拠に彼らが作るマアジや小肌(コノシロの若い個体)の開きがだんだん上等になってきているのだ。せっかくなのでお昼ご飯に開きを買って来る。本当は酢じめにすべきものだが、今回は天ぷらを作るつもりだ。もちろん文字の世界ではあるが、この日のボクは脳みそが江戸の町に飛んでしまっている。川端の安い天ぷら屋台の情景を描きながら、大きさを揃えて袋に放り込む。文字の世界のよいところは、前日まで1220年代、後鳥羽上皇の傍若無人から、その翌日には江戸時代後期の物価のこと、庶民の世界に迷い込むことができる、ことだ。そのときボクは四文銭二、三枚を懐に、じゃらじゃらさせて歩く江戸の町民そのものになりきっていたのだ。 静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた、いろいろな魚を一緒に煮つけにする。ダメになりそうな大根も一緒に煮たので、我が家の経済にもよろしいかも。このいろんなものを一緒に煮ることを「ごった煮」といい、庶民の経済だけではなく地球に優しいのだという話をしたい。若い世代で温暖化に関して危機感があるとかの報道があるのに、かたや膨大な天然飼料を膨大なエネルギーを使って消費し、温暖化を急激に進める養殖サーモンのブームだとか、遠く南氷洋まで膨大なエネルギーを使っての捕鯨の復活だとかを、まるで喜ばしいかのごとき報道がなされている。核の脅威に終末時計があるなら、生の無駄使い、エネルギーの使いすぎにも終末時計があってしかるべきだ。人間は、生をほとんど総てを地球の生き物から得ているのに、その生き物を追い込んでもいいのか? をまったく報じない。漁師さんなどの「ごった煮」は野菜は少しだけで様々な魚介類をごったに煮たものをいう。卑小なことのように思われるかも知れないが、ここに生物の生存確率を上げ、水産業の未来を明るくする可能性を感じる。兵庫姫路市の沖合いに坊勢島がある。ここで御馳走になった「ごった煮」は、底曳き網の水揚げの情景が見えるようなものだった。いろんな魚が混じることで生まれる味の相乗効果があるし、底曳き網の魚を無駄なく食べる知恵もある。富山県氷見市の「かぶす汁」にもそれがいえる。消費者も、野菜でも刺身の残りでも、スーパーで特売しているあらでもなんでもかんでも放り込んで「ごった煮」を作ろうよ、といいたい。
静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた、いろいろな魚を一緒に煮つけにする。ダメになりそうな大根も一緒に煮たので、我が家の経済にもよろしいかも。このいろんなものを一緒に煮ることを「ごった煮」といい、庶民の経済だけではなく地球に優しいのだという話をしたい。若い世代で温暖化に関して危機感があるとかの報道があるのに、かたや膨大な天然飼料を膨大なエネルギーを使って消費し、温暖化を急激に進める養殖サーモンのブームだとか、遠く南氷洋まで膨大なエネルギーを使っての捕鯨の復活だとかを、まるで喜ばしいかのごとき報道がなされている。核の脅威に終末時計があるなら、生の無駄使い、エネルギーの使いすぎにも終末時計があってしかるべきだ。人間は、生をほとんど総てを地球の生き物から得ているのに、その生き物を追い込んでもいいのか? をまったく報じない。漁師さんなどの「ごった煮」は野菜は少しだけで様々な魚介類をごったに煮たものをいう。卑小なことのように思われるかも知れないが、ここに生物の生存確率を上げ、水産業の未来を明るくする可能性を感じる。兵庫姫路市の沖合いに坊勢島がある。ここで御馳走になった「ごった煮」は、底曳き網の水揚げの情景が見えるようなものだった。いろんな魚が混じることで生まれる味の相乗効果があるし、底曳き網の魚を無駄なく食べる知恵もある。富山県氷見市の「かぶす汁」にもそれがいえる。消費者も、野菜でも刺身の残りでも、スーパーで特売しているあらでもなんでもかんでも放り込んで「ごった煮」を作ろうよ、といいたい。 静岡県熱海市、熱海魚市場に飲食店はない。市場に数時間立って右往左往していると矢鱈に腹が減るので、非常に残念、だ。話は変わる、ボクはFBでほぼ友達申請をしない。危険な方だけやっている。危険と言っても相手から申請されると失礼に当たるという危険である。いつの頃からか、FBで、たびたびおいしそーうな、卵焼きの画像が登場するようになった。これが熱海市にある、『ぶーちゃんのたまご焼き』だと気づいたのは最近のことである。卵焼きなら申請したかもわからないけど、この謎の店の卵焼きがFBに登場するのが謎であった。ちなみにFBで個人的な情報はいっさい見ないので、よほど卵焼きに惹かれたのだと思う。さて、話を5月10日にもどすと、案内して頂いた宇田水産の宇田勝さんに教わった、鰹節店を目指していたのである。信号でとまって、ひょいっと左を見るとなんと「ぶーちゃん」があったのである。この辺なのかなとは思ったものの、思わず違法駐車して訪ねたら朝ご飯が食べられるという。やれやれうれし、とカウンターに座ったら、とっても店の雰囲気がいい、じゃあーりませんか。たぶんぶーちゃんの奥さんが明るいし、お子様がお子様らしくていいからだろう。ちなみにボクは魚の子供よりも、人間のお子様が好きなのである。特に特に大騒ぎして、びゅんびゅん飛び回るような新鮮なお子様が好き。ぎゃーぎゃー泣いているのなんぞ見ると心が穏やかになる。(注/もちろん食べ物としてではなく、一緒に大騒ぎするのが好きなのよ)奥から本物のぶーちゃんが出て来たのに驚いた。ボクもぶーちゃん、彼もぶーちゃん、なのだ。
静岡県熱海市、熱海魚市場に飲食店はない。市場に数時間立って右往左往していると矢鱈に腹が減るので、非常に残念、だ。話は変わる、ボクはFBでほぼ友達申請をしない。危険な方だけやっている。危険と言っても相手から申請されると失礼に当たるという危険である。いつの頃からか、FBで、たびたびおいしそーうな、卵焼きの画像が登場するようになった。これが熱海市にある、『ぶーちゃんのたまご焼き』だと気づいたのは最近のことである。卵焼きなら申請したかもわからないけど、この謎の店の卵焼きがFBに登場するのが謎であった。ちなみにFBで個人的な情報はいっさい見ないので、よほど卵焼きに惹かれたのだと思う。さて、話を5月10日にもどすと、案内して頂いた宇田水産の宇田勝さんに教わった、鰹節店を目指していたのである。信号でとまって、ひょいっと左を見るとなんと「ぶーちゃん」があったのである。この辺なのかなとは思ったものの、思わず違法駐車して訪ねたら朝ご飯が食べられるという。やれやれうれし、とカウンターに座ったら、とっても店の雰囲気がいい、じゃあーりませんか。たぶんぶーちゃんの奥さんが明るいし、お子様がお子様らしくていいからだろう。ちなみにボクは魚の子供よりも、人間のお子様が好きなのである。特に特に大騒ぎして、びゅんびゅん飛び回るような新鮮なお子様が好き。ぎゃーぎゃー泣いているのなんぞ見ると心が穏やかになる。(注/もちろん食べ物としてではなく、一緒に大騒ぎするのが好きなのよ)奥から本物のぶーちゃんが出て来たのに驚いた。ボクもぶーちゃん、彼もぶーちゃん、なのだ。 まさか熱海に魚市場があるなんて、と思っている人も少なくないだろう。国内屈指の観光地で熱海市で、泊まることも、街歩きすることも、観光地なので観光することもできる。日本列島の京都にも負けないネームバリューと言えそうな気もする。ついでに長年関西に住んでいた谷崎潤一郎はやがて熱海に移り住む。名著、台所太平記の舞台でもある。両地の魅力拮抗するに、京都、熱海とのどっちつかずの自分に悩んでいたほどである。
まさか熱海に魚市場があるなんて、と思っている人も少なくないだろう。国内屈指の観光地で熱海市で、泊まることも、街歩きすることも、観光地なので観光することもできる。日本列島の京都にも負けないネームバリューと言えそうな気もする。ついでに長年関西に住んでいた谷崎潤一郎はやがて熱海に移り住む。名著、台所太平記の舞台でもある。両地の魅力拮抗するに、京都、熱海とのどっちつかずの自分に悩んでいたほどである。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で分けてもらったマグロの血合いぎしで作った塩マグロの出来上がりは5月5日だった。漬け上がってそろそろ二十日、今がいちばんうまいときかも知れない。お握りの作り方など書いても仕方がないが、ご飯に塩味をつけないのが自宅で食べるお握りのコツだと思っている。ご飯に味がない方が具の味が引き立つ。お握りの材料といってご飯と漬物くらい。大好きな甘い東京たくわんと、海苔はいただきもので、佐賀県有明海漁業協同組合のものだ。口溶け感がよく、香りがよく、味わいがしごく深い。干ものは熟成しないが塩蔵したものは熟成する。明らかに発酵ではない、塩と素材だけで生み出した味がする。お握りの具としては頂上の部類だと思う。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で分けてもらったマグロの血合いぎしで作った塩マグロの出来上がりは5月5日だった。漬け上がってそろそろ二十日、今がいちばんうまいときかも知れない。お握りの作り方など書いても仕方がないが、ご飯に塩味をつけないのが自宅で食べるお握りのコツだと思っている。ご飯に味がない方が具の味が引き立つ。お握りの材料といってご飯と漬物くらい。大好きな甘い東京たくわんと、海苔はいただきもので、佐賀県有明海漁業協同組合のものだ。口溶け感がよく、香りがよく、味わいがしごく深い。干ものは熟成しないが塩蔵したものは熟成する。明らかに発酵ではない、塩と素材だけで生み出した味がする。お握りの具としては頂上の部類だと思う。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。というのは何度も書いた。銭州の主要な釣り物はなにか? 意外にウメイロとアオダイではないかと思っている。シマアジ狙いや大物専門の方もいるが、基本はこの2種でいいと思う。2種は同じアオダイ属(同属と考えるとわかりやすい)の魚で、見た目も、下ろしても同じようにきれいである。面白いものであまりにもおいしい魚を食べると、どちらが上かとか下かではなく、種の違いさえもなくなる。ときどきどっちでもよくなるときがある。2種は釣れてうれしい魚そのものだと思うが、昨年から銭州でまとまって釣れているのがウメイロの方である。関東の人間にしかわからない話(関西なら紀伊半島になるのかな?)だが、知り合いの釣り人曰く、「外房へイサキを釣りに行くように釣れる」らしい。今季最初の銭州のウメイロは少し小振り体長29cm・769gを選んだ。ウメイロのよいところは、小さいものと大きいものとの、脂ののりの差がないことだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。というのは何度も書いた。銭州の主要な釣り物はなにか? 意外にウメイロとアオダイではないかと思っている。シマアジ狙いや大物専門の方もいるが、基本はこの2種でいいと思う。2種は同じアオダイ属(同属と考えるとわかりやすい)の魚で、見た目も、下ろしても同じようにきれいである。面白いものであまりにもおいしい魚を食べると、どちらが上かとか下かではなく、種の違いさえもなくなる。ときどきどっちでもよくなるときがある。2種は釣れてうれしい魚そのものだと思うが、昨年から銭州でまとまって釣れているのがウメイロの方である。関東の人間にしかわからない話(関西なら紀伊半島になるのかな?)だが、知り合いの釣り人曰く、「外房へイサキを釣りに行くように釣れる」らしい。今季最初の銭州のウメイロは少し小振り体長29cm・769gを選んだ。ウメイロのよいところは、小さいものと大きいものとの、脂ののりの差がないことだ。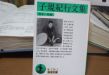 明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。
明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。



