コラム検索
検索条件
 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で分けてもらったマグロの血合いぎしで作った塩マグロの出来上がりは5月5日だった。漬け上がってそろそろ二十日、今がいちばんうまいときかも知れない。お握りの作り方など書いても仕方がないが、ご飯に塩味をつけないのが自宅で食べるお握りのコツだと思っている。ご飯に味がない方が具の味が引き立つ。お握りの材料といってご飯と漬物くらい。大好きな甘い東京たくわんと、海苔はいただきもので、佐賀県有明海漁業協同組合のものだ。口溶け感がよく、香りがよく、味わいがしごく深い。干ものは熟成しないが塩蔵したものは熟成する。明らかに発酵ではない、塩と素材だけで生み出した味がする。お握りの具としては頂上の部類だと思う。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で分けてもらったマグロの血合いぎしで作った塩マグロの出来上がりは5月5日だった。漬け上がってそろそろ二十日、今がいちばんうまいときかも知れない。お握りの作り方など書いても仕方がないが、ご飯に塩味をつけないのが自宅で食べるお握りのコツだと思っている。ご飯に味がない方が具の味が引き立つ。お握りの材料といってご飯と漬物くらい。大好きな甘い東京たくわんと、海苔はいただきもので、佐賀県有明海漁業協同組合のものだ。口溶け感がよく、香りがよく、味わいがしごく深い。干ものは熟成しないが塩蔵したものは熟成する。明らかに発酵ではない、塩と素材だけで生み出した味がする。お握りの具としては頂上の部類だと思う。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。というのは何度も書いた。銭州の主要な釣り物はなにか? 意外にウメイロとアオダイではないかと思っている。シマアジ狙いや大物専門の方もいるが、基本はこの2種でいいと思う。2種は同じアオダイ属(同属と考えるとわかりやすい)の魚で、見た目も、下ろしても同じようにきれいである。面白いものであまりにもおいしい魚を食べると、どちらが上かとか下かではなく、種の違いさえもなくなる。ときどきどっちでもよくなるときがある。2種は釣れてうれしい魚そのものだと思うが、昨年から銭州でまとまって釣れているのがウメイロの方である。関東の人間にしかわからない話(関西なら紀伊半島になるのかな?)だが、知り合いの釣り人曰く、「外房へイサキを釣りに行くように釣れる」らしい。今季最初の銭州のウメイロは少し小振り体長29cm・769gを選んだ。ウメイロのよいところは、小さいものと大きいものとの、脂ののりの差がないことだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。というのは何度も書いた。銭州の主要な釣り物はなにか? 意外にウメイロとアオダイではないかと思っている。シマアジ狙いや大物専門の方もいるが、基本はこの2種でいいと思う。2種は同じアオダイ属(同属と考えるとわかりやすい)の魚で、見た目も、下ろしても同じようにきれいである。面白いものであまりにもおいしい魚を食べると、どちらが上かとか下かではなく、種の違いさえもなくなる。ときどきどっちでもよくなるときがある。2種は釣れてうれしい魚そのものだと思うが、昨年から銭州でまとまって釣れているのがウメイロの方である。関東の人間にしかわからない話(関西なら紀伊半島になるのかな?)だが、知り合いの釣り人曰く、「外房へイサキを釣りに行くように釣れる」らしい。今季最初の銭州のウメイロは少し小振り体長29cm・769gを選んだ。ウメイロのよいところは、小さいものと大きいものとの、脂ののりの差がないことだ。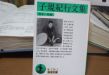 明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。
明治22年(1889)4月はじめに正岡子規(正岡常規・昇)は水戸に向けて歩行にて旅に出る。江戸川を渡って松戸駅(鉄道の駅ではなく宿と同じ)にいたり、そのまま足を伸ばして小金駅をこえる。12時近くになり草の屋で昼食をとる。〈我等を迎へしは身のたけ五尺五、六寸、体重は十七貫をはづれまじと覚ゆる大女なり。「菜は焼豆腐とひじきと鮫の煮たると也、いづれにやせんと問う。……」、さらば鮫にせんと……。一きれ食へば藁をくふが心地に吐き出したるに……〉場所は現、常磐線北小金駅あたり。サメの食べ方は東京都以北で煮つけ。三重県以南太平洋・瀬戸内海・九州で湯引き(ゆでる)だ。サメの種類も北はツノザメ科のアブラツノザメ、ネズミザメ科のネズミザメなど。南は主にドチザメ科のホシザメ・シロザメ・ドチザメ、カスザメ科のカスザメ・コロザメ、オオセ科のオオセ、エイになるがサカタザメ科のサカタザメ・コモンサカタザメなど多彩である。(日本海側や中国地方山間部のサメの食文化にはここでは触れない。)今現在も南北でサメの食文化が異なっている。常磐線開通前の水戸街道小金駅あたりで正岡子規が食べたサメは沖合いにいるネズミザメではなく、より岸近くにいるアブラツノザメと考えるべきだと思っている。 5月4日の遅い朝ご飯は「イカ焼きうどん」だった。東日本で、お昼にお好み焼きはあまりない。西日本に行くと、お昼ご飯がお好み焼きということが多々ある。最近、西の旅に出ていないので、昼前後になると、やけにこのお好み焼きのソースの香りが恋しい。昔、山口県岩国市で聞取していたまったく未知の人が連れて行ってくれたのも、お好み焼き屋だった。期待していただけに、岩国でなにもお好み焼きを食べることもない、とは思ったが、西日本で、お昼ご飯にお好み焼きの方が、むしろ自然なのだ。しかもミックスお好み焼きがとてもおいしかった。このときほど東日本と西日本の、お好み焼きの食べ物としての位置が違っていることを強く感じたことはない。ちょっと前のことだけど、徳島県徳島市のお好み焼き屋で、イカの焼きうどんを食べようと思ったとき、「豆玉」の文字が目に飛び込んできた。知り合いのDに甘い豆が入ったお好み焼き食べたことがありますか? と質問されたからだ。ちなみにこれ以前にも、このときもボクは「豆玉」をまったく、ほとんど食べていない。連れがほぼ全部食べてしまったからだ。イカ焼きうどんも食べていない。2人で3つ注文したときに、麺ものはそば(中華そば)がいいと連れが言ったからだ。できるだけ早く徳島県東部の「豆玉」を食べてみたいと思ったがすぐ忘れてしまっている。お好み焼き屋のイカうどんも食べたい。もちろんここ数年のことだけど、ボクのお好み焼きの麺の基本にあるのはうどんである。焼きうどんが好きだったときに、子供返りしているのだ。具の基本はイカで、特にスルメイカがいい。話が逸れ逸れになったが、連休中のボクに戻る。近所でスルメイカのげその特売をやっていた。買いました。それでは何を作りましょうとなり、いの一番にカゴに放り込んだのが蒸しうどんだったのである。焼きうどん作りは簡単である。材料を集める。キャベツ、この日はデルモンテのウスターソース(徳島では加賀屋のお好み焼きソースを使う)、蒸しうどん、板東粉(あおさ粉とも。アナアオサを特種な加工をほどこしてふりかけ状にしたもの)、鰹節粉だ。まずは蒸しうどんを流水でほぐす。水分をよくきる。げそ、キャベツは適当に切る。キャベツとげそを炒めて、うどんを加える。比較的ちゃんと炒めてウスターソースをかけてまた炒める。コショウを振る。これで出来上がり。なぜか、用意していたはずの板東粉がなかった。出したはずなのにないので、カツオ節粉だけかける。炒めたイカとソースはベスト相性だと思っている。ヒデとロザンナを聴くようである。うどんはむしろその愛を包み込むマントのようなものだ。蒸しうどん、もう一玉買えばよかったと思ったけどもう遅い。
5月4日の遅い朝ご飯は「イカ焼きうどん」だった。東日本で、お昼にお好み焼きはあまりない。西日本に行くと、お昼ご飯がお好み焼きということが多々ある。最近、西の旅に出ていないので、昼前後になると、やけにこのお好み焼きのソースの香りが恋しい。昔、山口県岩国市で聞取していたまったく未知の人が連れて行ってくれたのも、お好み焼き屋だった。期待していただけに、岩国でなにもお好み焼きを食べることもない、とは思ったが、西日本で、お昼ご飯にお好み焼きの方が、むしろ自然なのだ。しかもミックスお好み焼きがとてもおいしかった。このときほど東日本と西日本の、お好み焼きの食べ物としての位置が違っていることを強く感じたことはない。ちょっと前のことだけど、徳島県徳島市のお好み焼き屋で、イカの焼きうどんを食べようと思ったとき、「豆玉」の文字が目に飛び込んできた。知り合いのDに甘い豆が入ったお好み焼き食べたことがありますか? と質問されたからだ。ちなみにこれ以前にも、このときもボクは「豆玉」をまったく、ほとんど食べていない。連れがほぼ全部食べてしまったからだ。イカ焼きうどんも食べていない。2人で3つ注文したときに、麺ものはそば(中華そば)がいいと連れが言ったからだ。できるだけ早く徳島県東部の「豆玉」を食べてみたいと思ったがすぐ忘れてしまっている。お好み焼き屋のイカうどんも食べたい。もちろんここ数年のことだけど、ボクのお好み焼きの麺の基本にあるのはうどんである。焼きうどんが好きだったときに、子供返りしているのだ。具の基本はイカで、特にスルメイカがいい。話が逸れ逸れになったが、連休中のボクに戻る。近所でスルメイカのげその特売をやっていた。買いました。それでは何を作りましょうとなり、いの一番にカゴに放り込んだのが蒸しうどんだったのである。焼きうどん作りは簡単である。材料を集める。キャベツ、この日はデルモンテのウスターソース(徳島では加賀屋のお好み焼きソースを使う)、蒸しうどん、板東粉(あおさ粉とも。アナアオサを特種な加工をほどこしてふりかけ状にしたもの)、鰹節粉だ。まずは蒸しうどんを流水でほぐす。水分をよくきる。げそ、キャベツは適当に切る。キャベツとげそを炒めて、うどんを加える。比較的ちゃんと炒めてウスターソースをかけてまた炒める。コショウを振る。これで出来上がり。なぜか、用意していたはずの板東粉がなかった。出したはずなのにないので、カツオ節粉だけかける。炒めたイカとソースはベスト相性だと思っている。ヒデとロザンナを聴くようである。うどんはむしろその愛を包み込むマントのようなものだ。蒸しうどん、もう一玉買えばよかったと思ったけどもう遅い。 1970年前後、マアジの価値を上げたとされているのが、「あじのたたき」である。神奈川県小田原市周辺の料理で、「あじのたたきなます」ともいう。マアジを三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取り皮を聞く。これを細かく切ったものである。「みそたたき」、「なめろう」との違いは、サイコロ状の形が残った状態であること、味つけしていないところだ。しょうが、ねぎやみょうがなどの香辛野菜を使うなど徐々に変化しているが、もともとは漁師が船の上で作っていたものだ。一説に釣りのとき、コマセ(寄せエサ)がなくなり、釣れたアジ(マアジ)を細かく叩いてコマセに使ったとき、つまんでみたら美味であったので、作るようになったとも。小田原と東京との繋がりは深く、この「あじのたたき」が東京でも作られるようになり、あっと言う間に都内全域に広がる。■写真はもっとも基本的な「あじのたたき」。
1970年前後、マアジの価値を上げたとされているのが、「あじのたたき」である。神奈川県小田原市周辺の料理で、「あじのたたきなます」ともいう。マアジを三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取り皮を聞く。これを細かく切ったものである。「みそたたき」、「なめろう」との違いは、サイコロ状の形が残った状態であること、味つけしていないところだ。しょうが、ねぎやみょうがなどの香辛野菜を使うなど徐々に変化しているが、もともとは漁師が船の上で作っていたものだ。一説に釣りのとき、コマセ(寄せエサ)がなくなり、釣れたアジ(マアジ)を細かく叩いてコマセに使ったとき、つまんでみたら美味であったので、作るようになったとも。小田原と東京との繋がりは深く、この「あじのたたき」が東京でも作られるようになり、あっと言う間に都内全域に広がる。■写真はもっとも基本的な「あじのたたき」。 愛知県産クロダイを1尾かったら、いくつもの料理を撮影のために作ることになる。魚料理を作ったら、=それで食事となる。クロダイは中途半端な魚だと思っている。今、魚価が上昇傾向にある中、その上昇傾向に乗り遅れているのである。かなりの上物を買ってもお買い得感がある。高級魚だったのに大衆魚に成り下がっていると考えるとわかりやすいだろう。だから、日々気軽におかずにすればいいのだ。撮影のために作ったムニエルは、だれでも簡単に作れる普段着の料理だ。つけあわせの新じゃがの小じゃが、スナップエンドウは一緒に軽く塩ゆでして陸揚げに。にんじんも適当に切っておく。水洗いして三枚に下ろし、腹骨・血合い骨を取り、食べやすい大きさに切る。塩コショウして小麦粉まぶして、多めの油でじっくりソテーし、仕上げにマーガリン(バター)で風味づけする。このとき軽くゆでた小じゃが、にんじんも一緒にソテーする。あとは温めたパン、彩りのトマトと一緒にワンプレートに盛り付ける。クロダイ以外はあるものなんでもかまうことはない。料理にルールは無用である。これが遅すぎて、ぎりぎり午前中の、朝ご飯となる。ソテーしたクロダイの意外なほどの味のよさに感激するはずだ。強めにソテーした香ばしさと、身の豊潤さとに、味の大きな段差があるのがいい。自宅では、1ヶ月に1度しか飲まないコーヒーは、インスタントなのに上手に作れなかった。次の自宅コーヒーは来月だけど上手に作りたい。
愛知県産クロダイを1尾かったら、いくつもの料理を撮影のために作ることになる。魚料理を作ったら、=それで食事となる。クロダイは中途半端な魚だと思っている。今、魚価が上昇傾向にある中、その上昇傾向に乗り遅れているのである。かなりの上物を買ってもお買い得感がある。高級魚だったのに大衆魚に成り下がっていると考えるとわかりやすいだろう。だから、日々気軽におかずにすればいいのだ。撮影のために作ったムニエルは、だれでも簡単に作れる普段着の料理だ。つけあわせの新じゃがの小じゃが、スナップエンドウは一緒に軽く塩ゆでして陸揚げに。にんじんも適当に切っておく。水洗いして三枚に下ろし、腹骨・血合い骨を取り、食べやすい大きさに切る。塩コショウして小麦粉まぶして、多めの油でじっくりソテーし、仕上げにマーガリン(バター)で風味づけする。このとき軽くゆでた小じゃが、にんじんも一緒にソテーする。あとは温めたパン、彩りのトマトと一緒にワンプレートに盛り付ける。クロダイ以外はあるものなんでもかまうことはない。料理にルールは無用である。これが遅すぎて、ぎりぎり午前中の、朝ご飯となる。ソテーしたクロダイの意外なほどの味のよさに感激するはずだ。強めにソテーした香ばしさと、身の豊潤さとに、味の大きな段差があるのがいい。自宅では、1ヶ月に1度しか飲まないコーヒーは、インスタントなのに上手に作れなかった。次の自宅コーヒーは来月だけど上手に作りたい。 ウバガイの中にいる寄生虫で、人にはまったく害のない、貝にも迷惑かどうかわからない寄生虫である。ヒモムシともいう。ヒモビルは紐形動物門(ひもがたどうぶつもん)有針綱ヒモビル目ヒモビル科のヒモビルである。ウバガイ(ホッキガイ)を開き、外套膜周辺に比較的よく見かける生き物である。2cm〜3cmくらいあるので簡単に見つけることができる。
ウバガイの中にいる寄生虫で、人にはまったく害のない、貝にも迷惑かどうかわからない寄生虫である。ヒモムシともいう。ヒモビルは紐形動物門(ひもがたどうぶつもん)有針綱ヒモビル目ヒモビル科のヒモビルである。ウバガイ(ホッキガイ)を開き、外套膜周辺に比較的よく見かける生き物である。2cm〜3cmくらいあるので簡単に見つけることができる。 静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中に大きな「水フグ(ヨリトフグ)」が混ざっていた。大好きな魚で、こいつだけはどうしても食べたかったために分けていただいた。とは以前にも書いた。さて、湯引きと同じようなものだけど煮つけにしても絶品である。ついでに言うと、煮つけよりも冷やして煮凝りにしたほうがうまい。煮つけ=煮凝り、と思っても差し支えない。本種は無毒である。ただし原則的にフグ科の肝臓、卵巣は食用不可なので、ここでは素直に皮と筋肉だけを使う。
静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中に大きな「水フグ(ヨリトフグ)」が混ざっていた。大好きな魚で、こいつだけはどうしても食べたかったために分けていただいた。とは以前にも書いた。さて、湯引きと同じようなものだけど煮つけにしても絶品である。ついでに言うと、煮つけよりも冷やして煮凝りにしたほうがうまい。煮つけ=煮凝り、と思っても差し支えない。本種は無毒である。ただし原則的にフグ科の肝臓、卵巣は食用不可なので、ここでは素直に皮と筋肉だけを使う。 自分の食事を振り返って考える、という変なことを始めたから1月半以上がたつ。意外に面白いので続けていく。水産生物とヒトとの関わりを調べているので、スーパーの魚売り場はとても重要なのである。相馬市にはいくつかの魅力的なスーパーがあり、それぞれに特徴がある。魚が豊富な店で「にくもちがれい(ミギガレイ)」をたっぷり買って来た。非常に生息域の狭い魚で、漁業的には本州青森県から福島県までの太平洋沿岸の魚だと思っている。問題なのはおいしいのに、値が安いことだ。これは煮つけの地位低下と関係がある。煮つけのおいしさは食べればわかるものだが、作る人がいなくなっているのだ。さて、大きめの「にくもちがれい」のフライに、真子を集めて煮つけを主菜とした。この和食なのに洋食とされているフライと、江戸時代以来のしょうゆ味の煮つけがまったく別種の味わいで、それぞれご飯に合う。副菜は東京たくわんに、汁はトマト中心のみそ汁と非常にシンプルなやたらに遅い朝ご飯となったのは、この日、あまりにも整理しなければならない情報が多すぎたからだ。
自分の食事を振り返って考える、という変なことを始めたから1月半以上がたつ。意外に面白いので続けていく。水産生物とヒトとの関わりを調べているので、スーパーの魚売り場はとても重要なのである。相馬市にはいくつかの魅力的なスーパーがあり、それぞれに特徴がある。魚が豊富な店で「にくもちがれい(ミギガレイ)」をたっぷり買って来た。非常に生息域の狭い魚で、漁業的には本州青森県から福島県までの太平洋沿岸の魚だと思っている。問題なのはおいしいのに、値が安いことだ。これは煮つけの地位低下と関係がある。煮つけのおいしさは食べればわかるものだが、作る人がいなくなっているのだ。さて、大きめの「にくもちがれい」のフライに、真子を集めて煮つけを主菜とした。この和食なのに洋食とされているフライと、江戸時代以来のしょうゆ味の煮つけがまったく別種の味わいで、それぞれご飯に合う。副菜は東京たくわんに、汁はトマト中心のみそ汁と非常にシンプルなやたらに遅い朝ご飯となったのは、この日、あまりにも整理しなければならない情報が多すぎたからだ。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。銭州で釣ってくるのは、主にウメイロ、ナンヨウカイワリ、シマアジなどだ。この釣果を獺のごときにおっぴろげた中に見事なカンパチがあった。ほんの数年前に、元デルモのオネエサンに腹を引っ張られて、「こりゃだめだ、あんたも貴景勝のような固太りになりなさい」と言われたことがあるが、今回のカンパチなど貴景勝以上じゃないか、と思う。銭州は伊豆諸島神津島の南西にある。古く、春から初夏、大型のカンパチはこの海域で水揚げされていた。今、大型がじょじょに北上している。シオッコと呼ばれるサイズなど、北海道紋別でもとれる。相模湾北部でこのサイズが周年揚がるようになり、秋に北海道オホーツク海で成魚がとれる、のも時間の問題かも。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウは釣り名人の域に達しつつある。恐るべき釣果をこれでもかと見せびらかせて、ワハッハと笑っているが、笑いたくなるのも当然といった釣果である。銭州で釣ってくるのは、主にウメイロ、ナンヨウカイワリ、シマアジなどだ。この釣果を獺のごときにおっぴろげた中に見事なカンパチがあった。ほんの数年前に、元デルモのオネエサンに腹を引っ張られて、「こりゃだめだ、あんたも貴景勝のような固太りになりなさい」と言われたことがあるが、今回のカンパチなど貴景勝以上じゃないか、と思う。銭州は伊豆諸島神津島の南西にある。古く、春から初夏、大型のカンパチはこの海域で水揚げされていた。今、大型がじょじょに北上している。シオッコと呼ばれるサイズなど、北海道紋別でもとれる。相模湾北部でこのサイズが周年揚がるようになり、秋に北海道オホーツク海で成魚がとれる、のも時間の問題かも。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で魚を買っていたら、ボクの発泡に買っていないものが入っていた。「?」。 クマゴロウの妻に聞くと、「アレだそうです……」。そうだ、アレだ。お願いしたら、ちゃんとやってくれるところが、クマゴロウのすごいところである。このところ銭州で大釣りしているのも、日頃の行いがいいからだ。頼んでいたのは、売り物にならないマグロである。ただしよく見ると、今回の本マの切り身はそんなに悪くない。問題は少しだけ血合いがかぶっているくらいか。血合いぎしで売れそうでもある。ときは4月の始めに遡る。八王子の魚屋をかたっぱしからつかまえては、塩カツオのことを聞取していたのだ。中に西八王子の善さん(魚善)がいる。「カツオは作らないけどマグロで作るな」というのだ。以前、メジマグロ(クロマグロの若魚)で塩ガツオ的なものを作っているが、今回の場合は、魚屋がコロ(大物のマグロを三枚に下ろし、数等分した塊。ただし今現在、魚屋がコロを買うことはなくなりつつある)を買い、その切りつけた余りを使ったものである。だからマグロ屋でもある舵丸水産に問題ありのマグロを頼んでいたのだ。さて、ありがたく頂いて、少し成形する。切り落としたところは佃煮にする。これなど、誰が食べてもおいしいやろう! 的な味である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で魚を買っていたら、ボクの発泡に買っていないものが入っていた。「?」。 クマゴロウの妻に聞くと、「アレだそうです……」。そうだ、アレだ。お願いしたら、ちゃんとやってくれるところが、クマゴロウのすごいところである。このところ銭州で大釣りしているのも、日頃の行いがいいからだ。頼んでいたのは、売り物にならないマグロである。ただしよく見ると、今回の本マの切り身はそんなに悪くない。問題は少しだけ血合いがかぶっているくらいか。血合いぎしで売れそうでもある。ときは4月の始めに遡る。八王子の魚屋をかたっぱしからつかまえては、塩カツオのことを聞取していたのだ。中に西八王子の善さん(魚善)がいる。「カツオは作らないけどマグロで作るな」というのだ。以前、メジマグロ(クロマグロの若魚)で塩ガツオ的なものを作っているが、今回の場合は、魚屋がコロ(大物のマグロを三枚に下ろし、数等分した塊。ただし今現在、魚屋がコロを買うことはなくなりつつある)を買い、その切りつけた余りを使ったものである。だからマグロ屋でもある舵丸水産に問題ありのマグロを頼んでいたのだ。さて、ありがたく頂いて、少し成形する。切り落としたところは佃煮にする。これなど、誰が食べてもおいしいやろう! 的な味である。 自分の食事を振り返って考える、という変なことを始めたから1月半がたつ。意外に面白いので続けていく。ボクの場合、早朝に前日撮影準備した水産生物を撮影→画像の選択・保存、そのとき感じたことや、わかったことをテキスト化してサイトに反映する。過去の値段との比較もするので、早朝まんじゅう1個とお茶のみで、朝ご飯は早くても10時過ぎ、ときに11時近くになる。この日は、朝作って撮影した魚料理を中心に並べ終わったのが12時半なので、ほんまに朝ご飯なんかいな? と疑問に思ったりした。以下は作りましたるもの。【カツオの腹身の一夜干し】 福島県相馬市のスーパーで買い求めた腹身を立て塩に10分つけてほぼ1日干したもの。【クロダイの刺身】 一色産のクロダイはこの時点で脂が乗っていてうま味豊かであった。ご飯の時は濃口醤油ではなく、刺身醤油で食べる。【かすべの煮つけ】 福島県相馬市のスーパーで買ったツマリカスベの切り身を煮つけたもの。前日食べたものをそのまま冷蔵保存したら、見事に煮凝る。【フクロフノリの中華スープ】 福島県相馬市原釜で採取していたバアチャンに撮影用にいただいたもの。やはりフノリのみそ汁はおいしい。小皿に、大好きなスナップエンドウ(スナックエンドウと同じ物。ともに商品名の著作権が切れているので使い放題だと思う)と南相馬市タマゴヤの朝鮮漬。八王子綜合卸売センター八百角の社長がくれた謎のみかん。ちょっとだけ野菜が足らん気もする。
自分の食事を振り返って考える、という変なことを始めたから1月半がたつ。意外に面白いので続けていく。ボクの場合、早朝に前日撮影準備した水産生物を撮影→画像の選択・保存、そのとき感じたことや、わかったことをテキスト化してサイトに反映する。過去の値段との比較もするので、早朝まんじゅう1個とお茶のみで、朝ご飯は早くても10時過ぎ、ときに11時近くになる。この日は、朝作って撮影した魚料理を中心に並べ終わったのが12時半なので、ほんまに朝ご飯なんかいな? と疑問に思ったりした。以下は作りましたるもの。【カツオの腹身の一夜干し】 福島県相馬市のスーパーで買い求めた腹身を立て塩に10分つけてほぼ1日干したもの。【クロダイの刺身】 一色産のクロダイはこの時点で脂が乗っていてうま味豊かであった。ご飯の時は濃口醤油ではなく、刺身醤油で食べる。【かすべの煮つけ】 福島県相馬市のスーパーで買ったツマリカスベの切り身を煮つけたもの。前日食べたものをそのまま冷蔵保存したら、見事に煮凝る。【フクロフノリの中華スープ】 福島県相馬市原釜で採取していたバアチャンに撮影用にいただいたもの。やはりフノリのみそ汁はおいしい。小皿に、大好きなスナップエンドウ(スナックエンドウと同じ物。ともに商品名の著作権が切れているので使い放題だと思う)と南相馬市タマゴヤの朝鮮漬。八王子綜合卸売センター八百角の社長がくれた謎のみかん。ちょっとだけ野菜が足らん気もする。 静岡県熱海市の宇田水産、宇田勝さんに心太(ところてん)をいただく。ボクは太っていてデブな割りに「ところてん」が大好き。いただいていきなりうれしすぎて、ちゃんとお礼を言ったかどうか心配になる。主に紅藻類のマクサを採取して、お日様にさらしたものが、「天草」である。この「天草」を煮て、冷やして出来上がるのが「ところてん」だ。古代からの食品で古くは凝海藻(こもるは)と呼ばれていた。心太という漢字が出来て、「ところてん」と呼ばれるようになったのは江戸時代か、せいぜい室町時代だとされている。多種類の紅藻類テングサの仲間を使った寒天類は主に、長野県や岐阜県で作られていて、全国的だが、原藻を使って作る「ところてん」などが作られているのは海に近い地域である。紅藻類と言えば、東北日本海側の「えご」、「おきゅうと」もほぼ変わりがないものと考えた方がいいだろう。さっそく持ち帰って、天つきで突き出して、お昼ご飯の添える。作り方と言うよりも食べる準備と行った方がいいけれど。まず、湯で辛子を錬る。ガラスの器に氷を放り込んでおき、二杯酢を作る。その間にシャワーを浴びて、漁港で水揚げを見た後の塩気を体中から洗い流す。天つきでついて、冷やした器に放り込んだら出来上がりである。
静岡県熱海市の宇田水産、宇田勝さんに心太(ところてん)をいただく。ボクは太っていてデブな割りに「ところてん」が大好き。いただいていきなりうれしすぎて、ちゃんとお礼を言ったかどうか心配になる。主に紅藻類のマクサを採取して、お日様にさらしたものが、「天草」である。この「天草」を煮て、冷やして出来上がるのが「ところてん」だ。古代からの食品で古くは凝海藻(こもるは)と呼ばれていた。心太という漢字が出来て、「ところてん」と呼ばれるようになったのは江戸時代か、せいぜい室町時代だとされている。多種類の紅藻類テングサの仲間を使った寒天類は主に、長野県や岐阜県で作られていて、全国的だが、原藻を使って作る「ところてん」などが作られているのは海に近い地域である。紅藻類と言えば、東北日本海側の「えご」、「おきゅうと」もほぼ変わりがないものと考えた方がいいだろう。さっそく持ち帰って、天つきで突き出して、お昼ご飯の添える。作り方と言うよりも食べる準備と行った方がいいけれど。まず、湯で辛子を錬る。ガラスの器に氷を放り込んでおき、二杯酢を作る。その間にシャワーを浴びて、漁港で水揚げを見た後の塩気を体中から洗い流す。天つきでついて、冷やした器に放り込んだら出来上がりである。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産、活け締めのアイナメ(37cm ・963g)を買う。そろそろいい時季だというのもあるし、福島県相馬市の旅に出たついでに、この相双地区の郷土料理を作りたかったからだ。この絶品のアイナメで何を作るかというと、「たたき」である。岩手県、宮城県、福島県で「たたき」は細かく切った魚の身をねぎ、みそとたたいたものだ。宮城県では「みそたたき」という人もいる。ちなみに、震災前の原釜漁港で「アイナメのたたき、作りますか?」と聞いたことがある。ウミタナゴやホッケで作るが、アイナメでは作ったことがないという人が多かった。もちろん少人数に聞いただけで、『聞き書 福島の食』(農文協)には、しっかり相馬の郷土料理として登場している。「聞き書シリーズ」は1970年という急激な地域文化破壊年以前の、日常の食事に関する聞取であるため非常に重要な資料なのだ。 アニサキス症の責任は飲食店や魚屋が取るらしい。これは料理を提供する側に対して、あまりにも酷な話である。だいたい、それではアレルギー性のアニサキス症はだれが責任を取るのだろう。現在のアニサキス症の責任の所在に関しては、明らかに間違っていると思っている。さて、毎日毎日、アニサキス探しを続けている。寄生虫としてはアニサキスの線虫類と、扁形動物類に分けられるが、線虫類は断面が円形で細長いことで扁形動物と区別できる。さて、幼虫に関しては、硬骨魚類や軟体類内のアニサキスでもまずは内臓内で探す、筋肉に関してはつぶして水で濾して探せばなんとなかると思う。しかし幼虫でも小さな個体を探すのは容易ではないだろう。また、冷凍したら危険ではないというがアレルギーに関して、死んだ幼虫に抗体反応は起きないのか? 卵を取り込んだ場合にどうなるんだろう? などなど個人的に勉強しなければならぬことが多すぎる。
アニサキス症の責任は飲食店や魚屋が取るらしい。これは料理を提供する側に対して、あまりにも酷な話である。だいたい、それではアレルギー性のアニサキス症はだれが責任を取るのだろう。現在のアニサキス症の責任の所在に関しては、明らかに間違っていると思っている。さて、毎日毎日、アニサキス探しを続けている。寄生虫としてはアニサキスの線虫類と、扁形動物類に分けられるが、線虫類は断面が円形で細長いことで扁形動物と区別できる。さて、幼虫に関しては、硬骨魚類や軟体類内のアニサキスでもまずは内臓内で探す、筋肉に関してはつぶして水で濾して探せばなんとなかると思う。しかし幼虫でも小さな個体を探すのは容易ではないだろう。また、冷凍したら危険ではないというがアレルギーに関して、死んだ幼虫に抗体反応は起きないのか? 卵を取り込んだ場合にどうなるんだろう? などなど個人的に勉強しなければならぬことが多すぎる。 静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中に大きな「水フグ(ヨリトフグ)」が混ざっていた。大好きな魚で、こいつだけはどうしても食べたかったために分けていただいた。非常に昔の話になるが電動リールと言ったら深海のものしかなく、水深200mくらいなら手巻きであった。中深場釣りになると錘が重いので手巻きだと重労働なのだ。その重い仕掛けに白い風船、「水フグ」が2尾もついてくると、寒い時季でも汗が噴き出すくらいたいへんだった。この「水フグ」が3連発、すべてのハリについていようものなら、重いし、ハリス切れはするしでどうにもやりようがなかった。釣り師は捨てるが、これを船頭は拾って帰っていた。当時、下田の船宿で出してくれていたのが「水フグ」のみそ汁である、皮も肝も全部入ったみそ汁は想像を絶するうまさだった。こんなにうまい魚なのに、残念なことに今や相模湾では深刻な未利用魚なのだ。売れない魚の代表格で、売れなくしている犯人は厚生労働省である。フグをフグ調理師(県によって名称が違う)以外に出来なくしているためだ。完全に無毒のシロサバフグや本種などさえ、資格のない料理人に扱えなくしているのは非科学的である。フグは種の同定が出来、毒の部分を分けられるだけでいいはずだ。なのに技術面での制約がある。ついでに言わせてもらうと皮に毒のないトラフグの、皮の処理は安全とは何ら関わりがない。厚生労働省と各都道府県に、あの「水フグのみそ汁」を返せ! といいたい。
静岡県熱海市、網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中に大きな「水フグ(ヨリトフグ)」が混ざっていた。大好きな魚で、こいつだけはどうしても食べたかったために分けていただいた。非常に昔の話になるが電動リールと言ったら深海のものしかなく、水深200mくらいなら手巻きであった。中深場釣りになると錘が重いので手巻きだと重労働なのだ。その重い仕掛けに白い風船、「水フグ」が2尾もついてくると、寒い時季でも汗が噴き出すくらいたいへんだった。この「水フグ」が3連発、すべてのハリについていようものなら、重いし、ハリス切れはするしでどうにもやりようがなかった。釣り師は捨てるが、これを船頭は拾って帰っていた。当時、下田の船宿で出してくれていたのが「水フグ」のみそ汁である、皮も肝も全部入ったみそ汁は想像を絶するうまさだった。こんなにうまい魚なのに、残念なことに今や相模湾では深刻な未利用魚なのだ。売れない魚の代表格で、売れなくしている犯人は厚生労働省である。フグをフグ調理師(県によって名称が違う)以外に出来なくしているためだ。完全に無毒のシロサバフグや本種などさえ、資格のない料理人に扱えなくしているのは非科学的である。フグは種の同定が出来、毒の部分を分けられるだけでいいはずだ。なのに技術面での制約がある。ついでに言わせてもらうと皮に毒のないトラフグの、皮の処理は安全とは何ら関わりがない。厚生労働省と各都道府県に、あの「水フグのみそ汁」を返せ! といいたい。 4月19日、小田原魚市場には発泡に入りきらないタチウオの尾っぽが、あっちでひらひら、こっちでひらひらしている。と書いた。このとき二宮定置にいただいたタチウオを昨日やっと全部食べ尽くせた。日々慌ただしいので、忙しいときの救世主になった。いろいろ保存食にしたが、昨日のものは三枚に下ろして一口大に切り、塩コショウし、小麦粉をまぶした状態で冷凍したものだ。冷凍保存する場合はできるだけ、味つけしてからの方が劣化しない。
4月19日、小田原魚市場には発泡に入りきらないタチウオの尾っぽが、あっちでひらひら、こっちでひらひらしている。と書いた。このとき二宮定置にいただいたタチウオを昨日やっと全部食べ尽くせた。日々慌ただしいので、忙しいときの救世主になった。いろいろ保存食にしたが、昨日のものは三枚に下ろして一口大に切り、塩コショウし、小麦粉をまぶした状態で冷凍したものだ。冷凍保存する場合はできるだけ、味つけしてからの方が劣化しない。 福島県相馬市のスーパーで「にくもちがれい(ミギガレイ)」を2パック買って来た。この魚、まあまあたくさん揚がるのに産地周辺のみで流通している。低評価魚の代表格である。未利用魚を日本全国を見渡して話ができる人には会ったことがない。未利用の定義も曖昧だが、この魚のようにときにまとまって揚がりながら、売れないという魚を知っている人がいないのが残念でならない。未利用魚・低利用魚などもっとしっかり定義した方がいいと思うな。さて、この魚は水分が多いものの、料理法によっては非常にうまいのである。
福島県相馬市のスーパーで「にくもちがれい(ミギガレイ)」を2パック買って来た。この魚、まあまあたくさん揚がるのに産地周辺のみで流通している。低評価魚の代表格である。未利用魚を日本全国を見渡して話ができる人には会ったことがない。未利用の定義も曖昧だが、この魚のようにときにまとまって揚がりながら、売れないという魚を知っている人がいないのが残念でならない。未利用魚・低利用魚などもっとしっかり定義した方がいいと思うな。さて、この魚は水分が多いものの、料理法によっては非常にうまいのである。 カンパチはこのページにまとめることにした。まずは銭州産のカンパチでアニサキス探し。アニサキスは線虫動物門なので、同じように寄生する扁形動物門とは形態的に違うのだと思っている。なんと系統分類学の教科書までさかのぼって形態を頭に入れて探す。4㎏のカンパチを下ろしながら内臓を分けて最後には水に浮かせて探す。肝は半分つぶしてアニサキス科の線虫を探してみる。筋肉は腹部を半身分つぶしす。
カンパチはこのページにまとめることにした。まずは銭州産のカンパチでアニサキス探し。アニサキスは線虫動物門なので、同じように寄生する扁形動物門とは形態的に違うのだと思っている。なんと系統分類学の教科書までさかのぼって形態を頭に入れて探す。4㎏のカンパチを下ろしながら内臓を分けて最後には水に浮かせて探す。肝は半分つぶしてアニサキス科の線虫を探してみる。筋肉は腹部を半身分つぶしす。 朝っぱらから画像と個体を見続け同定していたら、右目がぼってり腫れてきた。目がつむれないので、ちょっとだけ息抜きにお握り図鑑を書く。ボクはバカにバカが好きだ。ついついバカの剥き身があると買ってしまう。といっても何が何だかわからないと思うが、バカガイ(青柳)の剥き身のことで活け(殻付き)よりも市場では普通である。舌のように見えるのが足でこの部分を刺身にする。あとに残るのはヒモ(外套膜)と水管だけど、今春はいきなり漬けにしている。バカヒモ漬けお握りが食べたいからだ。といっても簡単至極、ヒモと水管はきれいに薄い塩水の中で洗い、皮膜を取り除く。水分をよくきり、みりん・醤油の中につけ込む。漬け揚がったら(1時間くらいで漬け揚がる。漬けすぎても大丈夫)、お握りの具にするのだが、なんどやってもうまく出来ない。お握り型が小さすぎるのだと思っている。型なんて使うな、という市場人がいるが、不器用に輪を2つかけたようなボクはお握りが握れないのだ。
朝っぱらから画像と個体を見続け同定していたら、右目がぼってり腫れてきた。目がつむれないので、ちょっとだけ息抜きにお握り図鑑を書く。ボクはバカにバカが好きだ。ついついバカの剥き身があると買ってしまう。といっても何が何だかわからないと思うが、バカガイ(青柳)の剥き身のことで活け(殻付き)よりも市場では普通である。舌のように見えるのが足でこの部分を刺身にする。あとに残るのはヒモ(外套膜)と水管だけど、今春はいきなり漬けにしている。バカヒモ漬けお握りが食べたいからだ。といっても簡単至極、ヒモと水管はきれいに薄い塩水の中で洗い、皮膜を取り除く。水分をよくきり、みりん・醤油の中につけ込む。漬け揚がったら(1時間くらいで漬け揚がる。漬けすぎても大丈夫)、お握りの具にするのだが、なんどやってもうまく出来ない。お握り型が小さすぎるのだと思っている。型なんて使うな、という市場人がいるが、不器用に輪を2つかけたようなボクはお握りが握れないのだ。 網代漁業、網代魚市場で分けていただいた水産生物たちは、ボクにとっては至極面白すぎる魚たちだ。漁師さんにとっては迷惑な存在だが、料理好きならウッハウッハするものばかりでもある。選別していると、大量のウルメイワシがかなり痛んだ状態で出て来た。そこにキビナゴとカタクチイワシ、小さなヒメジ、マアジもある。半つぶれで、見た目は最悪だけど、別の見方をするとウマスギだしの素に見えてくる。ものすごく昔のことにになるが、千葉県勝浦市青灯(墨名)で会った定年退職釣り師のオヤジサンから、小サバやトウゴロウイワシのみそ汁のおいしさを教わっている。下ごしらえした小サバ(マサバ)をビニールに入れて持ち帰り作ったみそ汁の味は最高だった。以後、小サバの猛攻大歓迎となる。小魚をみたら、みそ汁だ、と思うようにもなった。今回、この小魚にユウレイイカを足してみそ汁を作る。
網代漁業、網代魚市場で分けていただいた水産生物たちは、ボクにとっては至極面白すぎる魚たちだ。漁師さんにとっては迷惑な存在だが、料理好きならウッハウッハするものばかりでもある。選別していると、大量のウルメイワシがかなり痛んだ状態で出て来た。そこにキビナゴとカタクチイワシ、小さなヒメジ、マアジもある。半つぶれで、見た目は最悪だけど、別の見方をするとウマスギだしの素に見えてくる。ものすごく昔のことにになるが、千葉県勝浦市青灯(墨名)で会った定年退職釣り師のオヤジサンから、小サバやトウゴロウイワシのみそ汁のおいしさを教わっている。下ごしらえした小サバ(マサバ)をビニールに入れて持ち帰り作ったみそ汁の味は最高だった。以後、小サバの猛攻大歓迎となる。小魚をみたら、みそ汁だ、と思うようにもなった。今回、この小魚にユウレイイカを足してみそ汁を作る。 網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中にハダカイワシが2個体混ざっていた。別に珍しい魚ではないが、久しぶりに味わえるであろう、珍味に舌が鳴る。ちなみに愛知県、三重県、高知県では干ものが名物となっている。ぜひこの珍味お試しあれ。たぶん、魚類中もっとも端的に味がいい魚のひとつである。味が濃いと言ってもいいし、味の量が多いと言ってもいいだろう。グリセリドなどの脂から来る濃厚さでもあるのだろう。あまりたくさんは食べられない。久しぶりなのでしっかりと検索する。検索すると種にたどり着けないという、不思議な迷路がハダカイワシ科にはある。結局、適当なところで断念してハダカイワシということにする。
網代漁業、網代魚市場で分けていただいた魚の中にハダカイワシが2個体混ざっていた。別に珍しい魚ではないが、久しぶりに味わえるであろう、珍味に舌が鳴る。ちなみに愛知県、三重県、高知県では干ものが名物となっている。ぜひこの珍味お試しあれ。たぶん、魚類中もっとも端的に味がいい魚のひとつである。味が濃いと言ってもいいし、味の量が多いと言ってもいいだろう。グリセリドなどの脂から来る濃厚さでもあるのだろう。あまりたくさんは食べられない。久しぶりなのでしっかりと検索する。検索すると種にたどり着けないという、不思議な迷路がハダカイワシ科にはある。結局、適当なところで断念してハダカイワシということにする。 くどいようだが、四国の人間にとってもっとも浮かんで来ない東京の地名が、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、武蔵村山市、東大和市だ。そんな東久留米市の市場で朝飯を食べた。市場内にはラーメン店、海鮮丼の店、食堂の3店舗がある。海鮮丼は水産物を調べている人間には鬼門である。つらつら思うに面白いことは面白いけど、丼上は今や迷宮のごときであって、食い物とは思えない。ラーメン店でラーメンという腹でもない。ちなみに通常の市場人(買い物が目的のという意味)にとって、市場飯は空腹を満たすためにある。あの店で●●食べなきゃ、なんてことは夢にも思わない。そんな欲求を満たすための市場飯は食堂がいちばんいい。市場内を2周回って『大丸食堂』に決めた。豊洲でも食堂飯が食いたいが、今やまったく食堂的な食堂がない。この市場のこの食堂も整然ときれいすぎるのが残念だが、品書きは魅力的である。できればトンカツ定食にしたかったが、この早朝のサイト運営がきつすぎて、胃の腑が受け付けそうにない。写真を見て、控えめな気持ちでミックスフライにする。女性二人だけの店ではないかと思うが、とてもテキパキとして、それほど待たされることもなく、アジフライ主役の定食がやってきた。あまりにも小ぎれいで市場らしくないよくできた定食だけど、それぞれに味はいい。アジフライの揚げ加減もいいし、マグロ類の肉を串に刺して揚げたのかな、と思うものもおいしい。もう少し市場らしい、ワイルドな感じが欲しい気がするものの、東久留米での市場飯はここかな。ほどほどに満たされた気分で、やたらに複雑な、幹線道路のない東京都西部地区の南北あみだくじ道路をくねくねと、くねらせて帰宅した。
くどいようだが、四国の人間にとってもっとも浮かんで来ない東京の地名が、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、武蔵村山市、東大和市だ。そんな東久留米市の市場で朝飯を食べた。市場内にはラーメン店、海鮮丼の店、食堂の3店舗がある。海鮮丼は水産物を調べている人間には鬼門である。つらつら思うに面白いことは面白いけど、丼上は今や迷宮のごときであって、食い物とは思えない。ラーメン店でラーメンという腹でもない。ちなみに通常の市場人(買い物が目的のという意味)にとって、市場飯は空腹を満たすためにある。あの店で●●食べなきゃ、なんてことは夢にも思わない。そんな欲求を満たすための市場飯は食堂がいちばんいい。市場内を2周回って『大丸食堂』に決めた。豊洲でも食堂飯が食いたいが、今やまったく食堂的な食堂がない。この市場のこの食堂も整然ときれいすぎるのが残念だが、品書きは魅力的である。できればトンカツ定食にしたかったが、この早朝のサイト運営がきつすぎて、胃の腑が受け付けそうにない。写真を見て、控えめな気持ちでミックスフライにする。女性二人だけの店ではないかと思うが、とてもテキパキとして、それほど待たされることもなく、アジフライ主役の定食がやってきた。あまりにも小ぎれいで市場らしくないよくできた定食だけど、それぞれに味はいい。アジフライの揚げ加減もいいし、マグロ類の肉を串に刺して揚げたのかな、と思うものもおいしい。もう少し市場らしい、ワイルドな感じが欲しい気がするものの、東久留米での市場飯はここかな。ほどほどに満たされた気分で、やたらに複雑な、幹線道路のない東京都西部地区の南北あみだくじ道路をくねくねと、くねらせて帰宅した。 アニサキスが気になってマサバを連日、小売店でも市場でも買って解体していた。その中で、料理して食べたのはなんと半身だけとは、欠食している方もいるこのご時世に申し訳ない。ただアニサキスの寄生率とまではいかないが、自分なりに何固体からアニサキスが出てくるか? 調べてみないわけにはいかない。中に冷凍マサバもありではあったが、主に太平洋側のもの5固体中1固体だけからアニサキスが出て来た。ちなみに筋肉からは出てこなかった。アニサキスライトを使ってすりつぶすようにして見たので間違いないだろう。廃棄、廃棄の連続であまりにも殺伐とした気分になったので、千葉県鴨川産の1固体だけ筋肉をつぶさないで作ったのが、「みそ煮」である。ちなみに「秋鯖」という言葉はおかしい。季語歳時記を最初にまとめたのは滝沢馬琴(1867-1848)だと思っている。この場合の季節は江戸のもので、例えば日本海側、ましてや九州には当てはまらない。もちろん温暖化で現東京の四季にも当てはまらないだろう。いまだに季語歳時記といっている俳諧師などが愚か者に思えてくる。日本海のマサバの旬はもともと新春以降であるが、太平洋のマサバも秋が旬なんて単純には言い切れないのである。実際、今回の太平洋マサバも卵巣が膨らんでいたのに脂が乗っていた。
アニサキスが気になってマサバを連日、小売店でも市場でも買って解体していた。その中で、料理して食べたのはなんと半身だけとは、欠食している方もいるこのご時世に申し訳ない。ただアニサキスの寄生率とまではいかないが、自分なりに何固体からアニサキスが出てくるか? 調べてみないわけにはいかない。中に冷凍マサバもありではあったが、主に太平洋側のもの5固体中1固体だけからアニサキスが出て来た。ちなみに筋肉からは出てこなかった。アニサキスライトを使ってすりつぶすようにして見たので間違いないだろう。廃棄、廃棄の連続であまりにも殺伐とした気分になったので、千葉県鴨川産の1固体だけ筋肉をつぶさないで作ったのが、「みそ煮」である。ちなみに「秋鯖」という言葉はおかしい。季語歳時記を最初にまとめたのは滝沢馬琴(1867-1848)だと思っている。この場合の季節は江戸のもので、例えば日本海側、ましてや九州には当てはまらない。もちろん温暖化で現東京の四季にも当てはまらないだろう。いまだに季語歳時記といっている俳諧師などが愚か者に思えてくる。日本海のマサバの旬はもともと新春以降であるが、太平洋のマサバも秋が旬なんて単純には言い切れないのである。実際、今回の太平洋マサバも卵巣が膨らんでいたのに脂が乗っていた。 最近、そのときどきそれぞれに何を食べたかを撮影している。画像を見ながら考えることも多く、また魚だけでは食事は成立しない、という当たり前のことがわかってくる。だいたい、自分が作ったもの以外も食べたいということがある。さて、相馬行から帰った翌日、4月29日なので、食材はほぼすべてが相馬で買ったものだ。相馬にはうまいものがたんとある。朝、おまんじゅう1個なのでたっぷりあれこれ食べたい。そんな遅すぎる昼兼用の朝ご飯である。原釜産「あおめがれい(マコガレイ)」の煮つけ。やはりカレイ科の中でも上位に君臨するおいしさだと改めて感じた。マコガレイが真子鰈たる所以の真子(卵巣)のおいしさ。これだけ真子が大きくなっていながら身の締まっているところなど申し分のない味である。松川浦産アサリのみそ汁。非常に粒が大きい。どことなく北海道産を思わせる。市内で買ったブロッコリーのわき芽とレタスのサラダ。市内中島ストアのみそ豆、タマゴヤの朝鮮漬け。この相馬ならではの惣菜、漬物が非常にうれしい。
最近、そのときどきそれぞれに何を食べたかを撮影している。画像を見ながら考えることも多く、また魚だけでは食事は成立しない、という当たり前のことがわかってくる。だいたい、自分が作ったもの以外も食べたいということがある。さて、相馬行から帰った翌日、4月29日なので、食材はほぼすべてが相馬で買ったものだ。相馬にはうまいものがたんとある。朝、おまんじゅう1個なのでたっぷりあれこれ食べたい。そんな遅すぎる昼兼用の朝ご飯である。原釜産「あおめがれい(マコガレイ)」の煮つけ。やはりカレイ科の中でも上位に君臨するおいしさだと改めて感じた。マコガレイが真子鰈たる所以の真子(卵巣)のおいしさ。これだけ真子が大きくなっていながら身の締まっているところなど申し分のない味である。松川浦産アサリのみそ汁。非常に粒が大きい。どことなく北海道産を思わせる。市内で買ったブロッコリーのわき芽とレタスのサラダ。市内中島ストアのみそ豆、タマゴヤの朝鮮漬け。この相馬ならではの惣菜、漬物が非常にうれしい。 連休中に水産生物(水産物)が切れた。ちょっと慌ただしいこともあり、連休明けにも1度しか市場に行けていない。ホームセンターに消耗品を買いに言ったついでに、鮮魚売場でお買い得品のスルメイカのげそを買って来た。長崎県産で成イカというよりもバラ(若い個体)である。それでもたっぷり入って500円ほどは安いと思う。これで3食をまかなう。最初のスルメイカのご飯は世にも簡単なアドリブ料理、だ。帰宅してから残り物を全部並べてみる。じゃがいも1個、にんじん半分、スナップエンドウ一握り、マシュルームだ。+ローリエ、にんにくにビネガー・オイル・スパイス・塩。
連休中に水産生物(水産物)が切れた。ちょっと慌ただしいこともあり、連休明けにも1度しか市場に行けていない。ホームセンターに消耗品を買いに言ったついでに、鮮魚売場でお買い得品のスルメイカのげそを買って来た。長崎県産で成イカというよりもバラ(若い個体)である。それでもたっぷり入って500円ほどは安いと思う。これで3食をまかなう。最初のスルメイカのご飯は世にも簡単なアドリブ料理、だ。帰宅してから残り物を全部並べてみる。じゃがいも1個、にんじん半分、スナップエンドウ一握り、マシュルームだ。+ローリエ、にんにくにビネガー・オイル・スパイス・塩。 連休明けの市場は不安定極まりない。止め(数日前に到着したもの)や微妙な荷(発泡の箱に入った魚介類などのこと)が多い。そんな不安定な市場で鮮度抜群、見事な高知県産シログチ(体長30.5cm・538g)を大発見した。まさに奇跡である。八王子綜合卸売センター、福泉のあんちゃんに聞くと入合(いくつかの魚を混ぜて1箱にしたもの)で来たらしい。しかも、5月の大振りのシログチの素晴らしさを知っている人は少ない、ので安い。この時季、上物のシマアジと並んでいたらボクは迷わずシログチに手を出す。味で勝負してシマアジを木っ端みじんに負かす、それほどおいしいからだ。関東ではイシモチと呼び、不安定ながら長年標準和名であった。これをときに併記されていたシログチに、標準和名を固定したことはとてもいい判断である。イシモチでは系統的に意味を持たない。
連休明けの市場は不安定極まりない。止め(数日前に到着したもの)や微妙な荷(発泡の箱に入った魚介類などのこと)が多い。そんな不安定な市場で鮮度抜群、見事な高知県産シログチ(体長30.5cm・538g)を大発見した。まさに奇跡である。八王子綜合卸売センター、福泉のあんちゃんに聞くと入合(いくつかの魚を混ぜて1箱にしたもの)で来たらしい。しかも、5月の大振りのシログチの素晴らしさを知っている人は少ない、ので安い。この時季、上物のシマアジと並んでいたらボクは迷わずシログチに手を出す。味で勝負してシマアジを木っ端みじんに負かす、それほどおいしいからだ。関東ではイシモチと呼び、不安定ながら長年標準和名であった。これをときに併記されていたシログチに、標準和名を固定したことはとてもいい判断である。イシモチでは系統的に意味を持たない。 日々、少ないときでも、3、多いときには10の魚料理を作っているので、食事も大方水産生物のものとなる。それにしてもヒラスズキの旬はわかりにくい。白ご飯は福井県の「いちほまれ」高知県産ヒラスズキ兜焼き。なんど作っても骨まで愛せると思う。おおばらごま油炒め(ハリギリの芽をゆでて、水にはなち、ごま油と醤油で炒め黒ごまを大量投入)。塩若布(ワカメ。茅場町木村海草店で頂いた試供品。水で洗っただけ)。間引き蕪の漬け物。本物の小蕪だと思って買ったらF!の間引きだった。本物の小蕪が食べたい。糸こん炒め煮(糸こんと子持ちヤリイカ真子とゲソ・ぎょうじゃにんにくを炒め煮にしたもので味つけは少量の酒と醤油)。間引き蕪と油揚げのみそ汁(福島県南会津町梁取みそ)。
日々、少ないときでも、3、多いときには10の魚料理を作っているので、食事も大方水産生物のものとなる。それにしてもヒラスズキの旬はわかりにくい。白ご飯は福井県の「いちほまれ」高知県産ヒラスズキ兜焼き。なんど作っても骨まで愛せると思う。おおばらごま油炒め(ハリギリの芽をゆでて、水にはなち、ごま油と醤油で炒め黒ごまを大量投入)。塩若布(ワカメ。茅場町木村海草店で頂いた試供品。水で洗っただけ)。間引き蕪の漬け物。本物の小蕪だと思って買ったらF!の間引きだった。本物の小蕪が食べたい。糸こん炒め煮(糸こんと子持ちヤリイカ真子とゲソ・ぎょうじゃにんにくを炒め煮にしたもので味つけは少量の酒と醤油)。間引き蕪と油揚げのみそ汁(福島県南会津町梁取みそ)。 前にも述べたことだが、四国の人間にとってもっとも浮かんで来ない東京の地名が、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、武蔵村山市、東大和市だ。小平市には同じクラスの友人がいたので、行ったことがあるが、それっきりこの中央線以北、西武沿線には縁がない。東久留米市はそんな東京都民にすら影の薄い市のひとつである。ただし、それでも東久留米市の人口は11万人以上もいるので、周りの無名の市と合わせると商圏としては大きい。つい先日の別の分野の勉強会で言われたことだけど、四国の人口は全部合わせても400万弱、徳島県など70万人ほどしかいない。この5市で徳島県全域と同等の商圏ということになる。ここにこれほど新しくて、魅力的な市場があることを知らなかったことは不覚である。建物が新しいだけではない。市場フラットであり、歩きやすいのも魅力的だろう。
前にも述べたことだが、四国の人間にとってもっとも浮かんで来ない東京の地名が、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、武蔵村山市、東大和市だ。小平市には同じクラスの友人がいたので、行ったことがあるが、それっきりこの中央線以北、西武沿線には縁がない。東久留米市はそんな東京都民にすら影の薄い市のひとつである。ただし、それでも東久留米市の人口は11万人以上もいるので、周りの無名の市と合わせると商圏としては大きい。つい先日の別の分野の勉強会で言われたことだけど、四国の人口は全部合わせても400万弱、徳島県など70万人ほどしかいない。この5市で徳島県全域と同等の商圏ということになる。ここにこれほど新しくて、魅力的な市場があることを知らなかったことは不覚である。建物が新しいだけではない。市場フラットであり、歩きやすいのも魅力的だろう。 福島県は国内随一のカツオ県である。宮城県が近いのもあるし、産地でもある。郡山市郡山魚市場にはカツオ競りなるカツオだけの競りがあるくらいだ。県内どこのスーパーに行ってもカツオの量が多い。カツオコーナーを設けているところもある。カツオも都内のスーパーと比べて格段にいい。福島に来たらカツオを買う、という考えは実に正しいのである。さて、相馬市内のスーパーで腹も(砂ずりとも言う可能性がある)ばっかり入ったパックがあった。これがスーパーに並ぶのもカツオ県だからだ。とりあえず1パック買ったものの、もう1パック探しても見つからない。たぶん並んでいた大方が売れてしまった後だろう。
福島県は国内随一のカツオ県である。宮城県が近いのもあるし、産地でもある。郡山市郡山魚市場にはカツオ競りなるカツオだけの競りがあるくらいだ。県内どこのスーパーに行ってもカツオの量が多い。カツオコーナーを設けているところもある。カツオも都内のスーパーと比べて格段にいい。福島に来たらカツオを買う、という考えは実に正しいのである。さて、相馬市内のスーパーで腹も(砂ずりとも言う可能性がある)ばっかり入ったパックがあった。これがスーパーに並ぶのもカツオ県だからだ。とりあえず1パック買ったものの、もう1パック探しても見つからない。たぶん並んでいた大方が売れてしまった後だろう。 食器に限りなく惹かれるのは、ボクが「からっちゃ(唐津屋)」に生まれたからだ。食器店のことを東日本で瀬戸物屋、西日本で唐津屋と呼んだ言語の地方性が失われて久しいのは残念でならない。相馬市内を歩いていて、「相馬焼」の文字に惹かれて食器店に吸い込まれた。
食器に限りなく惹かれるのは、ボクが「からっちゃ(唐津屋)」に生まれたからだ。食器店のことを東日本で瀬戸物屋、西日本で唐津屋と呼んだ言語の地方性が失われて久しいのは残念でならない。相馬市内を歩いていて、「相馬焼」の文字に惹かれて食器店に吸い込まれた。 福島県相馬市で水産物を探していて、忘れていたことを思い出す。しらす漁の北限である。「そうだ。相馬はしらす漁の(太平洋側の)北限だった」と思って調べたら、いつのまにか宮城県仙南の閖上、亘理が北限に変わっていた。とすると日本海側は、と調べたら富山県氷見だ。カタクチイワシの産卵場が北上しているのだ。これなど明らかに温暖化が原因である。相馬市で「しらす干し」を買うと言うことは、こんなきっかけをくれるということでもある。だから水産生物の加工品を買うということにも重要な意味がある。ちなみに相馬市では「ちりめん」も作っているようだ。これはまったく知らなかった。
福島県相馬市で水産物を探していて、忘れていたことを思い出す。しらす漁の北限である。「そうだ。相馬はしらす漁の(太平洋側の)北限だった」と思って調べたら、いつのまにか宮城県仙南の閖上、亘理が北限に変わっていた。とすると日本海側は、と調べたら富山県氷見だ。カタクチイワシの産卵場が北上しているのだ。これなど明らかに温暖化が原因である。相馬市で「しらす干し」を買うと言うことは、こんなきっかけをくれるということでもある。だから水産生物の加工品を買うということにも重要な意味がある。ちなみに相馬市では「ちりめん」も作っているようだ。これはまったく知らなかった。 【まずいきなり話の寄り道】最近の風潮、「見た目で食べる」の愚かしさである。牛肉・豚肉など丸のままの見た目で食べたらとても食えたものではない。ただ、この場合の見た目は肉になった状態のことなのだ。見た目を気にする人は、魚はまず丸のままで見ることになるが、魚も平等に肉になった状態で評価すべきだ。水産生物を丸のままの美醜で判断するから、エイやサメなどおいしいのに消費が減少する。基本肉の状態で売られるマグロやサーモン、アカムツ・キンメダイ・「きんき(キチジ)」など赤い魚ばかりが売れる。でも、でも見た目の悪い魚も味では決して負けてない!
【まずいきなり話の寄り道】最近の風潮、「見た目で食べる」の愚かしさである。牛肉・豚肉など丸のままの見た目で食べたらとても食えたものではない。ただ、この場合の見た目は肉になった状態のことなのだ。見た目を気にする人は、魚はまず丸のままで見ることになるが、魚も平等に肉になった状態で評価すべきだ。水産生物を丸のままの美醜で判断するから、エイやサメなどおいしいのに消費が減少する。基本肉の状態で売られるマグロやサーモン、アカムツ・キンメダイ・「きんき(キチジ)」など赤い魚ばかりが売れる。でも、でも見た目の悪い魚も味では決して負けてない! 谷崎潤一郎(1886-1965)の短編、「東京をおもう」(1934)に、「(東京から)遠く離れているときには、馬鹿貝の附け焼が恋しくなったり柱の山葵醤油が無上にたべてみたくなっったりする」というのが出てくる。蛎殻町(現人形町)に生まれ、明治時代に幼少時代を送る。父親は生粋のとまではいかないが江戸っ子で、江戸前の魚を食卓に上げていたようだ。当然、「馬鹿貝の附け焼」も柱(バカガイの貝柱)も、江戸時代からの家庭の味である。東京の下町で食べられていたという「馬鹿貝の附け焼」とはいかなるものだろう? 作ってみれば谷崎潤一郎の、東京の味への思いがわかるかも知れない。【話の寄り道。東京でバカガイのことを「青柳(あおやぎ)」と呼ぶようになったのは、そんなに古い話ではないのかも知れないと考えている。もしくは呼び名として主流ではなかった。築地場内(現豊洲)においても貝屋では「バカゲェ」という言葉が生きていて、青柳は小物屋が使う言葉であった可能性がある】作り方といっても複雑なものではない。たて(剥き身)を買って来る。もちろん活け(殻付き)があればいいに越したことはない。薄い塩水のなかで砂などをていねいに落とす。水分をよく切っておく。これを強火で焼き、酒・醤油のたれを塗りながら仕上げる。
谷崎潤一郎(1886-1965)の短編、「東京をおもう」(1934)に、「(東京から)遠く離れているときには、馬鹿貝の附け焼が恋しくなったり柱の山葵醤油が無上にたべてみたくなっったりする」というのが出てくる。蛎殻町(現人形町)に生まれ、明治時代に幼少時代を送る。父親は生粋のとまではいかないが江戸っ子で、江戸前の魚を食卓に上げていたようだ。当然、「馬鹿貝の附け焼」も柱(バカガイの貝柱)も、江戸時代からの家庭の味である。東京の下町で食べられていたという「馬鹿貝の附け焼」とはいかなるものだろう? 作ってみれば谷崎潤一郎の、東京の味への思いがわかるかも知れない。【話の寄り道。東京でバカガイのことを「青柳(あおやぎ)」と呼ぶようになったのは、そんなに古い話ではないのかも知れないと考えている。もしくは呼び名として主流ではなかった。築地場内(現豊洲)においても貝屋では「バカゲェ」という言葉が生きていて、青柳は小物屋が使う言葉であった可能性がある】作り方といっても複雑なものではない。たて(剥き身)を買って来る。もちろん活け(殻付き)があればいいに越したことはない。薄い塩水のなかで砂などをていねいに落とす。水分をよく切っておく。これを強火で焼き、酒・醤油のたれを塗りながら仕上げる。 昔、千葉県勝浦市へスルメイカ乗り合いに乗ったとき、荒天でなんと客はボク一人だった。今ではケータイがあるからドタキャンできるけど、海が荒れていると宿泊して翌日に出るということがあった。泊まっていろんな魚話を聞いたとき、ボクがクロダイ釣りで勝浦に通っていることを聞いて、「漁師はクロダイは食べない」と言われたことがある。千葉県保田で「ちんちん(クロダイの当歳魚)」を釣っていた人も「親は食べない」と話していたはず。当然、千葉県の広い地域で真子(卵巣)・白子(精巣)も食べないのではないかと考えている。
昔、千葉県勝浦市へスルメイカ乗り合いに乗ったとき、荒天でなんと客はボク一人だった。今ではケータイがあるからドタキャンできるけど、海が荒れていると宿泊して翌日に出るということがあった。泊まっていろんな魚話を聞いたとき、ボクがクロダイ釣りで勝浦に通っていることを聞いて、「漁師はクロダイは食べない」と言われたことがある。千葉県保田で「ちんちん(クロダイの当歳魚)」を釣っていた人も「親は食べない」と話していたはず。当然、千葉県の広い地域で真子(卵巣)・白子(精巣)も食べないのではないかと考えている。 人体に影響はない。扁形動物門吸虫綱二生亜綱斜睾吸虫目ディディモゾーン(ディディモゾイド)科(Didymozoidae Monticelli, 1888)ゴナポダスミウス属の種。ゴナポダスミウスなど多種類が存在する。扁形動物はまだ未開発な分野ではないか、と思うぐらい種の情報がない。マダイ、コショウダイ、マグロ類、ブリ、マサバ、トビウオなど多種類の魚類に寄生している。筋肉、鰓、内臓などにみられる。黄色みがかった袋状に見え、包丁などが当たると黄色い汁が出る。また黄褐色の染みのように見えることもある。非常に細長い体を折り曲げてこの袋状の中に入っている。雌は非常に長く6m前後になり、雄は小さく長さ10cm前後にしかならない。参考文献/『魚介類に寄生する生物』(長澤和也 成山堂書店) ■情報が集まり次第改訂していきます
人体に影響はない。扁形動物門吸虫綱二生亜綱斜睾吸虫目ディディモゾーン(ディディモゾイド)科(Didymozoidae Monticelli, 1888)ゴナポダスミウス属の種。ゴナポダスミウスなど多種類が存在する。扁形動物はまだ未開発な分野ではないか、と思うぐらい種の情報がない。マダイ、コショウダイ、マグロ類、ブリ、マサバ、トビウオなど多種類の魚類に寄生している。筋肉、鰓、内臓などにみられる。黄色みがかった袋状に見え、包丁などが当たると黄色い汁が出る。また黄褐色の染みのように見えることもある。非常に細長い体を折り曲げてこの袋状の中に入っている。雌は非常に長く6m前後になり、雄は小さく長さ10cm前後にしかならない。参考文献/『魚介類に寄生する生物』(長澤和也 成山堂書店) ■情報が集まり次第改訂していきます 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で愛知県一色産のクロダイを買った。1.3kgはサイズ的にも申し分がない。当然、時季的にお腹はでっぷりとして出産間近だということがわかる。普段なら買わないのだが、連休の狭間で他にめぼしい魚がない。しかもクロダイは年間を通して買っているが、5月始めのクロダイはたまたまではあるが買っていない。一色産のクロダイは明らかに活け締めである。昔ながらの粗野な締め方だけど死後硬直以前だ。うまく締めてある。さて、帰宅して真っ先に下ろすと卵巣が膨らみに膨らんでいる。やがてこの卵巣がほぐれ始めて産卵開始となる。三枚に下ろすと身に張りがあり、触った限りでも脂がのっているのがわかる。値段からすると大当たりだ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で愛知県一色産のクロダイを買った。1.3kgはサイズ的にも申し分がない。当然、時季的にお腹はでっぷりとして出産間近だということがわかる。普段なら買わないのだが、連休の狭間で他にめぼしい魚がない。しかもクロダイは年間を通して買っているが、5月始めのクロダイはたまたまではあるが買っていない。一色産のクロダイは明らかに活け締めである。昔ながらの粗野な締め方だけど死後硬直以前だ。うまく締めてある。さて、帰宅して真っ先に下ろすと卵巣が膨らみに膨らんでいる。やがてこの卵巣がほぐれ始めて産卵開始となる。三枚に下ろすと身に張りがあり、触った限りでも脂がのっているのがわかる。値段からすると大当たりだ。 アニサキスはときとして人体に害を及ぼし、アレルギーを引きおこし重症となる。一般にアニサキスと呼ばれているが、アニサキスとは、アニサキス科の何種類かの回虫である。正確には線形動物門双腺綱回虫目回虫上科アニサキス亜科アニサキス属(Anisakis )とシュードテラノーバ属(Pseudoterranova)の回虫をさす。最終宿主は鯨類(イルカなど)で、この体内で成虫になり、産卵する。海獣類、鯨類の排泄物と一緒に卵が体外に出て、孵化して孵化仔虫になる。それをオキアミなど動物プランクトンが摂取、動物プランクトンを魚類が食べることで今度は魚の内臓内に寄生する。その魚を鯨類が食べると、体内で成虫となり成熟、産卵する。この寄生された魚を生でヒトが食べることでアニサキス症になる。ただしヒトは最終宿主(成虫になって産卵できる環境を持つ生物)ではないので、取り込んでもアニサキスは長く生きていけない。
アニサキスはときとして人体に害を及ぼし、アレルギーを引きおこし重症となる。一般にアニサキスと呼ばれているが、アニサキスとは、アニサキス科の何種類かの回虫である。正確には線形動物門双腺綱回虫目回虫上科アニサキス亜科アニサキス属(Anisakis )とシュードテラノーバ属(Pseudoterranova)の回虫をさす。最終宿主は鯨類(イルカなど)で、この体内で成虫になり、産卵する。海獣類、鯨類の排泄物と一緒に卵が体外に出て、孵化して孵化仔虫になる。それをオキアミなど動物プランクトンが摂取、動物プランクトンを魚類が食べることで今度は魚の内臓内に寄生する。その魚を鯨類が食べると、体内で成虫となり成熟、産卵する。この寄生された魚を生でヒトが食べることでアニサキス症になる。ただしヒトは最終宿主(成虫になって産卵できる環境を持つ生物)ではないので、取り込んでもアニサキスは長く生きていけない。 カツオを下ろしていると、ときどき筋肉内(腹部)に白いものが散らばっていることがある。これが条虫(扁形動物門条虫綱)のテンタクラリアである。マグロ類にも寄生していることがある。今のところ内臓の中では見ていない。魚の腹部で見つかるものは幼虫で、最終宿主であるヨシキリザメなどの体内に入ると、成虫となる。
カツオを下ろしていると、ときどき筋肉内(腹部)に白いものが散らばっていることがある。これが条虫(扁形動物門条虫綱)のテンタクラリアである。マグロ類にも寄生していることがある。今のところ内臓の中では見ていない。魚の腹部で見つかるものは幼虫で、最終宿主であるヨシキリザメなどの体内に入ると、成虫となる。 トリガイの画像が足りないと思っていたら、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に殻トリ(貝殻つきで生きている状態)があった。値段を聞くと、ちょっとアニキ(すし屋用語で市場でも使う。数日前に仕入れたもの)らしく非常に安かった。信頼のおける仲買とのやりとりは、市場ではとても重要なことなのだ。ちなみに「水産物は鮮度が命」なんてほざく愚かな人間がいるととても助かる。このヤカラ達のお陰で、ちょっと古いくらいの水産物がすぐに安くなるからだ。売れ残った水産物にも意味があるし、実は料理法によっては古くても大丈夫というものがいっぱいあるのだよ。ボクなど古くなるのを待っていたりする。【話の寄り道。もちろん東京とか消費地限定の話だが。高級料理店は勝手に高い料理を作ればいいし、高ければ高いほど喜ぶ客もいるだろう。でもボクが好きなのは、この鮮度的なものでも、魚の種類でも自由な考え方ができ、客の懐のことを考えてくれる料理人・料理店店主である。】徹底的に貝殻の撮影をして、すぐにゆでる。貝殻ごと多めの塩を入れ、ゆでると軟体がぷくぷく浮き上がってくる。鮮度がいいとこんなに簡単には浮き上がらないけど、それでもトリガイはもっとも軟体部分を外しやすい二枚貝なのである。外れた軟体を氷を入れた塩水に落とし、軟体(足)の中のわたを押し出す。新たに氷を入れた塩水を作り、泥を完全に落とす。元気のいいトリガイはここまではしなくていい。水分をよくきり、食べやすい大きさに切る。合わせる野菜は「相馬せり」だ。本場宮城県産に比べて知名度は低いがとても香り高く、味がいい。これをゆでて冷水に落として水分をきり、食べやすい大きさに切っておく。酢みそは、塩分強めだけどとても味のいい福島県南会津町、山内麹店「梁取みそ」・米酢・少量の砂糖。塩分の強いみそなので、基本的に酢とみそだけで味を作りあげ、砂糖はマイルドにする程度加えるだけ。後はトリガイ、せり、酢みそを和えるだけ。
トリガイの画像が足りないと思っていたら、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に殻トリ(貝殻つきで生きている状態)があった。値段を聞くと、ちょっとアニキ(すし屋用語で市場でも使う。数日前に仕入れたもの)らしく非常に安かった。信頼のおける仲買とのやりとりは、市場ではとても重要なことなのだ。ちなみに「水産物は鮮度が命」なんてほざく愚かな人間がいるととても助かる。このヤカラ達のお陰で、ちょっと古いくらいの水産物がすぐに安くなるからだ。売れ残った水産物にも意味があるし、実は料理法によっては古くても大丈夫というものがいっぱいあるのだよ。ボクなど古くなるのを待っていたりする。【話の寄り道。もちろん東京とか消費地限定の話だが。高級料理店は勝手に高い料理を作ればいいし、高ければ高いほど喜ぶ客もいるだろう。でもボクが好きなのは、この鮮度的なものでも、魚の種類でも自由な考え方ができ、客の懐のことを考えてくれる料理人・料理店店主である。】徹底的に貝殻の撮影をして、すぐにゆでる。貝殻ごと多めの塩を入れ、ゆでると軟体がぷくぷく浮き上がってくる。鮮度がいいとこんなに簡単には浮き上がらないけど、それでもトリガイはもっとも軟体部分を外しやすい二枚貝なのである。外れた軟体を氷を入れた塩水に落とし、軟体(足)の中のわたを押し出す。新たに氷を入れた塩水を作り、泥を完全に落とす。元気のいいトリガイはここまではしなくていい。水分をよくきり、食べやすい大きさに切る。合わせる野菜は「相馬せり」だ。本場宮城県産に比べて知名度は低いがとても香り高く、味がいい。これをゆでて冷水に落として水分をきり、食べやすい大きさに切っておく。酢みそは、塩分強めだけどとても味のいい福島県南会津町、山内麹店「梁取みそ」・米酢・少量の砂糖。塩分の強いみそなので、基本的に酢とみそだけで味を作りあげ、砂糖はマイルドにする程度加えるだけ。後はトリガイ、せり、酢みそを和えるだけ。 一様水産生物を研究しているつもりなので、日々努力を重ねているつもりでもある。個人経営のスーパーのオッチャンに「暇でええよな」と笑われたことがあるけど、寸暇もないといってもいい。日々、専門書に取っ組まないといけないし、水産生物と組んずほぐれつだし、いつの間にか専門分野の問題点に行き当たってその分野の専門家と同次元で苦しんだりしているので、ボンヤリコンとしているわけではない。なので食事もいつの間にか、仕事になっちまったぜ。この週はヒラスズキを1本買って作った料理は7つなので、主菜ヒラスズキが続いたりする。この日の朝ご飯は、ヒラスズキ若狭焼き、子持ちヤリイカげそ&真子・ギョウジャニンニク・糸こんにゃく炒め、三つ葉の黒ごま炒め、あおさ佃煮、山椒の卵焼き、しゃくし菜だった。ヒラスズキ若狭焼き/切り身を若狭地(酒・醤油)を塗りながら焼き上げたもの。子持ちヤリイカげそ&真子・ギョウジャニンニク・糸こんにゃく炒め/八王子綜合卸売センター、『八百角』でもらったダメになりそうなギョウジャニンニクと子持ちヤリイカのげそ、糸こんを炒めたもの。そう言えば水戸の市場で糸こんとしらたきの違いを聞いたけど忘れた。三つ葉の黒ごま炒め/八王子綜合卸売センター、『八百角』で3束100円だったのでついつい買ってしまった三つ葉を使う。あおさ佃煮/茅場町『木村海草店』で買った。三重県志摩市英虞湾で養殖したヒロハノヒトエグサの佃煮。製造したのは愛知県。山椒の卵焼き/山椒の葉がダメになりそうだったので煎り卵にぶっ込んじまったぜ。しゃくし菜/埼玉県秩父地方特産しゃくし菜の漬物。
一様水産生物を研究しているつもりなので、日々努力を重ねているつもりでもある。個人経営のスーパーのオッチャンに「暇でええよな」と笑われたことがあるけど、寸暇もないといってもいい。日々、専門書に取っ組まないといけないし、水産生物と組んずほぐれつだし、いつの間にか専門分野の問題点に行き当たってその分野の専門家と同次元で苦しんだりしているので、ボンヤリコンとしているわけではない。なので食事もいつの間にか、仕事になっちまったぜ。この週はヒラスズキを1本買って作った料理は7つなので、主菜ヒラスズキが続いたりする。この日の朝ご飯は、ヒラスズキ若狭焼き、子持ちヤリイカげそ&真子・ギョウジャニンニク・糸こんにゃく炒め、三つ葉の黒ごま炒め、あおさ佃煮、山椒の卵焼き、しゃくし菜だった。ヒラスズキ若狭焼き/切り身を若狭地(酒・醤油)を塗りながら焼き上げたもの。子持ちヤリイカげそ&真子・ギョウジャニンニク・糸こんにゃく炒め/八王子綜合卸売センター、『八百角』でもらったダメになりそうなギョウジャニンニクと子持ちヤリイカのげそ、糸こんを炒めたもの。そう言えば水戸の市場で糸こんとしらたきの違いを聞いたけど忘れた。三つ葉の黒ごま炒め/八王子綜合卸売センター、『八百角』で3束100円だったのでついつい買ってしまった三つ葉を使う。あおさ佃煮/茅場町『木村海草店』で買った。三重県志摩市英虞湾で養殖したヒロハノヒトエグサの佃煮。製造したのは愛知県。山椒の卵焼き/山椒の葉がダメになりそうだったので煎り卵にぶっ込んじまったぜ。しゃくし菜/埼玉県秩父地方特産しゃくし菜の漬物。 今年はホタルイカが安い上に、まだ魚屋に並んでいる。スーパーにもあるので、ついつい手が出る。これをイタリアンな料理に使ってみた。といっても面倒な料理ではない。袋に中途半端に残っていたペンネを消費するためのイタリアーンでもある。ペンネのゆで時間は10分。ゆではじめたらフライパンにたっぷりのオリーブオイルとにんにく、鷹の爪をいれて熱する。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて、トマトを刻んだものを放り込む。ここに生ホタルイカを加えて、徹底的にどつく。体がばらばらになるくらいどつくが、ぬるニョロとしているのでなかなかパンチがきかない。トマトは煮過ぎると甘さが飛び、長時間煮込んでいる内にふたたび甘くなる。ここで注意しなければならないのは煮すぎないことである。パスタとのゆで時間を考えて甘味がいちばん強いときに火を止める。あとは味見をして塩コショウする。ソースがどろっとし過ぎていたらゆで汁で加減する。この場合、塩は不要。あとはペンネと和えるだけ。
今年はホタルイカが安い上に、まだ魚屋に並んでいる。スーパーにもあるので、ついつい手が出る。これをイタリアンな料理に使ってみた。といっても面倒な料理ではない。袋に中途半端に残っていたペンネを消費するためのイタリアーンでもある。ペンネのゆで時間は10分。ゆではじめたらフライパンにたっぷりのオリーブオイルとにんにく、鷹の爪をいれて熱する。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて、トマトを刻んだものを放り込む。ここに生ホタルイカを加えて、徹底的にどつく。体がばらばらになるくらいどつくが、ぬるニョロとしているのでなかなかパンチがきかない。トマトは煮過ぎると甘さが飛び、長時間煮込んでいる内にふたたび甘くなる。ここで注意しなければならないのは煮すぎないことである。パスタとのゆで時間を考えて甘味がいちばん強いときに火を止める。あとは味見をして塩コショウする。ソースがどろっとし過ぎていたらゆで汁で加減する。この場合、塩は不要。あとはペンネと和えるだけ。 福島県相馬市では主に旧城下の中村でスーパーを回ってみた。休日にも開いているスーパーは旅人にはまことにありがたい。【話の寄り道、旅の土産はスーパーで買うべし。同じ土産品が値が安い上に、地元でしか買えないものが発見できる。】相馬市は藩政時代から城のある中村と、漁港がある原釜に分かれていた。古くから、原釜でとれた魚を城下で消費する、という形が出来上がっていたのだと思う。スーパーに並ぶ、魚のラベルに「原釜水揚げ」がとても多いことにも、そんな歴史が偲ばれる。今回の相馬行で改めて感じたのはこの地のカレイ類が豊富であることだ。見つけた原釜産カレイ類は、「あおめがれい(マコガレイ)」、「にくもちがれい(ミギガレイ)」、「なめた(ババガレイ)」、「石がれい(イシガレイ)」「黒やなぎ(ヒレグロ)」、「柳かれい(ヤナギムシガレイ)」、「水がれい(ムシガレイ)」、「真がれい(マガレイ)」だ。江戸(東京)の前海江戸湾(東京湾)は昔からカレイ類の宝庫であった。江戸時代の江戸っ子はカレイ類をよく食べていたはずだ。明治期になって東北本線、常磐線ができるとそこに茨城県、福島県、宮城県からどっと新顔のカレイ類がおしよせてくる。後に北海道が加わる。国内でももっとも多種のカレイを食べていたのが東京なのだ。カレイ類は昔、もっとも人気の高い魚だったが、最近人気低落気味である。この最大の原因が煮つけを作らなくなったためで、その根本には米を食べなくなったことが挙げられる。ちなみに関東の市場人で、「原釜」を知らないという人は震災後に市場人となったのだと思う。原釜は関東にとって最大級の供給地だったし、関東の市場人ならおしなべて元の状態に復して欲しいと思っているはずである。さて、「あおめがれい」の切り身を市内『中島ストア』で買った。この小さなスーパーは実に楽しかったという話は後々に述べる。宮城県、福島県での呼び名、「あおめがれい」の漢字、意味がわからないので困っている。単純に考えると「青目鰈」だけど、目は青くないのだ。「あおめがれい」、すなわちマコガレイの面白いところは寒い時季は大衆魚で、気温が上昇すると高級魚に変身することだ。この高級魚の時季が温暖化で長くなっている気がする。4月の末、まだ、「あおめがれい」が活魚槽の主役になるのはもう少し後のことになる。今はまだ生殖巣が膨らんでいるので、庶民的な魚でしかない。
福島県相馬市では主に旧城下の中村でスーパーを回ってみた。休日にも開いているスーパーは旅人にはまことにありがたい。【話の寄り道、旅の土産はスーパーで買うべし。同じ土産品が値が安い上に、地元でしか買えないものが発見できる。】相馬市は藩政時代から城のある中村と、漁港がある原釜に分かれていた。古くから、原釜でとれた魚を城下で消費する、という形が出来上がっていたのだと思う。スーパーに並ぶ、魚のラベルに「原釜水揚げ」がとても多いことにも、そんな歴史が偲ばれる。今回の相馬行で改めて感じたのはこの地のカレイ類が豊富であることだ。見つけた原釜産カレイ類は、「あおめがれい(マコガレイ)」、「にくもちがれい(ミギガレイ)」、「なめた(ババガレイ)」、「石がれい(イシガレイ)」「黒やなぎ(ヒレグロ)」、「柳かれい(ヤナギムシガレイ)」、「水がれい(ムシガレイ)」、「真がれい(マガレイ)」だ。江戸(東京)の前海江戸湾(東京湾)は昔からカレイ類の宝庫であった。江戸時代の江戸っ子はカレイ類をよく食べていたはずだ。明治期になって東北本線、常磐線ができるとそこに茨城県、福島県、宮城県からどっと新顔のカレイ類がおしよせてくる。後に北海道が加わる。国内でももっとも多種のカレイを食べていたのが東京なのだ。カレイ類は昔、もっとも人気の高い魚だったが、最近人気低落気味である。この最大の原因が煮つけを作らなくなったためで、その根本には米を食べなくなったことが挙げられる。ちなみに関東の市場人で、「原釜」を知らないという人は震災後に市場人となったのだと思う。原釜は関東にとって最大級の供給地だったし、関東の市場人ならおしなべて元の状態に復して欲しいと思っているはずである。さて、「あおめがれい」の切り身を市内『中島ストア』で買った。この小さなスーパーは実に楽しかったという話は後々に述べる。宮城県、福島県での呼び名、「あおめがれい」の漢字、意味がわからないので困っている。単純に考えると「青目鰈」だけど、目は青くないのだ。「あおめがれい」、すなわちマコガレイの面白いところは寒い時季は大衆魚で、気温が上昇すると高級魚に変身することだ。この高級魚の時季が温暖化で長くなっている気がする。4月の末、まだ、「あおめがれい」が活魚槽の主役になるのはもう少し後のことになる。今はまだ生殖巣が膨らんでいるので、庶民的な魚でしかない。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で高知県須崎産ヒラスズキ36cm・868gを買った。最近、高知県からの荷が多いのは、産地としての高知県ががんばっているためかも知れぬ。さて、ヒラスズキとスズキは系統的に近い種で、非常に似ている。実際、片山正夫が1957年に記載するまでスズキ属はスズキ1種だけだと考えられていた。分類はともかく、両種、味はまったく違っている。ヒラスズキは外洋に面した岩礁域にいる魚なのに対して、スズキは淡水の影響を受ける水域にいることが多い。ヒラスズキは白身のマダイなどに似た身質で、スズキはどことなく淡水魚的な風味がある。これが生息環境の違いと、エサとなる魚や甲殻類もまったく違うためではないかと思っている。産卵期は秋から春にかけてと長く、旬は秋から春で最旬は冬だと思っている。4月末の今回の個体は、生殖巣はほとんど痕跡的で産卵後の個体だ。産卵のダメージからの立ち直りが早いようで、脂がほどほどあった。刺身にすると非常に味わい深い。改めてヒラスズキの旬は非常にわかりにくい、と感じさせられた。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で高知県須崎産ヒラスズキ36cm・868gを買った。最近、高知県からの荷が多いのは、産地としての高知県ががんばっているためかも知れぬ。さて、ヒラスズキとスズキは系統的に近い種で、非常に似ている。実際、片山正夫が1957年に記載するまでスズキ属はスズキ1種だけだと考えられていた。分類はともかく、両種、味はまったく違っている。ヒラスズキは外洋に面した岩礁域にいる魚なのに対して、スズキは淡水の影響を受ける水域にいることが多い。ヒラスズキは白身のマダイなどに似た身質で、スズキはどことなく淡水魚的な風味がある。これが生息環境の違いと、エサとなる魚や甲殻類もまったく違うためではないかと思っている。産卵期は秋から春にかけてと長く、旬は秋から春で最旬は冬だと思っている。4月末の今回の個体は、生殖巣はほとんど痕跡的で産卵後の個体だ。産卵のダメージからの立ち直りが早いようで、脂がほどほどあった。刺身にすると非常に味わい深い。改めてヒラスズキの旬は非常にわかりにくい、と感じさせられた。 2024年4月19日、二宮定置に、「ほぼブリサイズなので、ブリとしておきたい個体」を1尾いただいた。卑しい話が、だれかにいただける可能性が高いと思って行った小田原で、本当にいただいて、素直に嬉しいボクなのであった。アハハのハだ。ありがとうございました。しかも名人、Kai君に血抜きまでやっていただく。これ以上ない、ブリである。余談になるが、19日早朝、顔見知りの買受人と、「どこからブリにしていいのか?」という話をした。このところ6㎏サイズでもブリだという人がいるらしい。ボクとしては8㎏前後からブリだと思っているけど、脂があって上物で、それなりに大きければブリでいい、と考えている。
2024年4月19日、二宮定置に、「ほぼブリサイズなので、ブリとしておきたい個体」を1尾いただいた。卑しい話が、だれかにいただける可能性が高いと思って行った小田原で、本当にいただいて、素直に嬉しいボクなのであった。アハハのハだ。ありがとうございました。しかも名人、Kai君に血抜きまでやっていただく。これ以上ない、ブリである。余談になるが、19日早朝、顔見知りの買受人と、「どこからブリにしていいのか?」という話をした。このところ6㎏サイズでもブリだという人がいるらしい。ボクとしては8㎏前後からブリだと思っているけど、脂があって上物で、それなりに大きければブリでいい、と考えている。 前回の小田原魚市場行で、二宮定置にアジ(マアジ)を分けてもらった。昨日、打ち合わせで駅前に出たら、打ち合わせの後、またアジをいただいたのだ。連休は休めないので、休みをとって、父親と船釣りに行き、生まれて初めて釣ったものだという。アジの在庫がまだあるとはいえ、もらわないわけにもいかない。初めて釣り上げたアジはどこで釣ったのか? を聞き忘れた。実家がたしか静岡県なので、駿河湾としておこう。まず最初に、二宮定置にありがとう。たった3尾だけども仕事熱心な若い衆にもありがとう、なのだ。二宮定置でいただいたマアジ9尾はアジフライ用に仕込み保存して、1週間で食べきり、また今日、3尾揚げたので計12枚のアジフライを食べたことになる。それにしてもアジフライはいくら食べても食べ飽きない。昔話になるが、仕事を始めたばかりの頃、お昼ご飯はいつも、アジフライと決めている方がいて、一緒に出版社の地下で御馳走して頂いていた時期があった。本当はロースカツが食べたかったのに、毎回アジフライを2人前(4尾)、ご飯を1人前食べていたっけな。アジフライの作り方を書くのは無意味かも知れないが。マアジは開いて、腹骨・血合い骨を取る。背鰭を切り取り、腹側の縁に小骨が残っていることがあるので切り取る。水分をよくきり、塩コショウして、小麦粉をまぶす。溶き卵にくぐらせパン粉をつけて高温で一気に揚げる。それだけだ。自分好みにウスターソースをたっぷりかけて食らうとたまらない。1週間で12枚も食べているのに、食べ足りない。マアジをフライにした人は天才である。さて、今読んでいる、1950年前後の世相を映す中村武志の目白三平シリーズに、「あじの天ぷら」は出てくるのに、アジフライは出てこない。今、アジフライは普通だが、「あじの天ぷら」は珍しいと思う。いったいいつ頃からアジフライは日常的な料理になったのだろう?
前回の小田原魚市場行で、二宮定置にアジ(マアジ)を分けてもらった。昨日、打ち合わせで駅前に出たら、打ち合わせの後、またアジをいただいたのだ。連休は休めないので、休みをとって、父親と船釣りに行き、生まれて初めて釣ったものだという。アジの在庫がまだあるとはいえ、もらわないわけにもいかない。初めて釣り上げたアジはどこで釣ったのか? を聞き忘れた。実家がたしか静岡県なので、駿河湾としておこう。まず最初に、二宮定置にありがとう。たった3尾だけども仕事熱心な若い衆にもありがとう、なのだ。二宮定置でいただいたマアジ9尾はアジフライ用に仕込み保存して、1週間で食べきり、また今日、3尾揚げたので計12枚のアジフライを食べたことになる。それにしてもアジフライはいくら食べても食べ飽きない。昔話になるが、仕事を始めたばかりの頃、お昼ご飯はいつも、アジフライと決めている方がいて、一緒に出版社の地下で御馳走して頂いていた時期があった。本当はロースカツが食べたかったのに、毎回アジフライを2人前(4尾)、ご飯を1人前食べていたっけな。アジフライの作り方を書くのは無意味かも知れないが。マアジは開いて、腹骨・血合い骨を取る。背鰭を切り取り、腹側の縁に小骨が残っていることがあるので切り取る。水分をよくきり、塩コショウして、小麦粉をまぶす。溶き卵にくぐらせパン粉をつけて高温で一気に揚げる。それだけだ。自分好みにウスターソースをたっぷりかけて食らうとたまらない。1週間で12枚も食べているのに、食べ足りない。マアジをフライにした人は天才である。さて、今読んでいる、1950年前後の世相を映す中村武志の目白三平シリーズに、「あじの天ぷら」は出てくるのに、アジフライは出てこない。今、アジフライは普通だが、「あじの天ぷら」は珍しいと思う。いったいいつ頃からアジフライは日常的な料理になったのだろう? 小田原で見事なタチウオをいっぱいいただいて、ほぼ食べ終わったと思ったら、また来た、来ましたよ東の方の海から、相模原在住だという謎の釣り師が3本ばかり持って来た。こんなにタチウオ尽くめではやってられまへん。けど、ありがとう!さて、その日ボクは我が家にある、うな重の重箱を整理していたのだ。長さを量って、ご飯の量をみるために実際に詰めてみようなんて地味なことをやっていた。ただ、考えてみたら上に乗せるものがない。それで考えたのが「フライパン照焼」だけど、確かこの料理名は雑誌『四季の味』か、『暮らしの手帖』にあったもので、「フライパン蒲焼き」としても間違っていないはずだ。作り方はウルトラC級に簡単である。余談になるが、この2雑誌は昔はすごく優れていたのだ。当時、へんにかっこつけてまったく使えない料理は皆無で、読んだだけで、だいたいのコンセプトがわかり、すぐに作れるものばかりだった。最近買っていないけど、どうなってるんだろうな?
小田原で見事なタチウオをいっぱいいただいて、ほぼ食べ終わったと思ったら、また来た、来ましたよ東の方の海から、相模原在住だという謎の釣り師が3本ばかり持って来た。こんなにタチウオ尽くめではやってられまへん。けど、ありがとう!さて、その日ボクは我が家にある、うな重の重箱を整理していたのだ。長さを量って、ご飯の量をみるために実際に詰めてみようなんて地味なことをやっていた。ただ、考えてみたら上に乗せるものがない。それで考えたのが「フライパン照焼」だけど、確かこの料理名は雑誌『四季の味』か、『暮らしの手帖』にあったもので、「フライパン蒲焼き」としても間違っていないはずだ。作り方はウルトラC級に簡単である。余談になるが、この2雑誌は昔はすごく優れていたのだ。当時、へんにかっこつけてまったく使えない料理は皆無で、読んだだけで、だいたいのコンセプトがわかり、すぐに作れるものばかりだった。最近買っていないけど、どうなってるんだろうな? 市場旅につきものなのが市場めし、これがないと市場旅の楽しさ半減。市場の魅力も半減する。千葉県千葉市、千葉市地方卸売市場の関連棟は肉屋あり、大きな八百屋ありで、多彩、中でも面白かったのは向かい合った2軒の昆布や乾物を売る店だ。さて、長い長い関連棟を歩き回った後に向かうのが、2階にある食堂街であるが、2階にあることはおぼえているが、どこから上がるのか見当がつかない。長すぎる関連棟の、見つけにくい入り口の階段を上がらないと食堂街にたどり着けないのは、よそ者だけではなく、市場人にも不便ではないか。市場を設計した人間は、明らかに働く人のことをまったく考えていない。豊洲もそうだけど、行政や施工者はなぜ働く人のことに無関心なのだろう。中央部分が吹き抜けになっていて、左右に食堂が2軒、中華が1軒、レストラン(喫茶)が1軒の計4軒がまばらに散らばっている。明らかに閉店した店が多いのだろう。関連棟の大きさを考えると、寂しい限りである。その中の1軒は客がいないので却下。食堂は海鮮丼の写真を見てやめた。中華は前回食べているので避けた。市場飯に魚介類を選ばないのは、外食くらいは魚を避けて通りたいのもあるけど、その料理に仕入れの苦労が見えてしまうためだ。特に海鮮丼は値段を考えると仕方がないとは思うけど、いじましくていやだ。希に本物の地物の海鮮丼があると、嬉しくなるが、それは奇跡というものである。ついでに冷凍マグロや冷凍輸入エビ・イクラなどがダメだとは思わないけど、お里が知れているものは食べない主義なので悪しからず。
市場旅につきものなのが市場めし、これがないと市場旅の楽しさ半減。市場の魅力も半減する。千葉県千葉市、千葉市地方卸売市場の関連棟は肉屋あり、大きな八百屋ありで、多彩、中でも面白かったのは向かい合った2軒の昆布や乾物を売る店だ。さて、長い長い関連棟を歩き回った後に向かうのが、2階にある食堂街であるが、2階にあることはおぼえているが、どこから上がるのか見当がつかない。長すぎる関連棟の、見つけにくい入り口の階段を上がらないと食堂街にたどり着けないのは、よそ者だけではなく、市場人にも不便ではないか。市場を設計した人間は、明らかに働く人のことをまったく考えていない。豊洲もそうだけど、行政や施工者はなぜ働く人のことに無関心なのだろう。中央部分が吹き抜けになっていて、左右に食堂が2軒、中華が1軒、レストラン(喫茶)が1軒の計4軒がまばらに散らばっている。明らかに閉店した店が多いのだろう。関連棟の大きさを考えると、寂しい限りである。その中の1軒は客がいないので却下。食堂は海鮮丼の写真を見てやめた。中華は前回食べているので避けた。市場飯に魚介類を選ばないのは、外食くらいは魚を避けて通りたいのもあるけど、その料理に仕入れの苦労が見えてしまうためだ。特に海鮮丼は値段を考えると仕方がないとは思うけど、いじましくていやだ。希に本物の地物の海鮮丼があると、嬉しくなるが、それは奇跡というものである。ついでに冷凍マグロや冷凍輸入エビ・イクラなどがダメだとは思わないけど、お里が知れているものは食べない主義なので悪しからず。 静岡県西伊豆で年越しに食べられていた「塩かつお」は、「潮かつお」とも書かれ、11月になると丸のままの姿で塩漬けにし、干し上げたもの。単なる塩蔵品ではなく、干すという工程が入る。もうひとつの、より一般的な「塩かつお」がある。こちらはカツオの半身、もしくは切り身の塩漬け(塩蔵品)である。静岡・関東・東北だけではなく全国で作られていた可能性が高い。聞取をすると関東では日常的なおかずだったようだ。関東、静岡県では「塩かつお(塩がつお)」、宮城県石巻で「かつおのだぶ漬け」、気仙沼で「かつおの塩引き」という。カツオの産地での「塩かつお」の呼び名はもっとたくさんあると考えているので、ご存じの方がいらしたら教えて頂きたい。静岡県西伊豆で年末に作られていた「塩かつお」がハレの加工品だとしたら、カツオの産地で長年作られていた「塩かつお」はケの加工品である。
静岡県西伊豆で年越しに食べられていた「塩かつお」は、「潮かつお」とも書かれ、11月になると丸のままの姿で塩漬けにし、干し上げたもの。単なる塩蔵品ではなく、干すという工程が入る。もうひとつの、より一般的な「塩かつお」がある。こちらはカツオの半身、もしくは切り身の塩漬け(塩蔵品)である。静岡・関東・東北だけではなく全国で作られていた可能性が高い。聞取をすると関東では日常的なおかずだったようだ。関東、静岡県では「塩かつお(塩がつお)」、宮城県石巻で「かつおのだぶ漬け」、気仙沼で「かつおの塩引き」という。カツオの産地での「塩かつお」の呼び名はもっとたくさんあると考えているので、ご存じの方がいらしたら教えて頂きたい。静岡県西伊豆で年末に作られていた「塩かつお」がハレの加工品だとしたら、カツオの産地で長年作られていた「塩かつお」はケの加工品である。 日常的に陸上生物の筋肉・脂はとらないので、水産生物をのぞくと菜食主義者のようだ。それでも太ってしまうのは、想念を整理し始めると時間が無限大にかかり、座っている時間が長すぎるせいに違いない。小田原から持ち帰った魚をせっせと消費するといった日々である。そんなときに限って八王子綜合卸売共同市場、舵丸水産のクマゴロウが本マ(クロマグロ)のあらをくれたりする。魚がたっぷりあるときに限って魚がやってくるのは、いうなればボクのジンクスでもある。野菜もたっぷりあるし、作り置きの総菜類もある。ただ単純に料理を並べて、午前6時の朝ご飯は始まる。ご飯は今日から福井県の「いちほまれ」。サラダはサニーレタス、ブロッコリーの芽、トマト、レモネード(静岡県沼津市の食用柑橘類)、ブリマヨ(神奈川県小田原市産ブリ・マヨネーズ・ヨーグルト・コショウ・レモン)。神奈川県スーパーヤオマサで買った木綿豆腐(サカグチヤ 静岡県御殿場市)。こごみ胡麻よごし(コゴミ、煮きりみりん少量、醤油)。神奈川県小田原市産タチウオ塩焼き。クロマグロあら煮。わかめのみそ汁。たぶんカロリーは低めだと思う。満身創痍なので、できるだけ理想的な朝ご飯を目指している。
日常的に陸上生物の筋肉・脂はとらないので、水産生物をのぞくと菜食主義者のようだ。それでも太ってしまうのは、想念を整理し始めると時間が無限大にかかり、座っている時間が長すぎるせいに違いない。小田原から持ち帰った魚をせっせと消費するといった日々である。そんなときに限って八王子綜合卸売共同市場、舵丸水産のクマゴロウが本マ(クロマグロ)のあらをくれたりする。魚がたっぷりあるときに限って魚がやってくるのは、いうなればボクのジンクスでもある。野菜もたっぷりあるし、作り置きの総菜類もある。ただ単純に料理を並べて、午前6時の朝ご飯は始まる。ご飯は今日から福井県の「いちほまれ」。サラダはサニーレタス、ブロッコリーの芽、トマト、レモネード(静岡県沼津市の食用柑橘類)、ブリマヨ(神奈川県小田原市産ブリ・マヨネーズ・ヨーグルト・コショウ・レモン)。神奈川県スーパーヤオマサで買った木綿豆腐(サカグチヤ 静岡県御殿場市)。こごみ胡麻よごし(コゴミ、煮きりみりん少量、醤油)。神奈川県小田原市産タチウオ塩焼き。クロマグロあら煮。わかめのみそ汁。たぶんカロリーは低めだと思う。満身創痍なので、できるだけ理想的な朝ご飯を目指している。 2024年4月19日、神奈川県小田原市、小田原魚市場そば、港のおっかさんのところで市場人のための市場飯。この日は漁師さんも市場人もてんてこ舞いの忙しさで、ボク一人っきりの寂しすぎる、市場飯となる。市場人用の飯は、すぐ食べられて、しかも味がよくないとダメだ。ギンダラは地物ではないが、おっかさんが市場人のために仕入れた上物で、しかも名人でなければ作り出せぬ味。市場人は、観光客のように地物でもない魚介類たっぷりの海鮮丼に散在したいわけでもなく、ただただおいしい朝ご飯が食べたいのである。その点ではおっかさんの作る飯は天下一品なのだ。
2024年4月19日、神奈川県小田原市、小田原魚市場そば、港のおっかさんのところで市場人のための市場飯。この日は漁師さんも市場人もてんてこ舞いの忙しさで、ボク一人っきりの寂しすぎる、市場飯となる。市場人用の飯は、すぐ食べられて、しかも味がよくないとダメだ。ギンダラは地物ではないが、おっかさんが市場人のために仕入れた上物で、しかも名人でなければ作り出せぬ味。市場人は、観光客のように地物でもない魚介類たっぷりの海鮮丼に散在したいわけでもなく、ただただおいしい朝ご飯が食べたいのである。その点ではおっかさんの作る飯は天下一品なのだ。 相模湾をはじめ日本各地で、ブリ大漁にわいている。お祭りだーい、ブリ祭だーい、と騒いでいたら、担ぐ神輿がもうひとつあった、タチウオである。小田原魚市場には発泡に入りきらないサイズのタチウオの尾っぽが、あっちでひらひら、こっちでひらひらしている。定置網の中で大量の獲物に揉まれてギンギラギンではなく、銀皮が鈍色になっている。ともにかみ合った傷もある。魚を知らない人はこりゃダメだろうと思ってしまいそうだが、タチウオの場合、ギンギラギンはだめなのだ。脂があるほど剥げやすい。それなのに流通上はギンギンギラギラした方が高いなど、不思議でならない。小田原魚市場二宮定置に数尾いただいて、車に帰ったら、またいただいていた。二宮定置、どなたか知らないけどもうひとかた、ありがとう。タチウオだらけなので近所に配り、ブリは『市場寿司 たか』と半分こする。『市場寿司 たか』では、丼にしてお出ししたと思うがいかがだっただろう。そしてタチウオだが、きらめきはなかったが案の定、脂がたっぷり硬く締まった身に混在して白濁させているではないか。ちなみに相模湾だけではなく、東京湾にもタチウオがわいているのである。相模湾のも上等なら東京湾のも上等だと言っておきたい。ちなみに昔は相模湾にはあまりタチウオがいなかった。ましてや東京湾にはタチウオがほとんどいなかったはずである。このタチウオの増大は明らかに温暖化の影響だ。産卵場所が北に広がっているのである。もっともっとたくさんタチウオがわいている海域がほかにもあると思うが、いつからこの国はタチウオだらけになったのだろう。とれているときに、とれている魚種を食べるのがいちばん自然に優しい。今、タチウオとブリはたんとたんとおあがりやす、なのだ。
相模湾をはじめ日本各地で、ブリ大漁にわいている。お祭りだーい、ブリ祭だーい、と騒いでいたら、担ぐ神輿がもうひとつあった、タチウオである。小田原魚市場には発泡に入りきらないサイズのタチウオの尾っぽが、あっちでひらひら、こっちでひらひらしている。定置網の中で大量の獲物に揉まれてギンギラギンではなく、銀皮が鈍色になっている。ともにかみ合った傷もある。魚を知らない人はこりゃダメだろうと思ってしまいそうだが、タチウオの場合、ギンギラギンはだめなのだ。脂があるほど剥げやすい。それなのに流通上はギンギンギラギラした方が高いなど、不思議でならない。小田原魚市場二宮定置に数尾いただいて、車に帰ったら、またいただいていた。二宮定置、どなたか知らないけどもうひとかた、ありがとう。タチウオだらけなので近所に配り、ブリは『市場寿司 たか』と半分こする。『市場寿司 たか』では、丼にしてお出ししたと思うがいかがだっただろう。そしてタチウオだが、きらめきはなかったが案の定、脂がたっぷり硬く締まった身に混在して白濁させているではないか。ちなみに相模湾だけではなく、東京湾にもタチウオがわいているのである。相模湾のも上等なら東京湾のも上等だと言っておきたい。ちなみに昔は相模湾にはあまりタチウオがいなかった。ましてや東京湾にはタチウオがほとんどいなかったはずである。このタチウオの増大は明らかに温暖化の影響だ。産卵場所が北に広がっているのである。もっともっとたくさんタチウオがわいている海域がほかにもあると思うが、いつからこの国はタチウオだらけになったのだろう。とれているときに、とれている魚種を食べるのがいちばん自然に優しい。今、タチウオとブリはたんとたんとおあがりやす、なのだ。 今年はホタルイカが安い。非常に慌ただしい年でボイルは何度か食べているが、生ホタルは買っていない。そんなことを考えての市場行、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でヤギの剥き身を買っていて、すぐ隣にあったのが生ホタルだ。昔は丸のまま生で食べていた人がいたが、寄生虫(旋尾線虫)が問題となり、大型のイカと同様に下ろして刺身にするか、足(腕)だけにするかとなっている。生ホタルの魅力は半減した。今回、久しぶりの生を、リゾットにしたり、パスタにしたりするとボイルにはない味があることを発見した。生である意味は意外にも大きいではないか!当たり前だけど、ゆでたてを温かい内に食べてもおいしい。
今年はホタルイカが安い。非常に慌ただしい年でボイルは何度か食べているが、生ホタルは買っていない。そんなことを考えての市場行、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でヤギの剥き身を買っていて、すぐ隣にあったのが生ホタルだ。昔は丸のまま生で食べていた人がいたが、寄生虫(旋尾線虫)が問題となり、大型のイカと同様に下ろして刺身にするか、足(腕)だけにするかとなっている。生ホタルの魅力は半減した。今回、久しぶりの生を、リゾットにしたり、パスタにしたりするとボイルにはない味があることを発見した。生である意味は意外にも大きいではないか!当たり前だけど、ゆでたてを温かい内に食べてもおいしい。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウはフグ調理師である。時季にはいつもフグを在庫として持っている。4月になれば、フグも終い、終いのフグと言えばヒガンフグである。以上は以前書いたこと。ヒガンフグを買った目的は塩蔵ものを作るためだ。フグ科トラフグ属の魚は塩もの向きだと思っているので、じょじょに全種で作っていきたいと考えている。ヒガンフグはみがいて(毒を除去し)、三枚に下ろす。両側の身にべた塩をつけて、数時間ごとにひっくり返す。これを2日くらい続ける。表面の塩を洗い流し、水分を切り、ビニールなどに密閉する。数日間寝かせる。(今回は1週間)
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウはフグ調理師である。時季にはいつもフグを在庫として持っている。4月になれば、フグも終い、終いのフグと言えばヒガンフグである。以上は以前書いたこと。ヒガンフグを買った目的は塩蔵ものを作るためだ。フグ科トラフグ属の魚は塩もの向きだと思っているので、じょじょに全種で作っていきたいと考えている。ヒガンフグはみがいて(毒を除去し)、三枚に下ろす。両側の身にべた塩をつけて、数時間ごとにひっくり返す。これを2日くらい続ける。表面の塩を洗い流し、水分を切り、ビニールなどに密閉する。数日間寝かせる。(今回は1週間) 神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、ワタルさんのところに揚がったオニオコゼをおろしていたら、可愛らしいおもちゃのような子がポロリンコとこぼれ落ちた。16mmの、カニの赤ちゃん、メガロパである。このエビでもカニでもない、どことなくぎょうげた形の子が大好きである。春、堤防などで釣りをしていると、きらきらコバルトグリーンに輝くメガロパがミズスマシのように泳いでいることがある。これをバケツに放り込んで見ていると、ロボットのようだし、小さな宇宙船のようようでもある。のぞいている内に、釣りなどやっていられなくなるのはどうしてだろう。今回は、カニの赤ちゃんの話だが、この場合のカニは短尾下目というグループで、カニの研究者として世界的に有名であった酒井恒は真生のカニとしている。エビ(クルマエビなど根鰓下目)、エビ(抱卵下目)やヤドカリやタラバガニの異尾下目、カニの短尾下目などを十脚目という。動いたりはったりする足(脚)が10本だからだ。
神奈川県小田原市、小田原魚市場、江の安、ワタルさんのところに揚がったオニオコゼをおろしていたら、可愛らしいおもちゃのような子がポロリンコとこぼれ落ちた。16mmの、カニの赤ちゃん、メガロパである。このエビでもカニでもない、どことなくぎょうげた形の子が大好きである。春、堤防などで釣りをしていると、きらきらコバルトグリーンに輝くメガロパがミズスマシのように泳いでいることがある。これをバケツに放り込んで見ていると、ロボットのようだし、小さな宇宙船のようようでもある。のぞいている内に、釣りなどやっていられなくなるのはどうしてだろう。今回は、カニの赤ちゃんの話だが、この場合のカニは短尾下目というグループで、カニの研究者として世界的に有名であった酒井恒は真生のカニとしている。エビ(クルマエビなど根鰓下目)、エビ(抱卵下目)やヤドカリやタラバガニの異尾下目、カニの短尾下目などを十脚目という。動いたりはったりする足(脚)が10本だからだ。 深海のある相模湾の魚種の豊富さと水産生物の移り変わりがわかる。それにしてもブリとタチウオは大漁、大量。マフグ、イネゴチ、クエ、スズキ、マグフグ、ホウボウ、タカノハダイ、イシダイ、イシガキダイ、ソコイトヨリ、マダイ、ブリ(ブリサイズ・ワラササイズ・イナダサイズ)、カイワリ、イボダイ、イサキ、ヤマトカマス、シロサバフグ、クロダイ、マンボウ、メアジ、オニオコゼ、ミノカサゴ、ニジマス、マトウダイ、アカアマダイ、ハマトビウオ、ヒラマサ、カツオ、ヒラメ、ボラギンザメ、ミシマオコゼ、ボラ、アカヤガアラ、チダイ、ウマヅラハギ、シマウシノシタ、ツバメウオ、キジハタ、ネコザメ、ムシガレイ、タチウオ、アカエイ、ホシエイ。レイシガイ、クロアワビ、メイタガレイ、スルメイカ、アオリイカ、ケンサキイカ、マダコ、シマダコ。ウチワエビ、セミエビ、ゾウリエビ、カマクラエビ(ハコエビ)。アカナマコ。ワカメ。
深海のある相模湾の魚種の豊富さと水産生物の移り変わりがわかる。それにしてもブリとタチウオは大漁、大量。マフグ、イネゴチ、クエ、スズキ、マグフグ、ホウボウ、タカノハダイ、イシダイ、イシガキダイ、ソコイトヨリ、マダイ、ブリ(ブリサイズ・ワラササイズ・イナダサイズ)、カイワリ、イボダイ、イサキ、ヤマトカマス、シロサバフグ、クロダイ、マンボウ、メアジ、オニオコゼ、ミノカサゴ、ニジマス、マトウダイ、アカアマダイ、ハマトビウオ、ヒラマサ、カツオ、ヒラメ、ボラギンザメ、ミシマオコゼ、ボラ、アカヤガアラ、チダイ、ウマヅラハギ、シマウシノシタ、ツバメウオ、キジハタ、ネコザメ、ムシガレイ、タチウオ、アカエイ、ホシエイ。レイシガイ、クロアワビ、メイタガレイ、スルメイカ、アオリイカ、ケンサキイカ、マダコ、シマダコ。ウチワエビ、セミエビ、ゾウリエビ、カマクラエビ(ハコエビ)。アカナマコ。ワカメ。 日本各地で、ブリ大漁にわいている。昔、本州中部以南といわれた地域で外洋に面した海域に、ブリの大きな群れが入っているのだ。本来、4月、5月といえば高知県や愛媛県南部、九州南部でブリの大漁をみる。この時季の個体は、卵巣精巣は膨らみすぎて柔らかく、脂が少なく、身が痩せ気味というのが本来の形だ。ちなみにこの痩せたブリがまずいか? というとそんなこともない。需要もあって、これを上手に料理する人もいて、存在価値はそれなりに大きいということも忘れてはならない。今年はその産卵群が大量に入る鹿児島県東シナ海側で漁が安定していないのである。その代わりにとれた個体に脂があり、身に張りもある。今現在、全国的に揚がっているブはおしなべて、脂が乗っていて体層うまいということだ。以下は小田原ブリの話にしぼるが、今回の春ブリ大量は全国的であることもお忘れなく。相模湾で揚がっている個体は、ワラサかブリかと迷う6㎏〜8kgサイズが多いものの水揚げを見ているだけで、脂ののりが保証できそう、といったものばかりだ。とすると、相模湾でのブリの旬で漁の最盛期は弥生、4月になってしまうが、小田原のブリはまだ生殖巣がそれほど大きくなく、5月までいけそうなのである。6月の声をきけばオホーツクでブリが揚がり始めるだろう。これじゃ年がら年中ブリだ。そのひとつ、神奈川県小田原のブリ水揚げもまるで祭のときのように騒がしく、漁師も買受人もどことなく浮き浮きとして楽しそうでもある。
日本各地で、ブリ大漁にわいている。昔、本州中部以南といわれた地域で外洋に面した海域に、ブリの大きな群れが入っているのだ。本来、4月、5月といえば高知県や愛媛県南部、九州南部でブリの大漁をみる。この時季の個体は、卵巣精巣は膨らみすぎて柔らかく、脂が少なく、身が痩せ気味というのが本来の形だ。ちなみにこの痩せたブリがまずいか? というとそんなこともない。需要もあって、これを上手に料理する人もいて、存在価値はそれなりに大きいということも忘れてはならない。今年はその産卵群が大量に入る鹿児島県東シナ海側で漁が安定していないのである。その代わりにとれた個体に脂があり、身に張りもある。今現在、全国的に揚がっているブはおしなべて、脂が乗っていて体層うまいということだ。以下は小田原ブリの話にしぼるが、今回の春ブリ大量は全国的であることもお忘れなく。相模湾で揚がっている個体は、ワラサかブリかと迷う6㎏〜8kgサイズが多いものの水揚げを見ているだけで、脂ののりが保証できそう、といったものばかりだ。とすると、相模湾でのブリの旬で漁の最盛期は弥生、4月になってしまうが、小田原のブリはまだ生殖巣がそれほど大きくなく、5月までいけそうなのである。6月の声をきけばオホーツクでブリが揚がり始めるだろう。これじゃ年がら年中ブリだ。そのひとつ、神奈川県小田原のブリ水揚げもまるで祭のときのように騒がしく、漁師も買受人もどことなく浮き浮きとして楽しそうでもある。 昔々築地場内で、貝を剥くバアチャンに「ヤギ(バカガイ)好きだね」、と何度か言われたことがある。築地には貝専門店がいくつもあって、帰り際に剥き身にしてもらっていたものである。貝を剥く情景が市場から消えて久しく、これこそが東京本来の市場らしさだと思っていたボクは、わずかに残っていた江戸のよすがが消えたと思っている。八王子の市場に今、貝屋はないので、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でヤギの剥き身を買う。間違いなく産地は北海道である。足(刺身で食べる部分で。二枚貝が砂にもぐり込むときに使う)の色が淡いのである。それでも足に膨らみがあって春らしい。ときどき「北海道産よりも江戸前、木更津あたりが上だね」という人がいるが、ボク個人としてはそんなに違いがあるとは思えない。だいたい最近、江戸前の船橋、木更津、富津のバカゲェを食べていない。ちなみに元禄期(1700年前後)に、江戸の町は100万人前後の人口を抱えるようになり、水産物を江戸前である品川〜大島あたりではまかなえなくなり、旧葛飾郡(行徳、船橋市、千葉市、市原市)でも足りなくなり、木更津あたりに供給地を求めるようになる。この下総の二枚貝の集積地が市原市青柳になったのは、供給地の広がり故だと思っている。これが縁で、日本橋にあったときから魚河岸の仲買の里(出身地)が佃島だけではなく、浦安であったり、行徳であったり、船橋であったりしたのだ。まさか後に、三河(愛知県)、北海道と主産地が移り変わるとは思ってもいなかったはずだ。ヤギはあまりにも日常的なので深夜酒の前にさささっと仕込む。剥き身の水管とひもをはずし、皮膜を切り捨てる。水管・ひもは塩水で洗い水分をきって保存する。足は開いて、「イチ」と言う間ほどに湯に通す。水分をよくきる。これで刺身の出来上がりなので超簡単である。ちょっと贅沢にわさびをすり、福島県猪苗代町、稲川本醸造を冷やして1ぱいだけ。本醸造は香り弱く、辛口でバカに合う。ヤギはあまりにも日常的なので、味の表現が難しい。味覚学の世界では、いくつかのアミノ酸が合わさると甘いと感じると言うが、それだと思う。その甘味以上に感じられるのが渋味である。シ・ブ・ミと音にしていうとハードボイルドな感じがしていい。
昔々築地場内で、貝を剥くバアチャンに「ヤギ(バカガイ)好きだね」、と何度か言われたことがある。築地には貝専門店がいくつもあって、帰り際に剥き身にしてもらっていたものである。貝を剥く情景が市場から消えて久しく、これこそが東京本来の市場らしさだと思っていたボクは、わずかに残っていた江戸のよすがが消えたと思っている。八王子の市場に今、貝屋はないので、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産でヤギの剥き身を買う。間違いなく産地は北海道である。足(刺身で食べる部分で。二枚貝が砂にもぐり込むときに使う)の色が淡いのである。それでも足に膨らみがあって春らしい。ときどき「北海道産よりも江戸前、木更津あたりが上だね」という人がいるが、ボク個人としてはそんなに違いがあるとは思えない。だいたい最近、江戸前の船橋、木更津、富津のバカゲェを食べていない。ちなみに元禄期(1700年前後)に、江戸の町は100万人前後の人口を抱えるようになり、水産物を江戸前である品川〜大島あたりではまかなえなくなり、旧葛飾郡(行徳、船橋市、千葉市、市原市)でも足りなくなり、木更津あたりに供給地を求めるようになる。この下総の二枚貝の集積地が市原市青柳になったのは、供給地の広がり故だと思っている。これが縁で、日本橋にあったときから魚河岸の仲買の里(出身地)が佃島だけではなく、浦安であったり、行徳であったり、船橋であったりしたのだ。まさか後に、三河(愛知県)、北海道と主産地が移り変わるとは思ってもいなかったはずだ。ヤギはあまりにも日常的なので深夜酒の前にさささっと仕込む。剥き身の水管とひもをはずし、皮膜を切り捨てる。水管・ひもは塩水で洗い水分をきって保存する。足は開いて、「イチ」と言う間ほどに湯に通す。水分をよくきる。これで刺身の出来上がりなので超簡単である。ちょっと贅沢にわさびをすり、福島県猪苗代町、稲川本醸造を冷やして1ぱいだけ。本醸造は香り弱く、辛口でバカに合う。ヤギはあまりにも日常的なので、味の表現が難しい。味覚学の世界では、いくつかのアミノ酸が合わさると甘いと感じると言うが、それだと思う。その甘味以上に感じられるのが渋味である。シ・ブ・ミと音にしていうとハードボイルドな感じがしていい。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。以上は前回に書きとめた。このときお茶菓子代わりに兜焼きを作り、一度ダウンして昼下がりに腹の虫を慰めるために飯もんを作った。いちばん簡単にできる「南予風 鯛めし(鯛飯)」である。 鼻水攻撃で1日棒に振り、貴重な時間が消えてなくなる。今年もなんの収穫もなしに過ぎていくんだろうなと思いながら、埼玉県川島町、大河戸製麺の太焼きそば麺で焼きそばを作る。ときどき焼きそばを無性に食べたくなるボクだけど、今年になって、ずーっと「あとがけ」である。「あとがけ焼きそば」は山形県酒田市の名物でもあるが、調理の途中、ソースをからめ、ソースを焦がすという工程がない。味つけはテーブルのソースで好きにやってくれ、といった投げやりさが逆にいい。ソースをかけすぎると大変なことになるが、自己責任なので、文句のいいようがない。いろいろ上にのってゴージャスだったが、逆に麺は平凡だった。焼きそばとか、お好み焼きとかは明らかに1945年の戦後のものである。いろいろ歴史を語る向きがあるが、基本的に新しいと考えないとダメだと思っている。1945年以前にたどるのは歴史を複雑化して面白いけど、本質から大はずれしている気がする。江東区の老人は、小麦粉が世に氾濫したのは敗戦後、アメリカ軍によるという。関東平野の土壌とか小麦の生産量とかいろんなことを関東の名物焼きそばを語るときにつけ加えるが、戦後の粉食は意外に単純かも。当然、1960年前後の酒田市の「あとがけ焼きそば」も同様だと思う。ただ、中華の焼きそばと、この国の庶民が作り出したソースの焼きそばの違いは、調べると面白いと思う。さて、ボクが作るのは、あり合わせのものだけで作り、何も乗っけないで、とてもシンプルなものだ。味のいい埼玉の麺で作るので香ばしくソテーして麺そのものの味を楽しんでいる。ソースは千葉県で買ったカゴメのウスターソース。カゴメソースとブルドッグはどちらかというと酸味が薄く、優等生的な味だ。ソースに関しては。イカリソース、名前が出てこない北海道で買ったソースなど、ちょっとずつ地域によって違いがあるのが楽しい。こんな日常的なものの違いを楽しむのも旅だと考えている。
鼻水攻撃で1日棒に振り、貴重な時間が消えてなくなる。今年もなんの収穫もなしに過ぎていくんだろうなと思いながら、埼玉県川島町、大河戸製麺の太焼きそば麺で焼きそばを作る。ときどき焼きそばを無性に食べたくなるボクだけど、今年になって、ずーっと「あとがけ」である。「あとがけ焼きそば」は山形県酒田市の名物でもあるが、調理の途中、ソースをからめ、ソースを焦がすという工程がない。味つけはテーブルのソースで好きにやってくれ、といった投げやりさが逆にいい。ソースをかけすぎると大変なことになるが、自己責任なので、文句のいいようがない。いろいろ上にのってゴージャスだったが、逆に麺は平凡だった。焼きそばとか、お好み焼きとかは明らかに1945年の戦後のものである。いろいろ歴史を語る向きがあるが、基本的に新しいと考えないとダメだと思っている。1945年以前にたどるのは歴史を複雑化して面白いけど、本質から大はずれしている気がする。江東区の老人は、小麦粉が世に氾濫したのは敗戦後、アメリカ軍によるという。関東平野の土壌とか小麦の生産量とかいろんなことを関東の名物焼きそばを語るときにつけ加えるが、戦後の粉食は意外に単純かも。当然、1960年前後の酒田市の「あとがけ焼きそば」も同様だと思う。ただ、中華の焼きそばと、この国の庶民が作り出したソースの焼きそばの違いは、調べると面白いと思う。さて、ボクが作るのは、あり合わせのものだけで作り、何も乗っけないで、とてもシンプルなものだ。味のいい埼玉の麺で作るので香ばしくソテーして麺そのものの味を楽しんでいる。ソースは千葉県で買ったカゴメのウスターソース。カゴメソースとブルドッグはどちらかというと酸味が薄く、優等生的な味だ。ソースに関しては。イカリソース、名前が出てこない北海道で買ったソースなど、ちょっとずつ地域によって違いがあるのが楽しい。こんな日常的なものの違いを楽しむのも旅だと考えている。 千葉県千葉市、千葉市地方卸売市場は規模が大きく、関連棟も充実している。あまりにも細長いのが難点で、できれば正方形に近い形で作って欲しかった。長すぎるので途中で一休みしたくなる。そんな中間地点にあったのがミルクスタンド カワイだ。看板にたばこ、新聞、雑誌、牛乳、パンとある。この総てが今では斜陽である。あえて言えば菓子パンは売れるかも。あまりにも懐かしいので、ここで牛乳を飲む。フルヤ牛乳の4.2特濃牛乳だった。4.2は意味不明だったが、ガラスケースの上でフィルムをはがしてフタを開けてくれた。本当に懐かしいさがこみ上げてきた。
千葉県千葉市、千葉市地方卸売市場は規模が大きく、関連棟も充実している。あまりにも細長いのが難点で、できれば正方形に近い形で作って欲しかった。長すぎるので途中で一休みしたくなる。そんな中間地点にあったのがミルクスタンド カワイだ。看板にたばこ、新聞、雑誌、牛乳、パンとある。この総てが今では斜陽である。あえて言えば菓子パンは売れるかも。あまりにも懐かしいので、ここで牛乳を飲む。フルヤ牛乳の4.2特濃牛乳だった。4.2は意味不明だったが、ガラスケースの上でフィルムをはがしてフタを開けてくれた。本当に懐かしいさがこみ上げてきた。 東京都東久留米市、東京北魚で買い求めた新潟県佐渡産白バイは、明らかに富山湾、朝鮮半島東岸などにいる、カガバイよりも北にいるタイプ、ノッポバイだと考えた。このあたりは貝類学者の黒住耐二さんの考えとも一致する。中に1個体だけオオエッチュウバイが混ざっていた。とするとバイかご(バイガイ用のかご)の水深は400mくらいではないかと思われる。オオエッチュウバイはエッチュウバイ・ノッポバイと比べると深い場所にいるが、今回の佐渡沖ではその中間地点で漁が行われていて、オオエッチュウバイとノッポバイを水揚げ後選別している可能性を感じる。ちなみにノッポバイと比べるとオオエッチュウバイは大きいというのもあるが、ずんぐりむっくりして膨らみが強く、貝殻が薄くもろい。オオエッチュウバイは島根県、山口県などで大量に揚がる白バイ(エッチュウバイ)などと比べて、遙かに美味である。新潟県で名物として高値がつくのもわかる気がする。
東京都東久留米市、東京北魚で買い求めた新潟県佐渡産白バイは、明らかに富山湾、朝鮮半島東岸などにいる、カガバイよりも北にいるタイプ、ノッポバイだと考えた。このあたりは貝類学者の黒住耐二さんの考えとも一致する。中に1個体だけオオエッチュウバイが混ざっていた。とするとバイかご(バイガイ用のかご)の水深は400mくらいではないかと思われる。オオエッチュウバイはエッチュウバイ・ノッポバイと比べると深い場所にいるが、今回の佐渡沖ではその中間地点で漁が行われていて、オオエッチュウバイとノッポバイを水揚げ後選別している可能性を感じる。ちなみにノッポバイと比べるとオオエッチュウバイは大きいというのもあるが、ずんぐりむっくりして膨らみが強く、貝殻が薄くもろい。オオエッチュウバイは島根県、山口県などで大量に揚がる白バイ(エッチュウバイ)などと比べて、遙かに美味である。新潟県で名物として高値がつくのもわかる気がする。 かなり前の話だけど、コンビニで「ツナマヨがない」と騒いでいるお子様がいたので、そのときボクはー♪ 気がついたー♪ そうだ春休みだと。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で目的があってカツオを1尾買っていた。ツナマヨが頭にあったので、じっくりしみじみツナについて考えた。目的があって買ったカツオだが、余り半身を刺身で、というのをやめてツナマヨ作ろう!さて、ツナマヨとはなんだろう?ツナという魚の一覧に関してはサイトを見てもらうしかないのではしょる。料理であって料理ではないようなもので、ツナ(マグロ属)、カツオのツナ缶(オイル漬け・水煮缶)とマヨネーズを和えたものだ。どの家でも普通に作っているものが、コンビニのせいで一般名詞化した例のひとつだろう。考えてみると1985年に、まだ新人モデルだった広田けいこ(漢字忘れた)が、深夜にいなりずしを食べたくなったせいで、「いなりずし」が一般名詞化したのと同じである。蛇足だけど、このせいで「きつねずし」という言語が駆逐される。
かなり前の話だけど、コンビニで「ツナマヨがない」と騒いでいるお子様がいたので、そのときボクはー♪ 気がついたー♪ そうだ春休みだと。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で目的があってカツオを1尾買っていた。ツナマヨが頭にあったので、じっくりしみじみツナについて考えた。目的があって買ったカツオだが、余り半身を刺身で、というのをやめてツナマヨ作ろう!さて、ツナマヨとはなんだろう?ツナという魚の一覧に関してはサイトを見てもらうしかないのではしょる。料理であって料理ではないようなもので、ツナ(マグロ属)、カツオのツナ缶(オイル漬け・水煮缶)とマヨネーズを和えたものだ。どの家でも普通に作っているものが、コンビニのせいで一般名詞化した例のひとつだろう。考えてみると1985年に、まだ新人モデルだった広田けいこ(漢字忘れた)が、深夜にいなりずしを食べたくなったせいで、「いなりずし」が一般名詞化したのと同じである。蛇足だけど、このせいで「きつねずし」という言語が駆逐される。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で広島市産カンカン入り剥きガキを5つ買う。225円だった。あくまでもボクの場合だけど、マガキは10月から3月いっぱいまでにしている。今年はちょっとだけ遅れて、4月中旬にマガキ終いをする。そのための5つである。ちなみに懐石ではそろそろ「名残の」、とつきそうなマガキだけど、この4月がいちばんぽってり太っているのが残念でならない。近年、食い時を4月いっぱいまでに延長したくなっているが、イワガキと重なるのがいやなので、迷いに迷っている。思えば初カキフライは遅れ、昨年11月も末のことだった。振り返ってみると昔は10月の声を聞くと間違いなく秋深し、だったのに最近では11月に秋の気配を感じている。海水温の上昇にもだえくるしむ海藻たちの気持ちがわかる。さて、4月半ば、広島市江波の剥きガキは触ると弾力があり上々のものであった。帰宅後、剥きガキは大根おろしできれいにして、水分をきって、冷蔵庫で一休みしてもらう。市場から帰宅すると、買ったもの、送られて来たものを処理しなくてはいけないので、2時間前後魚介類にまみれる。ここでシャワーをあびるのだけど、お昼ご飯の大方を作っておく。カキフライの材料を集めて置く。剥き身に塩コショウし、小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。水産生物の細かい部分まで見たり撮影したりすると、脳みそも身体も疲れ切るので、この日はシャワーではなく湯船で身体を癒やす。風呂上がりに、皿にキャベツがなかったので、セルバティコを敷き、カキフライを揚げて並べてお終いである。これでビールといきたいところだけど、さんぴん茶を氷入りで。早く昼ビールをやりたいものだと思うけど、人生我慢が肝心なのだ。終いのカキフライがたった5個というのが、ボクの体調のせいなのも悲しい。でも、揚げたてのカキフライにご飯、ワカメのみそ汁にさんぴん茶は、いい昼ご飯だと思う。揚げたてのカキフライの、じゅわりと出てくるジュのうまさたるや筆舌に尽くしがたい。ご飯との相性がいいことにも喜びを感じる。ふと、「あ、あ」、今季もこれで、この渋甘い、濃厚なカキフライともおさらばか、なんて切なくもなる。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で広島市産カンカン入り剥きガキを5つ買う。225円だった。あくまでもボクの場合だけど、マガキは10月から3月いっぱいまでにしている。今年はちょっとだけ遅れて、4月中旬にマガキ終いをする。そのための5つである。ちなみに懐石ではそろそろ「名残の」、とつきそうなマガキだけど、この4月がいちばんぽってり太っているのが残念でならない。近年、食い時を4月いっぱいまでに延長したくなっているが、イワガキと重なるのがいやなので、迷いに迷っている。思えば初カキフライは遅れ、昨年11月も末のことだった。振り返ってみると昔は10月の声を聞くと間違いなく秋深し、だったのに最近では11月に秋の気配を感じている。海水温の上昇にもだえくるしむ海藻たちの気持ちがわかる。さて、4月半ば、広島市江波の剥きガキは触ると弾力があり上々のものであった。帰宅後、剥きガキは大根おろしできれいにして、水分をきって、冷蔵庫で一休みしてもらう。市場から帰宅すると、買ったもの、送られて来たものを処理しなくてはいけないので、2時間前後魚介類にまみれる。ここでシャワーをあびるのだけど、お昼ご飯の大方を作っておく。カキフライの材料を集めて置く。剥き身に塩コショウし、小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。水産生物の細かい部分まで見たり撮影したりすると、脳みそも身体も疲れ切るので、この日はシャワーではなく湯船で身体を癒やす。風呂上がりに、皿にキャベツがなかったので、セルバティコを敷き、カキフライを揚げて並べてお終いである。これでビールといきたいところだけど、さんぴん茶を氷入りで。早く昼ビールをやりたいものだと思うけど、人生我慢が肝心なのだ。終いのカキフライがたった5個というのが、ボクの体調のせいなのも悲しい。でも、揚げたてのカキフライにご飯、ワカメのみそ汁にさんぴん茶は、いい昼ご飯だと思う。揚げたてのカキフライの、じゅわりと出てくるジュのうまさたるや筆舌に尽くしがたい。ご飯との相性がいいことにも喜びを感じる。ふと、「あ、あ」、今季もこれで、この渋甘い、濃厚なカキフライともおさらばか、なんて切なくもなる。 ちょっとだけ日記風に。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。目の下一尺、1.1kg の理想的な大きさのマダイである。ちなみにマダイはこの目の下一尺から一尺半くらいがいいと思っておりまする。執念深い明石人(原はつきまへん)が飛ばしてきたタイなので、鮮度抜群やし、ちゃんと血抜きされてますので、これ以上望めない、といったものである。瀬戸内海といえば産卵期に大漁が続く「魚島の鯛」だが、5月、6月に大量に揚がるタイはそれほどはうまくない。「魚島の鯛」の手前まで文句なしにおいしくて、「魚島の鯛」になったら「これはこれで重宝します。おかずにします」と考えるべきである。産卵間近、産卵後のマダイを猫またぎというアホな魚通がいるが、大間違い。これはこれで料理のやりかた次第で抜群にうまいと、わざわざつけ加えておきたい。基本的に買った魚は計測して、撮影する。タイ科の魚は下ろす難易度が極めて低いのでほんの数分でばらばら事件となる。まっさきに作ったのが兜焼きである。「兜焼きなんぞ、なんで作ってもおんなしですがな」と昔、大阪市にある、長い長い商店街の曾我廼家五郎八に、養殖もののマダイの兜をすすめられたが、兜の塩焼きほど、そのタイの素性がわかるものはない。兜焼きは上物のタイで作らなあきまへん。ちなみにこの日、我が家にはおやつが枯渇していた。お茶を飲んでもつまむものがない。お菓子代わりの兜焼きでもある。
ちょっとだけ日記風に。八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に兵庫県明石市、明石浦漁業協同組合から明石鯛(マダイ)が来ていた。桜はまだちらほら残っているので、ぎりぎり桜鯛という言語を使ってもいいだろう。目の下一尺、1.1kg の理想的な大きさのマダイである。ちなみにマダイはこの目の下一尺から一尺半くらいがいいと思っておりまする。執念深い明石人(原はつきまへん)が飛ばしてきたタイなので、鮮度抜群やし、ちゃんと血抜きされてますので、これ以上望めない、といったものである。瀬戸内海といえば産卵期に大漁が続く「魚島の鯛」だが、5月、6月に大量に揚がるタイはそれほどはうまくない。「魚島の鯛」の手前まで文句なしにおいしくて、「魚島の鯛」になったら「これはこれで重宝します。おかずにします」と考えるべきである。産卵間近、産卵後のマダイを猫またぎというアホな魚通がいるが、大間違い。これはこれで料理のやりかた次第で抜群にうまいと、わざわざつけ加えておきたい。基本的に買った魚は計測して、撮影する。タイ科の魚は下ろす難易度が極めて低いのでほんの数分でばらばら事件となる。まっさきに作ったのが兜焼きである。「兜焼きなんぞ、なんで作ってもおんなしですがな」と昔、大阪市にある、長い長い商店街の曾我廼家五郎八に、養殖もののマダイの兜をすすめられたが、兜の塩焼きほど、そのタイの素性がわかるものはない。兜焼きは上物のタイで作らなあきまへん。ちなみにこの日、我が家にはおやつが枯渇していた。お茶を飲んでもつまむものがない。お菓子代わりの兜焼きでもある。 千葉県には船橋、柏市、松戸市、成田市、そして千葉市に水産を含む市場がある。それぞれに個性があり、地域を反映している。柏市は完全に消費地市場で上物も多く、荷の量も多い。仲卸が魅力的である。船橋市は東京湾を強く感じるところで、昔の築地を思わせるよさがある。松戸市は比較的安く、しかも仲卸が一般人に対して親切である、関連棟が魅力的だ。千葉市地方卸売市場の水産棟は規模が大きく、上物あり、マグロ屋が多く、比較的廉価なものもあり、塩乾などもある総合的な水産市場である。場内には、上物がたくさん並んでいた。生を扱うマグロ屋もあり、クエなどの超高級魚も並ぶ。
千葉県には船橋、柏市、松戸市、成田市、そして千葉市に水産を含む市場がある。それぞれに個性があり、地域を反映している。柏市は完全に消費地市場で上物も多く、荷の量も多い。仲卸が魅力的である。船橋市は東京湾を強く感じるところで、昔の築地を思わせるよさがある。松戸市は比較的安く、しかも仲卸が一般人に対して親切である、関連棟が魅力的だ。千葉市地方卸売市場の水産棟は規模が大きく、上物あり、マグロ屋が多く、比較的廉価なものもあり、塩乾などもある総合的な水産市場である。場内には、上物がたくさん並んでいた。生を扱うマグロ屋もあり、クエなどの超高級魚も並ぶ。 北海道室蘭市、『ヤマサン 渡辺』、山本涼子さんたちに送って頂いた、エゾバイ科モロハバイ属の巻き貝を完全に処理するのにはまだまだ時間がかかる。合計10㎏近くが我が家に眠っていて、基本的に全部のタイプを分けたつもりだだけど、全然行き着く先はわからない。千葉県立博物館に何㎏か送り、そのうちモロハバイ属の座談会をひらく。我が家にある貝類図鑑は13冊だが、県立博物館にはこの何倍もあり、紙で保存している論文も多い。この1つの属をめぐってああでもない、こうでもないと議論することは非常に有意義である。偉大なる貝類学者の一人である、吉良哲明(1888-1965。僧侶でもあった)は、この座談会的なものの中心にいて、貝類の分類をすすめていたのだと考えている。この非常においしい、北国の巻き貝は、我が家にある貝類図鑑では、モロハバイ、ヤゲンバイ、ヒモカケヤゲンバイ、ヒトハバイになるが、1種にまとめるべきか、それぞれ亜種としていいかは、ボクの段階ではわからない。ことほどさように同定というものは難しい。テレビの監修をやっていたことがあるし、問い合わせに応じたこともあるけど、画像だけで見るのは不可能なものがいっぱいある。4月中には結論を出すつもりだが、亜種すべてをページ化する。
北海道室蘭市、『ヤマサン 渡辺』、山本涼子さんたちに送って頂いた、エゾバイ科モロハバイ属の巻き貝を完全に処理するのにはまだまだ時間がかかる。合計10㎏近くが我が家に眠っていて、基本的に全部のタイプを分けたつもりだだけど、全然行き着く先はわからない。千葉県立博物館に何㎏か送り、そのうちモロハバイ属の座談会をひらく。我が家にある貝類図鑑は13冊だが、県立博物館にはこの何倍もあり、紙で保存している論文も多い。この1つの属をめぐってああでもない、こうでもないと議論することは非常に有意義である。偉大なる貝類学者の一人である、吉良哲明(1888-1965。僧侶でもあった)は、この座談会的なものの中心にいて、貝類の分類をすすめていたのだと考えている。この非常においしい、北国の巻き貝は、我が家にある貝類図鑑では、モロハバイ、ヤゲンバイ、ヒモカケヤゲンバイ、ヒトハバイになるが、1種にまとめるべきか、それぞれ亜種としていいかは、ボクの段階ではわからない。ことほどさように同定というものは難しい。テレビの監修をやっていたことがあるし、問い合わせに応じたこともあるけど、画像だけで見るのは不可能なものがいっぱいある。4月中には結論を出すつもりだが、亜種すべてをページ化する。 ウナギの旅を続けているとき、ボクの出身県である徳島県小松島の「竹ちくわ」を送って頂いたのはタイムリーだった。この「竹ちくわ」と関西に多い焼き蒲鉾はウナギ料理の歴史を考える上で非常に重要なのだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光)に生まれたので、生まれて初めての都会は徳島市だった。面白いもので、徳島県でももっと西の池田町(現三好市)の老人に聞くと最初の都会は高松だったという。ことの真意はともかく、池田町で食べられていた竹輪など練り製品は「えびちくわ」だったり、普通の穴の開いた竹輪など香川県観音寺あたりのもの。これが徳島本線の池田と徳島の中間地点のボクの町では、どちらかというと小松島市・徳島市・鳴門市で作った「竹ちくわ」、「かつ」、「長天」になる。同じ県の練り製品を考えてもこれだけの違いがある。水産物など食べ物を考えるとき、ぜったいにやってはいけないのが県単位で区切ることだ。家族と一緒に徳島市内にでて、丸新デパートとかつぼみやとかを連れ歩かれて、我慢に我慢を重ねる代わりに買ってもらったのがプラモデルや本だった。それと帰りに必ずねだるのが徳島駅売店の「竹ちくわ」だ。黄緑色の包み紙を持つのはボクの役割だったと思う。この「竹ちくわ」と冷凍ミカン、機関車の煤がボクの徳島本線の最初の想い出だ。横道にそれるが、子供の頃、機関車とディーゼルカーは知っていたけど高知に行って初めて電車に乗ったとき、都会だと感じたものだ。家族のいる東京に行くときの、大阪から東京までの電車では走り回るほど興奮した。電車に都会を感じるのは国内広といえども徳島県人と沖縄県人だけだったと思う。沖縄県にはすでに電車が走っているので、追い越された感が非常に強い。小学校に上がる前後から、「竹ちくわ」はボクの好物だった。たぶんかなり高かったのではないか? だから徳島駅で買うお土産だった。あまりに好きなのでボクだけが2本、3本食べていたっけなー。さて、なぜ竹輪は竹輪なのか? それは細い竹を切り、竹を適当な長さに切る。乾燥させない生の竹に魚肉(最初は主に淡水魚)を握りつけて、直火で焼く。古代には竹についた状態が完成形だったと思う。これが後に焼き上がったら竹から外すようになる。竹につけて焼き、切ると断面が輪なので、竹輪だ。徳島の「竹ちくわ」は焼いて抜かないままだ。たぶんこの国広しといえども、こんな原始的な姿を残した竹輪はないだろう。ちなみに蒲鉾の語源を同じように棒状のものに握りつけて焼く。この形が蒲の穂に似ているから、蒲鉾だとしているが、大間違いだと思っている。これは別項で述べたい。徳島の竹輪はやや甘めである。足(弾力といっても間違いではない)はある方だと思うが、その足が強すぎないのがいい。「竹ちくわ」を食べると、Homeward Bound ♪徳島県の山崎さんには感謝の致しようがない。
ウナギの旅を続けているとき、ボクの出身県である徳島県小松島の「竹ちくわ」を送って頂いたのはタイムリーだった。この「竹ちくわ」と関西に多い焼き蒲鉾はウナギ料理の歴史を考える上で非常に重要なのだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光)に生まれたので、生まれて初めての都会は徳島市だった。面白いもので、徳島県でももっと西の池田町(現三好市)の老人に聞くと最初の都会は高松だったという。ことの真意はともかく、池田町で食べられていた竹輪など練り製品は「えびちくわ」だったり、普通の穴の開いた竹輪など香川県観音寺あたりのもの。これが徳島本線の池田と徳島の中間地点のボクの町では、どちらかというと小松島市・徳島市・鳴門市で作った「竹ちくわ」、「かつ」、「長天」になる。同じ県の練り製品を考えてもこれだけの違いがある。水産物など食べ物を考えるとき、ぜったいにやってはいけないのが県単位で区切ることだ。家族と一緒に徳島市内にでて、丸新デパートとかつぼみやとかを連れ歩かれて、我慢に我慢を重ねる代わりに買ってもらったのがプラモデルや本だった。それと帰りに必ずねだるのが徳島駅売店の「竹ちくわ」だ。黄緑色の包み紙を持つのはボクの役割だったと思う。この「竹ちくわ」と冷凍ミカン、機関車の煤がボクの徳島本線の最初の想い出だ。横道にそれるが、子供の頃、機関車とディーゼルカーは知っていたけど高知に行って初めて電車に乗ったとき、都会だと感じたものだ。家族のいる東京に行くときの、大阪から東京までの電車では走り回るほど興奮した。電車に都会を感じるのは国内広といえども徳島県人と沖縄県人だけだったと思う。沖縄県にはすでに電車が走っているので、追い越された感が非常に強い。小学校に上がる前後から、「竹ちくわ」はボクの好物だった。たぶんかなり高かったのではないか? だから徳島駅で買うお土産だった。あまりに好きなのでボクだけが2本、3本食べていたっけなー。さて、なぜ竹輪は竹輪なのか? それは細い竹を切り、竹を適当な長さに切る。乾燥させない生の竹に魚肉(最初は主に淡水魚)を握りつけて、直火で焼く。古代には竹についた状態が完成形だったと思う。これが後に焼き上がったら竹から外すようになる。竹につけて焼き、切ると断面が輪なので、竹輪だ。徳島の「竹ちくわ」は焼いて抜かないままだ。たぶんこの国広しといえども、こんな原始的な姿を残した竹輪はないだろう。ちなみに蒲鉾の語源を同じように棒状のものに握りつけて焼く。この形が蒲の穂に似ているから、蒲鉾だとしているが、大間違いだと思っている。これは別項で述べたい。徳島の竹輪はやや甘めである。足(弾力といっても間違いではない)はある方だと思うが、その足が強すぎないのがいい。「竹ちくわ」を食べると、Homeward Bound ♪徳島県の山崎さんには感謝の致しようがない。 八王子綜合卸売センター、舵丸水産、クマゴロウが銭州通いを開始した。名人なのだろう、今年はシマアジ爆釣で、ゲストが少ない。ヒレナガカンパチ、ナンヨウカイワリ、オオヒメが本命の脇を彩る存在だけど、考えたらなんて豪華絢爛であることか。今回はこの準主役級、オオヒメ(体長35cm・920g)を密かに連れ帰ってきた。少し難しい話になるが、魚類のほとんどはスズキ目(非常に上の階級)に所属するので、ニュースなどで「スズキの仲間」というくらい意味不明の言葉はない。上から階級をたどると界→門→綱→目→科→属→種、で、本当に魚介類が知りたかったら目から種くらいまでの階級は知って置くといい。オオヒメはスズキ目フエダイ科ヒメダイ属である。フエダイ科は全国的とは言えないが、関東、静岡や紀伊半島、四国南部、九州南部、琉球列島で流通のプロには当たり前の魚なのである。高級魚は流通のプロが主に作り出すものだが、その高級魚の主役もタイ科からフエダイ科に移行している。東京には、小笠原からの定期便や伊豆諸島からも「おなが(ハマダイ)」、シマチビキ、同属のヒメダイとともにやってきているので、古くからフエダイ科に慣れ親しんでいる。ヒメダイ、オオヒメは極めて似ていて、東京を始め関東周辺では、ともに「おごだい」である。種は違っているが、流通上は同種と見なされているのだ。この2種を分けるのは魚類学者か魚類学に関心を持っている一部の人間だけである。種の見分け方は慣れないとできない。ただし、「大姫」の名の通りに、ヒメダイよりもオオヒメの方が大型になる。伊豆諸島からくるヒメダイ属2種では、昔は圧倒的にヒメダイの方が多かった。ところが最近、温暖化のせいかオオヒメの比率が上がってきているようなのだ。「おごだい」の味のよさは昔から東京では知られている。ここにオオヒメが混ざり、「おごだい」は量的にも増えている。安定的に入荷しているので、価格がやや高値ではあるが安定しているのである。ここにきて魚価全般が高騰しているために、最近、ヒメダイ・オオヒメの値段が安く感じるのだ。年間を通して味がよく、その上、歩留まりがいいので、お買いでもある。この専門家にとっては平凡な魚は、いまのところ一般人には遠い存在でしかない。これを機会に、一般人にも平凡な魚になるといい。
八王子綜合卸売センター、舵丸水産、クマゴロウが銭州通いを開始した。名人なのだろう、今年はシマアジ爆釣で、ゲストが少ない。ヒレナガカンパチ、ナンヨウカイワリ、オオヒメが本命の脇を彩る存在だけど、考えたらなんて豪華絢爛であることか。今回はこの準主役級、オオヒメ(体長35cm・920g)を密かに連れ帰ってきた。少し難しい話になるが、魚類のほとんどはスズキ目(非常に上の階級)に所属するので、ニュースなどで「スズキの仲間」というくらい意味不明の言葉はない。上から階級をたどると界→門→綱→目→科→属→種、で、本当に魚介類が知りたかったら目から種くらいまでの階級は知って置くといい。オオヒメはスズキ目フエダイ科ヒメダイ属である。フエダイ科は全国的とは言えないが、関東、静岡や紀伊半島、四国南部、九州南部、琉球列島で流通のプロには当たり前の魚なのである。高級魚は流通のプロが主に作り出すものだが、その高級魚の主役もタイ科からフエダイ科に移行している。東京には、小笠原からの定期便や伊豆諸島からも「おなが(ハマダイ)」、シマチビキ、同属のヒメダイとともにやってきているので、古くからフエダイ科に慣れ親しんでいる。ヒメダイ、オオヒメは極めて似ていて、東京を始め関東周辺では、ともに「おごだい」である。種は違っているが、流通上は同種と見なされているのだ。この2種を分けるのは魚類学者か魚類学に関心を持っている一部の人間だけである。種の見分け方は慣れないとできない。ただし、「大姫」の名の通りに、ヒメダイよりもオオヒメの方が大型になる。伊豆諸島からくるヒメダイ属2種では、昔は圧倒的にヒメダイの方が多かった。ところが最近、温暖化のせいかオオヒメの比率が上がってきているようなのだ。「おごだい」の味のよさは昔から東京では知られている。ここにオオヒメが混ざり、「おごだい」は量的にも増えている。安定的に入荷しているので、価格がやや高値ではあるが安定しているのである。ここにきて魚価全般が高騰しているために、最近、ヒメダイ・オオヒメの値段が安く感じるのだ。年間を通して味がよく、その上、歩留まりがいいので、お買いでもある。この専門家にとっては平凡な魚は、いまのところ一般人には遠い存在でしかない。これを機会に、一般人にも平凡な魚になるといい。 あんまりにも同じ物を見つめすぎると身体が熱くなる。巻き貝の世界は非常に難しい。取り分け形態的な連続性を考え始めると、きりがない。別に病気でもないのに身体が熱くなり、冷たい床に腹ばいになるのが、ボクの対処法。憂さ晴らしに埼玉県まで野菜や地域ならではのものを買いに行ってきた。そしてまた埼玉県川島町の直売所で、太巻き手打ちうどん弁当(うどんつき弁当)を買った。川島町のある埼玉県など関東平野は古くからの畑作地帯で小麦粉文化圏だ。1590年、徳川家が江戸入り後すぐから徳川家は米(戦国時代に耕地が増え、米の収穫量が増えると、米本位制となる。米は食料でもあり、金と同等のものでもある)の確保に苦しんだ。徳川家家臣団、江戸幕府を築く流入民に分け与える米が不足していたのだ。この米不足は1670年代に河村瑞賢が東北からの米廻船の新航路を見出すまで続く。考えてみると関東平野は古くは秩父平氏、次いで鎌倉幕府ができ、室町期に鎌倉公方、関東管領が統治する。鎌倉公方、関東管領の享徳の乱の後、この足利の支配が消えると、後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が、享徳の乱の続きを始める。後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が天下を取れなかったのは関東平野にこだわったからだ。ものなりの悪い土地の争奪戦にこの戦国武将達はなぜにこだわったのだろう。さて、旧比企郡にある川島町は旧川越藩の領地だ。川越は太田道灌の太田氏との繋がりがあり、江戸時代には小田原藩とともに特別な藩だった。川島町周辺では江戸時代から米はとれていたものの、伊達藩、仙台米と比べると質が落ちた。ある意味、米は藩に税として収めて、主食は麦だったのではないか。ちなみに戦後になっても埼玉県の米は東京での評価は低く、安かった。江東区の民俗学資料の米穀店の聞き書きに埼玉米は煎餅屋に下ろすために仕入れているもので、決して一般家庭では食べなかったとある。埼玉県北部や群馬県にみられるゆでうどん付き弁当は、その米不足の名残である。不思議な取り合わせで決して身体にはよくないと思うけど、いろんな味が楽しめるのでついつい手が出てしまう。
あんまりにも同じ物を見つめすぎると身体が熱くなる。巻き貝の世界は非常に難しい。取り分け形態的な連続性を考え始めると、きりがない。別に病気でもないのに身体が熱くなり、冷たい床に腹ばいになるのが、ボクの対処法。憂さ晴らしに埼玉県まで野菜や地域ならではのものを買いに行ってきた。そしてまた埼玉県川島町の直売所で、太巻き手打ちうどん弁当(うどんつき弁当)を買った。川島町のある埼玉県など関東平野は古くからの畑作地帯で小麦粉文化圏だ。1590年、徳川家が江戸入り後すぐから徳川家は米(戦国時代に耕地が増え、米の収穫量が増えると、米本位制となる。米は食料でもあり、金と同等のものでもある)の確保に苦しんだ。徳川家家臣団、江戸幕府を築く流入民に分け与える米が不足していたのだ。この米不足は1670年代に河村瑞賢が東北からの米廻船の新航路を見出すまで続く。考えてみると関東平野は古くは秩父平氏、次いで鎌倉幕府ができ、室町期に鎌倉公方、関東管領が統治する。鎌倉公方、関東管領の享徳の乱の後、この足利の支配が消えると、後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が、享徳の乱の続きを始める。後北条氏、上杉謙信の上杉氏、武田氏が天下を取れなかったのは関東平野にこだわったからだ。ものなりの悪い土地の争奪戦にこの戦国武将達はなぜにこだわったのだろう。さて、旧比企郡にある川島町は旧川越藩の領地だ。川越は太田道灌の太田氏との繋がりがあり、江戸時代には小田原藩とともに特別な藩だった。川島町周辺では江戸時代から米はとれていたものの、伊達藩、仙台米と比べると質が落ちた。ある意味、米は藩に税として収めて、主食は麦だったのではないか。ちなみに戦後になっても埼玉県の米は東京での評価は低く、安かった。江東区の民俗学資料の米穀店の聞き書きに埼玉米は煎餅屋に下ろすために仕入れているもので、決して一般家庭では食べなかったとある。埼玉県北部や群馬県にみられるゆでうどん付き弁当は、その米不足の名残である。不思議な取り合わせで決して身体にはよくないと思うけど、いろんな味が楽しめるのでついつい手が出てしまう。 東京都東久留米市、東久留米卸売市場協同組合は市場の建物が新しく、鮮魚、野菜、乾物、惣菜などとても多彩だ。埼玉に近いせいか、お茶の店が多いのも特徴だろう。鮮魚は2店舗しかないが、規模が大きく、多彩な水産物を並べている。そのひとつ、東京北魚は足立市場に本部がある大型店である。荷の産地も多彩で、八王子で見られない荷主(産地仲買で出荷してくる業者)も少なくなかった。ここで今季初めてのイワガキを買った。宮崎県延岡産である。宮崎県は三重県伊勢湾側とともにもっとも出荷時期が早い。延岡市には流れ込む河川が多く、しかも海岸線が入り組んでいる。意外に知られていないが、魚介類が非常に多彩なところでもある。ちなみに今や3倍体が当たり前なので、マガキは年がら年中流通しているが、ボクは信条として、10月〜3月いっぱいまではマガキ、4月〜8月くらいまではイワガキとしている。カキ類を食べない時季があるのも、非常に好ましいことだと考えている。貝殻に余分な生き物が付着しておらず、きれいだということは養殖されたものだ。殻長11.5mmはボク好みのサイズだ。イワガキは大きいほど高いが、大きいものがうまいわけではない。しかもその重さに正比例して可食部は大きくならない。
東京都東久留米市、東久留米卸売市場協同組合は市場の建物が新しく、鮮魚、野菜、乾物、惣菜などとても多彩だ。埼玉に近いせいか、お茶の店が多いのも特徴だろう。鮮魚は2店舗しかないが、規模が大きく、多彩な水産物を並べている。そのひとつ、東京北魚は足立市場に本部がある大型店である。荷の産地も多彩で、八王子で見られない荷主(産地仲買で出荷してくる業者)も少なくなかった。ここで今季初めてのイワガキを買った。宮崎県延岡産である。宮崎県は三重県伊勢湾側とともにもっとも出荷時期が早い。延岡市には流れ込む河川が多く、しかも海岸線が入り組んでいる。意外に知られていないが、魚介類が非常に多彩なところでもある。ちなみに今や3倍体が当たり前なので、マガキは年がら年中流通しているが、ボクは信条として、10月〜3月いっぱいまではマガキ、4月〜8月くらいまではイワガキとしている。カキ類を食べない時季があるのも、非常に好ましいことだと考えている。貝殻に余分な生き物が付着しておらず、きれいだということは養殖されたものだ。殻長11.5mmはボク好みのサイズだ。イワガキは大きいほど高いが、大きいものがうまいわけではない。しかもその重さに正比例して可食部は大きくならない。 新潟市は本州日本海側で唯一の政令指定都市だ。新潟市は単なる県庁所在地ではなく、隣県にとっての文化の中心でもある。地名の新潟は、潟を埋め立てて作られた「陸地」に新しくできた町という意味だと思っている。この「潟」は、福井県以北で見られる地名、湖沼名で、平野部特有の潟湖のことだ。当然、海に近い部分は汽水域になる。旧新潟市地域とその周り、現新潟市は、旧蒲原郡で一面の沼地だった。米どころではあったが、1960年くらいまでは胸まで泥に漬かりながらの田植えの光景が見られたようだ。冷たい泥田に浸かっての田植えは過酷だったに違いない。この泥田のど真ん中、旧亀田町にあるのが新潟中央卸売市場である。日本全国からの水産物と青果が集まるところで、活気がある。金沢中央卸売市場とともに規模からして大きい。新潟市は一大消費地でもある。全国からの荷などにも目を見張るものがある。ただいかんせん新潟の市街地からは遠い。新潟漁協市場が新潟市の市街の真ん中にあり、信濃川河口域で、漁港でもあるのにたいして、中央市場は田んぼの真ん中にある。仲買さんなども両市場の移動には苦労されているようである。
新潟市は本州日本海側で唯一の政令指定都市だ。新潟市は単なる県庁所在地ではなく、隣県にとっての文化の中心でもある。地名の新潟は、潟を埋め立てて作られた「陸地」に新しくできた町という意味だと思っている。この「潟」は、福井県以北で見られる地名、湖沼名で、平野部特有の潟湖のことだ。当然、海に近い部分は汽水域になる。旧新潟市地域とその周り、現新潟市は、旧蒲原郡で一面の沼地だった。米どころではあったが、1960年くらいまでは胸まで泥に漬かりながらの田植えの光景が見られたようだ。冷たい泥田に浸かっての田植えは過酷だったに違いない。この泥田のど真ん中、旧亀田町にあるのが新潟中央卸売市場である。日本全国からの水産物と青果が集まるところで、活気がある。金沢中央卸売市場とともに規模からして大きい。新潟市は一大消費地でもある。全国からの荷などにも目を見張るものがある。ただいかんせん新潟の市街地からは遠い。新潟漁協市場が新潟市の市街の真ん中にあり、信濃川河口域で、漁港でもあるのにたいして、中央市場は田んぼの真ん中にある。仲買さんなども両市場の移動には苦労されているようである。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウはフグ調理師である。時季にはいつもフグを在庫として持っている。4月になれば、フグも終い、終いのフグと言えばヒガンフグである。関東で庶民的なフグの代表格はショウサイフグで、例えば松尾芭蕉が魚河岸の弟子達に分けてもらい(想像です)、「ふぐと汁」にしたのも、ショウサイフグである。ヒガンフグはショウサイフグよりも少しだけ上等なもの、と考えるとわかりやすい。余談になるがフグ科で高級といえるのはトラフグだけで、丸のままだと比較的安い。もちろん誰でも下ろせないということもあるが、安いけど安くないのは以下を読んでもらうしかない。未成熟な個体がお買い得で、成熟が進むと割高になる。ちなみに典型的なフグといえば、フグ科トラフグ属(の仲間)のフグである。トラフグは皮が無毒だが、ほとんどのトラフグ属のフグの皮は有毒だというのもおぼえておくといい。取り分け、トラフグ属のヒガンフグは毒が強く、可食部分は筋肉だけだ。また、関東でヒガンフグを「赤目フグ(あかめふぐ)」と呼び、同じトラフグ属のアカメフグと混同しやすいのも要注意だ。定期的にヒガンフグを買うのは歩留まりを見るためだ。丸のままのフグの多くの値段は平凡だが、可食部分からすると明らかに高級魚である。今回の個体は雌1.4kgで可食部分は680gなので、歩留まり50パーセント弱だ。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産、クマゴロウはフグ調理師である。時季にはいつもフグを在庫として持っている。4月になれば、フグも終い、終いのフグと言えばヒガンフグである。関東で庶民的なフグの代表格はショウサイフグで、例えば松尾芭蕉が魚河岸の弟子達に分けてもらい(想像です)、「ふぐと汁」にしたのも、ショウサイフグである。ヒガンフグはショウサイフグよりも少しだけ上等なもの、と考えるとわかりやすい。余談になるがフグ科で高級といえるのはトラフグだけで、丸のままだと比較的安い。もちろん誰でも下ろせないということもあるが、安いけど安くないのは以下を読んでもらうしかない。未成熟な個体がお買い得で、成熟が進むと割高になる。ちなみに典型的なフグといえば、フグ科トラフグ属(の仲間)のフグである。トラフグは皮が無毒だが、ほとんどのトラフグ属のフグの皮は有毒だというのもおぼえておくといい。取り分け、トラフグ属のヒガンフグは毒が強く、可食部分は筋肉だけだ。また、関東でヒガンフグを「赤目フグ(あかめふぐ)」と呼び、同じトラフグ属のアカメフグと混同しやすいのも要注意だ。定期的にヒガンフグを買うのは歩留まりを見るためだ。丸のままのフグの多くの値段は平凡だが、可食部分からすると明らかに高級魚である。今回の個体は雌1.4kgで可食部分は680gなので、歩留まり50パーセント弱だ。 千葉県千葉市のスーパーで、「いわしのごま漬け」ではなく、「さばの胡麻漬」を買った。千葉県山武郡九十九里町、『小川水産』のものだ。九十九里浜の特産品ともいえそうな、「いわし(カタクチイワシ)のごま漬け」は都内でもよく見かけるが、それ以外のものは見かけたことがない。このような主要製品以外のものに出合えるは、千葉県だからだ。20年以上前、九十九里にカタクチイワシの水揚げを見に行ったとき、漁の話だけではなく「ごま漬け」の話もした。そのときもカタクチイワシが不漁であるときは、マアジやサバ類(マサバ・ゴマサバ)の小型を使って作っていたという話を聞いているのだ。ちなみに「いわしのごま漬け」は非常にうまい。昔、魚通を自称していた、高橋治も絶賛していたはず。それほどに間違いなしの名品なのである。
千葉県千葉市のスーパーで、「いわしのごま漬け」ではなく、「さばの胡麻漬」を買った。千葉県山武郡九十九里町、『小川水産』のものだ。九十九里浜の特産品ともいえそうな、「いわし(カタクチイワシ)のごま漬け」は都内でもよく見かけるが、それ以外のものは見かけたことがない。このような主要製品以外のものに出合えるは、千葉県だからだ。20年以上前、九十九里にカタクチイワシの水揚げを見に行ったとき、漁の話だけではなく「ごま漬け」の話もした。そのときもカタクチイワシが不漁であるときは、マアジやサバ類(マサバ・ゴマサバ)の小型を使って作っていたという話を聞いているのだ。ちなみに「いわしのごま漬け」は非常にうまい。昔、魚通を自称していた、高橋治も絶賛していたはず。それほどに間違いなしの名品なのである。 穀醤である醤(ひしお)、醤油の実(しょうゆの実)、もろみ、のない地域は少ないと思っている。穀醤とは別系統の、醤油のことをもっと深く知りたいと思っているので、我が家にある穀醤のデータを整理中だ。まだ我がデータベース内の「製造されている分布域」すらはっきりしないが、醤油の伝来以前からあるものなので、たぶん名前は違えども全国にあると思われる。ちなみに穀醤は大豆・麦・塩・水と麹で発酵させたもの。調味料ではなく、食べるためのものである。今回の福島県・新潟県の旅では、福島県内では見つけられなかった。探し回った挙げ句、新潟県内では大手の十日町市、『高長醸造場』のものを買い求めてきた。十日町市のある魚沼地域では盛んに「しょうゆの実」が作られており、小さな醸造所も多いことからして残念ではある。新潟県の「しょうゆの実」は比較的辛口で甘味がほとんど感じられない。水分が多いのも特徴だと思われる。ちなみに醤油伝来以前には調味料という概念がなかった可能性が高い。料理は、調味することは特殊で、調味しないで火を通しただけの料理だった。食べるときにつけて食べた、そのつけだれの役割を果たしていたのが、もちろん現在のものとはまったくの別物だとは思うが、穀醤である。ちなみにこの塩分濃度の高い、「『しょうゆの実』だけでご飯を食べるのが好きで他にはなにもいらない」という話を超高齢のご婦人に小千谷市の地スーパー、『たかのスーパー』で聞いたことがある。昔はそれが当たり前だったのかも知れない。新潟県でもそうだが、意外に穀醤を調味料として使う地域は少ない。
穀醤である醤(ひしお)、醤油の実(しょうゆの実)、もろみ、のない地域は少ないと思っている。穀醤とは別系統の、醤油のことをもっと深く知りたいと思っているので、我が家にある穀醤のデータを整理中だ。まだ我がデータベース内の「製造されている分布域」すらはっきりしないが、醤油の伝来以前からあるものなので、たぶん名前は違えども全国にあると思われる。ちなみに穀醤は大豆・麦・塩・水と麹で発酵させたもの。調味料ではなく、食べるためのものである。今回の福島県・新潟県の旅では、福島県内では見つけられなかった。探し回った挙げ句、新潟県内では大手の十日町市、『高長醸造場』のものを買い求めてきた。十日町市のある魚沼地域では盛んに「しょうゆの実」が作られており、小さな醸造所も多いことからして残念ではある。新潟県の「しょうゆの実」は比較的辛口で甘味がほとんど感じられない。水分が多いのも特徴だと思われる。ちなみに醤油伝来以前には調味料という概念がなかった可能性が高い。料理は、調味することは特殊で、調味しないで火を通しただけの料理だった。食べるときにつけて食べた、そのつけだれの役割を果たしていたのが、もちろん現在のものとはまったくの別物だとは思うが、穀醤である。ちなみにこの塩分濃度の高い、「『しょうゆの実』だけでご飯を食べるのが好きで他にはなにもいらない」という話を超高齢のご婦人に小千谷市の地スーパー、『たかのスーパー』で聞いたことがある。昔はそれが当たり前だったのかも知れない。新潟県でもそうだが、意外に穀醤を調味料として使う地域は少ない。 ときどきボクの車の屋根に乗って遊ぶ(じっとゲームしているだけだけど)近所のそろそろ小学3年生に、今日のお昼はなに食べた?(大人でも子供でも、必ず食事のことを聞くのはボクの職業的な病)と聞いたら、ポテサラサンドだという。「ポテトサラダをサンドイッチにするんだ?」というと「普通だよ」という。「チーズとハムたっぷりね」とはゴージャスな昼飯ではないか。小学2年生の日曜日の昼ご飯としては上等だな、と思った。なんとなくポテサラを作ってみたくなった。自宅では肉を食べないので、魚のポテサラである。さっそく和歌山県から来たミニマムサイズの美トンボ(ビンナガマグロ)のあら、上身4分の1、刺身切り落としなどを集めた。これをハーブブイヨン、塩、少量の白ワイン、水、ローリエ、セロリと一緒にことこと煮込む。単純に塩ゆでしてもいい。
ときどきボクの車の屋根に乗って遊ぶ(じっとゲームしているだけだけど)近所のそろそろ小学3年生に、今日のお昼はなに食べた?(大人でも子供でも、必ず食事のことを聞くのはボクの職業的な病)と聞いたら、ポテサラサンドだという。「ポテトサラダをサンドイッチにするんだ?」というと「普通だよ」という。「チーズとハムたっぷりね」とはゴージャスな昼飯ではないか。小学2年生の日曜日の昼ご飯としては上等だな、と思った。なんとなくポテサラを作ってみたくなった。自宅では肉を食べないので、魚のポテサラである。さっそく和歌山県から来たミニマムサイズの美トンボ(ビンナガマグロ)のあら、上身4分の1、刺身切り落としなどを集めた。これをハーブブイヨン、塩、少量の白ワイン、水、ローリエ、セロリと一緒にことこと煮込む。単純に塩ゆでしてもいい。 4月1日に八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で久しぶりに「関あじ」を買った。1996年に水産物で初めての商品登録したエポックメーキングなものである。当時から、「関さば」ほどではないが非常に高価だった。豊後水郷と伊予灘の境のいちばん狭い海域、大分県高島と愛媛県佐多岬の間、高島寄りでとれるマアジだ。すべて釣り物で、生きたまま帰港し、一定期間生かして、活け締めにして出荷したものである。古くからマダイなどでは当たり前だった活け越し(一定期間生かして活け締めにする)を、背の青い魚であるマアジやマサバにほどこすというところが画期的であった。ちなみに高橋治だったか、この海域の魚は他の地域と比べて格段にうまい、と言った人間が少なからずいた。このあたりの通ぶった人間の無知ぶりには呆れる。これだけはありえない。もちろん根つきの魚の味のよさはあるだろうが、同じような魚は日本全国にいる。例えば、新潟市沖、相模湾・東京湾や明石海峡、鳴門海峡などのマアジが味でひけをとることは決してない。要は出荷体制が完璧だったために生まれたブランドである。今でも流通上はダントツの値の高さではあるが、玄人受けはしていないと思っている。なぜか?大きすぎるのだ。今回の個体は、体長33cm・482gもある。もっと大きいのもあるようで、その大型の方がもっと高いようだそんな「関あじ」を注文してまで買う料理人がいるのはなぜか? を考えてみたい。
4月1日に八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で久しぶりに「関あじ」を買った。1996年に水産物で初めての商品登録したエポックメーキングなものである。当時から、「関さば」ほどではないが非常に高価だった。豊後水郷と伊予灘の境のいちばん狭い海域、大分県高島と愛媛県佐多岬の間、高島寄りでとれるマアジだ。すべて釣り物で、生きたまま帰港し、一定期間生かして、活け締めにして出荷したものである。古くからマダイなどでは当たり前だった活け越し(一定期間生かして活け締めにする)を、背の青い魚であるマアジやマサバにほどこすというところが画期的であった。ちなみに高橋治だったか、この海域の魚は他の地域と比べて格段にうまい、と言った人間が少なからずいた。このあたりの通ぶった人間の無知ぶりには呆れる。これだけはありえない。もちろん根つきの魚の味のよさはあるだろうが、同じような魚は日本全国にいる。例えば、新潟市沖、相模湾・東京湾や明石海峡、鳴門海峡などのマアジが味でひけをとることは決してない。要は出荷体制が完璧だったために生まれたブランドである。今でも流通上はダントツの値の高さではあるが、玄人受けはしていないと思っている。なぜか?大きすぎるのだ。今回の個体は、体長33cm・482gもある。もっと大きいのもあるようで、その大型の方がもっと高いようだそんな「関あじ」を注文してまで買う料理人がいるのはなぜか? を考えてみたい。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道別海町『丸イ 佐藤水産』からババノテが来ていた。漢字は「婆の手」で、年寄りの女性の手のように節くれ立っているという意味だ。「母の手(ハハノテ)」ともいう。昔、札幌中央市場で会った人は、「『身を粉にして働き、年を取り、手が節くれ立ち、(手の甲が)すすけたような色になった婆の手のようだ』という意味だけど、汚いという意味ではなく、尊敬の念を込めている」と市場人にしては詩的な表現をしていた。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産に北海道別海町『丸イ 佐藤水産』からババノテが来ていた。漢字は「婆の手」で、年寄りの女性の手のように節くれ立っているという意味だ。「母の手(ハハノテ)」ともいう。昔、札幌中央市場で会った人は、「『身を粉にして働き、年を取り、手が節くれ立ち、(手の甲が)すすけたような色になった婆の手のようだ』という意味だけど、汚いという意味ではなく、尊敬の念を込めている」と市場人にしては詩的な表現をしていた。 八王子綜合卸売センター、舵丸水産、クマゴロウが銭州で大釣りしてきた中に、ヒレナガカンパチが入っていた。今年の銭州はシマアジだらけで、釣り師のプライドからして「こっちを見ろよ」、と言われている気がするが、ボクはへそ曲がりなのでこっちに目が行く。市場で同じブリ属(ブリの仲間)のカンパチと並んでいたら、料理人はまずヒレナガカンパチは選ばなくなった。やっと市場での価値が安定してきたものと見える。両種は見た目がそっくりである。特に市場や魚屋では鰭が寝ているので、見わけがつかないという人の方が多いだろう。カンパチよりも少しずんぐりしていて、背鰭を立てると「鰭長間八」の名の通りにやけに長い。温かい海域にいるカンパチよりも、より温かい海域を好み。世界中の熱帯から温帯域に生息している。ちなみに、カンパチのおいしさを頭に描いて買うと、少しがっかりするはずだ。ただ、ヒレナガカンパチという別の魚を買ったと思えば、近年の価格帯からすると納得がいくと思う。最近、魚全般の値段が急激に上がっている。コロナのときから右肩上がりが続いている。それからすると歩留まりのいいヒレナガカンパチは安くておいしい、という評価が定着しそうだ。ほんの十年くらい前まで、ヒレナガカンパチは相模湾では珍しい魚だった。今でも湾北部には少なく、伊豆半島でも伊東あたりにいくと、カンパチよりも多いときがある。明らかに温暖化の申し子である。最近、豊洲だけではなく、関東周辺の市場では標準和名で流通している。このサイズでカンパチなら、「シオッコ」などと呼ぶことが多いが、大小にかかわらずヒレナガカンパチとしか呼ばれない。本来とれなかった、扱わなかった地域では、流通上標準和名が使われる。その典型的な例である。
八王子綜合卸売センター、舵丸水産、クマゴロウが銭州で大釣りしてきた中に、ヒレナガカンパチが入っていた。今年の銭州はシマアジだらけで、釣り師のプライドからして「こっちを見ろよ」、と言われている気がするが、ボクはへそ曲がりなのでこっちに目が行く。市場で同じブリ属(ブリの仲間)のカンパチと並んでいたら、料理人はまずヒレナガカンパチは選ばなくなった。やっと市場での価値が安定してきたものと見える。両種は見た目がそっくりである。特に市場や魚屋では鰭が寝ているので、見わけがつかないという人の方が多いだろう。カンパチよりも少しずんぐりしていて、背鰭を立てると「鰭長間八」の名の通りにやけに長い。温かい海域にいるカンパチよりも、より温かい海域を好み。世界中の熱帯から温帯域に生息している。ちなみに、カンパチのおいしさを頭に描いて買うと、少しがっかりするはずだ。ただ、ヒレナガカンパチという別の魚を買ったと思えば、近年の価格帯からすると納得がいくと思う。最近、魚全般の値段が急激に上がっている。コロナのときから右肩上がりが続いている。それからすると歩留まりのいいヒレナガカンパチは安くておいしい、という評価が定着しそうだ。ほんの十年くらい前まで、ヒレナガカンパチは相模湾では珍しい魚だった。今でも湾北部には少なく、伊豆半島でも伊東あたりにいくと、カンパチよりも多いときがある。明らかに温暖化の申し子である。最近、豊洲だけではなく、関東周辺の市場では標準和名で流通している。このサイズでカンパチなら、「シオッコ」などと呼ぶことが多いが、大小にかかわらずヒレナガカンパチとしか呼ばれない。本来とれなかった、扱わなかった地域では、流通上標準和名が使われる。その典型的な例である。 スーパーに行くのも、ボクにとっては旅である。いろんな刺激があっちこっちから飛んで来る。普段は行かない、駅前のスーパーに飲み物を買いに入ったら、懐かしすぎる「マースカレー」があった!1945年の敗戦後、新しい家庭料理をこの国とGHQは国策として広めていた。中にカレーがある。このあたりに関しては小菅桂子の『カレーの誕生』に詳しい。国民の体形の向上と主婦の家事負担の軽減である。当時、料理は主婦が作るもので、農家などで主婦はもっとも早く起きて朝食を作り、もっとも遅くまで家事をこなすのが普通だった。今でも昔の主婦はよく働いたものだ、なんて懐かしそうに言う愚か者がいるが、これは明らかな虐待である。料理は「ご飯に一汁一菜」にしても、当座食べるものを作っていても手間がかかる。ライスカレーはそれだけで、ご飯であり、おかずであり、汁でもあり、と完結しているのである。コロッケなどの戦前からのものではなく、戦後の新しい家庭料理の普及はちゃんとした目的があってのことなのだ。
スーパーに行くのも、ボクにとっては旅である。いろんな刺激があっちこっちから飛んで来る。普段は行かない、駅前のスーパーに飲み物を買いに入ったら、懐かしすぎる「マースカレー」があった!1945年の敗戦後、新しい家庭料理をこの国とGHQは国策として広めていた。中にカレーがある。このあたりに関しては小菅桂子の『カレーの誕生』に詳しい。国民の体形の向上と主婦の家事負担の軽減である。当時、料理は主婦が作るもので、農家などで主婦はもっとも早く起きて朝食を作り、もっとも遅くまで家事をこなすのが普通だった。今でも昔の主婦はよく働いたものだ、なんて懐かしそうに言う愚か者がいるが、これは明らかな虐待である。料理は「ご飯に一汁一菜」にしても、当座食べるものを作っていても手間がかかる。ライスカレーはそれだけで、ご飯であり、おかずであり、汁でもあり、と完結しているのである。コロッケなどの戦前からのものではなく、戦後の新しい家庭料理の普及はちゃんとした目的があってのことなのだ。 東京都東久留米市、東京北魚で新潟県産Buccinum を発見した。和名はエゾバイ属である。この属内に亜属(属の下の階級)が設けられていないのが不思議なほど種が多い。現在の奥谷図鑑(『日本近海産貝類図鑑 第二版』)は明らかに種の整理をしていっているようだが、産地からして妥当なんだろうか? という疑問が残る。魚類(脊椎動物は)は形態学的なものが比較的単純であるが、軟体類の形態学的な考察は大きさ、産地、水深、貝殻の感触など非常に複雑である。この『日本近海産貝類図鑑 第二版』の問題点の中に、市場などで白バイとして流通するグループがいる。このグループをアニワバイグループとしている研究者が多いので、これに従っている。ただ、アニワバイの形態と変異の多さと、本当に国内海域にいるのかという疑問があり、むしろ比較的安定的な形態を持つ、エッチュウバイを基本とした方がいいのではないかとも考えている。ただし、当方にはアニワバイのデータが少ないために、今後の課題として置くしかない。各ページの分類グループはアニワバイを使い、新たに一般分類に白バイを加えることにした。これと同時に、日本海でのアニワバイグループの空白部分を鑑みて、ノッポバイを復活させた。個人的にはアキタバイはノッポバイの一形態だと思っているが、貝類学者の黒住耐二さんとの意見が一致しない。https://www.zukan-bouz.com/com/白バイ
東京都東久留米市、東京北魚で新潟県産Buccinum を発見した。和名はエゾバイ属である。この属内に亜属(属の下の階級)が設けられていないのが不思議なほど種が多い。現在の奥谷図鑑(『日本近海産貝類図鑑 第二版』)は明らかに種の整理をしていっているようだが、産地からして妥当なんだろうか? という疑問が残る。魚類(脊椎動物は)は形態学的なものが比較的単純であるが、軟体類の形態学的な考察は大きさ、産地、水深、貝殻の感触など非常に複雑である。この『日本近海産貝類図鑑 第二版』の問題点の中に、市場などで白バイとして流通するグループがいる。このグループをアニワバイグループとしている研究者が多いので、これに従っている。ただ、アニワバイの形態と変異の多さと、本当に国内海域にいるのかという疑問があり、むしろ比較的安定的な形態を持つ、エッチュウバイを基本とした方がいいのではないかとも考えている。ただし、当方にはアニワバイのデータが少ないために、今後の課題として置くしかない。各ページの分類グループはアニワバイを使い、新たに一般分類に白バイを加えることにした。これと同時に、日本海でのアニワバイグループの空白部分を鑑みて、ノッポバイを復活させた。個人的にはアキタバイはノッポバイの一形態だと思っているが、貝類学者の黒住耐二さんとの意見が一致しない。https://www.zukan-bouz.com/com/白バイ さて、ボクのような不器用な人間にでも「おにぎり型」があれば、お握りが作れることを発見して以来、徹底的に握り飯三昧の日々にある。最近、米離れが進んでいるとされているが、農水省あたりも「お握り作ろうよ、超簡単だからキャンペーン」でもやったらいかがだろう。ボクなど「私にも作れます」なんて楽しい日々を過ごしている。(だれも台詞の元ネタわかんないだろうけど)いろんな具材を試している日々でもある。東京都大塚にある『ぼんご』のように「筋子にホッキサラダ」とかの合わせ技は先延ばしにして、まずは1種だけの単純なものから。さて、小売店でヤリイカを買って値段のチェックをしている。スーパーで売っているのは主に小振りの個体である。これはヤリイカは大きいほど高くなるので、スーパーだとどうしても小さい個体が並ぶのだと思われる。雄が大きく、雌は外套長で3分の2くらいにしかならないので、この産卵期の、小さいものは総て雌で子持ちだ。ヤリイカの真子は軽く煮ただけで食べてもうまいし、外套膜(胴)に真子を戻して、外套膜ごと焼き上げてもいい。
さて、ボクのような不器用な人間にでも「おにぎり型」があれば、お握りが作れることを発見して以来、徹底的に握り飯三昧の日々にある。最近、米離れが進んでいるとされているが、農水省あたりも「お握り作ろうよ、超簡単だからキャンペーン」でもやったらいかがだろう。ボクなど「私にも作れます」なんて楽しい日々を過ごしている。(だれも台詞の元ネタわかんないだろうけど)いろんな具材を試している日々でもある。東京都大塚にある『ぼんご』のように「筋子にホッキサラダ」とかの合わせ技は先延ばしにして、まずは1種だけの単純なものから。さて、小売店でヤリイカを買って値段のチェックをしている。スーパーで売っているのは主に小振りの個体である。これはヤリイカは大きいほど高くなるので、スーパーだとどうしても小さい個体が並ぶのだと思われる。雄が大きく、雌は外套長で3分の2くらいにしかならないので、この産卵期の、小さいものは総て雌で子持ちだ。ヤリイカの真子は軽く煮ただけで食べてもうまいし、外套膜(胴)に真子を戻して、外套膜ごと焼き上げてもいい。 八王子綜合卸売センター、八百角に甘草が来ていた。産地はわからないが手を伸ばしかけて、暫し躊躇する。市場から土手を越えて浅川に行けば、ノカンゾウ(野甘草 ワスレグサ科)だらけなのだ。ただ土手を越えていくのはいいとしても、浅川は犬だらけなのだ。特に朝夕など、ボクにとっては恐怖の世界といっても過言ではない。ううう、ワンワンなのだ。しかも、やわなボクは犬の●●●っこを思い浮かべて、土手の甘草は食べる気になれない。天ぷらにして和え物にしてと色々考えて、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にもどって天種を探す。小柱もなく、シバエビもない。あるのは「こはだ(コノシロの若い個体)」だけだ。必要最小限の2尾買って驚いた。ビックリするくらい高かったのだ。「なくてはならない魚」の水揚げが少ないとグイーーンと値を上げるのが、市場原理というものなのだ。水洗いしてもらって持ち帰る。「こはだの天ぷら」は江戸時代中期、江戸の町にはあったとされる天ぷら屋台にもあったのだと思う。細田安兵衛(現榮太樓總本鋪)の著書には三越呉服店の夕方の献立だったとある。(たぶん)締まり屋である三越呉服店のことだから「こはだ」はしごく安くて、しかも滋味豊かで、日常的にも手に入れやすかったのだと思う。江戸時代から明治にかけて、日本橋の上流にある一石橋あたりでもシラウオがとれていたくらいだから、三越呉服店の眼の前を流れる日本橋川にもたくさんいたはずなのだ。
八王子綜合卸売センター、八百角に甘草が来ていた。産地はわからないが手を伸ばしかけて、暫し躊躇する。市場から土手を越えて浅川に行けば、ノカンゾウ(野甘草 ワスレグサ科)だらけなのだ。ただ土手を越えていくのはいいとしても、浅川は犬だらけなのだ。特に朝夕など、ボクにとっては恐怖の世界といっても過言ではない。ううう、ワンワンなのだ。しかも、やわなボクは犬の●●●っこを思い浮かべて、土手の甘草は食べる気になれない。天ぷらにして和え物にしてと色々考えて、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にもどって天種を探す。小柱もなく、シバエビもない。あるのは「こはだ(コノシロの若い個体)」だけだ。必要最小限の2尾買って驚いた。ビックリするくらい高かったのだ。「なくてはならない魚」の水揚げが少ないとグイーーンと値を上げるのが、市場原理というものなのだ。水洗いしてもらって持ち帰る。「こはだの天ぷら」は江戸時代中期、江戸の町にはあったとされる天ぷら屋台にもあったのだと思う。細田安兵衛(現榮太樓總本鋪)の著書には三越呉服店の夕方の献立だったとある。(たぶん)締まり屋である三越呉服店のことだから「こはだ」はしごく安くて、しかも滋味豊かで、日常的にも手に入れやすかったのだと思う。江戸時代から明治にかけて、日本橋の上流にある一石橋あたりでもシラウオがとれていたくらいだから、三越呉服店の眼の前を流れる日本橋川にもたくさんいたはずなのだ。 水産生物とヒトとの関わりを知りたかったら、市場や漁港以上に小売店を見て歩かないとダメだ。そしてときどき買ってみる。ヤリイカは昔、昔から関東では高級イカであって、めったに安売りのスーパーなどには並ばないはずだった。ところが最近、駅前などの大型スーパーで特売品として売られているではないか。見た限りでは総て北海道産。外套長18cm以下の個体は元々安いものだが、今回の個体は23cm前後もある。これで税込み400円でおつりが来る。このサイズは明らかに雌だけど、それでも安い。鮮度はぎりぎり刺身になるといったものだが、胴は刺身に、げそや卵巣は煮つけや塩ゆでにすれば御馳走である。ヤリイカは眼が皮膜で覆われていることから閉眼類と呼ばれている。仲間にはケンサキイカやアオリイカがいるが、古来より閉眼類の多くが堂々の高級イカである。ケンサキイカが西日本に多いのに対して東日本と北海道に多い。北海道では温かい時季にスルメイカが、寒くなるとヤリイカが揚がるので、冬イカとも呼ばれている。温暖化でめっきり少なくなったと思ったら、市場にわんさか並んでいるなんて、イカの好不漁、種ごとの水揚げの比率は不安定だ。外套長22cm・140gを近所のスーパーで買ってきて、深夜の酒の肴にする。慌ただしいときなので、仕事終わりは深夜になりがちになると、消化にもよさげなイカは格好のものだと思っている。
水産生物とヒトとの関わりを知りたかったら、市場や漁港以上に小売店を見て歩かないとダメだ。そしてときどき買ってみる。ヤリイカは昔、昔から関東では高級イカであって、めったに安売りのスーパーなどには並ばないはずだった。ところが最近、駅前などの大型スーパーで特売品として売られているではないか。見た限りでは総て北海道産。外套長18cm以下の個体は元々安いものだが、今回の個体は23cm前後もある。これで税込み400円でおつりが来る。このサイズは明らかに雌だけど、それでも安い。鮮度はぎりぎり刺身になるといったものだが、胴は刺身に、げそや卵巣は煮つけや塩ゆでにすれば御馳走である。ヤリイカは眼が皮膜で覆われていることから閉眼類と呼ばれている。仲間にはケンサキイカやアオリイカがいるが、古来より閉眼類の多くが堂々の高級イカである。ケンサキイカが西日本に多いのに対して東日本と北海道に多い。北海道では温かい時季にスルメイカが、寒くなるとヤリイカが揚がるので、冬イカとも呼ばれている。温暖化でめっきり少なくなったと思ったら、市場にわんさか並んでいるなんて、イカの好不漁、種ごとの水揚げの比率は不安定だ。外套長22cm・140gを近所のスーパーで買ってきて、深夜の酒の肴にする。慌ただしいときなので、仕事終わりは深夜になりがちになると、消化にもよさげなイカは格好のものだと思っている。 ドイツ文学者の西義之は1922年台湾生まれ。内地(1945年以前の言語)に来たのは、「四校」と呼ばれた、旧制第四高等学校に入るためだろう。ということは彼の国内での故郷は金沢ということになる。「四校」というと井上靖の「夏草冬濤」の世界である。『定年教授の食卓』(春秋社)に、雑誌やラジオで何度も話題になったことのある「ドリコノ」とともに「炒り粉」の話が出てくる。〈田舎(たぶん石川県金沢市)で「炒り粉」を冷たい水で溶かして、塩と砂糖で味つけをして飲んでいた〉「炒り粉」は、ボクが小さい時は「はったい粉」。他には「麦こがし」、「香煎」、「おちらし」ともいう。麦を香ばしく炒って粉状にした食品で、中世以前からの食品である可能性が高い。徳島県美馬郡貞光町(つるぎ町貞光)の家では、お湯で錬って食べていた。どろっとしつつも飲めるくらい薄く溶いて、甘い味つけをして飲むというのはまったく未知の世界である
ドイツ文学者の西義之は1922年台湾生まれ。内地(1945年以前の言語)に来たのは、「四校」と呼ばれた、旧制第四高等学校に入るためだろう。ということは彼の国内での故郷は金沢ということになる。「四校」というと井上靖の「夏草冬濤」の世界である。『定年教授の食卓』(春秋社)に、雑誌やラジオで何度も話題になったことのある「ドリコノ」とともに「炒り粉」の話が出てくる。〈田舎(たぶん石川県金沢市)で「炒り粉」を冷たい水で溶かして、塩と砂糖で味つけをして飲んでいた〉「炒り粉」は、ボクが小さい時は「はったい粉」。他には「麦こがし」、「香煎」、「おちらし」ともいう。麦を香ばしく炒って粉状にした食品で、中世以前からの食品である可能性が高い。徳島県美馬郡貞光町(つるぎ町貞光)の家では、お湯で錬って食べていた。どろっとしつつも飲めるくらい薄く溶いて、甘い味つけをして飲むというのはまったく未知の世界である 福島県会津地方、南会津町、猪苗代町などのスーパーで「にしん山椒漬」をたっぷり買って来た。会津土産として比較的当たり外れがなく。ボク好みなのでついつい手が出てしまう。江戸時代、身欠きニシンは、北前船が越後(新潟県)の港にもたらし、そのまま越後街道を会津に送られてきていたはずだ。会津にとって身欠きニシンはきっと贅沢な食材だったに違いない。「にしん山椒漬」の本来の作り方は身欠きニシンをざっと水で洗い、腹骨や胸鰭などを取り去り、醤油・酒・みりん、大量の山椒の葉と一緒につけ込んだものだ。当然、漬け込み時期は春ということになる。最近のものは身欠きニシンを、米のとぎ汁(重曹を溶かし込んだ水かな)などでもどしてから漬けるのだと思われる。なぜならば身欠きニシンは、そのままでは渋味と苦味があるからだ。ちなみに個人が作ったという昔ながらの「にしん山椒漬」をいただいたことがあるが、苦味が残り、山椒の辛味があり、醤油辛くて好き嫌いがでる類いのものである。ボクはヨソモノなので、最近の苦味渋味を抜いて漬けた製品の方がすきだ。写真は『会津丸善水産(会津若松市)』のもの。ここに不思議なことが書いてあった。「焼いていただきますと、一層香ばしくお召し上がり頂けます」数年に一度程度食べるものなので毎回、そのまま食べて満足していた。この食べ方は、会津人が日常的に食べている内に、自然と編み出した食べ方に違いない。さて、そのままと、焼いてものを比べてみる。並べて食べて、もう二度と、焼かない「にしん山椒漬」は、食べないと思うほど、焼いた方がうまい。そのまま食べると、噛みしめるほどにニシンのうま味と独特の明らかに酸化した脂がじわじわときて、山椒の風味が適度にその野性味で、渋味を緩和してくれ、ふたたびニシンの味が来て、調味料の味が来てと、口中で「にしん山椒漬」の味が長々と感じられる。そこには、ニシンに塩を添加しないで硬く干して、山国に送られ、山国に人が汗水たらして稼いだ金で購い、山国ならではの若々しい山椒の葉と、発酵食品である酒・みりん・醤油と結婚させた、という大河ドラマ的な展開がある。ただ、食い物にそんなダイナミックなものを感じたいかというと、然にあらず。そんな面倒くさいことは不要である。
福島県会津地方、南会津町、猪苗代町などのスーパーで「にしん山椒漬」をたっぷり買って来た。会津土産として比較的当たり外れがなく。ボク好みなのでついつい手が出てしまう。江戸時代、身欠きニシンは、北前船が越後(新潟県)の港にもたらし、そのまま越後街道を会津に送られてきていたはずだ。会津にとって身欠きニシンはきっと贅沢な食材だったに違いない。「にしん山椒漬」の本来の作り方は身欠きニシンをざっと水で洗い、腹骨や胸鰭などを取り去り、醤油・酒・みりん、大量の山椒の葉と一緒につけ込んだものだ。当然、漬け込み時期は春ということになる。最近のものは身欠きニシンを、米のとぎ汁(重曹を溶かし込んだ水かな)などでもどしてから漬けるのだと思われる。なぜならば身欠きニシンは、そのままでは渋味と苦味があるからだ。ちなみに個人が作ったという昔ながらの「にしん山椒漬」をいただいたことがあるが、苦味が残り、山椒の辛味があり、醤油辛くて好き嫌いがでる類いのものである。ボクはヨソモノなので、最近の苦味渋味を抜いて漬けた製品の方がすきだ。写真は『会津丸善水産(会津若松市)』のもの。ここに不思議なことが書いてあった。「焼いていただきますと、一層香ばしくお召し上がり頂けます」数年に一度程度食べるものなので毎回、そのまま食べて満足していた。この食べ方は、会津人が日常的に食べている内に、自然と編み出した食べ方に違いない。さて、そのままと、焼いてものを比べてみる。並べて食べて、もう二度と、焼かない「にしん山椒漬」は、食べないと思うほど、焼いた方がうまい。そのまま食べると、噛みしめるほどにニシンのうま味と独特の明らかに酸化した脂がじわじわときて、山椒の風味が適度にその野性味で、渋味を緩和してくれ、ふたたびニシンの味が来て、調味料の味が来てと、口中で「にしん山椒漬」の味が長々と感じられる。そこには、ニシンに塩を添加しないで硬く干して、山国に送られ、山国に人が汗水たらして稼いだ金で購い、山国ならではの若々しい山椒の葉と、発酵食品である酒・みりん・醤油と結婚させた、という大河ドラマ的な展開がある。ただ、食い物にそんなダイナミックなものを感じたいかというと、然にあらず。そんな面倒くさいことは不要である。 知り合いの魚屋が「筍が出始めると、売りやすいよね」といった。それに、別の魚屋が「竹の子目張(筍めばる)っていうよね」なんて立ち話をした後に、筍(竹の子)と青森県産のウスメバルを買う。この場合の「めばる」とはウスメバルのことだからだ。関東では竹の子とメバルを煮合わせることが多い。この場合のメバルは、浅場にいるメバル(クロメバル・アカメバル・シロメバルのことで昔は1種とされていた)とウスメバルのことだ。今、春に多いのはウスメバルなので、たぶん魚屋の店先では、ウスメバルを指さして、お客に竹の子話をしているに違いない。この場合の「たけのこめばる」が呼び名であるのか、「竹の子がとれる時季と入荷の最盛期が同じで、たき合わせるとおいしい」という意味なのかは、判断にくるしむ。ただ、明らかに魚市場で「たけのこ」というと本種の荷(発泡の箱のことで魚が入っている状態のもの)が連想される。実際、それで通じたりする。ウスメバルは太平洋側でも揚がるが日本海側に多く、希に太平洋側のものがあると珍しいなと思えるほどだ。新潟県で「せいかい」、新潟県や福井県で「はつめ」、東京など関東では、比較的沖合いの水深100m以上に生息しているため「沖めばる」という。築地での聞取では昔は大量に入荷してきていたので、安い魚であったようで、東京都内の食堂メニュー「めばるの煮つけ」のメバルの正体は基本的に本種だったという。さて、いつの間にやら、八王子綜合卸売センター『八百角』で竹の子が特売しているではないか? 4月になれば竹の子は、こんなに安くなっていたんだね。ここ数年、やたらと慌ただしいので、竹の子出たのもご存じない。竹の子を1本かかえて、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にまわり青森県産ウスメバルを買った。
知り合いの魚屋が「筍が出始めると、売りやすいよね」といった。それに、別の魚屋が「竹の子目張(筍めばる)っていうよね」なんて立ち話をした後に、筍(竹の子)と青森県産のウスメバルを買う。この場合の「めばる」とはウスメバルのことだからだ。関東では竹の子とメバルを煮合わせることが多い。この場合のメバルは、浅場にいるメバル(クロメバル・アカメバル・シロメバルのことで昔は1種とされていた)とウスメバルのことだ。今、春に多いのはウスメバルなので、たぶん魚屋の店先では、ウスメバルを指さして、お客に竹の子話をしているに違いない。この場合の「たけのこめばる」が呼び名であるのか、「竹の子がとれる時季と入荷の最盛期が同じで、たき合わせるとおいしい」という意味なのかは、判断にくるしむ。ただ、明らかに魚市場で「たけのこ」というと本種の荷(発泡の箱のことで魚が入っている状態のもの)が連想される。実際、それで通じたりする。ウスメバルは太平洋側でも揚がるが日本海側に多く、希に太平洋側のものがあると珍しいなと思えるほどだ。新潟県で「せいかい」、新潟県や福井県で「はつめ」、東京など関東では、比較的沖合いの水深100m以上に生息しているため「沖めばる」という。築地での聞取では昔は大量に入荷してきていたので、安い魚であったようで、東京都内の食堂メニュー「めばるの煮つけ」のメバルの正体は基本的に本種だったという。さて、いつの間にやら、八王子綜合卸売センター『八百角』で竹の子が特売しているではないか? 4月になれば竹の子は、こんなに安くなっていたんだね。ここ数年、やたらと慌ただしいので、竹の子出たのもご存じない。竹の子を1本かかえて、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産にまわり青森県産ウスメバルを買った。 3月、八王子綜合卸売センター、福泉でクロマグロの若い個体である、「めじ」55cm・2.5145kgを買った。大阪など西日本では「よこわ」だ。たくさん料理を作りすぎたので全部とりあげることはできないが、一部だけ公開していきたい。じょじょに脂が抜けていきつつあるが、刺身で食べてもやたらにウマシだった。今回は、「塩マグロ」を作り、煮物を作り、ポキ、ぬた、中落ちのかきだしも作ったが、みなそれぞれに美味だった。プラス1品はラーメンである。「めじ」の料理以前の処理をしている間に昼食の用意をする。三枚下ろしにしたときの中落ちから身をかき出した後の骨を、多めの水に放り込んで、火をつける。沸きそうになったら弱火にしてアクを徹底的に引く。八角の小さな欠片、粒コショウを加えて、弱火でじっくりうまみを煮出す。味が出て来たと感じたら鍋止めする。
3月、八王子綜合卸売センター、福泉でクロマグロの若い個体である、「めじ」55cm・2.5145kgを買った。大阪など西日本では「よこわ」だ。たくさん料理を作りすぎたので全部とりあげることはできないが、一部だけ公開していきたい。じょじょに脂が抜けていきつつあるが、刺身で食べてもやたらにウマシだった。今回は、「塩マグロ」を作り、煮物を作り、ポキ、ぬた、中落ちのかきだしも作ったが、みなそれぞれに美味だった。プラス1品はラーメンである。「めじ」の料理以前の処理をしている間に昼食の用意をする。三枚下ろしにしたときの中落ちから身をかき出した後の骨を、多めの水に放り込んで、火をつける。沸きそうになったら弱火にしてアクを徹底的に引く。八角の小さな欠片、粒コショウを加えて、弱火でじっくりうまみを煮出す。味が出て来たと感じたら鍋止めする。 「かつ(フィッシュカツ)」はどのように食べていたのか、そして食べているのか、という話をしたい。徳島県の山崎さんから津久司蒲鉾の「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ」を送って頂いた。まことにありがとうございました。津久司蒲鉾がある小松島市(こまつしまし)は徳島県というもっともミニマムな県の中で、もっとも早くから市になったところである。ボクが子供の頃は殺伐とした噂もあり、また大阪に向かう船の発着所があった。ボクと小松島市の最初の関わりは曖昧だが、大阪万博のときにここから船に乗ったことだったと思う。模型を買うのも、徳島ホールで映画を見るのも徳島市だったし、祖母が丸新デパートやつぼみや(デパート)に行くのも徳島市だった。徳島市はボクにとってしごく馴染み深いところだが、小松島市は船の発着所のむせるような油と海のにおいの記憶しかない。どことなく東映や日活の映画に出てくる港町のようだった。知名度は低いものの徳島県は練り製品の会社が多いところだ。その多くが、大合併以前から市であった、小松島市と徳島市、鳴門市、阿南市にある。多くの練り製品が大阪と共通するものでしかないが、「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ(フィッシュカツ)」だけは徳島にしかない。ちなみに「かつ」の歴史は最低でも60年以上なので、新しい練り製品とは言えなくなっている。さて、「ちっか」は徳島市に行ったときに買うもので、どりらかというとハレの食べ物、「かつ」はいたって日常的なもので、ケの食べ物だった。値段も「かつ」の方が安かったはずだ。今回、「かつ」をたっぷりいただいたので、懐かしい食べ方をしてみた。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町字町貞光町)は1950年代、60年代、県内でもっとも小さな町だったが、県西部では池田町、脇町とともに長い商店街があった。日本中を回っているとわかることだけど、意外に長い商店街のある町は少ない。もちろん市なら当たり前だけど、町(市町村の)で、しかも小さな徳島県の中でも、もっとも小さな町域しかなかった貞光町に商店街があるのは不思議なことなのだ。我が家は商家だったので朝はとても忙しい。1970年くらいまで、午前5時、6時くらいに山から下りてきた人に戸を叩いて起こされ、売る、なんてこともあった。取り分け忙しいときには行商の菓子パンで済ましたり、冬は七輪が食卓脇にあったので餅を食べて学校に向かったものだ。考えてみると寒い時季、餅と惣菜と紅茶もしくはコーヒー、お茶という朝ご飯は商家ならではのものだろう。この惣菜の中にかなりの確立で「かつ」が登場した。
「かつ(フィッシュカツ)」はどのように食べていたのか、そして食べているのか、という話をしたい。徳島県の山崎さんから津久司蒲鉾の「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ」を送って頂いた。まことにありがとうございました。津久司蒲鉾がある小松島市(こまつしまし)は徳島県というもっともミニマムな県の中で、もっとも早くから市になったところである。ボクが子供の頃は殺伐とした噂もあり、また大阪に向かう船の発着所があった。ボクと小松島市の最初の関わりは曖昧だが、大阪万博のときにここから船に乗ったことだったと思う。模型を買うのも、徳島ホールで映画を見るのも徳島市だったし、祖母が丸新デパートやつぼみや(デパート)に行くのも徳島市だった。徳島市はボクにとってしごく馴染み深いところだが、小松島市は船の発着所のむせるような油と海のにおいの記憶しかない。どことなく東映や日活の映画に出てくる港町のようだった。知名度は低いものの徳島県は練り製品の会社が多いところだ。その多くが、大合併以前から市であった、小松島市と徳島市、鳴門市、阿南市にある。多くの練り製品が大阪と共通するものでしかないが、「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ(フィッシュカツ)」だけは徳島にしかない。ちなみに「かつ」の歴史は最低でも60年以上なので、新しい練り製品とは言えなくなっている。さて、「ちっか」は徳島市に行ったときに買うもので、どりらかというとハレの食べ物、「かつ」はいたって日常的なもので、ケの食べ物だった。値段も「かつ」の方が安かったはずだ。今回、「かつ」をたっぷりいただいたので、懐かしい食べ方をしてみた。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町字町貞光町)は1950年代、60年代、県内でもっとも小さな町だったが、県西部では池田町、脇町とともに長い商店街があった。日本中を回っているとわかることだけど、意外に長い商店街のある町は少ない。もちろん市なら当たり前だけど、町(市町村の)で、しかも小さな徳島県の中でも、もっとも小さな町域しかなかった貞光町に商店街があるのは不思議なことなのだ。我が家は商家だったので朝はとても忙しい。1970年くらいまで、午前5時、6時くらいに山から下りてきた人に戸を叩いて起こされ、売る、なんてこともあった。取り分け忙しいときには行商の菓子パンで済ましたり、冬は七輪が食卓脇にあったので餅を食べて学校に向かったものだ。考えてみると寒い時季、餅と惣菜と紅茶もしくはコーヒー、お茶という朝ご飯は商家ならではのものだろう。この惣菜の中にかなりの確立で「かつ」が登場した。 十日町市の「十日」は十のつく日に市が開かれていたためだ。今でも新潟県では巻町や三条など各地で日にちごとの市が開かれている。残念ながら十日町市では市が開かれていない。北魚沼で、2月末なのに雪がないというのも予想外だった。新潟県十日町市の商店街は長い。雪国ならではの雁木はアーケードに変わり、シャッターを下ろした店が目立つ。江戸時代には越後上布、越後縮の産地(江戸時代から昭和になっても織物は一大産業だった)であって、ある意味、北越雪譜に描かれているとおりのところだったのだろう。織物産業があって商業も盛ん。繁栄した町であった名残がそこここに見られる。加うるに、十日町市は信濃川に沿ってある。この町はコイをよく食べる地域だったという。考えて見ると新潟県は阿賀野川があり、信濃川、また旧蒲原郡に多い潟(平地の湿地帯の中の湖、池のこと)があるなど、淡水魚が重要なたんぱく源であったはずだ。十日町市にはウナギとコイの店があるが、この日は定休日だった。まあ今回の十日町は下見と思えば惜しくはない。商店街を十日町らしいものを探して歩くがなにもない。雁木は露地に少しだけ残っているだけだ。だいたい歩いている人が少なすぎる。時刻は1時過ぎ、せめて十日町市で昼飯をと、ふたたび商店街を歩く。新しい店には入りたくない。『小嶋屋』という長岡市にもあるのと同じ屋号のそば店があって、「へぎそば」も同じである。「へぎそば」はフノリをつなぎに使ったもので、ときどき食べたくなるが、この日は長時間労働のあとなのだ。余談になるが市場の旅は、だいたい午前2時くらいに始まり、魚(水産生物)の並ぶ競り場でみて、午前8時くらいに終了する。市場にいること今回は6時間。しかも新潟市はそのとき冷凍庫の中のようだった。とてもそばという気にはなれない。どんなに飢えてもチェーン店では食べないのがモットー、しかもネットは見ないので、ずんずん歩くしかない。向こうに洗いざらした紺色ののれんを見つけたときには涙がちょろりとした。
十日町市の「十日」は十のつく日に市が開かれていたためだ。今でも新潟県では巻町や三条など各地で日にちごとの市が開かれている。残念ながら十日町市では市が開かれていない。北魚沼で、2月末なのに雪がないというのも予想外だった。新潟県十日町市の商店街は長い。雪国ならではの雁木はアーケードに変わり、シャッターを下ろした店が目立つ。江戸時代には越後上布、越後縮の産地(江戸時代から昭和になっても織物は一大産業だった)であって、ある意味、北越雪譜に描かれているとおりのところだったのだろう。織物産業があって商業も盛ん。繁栄した町であった名残がそこここに見られる。加うるに、十日町市は信濃川に沿ってある。この町はコイをよく食べる地域だったという。考えて見ると新潟県は阿賀野川があり、信濃川、また旧蒲原郡に多い潟(平地の湿地帯の中の湖、池のこと)があるなど、淡水魚が重要なたんぱく源であったはずだ。十日町市にはウナギとコイの店があるが、この日は定休日だった。まあ今回の十日町は下見と思えば惜しくはない。商店街を十日町らしいものを探して歩くがなにもない。雁木は露地に少しだけ残っているだけだ。だいたい歩いている人が少なすぎる。時刻は1時過ぎ、せめて十日町市で昼飯をと、ふたたび商店街を歩く。新しい店には入りたくない。『小嶋屋』という長岡市にもあるのと同じ屋号のそば店があって、「へぎそば」も同じである。「へぎそば」はフノリをつなぎに使ったもので、ときどき食べたくなるが、この日は長時間労働のあとなのだ。余談になるが市場の旅は、だいたい午前2時くらいに始まり、魚(水産生物)の並ぶ競り場でみて、午前8時くらいに終了する。市場にいること今回は6時間。しかも新潟市はそのとき冷凍庫の中のようだった。とてもそばという気にはなれない。どんなに飢えてもチェーン店では食べないのがモットー、しかもネットは見ないので、ずんずん歩くしかない。向こうに洗いざらした紺色ののれんを見つけたときには涙がちょろりとした。 「黒ガレイ」は関東で一般的だが、関西ではあまり見かけない。関西のカレイ類の供給地が山陰を始め、日本海と瀬戸内海、紀伊水道だからだと思っている。関東の供給地は北海道と東北、常磐なのである。特に北海道は関東最大の魚の供給地であるということからも、「黒ガレイ」をよく食べるようになったのだと思う。ただ、問題なのは関東に住んでいるほぼすべての人がカレイはカレイでしかなく、種類があることすら認識していないことだ。ましてや「黒ガレイ」が2種のカレイの総称だとわかっている人はいないだろう。土曜日の昼下がり、近所のスーパーで売られていた「黒ガレイ」は標準和名のクロガレイであった。もう1種の「黒ガレイ」であるクロガシラガレイは昨年、今年とボクがが知る限りは見ていない。姿もそっくりなら味も同じ。やや水分が多く、身(筋肉)のうま味の量が少ないものの、料理次第ではとても味わい深い。ちなみにクロガシラガレイは東北太平洋側にもいるが、クロガレイは北海道の特産種である。この安くて料理次第とはいえ、おいしく食べられるカレイは2種あるとかはどうでもいいので、せめて「黒ガレイ」という言語でおぼえて欲しいものである。今回の切り身パックは側線の形からクロガレイとした。このようなパックを作る場合、1尾をばらさないで詰める方がやりやすいので、並べてみて体高からもクロガレイという結論になる。こんなことはやらなくてもいいので、安くておいしい「黒ガレイ」をみんな食べようぜ、といいたい。
「黒ガレイ」は関東で一般的だが、関西ではあまり見かけない。関西のカレイ類の供給地が山陰を始め、日本海と瀬戸内海、紀伊水道だからだと思っている。関東の供給地は北海道と東北、常磐なのである。特に北海道は関東最大の魚の供給地であるということからも、「黒ガレイ」をよく食べるようになったのだと思う。ただ、問題なのは関東に住んでいるほぼすべての人がカレイはカレイでしかなく、種類があることすら認識していないことだ。ましてや「黒ガレイ」が2種のカレイの総称だとわかっている人はいないだろう。土曜日の昼下がり、近所のスーパーで売られていた「黒ガレイ」は標準和名のクロガレイであった。もう1種の「黒ガレイ」であるクロガシラガレイは昨年、今年とボクがが知る限りは見ていない。姿もそっくりなら味も同じ。やや水分が多く、身(筋肉)のうま味の量が少ないものの、料理次第ではとても味わい深い。ちなみにクロガシラガレイは東北太平洋側にもいるが、クロガレイは北海道の特産種である。この安くて料理次第とはいえ、おいしく食べられるカレイは2種あるとかはどうでもいいので、せめて「黒ガレイ」という言語でおぼえて欲しいものである。今回の切り身パックは側線の形からクロガレイとした。このようなパックを作る場合、1尾をばらさないで詰める方がやりやすいので、並べてみて体高からもクロガレイという結論になる。こんなことはやらなくてもいいので、安くておいしい「黒ガレイ」をみんな食べようぜ、といいたい。 さて、トルコの魚のサンドイッチ(Balik Ekmek)」ってどんなもの? から始まって、古い写真のパンの見た目がフランスパン(我ながら古い表現だけど)のようだった、とか、魚はサバ(サバ属)でトルコなので、Atlantic chub mackerel だろうと行き着いた。それで今度はトルコのイワシはなんだろうと調べたら、Sardalya(Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) /ヨーロッパマイワシorニシイワシ) に行き着く。ノルウェー沖からイギリス、ポルトガル、スペイン、地中海、黒海に生息している。きっとトルコでは、タイセイヨウマイワシを使ってサンドイッチを作っているに違いない。
さて、トルコの魚のサンドイッチ(Balik Ekmek)」ってどんなもの? から始まって、古い写真のパンの見た目がフランスパン(我ながら古い表現だけど)のようだった、とか、魚はサバ(サバ属)でトルコなので、Atlantic chub mackerel だろうと行き着いた。それで今度はトルコのイワシはなんだろうと調べたら、Sardalya(Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) /ヨーロッパマイワシorニシイワシ) に行き着く。ノルウェー沖からイギリス、ポルトガル、スペイン、地中海、黒海に生息している。きっとトルコでは、タイセイヨウマイワシを使ってサンドイッチを作っているに違いない。 打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。
打ち豆という大豆の加工食品がある。大豆をもどしてぺたんこにつぶし、また干したたものだ。山形県米沢市・高畠町、新潟県各所、福島県会津地方・南会津地方、富山県氷見、福井県勝山、滋賀県北部余呉長浜で買って撮影している。もっと他の地域でも食べられていると思うが、山陰などでは探したが見つけていない。また太平洋側にはないのかも知れない。例えば青森県、岩手県には、「豆しとぎ(米のもある)」という粉状にしたものは普通に見られるが、打ち豆はないと思う。会津地方で打ち豆を買ったのはこれで二度目だが、前回は会津若松市で、今回は猪苗代でも南会津でも西会津と3カ所で買い求めている。考えて見ると中通り、浜通りでは見ていないと思うが、次回福島に行ったら探さないとダメだ。 昨年の秋、近所のなんでもかんでも売っている巨大なホームセンターで、目的のものが見つけられなくて迷子になって泣きたくなっていたら、眼の前にたくさん並んでいたのが握り飯の型である。握り飯といえば東京都大塚にある『ぼんご』だ。昨年暮れに立ち寄ったら、行列ができていた。この店、回転が早いので、並ぼうか? とは思ったものの、行列の長さが2倍以上になっているではないか? 板橋もそうかな? 諦めて帰ってきた。大塚でときどき仕事をしていたときなので、40年くらい前から知っているが、こんなに長い行列は見た事がない。ボクは不器用なのでお握りを握れない。でもときどき無性に食べたくなる。ただ、コンビニのお握りはあまり魅力がない。スーパーで売っているものなんて最低である。あまりにもたくさん並んでいたので、いちばん簡単な形のものでいちばん安いもの買ったが一度も使っていない。
昨年の秋、近所のなんでもかんでも売っている巨大なホームセンターで、目的のものが見つけられなくて迷子になって泣きたくなっていたら、眼の前にたくさん並んでいたのが握り飯の型である。握り飯といえば東京都大塚にある『ぼんご』だ。昨年暮れに立ち寄ったら、行列ができていた。この店、回転が早いので、並ぼうか? とは思ったものの、行列の長さが2倍以上になっているではないか? 板橋もそうかな? 諦めて帰ってきた。大塚でときどき仕事をしていたときなので、40年くらい前から知っているが、こんなに長い行列は見た事がない。ボクは不器用なのでお握りを握れない。でもときどき無性に食べたくなる。ただ、コンビニのお握りはあまり魅力がない。スーパーで売っているものなんて最低である。あまりにもたくさん並んでいたので、いちばん簡単な形のものでいちばん安いもの買ったが一度も使っていない。 八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産だという、「しゅーりがい」を買う。重さをチェックしたクマゴロウの恋女房は、ためらうことなく伝票に「ムールガイ」と書いた。今や「しゅーりがい」も、「しゅうりがい」も、「いのかい」も、イガイも消滅して、「ムールガイ」になってしまったのだ。本来、Mulgaï (ムール)はヨーロッパイガイと日本列島でも大繁殖しているムラサキイガイの、ヨーロッパ、アメリカ、カナダの呼び名であって、イガイはイガイなんだけど世間は標準和名イガイすらを抹殺しようとしている。驚くべきは産地の伝票すらムールとなっていることが多い。簡単にいうと、本来日本列島にいたイガイは、ヨーロッパから来た新参者のムラサキイガイに流通の場で量的に負けており、最近では呼び名すらカッコイイからかも知れないけど、「ムールガイ」にされているのだ。これじゃ、ヤマト王権に抹殺された縄文人じゃねーか。千葉市で、本来はマイクロシェルという、実に深い奈落のような底を這うような世界の研究家、黒住耐二さんとイガイ属の検索に関して話してきた。イガイ属の同定はとても難しい。簡単に考えると簡単だけど、自分で検索項目を考えないといけない。国内海域には本来いなくてサハリンなどからの移入種、キタノムラサキイガイを加えて考えると、余計に難しく脳みそが奈落の底に落ちていくような気がする。さて、イガイは撮影が終わったら、少量の水分(真水)で蒸し煮にしては貝殻の内側を撮影する。
八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で宮城県産だという、「しゅーりがい」を買う。重さをチェックしたクマゴロウの恋女房は、ためらうことなく伝票に「ムールガイ」と書いた。今や「しゅーりがい」も、「しゅうりがい」も、「いのかい」も、イガイも消滅して、「ムールガイ」になってしまったのだ。本来、Mulgaï (ムール)はヨーロッパイガイと日本列島でも大繁殖しているムラサキイガイの、ヨーロッパ、アメリカ、カナダの呼び名であって、イガイはイガイなんだけど世間は標準和名イガイすらを抹殺しようとしている。驚くべきは産地の伝票すらムールとなっていることが多い。簡単にいうと、本来日本列島にいたイガイは、ヨーロッパから来た新参者のムラサキイガイに流通の場で量的に負けており、最近では呼び名すらカッコイイからかも知れないけど、「ムールガイ」にされているのだ。これじゃ、ヤマト王権に抹殺された縄文人じゃねーか。千葉市で、本来はマイクロシェルという、実に深い奈落のような底を這うような世界の研究家、黒住耐二さんとイガイ属の検索に関して話してきた。イガイ属の同定はとても難しい。簡単に考えると簡単だけど、自分で検索項目を考えないといけない。国内海域には本来いなくてサハリンなどからの移入種、キタノムラサキイガイを加えて考えると、余計に難しく脳みそが奈落の底に落ちていくような気がする。さて、イガイは撮影が終わったら、少量の水分(真水)で蒸し煮にしては貝殻の内側を撮影する。 神奈川県小田原魚市場、二宮定置にイシダイをわけていただく。ありがとう!イシダイは時季になると食べ頃サイズ、1.5kgから2㎏の同級生が大きな群れを作って定置網に入ってくる。イシダイは漁の盛期を迎える。春はイシダイの食い頃、かつ旬なのである。とまでは何度も述べている。3月半ばのイシダイ料理の続きだ。市場での立ち話、「最近、カレイ(他の魚でも煮つけ用は)が人気がないのは煮つけを家庭で作らないからだ。店で出すと売れるのに……」から煮つけ方には2通りあるという話をば。なぜ、煮つけを家庭で作らないんだろう?失敗しにくい料理だし、歩留まりよく食べられるのに不思議でならない。たぶん、料理雑誌や料理本がいけないんじゃないかな? 難しそうに書きすぎている。要は魚など魚介類を液体で熱を通すだけなのだ。
神奈川県小田原魚市場、二宮定置にイシダイをわけていただく。ありがとう!イシダイは時季になると食べ頃サイズ、1.5kgから2㎏の同級生が大きな群れを作って定置網に入ってくる。イシダイは漁の盛期を迎える。春はイシダイの食い頃、かつ旬なのである。とまでは何度も述べている。3月半ばのイシダイ料理の続きだ。市場での立ち話、「最近、カレイ(他の魚でも煮つけ用は)が人気がないのは煮つけを家庭で作らないからだ。店で出すと売れるのに……」から煮つけ方には2通りあるという話をば。なぜ、煮つけを家庭で作らないんだろう?失敗しにくい料理だし、歩留まりよく食べられるのに不思議でならない。たぶん、料理雑誌や料理本がいけないんじゃないかな? 難しそうに書きすぎている。要は魚など魚介類を液体で熱を通すだけなのだ。 福島県から山形県の、太平洋側と日本海側のど真ん中を走る尾根に、比較的大きな盆地がぽつんぽつんとある。そのひとつに米沢市はある。伊達家、上杉家と有力大名が藩主となるくらいなので、稔りがよく、戦国時代には重要な拠点であったはずだ。この本州東北地方の真ん中に点在する町の産物は非常に面白い。米沢織があり、食べ物では山菜、コイが有名である。東に三陸、西に越後と水産物も東西から送られて来たに違いない。米沢市には地方公設市場がある。ここにある『かねしめ水産 ケーエスフーズ』で作っているのが「昔ながらのしょっぱい塩がつお」である。東北地方太平洋側ではとれたカツオに塩をして、山間部に送っていた。その終着点のひとつが米沢であったのだと思う。ちなみにこの国では長い間、魚介類を生で山間部に送ることは出来なかった。1925年昭和になり、1950年代高度成長期になってもこの国のコールドチェーン化(生鮮品の保冷しての流通)は進んでいなかった。1960年代になって初めて一般家庭で冷蔵庫が普及し始め、魚介類の水揚げから流通、販売、消費まで通しての保冷・冷凍技術が確立するのは1970年代になってからだという人も少なくない。当然、三陸ではコールドチェーンが確立するまで、カツオは節加工するか、塩蔵して出荷していたのだ。この産地から来ていた「塩かつお」の、塩分濃度が年々下がるとともに、入荷量が減ってきた。そんなとき消費地である米沢で作り始めたのが、この塩分の非常に高い「塩かつお」である。世の中が減塩減塩と騒ぎ、加工品全体の塩分濃度が下がる中、米沢近郊ではまだまだ塩分濃度の強いものが好まれていた。このように本来魚介類の産地で作られていた加工品が作られなくなり、消費地で作られるようになる例は少なくない。
福島県から山形県の、太平洋側と日本海側のど真ん中を走る尾根に、比較的大きな盆地がぽつんぽつんとある。そのひとつに米沢市はある。伊達家、上杉家と有力大名が藩主となるくらいなので、稔りがよく、戦国時代には重要な拠点であったはずだ。この本州東北地方の真ん中に点在する町の産物は非常に面白い。米沢織があり、食べ物では山菜、コイが有名である。東に三陸、西に越後と水産物も東西から送られて来たに違いない。米沢市には地方公設市場がある。ここにある『かねしめ水産 ケーエスフーズ』で作っているのが「昔ながらのしょっぱい塩がつお」である。東北地方太平洋側ではとれたカツオに塩をして、山間部に送っていた。その終着点のひとつが米沢であったのだと思う。ちなみにこの国では長い間、魚介類を生で山間部に送ることは出来なかった。1925年昭和になり、1950年代高度成長期になってもこの国のコールドチェーン化(生鮮品の保冷しての流通)は進んでいなかった。1960年代になって初めて一般家庭で冷蔵庫が普及し始め、魚介類の水揚げから流通、販売、消費まで通しての保冷・冷凍技術が確立するのは1970年代になってからだという人も少なくない。当然、三陸ではコールドチェーンが確立するまで、カツオは節加工するか、塩蔵して出荷していたのだ。この産地から来ていた「塩かつお」の、塩分濃度が年々下がるとともに、入荷量が減ってきた。そんなとき消費地である米沢で作り始めたのが、この塩分の非常に高い「塩かつお」である。世の中が減塩減塩と騒ぎ、加工品全体の塩分濃度が下がる中、米沢近郊ではまだまだ塩分濃度の強いものが好まれていた。このように本来魚介類の産地で作られていた加工品が作られなくなり、消費地で作られるようになる例は少なくない。






