壱岐勝本漁港のメジでねぎま
壱岐のメジは脂がのりすぎるくらいにのっている


上京して、ときどき友人と酒を飲むようになったとき、関西と関東の違いを最初に感じたのは刺身だ。
もちろん関西では「造り」なので言語的にも違うけど、関西だと「いろいろお造りできますよ」と料理店で言われ、当時わからないままに丸ハゲ(カワハギ)とかカレイ(メイタガレイ)とかをお願いしていた。
関東で「刺身」というと魚の種類を聞かれることはまずなかった。高級な料理店はともかく、安い食堂を兼ねるような飲み屋の刺身は赤身(マグロ)に決まっていたからだ。
大坂は白身を好み、江戸は赤身を好むとも言えるだろう。
歴史的にみても江戸ではマグロをよく食べる。
江戸はマグロの産地にも近い。今の千葉県である上総、安房はクロマグロの産地であった。とれたマグロは房総半島内房と三浦半島をジグザクに結ぶ水運が発達していたので、短時間の内に日本橋の魚河岸に運ぶことができた。
大坂の外海、マグロの産地は紀伊国、和歌山県だが遠く、その上、ここで揚がるのは「本ハツ」、キハダマグロだ。瀬戸内海という白身魚の宝庫が目の前に広がっていることも、白身を好むようになった要因である。
市場を見てもわかる。東京の豊洲市場でいちばん多いのが大物(マグロ)屋なのだ。
江戸では江戸時代以前から赤身魚をよく食べていたようだ。カツオがいい例だし、クロマグロの成魚はともかく、若い個体は盛んに食べていた。
庶民生活史の資料が増える江戸時代になると、よりマグロに偏る。江戸時代の文化文政期(1804-1830)の居酒屋の定番はマグロの刺身に、「ねぎま」だった。
もともとマグロは下魚とされ、比較的安い魚であった。江戸市中ではマグロの行商が行われていて、塩まぐろ(塩蔵)が売られていた。それが変化するのが江戸時代後半にさしかかる明和から天明(1764-1789)にかけてだ。この時代は田沼意次の自由で明るい時代でもあり、江戸時代の大きな変革期である。東西の文化的な地位が逆転し、経済的にも断然江戸が優位となる。この時代に、マグロは鮮魚で売られるようになり、汁や煮つけ、刺身でも食べられるように変わる。
文化期から天保期にかけて師走から春先にかけてマグロ事件ともいえそうな騒動が起こる。日本橋魚河岸は突然のマグロの大漁に遭遇する。数万本のマグロが魚河岸に並び、天保時代など、しわいやの滝沢馬琴すら、マグロを半身買いしている。
ちなみにこのときのマグロは二尺五寸(75cm前後)から三尺(90cm前後)なので、今のメジだ。これによってマグロのづけも含めて刺身がより身近なものとなり、「ねぎま」は居酒屋定番の品書きである豆腐よりも安くなる。
「ねぎま」は醤油仕立てでマグロの切り身とネギを煮たものである。漢字にすると「葱鮪」で、今では鍋仕立てにすることが多い。
八王子総合卸売協同組合、舵丸水産にあったのが長崎県壱岐、勝本漁港で揚がったメジ(クロマグロの若い個体)だ。8㎏もあるので丸買いではなく4分の1本を買う。これで三日三晩かけていろんな料理を作る。
マグロもうまいが、煮るほどにねぎネギが主役に成り代わる


今、江戸時代史にとっぷり漬かっているので、真っ先に作ったのは「ねぎま」である。
本来は刺身だが、本音を言わせたもらうなら、脂がのり過ぎていて、刺身で食べると重すぎた。2切れも食べるとギブアップしたくなる。脂の塊のような身を、割り下で煮ながら、脂を落としながら食べる。
割り下は酒・みりん・醤油・水を合わせて加減する。甘いのがよければ砂糖を使ってもいい。
マグロは大振りのぶつ切りにする。
大量のねぎを3、4㎝に切る。
ねぎを鍋に敷き詰めて、マグロのブツを煮ながら食べる。
ほとんど生でも食べられるが、少し煮て柔らかくなったものの方がボクにはおいしい。
マグロよりもねぎの方がおいしいと思えるほどなのも、「ねぎま」の特徴である。
大量にねぎを用意しておき、終いにねぎを煮て、ご飯を食べてもうまい。
『和漢三才図会』、『魚鑑』ほか原書以外にも、飯野亮介、大石慎三郎、大石学、鈴木晋一などなどの著書を参考にさせていただく。
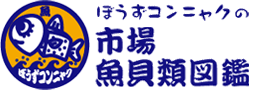








 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典






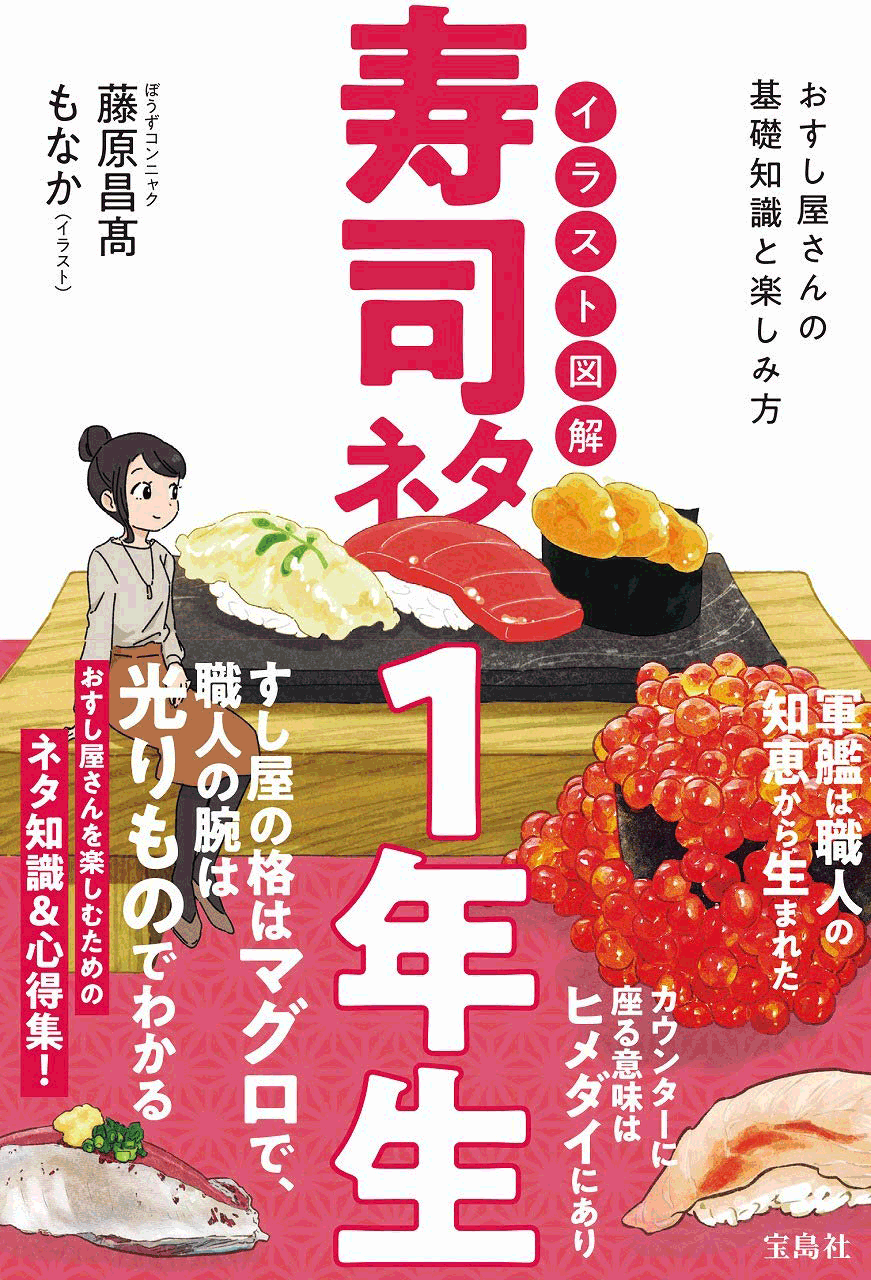 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



