 小説など活字となった文章の中の「カキフライ」を見つけてはつけ加えていく。できるだけ時代順に並べる。
小説など活字となった文章の中の「カキフライ」を見つけてはつけ加えていく。できるだけ時代順に並べる。まずはカキフライとは?
カキフライが生まれたのは日本だと思っている。海外にカキフライもしくは似た料理があるのかどうかはこれからの課題。
カキフライはカキの剥き身(マガキ)にパン粉をつけて揚げたもののことだ。
同様の料理にはチキンフライ、エビフライ、とんかつ(カツレツ)などがある。
「カキ(マガキ)」はわかるが、「ふらい」は揚げるという意味。
揚げるは、英語で「Fiy」、フランス語で「frire」でここから音をとったと思うべきだろう。
「とんかつ」の「かつ」はコートレット(côtelette)からきているとされている。コートレットは「カツレツ」にも変化する。
なぜか、マガキのフライを「かきかつ」とは言わない。
以上すべてパン粉をつけて揚げるという意味で同じだ。
カキフライを最初に造ったのは、今銀座で健在である『煉瓦亭』だとかの説がある。
『煉瓦亭(明治28年/1895)』は「とんかつ(カツレツ)」発祥の店だとされている。そしてマガキを使った「カキフライ」も、である。
ボクもカキフライは大好きで日本橋周辺で仕事をしていたとき、10月になると高嶋屋裏によく通ったものだ。
ちなみに徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれの田舎者が、カキフライを初めて食べたのは上京してからのことだ。
あまりにもおいしいのでショックを受けた記憶がある。
コラムの続きを読む
 2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。
2025年10月22日、福島県に入ると放射線量の表示板が高速道路に点々と続く。放射線量は0.2μSv/hとかだけど、これはほぼゼロに近い数値だと思われる。
原発事故は未だに続いているが、放射線の脅威は現状ではないということだろう。
さて相馬市の相馬という言語、また言語のもとになった相馬氏の歴史は古い。
相馬氏は国内でももっとも古い家だ。桓武平氏で、平安時代、後三年の役(1083-1087)に戦功をたて下総千葉郡に下って千葉氏が生まれるが、その庶流になる。
房総平氏(平家ではない)は関東に広がった平氏の一群でほかには秩父平氏、相模平氏の武士群が存在した。
もちろん源義家とその弟、義満、藤原秀郷などの子孫が関東に勢力を持つ。
相馬氏の祖は下総相馬郡をおさめて相馬を名乗り、奥州合戦(奥州藤原氏と源頼朝のたたかい)、南北朝の闘いで手柄を立てて現在の南相馬市、相馬市に定着する
相馬氏は平安時代、鎌倉時代源氏・北条執権時代を生き抜き、南北朝時代の戦乱も、戦乱に次ぐ戦乱の室町時代も息抜き、徳川時代になって相馬、中村藩の藩主となり明治まで続く。
コラムの続きを読む
 近所のスーパーで売っていた愛媛県産イトヒキアジは、魚価が高騰している中にあってもとてもお買い得だった。
近所のスーパーで売っていた愛媛県産イトヒキアジは、魚価が高騰している中にあってもとてもお買い得だった。おいしい魚だが、知名度が極端に低いので安いのだ。
めぼしい魚のない日で唯一光り輝いていたのにだれも気がつかない。
その日、探していたのはおかずになる魚だ。
2切れで321gあるので、独り者なら4食のおかずになる。
当日はボクの本棚を撮影に来た若い衆がいたので、一緒に試食していただく。
作ったのはバター焼きと、まーす煮だ。
沖縄では「がーらのバター焼き」、「がーらのまーす煮」だろう。
「バター焼き」は切り身に塩コショウして小麦粉をまぶし、多めの油で焦げ目がつくくらいソテーする。
仕上げに油をすて、マーガリンをからめる。
たべる直前にしょう油を垂らす。
ボク以上にカメラマンさんが夢中になる。
温めたパンを渡すときれいさっぱり食べてくれた。
イトヒキアジは少し味が淡泊すぎる。
上品な味の魚にはマーガリンのようなインパクトのある素材が合う。
焦げたマーガリンの味と上品な身の対比がいい。
コラムの続きを読む
 写真は水揚げ後、5日目の刺身だ。
写真は水揚げ後、5日目の刺身だ。6日目も同じく非常に美味であった。
福島県郡山市から12日に来て、撮影し、12日の深夜、翌日、と刺身を造っているが、味も食感もそれほど落ちない、というかうま味は増すばかりだった。
サザナミダイなどメイチダイ属の魚には不慣れなはずの下北半島揚がったものなのに、サザナミダイと気がついた人がいたこと自体が奇跡。
味の素晴らしさも相まって、感動的でもある。
12日深夜は食感こそよかったものの、うま味自体は少なく、おいしいとは思ったものの、平凡な味だった。
これが翌日、翌々日とうま味が増大する。
食感がなめらかで、それだけでもいいのに、舌に触れた途端に甘味が感じられ、うま味が延々と続く。
ちなみに今回のサザナミダイは非常に上品な白身で、時季のせいかそほど脂がのっていなかった。
身のうま味だけのおいしさなのに、強い衝撃が残る。
最後に残った菊正宗樽酒を用意していたが、無用だった。
コラムの続きを読む
 毎年、11月になって日本海の多くの県でズワイガニが解禁されると、必ず雌ガニ(兵庫県などでは、せこがに)を買う。
毎年、11月になって日本海の多くの県でズワイガニが解禁されると、必ず雌ガニ(兵庫県などでは、せこがに)を買う。雄ガニは年を越してから買うことにしていたが、今年は早々と山形県産で初物食いをすませてしまった。
山形県はズワイガニ漁解禁の狂騒の中にいないが、ボクには十二分においしいというか、十二分に贅沢である。
雄はともかく、今季日本海の初雌ガニは兵庫県浜坂産だ。
雌ガニである「せこがに」の問題点は食中に食べるものでも、酒の肴でもないことだ。
それならなんだ? と言われたら、おやつだ! と答えるしかない。
強めの塩水でゆでること10分ほど。
背を下にしてゆで、上にして板などに取る。
冷たい水をかけて粗熱を取る。
コラムの続きを読む
 八王子卸売協同組合、舵丸水産で今季初のむきガキ(マガキ)を買った。
八王子卸売協同組合、舵丸水産で今季初のむきガキ(マガキ)を買った。荷の箱が見つからなくて産地不明だったが岩手県産かも知れない。
持ち帰って驚いた。
全体に小さくて、破片としか思えない大きさのものまで混ざっている。
なのに高い。
舵丸水産では大きくて粒ぞろいのものは仕入れられなかったようだ。
今回は片栗粉を絡めて洗う。
布の上でつぶを揃えながら、極小だけを集めて、醤油に漬け込む。
この極小がバカにならないほど多いが、つぶを揃えたものの値段を聞くととても手が出ない。
こんなに遅い初むきガキも初めてだし、こんなにつぶの揃っていない小さなむきガキも初めてだ。
同時に炊飯の用意。
コラムの続きを読む
 胎内市中条は街歩きのできる貴重なところだった。
胎内市中条は街歩きのできる貴重なところだった。商店街が生きているのがいい。
こんなところに来たら、何をやるのか?
ただただ歩くだけ、それで充分楽しい。
歩きながら和菓子屋を見つけたら片っ端から買い求めようとしたが、なんだか中条町の和菓子屋は和菓子屋のようで和菓子屋のようでなく、洋菓子屋のようで、洋菓子屋のようでもない。
これと同じ感じは根室にもあった。
そろそろ新潟市に向かおうかと中心地から少し外れたところに、また和菓子屋があって、入ると洋菓子屋だった。
新潟県の菓子店の特徴は和洋がはっきりしないこと、かも知れない。
そこで買ったのが、久しぶりに出合った「たぬきケーキ」、そして「ロックケーキ」だ。
考えてみると「たぬきケーキ」は千葉県以来ではないか。
要するにタヌキの形をしていれば、「たぬきケーキ」だということがわかってきた。
周りが少し硬い生地で中がカステラ、上にクリーム(これなんていうんだろう)で頭を造り、繋がった目と鼻と尾がある。
そんなに出合っているわけではないが、このタイプは初めてだ。
コラムの続きを読む
 モウレツ釣り師である舵丸水産、クマゴロウが手渡ししてくれたシログチは非常に小振りだったが、掌に受けただけでただものではないと感じるものだった。
モウレツ釣り師である舵丸水産、クマゴロウが手渡ししてくれたシログチは非常に小振りだったが、掌に受けただけでただものではないと感じるものだった。小さいのに強い張りがあって大きく感じる。
しかも魚屋で釣り師なので首を折って血抜きしていて、カタカタである。
持ち帰ってすぐ計測して撮影、水洗いする。
三枚に下ろしてペーパータオルにくるんで保存、夕方に刺身、焼霜造りにする。
刺身を食べた途端に、焼霜造りは屋上屋を架すものだと思った。
シンプルな刺身一切れの食感が素晴らしいのである。
硬いのではなく、なんなくかめるのにシコっとする。
そして一気に甘味が広がり、明らかにその甘味は複雑なアミノ酸からくるものだとわかる。
旅の前で減酒に励んでいるのに、コップに酒をそそいでいる自分がいる。
やりすぎかな、と思った焼霜造り(あぶり)も結構毛だらけである。
どこにも欠点がない。
炙った皮目の香り、強いうま味で脳みそがうれしくて沸き立つ。
今は刺身びいきだけど、食べ終えた後に評価が揺れる。
いけないとは思いながら菊正宗樽酒を正2合。
コラムの続きを読む

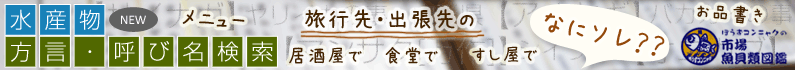

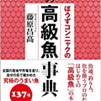 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
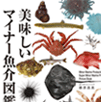
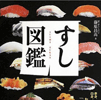
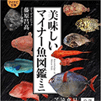
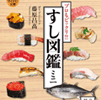

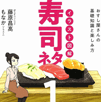 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























