 赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。
赤い蒲鉾を見ると手が出るのは、徳島県人のボクは子供の頃から蒲鉾は赤いものだと思っているからだ。板にのった赤い蒲鉾を「板つけ」と言った。
徳島県ではうどんに「板つけ」はつきものだった。
基本的に「板つけ」は赤い蒸し蒲鉾のことだけど、決して上等ではない、下手なものをさした。
香川でも「板つけ」、高知でも「板つけ」だけど愛媛県ではなんというのだろう。
全国的にどうなのかはわからないが、高知県宿毛市で買った『八馬かまぼこ』と『大原かまぼこ』の赤い蒲鉾は「板つけ」そのものであるが、表記は単に「蒲鉾」である。
またうどんの具として使うのか否かは不明だ。
コラムの続きを読む
 合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。
合併というものは町の名前を削除するだけではなく、町のよさも削除してしまいがちである。10月3日、今では新潟市西区内野町、でしかないが、合併前までは内野町だった。
合併は大失敗だという人が少なからずいるが、ボクなど暴挙だと思っている。
自治体(小さな行政)と行政区(大規模な行政)を分ければいいだけなのに、乱暴なことをやる。
さて、内野駅周辺は明らかに新潟市中心部への住宅地といったところだろうか。
例えば京王線だと調布とか、中央線だとすると荻窪だとか。
夕闇迫る頃、商店の灯りが点々と見える。
こんなところにはいい居酒屋がありがちである。
今回、越後新川の面々と訪ったのは『旬菜 籐や』という居酒屋である。
どうやら内野町にはいい居酒屋が少なからずあるようだが、そのひとつだ。
店内は満席に近い。
話が主となり、料理はおいしい記憶しか残らなかったが、一皿一皿外れなしだった。
コラムの続きを読む
 日本酒は旅先で、酒屋で買うのが好きだ。
日本酒は旅先で、酒屋で買うのが好きだ。ただ最近、普通にいい酒屋がとても少なくなっていて困っている。
やたらに珍しい酒とか、変な名前の酒とかを置いている酒屋が生き残り、普通の平凡だけど優秀な酒屋が消えつつある。
その点、『やしち酒店』はボクの理想の酒屋に近い。
まず酒の扱いがていねいである。
普通の良酒が普通に揃っている。
ほんの数百メートル先にある『樋木酒造株式会社』鶴の友は全種揃っている。
同町内の『塩川酒造』の酒がいい酒であることもわかった。
特に今回買った鶴の友3種はみな素晴らしかった。
新潟県の良酒が総て揃っているのに、さりげない。
コラムの続きを読む
 お茶の水、駿河台にあった学校の隣に居酒屋があった。
お茶の水、駿河台にあった学校の隣に居酒屋があった。神保町で働き始めてすぐに、この居酒屋で友人と酒を飲んだ。
この居酒屋に必ずあったのが「いしもちの塩焼き(シログチの塩焼き)」で、お願いするといつも生焼けだったので、いつも焼き直してもらっていた。
卒業したての頃、同級生とこの居酒屋で「いしもちの塩焼き」をお願いして、また生焼けだったので大笑いしたものだ。
以来彼とは会っていなかった。
そんな男とまた会うなんて。
「いしもちの塩焼き」には想い出がいっぱいある。
舵丸水産で1尾だけ「いしもち(シログチ)」を買ったのも、久しぶりに同級生とあったからだ。
それほど「いしもちの塩焼き」は東京を代表する魚料理であった。
東京湾で盛んだった「いしもち釣り」も、「焼き魚を釣りに行く」という感じだった。
さて、水洗いしてずぼ抜き(口から内臓を出す)し、振り塩をして1日寝かせる。
塩をして1時間程度で焼いてもいい。
我が家で丸のまま焼けるぎりぎりのサイズだったので、つきっきりで焼き上げる。
今回は焼き上げて間髪入れずに食べたが、塩焼きは冷めてから食べてもおいしいことも書いておく。
これでご飯を食べたが、小骨が少なく、身離れがいいなど、至っておかず向きの魚である。
取り分け皮の風味がいい。
この皮の風味は冷めた方が強く感じられるのは不思議だ。
データを見るとシログチの塩焼きは去年の秋に食べて以来だ。
来年は毎月味見して記録をとろう。
コラムの続きを読む
 新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。
新潟県西区五十嵐新川漁港周辺の生物・食物図鑑を作っていく。新川漁協に水揚げされる水産物は量的には多くないが、多彩である。
今回はカズラガイである。
新潟県・房総半島以南の比較的浅い砂地や泥場に棲息している。
今回のものは新川漁港の沖合、水深10m前後でとれたものだ。
貝を集めるという趣味がある。
コレクターという言葉は使いたくないが、いたって身近なところにいる軟体類である巻貝や二枚貝を集めるのは、すぐ始められるし、とても楽しい。
それぞれの貝には「手に入れやすいもの」、「手に入れるのが大変なもの」など多彩である。
中で巻き貝の種類は膨大で、未だに名前のない種もいる。
そんな中でもカズラガイはビーチコーミングでも刺網の混獲物としても手に入れやすいもののひとつ。
とても美しい貝なので、貝集めを本種から初めてもいいだろう。
協力/鈴木重雄さんさん、島谷将之さん・星野健一郎さん(拓洋丸)・中務謙吾さん(すべて新潟県新潟市西区五十嵐新川)
コラムの続きを読む
 10月17日、二宮定置に入った小型のアイゴの干ものは持ち帰ってすぐ、立て塩にして干したものでまったくくせも臭味もない。
10月17日、二宮定置に入った小型のアイゴの干ものは持ち帰ってすぐ、立て塩にして干したものでまったくくせも臭味もない。話が横道に逸れるが、徳島県県南に、このくせのない干ものを嫌う(臭い干ものが好きな)老人達(当然ほかの地域にもいまだにいる)がまだ存在するが、いかなボクの生まれが徳島県でも、この臭みが好きになる可能性はないと思っている。
このアイゴやタカノハダイ、ニザダイの臭みを好む傾向は、生まれてすぐから連綿と臭みのある魚を食べることで手に入れたものだろう。
このような臭みを好む老人達を継ぐ人もいない、と思う。
閑話休題。
アイゴのおいしさは、一に皮、二に身だ。
小さい個体のいいところは、意識しなくても身も皮も一緒に口に入ってしまうことだろう。
身に対する皮の量的な比率が大きいこともあると思う。
香ばしさと強いうま味が口の中いっぱいに広がる。
1尾だけゼンマイ状の内臓を残して干してみた。
臭みはあるものの内臓のうま味が恐ろしいほどに強い。
細長い袋状の消化管自体もおいしいが、ゼンマイの中には海藻らしいものが少し入っていて、独特の味がする。
小型なので臭みは耐えられないほどではない。
好きか? と言われると、好きではないが、これくらいなら珍重する向きもありそうである。
コラムの続きを読む
 あっちのスーパーで岩手県産をがあったとサンマ買い、こっちのスーパーで北海道産を見つけてまた買う。
あっちのスーパーで岩手県産をがあったとサンマ買い、こっちのスーパーで北海道産を見つけてまた買う。毎年、計測して撮影しているのだけど、今年は安くてありがたい。
近所で刺身用とあるものの北海道産を、これが最後かも、と思って買って、せっかくなので、丼にする。
焼霜造りと刺身を作って、ご飯に乗せるだけだけど、ご飯に一工夫する。
もうどこのものだかわからない柚子をご飯に振り、あらったみょうがと青じそを散らす。
そこに焼霜、刺身を乗せるだけだ。
高知県宿毛市、『篠上商店』のフンドウカネカ醤油を一回しかけて出来上がりだ。
やけに甘いフンドウカネカ醤油とサンマの刺身が、これまたやけに合う。
そろそろお終いか、と思うせいか、このサンマでしか味わえないおいしさが愛おしい。
それにしてもご飯とサンマってのも結構毛だらけである。
コラムの続きを読む
 言った憶えがあるので否定できないので非常に困った。
言った憶えがあるので否定できないので非常に困った。問題は「(アサリの)木更津ブルーは本当ですか」という話である。
たしかに初めてこの言葉を吐いたのはボクだと思う。
国内、中国など海外でみてもアサリの青い個体の比率は低いのに、千葉県木更津、富津のアサリは青い個体の比率が高い。
「木更津ブルー」はそこから飛び出した言語なので、犯人はボクだ。
でも今頃、どこで、どのような媒体で見たのか知らないけれど、わざわざ聞いてくるなんて、思いもしなかった。
ついでに、とあるDと撮影中に「空の色のようなブルーのアサリを見つけると、幸せになる」と言った気がする。
また、サービス精神旺盛なボクは、今回も、
「青い、ブルーのアサリを見つけると幸せになれるという木更津の伝説があるんです。もちろん木更津に限りません。四つ葉のクローバーよりも確実に幸せになると思います」
と言ったけど、本気にしなかったと思うけど、どうでしょうね。
ちなみに幸せになれる保証はない。
コラムの続きを読む

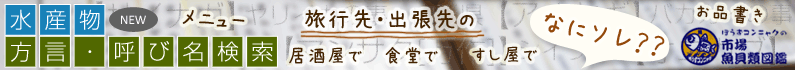

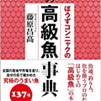 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
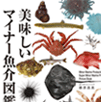
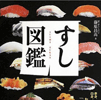
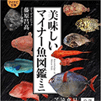
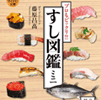

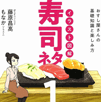 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























