正岡子規の「堅魚の刺身、薩摩芋の味噌汁」
正岡子規の舌はとても確かなり


明治三十三年(1900)十月十五、正岡子規は死の2年前であり、寝返りはおろか仰臥するか体を左に向けておくのが精一杯になる。
そんな状態にあっても日光が窓に差し込んでくると、〈午時(正午)は近づきたり〉と飯を待つ気持ちが募るのが子規らしいところだ。
ほどなく母、八重が長方形の膳に飯、一汁一菜をのせて来る。
〈あたたかきやはらかき飯、堅魚の刺肉(さしみ)、薩摩芋の味噌汁の三種なり。皆好物なるが上に配合殊に善ければうまき事おびただし。飯二碗半、汁二椀、刺肉食ひ尽くす〉
地獄のような苦しみを感じながら綴られる、正岡子規の文章の簡明さに恐れ入るしかない。
さて、薩摩芋の味噌汁は学生時代に正岡子規の文章で知っていたことを、フロッピーを変換して判明した。記憶力が悪いのでいつもお初だと思ってしまう。
ちなみに堅魚(カツオ)の刺肉と薩摩芋の味噌汁はとても合う。
確かにこの組み合わせで食う飯はうまい。
カツオは1900年にはまだ魚介類を氷で冷やしていなかったことからして、千葉県銚子産で舟運を使って一晩で日本橋の魚河岸に持ち込んだものだろう。このときすでに利根運河は完成しており、江戸時代以来の大動脈は関宿町まで北上しなくてよくなっている。
ちなみに当時、新暦の10月は比較的涼しかった。群馬県や東京都多摩地区で初霜の降りる時季だ。
相模湾からでも千葉県からでも、カツオを生の状態で運べる期間は春と秋に限られていたのである。
秋のカツオを正岡子規が食べられるのは明治34年を残すのみ。
『飯待つ間』(岩波文庫)
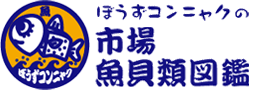








 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典






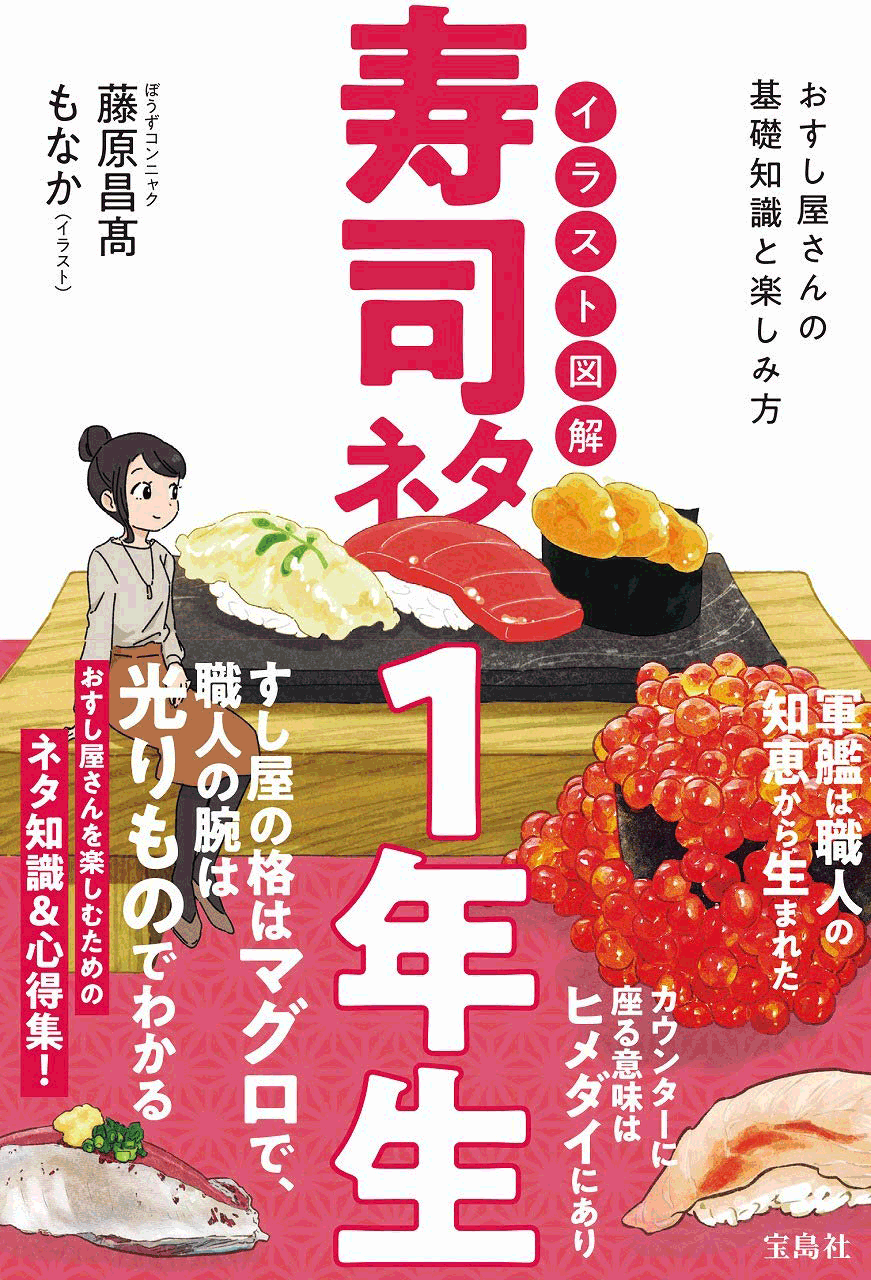 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



