 浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。
浜名湖の雄踏漁協で「ちんた(クロダイ)」をいただいた。浜名湖では300g以下を「ちんた」、以上を「くろだい」という。
今回の体長19cm・195g は競りに出すともなく、放流することになるらしい。
ちなみに1㎏前後は競り場に生きた状態で並んでいたし、直売所では刺身が売られていた。
これを活かして持ち帰っている途中、高速道路上で後ろからバシャバシャと音がする。
PAに入って見ると、「ちんた」が大暴れをしているではないか。
仕方なく締めて、血抜きしないで持ち帰った。
暴れたせいで尾鰭がぼろぼろ、決していい状態とは言えない。
帰り着いた日に下ろして翌日刺身にする。
大きさも、漁の後のボクの締め方にも、期待できるところはなにもない。
ところが、これがうまかったのである。
脂はないが、味がある。
口に入れてすぐに甘味とうま味があり、中だるみがない。
「ちんた」は「ちんた」なりのおいしさがあるのだな、なんて思ったものだ。
ついでに言えば水域での汚れや汚染に影響を受けやすい魚だが、浜名湖はこの点からしても大丈夫らしい。
コラムの続きを読む
 浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。
浜名湖の東西はともに遠江の西で、湖を挟んではいるが同じ地区だと思っていた。実際に行って、いろいろ話を聞くと、食文化はまったく別で、魚の評価も違っていた。
例えばヒイラギは、浜名湖の西の湖西市鷲津・入出では「ぜんめ」、「ぜんな」、東の浜松市雄踏では「ねこた(猫またぎ)」という。
西では食べ物で、東出は捨てる物だ。
東、雄踏漁協の漁師さんにお願いしなくても、いただくことが出来たのが「ねこた」である。
それでは浜名湖のヒイラギは、東西で味が違うのだろうか? というと、そんなことはない。
「ヒイラギはとてもうまい魚だ」ということを東の漁師さんにいただいたヒイラギで、改めて思う。
棘をハサミで切り取り、粗塩でぬめりを取って、水洗い。
あとはざっと煮るだけ。
高知市の漁師さんで、ぬめりも味だという人がいるので、ぬめり取りは不要かも。
身離れがよく、身に甘味があり、とってもおいしゅう、ござんした。
コラムの続きを読む
 カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。
カツオの切り身をあぶる地域は少なくないが、切りつけて塩を手につけてたたくのは高知県だけ、なのだろう。高知県の旅では中土佐町、いの町で実演しているのを見ている。
実に手慣れたもので、あぶる、切る、塩をつけた手でたたく、と次々に出来上がる。
あまりにもうまそうなので、思わず買ってしまいそうになる。
この本来、カツオで造る、「塩たたき」を「だるま(メバチマグロの幼魚)」で造る。
出来上がりを盛り付けて、すだちを1個全部搾り、みょうがに青じそに、にんにくを天盛りにした。
仕上げに追いスダチをする。
塩気は充分なので、スダチと香辛野菜だけの単純な組み合わせで食べる。
脂ののった「だるま」は、うま味も非常に豊かで恐るべきうまさである。
スダチ2個を搾ったが、もっと多くてもよかったかも。
香酸柑橘類の旬はまだまだ遠い。
コラムの続きを読む
 浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。
浜名湖に散らばる角網(小型の定置網)で揚がる魚の種類は非常に多い。大型魚はスズキ、クロダイ、ボラなどだが、むしろ小型魚であるコノシロ、はんだ(サッパ)、ねこた(ヒイラギ)、夏はぜ(ウロハゼ)などが多いようだ。
浜松市雄踏では「はんだ(サッパ)」は当日見た限りでは、競りに出すことがなく、廃棄されているようだった。
これは浜名湖西部の鷲津でも同じである。
ちなみにサッパは大きな括りではニシンやマイワシに近い魚で、腹部の底の部分に非常に硬い鱗があるのが特徴である。
水揚げを見ていたとき、雄踏漁協の漁師さんたちに分けていただいたので、持ち帰って計測して食べてみた。
それほど面倒な料理ではなく、岡山県で普通に作られている焼き漬けである。
じっくり時間をかけて素焼きにし、二杯酢に1日漬け込んだだけ。
酢と相性がいいのもあるが、非常にこくのある味で、濃厚なうま味が舌に残る。
サッパという魚は、小骨が硬くて多いという二重苦を背負っているが、うま味の豊かさという点ではニシン類の中でもトップクラスである。
岡山県人をして、「ままかり料理」の第一にあげる人が多いわけがわかる。
旅の後なので、静岡県藤枝市の志太泉 原酒を冷やして舌を洗う。
コラムの続きを読む
 山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。
山芋(今回は大和芋)をすって、大きめに切ったブツにかける、ので「山かけ」だ。「山かけ」で重要なのは大和芋をおろし器でおろし、そのあとすり鉢に移して徹底的にすることだ。
コツと言ってなにもないが、すり鉢の中で容赦もなくする、する。
手が疲れるくらいすったら、すり鉢の中にぶつを入れ、こんどは和えて、和えて、和える。
これも徹底的に和える。
大和芋はこれくらいしないとブツと混ざらない。
ボクの場合はあれこれやらず、生醤油とわさびで食べる。
「だるま(メバチマグロの幼魚)」なのに、中心に近い部分にも味がある。
一日寝かしてブツにしたせいか、下ろしたてよりも酸味がある。
大和芋の強いねばりと微かな渋味とうま味が、酸味のあるブツとよく合う。
コラムの続きを読む
 久しぶりに下ろすギマの大量の粘液に苦しんでもだえた。
久しぶりに下ろすギマの大量の粘液に苦しんでもだえた。昔から比較的食べていた浜名湖で、この魚が食べられなくなっているのは、このぬたぬたした粘液と硬い皮と、棘のせいらしい。
確かにべとべととぬめぬめとして、下ろす以前にぬめり殺されそうだ。
そして我が家はコバエだらけでもある。
コバエを追っ払いながら、ぬたぬたする魚の処理をするという地獄のような時間に、ふと気がついたことがある。
間抜けな小バエが1匹いて、ギマの体に着陸した途端動けなくなっているではないか。
そして2匹目も同じ運命をたどる。
そして3匹目も。
設置して3日目の「コバエがホイホイ」では、まだ1匹もとれていないのに、30分弱の間にべとべとする魚で3匹もとれた。
コバエには「コバエがホイホイ」よりもギマの方が有効かも。
コラムの続きを読む
 前回の浜名湖は11月で湖内の漁が終わろうとするときだった。いちばん楽なときに、何も考えないで行ったので、あまり意味のある浜名湖ではなかった。
前回の浜名湖は11月で湖内の漁が終わろうとするときだった。いちばん楽なときに、何も考えないで行ったので、あまり意味のある浜名湖ではなかった。20年振りの浜名湖は、ゼロからの一歩となる。
今回、聞取した情報量が多すぎ、脳内で処理できなかった。
当然、メモの、移動中での整理が追いつかなかった。
しかも暑い。
今回の浜名湖旅は、不正確な情報だらけであるが、じょじょに整理して、テキスト化していく。
今回の誤算は浜名湖の大きさと、地域性を考えなかったことだ。
当然、もらった情報は曖昧になる。
次回は地域を決めて、もっと予習してから行くこととする。
写真は車の中でメモ整理中に飲んだ三ヶ日みかんジュース。
値段以上で、体がゆるむ味だった。
帰宅後はメモの再整理も、持ち帰ったものの整理も出来ず、そのままダウン。
コラムの続きを読む
 料理法に一番というものはない、と信じている。
料理法に一番というものはない、と信じている。ときどき一番おいしい料理法は、とか聞かれると困る。
今回のイワシの梅干し煮などその最たる物だ。
岩手県産のマイワシ(マイワシ)は体長20cm・105g前後で脂が乗っていた。
ボクが梅干し煮にするときやりやすいサイズは、体長17cm前後で80gくらいがいい。
当然、大小で煮方が違う。
今回は水洗いして頭を落とし、3等分にする。
湯に落として冷水に取り、粗熱を取る。
常備菜ではなく単なる煮つけなので酢だき(水と酢でゆでこぼす)はしないで、真子・白子ともに酒・梅干し・水でことことと煮る。
仕上げに醤油を適宜加えて、またことことと煮る。
甘味は加えていないので、梅干しの酸味と醤油辛さだけの煮つけである。
脂がのっているマイワシに甘味を加えると、茶漬けには合わない、とボクは勝手に思っているからだ。
梅干し煮でも当座煮にするときは甘めにするし、酢だきもする。
煮物は臨機応変、その日の気分で作りたい。
こんなところで懺悔するのも変だけど、ボクが夏バテでも痩せないのは、茶漬けがやたらに好きだからだ。
とても三条中納言を笑えない。
コラムの続きを読む

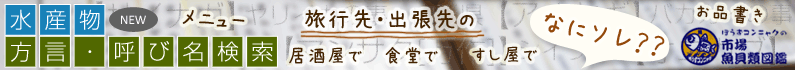

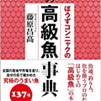 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
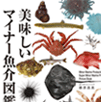
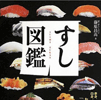
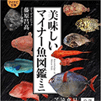
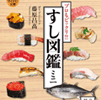

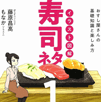 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























