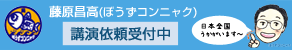メヌケ
一般的に「メヌケ」と呼ばれる水産物についてのまとめページです。
本ページの内容
メヌケ(目抜け)

アカシマメヌケ

深海に生息する大型の赤いメバル属の魚をメヌケという。「めぬき」という人もいる。
赤魚は別の一般名称で、メヌケとは別のグループである。
標準和名にメヌケがつき、わかりやすいものもあるが、和名だけでは判断できないものもある。
標準和名オオサガは、普通、使われることはなく。むしろ地方名の「こうじんめぬけ」、「本めぬけ」の方が一般的である。
またホウズキは比較的南に生息域を取る。昔からのメヌケとは言えないが、関東では同じ扱いとなる。
流通上は標準和名よりも多く使われている呼び名が重要である。
また標準和名クロメヌケは「メヌケ」とあるが、比較的浅場にいる上に赤くない。また一般に「青ぞい」と呼ばれることの方が多い。
「メヌケ」と呼ばれる水産物一覧
●印は「メヌケ」ですがそれ以外はメヌケの仲間ではありません。
-
アカシマメヌケ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深50〜600メートル。 アリューシャン列島、アラスカ〜カナダの太平洋沿岸。アカシマメヌケのページへ -
アラメヌケ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深84〜490メートル。 北海道〜千葉県銚子市の太平洋沿岸、丹後半島沖。 千島列島北部、カムチャツカ半島〜ベーリング海・アリューシャン列島、アラスカ湾からカリフォルニア州南部。太平洋側の冷水域に多い大型の赤いメバル類である。水揚げ量は極端に少なく。流通上は年に数える程度しか見ることがない。 またオオサガ(コウ・・・アラメヌケのページへ -
オオサガ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深200〜1300m。400〜800mに多い。 北海道オホーツク海沿岸、北海道太平洋沿岸〜銚子の太平洋沿岸、相模湾。 千島、天皇海山。北海道から相模湾までの深海にいるが、漁業的には茨城県以北だと思っている。日本近海に多いメヌケ類といった存在だ。ヒレグロメヌケとともに関東でも「目抜け」と呼ばれることが多い。 古・・・オオサガのページへ -
クロメヌケ
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深2-550m。水深200mより浅場にいることが多い。 北海道全沿岸、山形県飛島、新潟県、富山県、富山湾。 沿海州〜間宮海峡、サハリン南東岸・西岸、オホーツク海、千島列島、カムチャツカ半島南東岸、コマンドルスキー諸島、アリューシャン列島。東北でもとれるがほとんどが北海道東部、オホーツク海沿岸で水揚げされている・・・クロメヌケのページへ -
サンコウメヌケ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
オオサガのジュニアシノニムとなり、抹消。サンコウメヌケのページへ -
バラメヌケ
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深100-420m。 北海道〜青森県、新潟県、島根県の日本海沿岸、北海道〜千葉県銚子の太平洋沿岸、希に相模湾。 朝鮮半島東岸中部〜沿海州、千島列島。銚子以北にいるやや大型の赤いメヌケ類である。三陸、北海道などで水揚げがある。北海道では赤物と呼ばれている魚のひとつ。目抜け類(深海性の赤いメバル属)のなかではオオ・・・バラメヌケのページへ -
ヒレグロメヌケ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属
海水魚。水深100-600mに多く1200mよりも浅場。 北海道オホーツク海沿岸、北海道〜岩手県までの太平洋沿岸。 オホーツク海、千島列島、カムチャツカ半島南岸〜ベーリング海・アリューシャン列島、アラスカ湾〜カリフォルニア州南部。東北でも希に揚がるが生息域は国内産目抜け類の中でもっとも北に生息域をもち、主に北海道羅臼な・・・ヒレグロメヌケのページへ -
ベニメヌケ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科ホウズキ属
海水魚。水深420-1200m。 天皇海山。加工品原料として重要なクサカリツボダイの漁が天皇海山群で始まったのが1969年頃とされている。その混獲物だった可能性が高い。本種など赤い深場にいる大型のメバル類(当時はフサカサゴ科)の魚を「赤魚類」、「メヌケ類」といって流通していた。そのひとつだったのだと思われる。・・・ ベニメヌケのページへ -
ホウズキ ●
スズキ目カサゴ亜目メバル科ホウズキ属
海水魚。水深542〜900メートルの岩礁域。 青森県〜岩手県沖〜[東京都三宅島、和歌山県那智勝浦漁港]〜熊野灘、紀伊水道の太平洋沿岸、[富山湾 2008-2018 年に富山湾で新たに記録した魚類 木村知晴・西馬和沙・不破光大・稲村 修(魚津水族館)]、山口県の日本海側、鹿児島県種子島・口之島・奄美大島横当島横当島、悪・・・ホウズキのページへ