
10月3日の新潟旅はいつものように新潟漁業協同組合の競り場から始まる。
新潟県の水産物は南北に長い河岸線と、佐渡、そして日本海に広がる大和堆がある。
1種類の魚の量が多いのが日本海の特徴である。
底曳きが始まっているのでアカムツの量が多く、また新潟市名物「ふなべた(タマガンゾウビラメ)」がていねいな荷の作りで並んでいる。
オオエッチュウバイにチヂミエゾボラ(エゾボラモドキ)、カガバイ、ツバイなども新潟名物である。
まとまった量のズワイガニにも夏の終わりを感じる。
コラムの続きを読む

軽く眠っただけで、元気なくたどり着いても小田原魚市場をひとまわするとシャキットはしないけど、ある程度はしゃんとする。
最初にのぞいた二宮定置は、小型の魚が多くて大変だった。
ボクなど百パーセントお邪魔な、おデブなので、できるだけ邪魔にならないように魚を見た。
ちなみに漁獲された魚貝類は、直接人の口に入る方が漁業的には正しいし、自然にも温暖化にもいい。
でもそれが不可能なときもある。
今回の小イサキ、小ゴマサバなど決してまずいわけではないものの、これを完全に選別するためには漁師さんに限りない長時間労働を強いることになる。
仕方なく、ほとんどがダンベに放り込まれる。
まあ純国産飼料となって無駄なく利用してもらいたい。
自然相手なので仕方がないよな、といいながら、やや大きめの20m・110g前後のイサキを分けてもらっているボクって何だろうな?
帰宅して水洗いする。
刺身にしようかな? と思って鍋にする。
夕ご飯の友なので魚すき(三重県尾鷲で「じふ」、兵庫県で「じゃう」、島根県で「へか焼き」、「煮食い」など日本各地でいろんな料理名で呼ばれている)を作る。
まず割り下を作る。
水・酒・砂糖・醤油を割って一煮立ちさせ味加減をする。
三枚下ろしにして腹骨・血合い骨を取り、そぎ切りにする。
湯通しして冷水に落として水分を切る。
今回はつきこんにゃく、金時草、玉ねぎ、エリンギで小鍋仕立て。
イサキは塩焼きがいちばんだ、なんてことをいう愚か者がいるが、煮てもおいしいのである。
脂がのっているので舌の上で脆弱に崩れ、皮に独特の風味、身に甘味がある。
イサキばかり食べてしまいそうになるのを、つきこんにゃくをつまみ、金時草をつまむ。
酒無しの夕べにご飯がすすむ。
コラムの続きを読む

高知県宿毛市・大月町での水揚げを見て歩くのは、他県と比べると楽である。
温かいし、しかも時間が遅い。
東北など午前2時、3時から魚貝類が並びはじめるところがざらにある。
それでも6時からずーっと脳みそをフル回転させ、あっちこっち歩いて、メモをとると疲れてくる。
ちょっとだけでも座りたくなる。
競り場が一段落ついたとき、宿毛市街に朝ご飯を食べに行く。
与力水産、有田輝一さんおすすめの、『カフェレスト 花時間』という可愛らしい名前の喫茶店である。
名前とは裏腹に店内にいるのはご近所の普通のオバサンとオジサンで、ボクなど実に薄汚いデブなので安心する。
この朝ご飯を喫茶店で、というのは高知県全域での普通である。
愛知県の喫茶店朝ご飯文化は有名だが、ボクの勝手な意見だけれど、高知県の喫茶店朝ご飯文化の方が上だと思っている。
高知県の方がストレートに朝ご飯だからだ。
ちなみに愛知に行ったら逆に思える可能性だってある、ので、ボクはボク自体を信用していない。
コラムの続きを読む

古満目から宿毛市、すくも湾中央市場の競り場に移動する。
ここは昼近くまで水揚げが続く、フライト時間があるので見ることができたのはほんの一部だ。
今回は同定不能という魚はいなかったが、やはり興奮すること多し。
コラムの続きを読む
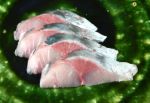
小田原魚市場をひとまわりして、初めて気がつくこともある。
そうだ、秋はオアカムロだ、というのもそのひとつだ。
見渡した限りでは、ボクにちょうどいいクチもの(いろんな魚がばらばらに入っているもの)や2、3尾の箱がない。
せっかく旬を迎えているのに、全体を見渡しても2箱しかない。
最近、オアカムロは引く手あまたの人気、なので決して安くはない。
そこに小田原のすし屋、『海攻』さんが来て、オアカムロ談義になる。
諦めて、別の魚に決めたとき、『海攻』さんが1尾だけ恵んでくれた。
ありがたや、である。
渋滞もなく帰り着いたのが、10時過ぎ。
魚の処理は仮眠後にして、オアカムロだけ下ろして刺身を数切れだけ。
ムロアジ属なので豊かなうま味がある。
上品で淡麗というのとは真逆の野性味溢れるうまさだ。
口の中で暴れると言ってもいい。
しかも脂が皮下に層を作っていて、口溶け感から甘さを感じる。
仮眠前に杯1ぱいだけの新潟市西区内野町「鶴の友 別撰」をなめる。
最近、これくらいでも鎮静効果がのぞめる。
コラムの続きを読む

八王子卸売協同組合、舵丸水産に香川県観音寺産のスズキが来ていた。
重さからすると平均2㎏前後で買いやすいので1本買いする。
以上は前回も書いた。
さて、刺身にして、今度はカルパッチョにする。
皮を引いた身をできるだけ薄く切る。
皿ににんにく、塩、オリーブオイルを敷く。
ここにスズキの身を並べて行く。
上からスプーンでとんとんと叩いて身を調味料と馴染ませる。
上からも軽く振り塩をし、高知県土佐市『白木果樹園』のピンクレモネードをたらす。
タイムと黄色い激辛唐辛子を散らし、ピンクレモネードも散らす。
スズキくらいカルパッチョに向いた魚はないかもしれない。
くせのない白身で身質がいいので多少たたいても食感は残る。
魚らしいうま味が豊かで、ほんのりと甘味がある。
最近、新しい白身魚が大挙して押し寄せているために、影が薄くなったスズキの、味の実力を再確認した。
ここにピンクレモネードのほどよい酸味、甘味が合う。
合わせたのはジンのソーダ割りにピンクレモネードで、ピンクレモネードずくめな夜だった。
コラムの続きを読む

9月27日の朝、水揚げが大方終わったあとに『古満目水主大敷組合』、福見真路さんが隅の方で何かをやっている。
割り箸、竹のヘラ、ラジオペンチでクロホシフエダイの内臓を抜いているのだ。
聞くと「かけのいお」を作っているのだという。
「掛けの魚」のことで、「掛魚」ともいう。
2尾腹合わせにした魚を家内、もしくは建物のどこかに掛けて供物とする。
掛けるのは干した魚であることもあるし、生の魚を掛けることもある。
大皿などに2尾の魚を抱き合わせただけで済ませる地域もある。
農家や、漁家、商家などで行われているが、農家は五穀豊穣、商家は商売繁盛、漁師の場合、豊漁を祈願し、また豊漁の礼として供える。
年内のえびす講、正月、小正月など行われるが、職業で時期は違っている。
古満目では年度替わりの10月に新しいものに替えるのだという。
今回はクロホシフエダイだが魚はなんでもいい。
塩漬けにしてからからに干して「おみきすずり」に掛ける。
「おみきすずり」の「お神酒」はわかるが「すずり」がわからない。
コラムの続きを読む

午前6時半、古満目の入江に入ると、まるで桃源郷のようなところだった。
複雑な地形で水面を見ると多種類のスズメダイ科、ムレハタタテダイ(?)の魚が岸壁に寄って群れている。
古満目漁協が見渡せる場所から漁港を撮影していたら、素直でいい感じの高校生と合う。
家族のために「めじか(マルソウダ)」を釣りに来たのだという。
お家は煙草農家だというが、煙草栽培はとても重労働である。
家業を継ぐのか否かはわからないががんばって欲しいな。
古満目漁港には7時に到着。
コラムの続きを読む
