マガキ、基本のキ2 読むカキフライ
カキフライの誕生は明治初期、以来永延と愛されている


小説など活字となった文章の中の「カキフライ」を見つけてはつけ加えていく。できるだけ時代順に並べる。
まずはカキフライとは?
カキフライが生まれたのは日本だと思っている。海外にカキフライもしくは似た料理があるのかどうかはこれからの課題。
カキフライはカキの剥き身(マガキ)にパン粉をつけて揚げたもののことだ。
同様の料理にはチキンフライ、エビフライ、とんかつ(カツレツ)などがある。
「カキ(マガキ)」はわかるが、「ふらい」は揚げるという意味。
揚げるは、英語で「Fiy」、フランス語で「frire」でここから音をとったと思うべきだろう。
「とんかつ」の「かつ」はコートレット(côtelette)からきているとされている。コートレットは「カツレツ」にも変化する。
なぜか、マガキのフライを「かきかつ」とは言わない。
以上すべてパン粉をつけて揚げるという意味で同じだ。
カキフライを最初に造ったのは、今銀座で健在である『煉瓦亭』だとかの説がある。
『煉瓦亭(明治28年/1895)』は「とんかつ(カツレツ)」発祥の店だとされている。そしてマガキを使った「カキフライ」も、である。
ボクもカキフライは大好きで日本橋周辺で仕事をしていたとき、10月になると高嶋屋裏によく通ったものだ。
ちなみに徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれの田舎者が、カキフライを初めて食べたのは上京してからのことだ。
あまりにもおいしいのでショックを受けた記憶がある。
三田純一の道頓堀、かき船のカキフライ
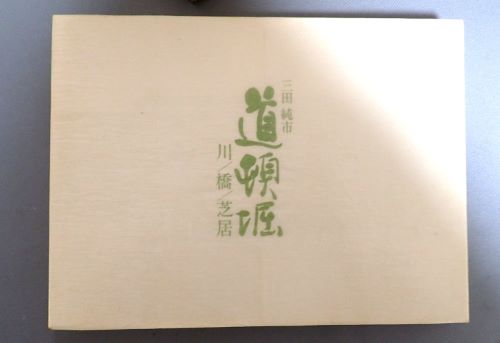
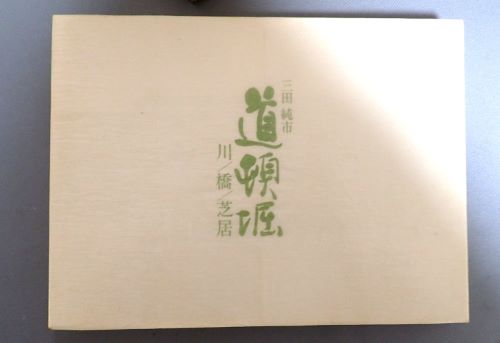
まずは、『道頓堀 -川・橋・芝居』(三田純一 白川書院 1975)
三田純一(1923-1994)は道頓堀にあった芝居茶屋「稲照」で生まれる。演劇の脚本家であり、芸能評論家でもある。
昭和四十年に廃業した「牡蠣料理 かき秀」は道頓堀戎橋南詰にあった「かき船」である。
大坂の「かき船」は宝永元年(1704)にはあったとしている。
広島県産の「かき(マガキ)」を商う店でやがて料理も出すようになる。
三田純一は〈道頓堀名物のかき船〉としているので、道頓堀川にはたくさんの「かき船」があったのだろう。
「牡蠣料理 かき秀」はそんな道頓堀に浮かぶ、「かき船」であった。
定食
つき出し
酢がき
かきフライ
どて鍋
かき御飯 または かき雑炊
立ち退き直前のかき秀のメニュー、これで千円は安い。
以上、道頓堀名物であった「牡蠣料理 かき秀」メニューが書きとめてある。
歴史の古い、「かき船」で実際に食べられていたかき料理は、「どて鍋」は有名だが、ほかのものはわかりにくいため、本書の食文化としての重要性は高い。


