 タイ科だけどクロダイは安い。
タイ科だけどクロダイは安い。今回の東京湾産もポケ、刺身、煮つけ、兜焼き、潮汁、そしてフライにした。
1尾1000円で、骨くらいで何も残らなかったので実に安いと思う。
魚というと刺身、刺身となりそうだけど、意外にトリで登場したフライが上だった。
これは時季ではなく、痩せているクロダイだったせいだ。
ほんの少しだけ、カレー粉を振ったのがよかったかも。
クロダイの場合、パン粉をつけて揚げると、筋繊維の間にジュ(肉汁というべきか)がたまる。
パン粉の香ばしさの内側に豊潤な地帯ができる。
この豊潤さにこそ、天然もののタイ科らしいよさがあると思っている。
ボクはじゃぶじゃぶウスターソース派なのだけど、大衆食堂的な味になってくれたところもうれしい。
半合のご飯を食い切るのにちょうどよかった。
デザートのまんじゅうはなしだけど、満足。
コラムの続きを読む
 2024年8月19日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室産11kgのブリを、もちろん丸ごとではなく、半身を買う。
2024年8月19日、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で北海道根室産11kgのブリを、もちろん丸ごとではなく、半身を買う。ちなみに最近、北海道のブリのほとんどが活ジメである。
外れがない。
刺身にして背の1㎏上を塩蔵する。塩鰤である。
我が家の塩鰤は松本の市場で出合った方達と、市内の魚屋、岐阜県飛騨地方の魚屋で聞いたとおりのやり方である。
本来は浜で作るものだが、最近、松本平や飛騨地方では家庭や魚屋で切り身で作ることが多いという。
大量の塩でまぶし、翌日水が出たら塩を足してまたまぶす。
これを1週間繰り返して、密閉する。
以上は前回、前々回も書いた。
塩ブリはときどき、気がついたように切り取って食べている。
塩の中で回転させて長々と塩蔵にしたので、切り身の芯の部分にまで塩が入っている。
コラムの続きを読む
 さて、未利用魚、未利用魚と騒がしいが、ちゃんとわかっている人いるんだろうか。厳密な意味での未利用魚は存在しないのに未利用魚という言葉が一人歩きしている。ということで、未利用魚の基礎知識を始める。
さて、未利用魚、未利用魚と騒がしいが、ちゃんとわかっている人いるんだろうか。厳密な意味での未利用魚は存在しないのに未利用魚という言葉が一人歩きしている。ということで、未利用魚の基礎知識を始める。当然国内各地で聞取をする必要があるが、例えば漁業者に聞いてもいいが、加工品業者、買受人(大卸・仲卸)、小売業の話も重要であり、消費者も重要だということを忘れている人がいる。むしろいちばん未利用魚がわからないのは行政、そして漁業者かも知れないという現実も知るべきだ。
また最近、未利用魚にマイナー魚を加えるなど、魚価の変動を知らずにいろいろ語る、間違ったことを言うヤカラまでいる。
魚価を知らなければ、未利用魚はわからない。そのためには、日常的に魚を買っていないとダメだが、そんな人間見た事がない。
未利用魚として問題になるダツとは、標準和名のオキザヨリとテンジクダツと、ダツの3種である。とりわけ前2種が深刻である。
国内海域にいるダツ科の魚は、サンマ、ハマダツ、ヒメダツ、ダツ、リュウキュウダツ、タイワンダツ、オキザヨリ、テンジクダツと8種類である。需要が高く水揚げ量の多いサンマ以外はすべての魚が未利用魚である。
ハマダツは本州青森でも見つかっているが、いまだに四国、九州以南に多く、全国的にみてそれほど問題のある存在ではない。ヒメダツ、リュウキュウダツ、タイワンダツも国内では比較的珍しい。
コラムの続きを読む
 6月入っていったい何尾マアジの塩焼きを食べただろう。
6月入っていったい何尾マアジの塩焼きを食べただろう。朝と昼ご飯は米の飯なので、米の飯に合うものを作る。
アジの塩焼きに、酢の物に、みそ汁は、理想に近い、ので、なんどもなんどもこのワンパターンを繰り返している。
中には近所の釣り師が釣り上げた体長34cmという超大アジもいたし、長崎県産もあり、紀伊半島の漁師さんから来た黒っぽいのもあった。
どれもこれもおいしすぎて困ったが、神奈川県二宮沖、体長17cm・90g前後がいちばんおいしかった。
比較するのは下の下だけど、マアジに関しては勉強中である。
例えば同じ相模湾産でも大アジ(マアジ)とは比較したい。
当たり前だけど、比較のために別の産地のものと一緒の日に焼いて食べてみたが、皮が柔らかくて、皮の間から吹き出してきた脂の風味がよくて、と二宮定置に分があった。
おいしいアジの塩焼きはご飯を食べるのを忘れさせる、と思っているが、残ったご飯にみそ汁をかけて食う日々だった。
蛇足になるが、築地場内(現豊洲市場)で仲卸のアジ担当は、目利きだけがなれる特別な存在だと教わっている。
確かに大きな金額が動く、アジの仕入れは特別なのだろう。
アジのよしあしを見て取るのはそれだけに、とても難しい。
たぶんだけど、二宮定置のマアジがずーっとトップとは限らない。
基本的に8月くらいまでが安定期だけど、今年の小田原のアジ、他の産地のアジの味はどうなるんだろう。
コラムの続きを読む
 先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。
先にもマアジでやってみたが、多田鉄之助(1896-1984)の本にあった、「(神奈川県)小田原地方で広く行われている」という「魚玉茶漬」をクロダイでやってみた。くどいようだが、1968年の本なので、1970年前後に始まる情報化の波に、地域本来の食文化が破壊される前である。
郷土料理は急速に失われつつある。
実際、小田原魚市場で「魚玉茶漬」を知っているか、聞いてもだれも知りはしない。
さて、ご飯をチンするところから。
コラムの続きを読む
 ミノカサゴの仲間であるフサカサゴ科を含むカサゴ亜目の旬はとてもわかりにくい。
ミノカサゴの仲間であるフサカサゴ科を含むカサゴ亜目の旬はとてもわかりにくい。ただミノカサゴは海水温の下がる10月になると見た目的にも精彩を欠く。
釣りをやっていたときにも、シロギス釣りの最盛期にくるミノカサゴはとてもうまかったものだ。
卵生なので産卵前の4月くらいから8月いっぱいがいいと思っている。
珍しいものではないが、流通量は少ないのでなかなかいちばんいい時季がわからないでいる。
ただ6月初旬のミノカサゴは抜群においしかった。
小田原の目利きが買い気を見せているわけは触っただけでわかった。
三枚に下ろすと身が盛り上がってくる。
刺身に引くのが楽しい。
皮なし刺身がこんなにうまいとは思わなかった。
脂はあるのかないのか、明確にはわからないけど、味にこくがある。
口の中で、おいしい時間が長い。
野締めなので望めないはずなのに食感が心地よい。
皮に湯をかけた皮霜造りは痩せた晩秋の個体で造っても、それなりにうまいが、今回時季の個体で造ったものは別格のおいしさである。
皮下に層があるのが感じられる。
皮にうま味があるのだけど、脂と混ざるのである。
しみじみ味わっている内に、久しぶりに「高清水」正一合をこえてしまう。
コラムの続きを読む
 昔、江戸川区にいたとき、魚屋でイサキを買うと、水洗いして振り塩をしてもらっていた。イサキは塩焼きというのが当たり前だった。
昔、江戸川区にいたとき、魚屋でイサキを買うと、水洗いして振り塩をしてもらっていた。イサキは塩焼きというのが当たり前だった。初めてイサキの煮つけを食べたのは後々のことで、伊豆半島の民宿でだ。
「いさぎは煮つけで食べた方がうまい」は、島根県美保関、定置網の漁師さんがボクにイサキをくれたときに言った言葉だ。
その朝、美保関の旅館の定食(泊まったわけではない)もイサキの煮つけだった。
塩焼きと煮つけを比べても仕方がないが、煮つけは塩焼き以上に大小あまり関係がない。
そう言えば、和歌山県紀の川市ではイサキとナスと煮合わせていたし、柿を買いに寄った奈良県五條市近くでは冬瓜が添えられていた。
時季の野菜と合わせて煮ると、とても日常そのもの、季節そのものが感じられていい。
煮つけは平凡な料理で、普段、そこに何気なくあるものである。
今回は神奈川県秦野市『じばさんず』で買ったマダケと煮合わせた。
まごうことなき飯の友である。
小イサキは手づかみで食らいつき、それはそれだけで完結する。
ご飯はもっぱら竹の子で食べることとなった。なぜだろう。
小イサキは煮つけると、それ自体が非常にうまい。
身離れがよくいくらでも食らえる。
食べることに集中して、ご飯に目が移らない。
その小イサキのうま味を吸収したマダケでご飯が、とても合う。
マダケには、とれたてをゆでたので非常に柔らかく、えぐ味などまったくない。
マダケの持つ強い甘味と、ちょっとだけ歯を刺激する竹らしい繊維を感じる食感、そしてご飯というのは最強と、もちろん食べているときは思っていた。
二宮沖の小イサキと秦野市の、時季のマダケで、初夏の味、味わっているぞ、という気になるのもいい。
コラムの続きを読む
 もしも真の節約生活をしたければ、水産物を徹底的に使い尽くすのがいちばんいいのではないか?
もしも真の節約生活をしたければ、水産物を徹底的に使い尽くすのがいちばんいいのではないか?水産物は多様に使えて、安いものは安い。
お金があるときは大型で高い魚を徹底的に使い倒す。
ないときは小さな魚を買うといい。
もちろんそのためには流通上の価値観や漁師の待遇改善をはからないとダメだけど、定置網や底曳き網などでとれるものをみな食べることで、節約も出来るし、地球にも優しいのだ。
日本列島で自給できる可能性がいちばん高いのが、米と水産物なのだから。
現状では今回の小アジ(マアジ)などは、ある程度の量が必要だし、大きさを揃えて、いろんな魚の間から選び出さないとダメだ。
そんな労力をかけてもほとんどお金にならない。
結局、魚粉に化けて二次的に人の口に入ることになる。
おいしいのにもったいないこと甚だしい。
さて、お菓子屋さんでもらった紙袋(かんぶくろ)に片栗粉と一緒に放り込んだのをがさがさ揺らし、ぱらぱらと油に落として、二度揚げする。
じゃがいもも一緒くたに放り込んだので、技と言えば最初は低温から中温に、仕上げは高温で揚げただけ。
これを、またまたお菓子屋でもらった別の紙袋に入れて、塩を振って食べ始める。
ここでコショウを振ってもいい。
小アジだけだとなんとなく単調だけど、じゃがいもと一緒だと、まったく飽きが来ない。
午後2時半に食べたのだけど、腹持ちがいいのでまんじゅうに手が伸びなかった。
満足感が高いといってもいいだろう。
紙袋の合わせ目に入った小アジの破片も食べて、凍頂烏龍茶で口の中を洗う。
ちょっとダウンしようか、それとも仕事の続きをしようかな、っと。
コラムの続きを読む

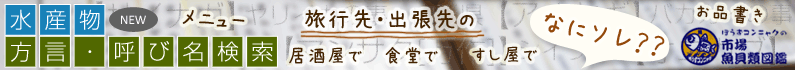

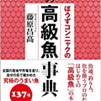 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
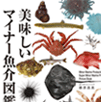
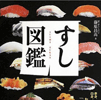
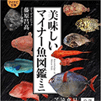
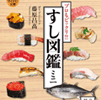

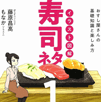 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生
























