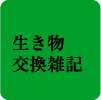 |
||||||||
 |
||||||||
| 自然保護官 相楽 充紀 Mitunori Sagara 1973年東京都向島生まれ |
||||||||
|
私のライフワークは「海辺の自然環境保全と自然環境教育」である。と書くと大仰かもしれないが、要は海の自然が好きなのである。といっても、昔から自然の中で暮らして、海がとっても好きでいつも海で遊んでいた少年時代でした! という風に育ってきたわけでもなく、生まれも育ちも下町向島の都会っ子(江戸っ子)なのである。だから、海の生物と出会えるのは、両親が連れて行ってくれるという特別な出来事であった。私が、ライフワークとしての海と出会うのはずっとずっと先の事である。 進学校に通っていた私は、有名大学に行くことしか頭になく、大学で何をしたいかについては熟考することがなかった。たまたま合格した大学は、地質の学科であった。海の生物に若干関心を持つようになったのは、海産哺乳類研究者神谷敏郎先生(註01)のイルカの講義を聞いてからだった。何となく海の生物は好きであったが、この時におぼろげながら海という方向性が出てきた。 その後、卒業研究で扱ったのがムラサキイガイであった。サンプル採集で網走から舞鶴まで十数か所海岸沿いを訪れた。卒研が海とフィールドが好きになったきっかけであり、この時に各県の水産試験場に色々お話を聞いて、水産試験場がどんなところなのか初めて知った。 大学院では、人と海の繋がりを研究したくて、環境科学研究科に進学し、伊豆半島をフィールドに漁業とダイビングを事例とした沿岸自然環境の利用と管理・保全について研究した。ここで、私のライフワークは何かを大きく掴めた。 就職は、水産を専攻していないにもかかわらず、運良く国家1種試験の水産職に合格し、農水省から内々定をもらった。同時に静岡県も水産職で合格していた。悩んだあげく、私は環境保護の立場からの視点に寄っており、海の自然を捉える場合、海を生業の場としている水産業の最前線の現場をもっと体で覚えなければいけないのではないかと思い、キャリア官僚の道を辞退し、静岡県水産試験場伊豆分場に研究員兼水産業改良普及員として漁業の現場や漁業者と深く付き合うこととなった。当時は正直、キャリア官僚を自ら棒に振ったことについて良かったのかな? 自問自答することも多かったが、今となっては漁業の現場にいたことで得られた経験や人脈が私のかけがえのない財産となっている。 静岡水試では、毎週のように潜水調査をして海藻や磯焼けの研究をし、御前崎周辺の磯焼けの持続原因と考えている藻食性魚類アイゴと格闘した。また海藻の研究を担当するにあたって横濱康継筑波大名誉教授のご指導を受けた。地域の海の自然への関わりとしては、総合学習、生涯学習や修学旅行生に海の環境の話をする機会を積極的に作って行った。。 ところで現在私は、環境省の自然保護官(註02)をしており、沖縄でサンゴ礁保全などの浅海生態系保全の業務をメインに行なっている。2001年に思い立って受験した国家1種試験の造園職にこれまた運良く合格して、環境省のレンジャー職に採用されたためである。 今は水産試験場で得た経験が非常に役立っている。沖縄の海や水産業を勉強するためにオフタイムにはスノーケルに行って写真撮影したり、市場に出かけたり、漁業操業に同行させてもらったりしている。それら調査結果をホームページ琉球・サンゴ礁の生物博物館にまとめている。9月30日〜10月5日(2003年)まで、「WEB博物館が現実世界に飛び出した」をコンセプトに琉球・サンゴ礁の生物博物館主催で「サガラナオミ海藻おしばアート展ー沖縄の海藻と伊豆の海藻ー」(註03)を開催する。個人的にもホームページを軸に色々と活動を展開して行きたい。 現場を志し、一度辞退したはずのキャリア官僚であったが、何の因果か結局その道に戻ってきてしまった。ただし、キャリア官僚になりたいと思ったことは一度もなく、海の自然保護を正面から取り組めるポジションはどこだ?と考えたら、そこに行き着いたというだけのことである。 私はとにかく現場が好きな人間であると改めて実感している。私の想像力が足りないのかもしれないが、イスに座り、机の上の書類や他人が調査したデータに目を通しているだけではあまり頭が働かない。今の職への転職の答えはまだ正解だったのかどうか分からない。ただいろんなポジションで仕事をしたことにより、自分がどういう立場、現場からの距離で仕事することが自らのライフワークを全うしていくのに一番良いということが見え始めてきている。そして今の職が永遠と海の仕事だけ出来るわけでもないことも、現場から必ずしも近くないことも気づいている。 とにかく、社会的地位、収入、出世ではなく、自分の人生を豊かに過ごすために、ライフワークに沿った生き方をしたいだけである。私の人生の軸は海であることは変わりそうもない。 自然を守ってあげて全く触らないという自然保護ではなく、自然と積極的に付き合って持続可能な範囲で最大限自然資源を活用していく自然環境保全の考えで行動して行きたい。自然環境保全は環境に優しいためにやるのではなく、人が快適な人間生活を出来る限り長い間できるために自然を利用していく最も合理的かつ経済的な行動だと考えている。漁業・漁村の現場に身を置いたことで、理想主義的・机上論的な自然保護や環境教育から一歩脱皮し、より地域の生活・文化に近い視点で「海と人の繋がり」について考えられるようになった。 海に関するホームページを開設したことにより、様々な人と交流することが出来た。今後も色々ホームページにアップしていき、引き続き沢山の人たちに海と人との繋がりを伝えていきたいし、色々な人たちと意見を交換していきたい。そして海辺の自然環境保全と自然環境教育について一緒に取り組んで行ける仲間に一人でも多く出会えれば幸せである。 |
|||||||
|
||||||||
| 註01 神谷敏郎 かみや・としろう 鯨類を始めとする海産哺乳類の研究者。94年に講座受講の際、シュライパー著、神谷先生他訳の著書を頂いた。その後、03年にジュゴンの調査で神谷先生が来沖の際、偶然再会することが出来、沖縄そばをすすりながら懇談した 註02 自然保護官 国立公園の管理や野生生物保護に従事する、環境省の職員。通称レンジャーと呼ばれている。採用試験が造園や林学など森林系の分野なので、筆者の様に海洋生物が専門の人間は極めて稀。しかしながら、今後は浅海域の保全が重要な課題となっている 註03 海藻おしば 海藻生理生態学が専門の横濱康継筑波大名誉教授(現志津川町自然環境活用センター所長)とその研究助手であった野田三千代さん(海藻デザイン研究所代表)が考案したもの。筆者が横濱先生から海藻研究の指導を受けている際、妻のサガラナオミが野田三千代さんに海藻おしば作成のお手伝いをしながら作成の指導を受けた。現在、両氏は海藻おしば教室を通じて、海辺の環境について教育活動を行なっている。海藻おしばの参考図書として両氏が共著した、「海藻おしば-カラフルな色彩の謎-」(海游舎)がある |
||||||||
関連コンテンツ
Copyright©2025 Bouz-Konnyaku All Rights Reserved.



 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典






 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



