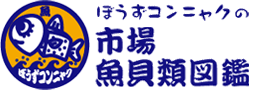コラム検索
検索条件
全22件中 全レコードを表示しています
 静岡県西伊豆で年越しに食べられていた「塩かつお」は、「潮かつお」とも書かれ、11月になると丸のままの姿で塩漬けにし、干し上げたもの。単なる塩蔵品ではなく、干すという工程が入る。もうひとつの、より一般的な「塩かつお」がある。こちらはカツオの半身、もしくは切り身の塩漬け(塩蔵品)である。静岡・関東・東北だけではなく全国で作られていた可能性が高い。聞取をすると関東では日常的なおかずだったようだ。関東、静岡県では「塩かつお(塩がつお)」、宮城県石巻で「かつおのだぶ漬け」、気仙沼で「かつおの塩引き」という。カツオの産地での「塩かつお」の呼び名はもっとたくさんあると考えているので、ご存じの方がいらしたら教えて頂きたい。静岡県西伊豆で年末に作られていた「塩かつお」がハレの加工品だとしたら、カツオの産地で長年作られていた「塩かつお」はケの加工品である。
静岡県西伊豆で年越しに食べられていた「塩かつお」は、「潮かつお」とも書かれ、11月になると丸のままの姿で塩漬けにし、干し上げたもの。単なる塩蔵品ではなく、干すという工程が入る。もうひとつの、より一般的な「塩かつお」がある。こちらはカツオの半身、もしくは切り身の塩漬け(塩蔵品)である。静岡・関東・東北だけではなく全国で作られていた可能性が高い。聞取をすると関東では日常的なおかずだったようだ。関東、静岡県では「塩かつお(塩がつお)」、宮城県石巻で「かつおのだぶ漬け」、気仙沼で「かつおの塩引き」という。カツオの産地での「塩かつお」の呼び名はもっとたくさんあると考えているので、ご存じの方がいらしたら教えて頂きたい。静岡県西伊豆で年末に作られていた「塩かつお」がハレの加工品だとしたら、カツオの産地で長年作られていた「塩かつお」はケの加工品である。 ウナギの旅を続けているとき、ボクの出身県である徳島県小松島の「竹ちくわ」を送って頂いたのはタイムリーだった。この「竹ちくわ」と関西に多い焼き蒲鉾はウナギ料理の歴史を考える上で非常に重要なのだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光)に生まれたので、生まれて初めての都会は徳島市だった。面白いもので、徳島県でももっと西の池田町(現三好市)の老人に聞くと最初の都会は高松だったという。ことの真意はともかく、池田町で食べられていた竹輪など練り製品は「えびちくわ」だったり、普通の穴の開いた竹輪など香川県観音寺あたりのもの。これが徳島本線の池田と徳島の中間地点のボクの町では、どちらかというと小松島市・徳島市・鳴門市で作った「竹ちくわ」、「かつ」、「長天」になる。同じ県の練り製品を考えてもこれだけの違いがある。水産物など食べ物を考えるとき、ぜったいにやってはいけないのが県単位で区切ることだ。家族と一緒に徳島市内にでて、丸新デパートとかつぼみやとかを連れ歩かれて、我慢に我慢を重ねる代わりに買ってもらったのがプラモデルや本だった。それと帰りに必ずねだるのが徳島駅売店の「竹ちくわ」だ。黄緑色の包み紙を持つのはボクの役割だったと思う。この「竹ちくわ」と冷凍ミカン、機関車の煤がボクの徳島本線の最初の想い出だ。横道にそれるが、子供の頃、機関車とディーゼルカーは知っていたけど高知に行って初めて電車に乗ったとき、都会だと感じたものだ。家族のいる東京に行くときの、大阪から東京までの電車では走り回るほど興奮した。電車に都会を感じるのは国内広といえども徳島県人と沖縄県人だけだったと思う。沖縄県にはすでに電車が走っているので、追い越された感が非常に強い。小学校に上がる前後から、「竹ちくわ」はボクの好物だった。たぶんかなり高かったのではないか? だから徳島駅で買うお土産だった。あまりに好きなのでボクだけが2本、3本食べていたっけなー。さて、なぜ竹輪は竹輪なのか? それは細い竹を切り、竹を適当な長さに切る。乾燥させない生の竹に魚肉(最初は主に淡水魚)を握りつけて、直火で焼く。古代には竹についた状態が完成形だったと思う。これが後に焼き上がったら竹から外すようになる。竹につけて焼き、切ると断面が輪なので、竹輪だ。徳島の「竹ちくわ」は焼いて抜かないままだ。たぶんこの国広しといえども、こんな原始的な姿を残した竹輪はないだろう。ちなみに蒲鉾の語源を同じように棒状のものに握りつけて焼く。この形が蒲の穂に似ているから、蒲鉾だとしているが、大間違いだと思っている。これは別項で述べたい。徳島の竹輪はやや甘めである。足(弾力といっても間違いではない)はある方だと思うが、その足が強すぎないのがいい。「竹ちくわ」を食べると、Homeward Bound ♪徳島県の山崎さんには感謝の致しようがない。
ウナギの旅を続けているとき、ボクの出身県である徳島県小松島の「竹ちくわ」を送って頂いたのはタイムリーだった。この「竹ちくわ」と関西に多い焼き蒲鉾はウナギ料理の歴史を考える上で非常に重要なのだ。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町貞光)に生まれたので、生まれて初めての都会は徳島市だった。面白いもので、徳島県でももっと西の池田町(現三好市)の老人に聞くと最初の都会は高松だったという。ことの真意はともかく、池田町で食べられていた竹輪など練り製品は「えびちくわ」だったり、普通の穴の開いた竹輪など香川県観音寺あたりのもの。これが徳島本線の池田と徳島の中間地点のボクの町では、どちらかというと小松島市・徳島市・鳴門市で作った「竹ちくわ」、「かつ」、「長天」になる。同じ県の練り製品を考えてもこれだけの違いがある。水産物など食べ物を考えるとき、ぜったいにやってはいけないのが県単位で区切ることだ。家族と一緒に徳島市内にでて、丸新デパートとかつぼみやとかを連れ歩かれて、我慢に我慢を重ねる代わりに買ってもらったのがプラモデルや本だった。それと帰りに必ずねだるのが徳島駅売店の「竹ちくわ」だ。黄緑色の包み紙を持つのはボクの役割だったと思う。この「竹ちくわ」と冷凍ミカン、機関車の煤がボクの徳島本線の最初の想い出だ。横道にそれるが、子供の頃、機関車とディーゼルカーは知っていたけど高知に行って初めて電車に乗ったとき、都会だと感じたものだ。家族のいる東京に行くときの、大阪から東京までの電車では走り回るほど興奮した。電車に都会を感じるのは国内広といえども徳島県人と沖縄県人だけだったと思う。沖縄県にはすでに電車が走っているので、追い越された感が非常に強い。小学校に上がる前後から、「竹ちくわ」はボクの好物だった。たぶんかなり高かったのではないか? だから徳島駅で買うお土産だった。あまりに好きなのでボクだけが2本、3本食べていたっけなー。さて、なぜ竹輪は竹輪なのか? それは細い竹を切り、竹を適当な長さに切る。乾燥させない生の竹に魚肉(最初は主に淡水魚)を握りつけて、直火で焼く。古代には竹についた状態が完成形だったと思う。これが後に焼き上がったら竹から外すようになる。竹につけて焼き、切ると断面が輪なので、竹輪だ。徳島の「竹ちくわ」は焼いて抜かないままだ。たぶんこの国広しといえども、こんな原始的な姿を残した竹輪はないだろう。ちなみに蒲鉾の語源を同じように棒状のものに握りつけて焼く。この形が蒲の穂に似ているから、蒲鉾だとしているが、大間違いだと思っている。これは別項で述べたい。徳島の竹輪はやや甘めである。足(弾力といっても間違いではない)はある方だと思うが、その足が強すぎないのがいい。「竹ちくわ」を食べると、Homeward Bound ♪徳島県の山崎さんには感謝の致しようがない。 千葉県千葉市のスーパーで、「いわしのごま漬け」ではなく、「さばの胡麻漬」を買った。千葉県山武郡九十九里町、『小川水産』のものだ。九十九里浜の特産品ともいえそうな、「いわし(カタクチイワシ)のごま漬け」は都内でもよく見かけるが、それ以外のものは見かけたことがない。このような主要製品以外のものに出合えるは、千葉県だからだ。20年以上前、九十九里にカタクチイワシの水揚げを見に行ったとき、漁の話だけではなく「ごま漬け」の話もした。そのときもカタクチイワシが不漁であるときは、マアジやサバ類(マサバ・ゴマサバ)の小型を使って作っていたという話を聞いているのだ。ちなみに「いわしのごま漬け」は非常にうまい。昔、魚通を自称していた、高橋治も絶賛していたはず。それほどに間違いなしの名品なのである。
千葉県千葉市のスーパーで、「いわしのごま漬け」ではなく、「さばの胡麻漬」を買った。千葉県山武郡九十九里町、『小川水産』のものだ。九十九里浜の特産品ともいえそうな、「いわし(カタクチイワシ)のごま漬け」は都内でもよく見かけるが、それ以外のものは見かけたことがない。このような主要製品以外のものに出合えるは、千葉県だからだ。20年以上前、九十九里にカタクチイワシの水揚げを見に行ったとき、漁の話だけではなく「ごま漬け」の話もした。そのときもカタクチイワシが不漁であるときは、マアジやサバ類(マサバ・ゴマサバ)の小型を使って作っていたという話を聞いているのだ。ちなみに「いわしのごま漬け」は非常にうまい。昔、魚通を自称していた、高橋治も絶賛していたはず。それほどに間違いなしの名品なのである。 福島県会津地方、南会津町、猪苗代町などのスーパーで「にしん山椒漬」をたっぷり買って来た。会津土産として比較的当たり外れがなく。ボク好みなのでついつい手が出てしまう。江戸時代、身欠きニシンは、北前船が越後(新潟県)の港にもたらし、そのまま越後街道を会津に送られてきていたはずだ。会津にとって身欠きニシンはきっと贅沢な食材だったに違いない。「にしん山椒漬」の本来の作り方は身欠きニシンをざっと水で洗い、腹骨や胸鰭などを取り去り、醤油・酒・みりん、大量の山椒の葉と一緒につけ込んだものだ。当然、漬け込み時期は春ということになる。最近のものは身欠きニシンを、米のとぎ汁(重曹を溶かし込んだ水かな)などでもどしてから漬けるのだと思われる。なぜならば身欠きニシンは、そのままでは渋味と苦味があるからだ。ちなみに個人が作ったという昔ながらの「にしん山椒漬」をいただいたことがあるが、苦味が残り、山椒の辛味があり、醤油辛くて好き嫌いがでる類いのものである。ボクはヨソモノなので、最近の苦味渋味を抜いて漬けた製品の方がすきだ。写真は『会津丸善水産(会津若松市)』のもの。ここに不思議なことが書いてあった。「焼いていただきますと、一層香ばしくお召し上がり頂けます」数年に一度程度食べるものなので毎回、そのまま食べて満足していた。この食べ方は、会津人が日常的に食べている内に、自然と編み出した食べ方に違いない。さて、そのままと、焼いてものを比べてみる。並べて食べて、もう二度と、焼かない「にしん山椒漬」は、食べないと思うほど、焼いた方がうまい。そのまま食べると、噛みしめるほどにニシンのうま味と独特の明らかに酸化した脂がじわじわときて、山椒の風味が適度にその野性味で、渋味を緩和してくれ、ふたたびニシンの味が来て、調味料の味が来てと、口中で「にしん山椒漬」の味が長々と感じられる。そこには、ニシンに塩を添加しないで硬く干して、山国に送られ、山国に人が汗水たらして稼いだ金で購い、山国ならではの若々しい山椒の葉と、発酵食品である酒・みりん・醤油と結婚させた、という大河ドラマ的な展開がある。ただ、食い物にそんなダイナミックなものを感じたいかというと、然にあらず。そんな面倒くさいことは不要である。
福島県会津地方、南会津町、猪苗代町などのスーパーで「にしん山椒漬」をたっぷり買って来た。会津土産として比較的当たり外れがなく。ボク好みなのでついつい手が出てしまう。江戸時代、身欠きニシンは、北前船が越後(新潟県)の港にもたらし、そのまま越後街道を会津に送られてきていたはずだ。会津にとって身欠きニシンはきっと贅沢な食材だったに違いない。「にしん山椒漬」の本来の作り方は身欠きニシンをざっと水で洗い、腹骨や胸鰭などを取り去り、醤油・酒・みりん、大量の山椒の葉と一緒につけ込んだものだ。当然、漬け込み時期は春ということになる。最近のものは身欠きニシンを、米のとぎ汁(重曹を溶かし込んだ水かな)などでもどしてから漬けるのだと思われる。なぜならば身欠きニシンは、そのままでは渋味と苦味があるからだ。ちなみに個人が作ったという昔ながらの「にしん山椒漬」をいただいたことがあるが、苦味が残り、山椒の辛味があり、醤油辛くて好き嫌いがでる類いのものである。ボクはヨソモノなので、最近の苦味渋味を抜いて漬けた製品の方がすきだ。写真は『会津丸善水産(会津若松市)』のもの。ここに不思議なことが書いてあった。「焼いていただきますと、一層香ばしくお召し上がり頂けます」数年に一度程度食べるものなので毎回、そのまま食べて満足していた。この食べ方は、会津人が日常的に食べている内に、自然と編み出した食べ方に違いない。さて、そのままと、焼いてものを比べてみる。並べて食べて、もう二度と、焼かない「にしん山椒漬」は、食べないと思うほど、焼いた方がうまい。そのまま食べると、噛みしめるほどにニシンのうま味と独特の明らかに酸化した脂がじわじわときて、山椒の風味が適度にその野性味で、渋味を緩和してくれ、ふたたびニシンの味が来て、調味料の味が来てと、口中で「にしん山椒漬」の味が長々と感じられる。そこには、ニシンに塩を添加しないで硬く干して、山国に送られ、山国に人が汗水たらして稼いだ金で購い、山国ならではの若々しい山椒の葉と、発酵食品である酒・みりん・醤油と結婚させた、という大河ドラマ的な展開がある。ただ、食い物にそんなダイナミックなものを感じたいかというと、然にあらず。そんな面倒くさいことは不要である。 「かつ(フィッシュカツ)」はどのように食べていたのか、そして食べているのか、という話をしたい。徳島県の山崎さんから津久司蒲鉾の「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ」を送って頂いた。まことにありがとうございました。津久司蒲鉾がある小松島市(こまつしまし)は徳島県というもっともミニマムな県の中で、もっとも早くから市になったところである。ボクが子供の頃は殺伐とした噂もあり、また大阪に向かう船の発着所があった。ボクと小松島市の最初の関わりは曖昧だが、大阪万博のときにここから船に乗ったことだったと思う。模型を買うのも、徳島ホールで映画を見るのも徳島市だったし、祖母が丸新デパートやつぼみや(デパート)に行くのも徳島市だった。徳島市はボクにとってしごく馴染み深いところだが、小松島市は船の発着所のむせるような油と海のにおいの記憶しかない。どことなく東映や日活の映画に出てくる港町のようだった。知名度は低いものの徳島県は練り製品の会社が多いところだ。その多くが、大合併以前から市であった、小松島市と徳島市、鳴門市、阿南市にある。多くの練り製品が大阪と共通するものでしかないが、「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ(フィッシュカツ)」だけは徳島にしかない。ちなみに「かつ」の歴史は最低でも60年以上なので、新しい練り製品とは言えなくなっている。さて、「ちっか」は徳島市に行ったときに買うもので、どりらかというとハレの食べ物、「かつ」はいたって日常的なもので、ケの食べ物だった。値段も「かつ」の方が安かったはずだ。今回、「かつ」をたっぷりいただいたので、懐かしい食べ方をしてみた。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町字町貞光町)は1950年代、60年代、県内でもっとも小さな町だったが、県西部では池田町、脇町とともに長い商店街があった。日本中を回っているとわかることだけど、意外に長い商店街のある町は少ない。もちろん市なら当たり前だけど、町(市町村の)で、しかも小さな徳島県の中でも、もっとも小さな町域しかなかった貞光町に商店街があるのは不思議なことなのだ。我が家は商家だったので朝はとても忙しい。1970年くらいまで、午前5時、6時くらいに山から下りてきた人に戸を叩いて起こされ、売る、なんてこともあった。取り分け忙しいときには行商の菓子パンで済ましたり、冬は七輪が食卓脇にあったので餅を食べて学校に向かったものだ。考えてみると寒い時季、餅と惣菜と紅茶もしくはコーヒー、お茶という朝ご飯は商家ならではのものだろう。この惣菜の中にかなりの確立で「かつ」が登場した。
「かつ(フィッシュカツ)」はどのように食べていたのか、そして食べているのか、という話をしたい。徳島県の山崎さんから津久司蒲鉾の「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ」を送って頂いた。まことにありがとうございました。津久司蒲鉾がある小松島市(こまつしまし)は徳島県というもっともミニマムな県の中で、もっとも早くから市になったところである。ボクが子供の頃は殺伐とした噂もあり、また大阪に向かう船の発着所があった。ボクと小松島市の最初の関わりは曖昧だが、大阪万博のときにここから船に乗ったことだったと思う。模型を買うのも、徳島ホールで映画を見るのも徳島市だったし、祖母が丸新デパートやつぼみや(デパート)に行くのも徳島市だった。徳島市はボクにとってしごく馴染み深いところだが、小松島市は船の発着所のむせるような油と海のにおいの記憶しかない。どことなく東映や日活の映画に出てくる港町のようだった。知名度は低いものの徳島県は練り製品の会社が多いところだ。その多くが、大合併以前から市であった、小松島市と徳島市、鳴門市、阿南市にある。多くの練り製品が大阪と共通するものでしかないが、「ちっか(竹ちくわ)」と「かつ(フィッシュカツ)」だけは徳島にしかない。ちなみに「かつ」の歴史は最低でも60年以上なので、新しい練り製品とは言えなくなっている。さて、「ちっか」は徳島市に行ったときに買うもので、どりらかというとハレの食べ物、「かつ」はいたって日常的なもので、ケの食べ物だった。値段も「かつ」の方が安かったはずだ。今回、「かつ」をたっぷりいただいたので、懐かしい食べ方をしてみた。徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町字町貞光町)は1950年代、60年代、県内でもっとも小さな町だったが、県西部では池田町、脇町とともに長い商店街があった。日本中を回っているとわかることだけど、意外に長い商店街のある町は少ない。もちろん市なら当たり前だけど、町(市町村の)で、しかも小さな徳島県の中でも、もっとも小さな町域しかなかった貞光町に商店街があるのは不思議なことなのだ。我が家は商家だったので朝はとても忙しい。1970年くらいまで、午前5時、6時くらいに山から下りてきた人に戸を叩いて起こされ、売る、なんてこともあった。取り分け忙しいときには行商の菓子パンで済ましたり、冬は七輪が食卓脇にあったので餅を食べて学校に向かったものだ。考えてみると寒い時季、餅と惣菜と紅茶もしくはコーヒー、お茶という朝ご飯は商家ならではのものだろう。この惣菜の中にかなりの確立で「かつ」が登場した。 福島県から山形県の、太平洋側と日本海側のど真ん中を走る尾根に、比較的大きな盆地がぽつんぽつんとある。そのひとつに米沢市はある。伊達家、上杉家と有力大名が藩主となるくらいなので、稔りがよく、戦国時代には重要な拠点であったはずだ。この本州東北地方の真ん中に点在する町の産物は非常に面白い。米沢織があり、食べ物では山菜、コイが有名である。東に三陸、西に越後と水産物も東西から送られて来たに違いない。米沢市には地方公設市場がある。ここにある『かねしめ水産 ケーエスフーズ』で作っているのが「昔ながらのしょっぱい塩がつお」である。東北地方太平洋側ではとれたカツオに塩をして、山間部に送っていた。その終着点のひとつが米沢であったのだと思う。ちなみにこの国では長い間、魚介類を生で山間部に送ることは出来なかった。1925年昭和になり、1950年代高度成長期になってもこの国のコールドチェーン化(生鮮品の保冷しての流通)は進んでいなかった。1960年代になって初めて一般家庭で冷蔵庫が普及し始め、魚介類の水揚げから流通、販売、消費まで通しての保冷・冷凍技術が確立するのは1970年代になってからだという人も少なくない。当然、三陸ではコールドチェーンが確立するまで、カツオは節加工するか、塩蔵して出荷していたのだ。この産地から来ていた「塩かつお」の、塩分濃度が年々下がるとともに、入荷量が減ってきた。そんなとき消費地である米沢で作り始めたのが、この塩分の非常に高い「塩かつお」である。世の中が減塩減塩と騒ぎ、加工品全体の塩分濃度が下がる中、米沢近郊ではまだまだ塩分濃度の強いものが好まれていた。このように本来魚介類の産地で作られていた加工品が作られなくなり、消費地で作られるようになる例は少なくない。
福島県から山形県の、太平洋側と日本海側のど真ん中を走る尾根に、比較的大きな盆地がぽつんぽつんとある。そのひとつに米沢市はある。伊達家、上杉家と有力大名が藩主となるくらいなので、稔りがよく、戦国時代には重要な拠点であったはずだ。この本州東北地方の真ん中に点在する町の産物は非常に面白い。米沢織があり、食べ物では山菜、コイが有名である。東に三陸、西に越後と水産物も東西から送られて来たに違いない。米沢市には地方公設市場がある。ここにある『かねしめ水産 ケーエスフーズ』で作っているのが「昔ながらのしょっぱい塩がつお」である。東北地方太平洋側ではとれたカツオに塩をして、山間部に送っていた。その終着点のひとつが米沢であったのだと思う。ちなみにこの国では長い間、魚介類を生で山間部に送ることは出来なかった。1925年昭和になり、1950年代高度成長期になってもこの国のコールドチェーン化(生鮮品の保冷しての流通)は進んでいなかった。1960年代になって初めて一般家庭で冷蔵庫が普及し始め、魚介類の水揚げから流通、販売、消費まで通しての保冷・冷凍技術が確立するのは1970年代になってからだという人も少なくない。当然、三陸ではコールドチェーンが確立するまで、カツオは節加工するか、塩蔵して出荷していたのだ。この産地から来ていた「塩かつお」の、塩分濃度が年々下がるとともに、入荷量が減ってきた。そんなとき消費地である米沢で作り始めたのが、この塩分の非常に高い「塩かつお」である。世の中が減塩減塩と騒ぎ、加工品全体の塩分濃度が下がる中、米沢近郊ではまだまだ塩分濃度の強いものが好まれていた。このように本来魚介類の産地で作られていた加工品が作られなくなり、消費地で作られるようになる例は少なくない。 八王子綜合卸売センター、福泉でクロマグロの若い個体である、「めじ」を買った。触った限りは脂はないとみたが、非常に美しい個体で思わず手が出てしまった。念のために鰭の確認をして、体のキズのあるなしを見る。鮮度がよく、美しいだけではなく完全無欠に近い。我がデータベースは同じ魚でも繰り返し繰り返し、丸々の状態、すなわち形態画像を取り直している。以上は前回と同じ。宮城県気仙沼や石巻で「かつおのだぶ漬け(カツオのだぶ漬け)」、「カツオの塩引き」と呼ばれ、関東周辺で「塩がつお」、三重県志摩地方・熊野地方で作られている「塩ぎり」と呼ばれているものがある。今や絶滅危惧食品であるが、1970年前後くらいまでは日常的な普通の食品であった。東北太平洋側から静岡県くらいまでのカツオの産地で塩蔵処理されて、東北の山間部、東京都をはじめ、関東、東海、紀伊半島の山間部に送られていた。三重県などで作られていたものは、岐阜県などにも送られていた可能性が高い。この日常的な「塩がつお」を産地で作っていた人、流通させていた人、売っていた魚屋などが寿命を迎えつつあり、記憶が永遠に失われようとしている。誤解が生まれそうなので、述べておくと、近年、西伊豆で師走になると飾られ、年取に食べる「塩がつお」が有名だが、あれは塩漬けにして干し上げたもので、ハレ(正月、年取)の日のために作るもの。一般的に流通していた、今回の「塩がつお」とは別のものである。本コラムは、あくまでも日常的に食べられていた「塩がつお」の話だ。山形県米沢市での聞取でもそうだが、じょじょに海辺でカツオの塩蔵品が作られなくなると、消費地で作られるようになる。またカツオではなく、サバ科のマグロ属やハガツオ属、ソウダガツオ属でも作られ、魚屋の店頭に並び、自家消費されるようになる。中でもマグロ類は都内でも魚屋などで生食できないものや色変わりしたもの、小型のもので作られていたようである。
八王子綜合卸売センター、福泉でクロマグロの若い個体である、「めじ」を買った。触った限りは脂はないとみたが、非常に美しい個体で思わず手が出てしまった。念のために鰭の確認をして、体のキズのあるなしを見る。鮮度がよく、美しいだけではなく完全無欠に近い。我がデータベースは同じ魚でも繰り返し繰り返し、丸々の状態、すなわち形態画像を取り直している。以上は前回と同じ。宮城県気仙沼や石巻で「かつおのだぶ漬け(カツオのだぶ漬け)」、「カツオの塩引き」と呼ばれ、関東周辺で「塩がつお」、三重県志摩地方・熊野地方で作られている「塩ぎり」と呼ばれているものがある。今や絶滅危惧食品であるが、1970年前後くらいまでは日常的な普通の食品であった。東北太平洋側から静岡県くらいまでのカツオの産地で塩蔵処理されて、東北の山間部、東京都をはじめ、関東、東海、紀伊半島の山間部に送られていた。三重県などで作られていたものは、岐阜県などにも送られていた可能性が高い。この日常的な「塩がつお」を産地で作っていた人、流通させていた人、売っていた魚屋などが寿命を迎えつつあり、記憶が永遠に失われようとしている。誤解が生まれそうなので、述べておくと、近年、西伊豆で師走になると飾られ、年取に食べる「塩がつお」が有名だが、あれは塩漬けにして干し上げたもので、ハレ(正月、年取)の日のために作るもの。一般的に流通していた、今回の「塩がつお」とは別のものである。本コラムは、あくまでも日常的に食べられていた「塩がつお」の話だ。山形県米沢市での聞取でもそうだが、じょじょに海辺でカツオの塩蔵品が作られなくなると、消費地で作られるようになる。またカツオではなく、サバ科のマグロ属やハガツオ属、ソウダガツオ属でも作られ、魚屋の店頭に並び、自家消費されるようになる。中でもマグロ類は都内でも魚屋などで生食できないものや色変わりしたもの、小型のもので作られていたようである。 久しぶりに東京都大田市場に行った。『フーディソン 魚ぽち』でいろいろ見せて頂いていたら、販売している加工品の中に、なんと「かつ」があった。徳島県小松島市の『津久司蒲鉾』のものである。今や、「フィッシュカツ」というようだが、どうにも、この、こじゃれた名は馴染めない。カレー風味のついた魚肉にパン粉をつけて揚げたものだ。島根県の「赤てん」、山口県などで作られている「魚ロッケ」、中国地方・愛媛県などの「がんす」、佐賀県の「ミンチころっけ」などなどと作り方の基本は同じである。徳島中央市場関連棟で会った老人は1945年の敗戦後、市場に大量に魚肉ソーセージが流通しだしたために、通常の蒲鉾竹輪が急激に売れなくなった。これに対抗するために作られたのが「かつ」だという。ボクは徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の商店街生まれである。ここに乳母車で朝方、食品を売りに来るオバチャンがいて、我が家で必ず買っていたのが「かつ」なのである。初めて食べたときには幼児で、まだテレビでは「チロリン村とくるみの木」をやっていたはずなので、1960年前後だ。口に入れたら辛くて、泣いた憶えがある。ひりひりをとるために砂糖をなめた。いつの間にか、このカレー味で、ぴりっと辛く、油でべとべとした「かつ」が食べられるようになり、お昼ご飯のおかずによく食べた。こちらも学校から昼ご飯に戻り、テレビ番組「おはなはん」が始まるまでに食べ終わり、昼休みが終わる1時までに学校に急いだ記憶とともに思い出す。さて、久しぶりに食べた『津久司蒲鉾』のフィッシュカツがとてもおいしいのは、懐かしさがプラスされているからかも知れない。ソースも醤油もつけないで、そのまま食べるのが好きだけど、食べ始めると止められない。2パック4枚しか買わなかったことを大いに後悔した。ちなみに徳島県内では、いくつもの蒲鉾店が「フィッシュカツ」を作っている。それほど違いはないが、いろいろ食べ比べてもいいだろう。ここだけの話だが、ちょっとだけ寂しいのは、昔食べた、あのべとべとがなくなり、あっさりと胸焼けしない味に変身していることだ。もう一度だけでいいので、あのべとべとが食べてみたい。
久しぶりに東京都大田市場に行った。『フーディソン 魚ぽち』でいろいろ見せて頂いていたら、販売している加工品の中に、なんと「かつ」があった。徳島県小松島市の『津久司蒲鉾』のものである。今や、「フィッシュカツ」というようだが、どうにも、この、こじゃれた名は馴染めない。カレー風味のついた魚肉にパン粉をつけて揚げたものだ。島根県の「赤てん」、山口県などで作られている「魚ロッケ」、中国地方・愛媛県などの「がんす」、佐賀県の「ミンチころっけ」などなどと作り方の基本は同じである。徳島中央市場関連棟で会った老人は1945年の敗戦後、市場に大量に魚肉ソーセージが流通しだしたために、通常の蒲鉾竹輪が急激に売れなくなった。これに対抗するために作られたのが「かつ」だという。ボクは徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)の商店街生まれである。ここに乳母車で朝方、食品を売りに来るオバチャンがいて、我が家で必ず買っていたのが「かつ」なのである。初めて食べたときには幼児で、まだテレビでは「チロリン村とくるみの木」をやっていたはずなので、1960年前後だ。口に入れたら辛くて、泣いた憶えがある。ひりひりをとるために砂糖をなめた。いつの間にか、このカレー味で、ぴりっと辛く、油でべとべとした「かつ」が食べられるようになり、お昼ご飯のおかずによく食べた。こちらも学校から昼ご飯に戻り、テレビ番組「おはなはん」が始まるまでに食べ終わり、昼休みが終わる1時までに学校に急いだ記憶とともに思い出す。さて、久しぶりに食べた『津久司蒲鉾』のフィッシュカツがとてもおいしいのは、懐かしさがプラスされているからかも知れない。ソースも醤油もつけないで、そのまま食べるのが好きだけど、食べ始めると止められない。2パック4枚しか買わなかったことを大いに後悔した。ちなみに徳島県内では、いくつもの蒲鉾店が「フィッシュカツ」を作っている。それほど違いはないが、いろいろ食べ比べてもいいだろう。ここだけの話だが、ちょっとだけ寂しいのは、昔食べた、あのべとべとがなくなり、あっさりと胸焼けしない味に変身していることだ。もう一度だけでいいので、あのべとべとが食べてみたい。 まだ、整理が出来ていないが市場だけで通じる言語は少なくない。これを集めて、徐々に分類していきたいと思っている。例えば今、「赤魚の粕漬」と呼ばれているものを「たいかす(鯛粕)」という人は少なくない。これはアラスカメヌケとか輸入ものの赤いメバル科の魚の粕漬けである。最初は国産のアコウダイで作っていたもので、アコウダイの粕漬けが縮められて「鯛粕」になる。そのアコウダイがとれなくなり、高騰して使えなくなったので、輸入魚を使うようになる。たぶん、その遙かに昔は本当に鯛(マダイ)で作っていたのかも知れぬ。福井県三国にある『日海水産』の名品、ボイルホタテ(ホタテガイのたぶん稚貝を塩ゆでにしたもの)もそのひとつ。市場の、年寄りの多くが「いたや」という。東京、豊洲市場を歩いていても、いまだに「いたや」という言語が生きているのがわかる。今では「いたや」=イタヤガイではないが、昔は日本海でたくさん揚がったイタヤガイ(鳥取県気高町の貝殻節にうたわれるのはイタヤガイ)をゆでて出荷していたのだと思う。その内、イタヤガイが揚がらなくなり、青森県産のホタテガイに活路を見出す。この『日海水産』のボイルホタテを「いたや」といまだに呼んでいる事実には、昔、信じられないくらいにたくさんのイタヤガイが日本海山陰・北陸などで揚がっていた、その歴史が保存されているのだ。この『日海水産』のボイルホタテのすごいところは、これがないと困るという飲食店が少なくないことだと思う。
まだ、整理が出来ていないが市場だけで通じる言語は少なくない。これを集めて、徐々に分類していきたいと思っている。例えば今、「赤魚の粕漬」と呼ばれているものを「たいかす(鯛粕)」という人は少なくない。これはアラスカメヌケとか輸入ものの赤いメバル科の魚の粕漬けである。最初は国産のアコウダイで作っていたもので、アコウダイの粕漬けが縮められて「鯛粕」になる。そのアコウダイがとれなくなり、高騰して使えなくなったので、輸入魚を使うようになる。たぶん、その遙かに昔は本当に鯛(マダイ)で作っていたのかも知れぬ。福井県三国にある『日海水産』の名品、ボイルホタテ(ホタテガイのたぶん稚貝を塩ゆでにしたもの)もそのひとつ。市場の、年寄りの多くが「いたや」という。東京、豊洲市場を歩いていても、いまだに「いたや」という言語が生きているのがわかる。今では「いたや」=イタヤガイではないが、昔は日本海でたくさん揚がったイタヤガイ(鳥取県気高町の貝殻節にうたわれるのはイタヤガイ)をゆでて出荷していたのだと思う。その内、イタヤガイが揚がらなくなり、青森県産のホタテガイに活路を見出す。この『日海水産』のボイルホタテを「いたや」といまだに呼んでいる事実には、昔、信じられないくらいにたくさんのイタヤガイが日本海山陰・北陸などで揚がっていた、その歴史が保存されているのだ。この『日海水産』のボイルホタテのすごいところは、これがないと困るという飲食店が少なくないことだと思う。 群馬県に行くと必ず買ってくるのが、「やなぎばえの佃煮」である。群馬県板倉町のハスミフーズのものである。古く、町内にはたくさんの淡水魚を扱う問屋(地元の淡水魚を集めてそのまま出荷したり、加工していた)があったが、近年ではハスミフーズをはじめ数軒しか残っていない。「やなぎばえ」という聞き慣れぬ言語を理解するには、国内の淡水小魚の呼び名を考える必要がある。淡水性の小魚の呼び名に「もろこ」とか「はえ」というのがある。特定の魚の呼び名ではなく、様々な魚の呼び名として使われている。その上、この2つの言語はかなり広範囲で使われているようだ。この淡水性小魚の呼び名の整理は非常に難しく、現在のところ五里霧中といった状態にある。ちなみにオイカワを「はえ」という地域があるが、実は食用としてのオイカワとは夏の成魚のことを差すのではなく、冬から春にかけての若い個体というか、未成魚のことだと考えている。とするとこの場合の「はえ」も小さな淡水魚という意味になる。また木曽三川の輪中地帯周辺で「新バエ」は小ブナのことだ。ここでも「はえ」に小さいという意味合いが見いだせる。群馬県板倉町で「やなぎばえ」は本来はタモロコの呼び名だと考えている。「やなぎ」は柳の葉のように細長い体形のことで、「はえ」は先に述べたように淡水の小魚で、まさにタモロコそのものである。ところがここ15年近く群馬県板倉町で「やなぎばえの佃煮」を買うと、タモロコとモツゴが一緒くたになっている。板倉町でモツゴは、「くちほそ(口細)」、「くちぼそ(同)」だ。この群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の渡良瀬川・利根川の水郷地帯では古くは大量にこの淡水の小魚がいて、それをとる人もたくさんいた。そこから考えると、「やなぎばえの佃煮」はタモロコの佃煮で、モツゴはモツゴだけの佃煮があったのかも知れない。同じものが東京都・茨城県古河市・埼玉県加須市・栃木県栃木市などでは「雑魚煮(ざこに、ざっこ煮)」という。余談だが、広い地域で淡水の佃煮(加工食品の正式な名称)を調べていると、佃煮が東京都中央区佃島で生まれたわけではなく、「佃煮」という言葉が生まれたに過ぎないことがわかる。さて、今回のものは国産原料を使っている。板倉町では地元でも漁が行われているが、霞ヶ浦への依存度が高い。原料の正確な産地はわからないが、関東周辺の可能性が高いのは、タモロコに対してモツゴのサイズが非常に小さいことからわかる。最近は淡水小魚が輸入され、また岡山県などから送られてくるが、その場合、比較的原料は大きさが揃っているのである。
群馬県に行くと必ず買ってくるのが、「やなぎばえの佃煮」である。群馬県板倉町のハスミフーズのものである。古く、町内にはたくさんの淡水魚を扱う問屋(地元の淡水魚を集めてそのまま出荷したり、加工していた)があったが、近年ではハスミフーズをはじめ数軒しか残っていない。「やなぎばえ」という聞き慣れぬ言語を理解するには、国内の淡水小魚の呼び名を考える必要がある。淡水性の小魚の呼び名に「もろこ」とか「はえ」というのがある。特定の魚の呼び名ではなく、様々な魚の呼び名として使われている。その上、この2つの言語はかなり広範囲で使われているようだ。この淡水性小魚の呼び名の整理は非常に難しく、現在のところ五里霧中といった状態にある。ちなみにオイカワを「はえ」という地域があるが、実は食用としてのオイカワとは夏の成魚のことを差すのではなく、冬から春にかけての若い個体というか、未成魚のことだと考えている。とするとこの場合の「はえ」も小さな淡水魚という意味になる。また木曽三川の輪中地帯周辺で「新バエ」は小ブナのことだ。ここでも「はえ」に小さいという意味合いが見いだせる。群馬県板倉町で「やなぎばえ」は本来はタモロコの呼び名だと考えている。「やなぎ」は柳の葉のように細長い体形のことで、「はえ」は先に述べたように淡水の小魚で、まさにタモロコそのものである。ところがここ15年近く群馬県板倉町で「やなぎばえの佃煮」を買うと、タモロコとモツゴが一緒くたになっている。板倉町でモツゴは、「くちほそ(口細)」、「くちぼそ(同)」だ。この群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県の渡良瀬川・利根川の水郷地帯では古くは大量にこの淡水の小魚がいて、それをとる人もたくさんいた。そこから考えると、「やなぎばえの佃煮」はタモロコの佃煮で、モツゴはモツゴだけの佃煮があったのかも知れない。同じものが東京都・茨城県古河市・埼玉県加須市・栃木県栃木市などでは「雑魚煮(ざこに、ざっこ煮)」という。余談だが、広い地域で淡水の佃煮(加工食品の正式な名称)を調べていると、佃煮が東京都中央区佃島で生まれたわけではなく、「佃煮」という言葉が生まれたに過ぎないことがわかる。さて、今回のものは国産原料を使っている。板倉町では地元でも漁が行われているが、霞ヶ浦への依存度が高い。原料の正確な産地はわからないが、関東周辺の可能性が高いのは、タモロコに対してモツゴのサイズが非常に小さいことからわかる。最近は淡水小魚が輸入され、また岡山県などから送られてくるが、その場合、比較的原料は大きさが揃っているのである。 コウイカ科のイカの特徴は「貝のような姿の動物」であった名残である、貝殻を体に有していることだ。貝殻は一般的には甲という。甲を持っているイカなので甲烏賊となり、科名(コウイカ科)種名(コウイカ)になっている。山間部に育ったボクに甲は珍しく、子供の頃、魚屋にお使いに行って、甲をもらって、うれしかった想い出がある。生物学者・谷田専治(1908年生まれ)は粉末にして歯磨き粉に用いる、…甲に彫刻して飾りものにする…止淋散と称して墨客に利用されると述べている。止淋散は不明。魚屋の中に乾燥して粉末にして血止めにするという人もいる。鯣(するめ)はイカの開いて干したもののことであるが、比較的大形の食用イカすべてで作られている。スルメイカは国内でたくさんとれ、鯣にもっともよく加工されるために、鯣烏賊と呼ばれるようになった。鯣に加工される主なイカは多い順にスルメイカ、ケンサキイカ、アオリイカのツツイカ類(体がスマートで貝殻がフィルム状)。シリヤケイカ、コウイカ、カミナリイカのコウイカ類である。ツツイカ類の鯣はスーパーなどでもよく売られているので、探せば手に入るが、コウイカ類の鯣を手に入れるのはなかなか難しい。コウイカ(ハリイカ)の干ものは徳島県鳴門市、阿南市で食べているのに、撮影し忘れるという失態をおかしているが、非常にローカルな食材である。そのコウイカ類の干ものに「甲つきするめ」がある。先に述べた谷田専治、軟体類学者・奥谷喬司の著書にあるし、塩乾加工の書籍にもある。長崎県雲仙市の佐藤厚さんはシリヤケイカ、コウイカで実際に作っていたとのことで、味はシリヤケイカの方がいいという。とすると「甲つきするめ」は主にシリヤケイカで作られていたのだろう。これは奥谷喬司がシリヤケイカは東シナ海でたくさんとれていた。「甲付するめ」にも製されていたということと一致する。
コウイカ科のイカの特徴は「貝のような姿の動物」であった名残である、貝殻を体に有していることだ。貝殻は一般的には甲という。甲を持っているイカなので甲烏賊となり、科名(コウイカ科)種名(コウイカ)になっている。山間部に育ったボクに甲は珍しく、子供の頃、魚屋にお使いに行って、甲をもらって、うれしかった想い出がある。生物学者・谷田専治(1908年生まれ)は粉末にして歯磨き粉に用いる、…甲に彫刻して飾りものにする…止淋散と称して墨客に利用されると述べている。止淋散は不明。魚屋の中に乾燥して粉末にして血止めにするという人もいる。鯣(するめ)はイカの開いて干したもののことであるが、比較的大形の食用イカすべてで作られている。スルメイカは国内でたくさんとれ、鯣にもっともよく加工されるために、鯣烏賊と呼ばれるようになった。鯣に加工される主なイカは多い順にスルメイカ、ケンサキイカ、アオリイカのツツイカ類(体がスマートで貝殻がフィルム状)。シリヤケイカ、コウイカ、カミナリイカのコウイカ類である。ツツイカ類の鯣はスーパーなどでもよく売られているので、探せば手に入るが、コウイカ類の鯣を手に入れるのはなかなか難しい。コウイカ(ハリイカ)の干ものは徳島県鳴門市、阿南市で食べているのに、撮影し忘れるという失態をおかしているが、非常にローカルな食材である。そのコウイカ類の干ものに「甲つきするめ」がある。先に述べた谷田専治、軟体類学者・奥谷喬司の著書にあるし、塩乾加工の書籍にもある。長崎県雲仙市の佐藤厚さんはシリヤケイカ、コウイカで実際に作っていたとのことで、味はシリヤケイカの方がいいという。とすると「甲つきするめ」は主にシリヤケイカで作られていたのだろう。これは奥谷喬司がシリヤケイカは東シナ海でたくさんとれていた。「甲付するめ」にも製されていたということと一致する。 多くの文学作品に出てくるのが東京都内、千葉県西部の佃煮である。山本周五郎の『青べか物語』などをみても、庶民にとっての基本的な菜(副菜)だったことがわかる。東京都をはじめ東京湾周辺には無数の海辺漁業(造語です)があった。汽水域ではたくさんの二枚貝が取れ、アミ類、シラタエビ、テナガエビ、スジエビなどに、アマノリ(アサクサノリ)、青のり(ヒトエグサやスジアオノリ)がとれていた。小魚としてはフナにモツゴや小型のハゼ類などもとる。これを江戸時代初期などは塩で煮て軽く干し、やがて醤油が使われるようになり、19世紀になると上等な品にはみりんが使われるようになる。東京湾周辺には汽水域や内湾の小型の水産生物を無駄なく使う食文化が生まれて、今に続いているのだ。この小魚文化の主役的な存在である佃煮屋が急激になくなってきている。佃煮好きとしてはゆゆしき問題だし、汽水域が暮らしの場から、自然保護とか自然観察だけの場になるのもイヤダネーと思う。だから今や貴重な佃煮屋めぐりをしている。台東区上野、下谷から浅草にかけては取り分け佃煮屋の多い地域で、ボクが上京したての頃には無数の佃煮店があったと記憶する。家族が浅草暮らしをしていたので、田原町を中心に念入りに歩き回っているが、佃煮屋は普通の町に溶け込んでいた。それが今や2軒、3軒と数えるほどになっている。今回台東区北上野、『湯葢』で買った佃煮は、あみ、あさり、雑魚佃煮、昆布、おまけのスジエビ(テナガエビ)だ。どれもいい炊き加減で保ちがよい割りにそれだけを食べても、箸が止まらなくなるほど味わい深い。無意味に、この店、22世紀まで残したいと思ったほどだ。
多くの文学作品に出てくるのが東京都内、千葉県西部の佃煮である。山本周五郎の『青べか物語』などをみても、庶民にとっての基本的な菜(副菜)だったことがわかる。東京都をはじめ東京湾周辺には無数の海辺漁業(造語です)があった。汽水域ではたくさんの二枚貝が取れ、アミ類、シラタエビ、テナガエビ、スジエビなどに、アマノリ(アサクサノリ)、青のり(ヒトエグサやスジアオノリ)がとれていた。小魚としてはフナにモツゴや小型のハゼ類などもとる。これを江戸時代初期などは塩で煮て軽く干し、やがて醤油が使われるようになり、19世紀になると上等な品にはみりんが使われるようになる。東京湾周辺には汽水域や内湾の小型の水産生物を無駄なく使う食文化が生まれて、今に続いているのだ。この小魚文化の主役的な存在である佃煮屋が急激になくなってきている。佃煮好きとしてはゆゆしき問題だし、汽水域が暮らしの場から、自然保護とか自然観察だけの場になるのもイヤダネーと思う。だから今や貴重な佃煮屋めぐりをしている。台東区上野、下谷から浅草にかけては取り分け佃煮屋の多い地域で、ボクが上京したての頃には無数の佃煮店があったと記憶する。家族が浅草暮らしをしていたので、田原町を中心に念入りに歩き回っているが、佃煮屋は普通の町に溶け込んでいた。それが今や2軒、3軒と数えるほどになっている。今回台東区北上野、『湯葢』で買った佃煮は、あみ、あさり、雑魚佃煮、昆布、おまけのスジエビ(テナガエビ)だ。どれもいい炊き加減で保ちがよい割りにそれだけを食べても、箸が止まらなくなるほど味わい深い。無意味に、この店、22世紀まで残したいと思ったほどだ。 関東で「ざっこ」、「ざこ」、「小魚」などと呼ばれているものをまとめる。同様のもので「もろこ」、「はや」があるが別項とする。関東で「ざっこ(雑魚)」はコイ目コイ科、十脚目テナガエビ科の淡水生物である。主流はモツゴとタモロコなどの小魚で、ここにスジエビ、テナガエビが混ざる。ともに淡水の比較的ながれのない水路や池(沼)、湖などに多い。例えば流れのあるところにいるウグイやオイカワなどは、関東では「ざっこ」には入らない。関東は平安時代から水田耕作も畑作も発達し、耕作地や住宅地域での土地開発が国内でももっとも進んだ地域である。鎌倉時代、室町時代、江戸時代と関東は政治的な中心地でもあった。ちなみに室町時代、政治の中心は京都にあったかのように見えるが、関東は明らかに独立国家であって、独立した政治が行われていた。時代が進むとともに土地改良が進み、水路や運河が発達する。この膨大に広がった水域である、用水路、水路、運河を住み家とするのがコイ科の小魚とテナガエビ科の小エビである。これをとる漁は今でも関東平野でほそぼそと続けられている。江戸時代の江戸御府内をはじめ関東平野全域に、たくさんの川と沼がある。今でも江戸時代葛飾であった東京都隅田川東岸、群馬県南部の埼玉県・栃木県茨城県にまたがる地域と、霞ヶ浦、北浦、手賀沼、印旛沼などは特に広い水域をもち、ときに水郷とさえ呼ばれている。関東平野は、もともと広大な水域を持っていた上に、より魚を取りやすい場所である水路が発達したために様々な水産加工品、料理が生まれる。江戸時代初期から大川河口域にある佃島で、江戸の猟師町で揚がった小魚類を煮上げて、浅草や日本橋の魚河岸などで商っていた。これで小魚類を醤油で煮たものを「佃煮」と呼ぶようになったとされる。今や「佃煮」は今や水産物を醤油で強く煮つめたものの総称になってさえもいる。ただ、佃島が関東で小魚を煮て食べた発祥の地とは思えない。この小魚を煮た「佃煮」を集めるとわかることだけど、関東平野は現在、「佃煮」と呼ばれる食品のもうひとつの発祥の地である可能性がある。「佃煮」を語るとき枕詞のように佃島が登場するのはいかがなものかと思うがどうだろう。ちなみに茨城県や利根川周辺に「煮干し」と呼ばれるものがある、汽水域、淡水域の生物を塩水で煮て、放冷したものである。こちらの方が歴史は古いと思っている。現在の「佃煮」は江戸初期は江戸府内だけのものだった可能性が高い。関東で醤油が手に入りやすくなった江戸時代中期以降に醤油味の煮物である「佃煮」が本当の意味で誕生したのだと思っている。さて、江戸(汽水域)を中心にした醤油味で小魚を煮たものと、関東平野のもの(汽水域と純淡水域)は歴史的にも原材料的にも入り混ざっていることも述べておかねばならない。
関東で「ざっこ」、「ざこ」、「小魚」などと呼ばれているものをまとめる。同様のもので「もろこ」、「はや」があるが別項とする。関東で「ざっこ(雑魚)」はコイ目コイ科、十脚目テナガエビ科の淡水生物である。主流はモツゴとタモロコなどの小魚で、ここにスジエビ、テナガエビが混ざる。ともに淡水の比較的ながれのない水路や池(沼)、湖などに多い。例えば流れのあるところにいるウグイやオイカワなどは、関東では「ざっこ」には入らない。関東は平安時代から水田耕作も畑作も発達し、耕作地や住宅地域での土地開発が国内でももっとも進んだ地域である。鎌倉時代、室町時代、江戸時代と関東は政治的な中心地でもあった。ちなみに室町時代、政治の中心は京都にあったかのように見えるが、関東は明らかに独立国家であって、独立した政治が行われていた。時代が進むとともに土地改良が進み、水路や運河が発達する。この膨大に広がった水域である、用水路、水路、運河を住み家とするのがコイ科の小魚とテナガエビ科の小エビである。これをとる漁は今でも関東平野でほそぼそと続けられている。江戸時代の江戸御府内をはじめ関東平野全域に、たくさんの川と沼がある。今でも江戸時代葛飾であった東京都隅田川東岸、群馬県南部の埼玉県・栃木県茨城県にまたがる地域と、霞ヶ浦、北浦、手賀沼、印旛沼などは特に広い水域をもち、ときに水郷とさえ呼ばれている。関東平野は、もともと広大な水域を持っていた上に、より魚を取りやすい場所である水路が発達したために様々な水産加工品、料理が生まれる。江戸時代初期から大川河口域にある佃島で、江戸の猟師町で揚がった小魚類を煮上げて、浅草や日本橋の魚河岸などで商っていた。これで小魚類を醤油で煮たものを「佃煮」と呼ぶようになったとされる。今や「佃煮」は今や水産物を醤油で強く煮つめたものの総称になってさえもいる。ただ、佃島が関東で小魚を煮て食べた発祥の地とは思えない。この小魚を煮た「佃煮」を集めるとわかることだけど、関東平野は現在、「佃煮」と呼ばれる食品のもうひとつの発祥の地である可能性がある。「佃煮」を語るとき枕詞のように佃島が登場するのはいかがなものかと思うがどうだろう。ちなみに茨城県や利根川周辺に「煮干し」と呼ばれるものがある、汽水域、淡水域の生物を塩水で煮て、放冷したものである。こちらの方が歴史は古いと思っている。現在の「佃煮」は江戸初期は江戸府内だけのものだった可能性が高い。関東で醤油が手に入りやすくなった江戸時代中期以降に醤油味の煮物である「佃煮」が本当の意味で誕生したのだと思っている。さて、江戸(汽水域)を中心にした醤油味で小魚を煮たものと、関東平野のもの(汽水域と純淡水域)は歴史的にも原材料的にも入り混ざっていることも述べておかねばならない。 今回の知床羅臼旅は脳みそが忙しすぎて、大好きなスーパーにもあまり寄れなかった。唯一、立ち寄ったのが『ビックマートみたに』という斜里町の地元系スーパーである。ここが素晴らしいというか大当たりだった。いろんなものを買い込んで送ってもらった。中に網走市にある『大谷蒲鉾店』の練り製品がある。北海道の練り製品、特に蒲鉾の特徴は足(弾力というか嚙むときこきこする感じ)がないということだ。小田原が始めた、「足こそ命」とは真逆である。個人的には足のある小田原型も、ない北海道型もともに好きで、優劣つけがたしといったところである。今どきの薄汚いアルファベット言語は使いたくはないので使わないが、本当は足がない方が自然には優しい。ついでにいうと北海道、特に知床半島というスケトウダラの産地近くに練り製品の企業がある、というのは非常にいいことだ。漁業には製造業というバックヤードが必要不可欠なのだ。時々、地方自治体の水産課や農水省の話で問題だなと思うのは、日本という国は超アホなので超縦割り行政で「水産系の製造業=農水省の管轄」ではないのである。閑話休題。北海道の練り製品のもうひとつの特徴は甘いということだ。これなど一部、九州の練り製品にも通じる。関西系の四国や中国地方が甘さ控えめなのとは違い、どす甘いのである。ちなみに甘いもんが大好きなので、北海道の練り製品はボク好みだ。
今回の知床羅臼旅は脳みそが忙しすぎて、大好きなスーパーにもあまり寄れなかった。唯一、立ち寄ったのが『ビックマートみたに』という斜里町の地元系スーパーである。ここが素晴らしいというか大当たりだった。いろんなものを買い込んで送ってもらった。中に網走市にある『大谷蒲鉾店』の練り製品がある。北海道の練り製品、特に蒲鉾の特徴は足(弾力というか嚙むときこきこする感じ)がないということだ。小田原が始めた、「足こそ命」とは真逆である。個人的には足のある小田原型も、ない北海道型もともに好きで、優劣つけがたしといったところである。今どきの薄汚いアルファベット言語は使いたくはないので使わないが、本当は足がない方が自然には優しい。ついでにいうと北海道、特に知床半島というスケトウダラの産地近くに練り製品の企業がある、というのは非常にいいことだ。漁業には製造業というバックヤードが必要不可欠なのだ。時々、地方自治体の水産課や農水省の話で問題だなと思うのは、日本という国は超アホなので超縦割り行政で「水産系の製造業=農水省の管轄」ではないのである。閑話休題。北海道の練り製品のもうひとつの特徴は甘いということだ。これなど一部、九州の練り製品にも通じる。関西系の四国や中国地方が甘さ控えめなのとは違い、どす甘いのである。ちなみに甘いもんが大好きなので、北海道の練り製品はボク好みだ。 八王子総合卸売協同組合、マル幸で北海道斜里町『丸中しれとこ食品』のアブラガレイの生食用フィレを買う。アブラガレイは北太平洋に生息する大型のカレイである。古くは北洋で大量にとれて、非常に安く市場に流れていた。安いので鮮度管理が行き届かないなどがあり、まずいカレイと思い込まれていた時期がある。岩手県での呼び名、「えんきり(縁切)」などは、一度食べたら二度と食べたくない、縁を切りたい魚という意味である。鮮度が悪い上に、昔は脂がのった魚は下級だったこともある。
八王子総合卸売協同組合、マル幸で北海道斜里町『丸中しれとこ食品』のアブラガレイの生食用フィレを買う。アブラガレイは北太平洋に生息する大型のカレイである。古くは北洋で大量にとれて、非常に安く市場に流れていた。安いので鮮度管理が行き届かないなどがあり、まずいカレイと思い込まれていた時期がある。岩手県での呼び名、「えんきり(縁切)」などは、一度食べたら二度と食べたくない、縁を切りたい魚という意味である。鮮度が悪い上に、昔は脂がのった魚は下級だったこともある。 三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに乾めかぶを送っていただいた。めかぶはワカメの根元にある成熟した胞子葉でここから胞子を放出する。ちなみに陸生植物は体の先端部分が成長点だが、海藻は根元が生長する。もっとも新しいみずみずしい部分でフコイダンなどが豊富に含まれている。食物繊維が豊富で胃腸などをきれいに掃き清めてくれて、体をすっきりさせてくれる。きっとリカさんはボクがデブなのを気遣って送ってくれたのだと思う。
三重県鳥羽市安楽島、出間リカさんに乾めかぶを送っていただいた。めかぶはワカメの根元にある成熟した胞子葉でここから胞子を放出する。ちなみに陸生植物は体の先端部分が成長点だが、海藻は根元が生長する。もっとも新しいみずみずしい部分でフコイダンなどが豊富に含まれている。食物繊維が豊富で胃腸などをきれいに掃き清めてくれて、体をすっきりさせてくれる。きっとリカさんはボクがデブなのを気遣って送ってくれたのだと思う。 東京都、豊洲場内、『鈴千代』でバカガイの干ものを買った。見つけたら手に取らずにはいられない、好きすぎてもだえくるしむ的な干ものである。年年高くなるのは、干ものにするほど大型のバカガイがとれなくなっているせいだろう。それでも財布の紐が緩む、緩む。バカガイは九州本島以北の干潟などに普通に見られる二枚貝だ。あまりにも愚かな行政や政治家が干潟や内湾の破壊に破壊をやりつくしているが、それでもけなげにも生き残り、ボクに口福感をくれたりする。バカガイとアサリ、ハマグリなどとの違いは階級(科)だけではなく、輸送に耐える力のありなしでもある。バカガイは潮干狩りをしたことがある方ならわかると思うが、ひ弱なのだ。だから市場で普通に見られるのは剥き身や、「はたき(塩ゆで)」なのだ。新川・小名木川で千葉県から日本橋に運んでいた昭和初期以前も、たぶんバカガイは剥き身、「はたき(塩ゆで)」が原則だったのだと思っている。同じ理由から乾物、すなわち干ものが作られた。かなり強めに干したもので保存性の高いものでもある。四十物は古くから流通の主流だった。今でも江戸前、内房、愛知県、三重県、愛媛県や九州北部でバカガイの干ものは作られている。年年小さくなっている気がするが、それでも魅力的、未来永劫残しておきたい加工品だ。
東京都、豊洲場内、『鈴千代』でバカガイの干ものを買った。見つけたら手に取らずにはいられない、好きすぎてもだえくるしむ的な干ものである。年年高くなるのは、干ものにするほど大型のバカガイがとれなくなっているせいだろう。それでも財布の紐が緩む、緩む。バカガイは九州本島以北の干潟などに普通に見られる二枚貝だ。あまりにも愚かな行政や政治家が干潟や内湾の破壊に破壊をやりつくしているが、それでもけなげにも生き残り、ボクに口福感をくれたりする。バカガイとアサリ、ハマグリなどとの違いは階級(科)だけではなく、輸送に耐える力のありなしでもある。バカガイは潮干狩りをしたことがある方ならわかると思うが、ひ弱なのだ。だから市場で普通に見られるのは剥き身や、「はたき(塩ゆで)」なのだ。新川・小名木川で千葉県から日本橋に運んでいた昭和初期以前も、たぶんバカガイは剥き身、「はたき(塩ゆで)」が原則だったのだと思っている。同じ理由から乾物、すなわち干ものが作られた。かなり強めに干したもので保存性の高いものでもある。四十物は古くから流通の主流だった。今でも江戸前、内房、愛知県、三重県、愛媛県や九州北部でバカガイの干ものは作られている。年年小さくなっている気がするが、それでも魅力的、未来永劫残しておきたい加工品だ。 兵庫県香美町香住、『丸松西上商店』のマアナゴの開き干しをいただいた。古くマアナゴの産地は東京湾、三河湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、北部九州などであった。江戸時代江戸で、天ぷらやすしの主な種となったのも、江戸湾(東京湾)で大量に水揚げされていたからである。その後、東京湾ではあまりとれなくなり、常磐茨城県産や三河湾産が目立ってきた。そこに宮城県産が加わる。近年では山陰、島根産が増えた。今、岩手県産が来て、とうとう北海道産が登場し始めている。産地が徐々に北上してきているのだ。3月の但馬旅まで兵庫県日本海側でマアナゴがたくさん水揚げされていることを知らなかった。新しい産地は水揚げ後の処理に苦しむのだけど、香住ではすでにサイズ分けされており、出荷体制も整っているようである。その内、都内市場で但馬産を見ることになりそうである。さて、今回の開き干しは但馬地方、香住漁港などに揚がったものを使って作られている。皮のヌメリをていねいに磨き落とし、強く干し上げられたもので塩分濃度は低めだ。強く干す利点はそれだけうま味が凝縮されていることと、一般家庭でも焼きやすいことである。
兵庫県香美町香住、『丸松西上商店』のマアナゴの開き干しをいただいた。古くマアナゴの産地は東京湾、三河湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、北部九州などであった。江戸時代江戸で、天ぷらやすしの主な種となったのも、江戸湾(東京湾)で大量に水揚げされていたからである。その後、東京湾ではあまりとれなくなり、常磐茨城県産や三河湾産が目立ってきた。そこに宮城県産が加わる。近年では山陰、島根産が増えた。今、岩手県産が来て、とうとう北海道産が登場し始めている。産地が徐々に北上してきているのだ。3月の但馬旅まで兵庫県日本海側でマアナゴがたくさん水揚げされていることを知らなかった。新しい産地は水揚げ後の処理に苦しむのだけど、香住ではすでにサイズ分けされており、出荷体制も整っているようである。その内、都内市場で但馬産を見ることになりそうである。さて、今回の開き干しは但馬地方、香住漁港などに揚がったものを使って作られている。皮のヌメリをていねいに磨き落とし、強く干し上げられたもので塩分濃度は低めだ。強く干す利点はそれだけうま味が凝縮されていることと、一般家庭でも焼きやすいことである。 脂ののったマサバを背開きにして塩漬けにしたものを「刺鯖(差鯖)」といった。要は塩蔵サバであるが、2尾一組で売り買いされ、1尾の頭部にもう1尾の頭部を刺し込んで1対にしたところから「刺鯖」と呼ばれるようになる。平安時代以前からのもので、細々とではあるが日本海の福井と鳥取に今に続いている。日本海では、5、6月(旧暦の初夏)の晩春から初夏に脂がのった大型の大量にとれた。今、多獲性魚としてのマサバの産地は太平洋が主だが、昔は日本海でも大量にマサバが揚がっていたのだ。これを浜で背開きにし、塩に漬け込む。この塩分濃度の高い塩漬けマサバは土用(太陽暦の7月半ばから8月半ばくらい)の頃に食べ頃になり、各地に行商(売り)に行く、もしくは近畿から中国地方に流通していた。歳時記では初秋である。北陸から山陰にかけて春に大型の脂ののったマサバが大量に揚がっていたときは、これを貨車に積んで日本各地に送っていたほどである。また第二次世界大戦後の1950年前後まで人が背負い、歩行と鉄道を使い山陽、近畿地方に運んでいた。日本海から山間部、京都、関西、瀬戸内海周辺へのマサバの道を、「鯖街道」といった。日本海はマサバの大産地だったのだ。京都などの「さばの棒ずし」のサバは昔は若狭から来ていたことでも有名である。この日本海のマサバが急激にとれなくなり現在に至っている。鳥取県の「刺サバ」の原料は今やタイセイヨウサバとなっている。「刺鯖」は夏の贈答品としても使われていた。江戸時代に上物は大名や将軍家などの献上品ともなっていたのだ。井原西鶴の『日本永代蔵 巻三の五』(貞享五年/1688)に没落してしまった大商人のことを表現するに〈……盆のさし鯖・正月の鏡餅も見た事なくて、……〉がある。要するに正月の鏡餅と同じくらいに、お盆には当たり前のものであったのである。『本朝食鑑』(人見必大 島田勇雄注釈 東洋文庫 平凡社 元禄10年/1697)には詳しい説明がある。〈鯖/(鯖の)しおづけ(漢字なし)にしたものを、刺鯖(さしさば)という。気味は生よりも勝れている。それで上下とも刺鯖を賞味している。近時、七月一五日には生荷葉(ハスの葉)で強飯を包んで膳に盛る。また生荷葉で刺鯖をくるんでこれに添える〉、〈(刺鯖は)昔はこれを神祇の供としたことが延喜式に記載されている、能登・伊予・土佐・讃岐・周防などの国が多く貢献した〉、〈1つの頭をもう一つの頭の鰓の間に刺し入れ、二つを相連ねて一重にし、これを一刺(ひとさし)という。当今漁市で販売しているのがこれである〉などなど。〈さしさば 塩さば二ひきを組んだものをいい、背開きのさばの塩乾もので、一ぴきのサバの頭にもう一ぴきのさばの頭を突きさして売っている。お精霊(しょらい)さんが家にいる間は生臭いものを食べてはならないのだが、両親のいる者だけは、さしさばをお膳にすえてもらえる〉。『聞き書 奈良の食事 奈良盆地の食』(農文協)からすると、奈良県でも刺鯖を旧暦のお盆に食べていた。長年、奈良県なので、古くから奈良盆地への魚の供給地であった熊野灘産のマサバと考えていたが、猛暑の初秋に食べるものだとすると日本海の町から売りに来ていたのかも知れない。今や「刺鯖」を作る業者は少なく、当方が確認できたのは福井県と鳥取県の2軒だけである。写真は加藤水産(福井県福井市鮎川町)の国産マサバを使い頭部に頭部を刺し込んだ伝統的な「刺鯖」。
脂ののったマサバを背開きにして塩漬けにしたものを「刺鯖(差鯖)」といった。要は塩蔵サバであるが、2尾一組で売り買いされ、1尾の頭部にもう1尾の頭部を刺し込んで1対にしたところから「刺鯖」と呼ばれるようになる。平安時代以前からのもので、細々とではあるが日本海の福井と鳥取に今に続いている。日本海では、5、6月(旧暦の初夏)の晩春から初夏に脂がのった大型の大量にとれた。今、多獲性魚としてのマサバの産地は太平洋が主だが、昔は日本海でも大量にマサバが揚がっていたのだ。これを浜で背開きにし、塩に漬け込む。この塩分濃度の高い塩漬けマサバは土用(太陽暦の7月半ばから8月半ばくらい)の頃に食べ頃になり、各地に行商(売り)に行く、もしくは近畿から中国地方に流通していた。歳時記では初秋である。北陸から山陰にかけて春に大型の脂ののったマサバが大量に揚がっていたときは、これを貨車に積んで日本各地に送っていたほどである。また第二次世界大戦後の1950年前後まで人が背負い、歩行と鉄道を使い山陽、近畿地方に運んでいた。日本海から山間部、京都、関西、瀬戸内海周辺へのマサバの道を、「鯖街道」といった。日本海はマサバの大産地だったのだ。京都などの「さばの棒ずし」のサバは昔は若狭から来ていたことでも有名である。この日本海のマサバが急激にとれなくなり現在に至っている。鳥取県の「刺サバ」の原料は今やタイセイヨウサバとなっている。「刺鯖」は夏の贈答品としても使われていた。江戸時代に上物は大名や将軍家などの献上品ともなっていたのだ。井原西鶴の『日本永代蔵 巻三の五』(貞享五年/1688)に没落してしまった大商人のことを表現するに〈……盆のさし鯖・正月の鏡餅も見た事なくて、……〉がある。要するに正月の鏡餅と同じくらいに、お盆には当たり前のものであったのである。『本朝食鑑』(人見必大 島田勇雄注釈 東洋文庫 平凡社 元禄10年/1697)には詳しい説明がある。〈鯖/(鯖の)しおづけ(漢字なし)にしたものを、刺鯖(さしさば)という。気味は生よりも勝れている。それで上下とも刺鯖を賞味している。近時、七月一五日には生荷葉(ハスの葉)で強飯を包んで膳に盛る。また生荷葉で刺鯖をくるんでこれに添える〉、〈(刺鯖は)昔はこれを神祇の供としたことが延喜式に記載されている、能登・伊予・土佐・讃岐・周防などの国が多く貢献した〉、〈1つの頭をもう一つの頭の鰓の間に刺し入れ、二つを相連ねて一重にし、これを一刺(ひとさし)という。当今漁市で販売しているのがこれである〉などなど。〈さしさば 塩さば二ひきを組んだものをいい、背開きのさばの塩乾もので、一ぴきのサバの頭にもう一ぴきのさばの頭を突きさして売っている。お精霊(しょらい)さんが家にいる間は生臭いものを食べてはならないのだが、両親のいる者だけは、さしさばをお膳にすえてもらえる〉。『聞き書 奈良の食事 奈良盆地の食』(農文協)からすると、奈良県でも刺鯖を旧暦のお盆に食べていた。長年、奈良県なので、古くから奈良盆地への魚の供給地であった熊野灘産のマサバと考えていたが、猛暑の初秋に食べるものだとすると日本海の町から売りに来ていたのかも知れない。今や「刺鯖」を作る業者は少なく、当方が確認できたのは福井県と鳥取県の2軒だけである。写真は加藤水産(福井県福井市鮎川町)の国産マサバを使い頭部に頭部を刺し込んだ伝統的な「刺鯖」。 魚類の塩蔵品に米ぬかを使った、「糠漬(ぬかづけ)」がある。これには2種類あり、新潟県から鳥取県の日本海と千葉県以北の太平洋側のものはまったくの別物である。日本海のものは製造に最低でも数ヶ月かかり、熟成して独特の風味があり、非常に塩分濃度が濃い。太平洋側のものは取れてすぐに糠と塩をまぶしただけのもので、糠の風味があるものの弱く、塩分濃度も低い。「へしこ」はサバ類とその卵巣、マイワシ、フグ(主にゴマフグ)、ゴマフグの卵巣、イカ(スルメイカ)が原料である。新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、滋賀県、兵庫県、鳥取県で作られ、販売されている。「へしこ」の語源は魚を漬け込んだときの液「ひしお」がなまった、福井県の方言「へし込む」、すなわち押す、から来ている、などの説がある。マイワシの糠漬は新潟県から鳥取県まで見られ、「へしこいわし」、「いわしへしこ」、「いわし糠漬(ぬかづけ)」、「糠いわし」、富山県では「こんかいわし」ともいう。サバ類の糠漬は今のところ、石川県、福井県、京都府、滋賀県、兵庫県、鳥取県で見つけているものの、能登半島以東の新潟県、富山県では見つけていない。サバの糠漬の分布に関してはまだわからないことが多いものの、能登半島以西の水産加工品ではないかと考えている。「さばへしこ」、「さば糠漬」という地域が多いが、石川県では「こんかさば(こんか漬)」とも言う。能登半島では糠のことを「こんか」というためだ。参考文献/『干もの塩もの』(石黒正吉 毎日新聞社 1975)、『全国水産加工品総覧』(福田裕、山澤正勝、岡崎恵美子監修 光琳)、『聞き書 兵庫の食事』(農文協)
魚類の塩蔵品に米ぬかを使った、「糠漬(ぬかづけ)」がある。これには2種類あり、新潟県から鳥取県の日本海と千葉県以北の太平洋側のものはまったくの別物である。日本海のものは製造に最低でも数ヶ月かかり、熟成して独特の風味があり、非常に塩分濃度が濃い。太平洋側のものは取れてすぐに糠と塩をまぶしただけのもので、糠の風味があるものの弱く、塩分濃度も低い。「へしこ」はサバ類とその卵巣、マイワシ、フグ(主にゴマフグ)、ゴマフグの卵巣、イカ(スルメイカ)が原料である。新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、滋賀県、兵庫県、鳥取県で作られ、販売されている。「へしこ」の語源は魚を漬け込んだときの液「ひしお」がなまった、福井県の方言「へし込む」、すなわち押す、から来ている、などの説がある。マイワシの糠漬は新潟県から鳥取県まで見られ、「へしこいわし」、「いわしへしこ」、「いわし糠漬(ぬかづけ)」、「糠いわし」、富山県では「こんかいわし」ともいう。サバ類の糠漬は今のところ、石川県、福井県、京都府、滋賀県、兵庫県、鳥取県で見つけているものの、能登半島以東の新潟県、富山県では見つけていない。サバの糠漬の分布に関してはまだわからないことが多いものの、能登半島以西の水産加工品ではないかと考えている。「さばへしこ」、「さば糠漬」という地域が多いが、石川県では「こんかさば(こんか漬)」とも言う。能登半島では糠のことを「こんか」というためだ。参考文献/『干もの塩もの』(石黒正吉 毎日新聞社 1975)、『全国水産加工品総覧』(福田裕、山澤正勝、岡崎恵美子監修 光琳)、『聞き書 兵庫の食事』(農文協) 漁業の町は漁師さんが魚をとる。当たり前だけどそれが核になるが、ただこれだけでは町は成り立たない。漁獲したもので鮮魚で出荷できるものは出荷する。それ以上に加工しないとダメなものを最適な方法で加工する。カマス類は九州から北海道まで、日本各地で漁獲され、量的にも多く重要なものとなっている。沿岸域で産卵するので稚魚から漁獲されている。稚魚はシラス漁に混ざると、多くが廃棄される。ただこれは産地での努力で出荷はできる。問題は鮮魚でも出荷できず、干ものなどにも加工できないサイズである。四国や九州ではこれを煮干しにする。やや強めの塩水で煮て放冷して干し上げたもの。この塩水で煮て放冷、干し上げて保存するというのは日本全国で行われていたのだと思う。ただこの煮干しの多様性がなくなりつつある。この煮干し加工のあるなしは、漁業の町を構築する上でも重要なポイントだと思う。
漁業の町は漁師さんが魚をとる。当たり前だけどそれが核になるが、ただこれだけでは町は成り立たない。漁獲したもので鮮魚で出荷できるものは出荷する。それ以上に加工しないとダメなものを最適な方法で加工する。カマス類は九州から北海道まで、日本各地で漁獲され、量的にも多く重要なものとなっている。沿岸域で産卵するので稚魚から漁獲されている。稚魚はシラス漁に混ざると、多くが廃棄される。ただこれは産地での努力で出荷はできる。問題は鮮魚でも出荷できず、干ものなどにも加工できないサイズである。四国や九州ではこれを煮干しにする。やや強めの塩水で煮て放冷して干し上げたもの。この塩水で煮て放冷、干し上げて保存するというのは日本全国で行われていたのだと思う。ただこの煮干しの多様性がなくなりつつある。この煮干し加工のあるなしは、漁業の町を構築する上でも重要なポイントだと思う。 静岡県伊豆半島西岸、カツオ漁の基地であった田子、安良里で、盛んに作られていたのが「潮かつお」だ。カツオの内臓を取り、丸ごとを塩漬けにして寝かせ、干し上げたもので、保存性がただの塩蔵品よりも高い。秋に塩につけ込んで干し、暮れには出来上がるのだが、生ハムのように独特の風味が生まれ、ものによってはスライスして生でも食べられる。西伊豆ではこれを正月飾りに使う。西伊豆から沼津周辺までの地域ではハレの日に食べるもので、年取・正月魚の代表的なものであった。塩蔵して干すという工程があり、明らかに冬の保存食の意味合いがあったものと考えられる。この干しの工程のあるものとは別により手軽に作れる「塩がつお」もある。浜に揚がったカツオ(サバ科のソウダガツオ類やハガツオなどでも作られている)、もしくは比較的近くの都市部に送られていた。干しの工程のあるよりもより日常的な味のものである。東北太平洋側、伊豆半島周辺、紀伊半島で作られているものでカツオだけではなくハガツオ、ヒラソウダなどでも作られていた。
静岡県伊豆半島西岸、カツオ漁の基地であった田子、安良里で、盛んに作られていたのが「潮かつお」だ。カツオの内臓を取り、丸ごとを塩漬けにして寝かせ、干し上げたもので、保存性がただの塩蔵品よりも高い。秋に塩につけ込んで干し、暮れには出来上がるのだが、生ハムのように独特の風味が生まれ、ものによってはスライスして生でも食べられる。西伊豆ではこれを正月飾りに使う。西伊豆から沼津周辺までの地域ではハレの日に食べるもので、年取・正月魚の代表的なものであった。塩蔵して干すという工程があり、明らかに冬の保存食の意味合いがあったものと考えられる。この干しの工程のあるものとは別により手軽に作れる「塩がつお」もある。浜に揚がったカツオ(サバ科のソウダガツオ類やハガツオなどでも作られている)、もしくは比較的近くの都市部に送られていた。干しの工程のあるよりもより日常的な味のものである。東北太平洋側、伊豆半島周辺、紀伊半島で作られているものでカツオだけではなくハガツオ、ヒラソウダなどでも作られていた。全22件中 全レコードを表示しています